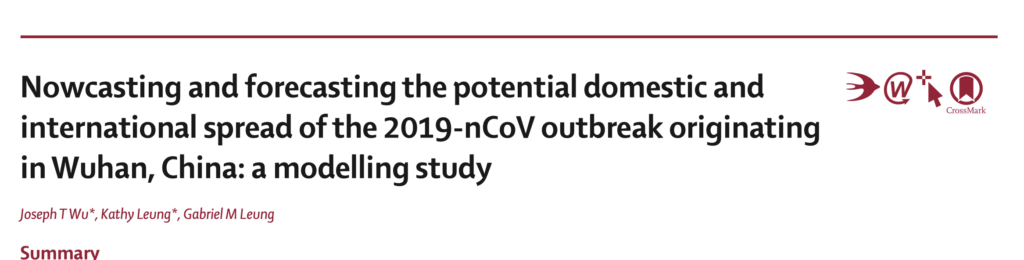2020年2月3日
化学兵器として使われるガスには様々な種類があるが、我が国で最も知られているのが、オウム真理教が無差別テロに使用したサリンをはじめとする有機リン化合物だろう。イラクではクルド人虐殺や湾岸戦争に使われたのではと疑われているが、実際のところ明確に戦争に使用されたという証拠は無いらしい。しかし、オウム真理教でも合成できるということは、密かに生産が行われており、戦争やテロに用いられる可能性は常に存在する。
これに対して、私のような平和ボケ人間は防毒マスク以外に避ける方法は無いと思ってしまうが、同じ生命科学でも、軍の研究者は私たちが思いもかけない対処法を考え付くようだ。今日紹介したいのは、米軍の化学防衛研究所からの論文で、有機リンを分解する酵素を肝臓に導入して神経ガスを耐え抜く身体を開発しようとした研究だ。タイトルは「Gene therapy delivering a paraoxonase 1 variant offers long-term prophylactic protection against nerve agents in mice(paraoxonase1変異遺伝子を導入する遺伝子治療によってマウスは神経ガスに対して抵抗性を獲得する)」で、なんと1月22日Science Translational Medicineに掲載されている。
有機リンガス兵器は呼吸器官から吸入した後血液中に溶け脳内でアセチルコリンエステラーゼを無毒化し、最終的に呼吸を支える筋肉が麻痺して死に至る。この研究の発想は単純で、有機リンを分解する酵素遺伝子をあらかじめ肝臓で発現さて、末梢血中で有機リンを分解させるというアイデアだ。
このグループはすでに無毒化分子としてparaxonase1を選び、機能を高めた変異分子IF11を開発している。この研究の目的は、この分子をコードする遺伝子を導入してガス攻撃に耐えるマウスを作れるかだ。様々な条件を検討した結果、アデノ随伴ウイルスを用いた遺伝子ベクター(導入のための運び屋)としてAAV8、遺伝子の発現を誘導するためにTGB遺伝子プロモーターを選び、これをマウスに注射している。
この方法だと、遺伝子は肝臓細胞に導入され、5ヶ月以上大量にparaoxonase1を合成し続ける。また注射するウイルスベクターの量に応じて血中のparaoxonase1の濃度を上げることも確認している。
あとは、この遺伝子を導入したマウスは、毒ガスに耐えるか調べるだけだが、予想通りだ。
有機リン化合物には様々な種類があり、処理効率(必要な血中のparaoxonase1濃度で代表されている)は異なるが、一定濃度さえ確保できれば全ての化合物に暴露しても、マウスはビクともしないで、普通の活動を続けることを示している。
実際には他にも様々な実験を行なっているが、詳細は省いていいだろう。要するに、ガスマスクなしに神経ガスをものともしない体を作ることができるという話だ。テロや戦争から身を守るために、ウイルスを予防的に注射する時代がこないことを祈りたい。
2020年2月3日
精子と異なり、卵子は成熟してから新しくリクルートされることはなく、発生過程で作られた卵子を生理サイクルのたびに少しづつ使っていく。このため、卵巣の中では常に静止期の卵子とともに、活性化された後の卵成熟過程から、排卵後の卵胞まで、多くのステージが共存している。
今日紹介する北京の中国アカデミー動物学研究所からの論文は、single cell transcriptome解析を用いて卵巣の老化を探った研究で2月6日発行のCellに掲載された。タイトルは「Single-Cell Transcriptomic Atlas of Primate Ovarian Aging(サルの卵巣老化のsingle cell trascriptome解析)」だ。
この研究では人間の代わりにサルを用いて、閉経期前後の卵巣の老化について調べている。これまで卵巣のsingle cell trascriptomeに関する研究をあまり目にしたことがないが、恐らくこれは卵子の大きさが他の細胞と比べて大きいということに起因するかもしれない。このグループは、卵子と他の細胞をバラバラにした後、分けたあと、single cell trascriptomeを調べている。結果、卵子4種類に加えて、顆粒細胞や、間質細胞、血管、平滑筋、NK、マクロファージなどを分別することに成功している。
特に重要なのは、C1からC4までの卵子成熟で見られる大きな変化で、それぞれのステージで特徴的な遺伝子ネットワークが活動している様子がわかる。これは当然で、この間に複雑な減数分裂を成し遂げる必要がある。一方、未熟卵子は静止期を維持する必要がある。
意外だったのがミトコンドリアの活性が未熟な卵子で高いことで、じっとしていてもエネルギーが必要なのは、脳と同じなのかもしれない。その後成熟が始まるとまず翻訳が高まり、減数分裂体制へと入っていくのがわかる。
ただこのこと自体は、だいたいわかっていることで特に新しいことはない。この研究の主目的は、このような様々なステージ、種類の細胞が共存する卵巣で、老化はどう起こっているのか、細胞個別に調べることだ。single cell transcriptomeで老化を調べるという着想は、卵巣だから必要性がわかったとも言えるが、今後老化の分子プロセスを調べる時、これがが重要なテクノロジーになること示唆している。
まず卵子についての結果だが、全てのステージで遺伝子発現のパターンが変わる、すなわち老化は全てのステージではっきりと検出できる。ただ、同じ卵子でもそれぞれ上下する遺伝子の種類は違う。面白いのは、活性酸素を抑える経路の遺伝子の低下が最もはっきりするのがC2ステージで、今後閉経の生物学を考える上で重要だと思う。
同様に卵子活性化に重要な顆粒細胞でも老化に伴う変化が起こるが、卵子と違い最もはっきりしているのが、活性化酸素を抑える遺伝子の低下と、アポトーシスの経路に関わる遺伝子が上昇している。
人間の顆粒細胞でも調べているが、これは付け足しで、以上が結果の全てだと言える。結局予想通りの結果であまり驚きはないが、今後様々な老化予防策により、この基本構造がどう変わるか面白いテーマができたと思う。また、組織と細胞という永遠の問題を、老化というプロセスを対象にsingle cell trascriptome調べようとしたことは評価していいように思う。
2020年2月2日
この前コロナウイルスの症例報告について紹介した時から 1週間も経っていないが、今やメディアもコロナ報道一色になってきた。と言っても、結局人混みを避けよ、手洗いを徹底せよ以外に、なんの具体的指示は出しようがない。様々な会社が有効な薬剤の治験を進めていると思うが、多くの人は軽い症状で終わりそうなこの病気に、パニックに後押しされて予防投与が行われるような事態が来ないよう、医療側も薬剤や抗体薬などが開発された時のプロトコルについて、現在わかってきた感染者と発病者、発病者と重症者の正確な調査を元に用意する必要があると思う。
今必要なのは、ニュースよりできるだけ科学的な把握だろう。この時、将来の予測には冷静なシミュレーション研究が重要だ。その意味で、香港大学から1月31日The Lancetにオンライン発表された研究は、参考になると思う。
香港大学からThe Lancetに発表されたシミュレーション論文 シミュレーションには信頼おけるデータを集めることがまず大事だが、武漢内の発表に頼るのではなく、武漢以外の都市で発生した確実な発病者の数、実際の人の移動などから逆算する手法で計算するというスマートな方法を取っている。この時、伝染する強さを一人から2.68人、感染者数の倍加する時間を6.8日として計算すると、1月25日時点で武漢には75000人の感染者がいたと推定している。また、武漢と最も交流が多い順番に、重慶、北京、上海、広州、深圳へ、1月25日時点でそれぞれ、435人、98人、111人、80人の感染者が移動したと計算している。
その上で今後の予想を計算すると、特に感染力を落とす手立てを講じなかった場合は4月1日をピークとする大流行が起こると予想している。
これについてはいくつかのメディアでも紹介されているが、この研究の重要な点は、人の動きと感染力を抑える手段の影響を計算している点で、
この流行は各都市間の移動を50%ぐらい制限しても、ほとんど変化がなく、例えば他の都市での流行が一月ずれる程度で終わる。 しかし、もし感染性を50%減らすことができれば(隔離、早期の治療、今言われている手洗いなど様々な対策)、パンデミックのピークは起こらない。 をシミュレーションで示している。すなわち、現状では感染を抑え込む努力を限りなく進めることがパンデミックを防ぐ唯一の手段というわけだ。
もちろんインフルエンザで見られるような季節性があるか、感染源の動物は駆除できるか、など多くの不確定要素はあるが、まだ感染者の多くない我が国では、隔離と患者のトラッキング、感染しないための注意を繰り返して、ウイルスの感染性をなんとか50%落とすことで乗り切れるのではと思う。
2020年2月2日
ネアンデルタールやデニソーワ人のゲノムが解析できるようになった最も大きなインパクトは、我々の先祖がデニソーワ人と交雑をし、その時生まれた子供たちから現在の私たちにゲノムの一部が伝わっているという発見だ。この時、ネアンデルタール人のゲノムはアフリカ人にはほとんど見つからないことも報告され、アフリカで生まれたホモ・サピエンスのうち、ユーラシアに移動したグループだけがネアンデルタール人と交雑したという歴史が定着した。
今日紹介するプリンストン大学からの論文はこれまで考えている以上にネアンデルタール人のゲノムがアフリカ人に流入し定着していることを示した論文で2月20日発行予定のCellに掲載された。タイトルは「Identifying and Interpreting Apparent Neanderthal Ancestry in African Individuals (アフリカ人に見られる明らかなネアンデルタール人の先祖を特定し解釈する)」だ。
現代人に残っているネアンデルタール人のゲノムを間違いなく特定するため、これまで用いられていたのは、アフリカ人にはネアンデルタール人ゲノムがほとんど存在しないという仮説にたって、ネアンデルタール人に存在して、アフリカ人に存在しない部分をまず選び出すという差分操作が行われていた。しかし、これは引き算することで、実際にはネアンデルタール由来でもアフリカ人にあるからということで除外することになる。
一方、一定の長さで配列の一致するかどうか比べることで、直接先祖かどうかを確かめる方法が存在し、親戚探しに使われている。この方法なら、今生きている個人のどの遺伝子がネアンデルタールの先祖と共通化を直接計算できるので、これを使えば上に述べた問題は解決できるはずだ。ただ、間違った断片をネアンデルタール人由来とする間違いを避けるため、直接先祖かどうなを確かめる方法は試みられていなかった。
この研究のハイライトは、推計学を用いたIBDmixを開発して、直接の先祖性を調べられるようにしたという点だ。特に似ている断片が長い場合はほとんど間違いがないレベルであることを示している。
このように直接先祖と共通の遺伝子を1000人ゲノムデータと比べることで、なんとネアンデルタール人のゲノムの3−4割を再構成できる。その上で、次に私たちがネアンデルタール人の先祖と共通の断片を持っているか調べると、アジア人やヨーロッパ人で約50Mb存在するのに対し、予想に反しアフリカ人でも18M b存在することを明らかにしている。これがこの論文の最も重要なメッセージで、今後この直接調べる方法で、他の人種や古代人を比べていくことでその真価はより明らかにされると思う。
その上で、ではアフリカ人とネアンデルタール人はどのように交流したのかをシミュレーションと実際のデータを比べて調べている。この時、合致する長さ、合致した断片の分布などすべてを、アフリカ人、ヨーロッパ人、東アジア人と詳しく比べて、アジア人とヨーロッパ人が分かれる前にホモ・サピエンスのゲノムがネアンデルタール人に流入し、それが現在共有されている部分と、アジア人とヨーロッパ人が分かれたあと、ヨーロッパ人がアフリカへ新たに持ち込んだネアンデルタール人ゲノムが存在することを示している。特に驚いたのが、現代人のゲノムがネアンデルタール人に入った時期が10-15万年前と計算されている点で、ネアンデルタール人はすでにアフリカにいないとしたら、ホモ・サピエンスはどこでどのように交流したのかぜひ知りたいところだ。
面白いのは、こうして新たに持ち込まれたネアンデルタール人のゲノムは、アフリカ人とヨーロッパ人で別々に淘汰圧にさらされることで、特に免疫系の遺伝子については、今後ますます面白い物語が聞ける気がする。
もともと数理に疎い私だが、直接先祖性を比べることの重要性はよくわかる。IBDmixの活躍に期待したい。昨日述べたようにアフリカ人のゲノム多様性は高い。その意味で、民族の関係を仮説なしに直接調べることの重要性は高い。
2020年2月1日
現在様々な理由から、アフリカ人のゲノム解析が精力的に進んでいる。まず何よりも、アフリカでホモ・サピエンスは誕生し、多様化した。ユーラシアに移動したのはそのうちの一部で、その時生まれた遺伝子多様性はアフリカに残っている。すなわちユーラシアに移動した人種に比してゲノム多様性が高い。しかも、ネアンデルタール人など他の人類との交雑程度が低い。これまで主にコケイジアンで進んできたゲノム研究では見落としてきた新しい事実が、アフリカ人ゲノムからわかるのではと期待される。そこで、今日明日とアフリカ人ゲノムに関する論文を紹介することにした。
最初の今日は、ワシントン大学を中心とするグループからの論文で、南アフリカコサ族の統合失調症のゲノム解析研究で1月30日号のScienceに掲載された。タイトルは「Genetics of schizophrenia in the South African Xhosa (南アフリカコサ族の統合失調症患者の遺伝学)」だ。
タイトルを見てコサ族は統合失調症が多いのかと勘違いしてしまったが、そうではない。中央アフリカから南アフリカへと移住して、独自の言語と文化を持つコサ族の統合失調症患者でゲノム解析を行い、他の民族とは異なる事実を発見しようとした研究だ。
コサ族とは南アフリカ黒人解放をリードしたマンデラさんが属する民族で、アフリカでは2番目に人口が多い。この民族の統合失調症患者さんと、正常人それぞれ約900人をリクルートし、エクソーム(ゲノムのタンパク質へと翻訳される部分)を解読し、両者の違いを比べている。
まずエクソームレベルでの配列多様性を比べると、予想通りアフリカ人の多様性は群を抜いている。しかも、民族間の交雑程度は少ない。
エクソーム解析で得られた様々な変異から、機能欠損につながる変異をリストし、それを患者さんだけで見られる稀な変異と、正常人でだけ見られる変異に分けている。例えばCNTNAP1(シナプス形成に関わる分子)の変異は4人の統合失調症で見られたが、正常人にはなかったが、これを症例変異と呼んでいる(実際にはもっと数を増やせば正常人でも見つかる可能性はある)。
こうして、正常人変異と、症例変異を比べた結果、
機能欠損変異は統合失調症患者さんの方により多く発見される。一方、機能に無関係な変異で見ると、そのような偏りは見られない。 統合失調症に偏る機能欠損型変異の3割はシナプス機能に関わる分子で占められる。 今回リストした統合失調症で偏って欠損していた遺伝子の多くは、これまでのデータベースを検索すると、統合失調症や自閉症で発現が低下しており、逆に双極性障害では発現が上昇している遺伝子が多い。 今回の結果は、スウェーデン人で調べたデータと共通しており、コサ族特異的ではない。 結果は以上で、結論はこれまでと変わることはない。すなわち、統合失調症は一つの遺伝子で決まる病気ではなく、複数の遺伝子が絡み合って形成される。統合失調症になると、生殖可能性は低下するので、おそらく症例に関わる遺伝子は常に淘汰圧に晒されており、その意味で新しく発生する遺伝変異が発症には重要になる。そして、病気のメカニズムとしては、シナプス伝達と可塑性が障害されることが考えられる。
コサ族で調べたことの意義がまだ明確ではない研究で終わってしまっているが、アフリカ人のゲノムを調べる重要性はよく理解できた。
2020年1月31日
ヒトES細胞樹立の是非を議論する総合科学技術会議専門委員会のメンバーだった頃、両親が廃棄することを決めた受精卵を、生殖以外の医療に転用する可能性について、曹洞宗の中野東禅さん、立教大学教授で司祭でもある関正勝さんを有識者として招き、意見をうかがったことがある。はっきりと覚えているわけではないが、関さんは、受精卵=一個の生命であることを強調して、受精卵からES細胞の作成には反対されたと思う。これは予想通りだった。一方予想が全く裏切られて驚いたのが、仏教を代表して来られた中野東禅さんの意見で、「2つの正義が対立したとき、大なるほうを取ることで小なるほうを犠牲にしても責任を取れる。胚に人為的介入をすることに大なる目的が明確で(慈悲と共生)、社会的認知があれば可能である。」(委員会資料より引用)と、今生きている社会や人を優先する考えだった。
伝統的な世界宗教(一神教)が誕生したのは、受精の概念が生まれるはるか前だ。精子と卵子が融合することがドイツのHetwigにより観察されたのはようやく1878年の話で、聖書や仏典に書かれているはずはない。ただ、仏教やユダヤ教のように世俗と信仰を無理に統一しようとはしない宗教では、科学は科学、信仰は信仰と割り切って、科学の進歩にいちいち信仰が煩わされることはなかったように思う。
一方キリスト教では事情が全く違う。卵子が発見され、卵子が受精によって発生することが科学的にわかると、この科学的事実を深刻に受け止め、それまで規範としてきた人の魂の誕生についてのアリストテレスの考え方(捨てられる月経血は畑で、この畑に精子という種が撒かれることで発生が始まり、魂を持った個体は両者が混合(性交)後40日に始まる。この時栄養分として月経血が胎児に回される結果月経が止まるという考え)が間違っていることを認め、議論を経て1869年以降、受精した卵子の発生が始まる時が個体の誕生であると教義を転換させている。
このように、重要な科学的進歩の意義を理解し、信仰の世界と統合しなければならないと考えるキリスト教の特質は、いまだに生命の始まりをアリストテレスの考えを少し読み換えて受精後40日目としているユダヤ教・イスラム教との間に、生命の誕生に関する定義の大きな違いを生んだ。この結果、受精後40日から人間が始まるとするイスラエルやイランで生殖補助医療がさかんに行われ、受精卵は両親が認めればモノとして使用するのが許されている。一方、カソリックでは受精卵はヒトであり決して毀損してはならないとしている。ヒトES細胞樹立についても、ユダヤ教、イスラム教は許可し、カソリックでは禁止することになった。
ちょっと前置きが長くなったが、なぜこのような話を持ち出したかというと、スコラ哲学の原典を読んでみて、受精をめぐる議論で見られたキリスト教の特質が、アリストテレスへの対応にも現れていると感じたからだ。すなわち、アリストテレスが西欧に再導入された時、彼の哲学は経験や観察に基づく科学的要素を強く持った思想だったと言える。実際、前回読んだアルベルトゥス・マグヌスも、トマス・アクィナスも、アリストテレスを信仰に反するとして拒否したり、あるいはギリシャ由来の一つの考え方に過ぎないと無視するのではなく、その重要性を認め、理解を深めた上で、なんとか信仰と統合を図れないか努力している。このアリストテレスをキリスト教に統一しようとするスコラ哲学の努力と、受精という科学的事実に直面して、それまでの教義をすてて、科学的事実を新しい教義に転換させた決断は、世俗(科学)と統一を図ろうとするキリスト教の特質を反映したものだ。ただいずれの努力も、信仰の世界を優先させた上での統一であるため、結局統一とは名ばかりの、一種の二元論で手を打つことになる。
このキリスト教の特質は、さらに遡ると以前述べたキリスト教の世俗性の問題に行き当たる。すなわち、三位一体、テオトコス(マリアは神の母)など、神の世界を信者の住む現実の世界と統合させようと、異端論争を経てコンセンサスを形成し教義を確立したのがキリスト教だ。この特質は、時代と共に進む科学由来の概念との関係でも間違いなく見られるはずで、受精と生命の始まりはほんの一例に過ぎない、あれほどガリレオを悩ませた天動説にしても、時間はかかったが1992年にヨハネパオロ2世はわざわざキリスト教の非を認めて謝罪している。「つい最近まで天動説を支持するとは何と時代遅れか」と非難する科学者が多いのはわかるが、私に言わせれば、キリスト教が世俗の問題にいちいち介入していることの方が驚きだ。
いずれにせよ、世俗を神の世界に統合しようと試みることは、逆からみるとキリスト教は不断に世俗化する宗教であることを意味している。などと考えているうち、「旧約聖書の創世記をキリスト教がどう理解していたのかを調べてみれば、キリスト教の世俗化(科学化)がもっとよくわかるのでは?」という考えがふっとよぎった。
実際、創世記はキリスト教にとっては大きな躓きの石として立ちはだかる。
まず天地創造や、アダム・イヴの誕生、ノアの箱舟など創世記の記述の多くは、聖書に書かれていても、もはやキリスト教徒の多くは文字通り信じていない。しかも、この神話はもともとユダヤ人の民族神話だった。
「死すべき人類のために、神は自分の分身、キリストをこの世に人間として送り、信じることで人間も復活し永遠の生命を得ることを実際に示した」がキリストのメッセージで、このメッセージの普遍的魅力がキリスト教を世界宗教へと発展させた。しかし、キリストと使徒達、そしてあとで改宗することになるパウロなど、キリスト教の基盤を作った人たちはユダヤ人で、福音書もマタイ、マルコ、ルカ伝まではキリストがアブラハムの子孫である事をわざわざ強調している。すなわち、キリスト教は最初ユダヤ教の一セクトとして始まった。
このような歴史的背景から、キリスト教でもユダヤ民族の書いた旧約聖書を正典として認めている。しかし旧約聖書の内容はユダヤ人の神話と歴史に他ならず、特に天地創造、ノアの箱舟、アブラハムと族長の物語と続く創世記は、ほとんどのキリスト教徒にとって無関係と言っていいのではないだろうか。私もキリスト教の家庭に育ち、中学もキリスト教教育を行う同志社で学んだが、旧約聖書の話は童話として捉えていた。サンタクロースと同じで、年齢が進むと信じるという話ではなくなる。
事実、いかに旧約聖書が正典だとしても、書かれたことが文字通り真実であるとはキリスト教でも主張しない。例えば、英国の教会と聖書学界が協力して完成させた「新英訳聖書によるケンブリッジ聖書注解」の第1巻、ロバート・デーヴィッド著、大野恵正訳の「創世記1」を読むと、旧約聖書をユダヤ民族が口承してきた様々な物語が、ダビデ・ソロモン治下のヘブル人王国の建設により集大成され、その後ヘブル王国の消滅の危機に際して民族の過去を書き残すことの重要性が認識された結果、創世記をはじめとする旧約聖書として文字化された明確に述べている。
図1ケンブリッジ旧約聖書注解 また、天地創造の話やノアの箱舟の話も、ユダヤだけではなく、中東に広く存在していたさまざまな神話の影響を受けた上で、選民としてのユダヤ人の民族の誇りや習慣を反映させたものとして捉えており、真実かどうかを問うことは意味がなく、その裏に隠れている書き手と、それを支える民族の意図を読むことが重要だと明確に述べている。すなわち、その背景を理解して、神と人間との関係を理解することは大事だが、書かれた内容は寓話に過ぎないと断じている。
一例としてアダムとイブ、すなわち人間の誕生と失楽園の物語について、この注釈書から引用してみよう。
「(失楽園)の物語全体は、悲劇のそれである。美しいものが人間のわがままによって打ち壊されてしまったという物語であって、人間は独立を得ようと努めながら、自分の本当の命を失ってしまうのである。語り手にとって、これは昔話ではなく、永遠に現実性をもった物語である。古代近東のさまざまな集団に起因する宗教的モティーフが語り手によって採用され、彼自身の経験というるつぼの中で変容される。詩と同様、信仰は少なからず象徴を通してその最新の真理を伝達する。しかし絶えず新しい意味を与えられるのである」 (同書 57ページ)。
結局、人間と神との永遠の関係を表現する寓話として、アダムの物語を捉えていることがわかる。
このように、書かれた内容そのものではなく、その意義や道徳などを問う、旧約聖書の物語についての考え方はキリスト教の教義が成立した400年には確立していたのだろうか?あるいは、人間の進化や、歴史についての現代の理解によって変化した結果の、現代的解釈なのだろうか?
これを知るため、トマスアクィナスより遡ること800年、すなわち三位一体、キリストの受肉などの重要な概念が固まった時代の最も有名な神学者アウグスチヌスが、「創世記」をどのように注解していたのか調べてみた。
図2 アウグスチヌスの創世記注解 この本は、アウグスチヌスが創世記の内容について、一節一節読み解こうとした著作だ。もちろん哲学書として推薦したいという本ではないが、読んで驚いた。5世紀、プラトンをはじめとしておそらく他のギリシャ哲学にも通じていたと思われるアウグスチヌスが、創世記の内容をいわば文字通り信じた上で、その内容について議論している。
もちろんアウグスチヌスも、旧約聖書が人間により書かれたものであることを認識している。しかし彼はそこに書かれた内容を、決して書き手が自由に生み出したものではなく、書き手が神により書かされたという認識で捉えている。そのため、先に見た近代の注釈書のように、例えば道徳的な意義とか、寓意とかを探るのではなく、一字一句書かれた文章の意図を問うている。私の説明だけではわかりにくいと思うので、いくつか引用してみよう。
例えばなぜ天地創造から人間の創造までが6日間で行われたのかは、6が完全数であるからだという理屈を着想し次のように述べている。
「六という数は、その構成要素の総計からなると言う意味での最初の完全数である。・・・・つまり倍加することによって、それが部分であるところの数を構成しうる。そのような部分のみの総計からなるのである。・・・六という数は、先ほどから説明し始めたように、その部分が総計されて、それ自身と等しくなる数である。・・・・六は約数を三つ持っている。六の六分の一、三分の一、二分の一である。六の六分の一は一であり、三分の一は二であり、二分の一は三である。ところがこれらの約数を総計すると、つまり一と二と三を足すご、六として完成するのである.・・・・だから完全数の日数で、つまり6日で神はその作られた業を完成されたのである。」 (アウグスチヌス著作集16、創世記注釈(I)、片柳栄一訳 103-104ページ。
この文章から、聖書で書かれた内容を文字通りけ取って、その上で「なぜ6日間」について考えぬき、最後に六がある意味で完全数であるというアイデアを得て大喜びしているアウグスチヌスが見える。ただ、この屁理屈には笑ってしまうだけだ。
また、神がわざわざ7日を休息日として休まれたのかについても真剣に議論している。おもしろいのは新約聖書と旧約聖書の矛盾について考えている箇所だ。
「だからここに書かれたこと、つまり第七の日に神は作られた全ての業を終えて安息されたということと、福音書のうちで全てのものを創られた其の方自身が「私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ」(ヨハネ5・17)と語られたことの双方ともが、いかにして真理であるかを我々の力の及ぶ限り探求し、また表現するよう、極めて正当にも理性によって促されているのである。」(同書116ページ)。
もちろん正しい答えがあるはずはないが、イエスが6日目に十字架に架けられ、墓の中で1日ゆっくり休まれたという話を持ち出して、旧約と新約は完全に一体化しており、本当は休みなく働く神は、天地創造の後自ら7日目に休息をとることで、安息日を天地創造の6日間を思い浮かべるため与えたのだというアイデアを提案している。
はっきり言って、アウグスチヌスの論理や議論自体も、神話の世界と同じレベルとしか思えない内容だが、それでも彼が聖書の言葉に完全に従った上で、あとは自由闊達、縦横無尽に思索を巡らせる、稀代のアイデアマン、思索家であったことがよくわかる。そしてキリスト教の信仰を優先するという立場を除けば、アウグスチヌスも、自由闊達に思考するギリシャの哲学者と同じであることもわかる。
例えば、旧約聖書では人間の誕生を、
「 主なる神は、土(アダマ)の塵で人(アダム)を形づくり、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きる者となった。 」
と、植物や動物を作ったのと同じように簡潔に書いている。しかし、当時の人は人間には身体と魂が存在すると信じていたはずで、その意味で旧約聖書の記述ではあまりにそっけないため、「では魂はどこからくるのか?」という疑問が生じる。もちろん、「命の息を吹き入れられる」という記述はアリストテレス的にいえばプシュケース=息=魂が身体に与えられたと納得してもいいのだが、物事を自分で考えないと気が済まないアウグスチヌスは、この問題を何ページも割いて議論する。そして、
「さて魂がそれ以前まったく存在していなかったとすれば、魂の原因的理拠が最初の六日の神の技のうちに損していたと言われることをどのように解したら良いのかと問われよう。神は第六の日に人間を神の似像として作られたのであり、この似像は魂にしたがってでなければ正しく理解されないであろう。しかし神が全てを同時に創られた時、神は将来あるはずの本姓は実態そのものを作られたのではなく、将来あるべきもののある種の原因的理拠を作られたのだと我々が語る時、我々が何か無意味なことを語っていると思われないよう注意すべきである。というのもこの原因的理拠とは一体何なのであろうか。人間の身体はまだ泥土からかたどられておらず、これにまだ魂が吹き込まれて作られていなかったのに、この理拠に従って神は人間を神の似像として作られたと言われているのである。人間の身体のある隠された理拠が損したのであり、これによって将来身体が形成されることになっていたのであるが、さらにそこから身体が形成されることになる素材、つまり土も損していたのであり、この土のうちにかの理拠がいわば趣旨のうちにあるように隠されていたと考えうる。これに対して造られるべき魂の本性、つまり人間の魂である息を作る本性が以前なかったのだとしたら、魂の原因的理拠はどこにつくりおかれたのであろうか。この理拠は神が「我々のかたちに、我々に似せて人を作ろう」と言われた時まず創られたのである。」
少し引用が長くなったが、人間創造に際して身体と魂を神がどの様に創ったのかについてのアイデアを提案している。実際には議論はさらに続くが、答えは明瞭で、神が身体と魂を用意した。この時、身体は土から作ったが、神の似像というプラトン的イデアが魂として吹き入れられ、人間ができる。この魂はは神の意志として最初から存在しており、それが土からできた身体に吹き込まれたというアイデアだ。まさにスーパー屁理屈で、ギリシャのソフィストを彷彿とさせる。しかし、いつか議論するが、18世紀の自然史誕生時、ビュフォンやボイルの生命観ともどこか通じるものがある。
この本の解説はこれぐらいで十分だ。あまりポジティブには評価しなかったが、しかし創世記についてのアウグスチヌス注釈を読むことで、アウグスチヌスが新プラトン主義を中世に橋渡しした人とされている意味がよくわかった。ギリシャ哲学ではまず問いが存在し、その問いに対する答えとそれに至る思考過程が議論された。一方、アウグスチヌスの場合、自由に広がる思考過程の背景には間違いなくギリシャ哲学がある。直接的には「神の似像」「原因理拠」といった言葉から推察される様に、プラトン、特に新プラトン主義の哲学がある。ただギリシャ哲学と異なるのは、このギリシャ哲学に裏付けられた思考過程が、最初から存在する答え(=聖書の言葉やキリスト教の教義)の正当性を証明するために使われる点だ。この最初から存在する答えの正当性を証明する理性という構造はスコラ哲学も同じだし、これがその後の西欧二元論の源になると思う。
最初の疑問「科学(世俗)とキリスト教」にもどろう。キリスト教の世俗化(人間との対称化)は、ローマ文化という世俗を統合することから始まった。しかし、世俗を信仰に統合することは、信仰が世俗化することと裏腹だ。その結果、キリストの受肉や、テオトコス(マリアは神の母である)といった神と人間の統合(逆から見ると神の世俗化)が行われ、神の似像=人間の姿が溢れる教会が誕生する。この結果、キリスト教は「イエスが人間の罪の身代わりに磔にされ、人間に希望を与えるため復活した」という教義の核が守られるなら、世俗を統合しようと常に試みる(逆から見ると常に世俗化していく)特異な一神教の道を進んでいく。これは科学との関係だけではない。例えば中世のバチカンと世俗権力との関係や、十字軍などを見ても同じことを感じる。
世俗を統合しようとして世俗化が進む構造は、一元論を目指して二元論が呼び込まれる構造と同じだ。この構造がキリスト教の特質として、アウグスチヌス、スコラ哲学と受け継がれていく。そして、この構造こそが17世紀、西欧だけで科学が誕生する基礎になっていることがアウグスチヌスを読んでみてよくわかった。この点については、次回スコラ哲学後期のオッカムを読んでから、さらに議論したいと思っている。
2020年1月31日
疫学的には昔から9割近くの肺ガンがタバコが原因であることが示されていたが、ガン細胞のゲノム解析が始まって、喫煙者の肺ガンではゲノムあたりの突然変異が数千、数万に及ぶことがわかり、なるほどタバコが正常肺のゲノムを傷つけ続けていることを認識できた。ただ、私の様に50歳近くまでタバコを吸っていた人間にとって悲しいのは、タバコをやめた人の肺ガンでも、喫煙者と同じ様に突然変異が多いことで、タバコをやめても昔の傷は治らないのかと思っていた。
ただ、ガンは多くの変異が集まって発生することから、発生したガンは変異の多い細胞だけ選択されていると考えられ、肺の通常の細胞がタバコでどのぐらい傷ついているかを明らかにしてはじめて、タバコをやめるメリットがより正確に計算できる。今日紹介するロンドン大学からの論文はガンを含む様々な病気で気管支鏡検査をした時に採取した個々の正常細胞ゲノムを調べ、禁煙した人と喫煙を続けている人とのゲノム変異を調べた研究で1月29日号のNatureに掲載された。タイトルは「Tobacco smoking and somatic mutations in human bronchial epithelium(喫煙による気管支上皮の体細胞突然変異)」だ。
この研究では様々な肺の病気で気管支鏡検査をした、非喫煙者、禁煙した人、喫煙者から、正常上皮をバイオプシーで採取、その組織から細胞コロニーを形成させ、単一細胞由来のコロニーを一人当たり11〜60個採取し、それぞれのゲノムを、だいたい16coverageで解読している。すなわち、同じ人から採取していても、多くの変異は細胞ごとに違っており、この方法でそれが解析できる。一つのコロニーから変異が見つかった場合、解析した配列の中に変異が含まれる確率(変異アレル頻度)は概ね50%で、コロニーが単一細胞から由来していることが確認できる。
実際には膨大な研究なので、結果は箇条書きにまとめると以下の様になる。
各細胞の突然変異数を個人あたりで平均すると、予想通り喫煙経験がない人と比べて、禁煙した人も含めて喫煙歴があると突然変異数は平均で数千のオーダーで高い。 ただ予想に反し、喫煙者と比べ、禁煙した人のコロニー同士の多様性は極めて高く、変異の少ない細胞と、変異の多い細胞が混じっている。 禁煙を実施した人の2〜4割の細胞はほとんど正常範囲の変異しかない細胞も見られるが、喫煙者ではこの様な変異の少ない細胞はほとんど存在しない。すなわち、細胞によってはほとんど正常という細胞が禁煙した人には存在するが、喫煙中の人には見られない。 突然変異のタイプを調べると、喫煙者も禁煙した人も、SBS-4と呼ばれる、肺ガンでよく見られる変異のタイプが多い。 予想通り、突然変異が多いほど癌遺伝子や、がん抑制遺伝子の変異も多く、この変化で細胞の進化的優位性が高まっていることも計算できる。 一方、テロメアは正常細胞に近いほど長く、驚くことに、禁煙をした人で変異の少ない細胞は、テロメアも長い。 以上の結果を相互すると、確かに喫煙歴があると、ゲノム変異が上昇するが、変異細胞は静止幹細胞からの新しい細胞で置き換わっている。この静止幹細胞は、変異原から守られており、その結果新しい細胞は変異が少ない、ということになるのだろう。ただ、これだけならもっと喫煙者にも正常に近い細胞が見られてもいいと思うが、ともかくタバコをやめると早い時期から正常型の細胞に置き換わってくれるということがわかったのは重要だ。ようするに、今からでも遅くない。
2020年1月30日
アルツハイマー病(AD)の神経細胞死に直接関わるのが、リン酸化TAUの増加であるというコンセプトは今や広く認められてきた。またADだけでなく、TAUタンパク質が神経変性疾患に深く関わっていることが明らかになり、これらをTaunopathyと総称する様になっている。こうみてくると、「TAUなんて危ないだけで、ゲノムから消えた方がいい。実際、TAU遺伝子をノックアウトしても、発生は正常に進むではないか」と考えるのもうなづける。
しかし、ノックアウトで何も起こらないとしても、TAUが微小管の安定化に関わることは細胞学的・生化学的に明らかになっている。このTauの機能の一端を見ることができるのが、今日紹介するスペイン・マドリッドのオチョア分子生物学研究所からの論文で、TAUは悪性の脳腫瘍グリオブラストーマの増殖を抑える効果があることを示した研究だ。1月22日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「The IDH-TAU-EGFR triad defines the neovascular landscape of diffuse gliomas (IDH/TAU/EGRの3極がびまん性グリオーマの血管新生の形を決める)」だ。
もともとこのグループはADでは悪役の TAUが、グリオーマの増殖を抑えるのではという考えを持っていた様だ。これを確かめるため、ガンのデータベースからTauの発現を調べてみると、グリオーマが悪性になるほどTauの発現が低下することを確認する。さらに、Tau発現の高いグリオーマでは患者さんの予後も良い。
グリオーマの予後を決めるもう一つの因子としてIDH1/2(isocitrate dehydrogenaseでこれが変異するとメチル化レベルが高まる)が知られており、変異がある場合は予後がいい。メカニズムは省くが、DNAメチル化レベルが高まる結果とされている。そこで、IDHの変異とTauの発現が関係がないかデータベースで調べると、期待通りIDH変異を持つグリオーマはTauの発現が高い。DNA メチル化が高まって遺伝子発現が上昇するのは直感に反するが、Tau上流の特定のサイトがメチル化され、染色体構造が変化した結果だろうと想像している。要するに、IDH変異がグリオーマを抑制できる一つの要因としてTauの発現を直接制御しているからだと結論している。
ではなぜTauがグリオーマの増殖を抑えるのか?これについては以前の研究をフォローしていないので頭がついていかないが,著者らはまずTauとEGFシグナルの関係に着目し、
Tauは微小管を安定化させることで活性化EGF受容体の分解を早める。Tauと同じ効果は微小管安定化剤でも得られる。 EGFシグナルが抑制されると、NFkBの活性化を抑制してグリオーマが間葉系細胞への変換を抑制する。 この間葉系への転換は、グリオーマに血管周囲細胞としての機能を付与することで、血管新生を更新させるが、これが抑制されることで、機能的血管新生が抑えられ、グリオーマが抑制される。 と解析を進めている。そして、IDH変異、Tau遺伝子クロマチンの変化、Tau転写の上昇、微小管の安定化、EGFシグナル低下、NFkBシグナル低下、グリオーマの血管周囲細胞への転換の抑制、血管新生抑制、グリオーマの悪性か阻止、と続くシナリオを提案している。
面白い話だが、まさに風が吹くと桶屋が儲かる話に似ており、この細い糸で全てが説明できるのか疑問を感じるが、これまで知らなかった様々なことが学べる論文として楽しんでおけばいいだろう。
2020年1月29日
現在オルガノイド培養というと、亡くなった笹井さんや、現在慶應大学の佐藤さんたちによって確立された、脳や消化器官のオルガノイドがポピュラーだが、その歴史は古く、例えば幹細胞からの組織形成にオルガノイドが使われる様になった最初は、ES細胞からのembryoid bodyだろう。他にも、胸腺のオルガノイド培養も免疫系ではよく使われていると思う。
当然、モデル動物でない材料を培養したいときに利用したい技術と言えるが、増殖因子の必要性などを考えるとそう簡単ではない。ところが今日紹介する佐藤さんがオルガノイド培養を最初に完成させたHans Clevers研究室から、人間やマウスと同じ条件で、蛇毒をつくる毒腺のオルガノイド培養が可能だという論文が1月23日号のCell に発表された。タイトルはそのものズバリ「Snake Venom Gland Organoids (蛇の毒線のオルガノイド)」だ。
蛇毒の多様性は著しく、それぞれがどの様に進化してきたのかは、遺伝子だけでなくそれを作るシステムを研究する必要があるが、上皮器官なのでもオルガノイドがうってつけだ。ただ、では佐藤さんたちが開発した複雑な培養カクテルを蛇で用意することは簡単でないと当然想像する。
ところがなんとCleversのグループは、マウスで樹立した条件をそのまま使えば蛇の毒線のオルガノイドが形成できることを示した。ただ、温度だけは32度で培養することが大事で、37度では増えない。私にとっての最も大きな驚きは、哺乳動物からずいぶん進化的に離れた蛇の複雑な培養が、同じ増殖カクテルで可能になった点だ。もちろんさらに至適な条件を達成するために、フォルスコリンなどを加えるという改良を行っているが、基本的にはマウスの条件でオルガノイドを長期間、継代することが可能になった。
あとは、こうして形成したオルガノイドを分化させて、蛇毒が合成されるかどうか、またどこまで正常組織に近いかを調べることになる。この系では、増殖している間は、蛇毒を分泌する能力がないが、増殖因子を全て除去すると分化が始まり、蛇毒遺伝子の発現が誘導できる。この蛇毒が機能的かどうか、まず細胞から分泌されること、そして分泌されたペプチドが神経や筋肉のGABAやアセチルコリン作動性シナプスを抑制することを確認している。
正常の組織とどこまで近いかについては、single cell trascriptome解析を行い、各細胞の割合は異なるが、正常組織とほぼ同じ細胞腫がオルガノイドで維持されていること、また異なるトキシンに対応する別々の上皮細胞を特定している。また、毒腺の近位側と遠位側から別々に調整したオルガノイドは、取り出された場所の記憶を維持しており、例えば毒素の発言で見ると、遠位側の方が多くの毒素を作ることも明らかにしている。
他にも様々な問題について調べているが、全て割愛していいだろう。さらに改良を加えれば、もちろん毒腺だけでなく、消化管組織全体の研究も可能になる気がする。
2020年1月28日
Single cell
trascriptome解析のパワーは驚くべきもので、今やトップジャーナルに掲載されてくる発生学や医学の研究では、使っていない研究の方が少ないといった状況になってきた。実際、腫瘍組織や免疫反応をモニターする目的にこの技術の価値は高い。極論すれば、何も考えなくても調べてみれば、そこで起こっているプロセスが見えてくるといった感じだ。その意味で、臨床の現場でも当然役に立つはずだが、疾患の解析研究がほとんどで、臨床の経過を把握して適切な治療を考えるといった状況で使われた論文は見たことがなかった。
今日紹介する米国国立衛生研究所からの論文は、single cell transcriptome検査が患者さんの状態を把握し治療を選択するのに役立つ可能性を示した、臨床の1例報告で1月20日Nature Medicineにオンライン出版された。タイトルは「Targeted therapy guided by single-cell transcriptomic analysis in drug-induced hypersensitivity syndrome: a case report (single cell trascriptomic解析結果に基づいた薬剤過敏症の標的治療:一例報告)」だ。
友人の愛媛大学名誉教授の橋本先生の総説によると、薬剤過敏性症候群(DiHS )は、薬剤の服用によって誘導される薬剤アレルギーの一種だが、難治性で薬剤投与を中止しても病気が進行する。また、この病気の長期化にヘルペスウイルスが関わっていることも明らかになってきた、特異な臨床経過をとる薬剤アレルギーだ。
多くの症例はステロイドの大量療法で治療されている様だが、この論文で紹介された症例はあらゆる治療に抵抗性で、ステロイドやサイクロフォスファマイド、さらにはミコフェノール酸モフェチルなど様々な免疫抑制剤を試みて、ある程度炎症を抑えることができても、薬を離脱できず、その結果腎障害が現れてきたという患者さんだ。皮膚科の経験はないが、医師なら原因を把握できているのに、治療に反応せずあれよあれよという間に悪化する患者さんは必ず経験している。
このとき、まず皮膚に浸潤している細胞を集めて、single cell transcriptome解析をしたら、治療ヒントが得られるのではと着想したのがこの研究で、詳細は省くが、強くサイトカインでJAK-STAT経路が活性化されているT細胞が局所に浸潤していることがこの検査でわかった。
驚くことに、薬剤により誘導されるアレルギー反応なので特定の抗原特異的T細胞が増殖していると思いきや、予想に反して多様なT細胞が反応していることもわかった。
一方、利用しやすい末梢血を用いた検査では、正常と比べて少し差が認められるが、やはり皮膚からの細胞が診断には必要な様だ。
これらの結果から、可能な治療標的を検討し、それまで利用した薬剤を除外すると、ヘルペウスイルス薬とJAK阻害剤が特定され、ウイルス薬を短期、JAK 阻害剤を長期間投与している。結果は劇的で、ステロイドホルモンやサイクロフォスファマイドの使用を減じても症状は再発せず、4ヶ月目の写真が示されているが、皮膚症状は完全になおり、さらにsingle cell trascriptome解析でも活性化リンパ節は消えている。
一例報告としてはここまでだが、この研究ではもう一度同じ様な薬剤反応を試験管内で誘導できるか実験的研究を行なって、薬剤過敏性症候群の反応の特殊性を検討している。試験管内でも、薬剤に対するT細胞活性化が見られるが、これはクラスIIMHC 依存的ではあっても、抗原特異性のないスーパー抗原様の反応であること、さらにこの試験管内の反応をJAK阻害剤だけでなく、抗ウイルス薬でも抑制できることを示している。
結果は以上で、この病気のメカニズム研究がどこまで進んでいるかフォローできていないが、この一例報告はこの病気の理解と治療を大きく進展させたのではという印象を持った。