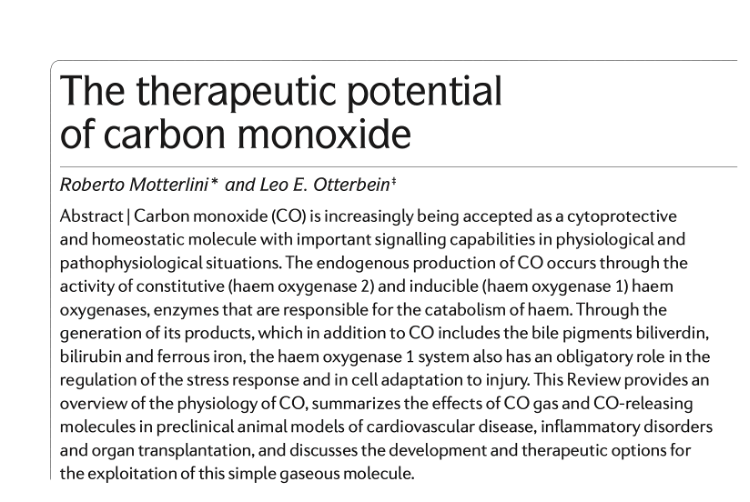2022年7月3日
寄生体に身体を操られるボディースナッチは、SFの世界だけではなく、動物界には結構見られる現象だ。しかし、今日紹介する中国・雲南獣医学研究所からの論文は、Flaviウイルス、蚊、皮膚細菌、そして人間を含む動物と、なんと4種類の生物が関わるという点では複雑の極みで、本当にこんな進化があり得るのかと思える研究だ。タイトルは「A volatile from the skin microbiota of flavivirus-infected hosts promotes mosquito attractiveness(Flaviウイルスに感染したホストの皮膚細菌叢からの揮発物が蚊を惹き付けやすくする)」で、6月30日Cellにオンライン掲載された。
デングウイルスやジカウイルスはネッタイシマカなどの蚊により媒介される。即ち、蚊に刺されたホストで増えたウイルスは、ホストがもう一度蚊に刺されることで初めて蚊に戻り、他のホストへと感染できる。このサイクルをウイルスの立場から考えると、感染ホストの中から体外の蚊を遠隔操作して、感染ホストへと誘導出来れば、増殖機会を増やすことが出来る。しかし、そんな都合のいい遠隔操作が可能なのか。
この研究では、まず感染マウスと、非感染マウスの臭いで満たされるようにしたチェンバーのどちらにネッタイシマカが移動するか調べる実験系を組み立て、なんと感染マウスの臭いは、ネッタイシマカを惹き付けることを明らかにしている。
これだけでも驚くが、感染マウスと非感染マウスから遊離される揮発物質を集め、この解析からアセトフェノンの量が最も多く変化することを突き止める。そして、アセトフェノンを塗布した非感染マウスや、人間の手にも蚊が引き寄せられることから、アセトフェノンこそがウイルスにより操作され、皮膚で作られる分子であることを明らかにする。
次に感染マウス皮膚でアセトフェノンが合成されるメカニズムを探り、皮膚細菌叢を除去するとアセトフェノンの合成が無くなることから、ホストの細胞ではなく、皮膚に常在する細菌叢がアセトフェノンを合成していることを突き止め、アセトフェノンを合成できる4種類の細菌を特定している。
ではなぜアセトフェノン合成細菌が感染ホストの皮膚で増殖するのか?感染ホストの皮膚を非感染ホストと比べることで、最終的にバクテリアに対する抗菌物質の一つRELMαの発現が低下すること、またアセトフェノン合成細菌4種類は、RELMαへの感受性が高く、結果感染によりRELMαが低下した皮膚では、通常より増殖が上昇することを示している。
さらに、この感染によるRELMα低下を補うためにビタミンAの摂取が有効であることも示している。
蚊の誘引物質の実験系、誘引物質の同定、誘引物質合成細菌の同定など、かなり高い実験能力が示された論文で、クエスチョンも面白いが、それをやり遂げる力量にも感心した。ただ、感染、自然免疫、RELMα低下のカスケードだと、別に蚊により媒介されるウイルス感染である必要はない。その点を明確にしてほしいと思う。
しかし、5月7日、ネッタイシマカの脳の活動を調べて蚊の誘引物質を探索する研究を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/19624 )。この研究の場合、誘引物質のカクテルが人間へ蚊を引き寄せる役割を演じていることが示されていた。同じ系を用いて、アセトフェノンの効果を調べる重要性を感じる。これによって初めて、これだけ複雑なサイクルをコントロールするウイルス進化が可能になったのか、理解できるようになるだろう。
2022年7月2日
食事を、見ながら嗅いで、ゆっくり味わいながら食べるほうが、ただ栄養として飲み込んで摂取するより身体にいいことがわかっている。これは、食べ物が視覚や嗅覚、そして味覚を通して脳を刺激し、これが消化吸収後にグルコース濃度が上がってインシュリン分泌が誘導されるより前に、迷走神経を介してインシュリンを分泌させ、代謝を前もって調節しているからと考えられている。この過程に、自然炎症の親玉、IL1β が関わることが最近示されている。
今日紹介するバーゼル大学からの論文は、食べ物の脳への刺激が IL1β を介してインシュリン分泌を誘導するメカニズムを明らかにした研究で7月5日号 Cell Metabolism に掲載された。タイトルは「The cephalic phase of insulin release is modulated by IL-1b(脳を介するインシュリン刺激はIL1βにより調節される)」だ。
この研究では IL1β が脳で働いて、迷走神経を介してインシュリン分泌を刺激するという仮説に基づいて研究を行っている。そこで、まず IL1β を低い濃度で腹腔および脳に注射する実験を行い、腹腔注射では影響がない濃度でも、脳に IL1β を注射するとインシュリン分泌が誘導されることを明らかにする。
次に空腹にしたマウスに餌を与え、最初の一口でマウスを採血、インシュリンを測定すると、食事は全く入っていないのに、インシュリンが分泌される。このとき、IL1β シグナルを抑える薬剤を前もって投与すると、インシュリン分泌が抑えられる。即ち、食べ物の脳への刺激がインシュリン分泌を誘導するには、脳内で IL-1β が分泌されることが必須だ。
この発見がこの研究のハイライトで、あとは
白血球で IL1β をノックアウトしても、脳の刺激によるインシュリン分泌は影響ないこと、このマウスと比べると、脳のミクログリアで最も強く IL1β 分泌が傷害されるようにしたマウスでは、脳刺激によるインシュリン分泌が起こらない。すなわち、ミクログリアが脳内の IL1β の源である。 おそらく視覚や嗅覚などの刺激によりすぐに IL1β がミクログリアから分泌されると、視床の傍脳室核を刺激し、この刺激が迷走神経を介して膵臓でインシュリン分泌を誘導する。 肥満になると、IL1β のレベルが元々高まってしまって、脳刺激による IL1β の効果が消失しており、この結果食事前のインシュリンによるコンディショニングが起こらず、肥満をさらに悪化させることになる。 以上が主な結果で、IL1β が迷走神経を刺激するメカニズム、食べ物の刺激でミクログリアの IL1β が分泌されるメカニズムなど、肝心なところがまだわからない。しかし、IL1β が脳と膵臓をつなぐという結果は重要だ。と言うのも、IL1β は自然免疫のエフェクターの親玉で、肥満、糖尿病、動脈硬化、そして老化などに関わることがわかっている。これが脳の食への感受性を鈍化させるとすると、最終的に肥満では楽しんで食べていないのではと思える。私のような食べることの好きな老人には今後も注目の領域だ。
2022年7月1日
ガス中毒といえば、まず頭に浮かぶ一酸化炭素が、なんと薬として使えると聞くとだれもが驚くはずだ。長年医学論文を読んできた私も全く初耳だった。当然今日紹介するハーバード大学からの論文のタイトル「Delivery of therapeutic carbon monoxide by gas-entrapping materials(治療用一酸化炭素をガスを閉じ込める材料を用いて患部に届ける)」を見ると、それだけで引きつけられる。
イントロ部分を読むと、一酸化炭素が何故薬になるのかまとめた総説が2010年、Nature Review Drug Discoveryに掲載されているので、ざっと目を通してみた。
勿論、ヘモグロビンに結合してしまうと酸素と拮抗して、呼吸が出来なくなる。しかし実際には私たちの体の中でも一酸化炭素が作られており、局所でヘムを持つ分子と相互作用を行い、様々な効果を発揮すること、特に血管リラックス効果のあるNO産生に重要な働きをしていることが述べられている。その結果、炎症や損傷治癒を促進する効果があり、外部からCOを投与しても、十分同じ効果を得ることが出来るようだ。
しかし、どうやって安全な量の一酸化炭素を患部に投与するのか?今日紹介する論文の目的は、大腸にCOを投与する方法の開発で、6月29日号Science Translational Medicineに掲載された。
極めて単純化して結果をまとめると、多糖類の一つキサンタンガム、メチルセルロース、そしてマルトデキストリンを基質にして、ホイップクリームを作り、そこに一酸化炭素を溶け込ませるという方法を用いると、経口的に胃を満たしたり、あるいは肛門から逆行的に直腸を満たして、局所でヘモグロビンと結合できることを示している。すなわち、COを比較的簡便に投与可能で、ヘモグロビンへの結合から見て、組織内で利用されていることを示している。
そして、安全な量を直腸に投与することで、
アセトアミノフェンによる肝臓の急性中毒を軽減できる。 デキストランスルフェーとによる慢性腸炎をほぼ完全に抑えることが出来る。 放射線による大腸上皮の障害を抑えることが出来る。 を実験的に示し、様々な病気の基礎治療として用いることが出来ることを示している。
大変勉強になったが、今後ホイップクリームの作り方などを工夫して、様々な治療に役立てられる可能性を感じた。