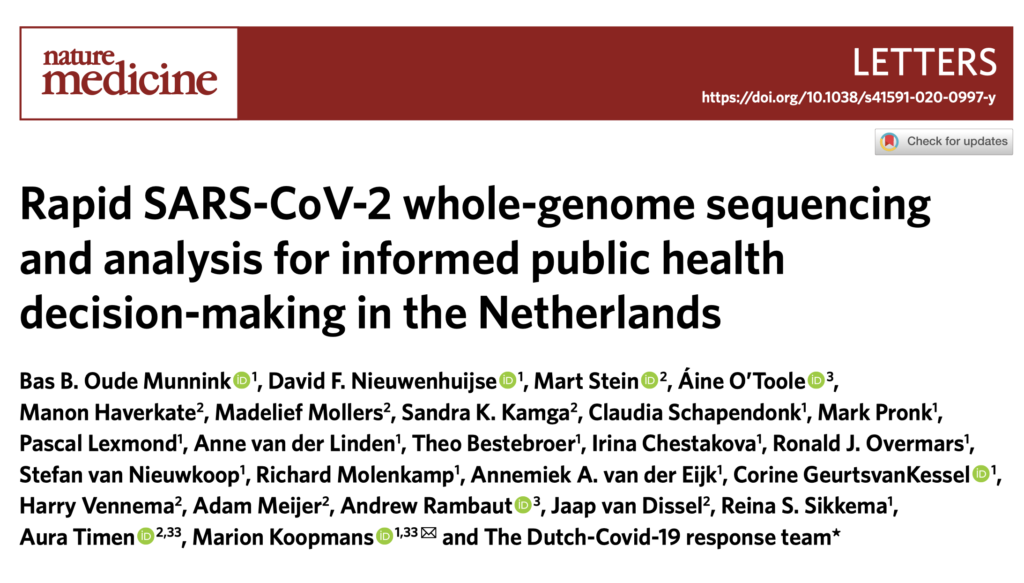2020年7月23日
現在急速に新型コロナウイルス(Covid-19)感染が広がりをみせており、緊急事態宣言時を超える勢いだ。ただ発表される感染者数なるものは、外野の私には何の指標なのかさっぱり理解できない。もしウイルス感染の広がりを把握したいなら、特定の地域でランダムサンプリングによるPCR検査をおこない、その感染状況から推定するしかない。ただ、我が国でそこまで手が回るようになるにはまだまだ時間がかかるだろう。
幸い、ウイルスは人から人へと感染を繰り返すたびに変異する。したがって、この変異を追いかけていけば、バイアスがかかったサンプルでも、ある程度社会全体の感染の広がりを推定することが可能になるのではと思っていた。ネアンデルタール人のゲノムの多様性から、当時の人口を推察するのと同じだ。例えば現在、感染経路が、追跡可能か、不可能か、が問題になっているが、ウイルスの系統樹データがあれば、予測精度は格段に高まることは間違いない。
そのためには刻々変化する感染者から得られるウイルスゲノムをリアルタイムで解析し、それぞれのウイルスの系統樹と個性を計算できるグループが必要になる。当然我が国の感染症研究所でもゲノム解析を行っているが、報告を読むと政策決定のための(例えば神戸のウイルスは東京由来とか)リアルタイムデータ提供を目指している計画とは思えない(間違っていたらごめんなさい)。
しかし今からでも遅くない。データに基づき感染の拡大を把握するため、PCR陽性者が感染しているウイルスゲノムをできるだけ多く調べることで、感染状況をとらえ、正しい政策判断につなげることができることを示した論文が、オランダからNature Medicineに発表された。
この研究ではオランダで2月最初の2症例が報告されて以来、クラスターや、医療施設で働く人たちを中心にモニターし、3週間で189種類のウイルスの全ゲノム配列が決定されている。
この結果、オランダでの感染は1月の終わりに遡れること、おそらくイタリアのスキー場由来の、すでに異なる2株のウイルスに由来していること、持ち込んだ人から地域単位で流行が起こっていることなどが明らかにされている。この研究の対象になった3週間ほどの間にオランダで分離され解析されたウイルス間で、平均の変異数は7.39であり、ランダムサンプリングによる感染拡大を調べる代わりに、ウイルスの側から感染拡大を推測できる可能性が高いことを示している。
要するに、ウイルスの系統樹は感染拡大を知るために極めて重要なデータになることが示された。とすると、現在の我が国のように、感染源を特定できない感染者が拡大し、都市から地方へと感染が拡大している状況の把握に必要なデータが、ウイルスゲノム解析から得られることを示している。
政策決定にも使えるデータとして重要なのはリアルタイムにデータが出ることだが、現在の次世代シークエンサーでは、どうしても解析が終わった時点で2週間かかる。とすると、政策決定には間に合わない。
この研究では常に配列を至適化するプライマーでウイルスを増幅し(ここまでは他の研究と同じだと思う)、それをナノポアフローセルで解析することで、時間の短縮に成功している。要するに、なんとか政策決定に役立てようと一工夫した結果だ。
ぜひ我が国でも、このスピード感でウイルスの解析が進むことを期待する。Go to Travelの評価も、これにかかっているような気がする。
2020年7月23日
相分離概念が導入された今は、核小体はリボゾームを合成するための分子が相分離で濃縮された区域と考えられ、そこではリボゾーム形成に必要なDNA、RNAそしてタンパク質が相転換で濃縮している。そこで合成されたリボゾームは核小体という相分離区域から分離され、最終的には核外へと移行しmRNAと結合して翻訳を行う。すなわち、相分離した区域は渦のように、ダイナミックに成分が変化しつつ、形態を維持していることになる。
今日紹介するトロント大学からの論文は、核小体という相分離体のダイナミックスを垣間見ることができる研究で7月15日号のNatureに掲載された。タイトルは「Nucleolar RNA polymerase II drives ribosome biogenesis(核小体内のRNAポリメラーゼIIはリボゾーム合成を推進する)」だ。
教科書的には、核小体でポリメラーゼI(pol I)が18S、5.8S、28SリボゾームRNAを合成し、そこに核小体の外でPol IIIにより合成された5SrRNAが移動して60S、40S リボゾームが合成され、相分離体から分離すると言えるが、この研究は核小体に普通のmRNA転写に関わるPol IIも局在しているという発見から始まっている。
核小体でPol IIは何をしているのか調べるために、短い時間Pol IIを阻害する実験を行うと、rRNA合成が低下することから、何らかの機能があることがわかる。さらに、免疫沈降で見るとrRNA遺伝子がコードされた領域の間にPol IIは結合し、Pol Iは期待通りrRNAの上流に結合していることがわかる。
次にpol IIが結合している領域はPol Iによりセンスnon coding RNA(ncRNA)が転写されていること、そしてpol IIは同じ領域のアンチセンスncRNAの転写に関わることが明らかになった。すなわち、pol Iとpol IIが同じ領域で一見拮抗しているような結果になった。
もちろんどちらもrRNA合成に必要なので、センス/アンチセンスそれぞれのncRNAが核小体維持にどう関わるかを次に調べ、
Pol IIはPol IによるセンスRNA転写を抑える。 センスncRNAは核小体の相分離構造を不安定にするが、Pol IIによりこれが抑えられることで核小体構造を安定化する。 Pol IIによるアンチセンスRNAはDNAとRループと呼ばれるトリプレックス構造を形成することでセンスncRNAの合成を抑制する。 このようにこのDNA領域にはPol I, Pol II, そしてヘリカーゼSenataxinがPol IIとこの領域との結合を調節している。 多くのガンではセンスncRNAの転写が高まっており、この結果核小体相分離体が不安定化することが、ガン細胞で核小体の構造が複雑化する原因になっている。 なぜ核小体を不安定化する要因をわざわざ維持しているのかなど、まだすっきりしないところもあるが、しかし核小体でのリボゾーム合成のダイナミズムを考えると、わざわざ不安定化させることの重要性もわかるような気がした。
2020年7月22日
大学生時代私もその傾向があったが、慢性的に排便異常が持続するにも関わらず検査で異常が認められないと、過敏性腸症候群(IBS)と診断される。これに対し、明らかに炎症症状が見られる場合は炎症性腸疾患(IBD)と診断されるが、実際には両者を診断するのは簡単ではない。
今日紹介するカリフォルニア大学デービス校からの論文はこの境を超えるメカニズムを探った研究で8月12日にCell Host & Microbeに掲載予定だ。タイトルは「High-Fat Diet and Antibiotics Cooperatively Impair Mitochondrial Bioenergetics to Trigger Dysbiosis that Exacerbates Pre-inflammatory Bowel Disease(高脂肪食と抗生物質は強調してミトコンドリアのエネルギー代謝を変化させ、腸内細菌叢の変化と炎症性腸疾患前段階を悪化させる)」だ。
炎症か過敏かの境を診断するためのマーカーの一つが便中に排出されるcalprotectinだが、まだ過敏症の段階(IBS)と診断された患者さんの中でcalprotectinが高い患者さんを選んで食事の傾向、および抗生物質投与歴などを調べると、高脂肪食と最近抗生物質の投与を受けた経歴が強く相関ししていることが明らかになった。このグループをIBDの前段階(pre-IBD)と分類して腸内細菌叢を調べると、IBSの段階で既にビフィズス菌や乳酸菌が低下し、pre-IBDになるとclostridiaが低下、Enterobacteriaceaeが上昇するという、IBDの特徴を示すようになることがわかった。
人間ではこれ以上の解析は難しいと、今度はマウスに高脂肪食と抗生物質を投与する実験を行い、両者を投与した時ほぼ人間と同じcalprotectinの上昇を伴うpre-IBD状態が誘導できることを示している。
同じ病態が再現できると、pre-IBDに至るメカニズムを調べることが可能になり、
高脂肪食に抗生物質(この研究ではストレプトマイシン)が加わると、上皮のミトコンドリアのエネルギー代謝がoxgenationの方向に移行し、腸内での酸素濃度が高まる。 この結果、好気的条件をこのむE coliが増殖し、腸内に炎症が誘導される。 抗生物質と高脂肪食は協調して腸上皮のPPARγの発現を低下させ、細胞代謝をoxigenation側へリプログラムするが、PPARγをamino salicylic酸で刺激すると、腸上皮の代謝は正常化し、炎症も抑えられる。 おそらく抗生物質は腸内細菌叢を除去することで、PPARγシグナルに関わるブチル酸を低下させ、高脂肪食は直接ミトコンドリアのエネルギー生産に作用して、pre-IBDを誘導する。 以上が結果で、特に新しい発見はないが、IBS段階でIBDへ悪化させないための介入については重要な情報だと思う。
2020年7月21日
造血幹細胞研究は細胞系譜追跡技術とともに発展してきた。幹細胞のコロニー形成法、limiting dilutionと骨髄移植、FACSによる幹細胞の濃縮、レトロウイルスによる幹細胞ラベル、そして単一幹細胞移植など、今から考えると懐かしい。しかし、FACSによる幹細胞の濃縮を除くと、研究手法は最近急速に変化した。これを支えるのがバーコードによる細胞ラベリングと、single cell RNA sequencingだ。
今日紹介するハーバード大学からの論文は新しい世代の造血幹細胞研究の典型といえる研究で、新旧の手法を見事に組み合わせて造血幹細胞の骨髄移植時の再構成能力を決めている遺伝子TCF15を特定した研究で、7月23日号Natureに掲載予定だ。タイトルは「Single-cell lineage tracing unveils a role for TCF15 in haematopoiesis (単位いつ細胞レベルの細胞系譜追跡によりTCF15の造血における役割が明らかになった)」だ。
この研究ではFACSで濃縮した造血幹細胞を、バーコードを組み込んだレンチウイルスに感染させ個々の幹細胞を識別できるようにする。その上で、1000個の標識した細胞を放射線照射マウスに移植、4ヶ月後にマウスの骨髄中に存在する様々な血液前駆細胞と最も未熟な造血幹細胞を別々に調整、scRNAseqでバーコードによる細胞の系譜と、遺伝子発現を同時に特定し、移植した1000個の中に含まれていた幹細胞の能力を分類しようとしている。
結果はこれまでの長年の研究で確認されてきた結果とほぼ同じで、幹細胞の中には早く分裂して多くの分化細胞を供給する幹細胞と、ゆっくり分裂し供給する分化細胞数は多くない幹細胞の2種類に分かれ、それぞれは発現遺伝子が異なっていることが確認された。
この研究ではこうして解析したドナーの骨髄から精製した未熟幹細胞をもう一度移植して、やはり4ヶ月後に骨髄細胞を採取してscRNAseqで解析することで、一次ドナーの造血系に存在するどのタイプの幹細胞が、造血再構成能力が高いかも調べている。さすが、バーコーディングならではと思える実験だが、結果は従来の結論を見事に確認している。すなわち、転写因子の発現パターンで決められているゆっくり自己再生して、分化細胞リクルートには大きく寄与しない血液幹細胞は、移植を繰り返しても同じ能力を維持して、造血の核として働くという結果だ。
ここまでだと、見事な結果とはいえ新規性がないと言われる可能性があるので、最後にクリスパーによるマウス内でのノックアウトを行い、その結果分化した幹細胞分画が増える遺伝子を探索し、TCF15を特定する。
TCF15は初期発生に重要な働きをすることが知られているが、造血幹細胞に関してあまり注目されてはこなかった。そこでノックアウトの効果を、クリスパーによる造血幹細胞のTCF15ノックアウトで確かめると、期待どおりゆっくり増殖する未熟幹細胞が消失する。また、蛍光遺伝子をTSF15に挿入してTCF15陽性、陰性の幹細胞を移植すると、陽性幹細胞のみ造血を再構成することを確認している。
幹細胞の自己再生に必要な分子TCF15まで到達している点も重要だが、従来の造血幹細胞研究と、新しい造血幹細胞研究を結びつけるという意味で、古い世代の私としては高く評価したい。
2020年7月20日
癌が腹膜に浸潤して腹水が貯留して患者さんの体力を奪う状態は、癌のなかでも最も進んだステージで、治療が困難だ。ただ、これよりさらに恐ろしい状態が知られている。これが、髄膜に癌が転移し、脳脊髄液を介して癌が中枢神経系全体に広がる状態で、おそらく免疫系が起死回生の逆転劇を演じてくれない限り、治すことは難しい。
今日紹介するスローン・ケタリング癌センターからの論文は、この髄膜癌腫症の治療法開発を目指した研究で7月20日号のScienceに掲載された。タイトルは「Cancer cells deploy lipocalin-2 to collect limiting iron in leptomeningeal metastasis (髄膜癌腫症ではガン細胞がleptocalin-2を使って結合した鉄を集めている)」だ。
この研究もsingle cell RNA sequencing (scRNAseq)の臨床医学への貢献を示す例で,髄膜癌腫症を発症した乳がん患者さんの脳脊髄液中のガン細胞をscRNAseqを用いて解析し、脳脊髄液(CSF)への浸潤が起こる条件を探っている。その結果、腹水と同じで、髄膜癌腫症でもCSF中にガン細胞をはるかに超える数の白血球やリンパ球の浸潤が見られる炎症が起こっていること、そして調べた全てのガン細胞で鉄の細胞内輸送に関わるlipocalin-2(LCN2)とその受容体が強く誘導されていることを発見する。
もともとCSFは栄養に乏しい低酸素環境で、がん細胞の増殖に適した環境ではない。このことを考慮すると、鉄を集めてくる分子が強く誘導されることは極めて理にかなっている。
そこでマウスモデルを使ってメカニズムを解析し、
CSF中でのがん細胞の増殖にはLCN2が必須で、発現を抑えると増殖が止まる。特に鉄イオンは低酸素条件での増殖に必須で、LCN2の機能が抑えられると、低酸素状態で細胞死に陥る。 LCN2は血液細胞から分泌される様々な炎症性サイトカインによって強く誘導される。 を明らかにしている。すなわち、鉄イオンを他の細胞との競合に勝って取り込んで、低酸素状態でも増殖できることが髄膜癌腫症の条件になる。とすると、鉄イオンをCSFから除去すると腫瘍の増殖を抑えられる可能性が出てくる。
最後に、鉄のキレート剤を脳室に投与してCSF内でのガンの増殖を調べると、期待通りガンの増殖を抑えることに成功している。
以上が結果で、臨床例の解析からスタートして、マウスモデルではあっても一つの治療法の可能性にたどり着いており、臨床まで進むことを期待したい。個人的印象だが、髄膜癌腫症の場合、すべてのタイプのT細胞が浸潤していることがscRNAseqから見て取れるので、うまくこれらを活性化して、ガンを除去する方法もぜひ開発してほしいと思う。
2020年7月19日
最近私の周りでも乳ガンにかかったという人が増えたが、手術しか手がなかった時と比べると、ネオアジュバント、手術、アジュバントを組み入れた治療へと大きく変化しており、年寄りにはよりはっきりと医学の進歩を感じさせてくれる。
ただ、まだまだ改良の余地があるようで、今日紹介するミラノ大学からの論文は、これに一種の断食、あるいは断食と同じ状態を再現できる食事を合わせると、ホルモン受容体陽性/HER2陽性乳がんのコントロールを高めることができるという研究だ。タイトルは「Fasting-mimicking diet and hormone therapy induce breast cancer regression (断食と同じ効果を持つ食事とホルモン治療により乳ガンの縮小を誘導できる)」だ。
この研究で用いた断食とは1週間に2日間水以外は摂取しない方法で、研究の真の目的は、Xentigenと名付けられた低炭水化物を中心とした食事療法が断食の代わりになることを示すことだ。
研究ではまず、Xentigen食により、断食と同じ効果が得られ、インシュリン、IGF1そしてレプチンの血中濃度が低下すること。それに伴い、エストロジェン阻害剤による乳ガン治療の効果がさらに高まることを動物実験で示している。
また腫瘍増殖を抑制するだけでなく、「嘘か?」と思えるほどの多様な効果を発揮する。まず、タモキシフェン治療による子宮内膜の増殖や内臓脂肪の増加を防ぎ、アディポネクチンの分泌を低下させ増殖をさらに抑制する。また、ガンの増殖を抑制する因子の一つEGR1を強く誘導することでもガンの増殖を抑える。これらの結果、薬剤耐性ガンの発生を抑え、さらには最近期待のCDK4/6阻害剤の効果を高める。
生化学の詳細は省くが、要するに断食状態を導入してくれる食事療法が乳ガン抑制に予想以上の大きな効果を持つことを示している。とは言っても、動物モデルだけでは論文は採択されない。この研究では36人の患者さんでXentigenベースの食事療法の効果を調べた治験で効果が見られたケースがあることを示している。また、期待通り食事療法でIGF1やアディポネクチンを低下させることも示しており、腫瘍増殖を助ける因子の分泌を抑えることは示している。しかし、これらは全て1/2相の段階で、実際には臨床効果についての最終結果は示されていない。
その点でフラストレーションは残るが、一部の例と、腫瘍増殖因子の抑制は達成できており、いい結果が期待され論文が採択されたのだと思う。早く結果を示して、乳ガンの治療に組み入れてほしいと期待している。
2020年7月18日
今日はようやく時間ができた週末なので、論文ウォッチで紹介した論文以外に、新型コロナウイルスに関する論文を紹介する。といっても、ソーシャルディスタンシングを遵守するための脳機能について調べた変わり種の論文だ。
米国立衛生研究所とカリフォルニア大学リバーサイド校からの論文で、米大統領が緊急事態宣言を発令した2週間後、どの程度ソーシャルディスタンシングを守ったかについてのアンケート調査と、ウェッブを通じて行う作業記憶のテストの相関を調べた研究だ。
「え!世の中の規範に従う心が記憶と相関するの?」と思ってしまうが、これまでもこの可能性は示唆されていたようだ。
研究では、例えば緊急事態宣言以降、パーティーなどの集まりをさけている、イベントには参加しない、握手やハグをしない、などすでに一般的になっているソーシャルディスタンシング遵守のための項目について、守っているからほとんど守らないまで、点数をつけさせ、各人のソーシャルディスタンシングスコアを計算している。
これと並行して、画面に映る5枚の異なるパネルの位置を1秒後に覚えているかどうかのテストを行いスコア化している。
面白いのは、これらすべてのテストをグーグルの提供するプラットフォームを用いてリモートで行なっていることで、まさに新型コロナウイルス流行時の調査研究のお手本と言っていいだろう。
すべての詳細を省いて結論を述べると、作業記憶力が高いほど、ソーシャルディスタンシングを遵守する傾向があるという結果だ。
極論すれば公明性や公共性もすべて記憶問題と結論できるので、にわかに信じがたいが、その時のムードや性格など様々な要件をすべて差し引いても、この結論は生き残るようだ。
著者も気になったのか、さらに公平性を調べるためのゲーム課題(詳細は省く)に参加してもらい、公平性と作業記憶力の相関を調べると、公平な人ほど作業記憶力が高いという結果を得ている。
作業記憶というのは、ある時間内に私たちが経験したことを一時的に脳内に保持する能力を指しており、長期記憶と区別しているが、結局周りの状況を集めて判断する能力が、ソーシャルディスタンシングを守る公共性につながると結論していいのだろう。
ただこれは米国での話だ。強制しなくとも自粛が徹底する国と言われている我が国で実際どうなのか、誰か是非調べてほしい。
2020年7月18日
前回、新型コロナウイルスに対する抗体反応は、もともと人間が生まれついて持っている(germ line:GL)抗原反応部位遺伝子(V遺伝子)(Vgl)の組み合わせで、十分高い活性の抗体が形成されるため、ウイルス抗原に合わて突然変異を蓄積するという通常の成熟過程があまり必要でないことを紹介した(https://aasj.jp/news/watch/13476 )。その後同じ結果を支持する論文が私が知る限りで2報発表されているので、人間はもともと活性の高い抗体を作れるように生まれついているのだろう。中和抗体を目指したワクチン開発には朗報と言える。
さらに、現在急速に進んでいる中和活性の高いモノクローナル抗体による治療開発も、実現は近いだろう。ウイルスに対する抗体が病気を悪化させる危険(ADE)も議論されているが、一旦中和活性のあるモノクローナル抗体まで到達すると、抗体分子に操作を加えることでADEを十分回避できる。高額ではあっても、治療の切り札の一つが手に入る日は近い。
しかし、ウイルス感染に対する免疫反応は、抗体反応だけではない。ウイルスがコードするタンパク質に対するT細胞反応が重要な鍵を握っている。いくらVglの組み合わせでいい抗体ができるとはいえ、反応が誘導されるためにはT細胞の助けが必要だ。さらに、多くのウイルスで、感染細胞標的にするキラー細胞がウイルス防御に重要な働きをすることが知られ、このようなウイルス特異的キラーT細胞を誘導できるワクチン開発が、様々なウイルスに対して進められている(https://aasj.jp/news/watch/12433 、https://aasj.jp/news/watch/13369 )。
ただウイルスに対するT細胞の反応を調べるのは抗体を調べるよりはるかに難しい。というのも、ウイルス抗原(ウイルスのタンパク質から切り出される短いペプチド)を認識するためには、このペプチドが組織適合性抗原(MHC)と一緒に細胞の表面で提示されないと、T細胞は反応できない。そして最大の問題はこのMHCの組み合わせが個人個人で大きく違っており(だからこそ移植臓器拒絶が親子間でも起こる)、T細胞がウイルスペプチドを認識する確率は、どのMHCを持っているかで大きく変化することが知られている(https://aasj.jp/news/watch/12923 )。
このように、ウイルスに対する免疫の議論には、抗体だけでなくウイルスに対するT細胞の反応を正確に測定することが必要になる。事実、困難を乗り越えてこの難しい課題にチャレンジした研究は読んでいても面白い。驚くことにLa Jolla研究所からの論文では、新型コロナウイルスに感染した人だけでなく、感染していない人にもT細胞免疫が成立していることが示唆された(https://aasj.jp/news/watch/13125 )。
今日紹介するシンガポール・デューク大学からの論文は、この研究をさらに進めて、異なるコロナウイルス感染によりT細胞免疫が成立する可能性について調べた研究で7月15日号のNatureに掲載された。タイトルは「SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls (Covid-19感染者、SARS感染者、および非感染者のSARS-CoV-2に対するT細胞免疫)」だ。
この研究では最初からコロナウイルス間でペプチド配列がよく似ている4種類のウイルスタンパク質に絞ってT細胞の反応を調べている。2つは構造タンパク質、NP-1,NP-2で、非構造タンパク質として選んだNSP7とNSP13はベータコロナウイルス間で完全な相同性が存在している。
これらのタンパク質からT細胞が認識すると予想できるペプチドを216種類作成し、40種類ずつプールして刺激に用いている。T細胞は末梢血に存在するT細胞で、反応はペプチド刺激によるインターフェロン分泌、および刺激されたインターフェロン分泌T細胞の数をフローサイトメータで数える方法を用いている。全てシンガポール在住の成人で、半分がアジア系なので、我が国での免疫状況を考える意味で参考になる。
結果は以下のようにまとめることができる。
新型コロナウイルスに感染した後回復したひと達は、全員ウイルスの構造タンパク質NP1およびNP2由来ペプチドに対してT細胞免疫が成立しており、直接インターフェロン分泌T細胞数を調べたケースではCD4,CD8両方の反応が見られた。一方、NSP7,NSP13に対して一定程度以上の反応が見られたのは3割程度の人だった。 以前SARSに感染した人で調べると、低いレベルではあるがやはり新型コロナウイルスNP1,NP2に対する反応を見ることができる。そして、このとき反応するT細胞は、試験管内でもう一度刺激しなおすと、100倍近い反応を示す。すなわち、刺激に反応して増殖し、さらに強い反応を示す記憶が成立している。 SARSにも、新型コロナウイルスにも感染経験のない人を調べると、なんと半分以上の人(19/37)がウイルスペプチドにはっきり反応する。この反応も、SARSに感染歴のあるケースと同じで、試験管内で刺激に応じて細胞が増殖する記憶反応を示す。特に驚くのは、非感染者はベータコロナウイルス間で保存されたペプチドにだけ反応している点で、ベータコロナウイルスのNSP7やNSP13に対するT細胞記憶が、新型コロナウイルスでも動員される可能性が示された。 非感染者で実際に反応しているペプチドを特定し、その由来を探ると、人間のコロナウイルスより、動物が感染しているベータコロナウイルス由来である可能性が高い。 以上が結果で、新型コロナウイルスに対する免疫をT細胞の反応から見ると、今議論されているウイルス型といった細かな差異とは全く関係なく、ウイルス間の共通部分に対する複雑な交差性をもった記憶が成立していることを示している。すなわち、様々なベータコロナウイルスに対する感染歴により、新型コロナウイルスに対するT細胞免疫が、地域ごとに成立している可能性すら示唆している。
今ウイルスに対する免疫については、様々な説が展開されているようだが、我が国でもまずこのレベルの免疫反応検査を行った上で議論しないと、結局何も結論は出ないと思う。
2020年7月17日
バーコード技術と単一細胞遺伝子解析技術を組み合わせたsingle cell RNA sequencing (scRNAseq)は、これまで器官や組織としてトップダウンに眺めてきたシステムを、細胞側からボトムアップに見ることを可能にした。その結果、発生、ガン、感染症など様々な状態を、全く新しい目で定義することが可能になっている。
今日紹介するマウスに存在する細胞のscRNAseqデータを集約するためのスタンフォード大学を中心にしたコンソーシアム、The Tabula Murisからの論文は、このマウスの細胞アトラスを異なる年齢で作成し、老化による変化を調べた研究で7月15日号のNatureに掲載された。タイトルは「A single-cell transcriptomic atlas characterizes ageing tissues in the mouse(単一細胞のトランスクリプトーム解析によりマウス組織の老化の特徴を明らかにする)」だ。
研究は単純で生まれてから、0、1、3、18、21、24、30月齢と異なる年齢のマウスから23種類の臓器を取り出し、細胞浮遊液を作成、scRNAseqを行い、この全てを一つの図上に展開したTabula Murisを作成する。結果、このテーブルでは細胞が由来した組織と年齢については色分けされており、これにより同じ血液細胞でも臓器別に遺伝子発現から特徴を調べることができる。
膨大なデータが集められたことは間違いなく当然紹介しきれない。そこで、論文としてまとめるために、幾つかの例に注目してこのテーブルの有用性を示したというスタイルになっている。その中の面白いと思った点だけ紹介しておく。
老化とともにp16を発現した静止期の老化細胞がほとんどの臓器で蓄積している。これと並行して、抗老化遺伝子としてよく知られているsirtuinファミリー分子の発現している細胞の割合が低下する。(これまでも紹介してきたように、このような老化細胞を積極的に除去するsenolysis治療の有効性を示しているように思える。) 例えば膀胱を例に比べると、老化とともに上皮細胞の割合が上昇し、逆に間質細胞の割合が低下する。これを反映して、コラーゲンなどのマトリックス形成遺伝子の発現が低下、一方で上皮細胞の遺伝子が上昇する。間質細胞の減少に伴い血管の量が低下するが、それでも浸潤血液細胞の数は増加する。(血管も含めた組織を支えるストローマ細胞が老化により疲弊する一方、慢性炎症は続くと言える)。 もちろん上皮細胞自体も低下する器官も存在する。例えば腎臓では、血管系の減少だけでなく、メサンジウム、細尿管などの現象がみられ、これらが老化に伴う腎臓機能の低下の背景にある。 リンパ組織では、T細胞の割合が低下し、逆にB細胞や形質細胞の数は上昇する。一方抗原受容体の多様性を調べると、TもBもクローンが老化とともに増加し、多様性が低下する。 どの細胞で最も大きな変化が見られるか調べると、脳と腎臓の存在する免疫細胞で最も大きな変化が認められる。特に脳では、この変化を担うのはミクログリアで、老化の影響を強く受けることがわかる。 他にも多くの変化の例が示されているが、省略する。これまで描いていたイメージと特に変わることはなく、老化した細胞が蓄積することと、慢性炎症が老化の重要な要素であることが確認できたが、これを詳細にわたって解析するための一つの基盤が提供されたと言っていいだろう。多くのアイデアがこのテーブルから生まれることを期待する。
2020年7月16日
現在神経投射を調べるためには、神経細胞に蛍光色素を注入し、そこからのビルアクソンがどこに到達しているかを蛍光顕微鏡で見る方法で行なっている。しかし、蛍光色素の数をある程度増やせるものの、同じ動物で同時に様々な神経からの投射を調べることはほぼ不可能に近い。しかし現在ではこのような場合、色素の代わりにバーコードを利用することが可能だ。
今日紹介するコールドスプリングハーバー研究所からの論文は、バーコードを用いて神経投射を追跡する可能性を検証した研究で7月9日号のCellに掲載されている。タイトルは「BRICseq Bridges Brain-wide Interregional Connectivity to Neural Activity and Gene Expression in Single Animals (BRICseq法は脳全体の領域間の結合性と、神経活動及び遺伝子発現を同じ動物で橋渡しする)」だ。
この研究では30塩基対のバーコードを挿入したシンビスウイルスベクターを脳の特定の領域に注射、その領域の神経細胞に感染させることで神経をラベルしている。シンビスウイルスは神経のアクソンを通って、支配領域まで到達するので、どこに特定のバーコードを持ったウイルスが存在するかを調べることで、投射の有無を確認できる。
実際には細胞体が存在する場所で最もウイルスの数が多く、神経軸索ではほんの少しのウイルスが存在していると考えられる。これを利用すると、バーコードの存在を追いかけることで、神経の投射を再構成することができる。
ただ神経の結合性を知りたい場合は、脳の解剖学的情報は必須になるので、ウイルスを投射した後、脳組織を小さなブロックに分けて、各場所のブロックにバーコードが存在するかを調べ、この情報から神経投射を再構成するという手間が必要になる。ただ、これが可能になると、あとは同じ脳の別の場所に何箇所もウイルスを注入し、異なる領域間の結合性を同時に再構成することが可能になる。
このために、脳全体をさらに小さなブロックに分け、それぞれのブロックからレーザーで細胞を取り出し、シークエンサーでバーコードの存在と種類を特定している。
何か極めてハイテクに見えるが、著者らは、この方法は手間はかかるが、多くの領域にバーコード付きウイルスを注入して、脳全体を各ブロックの配列を決め、結合性を再構成するためのコストは1ヶ月1万ドルで、どんな研究室でも可能な方法であることを強調している。
この研究のハイライトはあくまでも方法についての着想で、結果については、かなりの精度で投射を追跡することができるという以外にない。ただ、異なるマウスで同じ実験を繰り返してもほぼ同じ地図を作成できることから、再現性の高い方法であることを示している。
そして、この方法の妥当性を確かめるために、カルシウムイメージングで特定した機能的結合性とBRICseqを同じマウスで行い、BRICseqによる結合性と、カルシウムイメージングによる神経興奮の結合性が一致していること、さらにこれにアレン研究所で作成された遺伝子発現マップを重ね合わせ、10種類の遺伝子の発現でこの結合性が予想できることを示している。
要するに、脳の解剖学的結合性が、機能的結合性を支え、さらにこれが遺伝子発現の結果であるということを再確認させて、この方法の重要性を示している。しかし、バーコードの発展、すなわち「見るから読む」への転換はとどまることを知らない。