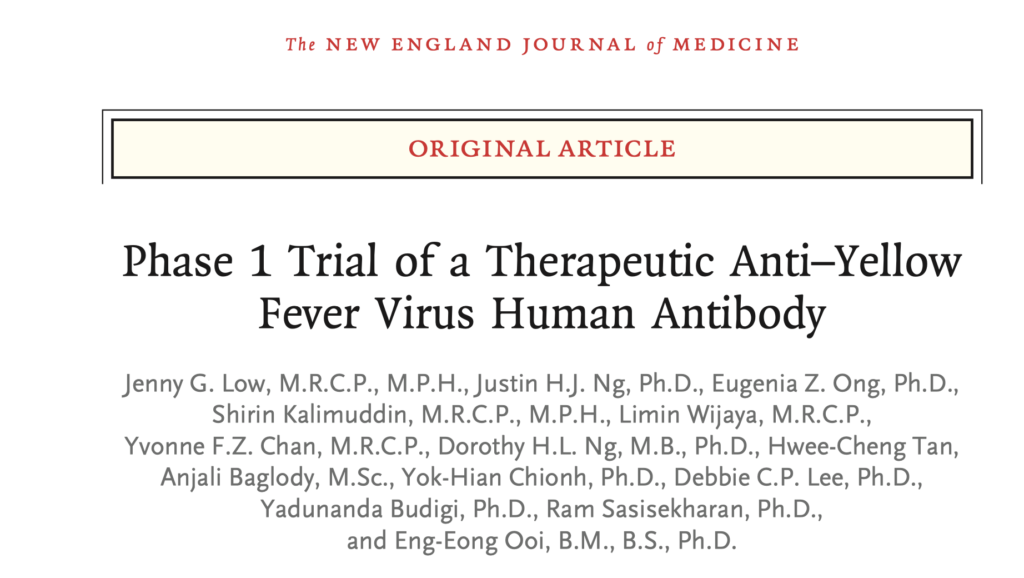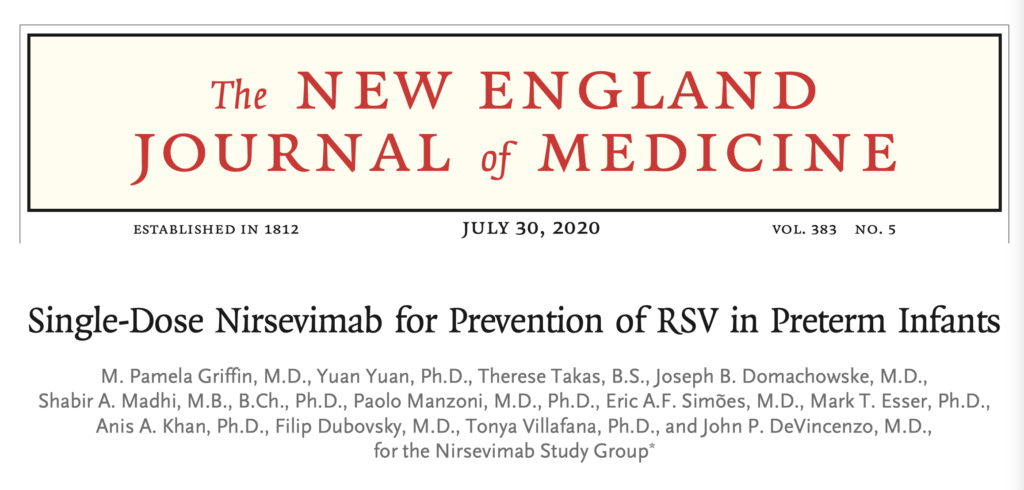2020年8月7日
現役を引退した頃は、様々な動物や植物のゲノム解読データはトップジャーナルに採択されていた。しかし、いつ頃からか新しい種のゲノム解読データは専門誌に回るようになり、そこまで手が回らない隠居の身では、ほとんど新しい種のゲノム論文を読まなくなってしまった。しっかり読んだ最後のゲノム論文は確かアフリカ爪ガエルのゲノムだったように思う。
今日紹介するニュージーランド・オタゴ大学からの論文は、同国固有種のムカシトカゲのゲノム解読についての研究で、新型コロナウイルスの論文であふれたNatureに8月7日オンライン掲載された。タイトルは「The tuatara genome reveals ancient features of amniote evolution (ムカシトカゲのゲノムは有羊膜類の進化の太古の特徴を明らかにする)」だ。
読んでみると、これまでの新しい種のゲノム研究と特に変わることなく、ゲノム全体の特徴とともに、進化過程に関する推察、そして種の特徴に関わる遺伝子についての考察と進んでいく。
ただ、ムカシトカゲは、ニュージーランドにだけ生き残ったゴンドワナ大陸に栄えた種の末裔で、絶滅危惧種であること、カメをのぞくと最も長生きする爬虫類で、100歳は生きるとされていること、体温が16〜21度と低いこと、薄暗い中で優れた視力を示すことなど、面白い性質を持っていることから、Natureに掲載されたのだろう。
中でも決定的に面白い点は、5Gというヒトゲノムを凌駕するゲノムを有し、この巨大サイズが最近まで活動的だった様々なタイプの繰り返し配列によって構成されていること、そしてこの繰り返し配列が爬虫類特有のタイプと、なんと哺乳類特有のタイプの両方が共存していることがわかった。すなわち、ムカシトカゲが有羊膜類が哺乳動物と爬虫類に分かれた時期の特徴を残していることが推察される。
もちろん、ムカシトカゲの持つ特徴についても、ゲノムからバックアップが行われている。中でも最も面白いのは、低体温をサポートする仕組みだが、温度を感じるTRP遺伝子の数が増大していることが、重要なメカニズムではないかと想像している。
他にも、夜行性であるにも関わらず、色彩を感じるオプシン遺伝子は5種類も存在し、しっかり色を感じることが明らかになった。成長するまでは逆に昼行性であることがその理由かもしれない。一方、機能的な嗅覚受容体が341も存在しており、夜行性の狩を支えているのかもしれない。
最後に、長生きの秘訣だが、抗酸化作用を持つセレノタンパク質が26種類存在し、このタンパク質翻訳に必要なセレノシステインに対する4種類のtRNAまで有している。低体温も重要なファクターだと思うが、この特殊なタンパク質の秘密をぜひ解き明かしたいものだ。
このように、特徴的遺伝子からも、進化の位置からも興味が尽きないムカシトカゲだが、ゲノムの進化はこれまでの通説に反して極めて遅いようだ。そして、ゲノムの多様性から推察される集団サイズだが、何回かの盛衰を繰り返しているが、現在では個体間の多様性に乏しく、絶滅の危機に瀕していることが推察される。
久しぶりに新しい種のゲノムの論文を読んだが、あらためて生物進化の壮大さに打たれる。
2020年8月6日
腸内細菌叢と健康の関係が示されて以来、様々な国民、民族の腸内細菌叢が集められ、比較されるようになった。これまで目にした論文から私が抱いているイメージは、同じ人の腸内細菌叢でも生活スタイルが変わると変化すること、民族性より、生活の都市化と細菌叢が関わること、都市化されない暮らしでは粗食でも細菌叢は豊かなこと、などだ。そして、なぜ原始的な粗食生活を送る部族の腸内細菌叢の種類が豊かなのか、秘密を解き明かすことの重要性を感じてきた。
今日紹介するアイルランド、コーク大学からの論文はIrish Travellersと呼ばれる都会の遊牧民とも言える人たちの腸内細菌叢を調べて、工業化と細菌叢との関係を調べた論文で7月号のNatureに掲載された。タイトルは「Microbiome and health implications for ethnic minorities after enforced lifestyle changes (少数民族の生活スタイルの変化による細菌叢と健康の変化)」だ。
この論文を読むまで全く知らなかったが、アイルランドには一般社会から離れてキャンプ生活を送る少数民族が何世紀にもわたって存在しておりIrish Travellersと呼ばれている。その生活のレポートはNational Geographicの写真から窺えるが(https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/08/irish-travellers-uphold-the-traditions-of-a-bygone-world/ )、イメージとしては欧州のジプシーを考えてもらえばいいと思う。ただ、遺伝的にはアイルランド人で、アイルランド内で一般社会から分離し、放浪生活を行っている。写真からもわかるように現在はキャンピングカーで放浪しているが、徐々に一定の地域に定着をはじめ、さらにはキャンピングカーを離れて自宅を所有するようになったグループも存在するようだ。
この研究では定着性の観点からIrish Travellersを3群(自宅を持つ群、子供時代に放浪していたが現在は定着している群、そして成人した後も放浪している群)に分けて、腸内細菌叢を調べている。
結果は驚くべきもので、Irish Travellersを生活スタイルで選り分けた3群では、それぞれ特徴的な腸内細菌叢を持っていることがわかった。そこで、世界中の細菌叢データベースと比べると、Irish Travellersは工業化先進国と、アフリカやポリネシアの非工業化途上国とのちょうど中間に分類されること、そしてIrish Travellers の3群は、非工業化から工業化の道筋の中間で、定着化により工業化への道を進んでいることが明らかになった。
すなわち、Irish Travellersが、工業化社会により起こる細菌叢の変化を研究するモデルとして最適な集団であることが示された。
実際、細菌叢から比較的正確に生活スタイルを予測できることから、今後どの生活様式が定着、工業化で変化したのか研究が進むと思う。もちろん初期的な相関解析を行っており、定着しているかどうか、子供の数、WHO精神健康指標、ペットの数などが強く相関することを示しているが、それぞれの要素間で相互作用があるため、詳しい相関解析は今後に待つ必要があると思う。
しかし、細菌叢を単純な健康指標として表面的に考えないことがいかに大事かを示す面白い論文だと思う。腸内細菌民俗学も面白そうだ。
2020年8月5日
WHOのテドロス事務局長が、「新型コロナウイルス(Cov2)に対する特効薬が今後も存在しない可能性がある」と述べたそうだ。特効薬など南北医療格差を拡大するだけで、途上国にはいくら待っても届くことはないと言う、警告の意味だと解釈したいが、医学上本気でそう思っているなら、最新の医学知識をほとんど勉強していない、公衆衛生テクノクラートと言う他ない。
というのも、コロナウイルスは最も複雑なRNAウイルスで、侵入後最初に起こるRNAの翻訳過程とそれに続くタンパク分解による機能分子生産過程を見るだけでも、途方もなく特殊で複雑な過程をうまく調節する必要があることがわかる。すなわち、ハイテク侵入部隊なので多くの条件が必要になり、戦線が延びて弱点が晒されやすい。これまでCov2に対する薬剤と称するものは、すべて他のウイルスに対して開発された、目的外使用だったが、Cov2がコードするほとんどの分子の構造と機能が刻々と明らかになりつつある今、Cov2特異的な薬剤が開発されることは時間の問題だと思っている。それも、ポリメラーゼに限らず、多くのCov2分子に対して開発されるだろう。
そして何よりも、昨日大規模治験入りが報道されたファイザーのモノクローナル抗体を皮切りに、各社入り乱れてモノクローナル抗体薬の投入が始まるように思う。と言うのも、Cov2に対するモノクローナル抗体は患者さんのB細胞から分離する抗体遺伝子を用いており、わざわざヒト化する必要がなく、いい抗体ならすぐに治験に入れる。実際、動物を用いた前臨床モデルでは、中和活性の高いモノクローナル抗体は治療効果が高いことが証明されている。
このように、高額になることを覚悟すれば、今後最も頼りになる治療法としてモノクローナル抗体薬が期待できると思っている。
例えば致死率9割に近いエボラ出血熱に対してレムデシビルと同時に治験が行われた2種類のモノクローナル抗体薬は、レムデシビルと比べて高い効果を示したことが昨年暮れに報告された(https://aasj.jp/news/watch/11936 )。
7月30日号のThe New England Journal of Medicineにはさらにモノクローナル抗体薬の成功を示す結果が2報発表された。最初はシンガポール国立大学からの論文で、モノクローナル抗体により黄熱病ウイルスの増殖を予防できると言う研究だ。
この研究は、黄熱病に対するモノクローナル抗体の安全性と効果を調べる1相の治験で、実際の感染症予防ではなく黄熱病ウイルスを弱毒化したワクチンスタマリルを投与した時のウイルス血症抑制効果を調べて、効果を検証している。
私も接種を受けたが、スタマリルは弱毒化されているとはいえ、ウイルス血症が起こるため1週間程度様々な症状に見舞われる人が多い。はっきりいえばそのぐらいして初めて、一回投与するだけで有効なワクチンとして認められているのだろう。このスタマリル接種後のウイルス血症をTY104抗体は完全に抑えている。また、抗体の半減期は2週間程度で、有害事象も許容範囲という結果だ。
黄熱病はワクチンが存在するので、発症者はそう多くないが、それでも発症した場合は抗体治療の可能性が示されたと言っていいだろう。
これは抗体を治療に用いる研究だが、同じ号のThe New England Journal of Medicineには抗体をRSウイルスの予防に使う可能性を示した論文が発表されている。
RSウイルスは今も途上国の子供の命を奪う最も厄介なウイルスだが、まだ有効なワクチンは開発できていない。しかし、途上国で利用できるかは別として、モノクローナル抗体が治療だけでなく、流行時に予防的に投与することで、ワクチンの代わりに使えることが示されてきた。
このアストラゼネカ社からの論文はこの方向の集大成とも言える治験研究で、中和活性を高め、さらに体内での半減期を5ヶ月にまで延長させたRSウイルスに対するモノクローナル抗体Nirsevimabを流行前に1回筋肉注射された幼児(平均3.2歳)を150日間追跡し、RSV を発症した症例数を調べている。
結果は、感染者を70%抑え、入院治療の必要な患者数を80%近く抑えることができたと言う結果で、ワクチンと異なり注射後すぐに効果があることから、ハイリスクグループを対象に流行時一回予防的注射を行うのは現実的解決策になると思う。
実際同じような半減期を伸ばした抗体の予防的使用はエイズなどにも実用化が進んでおり、当然新型コロナウイルスについても高リスクグループを守る方法として定着すると期待している。
エボラウイルスの治験でわかったように、もちろんモノクローナル抗体といえども、例えば植物で作らせた抗体は効果が見られなかった。ただ、ワクチンと異なり、同じ抗体を治療や予防に利用できる点が大きな利点で、最終的に最も効果が高い抗体が生き残ればいい。また、一旦いい抗体ができれば、様々な操作を加えて使いやすくすることも可能になる。
研究の速度から、新型コロナウイルスに対して、特効薬ができるのは時間の問題だが、以上の例から、最初に実現化するのは、モノクローナル抗体による治療、および予防ではないかと思う。おそらく、感染が拡大している地域に旅行する前に、一回抗体を注射して出かけることすらあり得る話だと思う。
2020年8月4日
ずいぶん昔になってしまったが、2015年4月にこのブログで、類人猿にはなく、ネアンデルタール人も含む人類だけに存在する遺伝子ARHGAP11Bの発見について紹介した(https://aasj.jp/news/watch/3151 )。大きな形質変化は遺伝子重複による新しい分子機能の誕生により起こることが多いが、この遺伝子も猿にも存在するARHGAP11Aの重複で誕生し、しかも本来の機能を全く失っていること、さらに新皮質特異的に発現し、マウスに強制発現させると驚くことに、マウスの脳にシワができたことを報告した。
この研究を行ったのは、ドレスデンで極性問題など優れた神経細胞生物学研究を続けているHuttnerのグループだが、今年、ついにこの分子がミトコンドリア内でアポトーシスなどに関わるPTPを阻害することで、グルタミンを分解してエネルギー変換を高め、神経幹細胞の増殖と高めることを発表した(Neuron 105:867, 2020)。
最初ARHGAP11B発見の論文を紹介した時、私も興奮して「もうすでにサルにこの遺伝子を導入する研究が行われているはずだ。」と書いてしまったが、今日紹介するHuttnerグループからの論文はまさに、猿(実中研のマーモセット)にこの遺伝子を導入したら、予想通り皮質の細胞数が増えたという話で、7月31日号のScienceに掲載された。タイトルは「Human-specific ARHGAP11B increases size and folding of primate neocortex in the fetal marmoset (人類特異的ARHGAP11Bはマーモセット胎児で新皮質の大きさとシワを増大させる)」だ。
この遺伝子発見後のHuttnerの執念の論文と言っていい。我が国の佐々木さんたちが磨いてきたマーモセットの遺伝子導入技術の助けを借りて、遺伝子発現に関わる領域ごとこの遺伝子をレンチウイルスに組み込み、受精卵へ遺伝子導入している。
Huttnerらしいと思うのは、人間化したマーモセットを見たいと思いつつ、それには倫理的問題があるので、帝王切開で発達途中で胎児を取り出し、新皮質がどう変化するかだけに焦点を当ててデータを取っている。
幸いこの方法で導入した遺伝子は新皮質に発現して、皮質のサイズを増大させるとともに、脳の褶曲といえる脳回の形成が進んでいることを示している。色々計測しているが、写真で見ると一目瞭然の変化だ。
最後に、皮質の各層の細胞数について調べ、皮質下部の神経細胞はあまり変化していないが、Satb2やBrn2で標識される上部の神経細胞数が大きく上昇していることを示している。そして、この変化が脳室下のラディアルグリア細胞、すなわち感細胞の増殖が高まる結果であることを示している。
結果は以上で、私が期待した実験に5年かかったということは、実中研のマーモセットに到るまでの道のりが長かったことを示している。しかし、読んでみるとマーモセットはこの目的には最適の動物に思える。今後は、脳のオルガノイドなどを用いて、マーモセットから、アカゲザル、チンパンジー、人間の比較が行われるような気がする。
2020年8月3日
この10年の生命科学の進歩を振り返ってみると、核酸バーコードを用いる様々な技術の発展が大きな役割を果たしていることがわかる。もっともポピュラーな例がsingle cell RNA sequencingで、一個一個の細胞のRNAを異なるバーコードがついたプライマーで増幅することで、回収した全ての配列をシークエンスしても、後からその配列がどの細胞由来か特定できる。この結果、一個づつ細胞を処理しライブラリーを作るという、職人技が必要なくなった。
これと並行して進んだのがバーコード組織学で、この概要については吉田さんとYoutubeで解説した(https://www.youtube.com/watch?v=k4YMvL46ksQ&t=573s )。とはいえ、実際にこれらの技術を用いた研究が論文として発表されるまでには時間がかかる。
今日紹介するLeuvenカソリック大学とUniversity College of Londonからの論文は、以前紹介したスライドグラスにバーコードのついたプライマーを貼り付けたスポットを並べてその上に組織を重ねることで、組織の位置情報を回収したRNAにつける方法(https://aasj.jp/news/watch/5490、https://aasj.jp/news/watch/9926 )と、組織上で、細胞が発現している複数の遺伝子を、バーコード化したプローブとin situでバーコードの配列を読む技術(https://aasj.jp/news/watch/8740 )を組み合わせて、アルツハイマーで見られるアミロイドプラークが周りの細胞にどのような変化を誘導するのか調べた研究で8月20日号のCellに掲載予定だ。タイトルは「Spatial Transcriptomics and In Situ Sequencing to Study Alzheimer’s Disease (空間的トランスクリプトームとin situシークエンシングをアルツハイマー病の研究に応用する)」だ。
タイトルからもわかるように、この研究の第一の目的はバーコード組織学手法を利用してみるということだ。その対象として選んだのがアルツハイマー病(AD)モデルマウスで、アミロイドプラークの周りの遺伝子発現を100ミクロンのスポットに分けて解析し、アミロイドにより誘導される変化を特定、そこから発見された遺伝子セットを今度は同時にin situシークエンシングを用いて細胞レベルの発現を調べ、両方のデータを合わせてアミロイドプラーク特異的作用を特定しようとしている。
よく読んでみると、組織情報を犠牲にしたscRNAseqと比べると、やはりキャプチャーできるRNAの数は限られており、tSNE展開した時の解像度は低そうだ。またin situ sequencingもまだ感度の点では改良の余地が大きそうだ。おそらく、これらのテクノロジーを使うためには、お金だけでなく、まだまだ熟練が必要だという印象を持った。
しかし組織情報を取り入れることで、アミロイドプラークの近くで誘導される変化をとらえることには成功しており、以下のような結果を得ている。
C1qをはじめとする補体系がアミロイドプラークに反応したミクログリアとアストロサイトのシグナル伝達に関わる。また、このカスケードは、やはりミクログリアから分泌されるAPOEにより調節される。 プラークの近くのオリゴデンドロサイトでミエリンに関わる遺伝子を中心に、変化が見られるが、プラークで誘導されたほとんどの遺伝子は、老化が進むと逆に発現が低下する。 今回のマウスモデルと、ヒトでのAD組織を比べると、一致している点もあるが、変化する遺伝子の種類など、かなりの違いが見られる。おそらく、マウスモデルがプラークに対する純粋な反応を見ているのに対し、ヒトではTauの変化など多くの要因が重なった結果を見ているからと考えられる。 結論としては、アミロイドプラークは無毒化されたゴミではなく、局所で周りの細胞に明らかに悪さをしているということになるが、この結論より、バーコード組織学が実際に使われているのを実感できたことの方が、私にとってはインパクトが大きかった。
2020年8月2日
P53は最も重要なガン抑制遺伝子で、多くのガンで発ガン過程で遺伝子が欠失したり、あるいは機能欠損型変異が起こる。このような変異の中で、172番目や270番目のグルタミン酸がヒスチジンに変化した突然変異は、dominant negative型として知られ、正常p53機能が片方の染色体に存在してもその機能を抑えてしまい発ガンに関わると考えられてきた。
今日紹介するイスラエルヘブライ大学からの論文は変異型(R172H)の機能が腸内細菌叢の環境では2面性を持つことを示した論文でp53 分子の機能の多様性を改めて示した研究で7月29日Natureオンライン版に掲載された。タイトルは「The gut microbiome switches mutant p53 from tumour-suppressive to oncogenic (腸内細菌叢が変異型p53を腫瘍抑制分子から発ガン分子に変える)」だ。
もともとこの研究はp53(R172H)の発ガンメカニズムを探ろうと始められたのだと思う。この変異を腸上皮で発現するように遺伝子操作し、さらにp53の安定性を高めるようにCKIα遺伝子をノックアウトしたマウスを作成し、腸の変化を調べている。
と、驚いたことに、空腸ではガン抑制的に働くのに、大腸では発ガンを促進していることがわかった。すなわち、腸の環境に応じて働きが変わる。
腸の自己再生や、発ガンにはWntシグナルが関わっているので、次にp53(R172H)存在下で空腸と回腸でWntシグナルの強さを下流分子の発現を指標に調べると、空腸ではWntシグナルが抑えられ、一方回腸では高まっているという2面性があることがわかった。
この2面性が、上部と下部消化管の環境の違いによるのか、あるいは細胞自体の差によるのかを調べる目的で、腸の幹細胞を培養するオルガノイド培養を行い、変異型p53は本来Wntシグナルを抑え、発ガン遺伝子が揃った場合も、その増殖を抑える能力があることを示している。すなわち下部消化管へと移ると、このガン抑制機能からガン促進機能へとスイッチが起こることが推定される。
当然のことながら、腸内細菌叢がこのスイッチに関わる可能性が示唆されるので、変異型p53を導入したマウスを抗生物質で処理して腸内細菌叢を除去する実験を行なっている。結果は期待通りで、大腸で見られた上皮の異常増殖は見事に抑制され、腸内細菌叢がないと変異型p53はガン抑制的に働くことを明らかにしている。
最後に変異型p53をガン抑制からガン促進へスイッチする分子を探索し、漬物など、植物の発酵に関わる乳酸菌(プランタルム)や、枯草菌が合成するgalic acidがスイッチであることを突き止めている。実際、オルガノイド培養にgalic acidを加えると、変異型p53は増殖抑制ではなく、増殖促進を誘導する。
以上が結果で、残念ながらなぜgalic acidがスイッチを入れるのかについては明らかにできていないが、ここで調べられた変異型p53は決して珍しくないことを考えると、これを悪性化のシグナルにしない食事や薬といった介入方法の開発は重要となるように感じる。
2020年8月1日
私たちが言葉や音楽を認識するプロセスは当然のことながら複雑だ。私たちの声を機器により分析すると、異なる波長での振動の集合体であることがわかる。この要素は大きく振幅変調(エンベロープ)と呼ばれる音の振幅の時間変化と、その枠の中で素早く振動する時間微細構造波に分けられ、実際デジタル処理による音楽の伝送はこのような分解した要素を別々にして処理する。言葉で言うと、基本的なシラブル認識はこのエンベロープの波形が認識される。結局音とは空気の様々な振動が時間の同時性として統合されたものになる。
これらを受け取る私たちの感覚器も、蝸牛有毛細胞の興奮に変換して認識しているので、基本的にはデジタル処理と同じだと思う。ただ、正確な時計の上に重ね合わせる電気的処理とは異なる時間統合が必要になり、言語特有の処理様式が知られている。声や音楽とは無関係の、振幅が異なるホワイトノイズを聞くときは同じSTGと呼ばれる脳領域が興奮するが、言葉の場合早いエンベロープは両側のSTG が興奮し、遅いエンベロープに対しては左側だけが興奮することが分かっている。すなわち、言語を他のノイズから抽出して処理している。
今日紹介するパリ大学からの論文は、この言語抽出処理能力が生まれたばかりの子供でも備わっているのか調べた研究で7月22日号のScience Advanceに掲載された。タイトルは「Speech perception at birth: The brain encodes fast and slow temporal information(新生児の言語認識:脳は早い波と遅い波を別々に処理している)」だ。
この研究ではなんと生後2ヶ月の子供に遠赤外線を感知する脳の血流系を用いた神経興奮計測を行っている。ヴォコーダーと呼ばれる一種のシンセサイザーを用いて、「Pa」のような簡単なシラブルを、1)元の声のまま、2)時間微細構造を全て取り除いた音、3)時間微細構造と早い波のエンベロープを取り除いた音、を聞かせて、STG興奮の違いを比べている。シラブルがPaであることを認識するためには3)の条件で十分可能だが、もちろん新生児が音を言語として認識しているかどうかはわからない。
実験の詳細は全て省いて結論だけを紹介すると、
元の音に対する反応と、遅い波だけを残した音への反応がよく似ているが、早い波と遅い波両方のエンベロープが残った音に対しては、反応が異なる。 シラブルとしての認識は遅い波のエンベロープだけでいいので、Paという音を抽出して認識するシステムは出来上がっている。 新生児でも、遅い波のエンベロープと早い波のエンベロープを別々に処理する回路が備わっている。 おそらく、今回使われた音は、成人の言葉に対して反応する領域の興奮を誘導している。 要するに、「言葉を他の音から抽出し、遅い波のエンベロープを共通の意味として認識するシステムが新生児で出来上がっており、一方音の詳細な特徴(例えば声の違い)を左右のSTGを用いて処理する仕組みも出来上がっている」、が結論になる。
個人的に考えると、「コミュニケーション」に関わる音の認識システムから進化しているように思えるが、言語の入り口の入り口でもこれほど複雑なことがよくわかる。
2020年7月31日
このブログで論文紹介を続けてすでに7年を超えている。ほぼ毎日紹介しているので2500以上の論文を紹介しているが、紹介した中からウイルスと検索をかけると、274論文がヒットする。もちろん全てがウイルスに直接関わるわけではないが、医学研究の多くがウイルスに向けられていることが改めてわかった。
しかし新型コロナウイルス登場以来、研究スピードは倍加している。その結果、これまであまり興味を持たなかったウイルスがコードするタンパク質について、多くの論文を読むことができ、ほんの一握りの分子しか持っていないウイルスがホストの中で増えるために進化させてきたメカニズムに驚嘆している。
中でも自然免疫を逃れるメカニズムを何重にも備えているのに驚く。一つは以前紹介した核内輸送システム、インポーチンの阻害作用で、これによりインターフェロンの転写を抑える(https://aasj.jp/news/watch/12749 )。もう一つがウイルスRNAをメチル化する酵素で、これによりウイルスRNAは自然免疫感知機構の網をくぐることができる。
今日紹介するフランクフルトのゲーテ大学からの論文は、新型コロナウイルスはさらにインターフェロン刺激に関わるインターフェロンにより活性化されウイルス防御に関わるタンパク質のISG15化を抑制することで自然免疫から逃れていることを示した研究で7月29日Natureにオンライン掲載された)。タイトルは「Papain-like protease regulates SARS-CoV-2 viral spread and innate immunity (パパイン型プロテアーゼはSARS-CoV2の伝搬と自然免疫に関わる)」だ。
恥ずかしいことにここまで新型コロナウイルス(CoV2)の論文を読んでいても、CoV2がM-プロテイン以外のプロテアーゼを持っているということは知らなかった。しかしSARSの研究からこのパパイン型プロテイン(PLpro)も、ウイルスRNAのポリメラーゼコンプレックス形成に関わり、ウイルスの増殖に必要であること、さらにISG15をタンパク質から切り離して自然免疫抑制に関わることが知られていた。
ISG15はユビキチンと同じようにタンパク質を修飾して、分解の目印になる分子だが、この研究ではPLproを精製し、このISG15をタンパク質から切り離す活性をSARSのそれと比べることから始め、Cov2のPLproのほうが強いISG15をタンパク質から切り出す活性を持つことを明らかにしている。一方SARSのPLproはISG15より、ユビキチンをタンパク質から切り離す活性が強い。すなわち、ユビキチン化を標的にしていても、Cov2-PLproはISG15を標的にし、SARS-PLproはユビキチンそのものを標的にしていることが明らかになった。(高い相同性を持つウイルス間で、すでにこのような大きな基質の違いが出ていることに驚く。)
この結果、SARS とCoV2は同じ自然免疫でも、SARSはTNF―NFkb経路、CoV2はIRF3を介するインターフェロン経路をより強く抑制することがわかった。
SARSのPLproに対してはすでにGRL-0167が開発されているが、上記の検出系でGRL-0167がCoV2―PLpro活性を阻害することを確認した後、ウイルス感染細胞をGRL-0167で処理する実験を行い、ウイルスの増殖伝搬とともに、インターフェロンによる自然免疫系を抑制する二重の効果があることを明らかにしている。
以上の結果は、新型コロナウイルスに対して増殖と自然免疫の両面から攻めることができる薬剤が開発できることを示唆しており、GRL-0167がそのまま利用できなくとも、開発は時間の問題だろうと期待している。
2020年7月30日
古今東西、人間は重大な決断に当たって占いや予言を大事にしてきた。卑弥呼からラスプーチンまで、占い師の予言が政治を左右した事例は枚挙にいとまがない。しかし、真面目に考えれば予言がそうそう的中するはずはないから、不確かな予言で行えた政治の方が、いい加減だったと思う(今でも予言や占いを信じる人は多く、異論も多いと思うが)。
なぜこんな話から始めるかというと、新型コロナ感染の拡大に対する政府・市民(メディア)と科学者たち(専門家委員会に限らず全ての)の議論を見ていると、「第2波です」とか「10万人の死者が出ます」とか、「すぐ収束します」などと語る科学者は、かっての占い師のようにとらえられているのではとフッと感じてしまったからだ。
一度収束したかに見えた新型コロナ感染者数が、日本中で再びジワジワと拡大し始めた今、誰もが明日、来週、来月、そして来年の予測を心待ちにしていることは間違いない。もちろん現代の予測は、占い師の時代とは違う。科学者による科学的データに基づいた予測が期待されている。しかし、的中したのか、間違っていたのか、今も確信が持てずにフラストレーションだけが残る西浦さんの「放置すれば40万人死亡」仮説が唯一のモデルとして示され、大きなリセッションを経験したわが国は、当時を超える感染者数が出ても、どの予言を信じればいいのか途方に暮れているように思う。
この感覚は決して一般の人だけではない。かく言う私も、流布している科学者の御宣託が、現状では根拠のない予言と変わることがないと感じていても、それを明確に指摘できないというフラストレーションを感じていた。
ところが、The New England Journal of Medicine 383; 4(2020)に掲載された論説を読んで、感染モデルについて頭の整理がつき、フラストレーションは解消されたので、私と同じように感染モデルにフラストレーションを感じておられる皆さんにぜひ紹介することにした。
タイトルには、感染モデルは「何か間違っているぞ」と感じつつ、「利用せざるを得ない」という我々の気持ちが表現されており、著者には私たちのフラストレーションがわかっていると期待できる。
事実期待通りで、まず感染モデルは、1)統計的予測モデル、2)メカニズムベースのモデルの2種類に分けてうまく説明してくれている。
統計予測モデルはこれまでのデータを、新しいデータに当てはめ、未来を予測する手法で、例えばIHMEモデルでは、中国やイタリアの統計を、例えば日本にあてはめることに相当し、統計に現れる実際の感染過程については情報として含まれていないため、長期の予想は全く不可能であると断じている。NYではこうだから日本も同じになるという予想は今も記憶に新しいし、西浦さんのモデルもこの範疇といっていいだろう。
一方、メカニズムに基づくモデルとは、ウイルスの性質、感染性、抵抗力、社会的接触度、など出来る限り多くの要素データを集め、そこから予測する方法で、パラメータがうまく集まれば、長期の予測も可能になる。例えば、全ての人に抵抗力があることが証明できれば、ウイルス感染は拡大しようがないといった具合だ。ただ我が国の場合、現時点でわからないことが多すぎる。そもそも、このウイルスについての様々なパラメータはほとんど明らかでないし、無症状感染者の行動履歴といった行動学的パラメータもほとんど集まっていない。
この論説では、メカニズムに基づく予測が可能になるための最低条件として、
新型コロナウイルスに対する免疫反応の正確な理解と、免疫状態の正確な測定。 無症状感染者の感染性、免疫状態の把握。 感染者、非感染者の行動記録に基づく接触のデータの取得。 を挙げている。
この論説を私なりに解釈すると、
統計による予測モデルは、例えば「経済と感染防御の両立」といった長期計画には向いていない事。 長期予測のためには、感染者数だけでなく、ウイルス伝搬に関わる多くのパラメータを集めるメカニズムに基づく予測手法が必須であること。 ただ、メカニズムに基づく予測のためには、まだまだデータが集まっていない事。 と理解した。
ただこれでは予測モデルを信頼するなといっていることに等しいので、この論説では予測モデルを受けとる側が以下の質問を問い続けることで、予測モデルが「useful」になるとまとめている。その5つの問いとは;
モデルの目的と、予測可能な時間レンジは明確か? モデルが寄って立つ仮定は正確に示されているか? モデルの不確実性要素を正確に把握して、提示できているか? 統計モデルの場合、どのデータをモデルに使ったのか? モデルは普遍的か、あるいは特定の対象を設定しているのか?(例えば都市と農村) 以上、この論説を上手く紹介できたかどうか自信はないが、私はこ今後どのように感染モデルと接していけばいいか頭の整理がついた。是非みなさんも自分で読んでみられればと思う。
翻って我が国の状況を考えると、メカニズムを取り入れた長期予想がもとめられているが、これを可能にするには、あまりにも利用できるパラメータが存在しないと言えるように思う。論文を読んでいるとわかるが、この点に関しては先進国とは言えない状況だ。とすると、当分我が国では、他の統計をそのまま並行移動して利用するか(西浦型)、限られたデータをもとに「エイ!」と占うかしか方法はない。この状況を超えるには、本当の科学的データ収集が必要になるが、PCRの検査数がまだ議論の焦点になっている我が国でいつこれが実現するのか?心は晴れない。
2020年7月30日
メトフォルミンは肝臓での糖新生を抑制し、インシュリン抵抗性の改善することから2型糖尿病の安全な治療として最もよく使われている薬剤だが、他にも抗炎症作用や、脳細胞の活性化など、魔法の薬といってもいいような作用を持つ薬剤だ。この不思議については、「西川伸一のジャーナルクラブ」でも一度議論した(https://www.youtube.com/watch?v=FBBh8JsJguQ&t=315s )。
今日紹介するトロント大学からの論文はメトフォルミンが放射線でダメージを受けた脳の幹細胞の回復を高め、記憶障害の出現を抑えるという研究で7月27日号のNature Medicineに掲載された。タイトルは「Assessment of cognitive and neural recovery in survivors of pediatric brain tumors in a pilot clinical trial using metformin (小児脳腫瘍の生存者のメトフォルミンのパイロット治験で見られた認知機能と神経細胞回復)」だ。
20世紀、脳研究のうち概念が大きく変化したのは、成人になっても脳の神経細胞が幹細胞からの供給を受けるという発見だが、もちろん発達期の幹細胞システムはもっと活発だ。実際、小児の脳腫瘍などで放射線照射を受けた後、細胞数が低下し、脳機能障害が後遺症として残ることが知られている。
この研究ではまず、放射線照射を受けたマウスの幹細胞活性を試験管内で測定する実験系と、照射後50日前後での認知機能テストを行うモデル系で、メトフォルミンの作用を調べている。
試験管内での結果は明瞭で、放射線後減少する幹細胞の数は、50日で回復するが、歯状回では回復が遅く、細胞数の減少が後遺症として残るが、メトフォルミンはこの後遺症の発症をほぼ完全に回復させる。また、脳組織の幹細胞数を調べても、同じように放射線照射により幹細胞の回復が遅れるが、メトフォルミンはこれを正常化する。
最後に、では作業記憶について調べると、面白いことにオスでは放射線による後遺症はほとんど出ないが、メスでは放射線による後遺症として記憶障害が残り、これをメトフォルミンは回復させることがわかった。
メトフォルミンはこれまでも小児に投与しても問題がないことが知られているので、前臨床結果を基礎に、治験に進んでいる。ただ、マウスではメスで効果が強く見られてはいるが、この前臨床では男女を問わず、放射線照射を受けた平均7歳の子供について、メトフォルミンが脳機能の回復に効果があるか調べている。
無作為化されてはいるが、治験プロトコルは複雑で、基本的には放射線照射を受けた全ての治験者にメトフォルミンを投与するが、照射後12週間メトフォルミンを投与し10週間の間隔をおいて偽薬を12週投与するA群と、最初の12週は偽薬を投与、10週間の間をおいて、メトフォルミンを12週投与する
複雑なので簡単にまとめると、メトフォルミンは照射直後から投与すると、記憶機能の障害を抑止する効果がある。ただ、最初の12週間偽薬投与された群では、後半に投与したメトフォルミンの作用はほとんど見られないことがわかった。この機能的効果は、脳梁の白質の体積から見られる、神経細胞の回復とも一致しており、メトフォルミンが神経幹細胞機能を助けて、脳障害からの回復を促進する可能性が強く示唆されたといっていいだろう。
今後、女性、男性に分けて、もう少し単純な治験プロトコルで、効果を検証してほしいと思う。効果が確かめれば、小児ガン治療に大きな貢献になると思う。