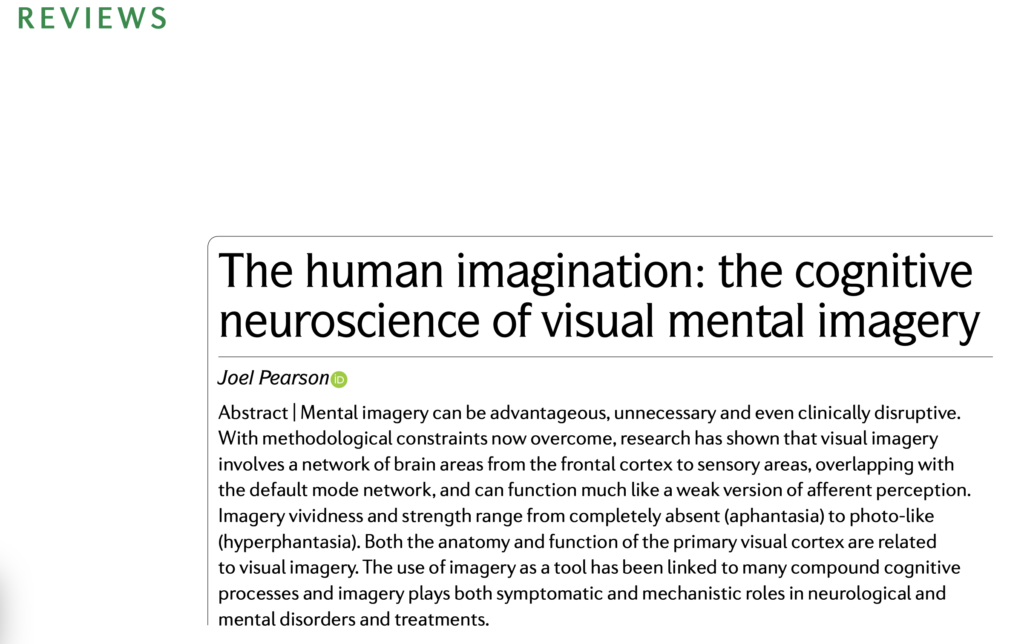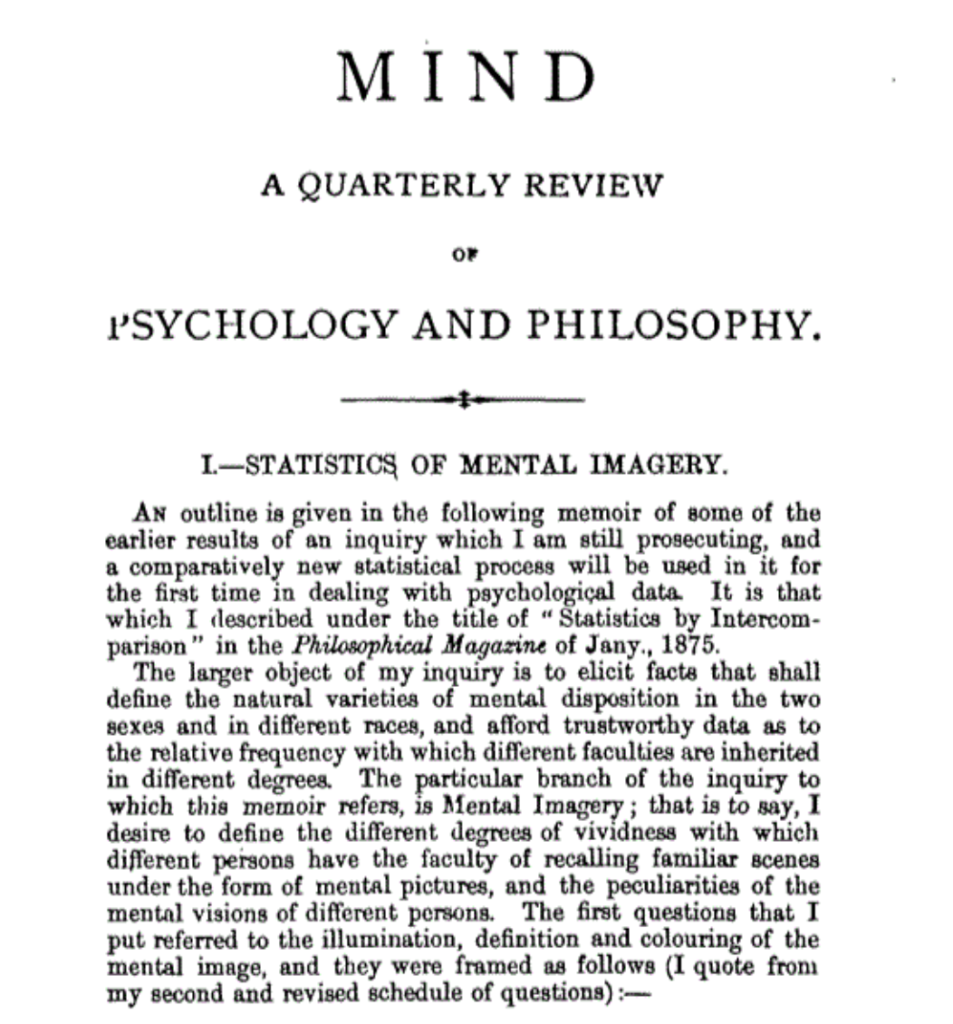2021年1月22日
ある時、米国の健康保険システム(KP)の研究所から発表された妊娠時に受けたインフルエンザワクチンの子供への影響を長期的に調べた研究を読んで驚いたことがある。健康保険システムでは、医療保険を払う側と、健康管理や医療提供側が一体化しており、従って会員が健康であるほど利益が上がる。当然、妊婦さんについてもワクチンを受けてもらいたいというインセンチブが働く。結論は喘息や自閉症など様々な疾患について、インフルエンザワクチン自体は影響がないというものだったが、驚いたのはこのコホートに参加した妊婦さんたちの内訳で、25%がマスター以上の学位取得とあった点だ。これは、この健康保険組合が富裕層に傾いた構造になっていることを示すが、それとともにワクチン接種には自ら情報を収集し、それに基づいて決断するという過程が重要で、そのための教育の重要性を示していると考える。
いずれにせよ、妊娠時に感染症にかかると胎児に様々な問題が起こることは事実で、ウイルス感染の場合、現在それを防ぐのはワクチンかソーシャルディスタンスしかない。とはいえ、長い進化の過程で、この様な状況から胎児を守る方法も進化しているはずで、今日紹介するデューク大学からの論文は、これにエストロジェンシグナルが関わることを示した面白い論文だ。論文のタイトルは「GPER1 is required to protect fetal health from maternal inflammation(GPER1は母親の炎症から胎児を守るのに必要)」で1月15日号のScienceに掲載された。
母親の炎症シグナルの重要な経路は、1型インターフェロン(IFN)を介しているので、この研究では人間の上皮細胞を用いてCRISPR/Cas9ノックアウトスクリーニングを行い、IFNシグナルを抑える分子を探索し、エストロジェンのなかでもエストラジオールに反応する受容体GPER1がIFNシグナルを抑えていることを発見する。
エストラジオールで誘導され、炎症を抑えるという意味ではまさに目的に合致した分子と言え、この分子に焦点を当てて実験を行い、
GPER1はエストラジオールを介してインターフェロンシグナルを抑制するが、細胞自体の生存には影響がない。また、この抑制効果は特異的阻害剤G15で完全にキャンセルできる。 母体にインフルエンザを感染させる実験システムで、GPER1を阻害すると、胎盤特異的にインターフェロンシグナルにより誘導される様々な分子の発現が上昇する。組織学的には、胎盤の血管内皮の脱落が見られる。 妊娠中にGPER1の機能を抑制すると、それだけではほとんど影響ないが、インフルエンザ感染マウスでは、出生仔数が低下する。 Poly(I:C)アジュバントで妊娠マウスの炎症を誘導する系でも、炎症により誘導される出生仔数の減少がさらに悪化するとともに、胎児死亡率も大きく上昇する。 ことを明らかにしている。
結果は以上で、胎児を母親の炎症から守る仕組みの一端が明らかになった。このメカニズムははっきりしないが、転写レベルでの調節で、さらなる標的を見つけるためにも今後の研究が必要だ。幸い、GPER1に対する特異的阻害剤G15は、他のエストロジェン受容体には影響しないので、母親に炎症が見られる時など、その影響を軽減するために利用される可能性は高い。
2021年1月21日
うつ病の治療として、脳領域を直接電気的に刺激する深部脳刺激や、あるいは外から電磁場を照射する経頭蓋磁気刺激療法が使われる様になり、薬剤の効果が全く見られない症例に効果があることが分かってきた。ただ臨床治験で効果が見られたからといって、決まった場所に電極を留置する方法では、極めて多様性の高い脳の病気では、結局効くかどうかやってみないとわからない。
この精度を上げるため、電極を挿入する場所を、電極を留置する手術中に刺激を繰り返しながら患者さんの反応を記録し、最適な場所に留置する方法が始められている。今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、刺激に対する脳の反応を徹底的に調べれば最適の脳刺激治療が可能か、実際のうつ病患者さんで調べた研究で1月18日Nature Medicineオンラン版に掲載された症例報告だ。タイトルは「State-dependent responses to intracranial brain stimulation in a patient with depression (うつ病患者さんでの状態に応じた脳内刺激に対する反応)」だ。
この研究の目的は、うつ病患者さんの脳の様々な場所を刺激して、うつ病に関わる気分の変化を見ることで、新しい刺激の方法を探ることだ。このために、脳の外から針を何本もさして、この研究では160箇所の電気信号を拾うとともに、その場所を刺激できる様にして、10日間病院で観察している。また、針を刺した場所は、眼窩前頭皮質、扁桃体、海馬、内包前脚腹側、腹側線条体、前帯状皮質と徹底している。
あらゆる治療に抵抗性で、長期の鬱状態を繰り返し、自殺の心配がある重症のうつ病であるとはいえ、これほどの数の電極を留置して、10日間も過ごすなど、我が国ではほとんど許されない様に感じる。
しかしこの10日間で、様々な場所に100Hzと1Hzの異なる周波数で刺激を加えながら患者さんの自覚的な訴えと、医師の判断を総合して、刺激の効果を検証している。その結果が、図でまとめられているが、膨大なものだ。ただ、これまでうつ病に対して電極が挿入されていた眼窩前頭皮質を始め、内包前脚腹側、腹側線条体、前帯状皮質の刺激で明確な反応が記録されている。例えば眼窩前頭皮質刺激により患者さんは「静かに本を読んでいる喜び」、また内包前脚腹側、腹側線条体の刺激では、「ウズウズする喜び」が得られたと述べている。
これらの反応は再現性が高いが、その領域の活動状態と刺激のタイミングが重要であることもわかっている。例えば、眼窩前頭皮質の刺激の場合、脳の活動が高いときに1Hzの刺激を行うと鎮静効果があるが、活動が低いときに1Hz刺激を行うと余計お落ち込む。逆に前帯状皮質では、活動が低いときに100Hz刺激を行うと、気分が改善するが、もともと高いときに刺激すると逆効果になる。実際にはこの様な記録を、1回10分の刺激を行うというプロトコルで、各電極について詳しく行い、膨大な結果が集められている。
話はこれで終わりで、この結果の最適治療とは何かについては全く述べられていない。ただ、私自身膨大なデータについて全て目を通しているわけではないが、脳に電極を挿入して患者さんの反応を見るという古典的な方法を近代化して、感情や気分といった人間特有の脳活動について調べられたということに感動すら覚える。
ペダルを踏むと気持ちが良くなる刺激を扁桃体に送ると、ネズミはペダルを踏み続けるという実験があるが、考えてみるとこの研究はうつ病の治療に同じ方法を用いようとしていることもよくわかる。とすると、これが本当の治療につながるのか、ペダルを踏んで症状をとるだけで終わるのか、知りたいところだ。もし対症療法効果しかないなら、うつ病を克服するということが、脳内で新しい回路を形成し直して、気分の回路を新しく支配するという大事業であることがわかるはずだ。
2021年1月20日
動物にとって、食べられるかどうかの判断は、記憶とともに、その時の匂いと味で決めるしかない。事実、苦味は食物を忌避する重要な引き金になる一方、甘みは食欲をそそる。生存のための重要性で見れば、苦味感覚を直接行動につなげることが重要で、事実鳥類では甘み感覚だけが欠損しているケースが多い(ペンギンは全ての味感覚を失っている:https://www.brh.co.jp/salon/shinka/2015/post_000007.php )。
とはいえ、食べ物の中には苦味と甘みが混ざっているのは当たり前で、少し甘いからといって食欲が亢進してしまうと命に関わる。このとき、苦味に対する忌避行動を優先するメカニズムを探ったのが今日紹介するコロンビア大学からの論文で1月7日号のCellに掲載された。タイトルは「Top-Down Control of Sweet and Bitter Taste in the Mammalian Brain (哺乳動物の脳での甘みと苦味のトップダウンコントロール)」だ。
これまでの研究で、甘みと苦味に関わる神経細胞は、末梢から脳幹へ投射するまで全く分離していることが分かっている。この研究では、脳幹に存在する甘味神経と苦味神経を区別できる分子マーカーをまず開発し、光遺伝学的に、それぞれを特異的に刺激したとき、実際味を感じた時と全く同じ反応を誘導できることを確認する。以上の結果は、脳幹神経で両者が区別され、それが直接行動につながること、そして両者はこのレベルまで全く混じり合わないことを示している。
しかし、苦味感覚の方が甘味感覚に優先されることは、苦味の認識が甘味の感覚を変化させている、すなわち両方がどこかで相互作用していることを示している。そこで、甘味を認識する皮質領域GCbtと甘味を認識する扁桃体領域(CeA)をそれぞれラベルして、それぞれから脳幹へ神経回路が投射しており、これが異なる味の優先性を決める働きをしていることが示唆された。
そこで、苦味の認識を行うGCbt領域の興奮神経を光遺伝学的に刺激したとき、脳幹の甘味神経細胞の興奮を抑えるか調べ、期待通り脳幹の甘味感覚神経の興奮が抑えられることを明らかにする。すなわち、苦味の皮質での認識が、脳幹の甘味刺激を抑える。
次に扁桃体での甘味の認識が、脳幹での苦味神経の興奮に及ぼす影響を調べると、今度は面白いことに苦味神経の興奮を高めることを発見する。これによって、甘いもので満足している時でも、苦味のある危険性に備えていると言える。
この回路をさらに詳細に調べると、GCbtからの脳幹への直接のフィードバックも存在するが、GCbt部位の興奮がまず扁桃体の甘み認識領域へ投射し、ここで発生した抑制回路が脳幹の甘味神経細胞を抑えている経路が主要な経路であることを示している。
以上、極めて理にかなった、単純な回路形成が、苦味シグナルを常に食物忌避行動へ導いているのがよく理解できた。ただ、この様なネズミでの実験結果がそのまま人間に当てはまるかはわからない。というのも、私たちはさらに経験を積み重ねて、苦味も甘みも楽しめることは、ゴーヤやチョコレートやコーヒーを嗜むことからもわかる。これが程度問題なのか、あるいはさらに複雑な回路を獲得したのか、興味が湧く。
2021年1月19日
今回の新型コロナ感染に関する研究の世界の動向を眺めていると、我が国では今も免疫学の主流がマウスを用いた研究で、結果新型コロナウイルス感染した人たちの免疫反応を詳しく調べる体制ができていなかったことがわかる。このことは、以前からこのHPでも指摘してきたが、基礎研究が軽視されているという我が国で、人間についての研究が遅れているのは不思議な現象だ。
逆に現在のヒト免疫学を代表するのが、T細胞遺伝子クローニングで有名な分子生物学者M.Davisで、新しく開発された様々な分子生物学的技術を駆使して人間の免疫機能を解析し発表しているのを見ると、一種の感動すら覚える。
そのM.Davisにとって、人間の免疫学を研究するときの様々な制約を突破することは最大の課題で、特に免疫反応が行われる座と言えるリンパ組織を扱いたいと強く望んでいたことは想像に難くない。今日紹介するスタンフォード大学M.Davis研からの論文は、この念願が不十分であっても叶いそうだということを示す研究で1月号のNature Medicineに掲載された。タイトルは「Modeling human adaptive immune responses with tonsil organoids (扁桃のオルガノイドを用いてヒトの適応免疫反応のモデルを作る)」だ。
しかし一つのエポックを作った分子生物学者が、今度はオルガノイド培養の開発を試みているのも感慨が深いが、そのために現在でも様々な理由で行われている扁桃摘出で得られる組織を使うとは、目の付け所に感心する。
そして、扁桃組織細胞の浮遊液を作成して凍結しておき、その細胞を溶かしてトランスウェルと呼ばれる二重構造の培養皿で凝集させて培養する方法を開発する。この培養で凝集させる過程にインフルエンザ生ワクチンを加えて、そこで起こる免疫反応を、様々な生化学・分子生物学的テクノロジーを用いて検出している。
結果だが、トランスウェル内では不思議なことに扁桃細胞は自然に凝集塊を形成し、そこには抹消免疫組織で見られるほぼ全ての細胞が存在し、抗原に対して新しい免疫反応が誘導され、抗体が作られるとまとめられる。もちろん免疫学の新しい概念が生まれるというわけではないが、期待していることがしっかり再現できることがこの研究の主目的で、それはクリアできている。
残念ながら、これまで末梢血を用いた試験管内抗体反応と比べて何が違うのかについては、もう少し議論してほしいところだが、特にサイトカインを加えることなく、抗体が誘導され、しかも抗体の親和性が高まっていくこと、また、インフルエンザ特異的リパートリーが拡大するとともに、クローンの進化やスイッチも起こることが観察できること、そして何よりも試験管内では再現が難しい肺中心の様な構造が形成され、しかも抗原で刺激したとき、胚中心型のB細胞が維持されることなど、かなり満足できる水準に達していると言える。
さらに、かって摂取されたワクチンに対する反応も見ており、期待通りいわゆるメモリー型の反応を誘導できること、また全く新しいタンパク抗原に対する免疫反応誘導に必要なアジュバントの性能を確かめるのにも使えることも示し、今後ヒト免疫組織の反応を調べるためのモデルになると結論している。
そして最後の仕上げとして、新型コロナウイルスのアデノウイルスベクター型ワクチンに対する反応も調べ、スパイクなど異なる抗原に対する中和抗体を含む抗体反応が誘導されることを示している。残念ながら、今注目のRNAワクチンに対する反応は調べられていないが、筋肉注射されたワクチンがすぐにリンパ節で反応を誘導することがわかっていることから、是非調べてほしいと思う。
以上、M Davisの人間の免疫反応解析への執念がひしひしと伝わる論文だった。
2021年1月18日
AASJの二人の理事(藤本、麻生)と私は、全身に異所性の骨化が進む病気FOPを通して知り会った。その結果、FOPに関する重要な論文を見落とさない様常にプレッシャーがかかっている。その意味で、今日紹介するミシガン大学からの論文はFOPを理解する上で極めて重要な貢献ではないかと思う。タイトルは「Augmented BMP signaling commits cranial neural crest cells to a chondrogenic fate by suppressing autophagic β-catenin degradation (神経堤細胞でのBMPシグナルの更新はオートファジーによるβカテニン分解を抑えて軟骨への分化を誘導する)」で、1月12日号Science Signaling に掲載された。
少し余談になるが、この論文の責任著者の三品さんは、発生過程でのBMPシグナル研究の第一人者だが、所属がミシガン大学と知って驚いた。というのも、私の頭の中では、日本に戻って定着していると思っていた。結局彼にとって日本は研究し良い環境ではなく、おそらく最近ミシガン大学に移ったと思う。せっかくUターンしてくれた研究者が、また我が国を離れるという状況を見ると、今、問題になっている科学技術力低下の原因を見る様な気がした。
FOPはBMPシグナルを伝達するアクチビン受容体1(ACVR1)の突然変異による分子機能亢進によることははっきりしているが、なぜ発生過程では大きな異常が見られないのか、何が骨化の引き金になるのか、骨化するのは筋肉細胞そのものなのかなど、わからないことが多い。
三品さんたちは以前から、FOP変異をACVR1の活性化型の影響を調べる目的で研究してきた。今回は、この変異を神経堤細胞で発現する様にして調べたところ、FOPと同じ異所性の骨化が誘導できることを発見する。完全に同じとは言えないまでも、初めてFOPの動物モデルができたことになる。
シグナルを熟知した発生学者の仕事で、詳細は省くが、この骨化のメカニズムを追求する中で、神経堤細胞が鰓弓へ分化した後、様々な系列へとコミットする段階の初期にACVR1のシグナルが高まると、軟骨へと分化が誘導され、それが本来骨でないところに移動した後、骨に分化することを突き止める。
鰓弓細胞を培養してACVR1シグナルを抑える実験で、培養1日目には効果が見られるが、それ以降は全く効果がないことから、このシグナルは軟骨系への分化のコミットメント時のみ働くことがわかる。これは、FOP治療にとっても重要で、どの時期かわからないが、かなり早い段階でACVR1をピンポイントで抑えることの重要性を示唆している。
そして最後にFOP型ACVR1のシグナル伝達機構について解析し、ACVR1活性の亢進は、まずmTORの活性化を誘導し、これが鰓弓細胞の軟骨へのコミットメントに関わることを明らかにする。事実、現在iPS研究所でFOP治療にも使われているmTOR阻害剤は軟骨へのコミットメントを抑える活性がある。ただ、これも鰓弓細胞が分化決定する最初の段階だけで、後には全く効果がない。このことから、細胞分化系で特定される薬剤も、投与する時期が重要で、軟骨への分化決定がFOPでいつ起こったのかを再検討することが重要になる。
この研究ではmTORがなぜ軟骨形成を誘導するのかについても明らかにしている。様々なシグナル経路を調べた結果、mTOR活性化は、オートファジーを抑制し、オートファジーによりβカテニンの分解が抑えられて、Wntと同じ様にシグナルが入って、軟骨への分化が促進されることを明らかにしている。
この研究は盛り沢山で、発生過程での軟骨形成が、一般的に考えられているオーソドックスなBMPやWntシグナルだけでなく、両方がオートファジーを介してクロストークする微調整の支配下にあることを示しており、今後発生や疾患を考える上で新しい概念を提供している。
そして何よりも、FOPの成立機序について多くの示唆を与えている。これまで未分化細胞から骨細胞への分化を抑制する薬剤がiPS研究所の池谷さんたちにより特定されており、またACVR1の機能を特異的に抑制する薬剤も開発されている。この研究から、これらの薬剤は軟骨への分化決定過程にピンポイントで投与する必要があることが明らかになった。とすると、この感受性がFOP発症全過程のどの時期なのか明らかにすることが最も重要な課題になる。さらに、一旦コミットした軟骨が骨化する過程を標的にする重要性も明らかになった。
BMPシグナルと骨化というと、そのままわかった気になってしまうことが落とし穴で、この落とし穴から抜け出せたという意味で、三品さんたちの研究は重要だ。
2021年1月17日
「炎症は痛みを抑える」などと書くと、ほとんどの方は書き間違いだと思われるはずだ。というのもギリシャの昔から炎症はCalor(熱)、Rubor(発赤)、Tumor(腫れ)そしてDolor(痛み)を伴うものと決まっており、これを疑う人はなかった。しかし、炎症、特に自然炎症のメカニズムがわかってくると、なぜ痛みがインフラマゾームを活性化する炎症過程で誘導するのか明確に答えることは簡単でない。私の素人理解では、炎症による破壊組織から遊出される様々な分子が痛み受容体を刺激するためだろうと考えてきた。
今日紹介するデューク大学からの論文は、この意味で画期的で、自然炎症は実際には痛みを抑える働きがあるという、全く新しい可能性を示した研究で1月13日Natureにオンライン出版された。タイトルは「STING controls nociception via type I interferon signalling in sensory neurons (STING は痛み受容を感覚神経のインターフェロンシグナルを通してコントロールしている)」だ。
これまで抹消の痛み受容体刺激が中枢での免疫反応を誘導する過程は研究が進んでいたが、炎症自体が痛み受容体の機能に影響するかどうかについては研究されていなかったようだ、この研究では、自然免疫でインターフェロンが誘導される下流のシグナル分子STINGを髄腔内投与して脊髄の自然免疫系を活性化して、その時の様々な痛みに対する反応を調べている。
「炎症=痛み増幅」というこれまでの概念を覆し、ATING活性化は様々な痛みに対する閾値を上げて、痛みを軽減する。例えば、微小管形成阻害によるガン治療で見られる末梢神経障害やガン転移による骨の痛みまで、中枢でブロックしてくれる。逆に、STINGを阻害したり、あるいは STINGが欠損したマウスでは痛みの閾値が下がる。すなわち、STINGは炎症シグナルを受けて、常に神経の閾値を高めていることが明らかになった。
このメカニズムを探ると、神経系では炎症シグナルを受けたミクログリアでSTINGが活性化し、これにより1型インターフェロン(IFN)が分泌され、これが神経細胞でカルシウムやナトリウムチャンネルの量を調節して、痛み受容体の閾値を高めて、痛みを抑えていることがわかった。実際、IFNを髄腔内投与すると、痛みの閾値を上げて感受性を下げることができる。一方、神経細胞のIFN受容体をノックアウトするとこの効果はなくなる。
最後に猿を用いて同じ実験を行い、ADU-S100と名付けられたSTING活性化剤を髄腔に持続投与することで、IFN分泌が上がり、高い鎮痛効果を発揮することを示している。また、神経培養を用いて、同じ効果が人間でも得られることも示している。
結果は以上で、脊髄にカテーテルを用いて投与する必要があるが、新しいタイプの、しかも結構万能の鎮痛剤が開発できる可能性がある。ほぼ前臨床は終わっており、治験が行われるのもすぐではないかと期待される。
まさに炎症により痛みを抑える治療ができそうだが、これがギリシャ以来の炎症概念を損なうものでないことも申し添えた方がいいだろう。お分かりのように、これは全て中枢での話で、神経端末が存在する抹消では、おそらく炎症により痛み受容体が刺激されるというスキームは間違いがない。
しかし、IFNも痛み受容体も、外界からのストレス需要の鍵となる分子だが、これからは異なる細胞システムのストレスへの反応の統合を理解するための鍵になるように思う。
2021年1月16日
抗老化というと、老化細胞の生成を抑えて達成するものと一般には理解され、そのための様々なサプリメントが世に出回っている。しかし、これまで何度も紹介した様に(https://aasj.jp/news/watch/3057 )、老化が始まった細胞を積極的に殺してしまうsenolysisが、個体を若返らせるためには最も有効な方法だと思っている。というのも、この方法で肺線維症や腎硬化症など、老化が早く進行してしまう病気を抑えることが証明されている。とはいえ、現在senolysisを誘導する方法としてはダサニチブの様なリン酸化阻害剤や、免疫システムを用いた細胞除去が必要で、どれも気軽に使える方法ではない。
今日は久しぶりに我が国からの論文、東大医科研の中西真さん達が1月15日号のScienceに発表した論文を紹介する。senolysisをグルタミン代謝を抑えることで実現できることを示した論文で、抗老化を実現する手法としては画期的な研究だと思う。タイトルは「Senolysis by glutaminolysis inhibition ameliorates various age-associated disorders(グルタミン分解阻害によるsenolysisは様々な老化に伴う異常を軽減する)」だ。
この研究ではp53を活性化して老化を誘導した線維芽細胞の遺伝子発現と遺伝子ノックダウン解析から、細胞老化で細胞内のアシドーシスが起こると、mRNAの安定化を通してglutaminase1(GLS)の発現が高まること、また老化細胞が生存するためにはGLSが必須で、酵素活性を阻害すると老化細胞の細胞死を誘導できることを発見する。すなわち、senolysisをグルタミン代謝系の操作で実現できることが明らかになった。
そして、グルタミン分解抑制による細胞死のメカニズムを様々な角度から調べ、最終的に酸性に傾く細胞質のpHを中和するためにグルタミン分解が行われると結論している。また老化細胞はリソゾーム膜が障害されることでアシドーシスに陥りやすく、またアシドーシスが続くとミトコンドリア膜上のPTPが開いて細胞死が誘導されるため、これを防ごうとglutaminase活性が高まり、アシドーシスを中和して細胞をなんとか生存させていることを示している。慢性炎症も含め、様々な細胞ストレスが老化につながることを十分納得させるシナリオだと思う。
最後に、GLNの発現が、確かにマウス体内の老化細胞で高く、阻害剤を老化マウスに投与する実験を行い、腎硬化症や肺線維症を改善するなど、様々な老化に関連する異常を防ぐとともに、いわゆる慢性炎症をおさえる効果があることを示している。
結果は以上で、senolysisを代謝調節から実現できることを示した点で画期的だと思う。グルタミン代謝は、ガン制圧も含めて様々な方面で研究されており、多くの阻害剤も開発されている。また、アシドーシスとそれによるミトコンドリア膜PTPを介する細胞死という下流の経路も明らかにしている点も、今後新しい抗老化剤開発に寄与する様に感じる。いずれにせよ、senolysisをより身近に感じさせてくれる優れた研究だと感心した。
ずいぶん昔になるが中西さんが名古屋市立大学医学部に在籍の頃「DNAメチル化と細胞周期:プロの仕事」と紹介したことがある(https://aasj.jp/news/watch/489)。今回もプロの仕事が発揮されたと思う。
2021年1月15日
何回か紹介したと思うが、今「Art Meets Science 学生プロジェクト」(https://www.facebook.com/artsmeetsscience/ )のお手伝いをしている。リモートになってから関西からも参加しやすくなり、定例のミーティングでは、芸術に関する脳科学論文を紹介する役割をいただいて、張り切ってやっている。特に東京藝大の学生さんとの交流は新鮮で、様々な新しい問題を考える機会になる。先日述べた「脳で触る」プロジェクトから考え直してみたクオリア問題(https://aasj.jp/news/watch/14623 )もそうだが、音楽でも美術でも、感覚の鋭さ以上に、豊かな心的イメージを形成する能力が問われる様に思う。
そんなわけで、最近は心的イメージに関わる論文を特に気をつけて探す様になったが、そんな時、今日紹介するシカゴ大学からの論文を見つけた。タイトルは「Quantifying aphantasia through drawing: Those without visual imagery show deficits in object but not spatial memory (Aphantasiaを定量化する:視覚的イメージが欠損した人は空間記憶は正常だが、物の記憶が障害されている)」だ。
このタイトルを見たとき、まずAphantasiaという初めての言葉に釘付けになった。ファンタジアがない。そしてこれが視覚的イメージを呼び起こせない人のことだとわかった。要するに、心的イメージ形成がうまくいかないとすると、芸術的創造性の対極を意味する。
そこでまずAphantasiaをPubMedで調べると、まだ関連する論文は15報しか上がってこない。現時点のcovid-19論文92553報と比べると、認知0と言っていいだろう。幸いこの15報の中にあるオーストラリア・South-Wales大学のPearsonが2019年にNature Reviews Neurosciences に発表した総説はAphantasiaを理解するには最適だと思う。
これによるとAphantasiaとは、何かを頭の中でイメージすることができない人を意味し、1880年Galtonにより最初に指摘された。
「多くは、先天的なもので、物を思い描くことが難しいことを自覚はしていても、日常生活には全く影響がない。これまでは自覚的な症状を診断するための、VVIQやOSIQなどの問診基準で診断されてきたが、残念ながら脳波やMRIといった診断手段ではまだはっきりした定義はできていない。唯一、それぞれの目に異なるイメージを提示してどちらが見えるかを問う、心的イメージによるバイアスを調べると、Aphantasiaの人は先にイメージのバイアスを与えても、影響されにくいことから、客観的な指標で診断が可能である」などが述べられている。
今日紹介するシカゴ大学の論文は、Aphantasiaを診断するための新しい方法の模索で、これまで問診からAphantasiaと診断された人たちと、コントロール群をウェッブで集め、写真を見せたあと思い出して描くという課題と、同じ写真を見ながら描くという課題を与えて、描かれた絵を分析し、Aphantasiaの特徴を調べている。
ある程度Aphantasiaの知識があると納得の結果で、次の様にまとめられる。
Aphantasiaは現在VVIQ,OSIQで診断されているが、この診断法を使うと正常と明確に分離が可能で信頼できる。 絵を見ながら描く能力は正常と変わらないが、思い出して描くとき描けるものの数が大幅に減る。しかし、それぞれの配置、すなわち空間記憶は正常。 思い起こすものの数は少ないが、正常より間違いは少ない。 記憶を描くとき文字での説明を許可すると、正常人と比べて多くの文字やシンボルによる説明を用いる。 すなわち、Aphantasiaでは空間と物の記憶が分離していること、それをカバーするためにシンボルに頼るという構造が見えてくる。先にはっきりした脳生理学的定義はないといったが、心的イメージの形成には様々な脳領域に記憶されている部分を選択、統合した後、1次視覚野に再投射する過程が存在することが知られており、今回の結果、特に空間記憶と物記憶の分離と、イメージとシンボルとの関係を手がかりに脳生理学的研究が進む気がする。
ただ、論文を読んでいて、自分自身も言語や文字に頼る頭でっかちになって、心的イメージ形成能力が失われていることもよくわかった。実際、思い出して言語的に述べるのは得意だが、ビビッドなイメージとして示すのは苦手だ。とすると、失読症でも見られる様に、私たちの脳では、イメージとシンボルが常に鬩ぎ合っている様に思う。その意味で、科学の学生と芸術の学生の出会いは重要だと思う。
2021年1月14日
Diapauseという言葉をご存知だろうか。Wikipediaで見ると、”delay in development in response to regularly and recurring periods of adverse environmental condition” と定義しており、基本的には発生途中で環境が悪化したとき、改善するまで発生が止まることを意味する。
実はこの言葉はES細胞を利用したことのある研究者には馴染みが深い。というのも、ES細胞の維持に必須で発生にも絶対必要だと思っていたLIFを欠損したマウスを作成しても、特に発生に異常は起こらないのだが、マウスをストレス下に置いたときに起こるDiapauseがうまく起こらないため、胎児が流産するというAustin Smith 達の論文に驚いた経験があるからだ。もちろんストレスが去れば、そのまま発生は再開される。
このdiapauseがガンでも起こっていることを示したのが今日紹介するトロント大学からの論文で1月7日号Cellに掲載された。タイトルは「Colorectal Cancer Cells Enter a Diapause-like DTP State to Survive Chemotherapy (大腸癌細胞は化学療法に耐えるためにdiapauseの様な薬剤耐性段階に入る)」だ。
この研究は、患者さんの大腸癌を免疫不全マウスに移植して増殖を調べる実験系で一般的に用いられる化学療法を行い、化学療法抵抗性のガン細胞が発生するメカニズムを調べるという、方法論としてはこれまで何度も用いられた、特に新味のない研究と言える。
ただこれまでこの様な研究から示されたのは、ガンの幹細胞モデルと呼ばれる考え方で、未熟な増殖しない幹細胞は薬剤耐性で、この段階で薬剤感受性が失われた新しい変異細胞が生まれ、増殖を始めることでガンが再発すると考えるモデルだ。
この研究ではイリノテカンを含む化学療法に対する大腸癌の反応を調べるうちに、治療初期段階で見られる耐性細胞は、幹細胞といった特殊な段階に集約されるのではなく、多様な細胞が一時休眠をしている可能性に気づいている。すなわち、幹細胞に集約する階層的なモデルではなく、全てのガン細胞が化学療法に対して一時的に休眠状態に入る、すなわちdiapauseモデルが起こっていることになる。
これを確かめるため、それぞれのガン細胞にレトロウイルスでバーコードを挿入し、化学療法による休眠で、バーコードの多様性が維持されるか調べている。もし幹細胞モデルなら、特定のバーコードに集約することが考えられる。答えは期待通りで、バーコードの多様性は化学療法によっても維持されることがわかった。すなわち、全ての多様な細胞がそのまま休眠期に入る。
後は休眠期のガン細胞の遺伝子発現を調べ、マウス胚盤胞期におこるdiapauseと同じ様な遺伝子発現プロファイルが見られることを示して、これが確かにdiapauseに対応する状態であることを確認している。
最後はメカニズムだが、例えば胚盤胞期のLIFの様な因子は残念ながら見つかっておらず、何がスイッチを入れるのかについては明らかでない。ただ、胚と同じで、mTOR経路が抑制され、代謝から増殖まで様々な分子の発現が低下していること、逆にこれを埋めるためのオートファジー機構が亢進していることを明らかにしている。また、mTOR阻害剤で同じ様にdiapause状態を誘導できることから、おそらくこの上流にある何かがガンのdiapauseのスイッチを入れているのだろう。実際、様々な癌で、化学療法を行うとdiapauseの遺伝子発現スコアが高まることも示しているが、スイッチは明確にはなっていない。
話はこれだけだが、もし多くのガンでdiapauseが治療初期に見られ、これがガンの薬剤耐性に関わるなら、この時期のdiapauseを抑制する方法の開発は、化学療法の効果をさらに高めると期待できる。この研究では、オートファジーの抑制がその鍵になると示唆しているが、これまでの研究を見るとこれだけでは足りないだろう。是非diapause自体のシグナルを見つけて、新しい治療法につなげてほしい。ひょっとしたらLIF?
2021年1月13日
この前zoomで中学校の同窓会をしていたら、茶カテキンが新型コロナウイルスに効果があることを産経で読んだので、感染予防目的で飲んでいると聞いて驚いた(飲むこと自体に問題はないが)。これは大阪府の吉村知事がポピドンヨードでうがいすれば重症化が防げると言って批判の的になったのと同じで、口内のウイルスを減らすということと、気道を通した感染による肺炎を単純に結びつけたことに間違いがある。もし本当に臨床効果があれば、間違いなく全国の待機感染者に勧められているだろう。メディアが断片を結び付けて、素人を騙している典型で、最後は記者発表した大学のせいにして後は知らん顔なのだろう。
ただ、口内のウイルス量を減らす効果があれば、ヨードもカテキンも捨てたものではない。すなわち、他の人にウイルスを感染させる最大の原因は唾液由来の飛沫だとすると、人と会う前にうがいをしたりお茶を飲んでウイルスが減るなら、完全とは思はないが、うつさないという点では少しは効果があるだろう。とすると「他の人に感染させない」という思いやりの心を強調して記者発表したり、報道することが必要だと思う。
今日紹介するワシントン大学からの論文は、一種の民間療法も、科学的に検証し、使い方まで明示すれば、立派な医学になることを示した研究で、少し軽めの論文紹介として取り上げることにした。タイトルは「Anti-neutrophil properties of natural gingerols in models of lupus(自然のgingerolが示すループスマウスモデルでの抗好中球活性)」で、JCI Insightというレッキとした医学雑誌に12月29日オンライン出版された。
この研究は生姜のエキスが炎症を抑える効果があるという民間療法からスタートしている。研究自体は、生姜から分離したgingerolと呼ばれる有機化合物が、白血球の炎症による血管炎を防止して、SLEの様な自己免疫性の血管炎を抑えるはずだという仮説に基づいている。
これを確かめるために、以前紹介した白血球がパンクする現象NETosis(https://aasj.jp/news/watch/14242 )をエンドトキシン処理などで誘導し、gingerolがNEtosisを抑制できるか調べ、10μM程度で強く抑制できることを示している。
次に、この効果の作用機序を調べ、活性酸素産生が抑制されること、そしてこれらの変化は、Phosphodiestraseを阻害することでcAMPの濃度が高まることによる結果であることを示している。
作用機序はここまでで、後はTLR7を刺激する物質を皮膚に塗布し続けることで誘導される自己免疫性の血管炎を抑制する実験を行い、
gingerol腹腔内投与によりNEtosisを体内でほぼ完全に抑えること、 全身性の自己免疫反応の結果起こる、抗DNA抗体などの自己抗体の出現を抑えられること、 自己抗体による血栓形成を抑えられること、 同じ効果は、phosphodiesterase阻害剤rolipramでも得られる。 ことを示している。すなわち、生姜エキスが白血球の炎症を抑えることで、ループス型の自己免疫病を抑えることができるという結果だ。
論文としてはこれだけで、古典的な薬理実験と言える。ただ好感が持てるのは、一般的に生姜サプリに用いられている量でこの実験を行っていること、経口で投与しても血中に到達できることなどを議論した後、それでも薬剤として使うのではなく、サプリメントとしてリスクを下げる方向で治験を行う方向を示している点だ。最終的には治験が終わって初めて評価ができるので、アウトカムを明示した治験を目指すという点が重要だ。
最後に個人的な印象を述べておくが、戯言と受け取ってほしい。ここで扱われた、NEtosis、抗phospholipid自己抗体による血管炎、血栓症などは、まさに新型コロナの重症化因子になっている点だ。その意味で、重症化防止のための治験を計画してもいい様な気がした。