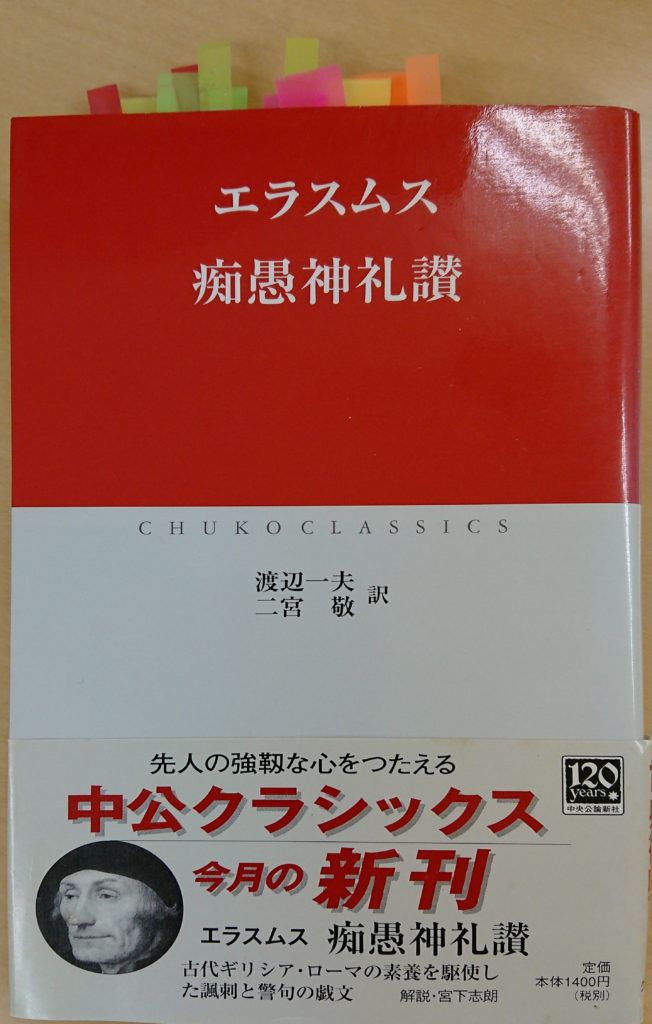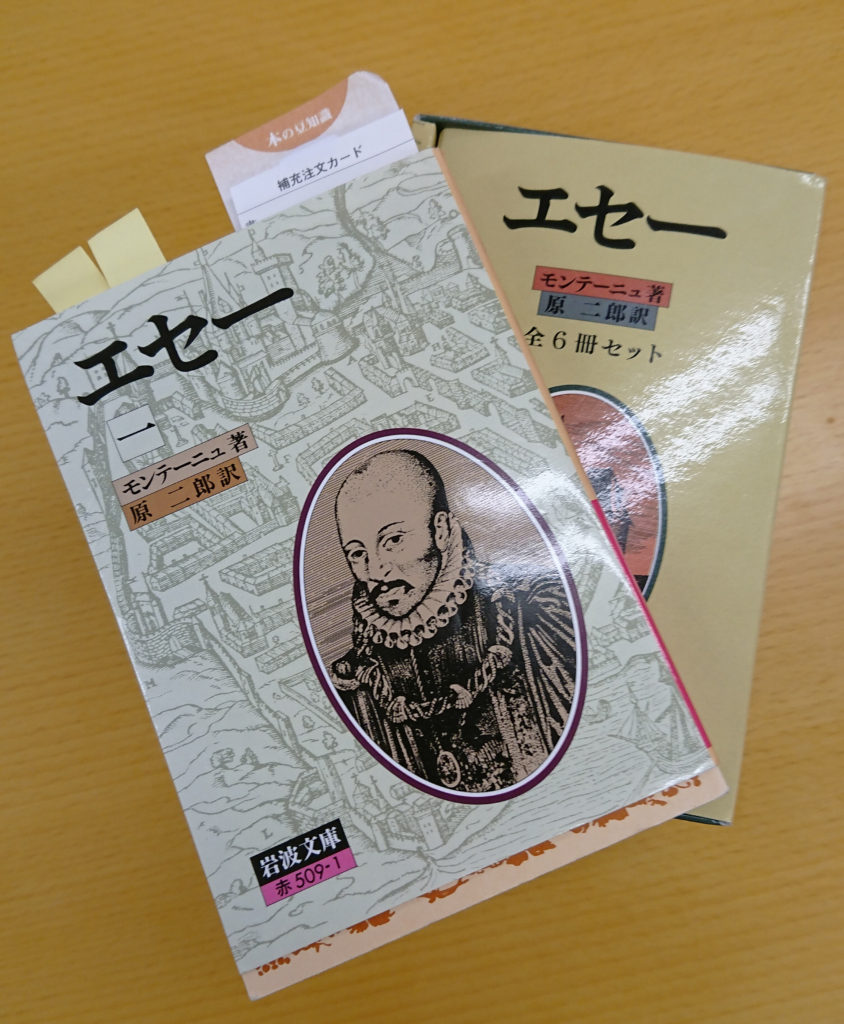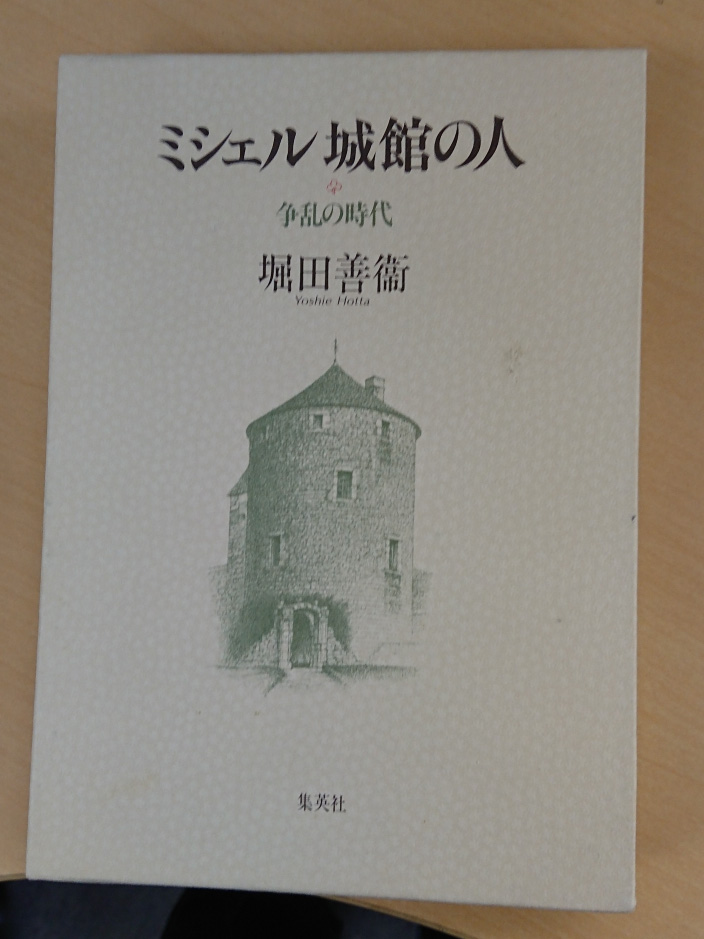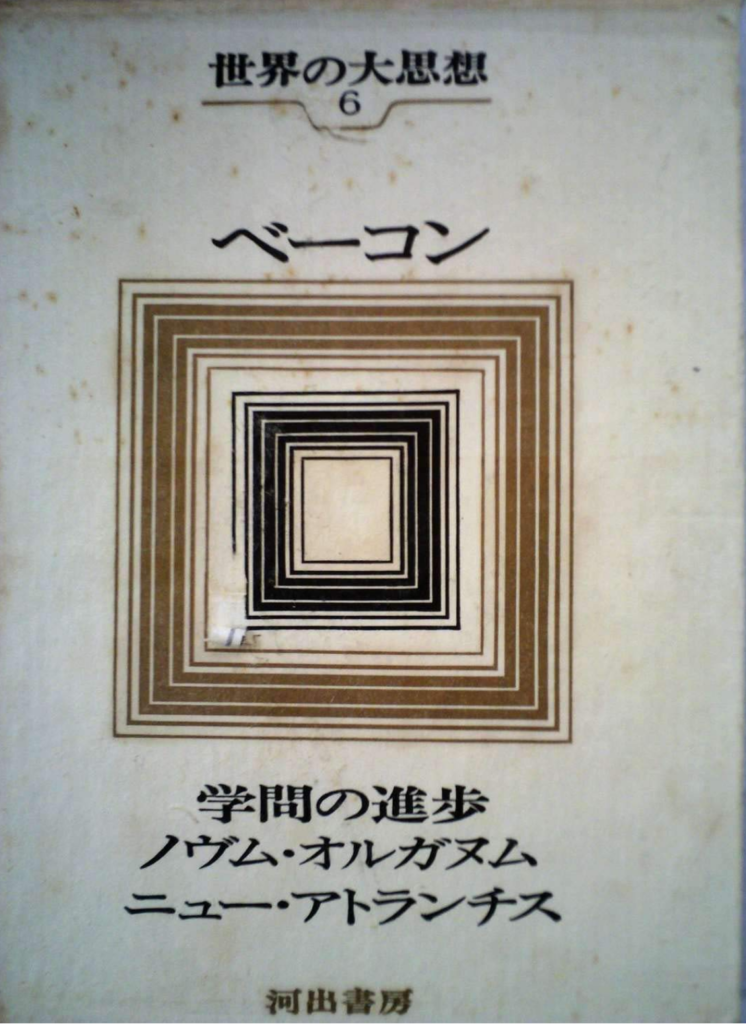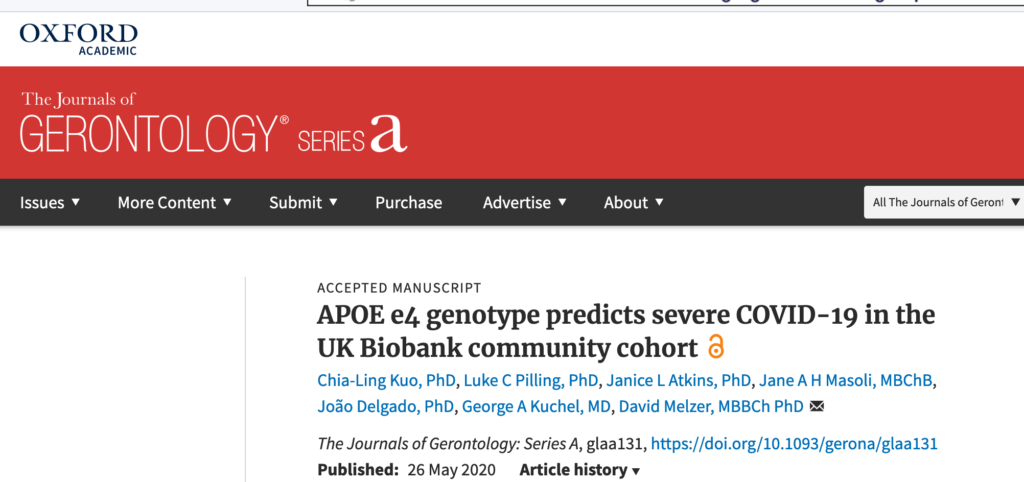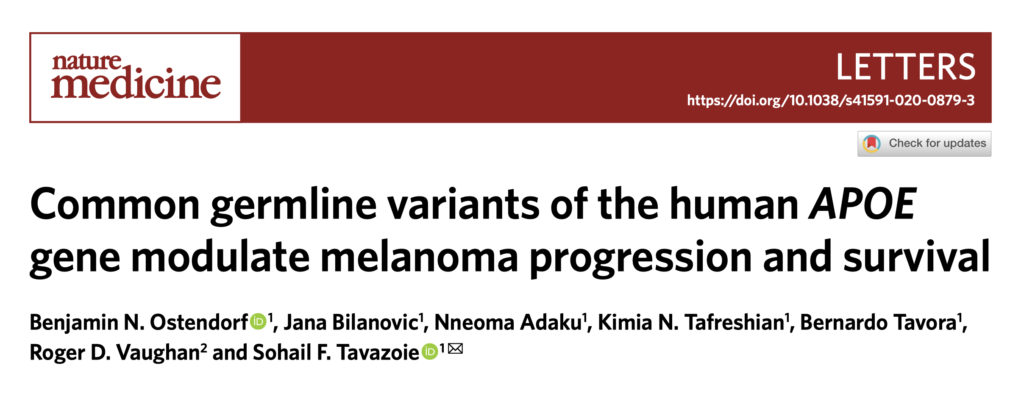2020年6月7日
これまでウイルス制御に用いられる手段は、ウイルスタンパク質に対する薬剤、ウイルス侵入に関わるホスト細胞に対する薬剤や抗体、ウイルスタンパク質に対する免疫反応、そしてウイルス感染細胞に対する免疫反応に限られていた。最近になってCRISPRも含め核酸医学が介入手段に加わったが、標的分子を抑えるという点では同じだ。
ところが今日紹介する上海/復旦大学からの論文はなんとペプチドを用いてウイルス粒子に穴を開けてしまうという、これまでにない方法の可能性を示す研究で6月3日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「An amphipathic peptide targeting the gp41 cytoplasmic tail kills HIV-1 virions and infected cells (AmphipathicなペプチドはHIVのgp41タンパク質細胞質内領域と結合してHIVウイルス粒子を賦活化する)」だ。
この研究では最初ウイルスEnvタンパク質の一部のペプチドを用いれば、ウイルス自体の感染を抑えられるという単純な発想で、Envタンパク質配列をカバーする15merのアミノ酸ペプチドライブラリーをスクリーニングし、F9170と名付けたgp41分子の細胞質内ドメイン由来のペプチドがウイルス感染をブロックすることを発見する。
おそらく最初は細胞外のドメイン由来ペプチドに活性があると予想していたと思うが、なんとウイルスエンベロップ内部の領域に対応するペプチドが活性を持つという意外な結果で、ウイルスタンパク質を真似ることで感染を抑えるという話ではなくなった。そこでこのペプチドをウイルス粒子に加える実験を行い、なんとウイルス粒子に穴が開いて、パンクさせることで、感染が防がれることを発見した。
さらにメカニズムを探ると、このペプチドはamphipathicな性質を持ち、ウイルスエンベロップに侵入し、gp41のLLP1と呼ばれる領域と相互作用を起こして、エンベロップに穴を開けることがわかった。すなわち、デタージェントと同じようなメカニズムでウイルス粒子を不活化する。ただ、このペプチドはウイルス特異的で、毒性はほとんどない。さらに、同じようにgp41を細胞表面に発現しているウイルス感染細胞もこのペプチドで穴を開けることができる。すなわちウイルス粒子だけでなく、感染細胞も殺せることがわかった。
これに基づき、猿を用いたウイルス制御実験を行い、期待通り血中ウイルスを検出できないレベルまで低下させること、また副作用はほとんどないことを示している。
全く新しい原理のHIV感染制御法と言えるが、課題も多い。まず完全にウイルス粒子が消失するのに、ペプチド投与をやめるとすぐにウイルスが現れることから、このペプチドだけではよほど濃度を上げない限り根治は難しい。また、半減期が短く、1日に何度も投与する必要がある。このため、臨床に応用するためには、まだまだ改良が必要だが、ともかく原理の異なる方法が開発できたことは重要だと思う。
実験の中でMERSに対するペプチドも可能性があることを少し述べているので、新型コロナについても同じような戦略が取れる可能性はあるので、その点でも期待したい。
2020年6月6日
新型コロナ騒ぎで全国的に病院収入が1割減ったことが報じられている。コロナ自体での損失を区別して詳しく精査する必要があるが、この落ち込みが不要不急の医療に当たるのだろうか。
特に興味があるのは、これが世界的傾向なのか、そして高血糖、高脂血症、高血圧などの生活習慣病に関する診療がどの程度減ったのかだ。というのも、この分野の医療費を減らすことが、各国の重要なテーマだった。今回の事象が各国の思惑どおり、メタボで病院に行く前に、まず予防という糸口になればいいが、まだまだ読めない。
今日紹介する世界中の研究機関が集まって発表した論文は2018年の世界の血中コレステロールマップを作成して、前回世界規模で行われた1980年と比較した研究で6月3日号のNatureに掲載された。タイトルは「Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol (コレステロール異常の世界的震源地を洗い直す)」だ。
この論文がNatureにふさわしい論文かとも思うが、世界中から1億人の総コレステロール値と、善玉以外のnon-HDLコレステロール値を集め、同じ土俵に乗せて比較することは大変な作業だと思う。
結果は明瞭で、40年前は最悪だった欧米諸国で、総コレステロール値の大幅改善が見られる一方、東南アジア、東アジアでは急速な上昇が見られる。しかし、絶対値で見ると、欧米諸国の値はまだ高いレベルにある。
しかしここからHDLを除いた、いわゆる悪玉で調べると、西欧諸国は絶対値でも低いレベルに落ち着いている一方、東南アジアでは東ヨーロッパに並んで最高値を叩き出している。
面白いことに、総コレステロールの増加は著しいが、東アジアのnon-HDLの絶対値は中程度で、東南アジアとは大きく異なっている。これと並行して、虚血性心疾患による死亡率が、西欧では大きく低下している一方、東南アジアを筆頭に、南アジア、東アジアで大きく上昇している。
要するに、所得が上昇すると最初は高脂肪食へ移行するが、さらに所得が上昇すると、健康に配慮した食生活に変わることを示しており、どの国も経済発展すれば自然にマインドが変わって健康になることを示している。
などと考えながら、コレステロールの変化マップを眺めてみと驚くのは、我が国ではこの40年、ほとんど変化が見られない点だ。幸い、40年前はほとんど世界の平均値だったことを考えると、今も世界の平均値にあると言えるだろう。メタボも我が国では気にすることはなさそうだ。
2020年6月5日
スコラ哲学紹介の最後となったオッカムを読んだ後(https://aasj.jp/news/philosophy/12487 )、すぐに17世紀近代(デカルト)に移っても良かったが、せっかく順番に読んできたので時代を飛ばさず橋渡しに16世紀を代表する、しかも「生命科学者の目」からみて推薦できる一人を選んでみたいと考えた。スコラ哲学と比べると、トマス・モア、エラスムス、モンテーニュ、フランシス・ベーコンなど16世紀には名前が知られた哲学者(?)が多い。そこで今回、4人の代表的な著作をまず読んでみた。
前回マルクス・ガブリエルを紹介した時(https://aasj.jp/news/philosophy/12813 )、20世以降、哲学から排除されてしまったように見える「宇宙の中の精神」といった形而上学的課題を、今も哲学の課題であるととらえ、新たな目でチャレンジしている点が、彼の新鮮さだと述べた。逆にいうと、形而上学的課題を哲学から排除しようとする雰囲気が20世紀にはあったように思う。ただこのような根本問題への哲学的チャレンジを諦める傾向はギリシャからローマ時代に移行した後にも見られ、哲学(少なくとも読める形で残っている)が処世術といってもいいほど極端に世俗化したことについてはすでに述べた(https://aasj.jp/news/philosophy/11539 )。
今回4人の著作を読んで、16世紀も哲学不毛の時代で、逆に形而上学的な課題はスコラ哲学議論と軽蔑されていたのがわかった。こうしてスコラ哲学からルネッサンスへと思想をたどってみると、世俗の勢いが増す時に、神学も含めて哲学は形而上学的課題を無視したり、軽蔑したりする傾向を示すようだ。ただ20世紀の場合、この世俗を代表したのが科学ではなかったかと思える。だからこそ、哲学にもう一度形而上学的課題を取り戻すために、マルクス・ガブリエルがその批判の矛先を向けたのは科学だった。何れにせよ、科学と哲学の関係については、17世紀を考える時扱ってみたい。
さて今回4人の著作を読んでみて、16世紀哲学を「ルネッサンス、宗教改革によりキリスト教会の相対的地位が低下し、世俗の王の権力が強まることで、教会に属さない世俗の賢人が現れ、人間のあり方(=ヒューマニズム)を論じた時代」と総括することにした。
世俗の賢人の最初はトマス・モアだ。教会内の神学者が担ったスコラ哲学時代と違い、16世紀を代表する思想家の多くは何らかの形で宮廷につかえる人たちで、トマスモアも大法官にまで上り詰めた国王の重臣だ。忙しい実務の合間に書いたのが有名な「ユートピア」で、この造語は今も理想郷を表す単語として定着している。
ユートピアはモアが考えた理想の国の話だが、おとぎ話というより16世紀の現実に即して構想されている。間違いなくプラトンの共和国を念頭に書かれたと思うが、ユートピアとはいうものの、プラトンの共和国と同じく国王が存在する。彼の描いた王はプラトンが述べた哲人王と同じで、哲学に基づく徳の精神で国を導く賢人に他ならない。面白いのは、この国で大事な哲学とは「宇宙の中の精神」を問うようなスコラ哲学でないとはっきり述べている点だ。モアにとって、形而上学などは世俗を中世に引き戻す邪魔な存在以外の何物でもなかったようだ。
ユートピアは読み物として面白く、構想が詳細にまでわたっていることに感心する。例えば奴隷の問題についてみてみよう。まず驚くのは、敵の捕虜といえども自由を奪うことは断じて禁止で、自由を奪えるのは唯一犯罪を犯した者だけだ。この時、罰として強制作業を要求できるとしており、現代の懲役刑と同じだ。さらに現代的なのは、市民権はないが外国から来て、自分で奴隷のような仕事を望む輩のことまで述べている。これも現在の外人労働者に相当する。このように内容は哲学というより、道徳的な賢人が世の中に向かって語る「お言葉」といっていいだろう。当然、いわゆる哲学からの引用は少ない。キンドルなので検索機能を利用して調べてみると短い本のなかにプラトンについての引用は15箇所もあるのに、例えばアリストテレスは1回だけで、しかも哲学の内容についての引用ではない。生命科学者の目から見ると、得るところは少ない。それでも、ユートピアに書かれた政治思想は革新的で、結果反逆罪で処刑されることになる。
世俗の賢人の二人目はエラスムス。他の三人と比べると、宮仕えはほとんどせず、自由な学者として過ごした賢人と言える。彼が友人のトマスモアの家に滞在しているときに書き上げたのが「痴愚神礼讃」で、モアのユートピアはこの本に刺激を得て描かれたと言われている。
この本も一種のおとぎ話だが、モアのユートピアとは真逆で、架空の異教の女神の目を通して現状を痛烈に批判しすることで、理想的社会を探るという構成になっている。この本ではモアのユートピア以上に、当時の庶民が生き生きと描かれており、同時代のピーター・ブリューゲルの描いた庶民の姿と完全に重なり合う。もちろん、この世相の中にはキリスト教も含まれており、キリスト教信者であったエラスムスがよくまあここまで言った思える文章も多い。たとえば人間が真実より嘘が好きなことを示す例として述べたくだりを引用してみよう。
「(教会の説教では・・)、真面目なことが話されていると、聴衆は眠ったりあくびをしたり退屈したりしています。ところが、説教師が小母さんがなさるようなおとぎ話を始めますと、会衆は全部目を覚まして、口をポカンと開けて聴き惚れます。・・・聖ゲオルギウスだとか、聖クリスフォルスだとか、聖女バルバラだとかいう、ちょっとおとぎ話風な、聖職離れした聖人がいることになりますと、相手が聖ペテロだとか聖パウロだとか、また主キリストご自信だとかいう場合よりも、はるかに崇拝されるようになれるのですよ」
ここに書かれた「痴愚性」はいつの時代も変わらないことがよくわかる。これがエラスムスが現代にも通ずるヒューマニストとして評価される理由だろう。
重要なのは、モアのユートピアと同じで、「哲学=スコラ哲学」については、手厳しく軽蔑している点だ。例えば、
「さてこの面倒な上にも面倒な彼らの道具立ては、数限りもないスコラ学派の流派のおかげで、もっと霊妙でしち面倒臭いことになっていますから、実在論者や唯名論者やトマス派やアルベルトゥス派やスコトゥス派など、私は主なものの名前しかもうしませんが、こういう多くの学派の羊の腸のようにクネクネ曲がった道よりも、寧ろ迷路から抜け出す方が皆さんにとっては易しいことでしょう」
という文章から、当時の大学では、「実在論だ、唯名論だ、あるいはオッカムだ」と、過去の思想を担いで口角泡を飛ばす議論のための哲学論議行われていたことが推察される。これは20世紀にも通ずるが、世俗化が進むとアカデミックな議論はどうしても浮世離れしてしまい、「哲学議論」は一般人も世俗の賢人も軽蔑する悪いイメージが定着していたことがわかる。
世俗の賢人の3人目は、我が国で最も知られた16世紀のヒューマニスト、モンテーニュだ。彼もボルドー市長に選ばれるとともに、宮廷でも仕えた貴族で、彼の「エセー」はわが国でも広く知られている。私自身もずいぶん昔、抜粋本では読んだ覚えはあるが、全く印象は残っていなかった。今回もう一度読んでみようと全6巻新たに取り寄せて読み始めた。しかし、モアやエラスムスとは異なり、断片的文章の集まりで、すぐ退屈してしまった。賢人の思想というより、賢人の独白といった感じで、1巻読むのが精一杯で、これ以上続ける気にならなかった。
いきなりネガティブな結論になったが、エセーは彼の生きた時間に沿って書かれている独白なので、最後まで読み通せば16世紀の個人主義的ヒューマニズムのあり方もよくわかったのかもしれない。読み通していないのにそう思うのは、堀田善衛さんの「ミシェル城館の人」を読んだからで、エセーを読んだことのなかった私も、随分昔この本を読んで、カソリックとプロテスタントの抗争と世俗の権力をめぐるヨーロッパ全体の抗争が複雑に絡み合った時代と、その時代を世俗の賢人として生きたモンテーニュについて理解することができていた。
今回もう一度読み返したが、史実とフィクションがうまくブレンドされた16世紀を知るための素晴らしいガイド本になっている。しかし率直な印象を述べると、堀田さんはモンテーニュをあくまでもこの時代を案内するためのガイド役として登場させ、彼を思想家というより、家族や世間の間で苦労しながら自分を守ろうと努力している思索家として描いている。実際、モンテーニュ自身も、体系的思想など全く重視していなかったようだ。
堀田さんはこの本の中で、
モンテーニュの『エセー』(試み)は、実に進行形の思想の歩みを示すものであった。さればストア派の思想の枠を出て、精神と肉体の様々な存在の仕方の認識を経て、精神と肉体の解放と自由の歩みを示すものであり、その試みはつねに運動を伴っているのであった。それは固定した、一定の思想の平べったい陳述ではなかった。たとえば思想の陳述に、明確な、枠組みのはっきりした起承転結を求める人や、何につけても結論だけを求めるような人には、『エセー』は怪物的なまでに雑駁な、ある種の集積物と見えるかもしれないであろう。
(ミシェル城館の人 第三部 精神の祝祭 )
と述べて、エセーは思索の集積で、私のように「平べったい思想」を求めてはならないと戒めている。そして「 私はその日その日を生きている。そして失礼は承知の上で、ただ私のためだけに生きている。私の目的はそこに尽きる。 」という彼の晩年の言葉を引用して、同じ世俗の賢人でも、モアやエラスムスとは対極的な、極めて個人主義的傾向の強い賢人として描いている。
このように科学や哲学の観点から見ると、この3人の人文主義者の貢献は大きくないように思うが、しかし権威を疑い自分で考える、個人主義や主観主義の先駆けとして17世紀近代を準備したことは間違いない。この点では、世俗の賢人4人目、フランシス・ベーコンも同じだが、他の3人と比べるとベーコンの科学、哲学への貢献は大きい。世俗の人としては英国で大法官にまで上りつめた貴族だが、経歴を読むと失脚と復活を繰り返し、おそらく4人の中では最も政治的野心の強い賢人だったと思う。実際、著作からもヒューマニストと言う印象はほとんど感じられない。今回読んだ河出書房の世界の大思想には3つの著作が収載されている。この中のニュー・アトランティスは、ベーコンがモアのユートピアに対抗して理想郷を描こうとした作品で、他の3人と同じ側面を見せる作品だが、モアの構想と比べると理想からはほど遠く、退屈な本だった。政治的野心満々の賢人にはユートピアは構想できないことがよくわかる。
しかしこのようなギラギラした政治家に、賢人としての能力と知識が備わっていたことが重要で、他の3人と比べて彼が科学や哲学に大きく貢献できたのは、彼が政治家として現実的に世界と向き合っていたからではないだろうか。このことが最もよくわかるのが、「学問の進歩」で、この本を元にベーコンの思想を見てみよう。
この本は、国王に対して学問の重要性を進言すると言う形式で書かれており、まず主張しているのが、知識を信頼し、できるだけ蓄積し、それに基づいて判断することの重要性だ。現代風に言えば、エビデンスに基づいて判断することの重要性で、政治家としては当然の話だ。しかし、我が国の政治状況からもわかるように、エビデンスに基づいて判断することほど難しいことはなく、個人の思いつきや独断が判断を支配する。実際、今も昔も政治家の多くは学問など学者の遊びで役に立たないとバカにするようで、ベーコンも「学問は人間の気質をゆがめ、そこねて、支配や政治に関することがらに向かなくさせる。 」とか、様々な理由をあげつらって学問蔑視の風潮が存在することを嘆き、アレキサンダー大王や、シーザーを例に、学問を通して知識を蓄積することの重要性を説いている。
学問が無意味であるとする様々な批判について一つ一つベーコンが丁寧に答えているのを読むと、今も昔も全く変わらないと思う。例えば、学問する時間などないと言う批判については、
「学問はあまりにも多くの時とひまをくうという異議の申し立てについては、わたくしはこう答える。ずばぬけて思いきり活動的な忙しいひとにも、(きっと)仕事がそのうちにたてこんでくるのを待っているあいだの、手すきの時間はたくさんある。 」
どんなに忙しい人でも、学問の時間がないと言うのは理由にならないと一括している。
この「学問ノススメ」の確信は、そのまま学問の方法論へと向かう。ベーコンにとって学問とは、現実の世界に向き合い、世界と自分との相互作用の中で知識を蓄積する事で、自分の好き勝手に集めるものでも、一方的に外から与えられるものでもない。従って、信頼できる知識と、信頼できない知識をまず判断する事が必要になる。ここでも紹介したプリニウスの博物誌(https://aasj.jp/news/philosophy/11539)やアルベルトゥス・マグヌス(https://aasj.jp/news/philosophy/12074)についても、
「同じように自然誌においても、しかるべき選択と判定がなされていないことがわかるのであって、たとえば、プリニウス〔ローマの博物学者、「自然誌」の著者、後二三─七九年〕やカルダヌス〔ルネサンス期イタリアの自然哲学者、医学者、数学者、一五〇一─一五七六年〕やアルベルトゥス〔ドイツ出身のスコラ学者、その博識のゆえに大アルベルトゥスとよばれた。トマス・アクィナスの師、一一九三年頃─一二八〇年〕やアラビアの多くの学者の著作にあきらかであるように、それらは、寓話の類にみちみちており、それがまた大部分、真偽のほどもたしかめられていないばかりか、評判のうそごとであって、じみで、まじめな学者たちには、自然哲学の信用を大いにおとしている」
と断じて、知識の信頼性を判断する方法論の重要性を述べている。
ベーコンにとって、世界についての知識は分野を問わずできる限り集める事が学問だが、間違った知識を区別するためにも、分野を整理し、それを体系化する作業を繰り返す必要があると考えている。この点で、他の3賢人と異なり、自然哲学から倫理学まで知識を体系的に整理しようとしたアリストテレスへのベーコンの評価は高い。その結果、ベーコンが考える知識体系の中に形而上学も含まれており、形而上学、自然神学、自然哲学など異なる次元から多元的に世界に向き合う事の重要性を説く。少し長くなるが、彼が形而上学の重要性を述べている箇所を引用しよう。
「それゆえ、わたくしがいま解するような、形而上学という名称の用法と意味とに話をもどすことにしよう。すでに述べたところによって、わたくしが、これまで混同して同一のものとされていた、「第一哲学」すなわち最高の哲学と形而上学とを、二つの区別されたものと考えようとすることはあきらかである。というのは、前者をわたくしは、あらゆる知識に対する親または共通の祖先とし、後者をいま、自然に関する学問の一部門または子孫としてもちこんだのであるから。なお、わたくしが最高の哲学に、個々の学問に対して無差別で不偏である共通の原理や一般的命題の探求をわりあてたこともあきらかである。わたくしは、それにまた、量、類似、差異、可能性などという、実体の相対的で付加的な性質の作用に関する研究をもふりあて、そしてこの哲学に、それらの性質は論理的にとり扱うべきではなく、自然において作用するものとしてとり扱うべきであるという差別と規定をもうけたのである。なおわたくしが、これまで形而上学と混同されてとり扱われていた自然神学に、それの範囲と限界を規定したこともあきらかである。それゆえ、いまここに問題となるのは、何がなお形而上学のために残されているかということであるが、この問題に関して、自然学は、質料に包みこまれ、したがって変化するものを考察し、形而上学は、質料からひき離されて変化しないものを考慮するという点まで、古人の考えを保存しても、真理をそこなうことはないであろう。また、自然学は、自然界にただ存在と運動だけを想定するものをとり扱い、形而上学は、自然界になおそのうえに理性と知性とイデア〔原型〕をも想定するものをとり扱うといってもよかろう。しかし、その相違は、つぎのようにはっきり表現すると、もっともなじみぶかく、わかりやすい。すなわち、われわれは、さきに自然に関する哲学一般を原因の研究と結果の生産とに区分したように、原因の研究に関する部分をも、原因の一般に認められている堅実な区分〔アリストテレスの「四つの原因」の説、「形而上学」一の三等〕に従って、細分する。すなわち、〔原因の研究に関する自然哲学のうち〕自然学という部門は、質料因と作用因をとり扱って研究し、形而上学という他の部門は、形相因と目的因をとり扱うのである。フィジック〔自然学〕は(それをわれわれの医術を意味する慣用法に従ってではなく、その語源に従って解すれば)、自然誌と形而上学との中間に位する。というのは、自然誌は事物の種々相を記述し、自然学は原因を、ただし変易的なまたは相対的な原因を記述し、そして形而上学は固定的で恒常的な原因を記述するからである。 」(ベーコン. ワイド版世界の大思想 第2期〈4〉ベーコン)
このように、世界を理解するためには、自然神学と形而上学を混同することなく、アリストテレスが考えた4つの因果性を理解するためには、眼に見える因果性(質料因と作用因)を研究する自然誌とともに、形相因や目的因のような眼に見えない因果性を扱う形而上学が必須であると述べている。さらには自然誌と形而上学の中間に、目的因も含めて考える医学生物学といってもいい中間的学問が必要なことまで指摘している。生命科学に関わってきた人間としては、読むだけでゾクゾクする文章だ。科学も、哲学も、宗教も、世界を理解するためには全て必要だとする多元的な見方は、現代に形而上学を復活させようとしたマルクス・ガブリエルに重なる。
このような多元的な知識の重要性の認識は、次にこの多元的知識をもとに何が真実かを判断するときの方法論へと移る。そして「ノヴム・オルガヌム」(大革新)というタイトルから彼の自信のほどがうかがわれる著作で、新しい方法論として示されるのが「帰納法」だ。
「さて、わたくしの方法は、実行することは困難であるけれども、説明することは容易である。すなわち、それは確実性の階段をつくる方法であって、感覚の権能を、それにある種の制限を加えて認めるが、しかし感覚につづいておこる精神のはたらきは大部分しりぞけて、感官の知覚から出立する新しくて確実な道を精神のために開く方法である。」
と述べ、3段論法などこれまでの方法論は個人的な予断の入る余地があまりに多すぎて信頼できず、「確実性の階段を作る方法 」で、「感官の近くから出立する新しくて確実な道 」、すなわち帰納法こそ信頼できる方法論であると述べている。
ベーコンの偉大さは、帰納法の重要性を論じた上で、帰納法がまだまだ完成していないことをはっきりと告白している点だ。
「ところで、一般的命題をうちたてるさいには、これまで用いられてきたのとは別の形式の帰納法を考え出さなければならない。しかもその帰納法は、ただ第一原理(といわれるもの)についてだけではなく、低次の一般的命題や中間の命題についても、いな、すべての一般的命題についても、それを証明し発見するために用いられなければならない。というのは、単純枚挙による帰納法は子どもじみたものであって、その下す結論はあぶなっかしく、矛盾的事例によってくつがえされることを免れず、そしてたいていの場合、あまりにも少数の、それも手近にある事例だけによって断定を下すからである。しかしながら、諸学と技術との発見と証明に役だつ帰納法は、適当な排除と除外によって自然を分解し、そうしてから否定的事例を必要なだけ集めたのち、肯定的事例について結論を下さねばならぬのであるが、このようなことは、定義とイデアを論究するためにある程度この形式の帰納法を用いたプラトン〔たとえば、「国家」第一巻において「正義」について〕によってのほかは、まったくまだなされたことはなく、また試みられたことさえもないのである。しかしながら、このような帰納法または証明をうまくうちたてるためには、これまでどんな人間も考えたものがないほどじつに多くのことがなされねばならず、したがってこれまで三段論法に費やされたよりももっと多くの労力がそれに費やされねばならぬのである。 」
事実、現在も帰納法は「確実性の階段」を完成させるまでには至っていない。しかし、生命科学を始め、力学的因果性では理解できない多くの領域で最も重要な方法論になっていると言える。20世紀に入って、情報科学が進んだおかげで、帰納法も大きく進展した。全ての過程が見えるわけではないが、AIのパワーを見ると、新しい帰納法が生まれたという実感がある。その意味で、ベーコンは現在の情報科学の原点と言っていいのかも知れない。
ノヴム・オルガヌムは短い著作で、翻訳もわかりやすいので、生命科学を志す人にはぜひ読んで欲しいと思うが、ここに現れる思想は極めて近代的で、ヨーロッパの科学・哲学のルーツを見る思いがする。
長くなったのでまとめに入ろう。
16世紀はダビンチやミケランジェロが活躍した後期ルネッサンス期と重なるが、ヨーロッパ全土で戦争が絶えず、また宗教改革を通して、カソリックの力が低下、代わりに世俗の力が勃興した時期だ。これを反映して、当然哲学も大きな変化を遂げ、それまでキリスト教と一体だったスコラ哲学者に変わって、教会やアカデミアから独立した世俗の賢人が生まれる。しかし、世俗化は哲学の退潮とも同義で、モア、エラスムス、モンテーニュなどの有名な人文主義者は生まれたが、その後の哲学に対する貢献はほとんどなかったと言える。
ベーコンを読むまでは、これが私の16世紀の総括だったが、ベーコンを読んで一変した。引退後は自分で様々な実験を行なったと伝えられているので、コペルニクスに代表される科学の進展にも理解があり、政治的野心も隠さない、一種の超人だった。事実に基づき、宗教、政治、哲学、科学まで排除することなく多元的視点を貫ぬくことを説いたことが彼の哲学への貢献だ。マルクス・ガブリエルを読んでからベーコンを読んだが、読みながらずっとガブリエルを思い出していた。16世紀のマルクス・ガブリエルなどというと本末転倒だが、自由奔放な思想で新たに哲学を復興させようとした点も重なって見える。
多元主義と帰納法を基礎におくベーコンの思想は、近代に足を踏み入れているどころか、二元論を超えているようにさえ思う。少し褒めすぎた気もするが、ベーコンの思想を知ってから17世紀哲学を読んでみると、全く違った印象が得られるのではと今から楽しみだ。次回はデカルトから始めよう。
2020年6月5日
イスラエルを訪問した時、死海文書が展示されている博物館も訪問したが、建物のイメージは鮮明に残っているのに、死海文書のイメージはほとんど残っていない。たしかに、ちょうどキリスト教が始まる時代の旧約聖書テキストの発見は20世紀最大の発見とされているが、我々アジア人にはなかなか実感がない。ただ、現役を退いて自由に様々なことを知るうち、ギリシャ イオニアの哲学とほとんど同時期に誕生した一神教のルーツ、ユダヤ教の成立過程や、そこから派生したキリスト教との関係などは、人間に普遍的な精神的特徴を理解するためには重要なイベントであることが理解できる。その意味で、もう一度死海文書を見に行きたいなと今は思っている。
今日紹介するイスラエル・テルアビブ大学からの論文は、この死海文書の断片のDNAからテキストが書かれた場所や状況を推定し、文書学を助けようとする試みで6月11日号のCellに掲載される。タイトルは「Illuminating Genetic Mysteries of the Dead Sea Scrolls (死海文書の遺伝的ミステリーを明らかにする)」だ。
旧約聖書は、天地創造からユダヤ人の歴史、預言者の言葉からさらには恋の歌まで多種多様なテキストが含まれている。古事記、日本書紀から万葉集が一体となったようなテキストなので、誰が書いたのか、いつ集大成されたのかなど、解決すべき問題は多く、その意味で最も古いテキスト死海文書の重要性は計り知れない。
この研究のポイントは死海文書の多くが羊皮紙に書かれているので、そこに残る家畜のDNAを解析すれば、羊皮紙が由来した動物の種類や、生息場所を特定することができ、これにより死海文書断片の関係性を推定できると着想した点だ。ただ、言うは易く行うは難しで、骨の中で守られているDNAの解析とは話が違う。使われた方法を見ると、DNA配列決定から情報処理技術まで多くの方法を独自で開発した大変な研究だとわかる。
その結果、今回解析した39種類の断片は、牛、羊、山羊由来の羊皮紙が使われていることがまずわかった。なかでも、同じエレミア書が書かれた羊皮紙の一部が、牛の皮でできている点で、発見されたクムランを含む死海では牛を飼うことはほとんどなかったことを考えると、アフリカなどから持ち込まれた可能性が強く示唆される。使われている文字からも、この可能性は指摘されており、今後統合的な研究からエレミア書がどう書かれたのかについても研究が進む。
多くの羊皮紙は羊が使われているが、ミトコンドリアの解析から、この地域の羊の遺伝子型と対応させることができ、それぞれの羊皮紙がどこで作られたのかを推定することができる。また、ゲノム遺伝子断片を対応させることで、解析した各断片の関係から、産地などを特定することができる。事実、死海文書の中に旧約聖書とは関係のない断片が存在することも今回確認できている。
さらに、ユダヤ文化の多様性についても羊皮紙の由来を探ることで解析することができ、その例として天使の歌と呼ばれるグノーシス派とも関係付けられる文書が、クムランだけでなく、マサダで書かれた文書にも存在することが確認され、天使の歌が当時広く知られていたことも明らかになった。
よく読んでみると科学が手伝えるのはほんの一部ではあるが、ゲノム科学のさらなる可能性を示す面白い論文だと思う。
2020年6月4日
コロナ感染で日本の政府や専門家は熱が出ても自宅で4日待てという戦略をとった。疫学的には正しいかもしれないが、しかし4日間自分の体についてのなんの情報もなくそのまま待つことは大変だったと思う。しかも急速に進展するかもしれないなどと、マスメディアから情報が入ってくる。これを解決する一つの方策として遠隔医療が解禁された。
このようにポストコロナで遠隔医療は加速するが、これは従来の医者と患者の関係がそのまま診療所から自宅へテレビ電話で移行するだけの話ではない。病院に行けない患者さんの不安を取る必要がある。したがって、診断や治療をできるだけ患者さんの側で済ませられる技術が急速に進んで、医師の診断、そして治療への関与すら低下していく可能性が高い。この診断には個人のメディカルレコード、症状、将来自宅で可能になる様々な検査を処理するAIの開発が必須だが、個人ゲノムデータから計算される病気のリスクスコアは役に立つと考えられる。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、個人ゲノムデータサービスによって解析されたデータをリュウマチ性関節炎の治療に使う可能性を調べた研究で5月27日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Using genetics to prioritize diagnoses for rheumatology outpatients with inflammatory arthritis (炎症性の関節炎で受診する患者さんの診断に遺伝情報を使う)」だ。
考えてみると、個人ゲノムサービスは個人に様々な病気のリスクを伝えるだけで終わることが多かった。おそらくこれが我が国では個人ゲノムサービスが発展しない原因だったと思う。しかし、例えばコロナにかかりやすいリスクが計算できれば、サービスを受ける人は急増するだろう。すなわち、個人ゲノムが、診療の入り口で役にたつことが個人ゲノムサービスの進展には必須になる。
この研究では関節炎を起こす5種類の病気に絞って、これまでのゲノム研究に基づくリスクスコアを計算できるG-PROBを開発した。そして、関節痛などで診療を受けた患者さんの診断過程にこのG-PROGが役にたつかを、3種類のコホートを用いて、異なる条件で検証している。ここでは、初診から診断に当たるまで、丹念にレコードを照らし合わせた3番目のセッテイングの結果だけに注目して説明する。
実際の診療に当たっていないので詳しくはないが、確かに関節痛の患者さんの正確な診断に至るのは簡単ではなさそうだ。この研究では、G-PROG スコアを組み合わせることで、少なくとも候補疾患を一つは外すことができ、84%で2つの候補を外すことができることを示している。そして、専門家の最初の診断名の35%は後で変更されていることを考えると、G-PROGと症状を組み合わせた確率計算を用いると、65%が最終診断と一致していることは、G-PROGによりほとんど専門家のレベルの診断が可能になることを示している。また、血液検査のデータを加えると、その正確度を22%高めることができる。
以上、個人ゲノムサービスデータは、臨床医、特に家庭医での診断レベルを高めるのに大きく役にたつという結果だ。
この研究の重要性は、病気のリスクを並列的に示すだけと考えがちな個人ゲノムサービスが、アプリケーションによって、特定の疾患群の鑑別診断に使えることをしめした点だ。このように、一般のお医者さんが個人ゲノムが役立つと実感できれば、このサービスは拡大すること間違い無いと思う。
2020年6月3日
最初このブログは、一般の人に生命科学の最新の研究を紹介する目的で書き始めたが、わかりやすく書くという点では、どうも私は向いていない。結局対象としては少し専門知識のある人向けになっていると思う。分野についてはできるだけ広くカバーして、新しい研究についての情報を伝えようと努力し、個人的趣味はなるべく出さないように心がけている。
ただ、今日は1年に一回の誕生日ということで、極めて趣味的な論文を選ぶことにした。個人的な興味から論文を漁っている分野は、Abiogenesis、言語など様々あるが、下世話な興味としては芸術家の頭の中についての研究がある。例えば、東京芸大の美術の学生さんと話していたとき、彼らが鏡を見ないで自分の顔をイメージできることに気づいた。 生まれつきか、訓練か、要するに私たち凡人とは文字通り頭の構造が違う。何が違うのか?画家と一般人とに自分の顔を思い浮かべてもらって(今トライしてもはっきりしたイメージは私の頭に湧いてこない)、機能的MRIで活動領域に違いがないか是非知りたいといつも思っている。もちろん自分も実験台として参加したい。
そんなわけで、今日は音楽家と一般人の脳活動の差について調べたフライブルグ大学からの論文を紹介したい。タイトルは「Musicians use speech-specific areas when processing tones: The key to their superior linguistic competence? (音楽家は言語特異的領域を音の処理に使う:これが音楽家が言語能力が高い理由?)」で、Behavioural Brain Researchにオンライン掲載された。
この研究では音楽家は高い言語能力を備えているという仮説から始めている。あまり考えたことはなかったが、確かに有名な音楽家は話がうまいように思う。この理由としては、音楽と言語の両方に関わる脳領域の反応性が、音楽の訓練により、その結果言語能力もひきずられて高まる可能性と、もう一つは音楽の訓練により、通常は言語特異的な領域を、音楽の認識にも動員できるようになり、その結果言語能力が高まる可能性だ。
この研究では、子音と母音の組み合わさったシラブルの中から、あらかじめ教えておいたシラブルを聞き分ける言語課題と、様々な楽器で弾いた同じ音の中からピアノの音を聞き分ける音楽課題を行い、目的の音を聞いた時の反応性の速さを見ている。
この程度の課題だと、まず間違う人はいない。驚くことに、反応性で見ると、言語課題も、音楽課題も、音楽の訓練を受けた人の方がはるかに早く目的の音を認識する。100ms以上の差なのでかなり大きいと思う。
この課題を行いながら機能的MRIで脳の活動を音楽家と、一般人で比べると、同じ課題に動員される領域の差と、反応領域での反応の強さがわかる。結果は以下のようにまとめられる(脳領域の名前は全て省くが言語野や聴覚領域が中心になる)、
言語野の近くには、今回の言語課題と音楽課題の両方で反応する領域がいくつか特定できるが、その反応性は音楽の訓練を受けていた人の方が高い。 音楽の訓練を受けた人は、普通の人では言語課題にしか反応しない領域を音楽課題に反応できる。 もちろんこれだけで、音楽家は言語能力が高い理由がわかったとは到底言えないが、しかし音楽家の頭の中が違っていること、そして言語と音楽の認識に共通性があることもよくわかる。
今日の私の趣味に付き合っていただいた人は、HPの「生命科学の現在」として書き残している「言語の誕生」(https://aasj.jp/news/lifescience-current/10954 )をぜひお読みいただきたいが、そのなかで、
実際には、失音楽症の表現は極めて多様で、個人差が大きく、失語症以上に決まった領域にマッピングが難しい。例えばラベルのようなプロの音楽家の失音楽症は左側頭葉の障害による場合が多いことが知られている。一方、多くの失音楽症の症例を集めて検討した研究(例えば2016年、Journal of Neuroscienceに報告された77症例の検討:Sihvonen et al, J.Neurosci. 36:8872, 2016)では、失音楽症の半数に失語が合併しており、言語と音楽能力に関わる共通脳領域の関与を示している。
と、音楽家は言語野を音楽に使うことが失語の研究から推察できることを紹介した。このように、言語と音楽のルーツは、ホモ・サピエンス独特の知能のルーツを知ることにもつながる。
他にも、自閉症の子供さんが音楽訓練によって、言語野を開発できるとすると、今行われている音楽療法をさらに科学的に発展させることもできるだろう。このように芸術家の頭の中は、面白いだけでなく役に立つこと間違いない。
また明日から、現代を代表する論文を探して紹介する作業を、体力の続く限り続けますのでよろしく。
2020年6月2日
腫瘍組織に細菌が存在することは昔から知られていた。また、いくつかの細菌は腫瘍の増殖を促進することも知られている。ただ、このような話を聞くとき、細菌が細胞の間に存在していると言ったイメージで考えていた。
今日紹介するイスラエル ワイズマン研究所からの論文は、腫瘍組織に存在する細菌の多くは細胞内に寄生し、それぞれのガン特有の細菌叢を形成していることを示す研究で5月29日号のScienceに掲載された。タイトルは「The human tumor microbiome is composed of tumor type–specific intracellular bacteria (人間の腫瘍組織の細菌叢はガンのタイプに特異的な細胞内バクテリアからできている)」だ。
この研究ではまず数多くのガン組織を集め、そこから調整したDNAの中に存在するバクテリアリボゾーム検出と並行して、細菌特異的成分であるLPSやリポタイコ酸を抗体染色で検出し、まずそれぞれのガン組織にどの程度の細菌が巣食っているのか、細菌はどこに生息しているのかを調べている。
実際には、サンプル調整中に起こる汚染で侵入したバクテリアを除外することが重要で、様々な工夫を重ねて、細菌の量が最も多いのが乳がんで、骨肉腫、すい臓がん、グリオブラストーマと続くことを明らかにしている。
そして驚くのは、in situで細菌の16Sを染色すると同時に、LPSやリポタイコ酸を染めると、全てガン組織の細胞内に存在することがわかった。詳しく観察すると、膜成分のリポタイコ酸は全てマクロファージ内に存在し、貪食された膜成分が検出されると考えられる。一方、16Sは、ガン細胞および血液細胞に存在し、他の細胞には存在しない。ガン細胞内に細菌の16Sが検出されるのに、膜成分のリポタイコ酸が存在しないと言うことは、細菌は細胞壁のないL-formで存在することを示唆するが、電子顕微鏡的に確かめている。
さらに驚くのは、これらの細菌が一つの種類というのではなく、一種の生きた細菌叢を形成している点で、乳がんには175種類の細菌が存在している。また、細菌だけが利用できるD-アラニンがガン細胞内で取り込まれることから、細胞壁は持たないが細胞の中で細菌が生きていることを明らかにしている。
次に、single cell レベルの配列決定を行い、それぞれのガンでどのような細菌が増殖しているのかを調べると、それぞれのガンで特徴的な細菌セットが維持されていることがわかる。これは、ガンとの共生など、一種の相互作用の可能性を示唆する。そこで、細菌のもつ代謝経路と、ガンの関係を調べると、骨肉腫では骨のコラーゲンを分解する酵素を細菌、喫煙者の肺がんではタバコの有害物質を分解する酵素を持つ細菌、などが特定されている。
他にも細菌が免疫系細胞内に存在することは当然自然免疫を誘導するので、おそらくガンの進展にも関わるかもしれない。
以上が結果だが、細菌叢をホストの細胞内の細菌叢として見直すことで、ガンの治療標的も見えてくるかもしれない。しかし、細胞壁のないL-formがこれほどの数で存在するとは、バクテリアの適応力恐るべし。
2020年6月1日
例えばピーナツを食べた後急にショックが起こるアナフィラキシーショックの分子メカニズムは、一昨年亡くなった石坂先生のIgE の発見を発端に詳しく解析されている。IgEがプラズマ細胞から分泌されると、マスト細胞上のFcε受容体に結合し、維持される。そこに抗原が来ると、IgEが抗原の周りに集合し、これがFcε受容体を刺激、その結果ヒスタミンなど様々なエフェクターが分泌されアナフィラキシー反応を起こす。このようにほとんど解明し尽くされていると思っていても、本当はまだ理解できていない点もある。特に、抗原特異的IgEが存在することがわかっているのに、アナフィラキシーを起こさない人が多くみられるが、上のシナリオでは全く説明できない。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、アナフィラキシーが起こるためにはIgEができるだけでは不十分で、IgEがシアリル化されている必要があることを示した論文で5月28日号Natureに掲載された。タイトルは「Sialylation of immunoglobulin E is a determinant of allergic pathogenicity (IgEのシアリル化はアレルギー反応の決定要因)」だ。
50年近く研究されても、こんなことが明らかになっていなかったのかと思える典型だが、このグループは様々な抗原に対してアレルギー反応を起こしている患者さんのIgEと、血中IgEが存在するのにアレルギーが起こっていない人のIgEを用いて、マスト細胞刺激実験を行い、アレルギー患者さん由来のIgEだけがマスト細胞のエフェクター分泌を刺激できることを確認し、抗原特異的IgE分子自体にFcε受容体を刺激する能力の差があることを明らかにしている。
次にこのIgE分子自体の差が糖鎖の修飾の差にあると仮説を立て、アレルギー誘導能力と糖鎖との相関を調べ、両者で糖鎖の修飾の差が確かにあること、中でもシアリル化にはっきりとした差があることを明らかにする。また、シアリル化修飾はノイラミニダーゼで外すことができるので、アレルギー誘導能力のあるIgEをノイラミニダーゼ処理すると、アレルギー誘導能力が消失する。
以上の結果は、IgEがシアリル化されていることが、抗原結合後のFcε受容体刺激誘導に必須であることを示している。しかし、シアリル化自体は、IgEと抗原の結合、半減期、Fcε受容体との結合には影響がないことも明らかになった。従って、シアリル化がどのように受容体シグナルに影響するのかについての分子メカニズムは、この研究では残念ながら答えが出ていない。
しかし、シアリル化が必要であることは明らかになったので、刺激活性のないIgEを用いてアレルギー反応を抑えられるか実験を行い、抗原特異性を問わず10倍のシアリル化されていないIgEが共存すれば、アレルギー反応が起こらないことを示している。
そして最後に、IgEの抗原結合領域を、糖鎖を切断するノイラミニダーゼに置き換えた分子を設計し、Fcε受容体に集まるIgEから糖鎖を外してアレルギー反応を抑える実験を行い、濃度依存的にアレルギー反応を抑えられることを示している。
結果は以上で、この方法で完全に反応を抑制できるところまで行っていないが、命にも関わるアナフィラキシー制御を可能にする面白い方法が開発されたと思う。しかし、こんなことが今ようやくわかったのかと、驚きの論文だった。
2020年5月31日
18世紀、生命現象を物理的因果性と比較しながら考えるNatural Historyが発展し、この延長に19世紀のダーウィンが生まれるが、Natural Historyの生命についての結論は「自然目的により組織化されている点で、物理的因果性とは異なる有機体とするカントの有機体論」で止まったように思う。カントが終着点とは、哲学も科学も渾然としていた時代に見えるが、実際にはカントは科学者といってもいいほど科学への造詣が深かった。
ダーウィンは、この科学とは相容れないように思える自然目的を、彼の進化アルゴリズムで説明した、すなわち目的論を排除したわけだが、進化を考える時に目的や機能といった因果性を頭の中から排除することは難しい。というのも、現在の生物のHistoryを考える時、現在の姿が目的になるので、それを排除するのは簡単でない。その意味で、その過程を科学的に説明できるなら、目的や機能といった、厳密に言えば非科学的(?)概念を積極的に取り入れて研究することは問題ないと私は思う。
今日紹介するシカゴ大学からの論文は、ヘモグロビンが現在のα2β2の4量体をなぜ取るようになったのか、現在の形質を目的として過去の分子過程を再構成しようとした論文で5月28日号のNatureに掲載された。タイトルは「Origin of complexity in haemoglobin evolution (へモグロビン進化過程での複雑性の起源)」だ。
ヘモグロビン(Hb)は4量体を取ることで、酸素の結合と解離を効率よく行えるわけだが、遺伝子配列上の進化という点から見てしまうと、酸素結合性のサイトグロビン、グロビンE、そしてミオグロビンなどの酸素結合性分子と同じ先祖から進化した分子ファミリーとして納得して終わる。
この研究では、ミオグロビンは多量体を形成しないのに、なぜHbは4量体を形成できるのかという問題に置き換えて、遺伝子配列の条件を検討している。すなわち、現在の分子を目的として、その機能を達成するために必要なアミノ酸の変化を追跡しようとしている。通常この目的のためには、現存の多くの生物の中から中間形を探し出し、その遺伝子配列を決定するのがこれまでの方法だったが、この研究では現存のHbの祖先形をコンピュータで推察して、そのタンパク質を再構成し、機能を調べるという、かなり大掛かりな手法を用いている。
まず配列からミオグロビンとHbの先祖型、HbαとHbβ共通の先祖型、そしてHbα、Hbβそれぞれの先祖型のアミノ酸配列を推定して、その情報から先祖型分子を再構成している。このインフォーマティックスについてはちんぷんかんぷんだが、驚くことにミオグロビン先祖型はモノマーだけ、α、βそれぞれの先祖型は4量体を形成できることを示しており、このような手法がかなり進んでいることをうかがわせる。
さらに驚くのは、αβ共通の先祖型を再構成すると、2量体は作れるが、4量体は形成できない。すなわち、モノマー、ダイマー、テトラマーという機能的進化が再構成されている。
あとはこの先祖形の物理化学的性質や構造を詳しく解析、どのアミノ酸を変化させると新しい機能を獲得できるか調べ、まずミオグロビンとの共通先祖形のInterface1と呼んでいる部位に一個突然変異が入ると、酸素結合性はそのままで2量体形成が可能なHbの先祖形が生まれ、次にInterface2と呼ばれる場所にいくつかの変異が蓄積することで、4量体形成が可能になる。これに伴い、酸素結合能は低下するが、これによって酸素を結合したり遊離することが可能になるというシナリオだ。
分子進化というとどうしても配列レベルでの研究を読むことが多かったが、ここまで機能の再構成が可能な面白い実験進化学の領域が出来上がっていることに感心した。
2020年5月30日
APOEには3種類のアイソフォームが存在し、それぞれのアイソフォームは様々な形でアルツハイマー型認知症に関わっている。例えばAPOEのε4アイソフォームはアルツハイマー病のリスクを10倍以上高めることが知られている。一方、稀なアイソフォームだが、クライストチャーチ型変異を持つAPOEによって、アミロイドがどれほど蓄積しても認知症状が出ない老人がいることを示した論文を以前紹介した(https://aasj.jp/news/watch/11677 )が、場合によっては認知症リスクを下げる。
今、私が最も期待している新型コロナの研究分野は、感染や重症化の遺伝的リスクについての論文だ。当然のことながら組織適合抗原については論文が出始めたし、欧米でのゲノム解析が進んでいるので、多くのリスクファクターがわかるのも時間の問題だろう。これによって、個人の感染や重症リスクをあらかじめ知ることができることは大きい。ただ論文として現れるにはまだ少し時間がかかるようだ。
それでもゲノムデータの揃っているコホート研究から断片的な論文は発表されている。例えば50万人規模の英国バイオバンクに登録された人たちも当然コロナに感染し、600人近くの人がPCRで陽性と診断されている。この人たちのAPOEのアイソフォームを調べると、様々なリスクファクターを補正した後でもE4アイソフォームを持つ人がオッズ比で2.5倍ぐらい高いことが示された。これは、すでに認知を発病した人を除いても同じなので、APOE4が感染しやすさのリスクであることを示している。
残念ながらデータはこれだけで、今後診療データを集めた検討が行われることで、重症化などについても相関が見えてくるだろう。ただ、感染性が免疫反応と関わるとすると、E4が免疫を抑えることになるが、ちょっと違和感がある。
実際ほとんど同じ時にNature Medicineにオンライン出版されたロックフェラー大学からの論文では、悪性黒色腫への免疫反応はE4アイソフォームを持つ人の方が高いという結果が示されているので最後に紹介する。
このグループはAPOEのアイソフォームが異なるモデルマウスを用いて、E4の生理活性を調べていたようだ。一つの試みとして、マウスメラノーマを注射してE4と E2アイソフォームのマウスを比べると、E4マウスでは腫瘍の増殖が強く抑えられる。そして、この原因が腫瘍内での免疫系細胞の数に反映されていることを明らかにしている。すなわち、E4マウスでは腫瘍内のキラー細胞やNK細胞の数が高まっている。すなわち抗腫瘍免疫について言えば、明らかにE4アイソフォームの方が良い効果がある。
これが特殊なマウスモデルのせいでないことを示すため、今度はメラノーマ患者さんのデータベースから生存期間とAPOEアイソフォームとの相関を調べると、E4(E3も)アイソフォームは長期間生存するチャンスが大幅に高まっている。
これが免疫系の効果であることは、E4アイソフォームの人ではチェックポイント治療の効果高いことからも推察される。
このように、少なくともガン免疫で腫瘍内への細胞浸潤と腫瘍障害で見たときは、アルツハイマーリスクであるE4も捨てたものではない。おそらく、新型コロナに対してももう少し精密な研究が進めば、より免疫との関わりが見えるだろう。いずれにせよ、早く大規模ゲノム検索結果が発表されるのを心待ちにしている。