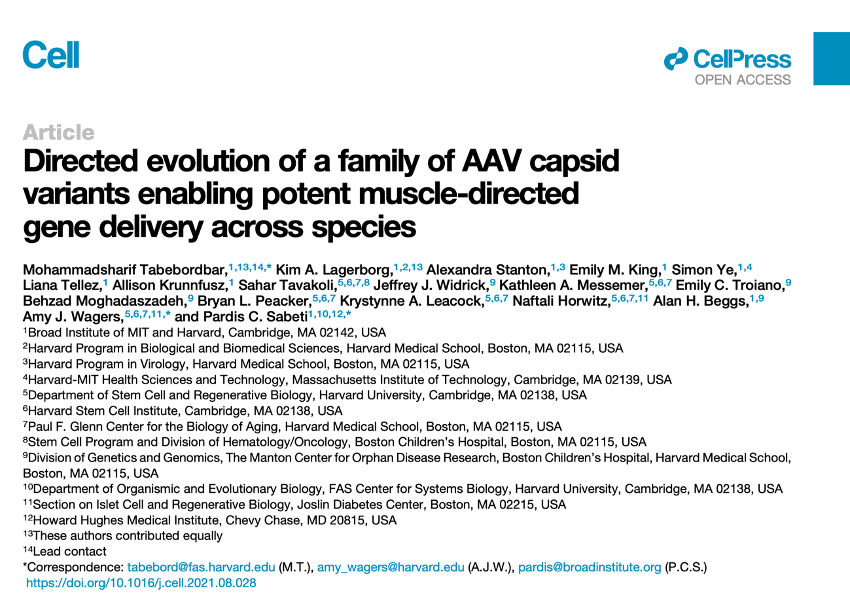2023年5月2日
動物のゲノムを世界中の研究者が協力して研究することで、動物の進化、そして最終的には人間を作る条件を明らかにしようとするZoonomiaプロジェクトが進んでいる。今週号の Science はこのプロジェクトに関わる研究論文を特集として掲載していた。
その中で私の目を最も引いたのがMITとエール大学から共同で発表されていた、ヒトだけで欠損しているゲノム変化を特定し、それが人間の進化にどう関わるか調べた壮大な研究で、4月28日号 Science に掲載された。タイトルは「The functional and evolutionary impacts of human-specific deletions in conserved elements(ゲノム保存領域内のヒト特異的欠損の機能的進化的インパクト)」だ。
これまでさまざまな動物と比較することでヒト特異的ゲノム変化を探る論文のほとんどは、サルには存在せず、人への進化で初めて現れたゲノム変化を追跡してきた。しかし、失うことで新しい性質が得られることも当然考えられるので、ヒト特異的欠損も存在するはずだが、解析が難しいのかあまり追求されてこなかった。
今日紹介する論文は、Zoonomiaゲノムデータをフルに活用して、ゲノム内のほとんどの動物で保存されている領域の中で、ヒトだけに見られる欠損をまず特定している。その結果、1ベース欠損から10ベース以上の欠損まで、なんと1万を超える欠損箇所が見つかった。ほとんどの欠損はエクソン間や遺伝子と遺伝子の間の領域で見られる変異で、その半分は1ベース欠損なので、よく見つけるものだと、そのインフォーマティックスに感心する。
次にこの変異の機能を調べるためさまざまなインフォーマティックスの手法を用い、
知能障害、統合失調症、うつ病などGWASにより特定される脳疾患の1分子多型と重なる欠損が見つかる。
欠損は、遺伝子調節領域に多く、支配される遺伝子の発現は脳に高い。
これらはインフォーマティックスを用いて明らかにできることで、転写活性の変化や、組織特異性については実際の細胞や個体で調べる必要がある。
ここではチンパンジーゲノム領域と、それに対応するヒト特異的欠損を持った領域DNAを何百箇所について合成し、合成されたすべてのライブラリーを異なる組織を代表する細胞株に導入、それぞれの領域により転写されたRNA量を測定することで、ヒトへと分化した時の転写活性の変化をを調べている(これほど大掛かりな実験が可能になっているのを見ていると、時代が変わったことを実感するが、この結果多くの領域の転写活性をチンパンジーと人で比べることができた。
結果だが、多くの変異は転写活性分子との結合を高めたり、あるいはリプレッサー分子の結合を抑えることで、ネットとしては転写が上昇する方向に変化させることを示している。このあとは、それぞれの領域の変化による形質変化を調べることになるのだろうが、この研究では入口として、2種類の遺伝子で、確実に転写活性がヒト型変異で変化する事を示すのに費やしている。
まず脳の発生にも関わる脱リン酸化酵素PPP2CA遺伝子調節領域の6bp欠損が、クロマチン構造を変化させ、レポーター遺伝子の転写を高める事を確認している。
次に、細胞外マトリックスの発現を調節するLOXL2を取り上げ、ヒトだけに見られる1bp欠損により、リプレッサー結合が阻害され、発現が高まることで、下流のミエリン化に関わる分子が活性化し、神経伝導が高まる可能性を示唆している。
以上が結果で、簡単に紹介するのが申し訳ないほどの力作だが、この変異が実際の形質をどう変化させるのかについては今後の研究を待つ必要がある。いずれにせよ、ここまで整理がつくと、関係する分子を研究している人たちの道標になる事間違いない。失う事で得られるものの探索はロマンチックだ。
2023年5月1日
原因不明の肺線維症は、今もなお原因はおろか治療する方法も見つかっていない。自ずと治療は対症療法になり、今の所、病気の進行を止めるところまでは至っていない。私も、3年前に医学部の同級生をこの病気で失ったが、毎日論文を読んでいても、適切なアドバイスができなかったことは辛い思い出だ。いずれにせよ、原因のわからない肺線維症(IPF)では、肺が障害を受けたと勘違いして、ブレーキなしの修復機構が働き続けるのではと考えられている。
今日紹介するヒューストン大学からの論文は、IPFの上皮細胞を移植することで、肺線維症をホストに誘導できることを示し、さらには線維化を誘導できる異常上皮細胞の培養に成功した研究で、4月26日号 Science Translational Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Cloning a profibrotic stem cell variant in idiopathic pulmonary fibrosis(突発性肺線維症の炎症誘導性の変異幹細胞のクローニング)」だ。
なんといってもこの研究のハイライトはIPF患者さんの肺組織から、試験管内で増殖する上皮細胞を樹立した点だ。通常、病気によりエピジェネティックな変異が起こっていても、培養すると正常と差がなくなることが多いのだが、今回樹立できたIPF肺上皮細胞は、免疫不全マウス皮膚に移植すると、移植局所に強い繊維化を誘導することがわかった。すなわちIPF誘導活性を保ったまま上皮を培養することに成功した。
次に、まださまざまな細胞が混在するこの培養から、この論文でCluster Bバリアンとと呼んでいる細胞を分離し、この集団が線維症を誘導できる責任細胞であることを特定するとともに、試験管内で肺の線維芽細胞と共培養することで、線維芽細胞の増殖、コラーゲン分泌を誘導することを示し、試験管内の肺線維症誘導モデル系を作るのに成功している。
次に、このIPFで変化したと考えられるCluster B バリアントに相当する細胞がIPF患者さんに存在するのか調べ、同じ性質を持つ細胞がIPF患者さん特異的にみられること、中でも肺下葉に濃縮していることを明らかにしている。
次に他の疾患とsingle cell RNA sequencingを用いた比較を行い、同じ線維化を伴う閉塞性肺疾患とはメカニズムが異なる一方、ブレオマイシンによる肺線維症ではほぼ同じ分子細胞的メカニズムが働いている事を示している。
この結果は、IPFもブレオマイシン肺線維症も、おそらく共通の要因でクラスターB細胞を刺激、リプログラムして、炎症誘導性を誘導していることを示唆している。従って、ブレオマイシン誘導モデルは、今後上皮のリプログラムを誘導する条件を調べるために有用であることを示している。
最後に、リプログラムされた上皮細胞の線維化誘導能を抑えることのできる薬剤を探索し、これまでブレオマイシンによる肺線維症を抑制できることが知られているEGF受容体阻害剤が高い効果を示すことを明らかにしている。
以上が結果で、ともかく肺線維症を誘導できる培養細胞を確立できた点が一番のハイライトで、肺線維症研究に新しい方向性を示した。もちろん治療にはまだまだかかると思うが、優れた研究システムが完成できたのではと期待している。
2023年4月30日
アルツハイマー病(AD)治療としてアミロイドβに対する抗体治療が認可されたが、もう一つの重要課題は、Tauの凝集と伝搬を標的にする治療薬の開発だ。最近紹介したように、Tau凝集に至るメカニズムを解析して、それに関わる分子標的を見つけ出し、薬剤を開発する方向の研究が、これを達成するための王道のように思えるが、最もストレートなのはTauの発現量を抑えてしまって、凝集を抑えるという戦略だ。
驚くことに今日紹介する英国 College of London からの論文は、この方法によるAD治療の第1相臨床治験についての報告で4月24日 Nature Medicine にオンライン掲載された。タイトルは「Tau-targeting antisense oligonucleotide MAPT Rx in mild Alzheimer’s disease: a phase 1b, randomized, placebo-controlled trial(Tauを標的にしたアンチセンス核酸治療MAPTRxを用いた軽度アルツハイマー病患者さんの治療:第1相無作為化偽薬治験)」だ。
MAPTRxはベンチャーファーマIONISにより開発されたTau遺伝子に対するアンチセンス核酸で、細胞内でTauのmRNAを破壊し、タンパク質翻訳を低下させる。すでに髄腔内投与により、Tau異常マウスの寿命を延ばせることが明らかになっており、これで前臨床はクリアされたとして、今回第1相治験に進んでいる。
患者さんはさまざまな量のアンチセンスRNAあるいはプラシーボを脊髄腔内へ注射で投与している。髄腔投与という困難な治験なのに、プラシーボ群を設定し完全を期しているのは、意気込みを感じる。髄腔への投与回数は、4週間に1回(総数4回)、あるいは12週間に1回(総数2回)で、その後35周まで経過を観察している。脊髄腔内注射は、それだけでも頭痛などさまざまな副作用を伴うので、この第1相治験ではテスト群で95%、プラシーボ群で75%の軽度から中程度の副作用が認められる。しかし、重症の副作用は13週間にわたって認められなかったので、第1相で安全性は確保できたと結論している。
この治験の目的の一つは、髄液中や血液に注入した核酸が検出できるかどうかだが、注入量に比例して、2−4時間をピークとして注入核酸を検出することができる。
そして、最も知りたいMAPTRx投与で髄液内のTauが低下するかどうかだが、60mg投与群でTauの髄液濃度が60%以上低下する。また、凝集するリン酸化Tauも半分近くにまで低下させられる。
以上が結果で、髄液中のTauが低下したとしても、Tauの蓄積を抑制できたのかはこの治験ではわからない。ただ、動物実験から考えて、ある程度期待できると考えているようだ。しかし、35週まで観察して、認知機能については、おそらくある程度のデータはあると思うが、全く記載していない。おそらく認知症上の軽い患者さんを選んでいるからで、判断にはさらに時間がかかるのだと思う。それでも、Tauのレベルが期待以上に減少していることを考えると、Tauの翻訳を止めるという最も単純な発想の治験がうまくいったことになる。
脊髄腔注射を繰り返すことは患者さんの負担になるのと、ADでは治療を一生続ける必要があることを考えると、おそらく新しい髄腔内長期投与の方法開発が次の重要な課題になるように思う。
2023年4月29日
Nature Collectionというサイトがあり、特集として選んだ様々なテーマについてエディターやライターの記事が集められている。いつも目を通しているわけではないのだが、たまたまウェッブサイトを見ていたら、3月のNature Collectionとして慢性腎臓病(CKD)が特集されており、掲載された10編の総説の中に、最近注目すべきCKD研究がまとめてあったので紹介することにした。タイトルは「Chronic Kidney Disease:Highlights from research(慢性腎臓病:研究のハイライト)」で、サイエンスライターのMichael Eisensteinが担当してまとめている。
ただ、この記事に行く前にAmanda Keenerにより書かれた「The surprise blockbuster(ブロックバスターの驚き)」について少しだけ紹介しておこう。この記事では最近糖尿病治療として広く使われるようになったSglut2阻害剤が、糖尿病だけでなく、CKDの腎臓を守る働きがあることが明らかになり、様々な腎疾患や他の病気への使用が拡大しつつあることがレポートされている。Sglut2は腎臓尿細管でグルコースとナトリウムの再吸収を抑えるのだが、このHPで紹介したように、他の分子標的にも効果を持つことが示されており、一種魔法の薬としてさまざまな問題に利用できることがわかってきた。この結果、スタチンや、血圧硬化剤に次ぐ製薬業界のブロックバスターの地位を確立する勢いで、今後も注目して紹介していきたい。
さて、Eisensteinの記事では、5編の論文が紹介されており、それぞれについて紹介する。
1)Nature Med. 28, 1412–1420 (2022). コロンビア大学からの論文で、大規模コホートからCKDと相関が見られるゲノム多型を合わせたリスク指標を開発し、これによりCKDリスクのオッズ比が4-8というハイリスクグループを選別できることを明らかにしている。すでに述べたようなCKD治療の進展を考えると、リスクを把握することの意義は大きい。
2)Sci. Transl. Med. 14, eabj4772 (2022).:わが国の西中村さんなど、ヒトiPSから腎臓組織を形成する方法が確立してきたが、このハーバード大学からの論文では、同じように調整した腎臓のオルガノイドをシスプラチンで処理してCKDを誘導し、障害に対応する修復機構をオルガノイドで研究できること、またこの系を利用するとこの修復機構を促進する薬剤の発見に成功している。
3)Nature Immunol. 23, 947–959 (2022):ペンシルバニア大学からの論文で、尿管を閉塞させて誘導される腎臓の繊維化機構についてsingle cell RNA sequencingで解析し、尿細管から分泌されるケモカインにより好塩基球が浸潤することが繊維化に大きく寄与していることを明らかにしている。このメカニズムに基づき、好塩基球を除去する処理を行うと、繊維化を防ぐことができることから、臨床研究が待たれる。
4)Sci. Transl. Med. 14, eabj2681 (2022):バージニア大学からの論文で、CKDの炎症にSphingosin-1-phosphate(S1P)が深く関わることと、そのメカニズムを明らかにし、S1P分泌に関わる分子Spnsを特定している。そしてスクリーニングにより得られたSpns阻害化合物が腎臓の炎症を抑制できることを示している。このプロセスはかなり腎臓特異的なので、新しい治療法の開発に直結する。
5)N. Engl. J. Med. 385, 2507–2519 (2021).:インディアナ大学からの論文で、CKDの患者さんは高血圧を併発することが多いので、サイアザイド系の利尿剤クロルタリドンを進行したCKDに投与する無作為化臨床治験を行い、コントロールが難しかった高血圧を抑えることができたという論文だ。これについては、こんなことが行われていなかったのかという印象が強いが、ステージごとにまだまだ最適の標準治療を開発できる可能性があることがよくわかる。
以上が結果で、CKDを透析や腎移植を必要としないステージでコントロールする医療は今後急速に発展することが期待できる。
2023年4月28日
2016年8月、ガラパゴスのグンカンドリにGPSと脳の活動を拾うため、両半球に脳波測定器を装着して、 飛行中に両方の脳半球が完全な睡眠状態に入るかを調べた研究を紹介したことがある(https://aasj.jp/news/watch/5615 )。事実、寝るために高い高度に飛び上がった後、上昇気流をつかむと完全に寝るようだ。すなわち、寝るための行動がしっかりパターン化している。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、まさにこの逆で、長期間休むところのない大海で狩りをするゾウアザラシは、潜水の最後に徐波睡眠に入り、REM睡眠でバランスを失った後覚醒を始めて浮き上がることを示した研究で、4月21日号の Science に掲載された。タイトルは「Brain activity of diving seals reveals short sleep cycles at depth(潜水中のゾウアザラシの脳活動は深海での短い睡眠サイクルであることを明らかにした)」だ。
グンカンドリと比べるとゾウアザラシは大きいので、装置は大きくていいが、しかし長期間海水や水圧に耐える必要がある。実際、頭全体を覆う脳波計と、紡錘のロガー、発信装置という大がかりな仕掛けをゾウアザラシに装着し、長期間の記録に成功している。
ゾウアザラシは陸で休んでいるときはほとんど寝ている。しかし、海に入るとほとんど睡眠時間が減っていき、一回30分ほどの潜水時に眠ることになる。この潜水時の睡眠は同じようなパターンをたどるが、300m近く潜る30分程度の潜水では、200m潜ったぐらいから浅い徐波睡眠。続く深い所徐波睡眠の後に、REM睡眠が現れる。面白いことに、徐波睡眠中は泳ぐ姿勢を保っているのだが、深い徐波睡眠が途切れる頃から、急に仰向きに反転し背泳ぎのような姿勢になった後、REM睡眠で身体の筋肉が動き始めるとらせん状にグルグル回転しながら落ちていく。そしてREM睡眠が終わると、覚醒して正常の泳ぐ姿勢を回復し、水面目指して急上昇するという一連の過程が明らかになった。
深く潜ったときは同じようなパターンをとることが多いが、岸近く潜水深度が浅い場合は、REM睡眠が現れないことが多い。
以上が結果で、
外洋に出たゾウアザラシはほとんど睡眠をとらないこと、
睡眠のほとんどは潜水中に短く済ませていること、
潜水の睡眠では徐波睡眠だけでなくREM睡眠も存在すること、
一方、陸上や棚のある海岸では、寝るときはもっぱら陸に上がったときであること
などを明らかにしている。
ライオンのように四六時中寝ているように見える動物がいる中で、睡眠がこんなに短くていいのだろうかと心配になるが、草食動物は体重が増えるほど睡眠時間が短いことが知られているようだ。従って、どんな状況でも、睡眠を少しでも確保するシステムが進化していることに感心すべきだろう。
2023年4月27日
タスマニアデビルの顔に発生するガン(DFT)についてはこれまで4回も紹介してきた。これまで注目してきた理由は、DFTが個体から個体へと感染する致死的なガンという驚くべき性質を持っているからだ。これまで、細胞レベルで感染できるがんについてはいくつか報告されているが、現在もなお感染が進行中で、研究が進んでいるケースはDFTだけだ。さらに、最初1996年にDFT1が発見されたあと、2014年には独立して新しい地域にDFT2が発見されている。
通常のガンももちろん進化を繰り返すが、個体の死亡によってその進化は一回限りで終わるが、DFTは個体から個体へと感染するため、進化が終わらない。どこまでガンがホストの環境に適応し、どのような形質変化が起こるのか、そしてどこかで進化が止まることがあるのかなど、通常では難しい研究が可能になっている。
今日紹介する英国ケンブリッジ大学からの論文は、DFT1、DFT2それぞれ78種、41種を集めて全ゲノム解析を行いDFTの発生や進化について詳しく解析した研究で、4月21日号 Science に掲載された。タイトルは「The evolution of two transmissible cancers in Tasmanian devils(タスマニアデビルに発生した2種類の感染性ガンの進化)」だ。
実験としては、独立したガンのゲノムを解読し、それぞれの関係を調べた研究なので、最終的に明らかになった結果について箇条書きでまとめおいた。
DFT1とDFT2は全く独立したガンで、ガンの変異タイプから、人為的要因(たとえば環境汚染など)や気候要因などは考えにくいので、自然発生したものと考えられる。とすると、同じようなガンは、タスマニアデビルの進化過程で何回も発生し、タスマニアデビルはそれを乗り越えてきたと考えられる。
ゲノムの系統樹から、DFT1が発生したのは1986年と推定されるが、発見されるまでに10年を要している。一方、DFT2の発生は2011年ごろと推定され、発見まで3年を要している。DFT2の方は発見が早いので、悪性化と感染性の関係を結論できないが、DFT1について、その地域でのガンの報告が全くなかったことから、まず感染性のガンとして始まり、その後ホストに適応する過程でガン化したと考えられる。
これまでDFTの発生に関わるガンのドライバーについては決定的な結論はない。この研究では、おそらくゲノム上の大きな変化によりDFT1では転写因子LZTR1、DFT2では増殖因子受容体PDGFRαのコピー数が変化して感染性と増殖優位性が発生したと考えている。
それぞれのガンでは、多くのタイプの変異が蓄積し続けており、またホストに適応して変異が選択されていることがわかる。この過程で、よく知られた様々なガンのドライバーの変異が進み、ガンがさらに悪性に変化していることがわかる。現在まで、DFT1、2とも変異数は上昇し続けており、進化の果てがあるのかについてはわからない。
進化の過程で、DFT2はDFT1より増殖速度が速くなっており、この結果DFT2は新しく発生したにもかかわらず、あらゆるタイプの変異数が多い。ただ、増殖速度の変化だけでこれが起こったわけではなく、修復異常やトランスポゾン活性化などは、DFT2で見られている。今後もDFT1、DFT2の違いが維持されるのかどうか興味深い。
一頭の個体から分離したDFTのかなりの割合で、2種類以上のクローンが特定できることから、複数のクローンが共存して感染するケースは多い。
以上が主な結果だが、タスマニアデビルでDFTが稀なイベントが起こったのではなく、今後も新しいDFTの発生が考えられるということと、30年近く経っても進化の果てには到達できていないことが最も重要な結論になる。
2023年4月26日
皮膚の損傷治癒というと生体内で経過が詳しく追えることから、高等動物の再生研究では最も進んでいると思っていたが、今日紹介するロックフェラー大学、Fuchs研究室からの論文を読んで、まだまだ解析を必要とする重要問題も存在していることがよくわかった。タイトルは「A tissue injury sensing and repair pathway distinct from host pathogen defense(病原体に対する反応とは異なる組織損傷の感知及び修復過程)」で、4月24日 Cell にオンライン掲載された。
様々なストレスによる自然炎症というスキームを知ってしまうと、入り口は様々でも結局同じストレス、炎症反応が誘導されると思い込んでしまうのだが、「損傷の感知特異的に誘導される損傷治癒も存在するのでは?」と問うたのがこの研究だ。
皮膚に上皮が削れる小さな傷をつけたとき、傷の縁に発現する遺伝子を調べ、想定外の分子IL24が損傷後1日目で、特に上皮幹細胞に強く発現することを発見する。無菌動物や免疫不全動物でも同じ反応が起こることから、一般的な自然免疫経路ではなく、IL24刺激により誘導されるSTAT3分子により引き金が引かれる過程であることを発見した。
そこでIL24を欠損したマウスを作成すると、全く正常に発生・成長するが、外傷による損傷治癒が4日ぐらい遅れる。組織的にこの遅れを調べると、傷の縁での上皮幹細胞の増殖が遅れるだけでなく、損傷部位の線維芽細胞の増殖が抑制され、さらに血管新生も抑えられる。また、同じ遅れは、IL24を上皮だけで欠損させた動物でも起こる。
次に損傷によりIL24を誘導する刺激を探していくと、損傷部位に生じる低酸素刺激によりHIF1αが活性化され、これがIL24の誘導に関わること、さらにはIL24シグナル自身もHIF1αと協調して、誘導されたIL24刺激が継続するように働いていることを明らかにしている。
以上の結果は、皮膚の損傷自体が低酸素、そしてIL24を誘導して、損傷治癒を組織化していることがわかる。損傷治癒自体は、この経路が存在しなくても起こるのだが、時間がかかる。
主な結果は以上だが、面白いのはIL24がグルコーストランスポーターであるGlut1の発現を高めて、グルコースからピルビン酸、乳酸への嫌気的過程を誘導している点で、ガンと同じように損傷部位の代謝をリプログラムして、変化に備えるところまでIL24が受け持っているのがわかる。また、マクロファージを、外来の光源処理に備える態勢をとらせることも面白い。すなわち、多くの過程を指揮している。
最終的な損傷治癒は起こるが、IL24自体で皮膚全体の増殖活性を高めることも示されており、ひょっとしたら褥瘡などの医療や美容にも使える気がする。読んでみると、特に驚くことはないが、重要な発見だと思う。
2023年4月25日
オメガ脂肪酸とかDHAといった必須脂肪酸は、一般の人にも知名度が高い。勿論、リノール酸から合成されるオメガ6はアラキドン酸、オメガ3はEPAを経てプロスタグランジンなど炎症調節の主役分子の材料として極めて重要だが、有名になった最大の理由は、脳の働きをよくするという様々なコマーシャルのおかげではないかと思う。
事実、脂質異常を伴う自閉症スペクトラム(ASD)が存在するし、またASDの方では動脈硬化などの発症率が高い。ただ、極めて希な遺伝異常を除くと、脂肪代謝の変化と脳機能を結びつけるのは簡単ではない。
今日紹介するオーストラリア、クイーンズランド大学を中心とする多施設からの論文は、主にASDの児童について行われている徹底的なコホート研究で得られた血清中の網羅的脂質分析結果を、症状やゲノム解析と相関させ、ASDで脂質代謝異常が起こっている可能性と原因を探った研究で、4月号の Nature Medicine に掲載された。タイトルは「Interactions between the lipidome and genetic and environmental factors in autism(自閉症での網羅的脂質解析データと遺伝的、環境的要因の相互作用)」
現在、様々なところで、ゲノム、エピゲノム、遺伝子発現に加えて、蛋白質や脂肪の網羅的解析が行われ、膨大なデータの中に見られる相関から、病気を理解する研究が進んでいる。この研究ではオーストラリアで進むASDのコホート研究を材料に、脂質データの解析方法を探ったのがこの研究だ。
我々も受けるような検査では、ASD児はコレステロールが低い傾向がみられるがオメガ6など限られている。一方で、睡眠障害で相関をとると、DHAが上がってくる。一方、知能ではDHAのようなオメガ3ではなく、オメガ6脂肪酸との相関がはっきりしている。
ただ、血中の脂質は、遺伝、食事、環境、薬剤、年齢、性別など様々な要因で変化する。この研究では統計学の苦手な私には理解出来ないレベルの様々な情報処理方法で、この相関の実際の原因について探っている。
あらゆるデータを省略してこのグループの結論だけ述べると、
生活習慣などの要因は大きいものの、ASD、知能、睡眠障害の遺伝的相関と関連して現れる脂質異常は確かに存在する。
しかしASDでDHAなどが低下するのは、ASDによる生活習慣の変化が先で、その結果、肉の消費が減少したりする二次的な可能性が高い。
一方、睡眠障害や知能障害は、神経機能とは無関係の食生活の乱れに起因して、この結果DHA等が減少するだけでなく、さらに腸内細菌叢にもこの乱れが働いて、血中脂質異常が起こっている可能性が高い。
ただ、脂質異常の影響が有意なのは睡眠障害だけで、DHAが低下すると睡眠障害が起こっていると推計学的に結論できる。
以上のことから、児童の睡眠障害にリノレイン酸やDHAを摂取させる治療は有効性が期待できる。
血中脂質はあまりに複雑な要因で形成されるため、一筋縄ではいかないという結果だが、それでもこの藪をかき分けて進む情報処理方法が進んでいることに感心した。
2023年4月24日
まず Nature誌から提供されているURL(https://www.nature.com/articles/s41586-023-05964-2/figures/4 )をクリックして見てください。
この図は脳に少しでも興味のある人なら一度は見たことのある運動野が身体とどう繋がっているかの地図だ。左側が私たちが見慣れてきた地図で、脳の上に描かれたホムンクルスは、決してバランスが取れておらず、複雑な動きが必要な手や、口に多くの領域が割り当てられていることが表現されている。この図は、カナダの脳外科医ペンフィールドが、てんかん手術時に、これらの部位を刺激し、反応があった身体部位を書いている。論文は1937年発表だが、この図自体は1948年版とされており、まさに私が生まれた年で、私も医学部で初めて目にしてからずっとこの図と付き合ってきたことになる。
勿論ペンフィールド自身もこの図は一種のメモのようなものと言っているように、これをそのまま受け取ることの間違いは指摘されてきた。この疑問を精度の高い機能的MRI(fMRI)を用いた神経領域間の結合解析を用いて調べ直したのが、今日紹介するワシントン大学からの論文で、4月19日号 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex(体性-認知行動ネットワークが運動野のエフェクター領域と交互に存在する)」だ。
この研究の答えは、同じ図の右側に示されており、ペンフィールドマップと大きく異なっているのがわかる。一つは、直接身体につながるエフェクター領域の間に、認知と運動を調節する領域が交互に存在すること、そしてエフェクター領域が末梢を中心に体幹の方に向かって同心円的かつ対照に領域が分布していることがわかる。
研究では安静時に領域間の結合を調べるRSFCと呼ばれる方法と、決まった運動を指令して身体を動かしたときの運動野の活動の記録を組みあわせ、運動野各領域の機能を特定している。そして図に示すように、直接運動には関わらない領域がエフェクター領域を分断していること、この領域が注意や行動選択に関わるcingulo-opercular networkをはじめとする中枢ネットワークと強く結合するとともに、エフェクター領域とも結合していることを明らかにする。
すなわち、何らかの意志を持って、行動をプランするときの活動が、エフェクター領域に伝わる前に、このinter-effector領域に投射され、様々なエフェクター領域を一つの運動にまとめ上げるという構造を運動野が持っていることを明らかにした。
面白いのは、詳細な運動に関わる指や舌といった領域は、inter-effector領域から離れていることで、おそらく意志を持った行動は体幹へとまず伝わるような構造になっている点だ。勝手に思っているだけだが、手続き記憶により無意識に行われる運動と、意志を持って行われる運動もこのような構造でうまく分離されている可能性もある。
このような大きなマップが書き直されることは、一番重要なのは卒中などによる障害に対するリハビリ戦略だ。おそらく、発話に関わるような失語にも重要な地図になるような気がする。さらには、意図や意志といったプランに基づく運動支配の理解が重要なのがパーキンソン病なので、運動野のみならず感覚野も統合された正確な地図が描かれることを期待する。
2023年4月23日
筋ジストロフィーなど,筋肉に遺伝子を導入すれば治癒が可能な病気は多い。ただ、筋肉は体中に分布しており、それらの全てに遺伝子を導入することはそう簡単ではない。たしかに、アデノ随伴ウイルス(AAV)のように筋肉に効率に遺伝子を導入できるベクターは存在するが、筋肉特異的ではないのと、筋肉全体に導入すべくシステミックに遺伝子を注射すると、ウイルス中和抗体が出来て、繰り返し投与が出来なくなる。
これを克服すべく2021年、ハーバード大学でインテグリンを標的にするペプチドを表面に発現するMyoAAVと名付けられたAAVベクターが開発され、静脈注射でかなり筋肉特異的遺伝子導入が可能になった。そして、これを静注することで、全身の筋肉に遺伝子が導入できることも示された。
今日紹介するシンシナティ小児病院からの論文は、AAVではなく、導入遺伝子がホストゲノムに統合されるレンチウイルスを筋肉特異的に導入するベクターの開発で、4月18日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Enveloped viruses pseudotyped with mammalian myogenic cell fusogens target skeletal muscle for gene delivery(哺乳動物の筋肉融合分子を発現したエンベロップ型ウイルスによる遺伝子導入)」だ。
この研究ではコロナウイルスのようにエンべロップを持つウイルスVSVに注目し、筋肉発生時に筋肉同士が融合する過程を調節するMyomakerとMyomergerの2種類の分子を発現しつつ、VSV自身の細胞融合分子を欠損したVSV粒子を合成するパッケージャー細胞をまず作成し、この細胞にレンチウイルスベクターを感染させ、このウイルスがVSVエンべロップにパッケージできるシステムを開発している。
正直、ハーバード大学の論文と比べると、パッケージ法が複雑で、どうしても遺伝子導入効率は低い印象がある。さらに、Myomaker+Myomergerは特異性は抜群だが、筋肉が融合する段階でしか遺伝子導入が出来ない。そのため、筋肉に負荷をかけて肥大を誘導するとか、筋肉を傷害する必要がある。
しかし、レンチウイルスを用いているので、一度導入されると一生遺伝子発現が維持される。さらに、一部の筋肉幹細胞もこのウイルスで遺伝子導入が可能で、この結果、この幹細胞に由来する筋肉細胞は全て遺伝子が導入されることになり、筋ジストロフィーの場合、正常細胞が時間とともに増加することを期待できる。
実際、生後2週間の筋ジストロフィーモデルマウスに2週おきにディストロフィン遺伝子導入をすると、全身の筋肉で2−4割の筋肉にディストロフィンが発現し、機能的にも大きな改善を示すことが示された。
以上が結果で、導入効率という点ではMyoAAVに後れをとっているのと、最終的に問題になる心臓には全く導入できない点で問題がある。ただ、エンベロップ型ウイルスを細胞特異的ベクターとして使えることが示されたことで、今後はより効率の高い方法の開発、あるいは人工エンベロップなど様々な方向への発展が期待できる。おそらくワクチンと一緒で、いくつかの方法を組みあわせて患者さんの根治を目指すことになる気がする。