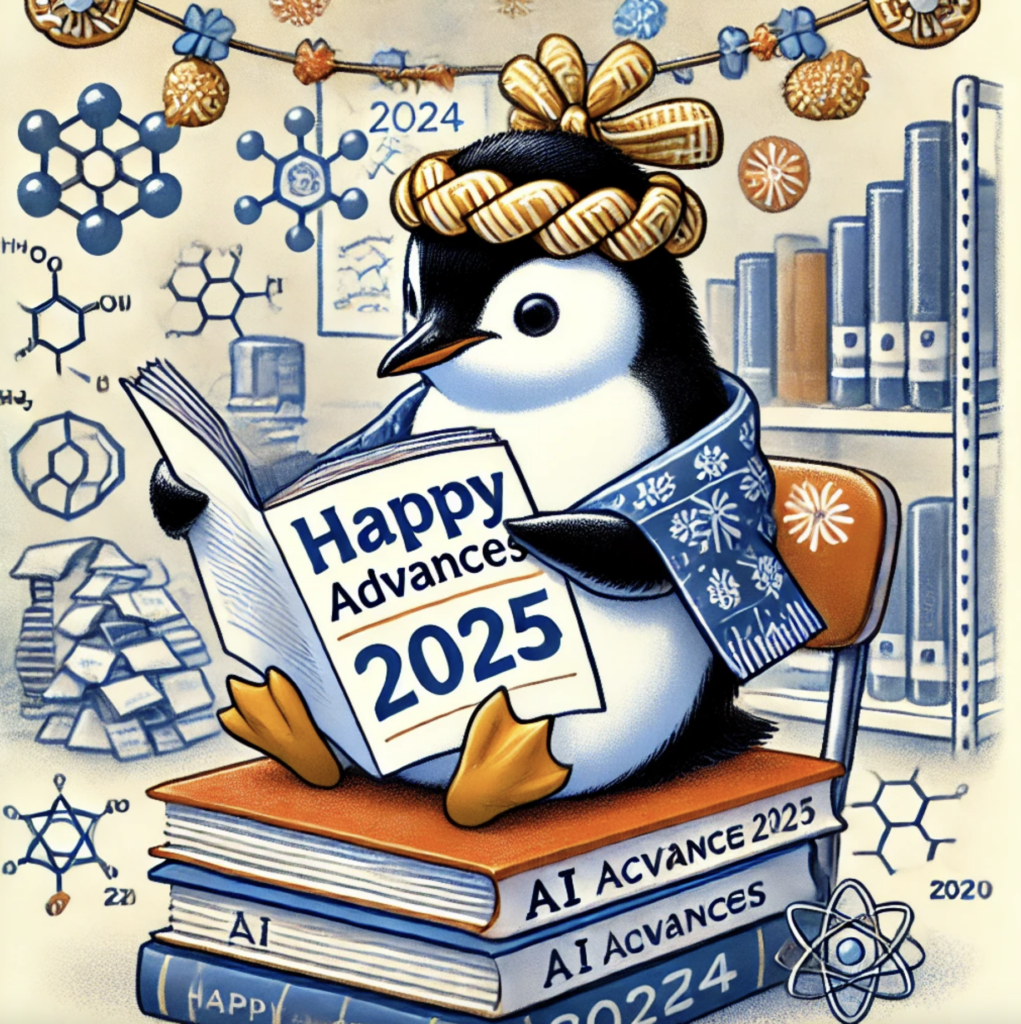皆様改めて明けましておめでとうございます。
さて、昨年アルツハイマー病研究分野での私の一押しは、store operated calcium channel(SOCC)の機能を調節する機構が異常 Tau により破壊され、細胞質のカルシウムバランスが変化することがアルツハイマー病 (AD) 発症に関わる重要な過程で、SOCC の調節に関わる細胞内マトリックスを再構築する薬剤が、AD の進行を止めることができることを示した、ベルギーからの論文だった。この論文が示すことは、小胞体 (ER) と細胞膜の間で Ca イオンをやりとりして局所細胞質の Ca を維持することの重要性だ。
今日紹介するコーネル大学からの論文は、樹状突起から飛び出たスパインでのシナプス刺激を樹状突起全体の興奮に拡大させる細胞膜と ER を統合している分子機構について明らかにした研究で、元旦に紹介するにふさわしい極めて重要な研究だと思って取り上げた。タイトルは「Periodic ER-plasma membrane junctions support long-range Ca 2+ signal integration in dendrites(ERと細胞膜の規則正しく繰り返す接合構造が樹状突起でCaシグナルを遠くへの伝達を支持している)」で、12月20日 Cell にオンライン掲載された。。
神経の樹状突起から飛びだした多くのスパインは他の神経とのシナプスを形成し、ニューラルネットでの重み付けの基盤を形成している。この論文を読むまで、スパインでの神経興奮は軸索での伝達のように膜の電位差により開くカルシウムチャンネル(voltage gated calcium channel;VGCC)をリレーして膜を伝わっていくのかと考えていたが、実はそう簡単な話ではなかったようだ。
この研究では、スパインに張り巡らされた ER が筋肉の収縮を統合する筋小胞体と同じような機能を持つのではと考え、まず樹状突起に存在する ER 構造を調べると、見事にレールのようにつながるネットワークができており、しかも細胞膜との間に VGCC や JPH3 と呼ばれる細胞膜と ER の結合を調節するタンパク質が、規則正しい間隔で並んだ接合部が形成されていることを明らかにする。
重要なことは、この接合部は細胞骨格分子とは全く無関係で、JPH3 分子により独自に決められており、JPH3 がノックダウンされると接合部は減少する。そして、JPH3 分子は接合部に VGCC を集めてくる役割を持っており、しかも神経活動が高まると、この接合部は多くの VGCC を集めてより興奮性の高い接合部へと変化する。
この接合部の構造的変化は、スパインの興奮により活性化される CAMKII が接合部に集まって誘導され、神経刺激はスパインの構造を変化させることが知られているが、スパインだけにとどまらず周りの細胞膜と ER 接合部まで変化が及び神経の反応性が決まることがわかる。
さらに、この接合部には ER から Ca を放出して細胞質の Ca 濃度を維持する RyR カルシウムチャンネルとともに細胞質の Ca を調節する SOCC とそれを ER にリンクさせる STIM2 分子も集まっており、興奮局所での Ca イオンのホメオスターシスを維持する複雑な仕組みが集まっていることがわかる。
最後にこの構造の意義を調べるため、1個のスパインを刺激したとき、ER 内での Ca 濃度がどのように変化するかを調べると、なんとスパインから20ミクロン離れた ER まで Ca 濃度の低下が及び、また刺激を繰り返すと ER の Ca 濃度変化が減衰しながらも繰り返されることを観察し、ER からのカルシウム放出に関わる RyR と VGCC が一緒になってスパインからの刺激を樹状突起を通して伝えていることが明らかになった。
以上が結果で、元旦早々難しい論文の紹介になったが、スパインでの刺激が、どのように神経全体で共有されるのかという素朴な疑問に、構造と機能から明確に答える素晴らしい論文だ。さらに、最初に紹介したベルギーの論文を考えると、明らかになった新しい機構は AD の理解にも必須だと思う。AD では神経細胞が失われることだけが問題にされるが、それ以前の神経過程では、シナプスからのシグナル伝達の低下が必ず見られるはずだ。この点でも、この研究の意義は大きい。