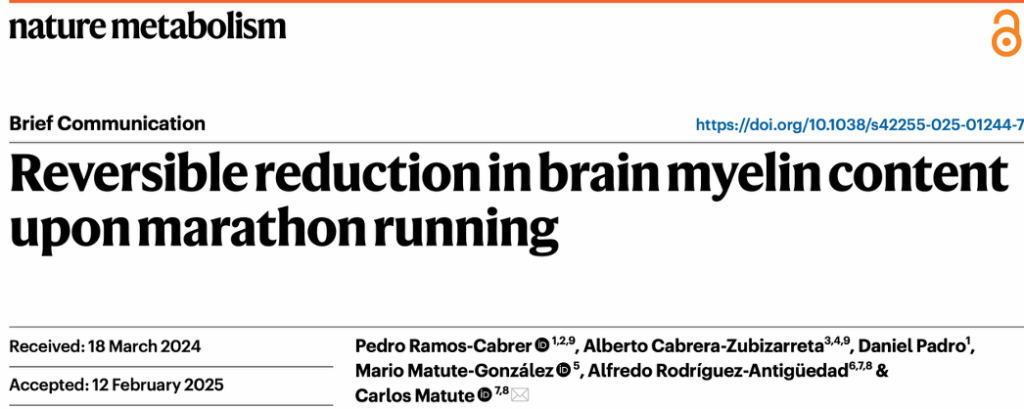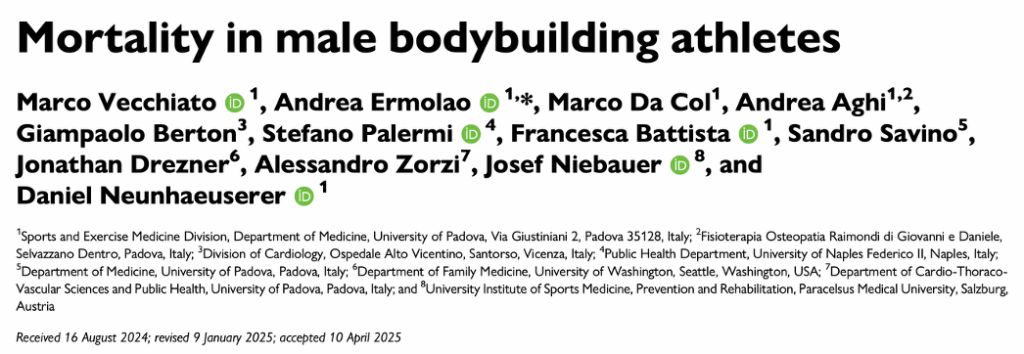2025年5月31日
しゃっくりの時に舌を引き出して治すのは迷走神経末梢枝を刺激して、横隔膜の感覚・中枢・運動神経回路を刺激し、しゃっくり反射回路を止めるのが目的だが、迷走神経が脳と身体をつなぐ神経回路の要であることを利用して、頸部の迷走神経主幹部の刺激を様々な病気の治療に使う試みが続けられてきた。その結果、難治性てんかんやうつ病にまで効果が見られるという臨床研究が発表されている。
この方法が病気の治療だけでなく、脳卒中のあとのリハビリテーションを促進することを完全にコントロールした国際治験が2021年4月の The Lancet に発表されたが(日経メディカル紹介記事:https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/lancet/202105/570285.html )、その効果は極めて高く驚いた。我が国では臨床で利用されていない可能性が高いと思うが、期待している。
今日紹介するテキサス大学ダラス校からの論文は、頸部迷走神経主幹部への刺激装置を小型化して、これを脊髄損傷による上肢のリハビリテーションの促進に使えないか調べた研究で、迷走神経刺激がますます拡大していることを認識できる研究だ。驚くことに、このような臨床研究を Nature が採択し、5月21日オンライン掲載されている。タイトルは「Closed-loop vagus nerve stimulation aids recovery from spinal cord injury(Closed loop迷走神経刺激は脊髄損傷からの回復を支援する)」だ。
オープンアクセスなので、実際の論文の図のURLを示しながら解説するが、対象は脊髄神経の一部が残っている不完全脊損の患者さんで、損傷後5年以内の19例について、同じ方法のリハビリテーションを行いながら、片方では迷走神経刺激を運動の状態に合わせて制御するclosed loop回路で刺激している(https://www.nature.com/articles/s41586-025-09028-5/figures/1 )。
刺激は完全にそれぞれの個人に合わせて、しかもリハビリテーション時の運動能力に合わせた刺激が提供される。ただ、刺激されているのは迷走神経なので、刺激に応じてアセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニンなどが脳内で放出されて、神経回路の可塑性が高まることを狙っている。
リハビリテーションも工夫されており、つまんだり、回したり、スティックを動かしたり、図で示した様々な運動を組み合わせるとともに、能力に合わせたテレビゲームを行って、回復を試すことができるようになっている(https://www.nature.com/articles/s41586-025-09028-5/figures/3 )。
この研究では18リハビリセッション、36日目に効果が調べられているが、専門家が評価してリハビリテーションの効果を様々な運動で確かめることができている。
最初の治験ではリハビリを行うときに、作業療法に関わる人がスイッチを押す方法で刺激が行われていたが、運動に応じて完全に自動化する機械もテストしている。その結果、コントロールと比べはっきりと腕と手の運動能力が高まっている。
一方で迷走神経を刺激することで心配される心拍数低下などの副作用が見られる心配はあるが、おそらく副交感神経興奮などで代償されるのか、それほど大きな問題にはなっていないようだ。
リハビリテーションに対するモティベーションを維持するのが回復への鍵になるが、人での問題、また患者さんの気力の問題などで、時間がたつとともにモティベーションは下がってしまう。しかし、自動化されたシステムで、しかもクローズループ回路を利用して個人に合わせた迷走神経刺激で回復が実感できれば、臨床的には大きな進歩になると思う。期待したい。
2025年5月30日
動脈硬化による心血管障害のリスクを下げる目的でフィブラート系薬剤が使われており、この薬剤が高脂血症を抑え、心臓死を抑える効果があることがいくつかのコホート研究で示されている。ただ、PPARαは遺伝子制御因子として本来の遺伝子結合部位に結合して下流の遺伝子発現を調節するだけでなく、transrepressive 作用と呼ばれる、他の転写因子の作用を抑える作用も持っているので、薬剤が効果を示すメカニズムをさらに明らかにする必要があった。
今日紹介するフランスリールにあるパストゥール研究所からの論文は、高脂血症により強い動脈硬化が生じるマウスで、PPARαの発現場所、そして作用モードを変化させられるようにして、PPARα活性化剤フィブラートの作用を調べた研究で、5月28日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Anti-inflammatory, but not lipid-lowering, activity of hepatocyte PPARα improves atherosclerosis in Ldlr-deficient mice(LDL受容体欠損マウスの動脈硬化は、PPARαの脂肪抑制効果ではなく、抗炎症作用を介して改善している)」だ。
この研究では、LDL受容体ノックアウトマウスに高脂肪食を与えて高脂血症を誘導している。このマウスにフィブラートを経口摂取させると、高脂血症が抑えられ、動脈硬化を抑えられる。
ただ、PPARα は様々な組織に発現しているので、フィブラートの効果が肝臓の PPARαを介して作用しているかを調べるため、アデノ随伴ウイルスに PPARα遺伝子を組み込んで、LDL受容体欠損と PPARα欠損を組み合わせたマウスに静脈注射することで、肝臓だけに PPARα が復元したマウスを作成し、これにフィブラートを投与している。
期待通りフィブラートは高脂肪血症を抑え、動脈硬化の発生をおさえることから、フィブラートの効果は基本的に肝臓の PPARα 活性化を介していることが明らかになった。
この研究のハイライトは、今度はこの系に脂肪合成に関わる転写因子としての PPARα 活性が欠損しているが炎症性サイトカインの分泌に関わる transrepressive 作用が残っている変異PPARα を、アデノ随伴ウイルスに組み込んで、肝臓に導入し、このマウスにフィブラートを接種させていることである。接種後、期待通りにIL-1βをはじめとする様々な炎症性サイトカインの発現が強く抑制されるが、それとともに一定程度高脂血症も抑えられ、しかも完全に動脈硬化のリスクを抑えることができた。
以上の結果は、フィブラートは、これまで疑うこともなく当然とされていた脂肪やコレステロール合成を直接抑える転写因子の作用を介するのではなく、他の転写因子の活性を変化させるtransrepressive作用により自然炎症を抑えることが主要因であることを示している。
これを確かめるために、肝臓の single cell mRNA analysis を行い、肝臓での炎症促進分子の発現が抑えられ、この結果、肝臓への白血球の浸潤と炎症誘導、血中 IL-1βの上昇が抑えられていることを確認している。
以上が結果で、PPARαが本来の脂質代謝調節とは独立して、Transrepressive作用を介して炎症性サイトカインの転写抑制に関わることがわかっていても、脂質代謝を標的としていると決め込んで臨床で使ってきたという、私たちの先入観に鋭く切り込んだ面白い研究だと思う。フィブラートの有用性については、何ら変わるところはないと思うが、炎症を中心に患者さんの経過を見ていくことが重要になる。
2025年5月29日
スピロヘータ科のボレリア属はライム病や回帰熱の原因菌で、マダニにより媒介されるライム病は現在もなお感染が見られる。多くは、他の動物により維持されていることが多く、ハイキングでマダニに噛まれて感染する。このように、ボレリアの多くはダニによる感染で、動物がダニとボレリアを維持するこが多いが、ダニからシラミに宿主を換えた回帰熱の原因になるボレリアは、人間特異的な病原菌へと変化した。
今日紹介する University College London からの論文は、ボレリアがダニからシラミにベクターを乗り換えて人間特有の回帰熱の病原菌へと変化した歴史を古代ゲノムから明らかにしようとした面白い研究で、5月22日号 Science に掲載された。タイトルは「ボレリア菌の古代ゲノムはシラミにより媒介される回帰熱の進化の歴史を明らかにする」だ。
埋葬されていた人間の骨髄からは人間以外の様々なDNAが検出されるが、その個体が生きていた時期に存在していることが確認できると、当時の様々な細菌のゲノムを調べる材料になる。例えば現在の歯周病に関わる菌のいくつかはネアンデルタール人の歯石から検出できる。
この研究ではその中からボレリアでシラミへとベクターを乗り換えた B.recurrentis のゲノムを探索し、鉄器時代から中世までのボレリアゲノムを再構成することに成功している。
現存のボレリアゲノム研究から、シラミに乗り換えた B.recurrentis ではゲノムのサイズが減少し、病原性が高まることが示され、大きなゲノム変化が起こっており、ダニからシラミへの転換を追跡するのは簡単ではなかった。この研究で、2200年前の英国鉄器時代のボレリアが再構成されることで、かなり正確な系統樹を書くことに成功し、最も近いダニ媒介の回帰熱菌 B.Duttoni と約5.6千年前に分離したことがわかった。
重要なことは鉄器時代のボレリアと、中世のボレリア、そして現代のボレリアはそれほど大きな変化が見られないことで、種が分岐してから大きな変化がないとすると、おそらく5−6000年前にシラミへの乗り換えが起こったと想像できる。面白いのは、この時期に人間は定住が進みヒツジなどの家畜の飼育が進み、毛皮などを用いた衣服を着用するようになったらしい。即ち、ケジラミからコロモシラミへの転換とともに、ボレリアが人から人へと感染する病原菌になった可能性が示唆される。ただ、この乗り換えを後押しする決定的な遺伝要因を特定するには至っていない。
一旦 B.reccurentis が分岐してからの変化は大きくないとはいえ、しかし B.duttoni からゲノムに組み込まれたプラスミドを中心に2割ゲノムサイズが低下している。ほとんどは不活化されているプラスミドなのでシラミへの乗り換えでゲノムサイズを落とす適応が起こったと考えられる。
ただ、必ずしも遺伝子の数が減る方向だけではなく、実際 B.recurrentis になって165個の新しい遺伝子が獲得されているので、極めてフレキシブルな進化が、主にプラスミドを媒介として起こっていることがわかる。おそらくこの中にシラミへの乗り換えに関わる遺伝子も存在するのではないだろうか。
次に、2200年前と中世・現在のボレリアの違いを調べると、例えばプラスミドの分離に関わるボレリアに広く分布する遺伝子が中世型への変化で失われ、新しい遠縁の分子で担われるようになっていたり、組み換えに用いられる RecA が欠損したりと、なかなか面白そうな変化が見られる。これが、人間の回帰熱の歴史とどう関わるのか興味を引くが、今後の課題になる。
他にも点突然変異を調べていくと、ホストの免疫から逃れる仕組みを中心に変化が見られるのも面白い。
以上、まだ病気の歴史とボレリアの歴史を対応するところまではできていないが、古代ゲノムの研究から分岐してきた古代病原菌の研究は人間の進化過程の解明に欠かせない。
2025年5月28日
多くの神経変性疾患で共通の原因がタンパク質の細胞内沈殿形成で、アルツハイマー病のTau、パーキンソン病のαシヌクレイン、そしてALSでのTDP-43はその典型例だ。このブログでも紹介したが、最近これらタンパクが相分離により濃縮されることが凝集形成に関わることが明らかになってきた。
今日紹介するドイツ・ドレスデン工科大学、ドレスデンマックスプランク研究所、そしてテキサスA&M大学からの論文は、TDP-43の相分離から凝集までの過程と、背景にある分子基盤を明らかにした力作で5月23日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Intra-condensate demixing of TDP-43 inside stress granules generates pathological aggregates(TDP-43の異常凝集はストレス粒子相分離体内での分離により起こる)」だ。
これまでTDP-43単独でも相分離が起こることが知られていたが、必要な細胞内濃度が現実ではないので、もっと低い濃度でTDP-43が相分離し、その後凝集体を形成する過程を詳しく調べている。この結果、低い濃度でも細胞がストレスに晒され、RNAと結合タンパク質が集まったストレス粒子が形成されると、そこにTD-43が組み込まれることで相分離し、その中で今度はTDP-43単独の凝集体を形成して相分離体から離脱することを発見する。
この過程をガイドしているTDP-43の様々な領域や、結合するタンパク質について徹底的に調べている。例えばTDP-43はRNA結合タンパク質なので、RNA結合性がなくなると相分離できないし、その結果凝集も起こらない。また、RNAをスキャフォールドとして相分離体を形成するタンパク質HSPB1をノックアウトすると、TDP-43の相分離も起こらない。これらの解析からTDP-43は低い濃度でもRNAに結合して、細胞ストレスにより誘導されて相分離が起こるストレス粒子内に取り込まれて相分離に参加する。
ストレス粒子が形成される細胞ストレスの多くは、酸化活性上昇を伴うことが多いが、これが起こると今度はTDP-43のRNA結合ドメインに存在するシステインがむき出しになりS-S結合が始まり、これを引き金にしてRNAから離れるとともにTDP-43同士の結合が始まる。これにより、細胞内でTDP-43が相分離体から分離して、液相から固相への転換が起こることが観察される。
分子シミュレーションや、分子の一部を改変する実験から、相分離体への参加、相分離体からの離脱、そして固相への転換による凝集体形成までの分子基盤を完全に明らかにしているが、ここでは割愛する。その上で、培養細胞実験系だけでなく、iPS由来運動神経細胞などを用いて同じ過程が起こることも確認している。
以上が結果についてのかなり省略した説明だが、これまで知られているALSの発症に関わる変異や、観察をほぼ全て説明できる。そして、相分離から凝集に至る分子についてもほぼ明らかになったので、うまくいけばこの過程を抑制する方法を見つけられるのではと期待される。
説明すると簡単だが、膨大な実験に基づくわかりやすい研究で、この論文は実際に手に取って読んでほしい。神経変性疾患のタンパク質凝集のことがよく理解できるようになる。
2025年5月27日
今日は細菌叢によって起こる意外な攪乱現象について論文を2報紹介する。
最初のプリンストン大学からの論文は、ケトン食が PI3K阻害剤の作用を高めるというこれまでの報告を解析し直して、この作用がケトン食とは全く無関係の原因で起こることを示した研究で、5月29日号 Cell に掲載された。タイトルは「Microbiome metabolism of dietary phytochemicals controls the anticancer activity of PI3K inhibitors(食に含まれるフィトケミカルは細菌叢で代謝され、PI3K阻害剤の抗ガン作用を調節する)」だ。
まさに風が吹くと桶屋が儲かる的な話で、結論を先に述べると、「マウスの固形飼料に含まれる大豆由来のフィトケミカルが細菌叢により代謝され (soyasaponin から soyasapogenol) 、これにより肝臓の解毒システムが活性化され、これが PI3K阻害剤の肝臓での代謝を高めるため、同じ量を服用してもフィトケミカルを含む食事をとると、薬剤の効果が低下する」になる。
この実験では最初ケトン食で PI3K阻害剤効果が上がる原因を追及し、これがケトン食のマクロニュートリエント構成にあるのではなく、マウス固形食に含まれる何らかの分子が細菌叢により代謝されて、これが PI3K阻害剤の分解を促進することを突き止める。事実、通常の固形餌を与えても、細菌叢を抗生物質で除去すれば、PI3Kの血中有効濃度は維持できる。
そこで固形餌の成分を分析し、大豆由来のフィトケミカル、soyasoponin が細菌叢により代謝された産物soyasaponenol が肝臓の解毒システム発現を誘導し、その結果 PI3K が肝臓で分解されるため、薬剤の効果が低下することを突き止める。
以上が結果で、我々大豆をよく食べる民族にとっては重要な発見だと思う。コロナウイルス治療薬として最初に使える様になったパキロビッドは、ニルマトレルビルの分解をリトナビルで抑えて使うが、同じような工夫が他の薬剤にも必要かもしれない。
もう一報は、シンシナティメディカルセンターからの論文で、老化とともに増加する血液のクローン性増殖に、グラム陰性菌が分泌するADP-heptoseが直接関わっている可能性を示した研究で、4月23日Nature にオンライン掲載されている。タイトルは「Microbial metabolite drives ageing-related clonal haematopoiesis via ALPK1(細菌叢由来代謝物はALPK1を介して老化に伴うクローン性血液増殖に関わる)」だ。
4月19日に紹介したやはりクローン性増殖に関する研究はDNMT3a変異によりミトコンドリアの活性が高まることがクローン性増殖の要因であることを示していたが(https://aasj.jp/news/watch/26596 )、一ヶ月もしないうちにこの論文は細菌叢由来分子がクローン性増殖を誘導できる可能性を示しており、この分野が多くの研究者を集めていることがわかる。
この研究ではマウス実験系で、DNMT3a変異血液細胞を移植したとき、ホストの腸管上皮が傷害されていると増殖力が高まることの発見から始まっている。通常の上皮障害を誘導する硫酸デキストランを接種させるとなんと増殖は5倍近くになり、それが維持される。ところがこの効果は抗生物質で細菌叢を除去すると消える。
この原因を追及して、結局、老化や上皮障害で増加してくるグラム陰性菌由来の分子が血中に流れてクローン性増殖を高めることを発見し、この分子をグラム陰性菌がLPSを合成する過程で分泌するADP-heptoseであることを突き止める。
実際、若い人ではADP-heptoseは全く血中に流れていないが、老化するとADP-heptoseが血清中に検出できる。そして、この血清、あるいはADP-heptoseを直接DNMT3a欠損血液細胞に加えると細胞の増殖を誘導できる。
このシグナルについても検討し、細菌由来物質のセンサーとも言えるALPK1チロシンキナーゼを介して、NFkbシグナル経路が活性化する結果であることを示しているが詳細は割愛する。要するに老化に伴うADP-heptoseの上昇と、DBMT3aによるALPK1の発現上昇が合わさった結果がクローン性増殖を誘導することになる。
ではこの結果と、ミトコンドリア活性化をメトフォルミンで抑えるという結果は並立するのか。細胞の中での話としては全然問題なく両立していいと思う。ただ、メトフォルミンは細菌叢に働いてグラム陰性菌が増加することも示されているので、こちらは両立しない。ことほど左様に細菌叢は複雑だ。
2025年5月26日
両親が健康な場合、流産児の明らかな形態的異常が見つからない限り、流産の原因を探ることは難しい。幸い、ゲノム解析が進んだ結果、流産胎児のゲノムと両親のゲノムを比べることで、ゲノムレベルの異常を特定できるようになってきた。
今日紹介するアイスランドにあるデコード社とデンマーク・コペンハーゲン大学からの論文は、流産した胎児や胎盤のゲノム解析から流産の原因になる遺伝子変異を明らかにしようとした研究で、5月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Sequence diversity lost in early pregnancy(初期妊娠中の流産で見られる配列の多様性)」だ。
デンマークは国民のコホート研究が徹底している国だが、流産についてもコペンハーゲン流産研究というコホートが存在し、すでに467例の初期流産胎児組織が集められ、同時に両親の血液も採取されている。このおかげで、流産胎児のゲノム配列決定を行って、両親と比べることで、どのような変異がいつ発生したのかを特定することができる。この研究で正常胎児のコントロールはないが、代わりに正常に生まれてきた子供のゲノムを両親と比べた多くのデータを参照することができる。
まず流産胎児と言っても血の塊みたいなもので、母親の組織も多く混じっており、研究で最も重要なのは、これらの組織から胎児や胎盤組織を正確に採取することで、これを500例近く行ったことに驚く。この方法では塩基変異まで全ての変異を特定できるが、それが流産の原因になったと特定するのは簡単ではない。研究ではまず、染色体の数の変化が起こる大きな変異を探索している。この結果、流産児の44%は染色体の一部の数の大きな異常が認められ、さらに6.4%が三倍体を示すことがわかっている。即ち、流産の半分以上は染色体の大きな部分に起こる染色体変化によることがわかった。
詳細は省くが、染色体異常の起こり方を特定することもできる。例えば最も数の多い16番目のトリソミーは全て母親の減数分裂のエラーによることがわかる。そして、他の染色体も含めかなりの割合で、減数分裂前の分裂でできる姉妹染色体形成児の異常であることが特定できる。一方父親の減数分裂異常で起こる染色体異常は4番や15番など限られた染色体に見られる。そして、数の増えたり減ったりしている部分の境界を特定すると、減数分裂時に起こる組み替えのホットスポットで起こっていることがわかる。元々減数分裂時に染色体の組み替えが起こり、これが我々ゲノムの多様性を維持するための重要な過程なので、このような初期妊娠中に起こる流産を防ぐためには、卵子や精子の質を決定する手段がない限り難しい。さらに、女性の場合減数分裂途中で長い休止期に入ることが、例えば8番や16番の染色体異常が起こりやすい原因になっている。
このような大きな変化以外に、6.6%は胎児だけに見られる点突然変異や小さな欠失・挿入によるを特定することができる。また、このような変異が見られる頻度は、正常時と両親を比べた場合より明確に高いため、おそらくこれらが流産の原因になっていると想像できる。事実特定された多くの遺伝子は、胎児発生や胎盤形成で強く発現しており、発生異常の原因になっている可能性を示唆している。
なかには明らかに発生異常に繋がることが明確な遺伝子も存在している。面白いのは単一塩基変異の多くが Thiopurine によるガン治療でも見られる C>G 変異で、原因究明が待たれる。
主な結果は以上だが、おそらくこの論文の重要性は、徹底的にゲノムを両親と比べても全く異常が見つからないケースが4割以上存在するという事実だろう。ゲノムの変異の方は、結局前もってゲノムを調べない限り防げない。しかし、残りの4割の原因がわかれば、流産の確率を大幅に減少させられる可能性は残る。
2025年5月25日
細胞系譜の追跡は発生学の重要なテーマで、これまで様々な方法が開発されてきた。追跡時間が長い場合は、分化や成長の跡も変化しない細胞の標識法が必要になる。そのため通常はゲノム上に起こった変異を利用して追跡に使っている。
今日紹介するバルセロナの科学技術研究所からの論文は、これまでの常識を覆し、エピジェネティックな変異も細胞系譜追跡のクローン標識に使えることを示した研究で、5月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Clonal tracing with somatic epimutations reveals dynamics of blood ageing(体細胞のエピ変異は血液細胞の老化による変化を明らかにする)」だ。
この研究の結論は、「DNAのメチル化パターンも細胞クローンの長期間の標識として使えることを明らかにし、これを用いて老化に伴う血液のクローン増殖を正確に解析できる」とまとめられるが、この論文を読んでみて、結論よりも何よりも、single cell を解析する方法がここまで進歩し、いくつかを自由に組み合わせることができるのかという驚きの方が大きかった。
DNAメチル化パターンは様々な要因で変化するので、クローン標識に用いられないと考えるが、染色体として閉じたヘテロクロマチン領域は安定していることが知られている。この研究では、メチル化されると制限酵素で切断できない領域を利用して、少量のDNAでメチル化状態を特定できる部位を約450カ所選んで、の450カ所のメチル化のパターン(エピ変異)を細胞標識に用いられるか調べている。
これがクローン標識になることを示すためには、オーソドックスなゲノム変異に基づくクローン解析と組み合わせる必要がある。そこで、レンチウイルスにバーコード配列を導入し、これをクローン標識にし、ゲノム標識で特定できるクローンとエピ変異で特定できるクローンが一致していることを確認している。
もちろんエピ変異の中には、血液分化により変化したパターンも含まれる。例えばリンパ球と白血球ではメチル化パターンが異なる。実際、single cellエピ変異を調べると、一部は細胞分化とともに変化する変異が存在し、クローン標識としては役に立たない。しかし、血液の分化度を示す標識として用いることができることから、エピ変異を血液細胞分化の標識とクローンの標識として同時に使うことができる。予想通り、分化の標識として使えるエピ変異はオープンクロマチンの遺伝子プロモーター部分に存在し、クローンの標識に使うエピ変異はヘテロクロマチン部分に限局している。
このようにレンチウイルスを用いて遺伝子を導入する方法は人間には使えない。そこで、クローン増殖を誘導することが知られている150カ所のこれまでクローン増殖との関わりが知られている変異をsingle cellレベルで同時に増幅し、epi変異とともに解析する方法を開発し、ゲノム変異とエピ変異の一致について解析している。
結果、ゲノム変異により増殖したクローンはエピ変異パターンでも特定できることを示している。さらに、ゲノム変異は見つからなくても、エピ変異だけが見られるクローン増殖が存在することも明らかにし、エピ変異解析は特にクローン増殖解析に有効であることがわかる。
他にも、今度はsingle cellレベルでミトコンドリア遺伝子の変異を調べる方法と組み合わせて、それぞれはゲノム変異以上にクローン標識に使えることを示している。最後に、エピ変異パターンが血液分化とクローン解析を同時に行える利点を生かして、高齢者の血液を解析し、エピ変異が様々な分化度の幹細胞で起こったあと、長期間維持されること、また人間では50歳ぐらいからエピ変異が起こり始め、これが体内時計の代わりをすることを示している。
いずれにしても、エピ変異の解析方法を開発した上で、それをバーコード導入や、ゲノム変異、ミトコンドリア変異のsingle cellレベルの解析と自由に組み合わせて実験を進めているのを見ると、老兵はただただ目を見張る。
2025年5月24日
今日は少し趣向を変えてアスリートの健康リスクについての論文を2報紹介する。
まず最初のバスク大学からの論文は、プロフェッショナルのアスリートではないが、マラソン完走後の脳変化を調べた研究で、この号の表紙になっている。
これまでウルトラマラソンランナーでは完走後に脳が縮小することが報告されていたが、この研究では様々なマラソン大会参加者からボランティアを募集し、10人についてマラソン前、マラソン後48時間以内、2週間後、2ヶ月にMRI検査を行っている。検査は脳白質のミエリンの量に焦点を当てている。といっても実際にはミエリン層に蓄積された水の量を量って、ミエリンの量としている。従って、脱水など他の要因でミエリンが減って見えることはあるが、今回測定できたのは正確にミエリンの量を反映していることを確認している。
さて結果だが、マラソン完走後48時間以内ではミエリンの量が平均で25%近く減少する。この減少は、運動神経とその調節に関わる領域で高いことから、おそらくグルコースの供給が低い時に長期間神経活動を維持するために、脂質でできているミエリンをエネルギー源として供給しているのだろうと結論している。本当にミエリンが局所でエネルギー源として働いているのかは、動物で実験可能だと思う。
研究ではマラソン完走後2週間、2ヶ月でも同じ検査を行い回復を調べている。2ヶ月ではほぼ完全に回復しているが、2週間ではまだ完全な回復は見られていない。
以上が結果で、マラソン愛好家も少し気になるところだろう。重要なのは、ミエリンが減少しているときにどのような症状があるのかをはっきりさせることだろう。また、脳内のグルコースを高める方法の開発も重要な気がする。
次の論文はイタリアパドバ大学からの論文で、2005年から2020年に開催されたプロフェッショナルのボディービル・コンペティションに参加したボディービルダーを協会の登録をベースに追跡し、平均8.5年の経過観察期間中の死亡とその原因を調べた研究で、4月10日 European Heart Journal にオンライン掲載された。
統計的に妥当な集計が行われていることを確認した上で、死亡率をプロフェッショナルなボディービルダーとアマチュアで比べると、なんとプロはオッズ比で5−6倍死亡率が高い。そして、最も多い死亡原因は心臓の突然死で、37%にも登る。
即ちプロフェッショナルボディービルダーは心臓死の高いリスクを背負っていることが統計的に示された。解剖が行われたケースでは、ボディービルダーの心臓が肥大していることが確認されており、心筋の強化が逆に突発的な心臓死の原因になっている可能性が高い。
これが純粋なボディービルディングの結果かどうかははっきりしない。というのもボディービルディング協会ではドーピング規制がほとんどなく、多くのボディービルダーは筋肉増加ステロイドなどの増強剤を使っている。実際、アマチュアでは突然死がそれほど上昇していないことを考えると、増強剤の影響による可能性は大きい。その意味で、この結果を受けてボディービル協会もドーピング規制を厳しくした方がいいと結論している。
他にも、ボディービルダーはアミノ酸やプロテインを多量に摂取する傾向があり、これが腎不全に繋がることも知られている。とすると、プロもアマも健康第一で競争を楽しむことが重要だといえる。
2025年5月23日
今日紹介するニューヨーク大学からの論文はシステイン欠損を数日続けるだけで身体の脂肪をほとんど燃やすことができることを示した驚くべき研究で、5月21日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Unravelling cysteine-deficiency-associated rapid weight loss(システイン欠損による急速な体重減少を明らかにする)」だ。
システインはメチオニンとともに硫黄を含むアミノ酸で、タンパク質に取り込まれるとSS結合を通して高次構造を決める重要なアミノ酸として働く。ただシステインはタンパク質の構成要素として働くだけでなく、グルタチオンへと変化して酸化ストレスを抑える。さらには様々な細胞毒の解毒作用も持っている。その上に、分解により生じる硫化水素は細胞のエネルギー代謝調節に重要であることもわかっている。このような多様な機能から、現在ガンの代謝プログラムとの関わりでシステインが盛んに研究されている。
このようにシステインが細胞代謝に重要だとわかっていても、システインが欠損すると数日で体重が3割減るとは誰も想像できなかったと思う。必須アミノ酸やシステインが欠損した状態を詳しく調べる途中で、体内でシステイン合成ができないように合成酵素を欠損させたマウスにシステインフリー食を与えて、完全にシステインの供給を絶つ実験を行っている。
他の必須アミノ酸を欠損させた場合でも急速に体重が減る。これはintegrative stress response (ISR) が誘導され、翻訳が低下するとともに、FGF21やGDF15が上昇して代謝を変化させる結果であることがわかっている。ただ、システインを完全に遮断した場合はこれを遙かに超える体重減少が見られ、1週間でなんと体重が3割低下する。
組織学的に調べると、なんと脂肪組織から脂肪が消える。これは決して脂肪細胞が失われたわけではなく、脂肪が消費される結果であることがわかる。この間マウスは飢えでぐったりするといった症状を示すことは全くなく、正常と同じレベルの活動性を維持している。ただ、酸素呼吸は少し低下する。
脂肪組織を詳しく調べると、白色脂肪組織で脂肪を熱に変えるUCP1を発現した褐色脂肪組織への転換が進み、その結果代謝に脂肪が使われ、また多くは熱として放出された結果、これほど急速な脂肪組織減少が可能になっている。
あとは、肝臓、筋肉、脂肪組織などの遺伝子発現を調べ、この変化の原因を探っている。通常の必須アミノ酸欠損で起こるISRが起こっていることは確認されるが、これに加えて酸化ストレス反応 (OSR) が加わっていることがわかる。これはシステインがグルタチオン合成に必須であるためで、これが低下して酸化ストレスが上昇している。
この2種類のストレスが揃う結果、脂肪やコレステロールの合成が低下し、逆に分解が上昇する。
これがISRとOSRが揃う結果であることを確認するため、必須アミノ酸を欠損させISRを誘導するとともに、グルタチオンの合成を止める化合物を加えると、システインが存在しても同じような効果が見られる。余談になるが、システインの体内での合成を止めることは難しいので、この戦略は短期であれば体重減少治療として使える可能性はある。
ただ、システイン遮断効果は、ISR+OSRよりさらに強いので、システイン遮断独自の要因もあると探索し、エネルギー代謝の中心にあるCoAの濃度が、システイン遮断特異的に低下することで、より強く脂肪依存性のエネルギー代謝へのシフトが起こることを示している。
以上が結果で、理屈よりもともかくその効果に驚く。元々硫黄を含むメチオニンやシステインを制限することで長生きするという話がある。システインは酸化ストレス抑制には必要だが、硫化水素を合成して毒性を発揮するので、このバランスをあまり狂わせるとかえって短命に繋がると思っていたが、今日の論文を読んでシステインにはまだまだ知らない秘密があることがよくわかった。
2025年5月22日
パーキンソン病 (PD) は神経細胞が変性により失われる病気なので、治療としては失われた細胞を取り戻す再生医療、あるいは他の細胞にドーパミン産生を肩代わりさせる遺伝子治療が中心になる。ただ、細胞喪失の原因を少しでも和らげて、経過を遅らせる治療も重要だ。その一つが、神経を傷害する異常αシヌクレインを抗体で除去する方法でおそらく多くの研究が進んでいる。これと平行して、様々な薬剤でαシヌクレインの影響を抑える方法も開発が進んでおり、このブログでも異常αシヌクレインに対する神経細胞の反応を阻害して細胞死を防ぐc-Able阻害剤(https://aasj.jp/news/watch/21414 )、またαシヌクレインの伝搬を防ぐAXLキナーゼ阻害剤(https://aasj.jp/news/watch/26237 )などについて紹介してきた。
まず今日紹介するPDの進行を防ぐ薬剤開発を目指した研究論文を読んで驚いたのは、AXLキナーゼを報告した上海復旦大学大学の同じ研究施設からの論文だが、主要著者が全くことなる点だ。内情はわからないが施設内ですごい競争が行われているのだろうか?今日紹介する論文のタイトルは「MEK1/2 inhibitors suppress pathological α-synuclein and neurotoxicity in cell models and a humanized mouse model of Parkinson’s disease(MEK1/2阻害剤は異常なαシヌクレインと神経毒性を細胞モデルとヒト化したパーキンソンモデルで抑えることができる)」だ。
MEK1/2阻害剤というとメラノーマやRAS活性化ガンに現在使われている薬剤で、タイトルを見たとき「え!これがPDに効くの?」と驚いた。研究ではラベルしたシヌクレインの細胞内の濃度を低下させる薬剤がないか、既存の50種類の化合物を細胞に加えて探索した結果、MEK1/2阻害剤に効果があることを発見している。即ち、正常シヌクレインの細胞内濃度を下げる効果がMEK阻害剤にある。また、神経細胞を異常シヌクレインに暴露して細胞内でのリン酸化シヌクレイン、さらには繊維化シヌクレインを誘導する系では、正常と同じように異常シヌクレインも抑えることができる。すなわち、全てのシヌクレインの細胞内濃度を下げることができる。
このメカニズムについて細胞レベルで調べると、正常シヌクレインについてはMEK阻害剤はオートファジーを抑えるTFEB分子をリン酸化して、オートファジーを促進することで細胞濃度を下げている。ところがこの経路はリン酸化及び異常シヌクレインの除去には関与していないこともわかった。
そこで異常シヌクレインに暴露したときに誘導されるαシヌクレインのリン酸化、その後の凝集に関わる分子として知られるPLK2キナーゼ活性について調べると、MEK阻害剤でPLK2タンパク質の細胞内濃度が低下することを発見する。その結果、正常シヌクレインのリン酸化が低下し、シヌクレイン凝集も抑えられることがわかった。これをまとめると、MEK阻害剤は異常シヌクレインの原料になる正常シヌクレインの濃度をオートファジー促進で下げると同時に、シヌクレインリン酸化に関わるPLK2の濃度を下げることで、リン酸化シヌクレイン、凝集シヌクレインの生成自体を抑えることがわかった。
最後に、米国バイオベンチャーSpringWorksが開発し神経線維腫症の治療治験が進行中の、脳血管障壁を通過できるMEK阻害剤Mirdametinibを投与して、シヌクレインをヒト化して異常シヌクレインを線条体に注射してPDを誘導するPDモデルマウスの症状と病理を抑えられるか調べ、強い副作用なしに症状及び病理レベルでPDの進行を抑えられることを明らかにしている。
以上が結果で、今年2月に紹介した論文よりはずっと臨床に近いところまで研究が進んでいるので、是非治験を進めてほしいと思う。細胞移植と言ってもPD患者さんの数を考えると、そう簡単に治療数の拡大は見込めないだろうが、以前紹介したAble阻害剤と今回のMEK阻害剤による治療は重要だと思う。