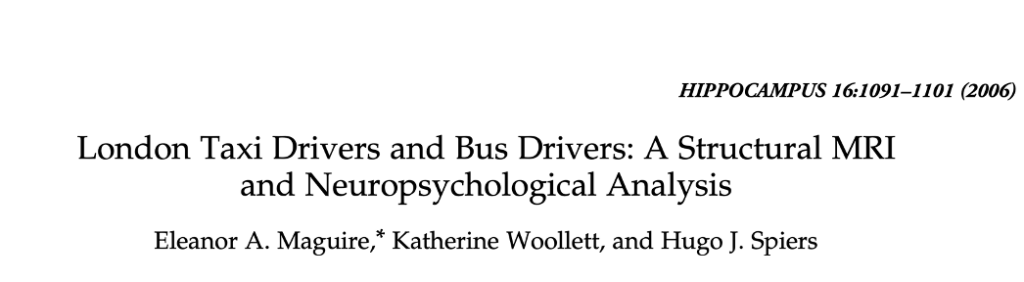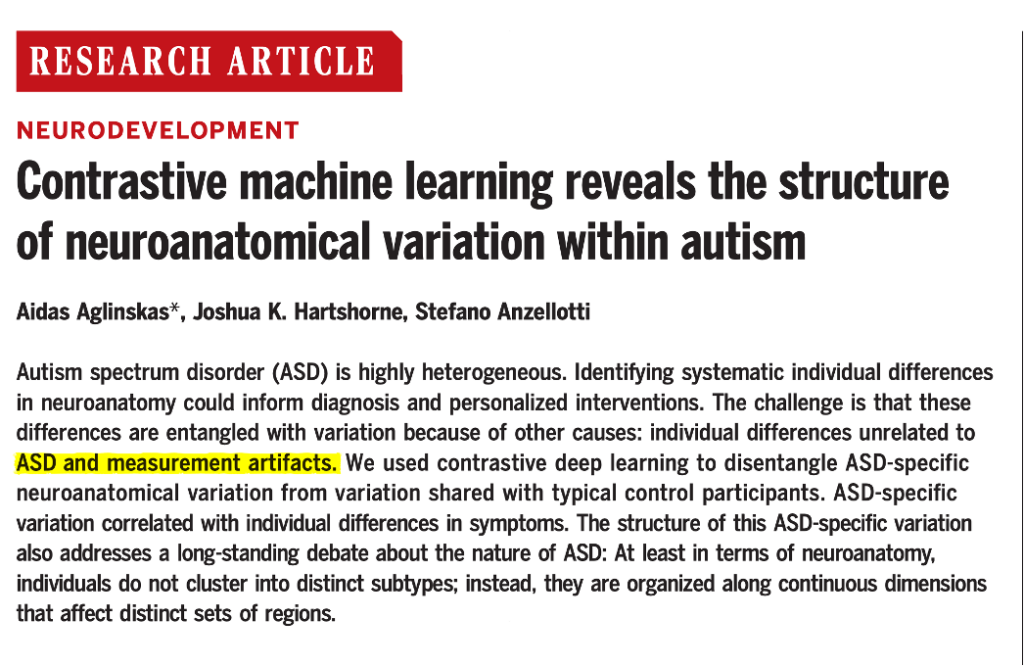2022年6月24日
まず今日紹介するチューリッヒ工科大学からの論文のタイトル「The metastatic spread of breast cancer accelerates during sleep(乳ガンの転移性進展は睡眠中に促進される)」を見て欲しい。
要するに乳ガンの転移は寝ているときに促進されるという恐ろしい報告で、タイトルを見ただけで引きつけられる。ちょっと知識があると、そもそも転移というプロセスが、一日より短い単位で変動するなどあり得ないと思うので、また羊頭狗肉かなどと思いながら、どんな実験を行っているのか興味津々で読み進めることになる。結論的に言うと、羊頭狗肉ではないし、実験の着想は面白いが、最終結果は至極まっとうで「幽霊の正体見たり枯れ尾花」といった感じだ。
要するにガンの転移が概日リズムに従っているという話だが、一番重要なのは転移の量を時間単位でどう測定するのかだ。この研究では、このHPでもずいぶん前から紹介している Circulationg Tumor Cell(CTC:https://aasj.jp/news/watch/1821)を転移の指標としている。
ここまで読むとなるほどと、着想に感心するが、実際 CTC が多く遊離される乳ガン患者さんの血液を調べると、夜の方がなんと10倍以上高いことがわかった。おそらく予想を超える違いで、この発見が研究の全てと言っていい。
同じ現象を今度は乳ガンを誘導したマウスで調べると、マウスの場合昼に寝るので、寝ている昼をピークとして CTC 数が変動する。より詳細な実験が可能なマウスを使って、
腫瘍に直結する静脈を調べ、腫瘍からの遊離自体が概日リズムに支配される。 睡眠中に遊離された CTC は、活動中の CTC と比べて、静脈注射したときより多くの転移巣を形成する。 遺伝子発現を見ると、睡眠中の CTC は増殖に関わる遺伝子の発現が上昇している。 全ては概日リズムに従っており、メラトニン投与で睡眠を誘導すると、CTC の数が増える。 など様々な現象を明らかにしている。まさに、トーランドットの名アリア、Nessun Dorma・誰も寝てはならない、がガンと闘う鍵となる。
そして最後に、概日リズムでガンの活性を変化させる要因を探索し、インシュリン受容体、様々なホルモン受容体などの発現との相関を発見する。その上で、デキサメサゾンやテストステロン投与や、インシュリン投与実験を行い、これにより CTC の数を強く抑制できることを示している。すなわち、活動期に様々なホルモンが上昇し、これがガンの増殖や転移を抑えるという結果になる。もし最初にこの現象捉えて、ガンの活動をデキサメサゾンが抑えると結論してしまえば、Nature にはまず通らない。まさに、幽霊、幽霊とまず騒いでみることも論文を面白くするコツであることがわかる。
とはいえ、ガンの治療を考える時、夜にガンだけが活動を始めるのだとすると、治療をそれに合わせる意味は十分にあるだろう。例えば乳ガンでCDK4/6阻害剤が用いられるが、通常食後に投与しているのを寝る前に飲んだ方が、効果の点ではいいはずだ。いろいろ述べたが、面白い研究だと思う。
2022年6月23日
できる限り分野を広げて論文を読もうと思ってはいるが、偏りが出ることは否めない。従って、一定間隔で面白い論文に当たって頭の中をアップデートする必要がある。でないと、どうしてもその分野から遠ざかることになる。そんな一つの領域が中心体(Centrosome)だが、この知識をアップデートするためにミュンヘンのヘルムホルツセンターのMagdalena Götzラボからの論文は最適だ。特に神経発生学の深い知識の中で中心体を見ている点で、専門外にもとっつきやすく、多くの学びがある。3年前彼女のラボからの論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/9768 )、今日紹介する6月17日号のScienceに掲載された論文は、中心体からしか見られない新しい世界を教えてくれる面白い論文だ。タイトルは「Spatial centrosome proteome of human neural cells uncovers disease-relevant heterogeneity(ヒト神経細胞の中心体に集まる蛋白質の解析から疾患に関わる多様性を見ることが出来る)」だ。
中心体はどうしても微小管オーガナイザーとして見てしまい、細胞種によりそれほど大きな違いはないと思ってしまうが、この研究の最初の疑問は、「中心体に集まる蛋白質に、細胞の機能に応じた違いはないのか?」だ。このために、ヒトiPSから神経幹細胞、さらには神経細胞を誘導し、それぞれから中心体に集まる蛋白質を特殊な方法で探索している。その方法は、中心体の必須蛋白質10個を選び、これと相互作用する蛋白質を精製する方法で、つまり一種の蛋白質を餌として食いつく蛋白質を釣り上げるフィッシングのような方法だ。例えば中心体の真ん中に位置するCEP63を餌にすると、神経幹細胞では233種類、神経細胞では529種類の蛋白質が釣れてくる。
重要なことは、こうして釣れてくる分子は、神経幹細胞と神経細胞のような近い関係でも、共通の分子は一部で、大半はそれぞれの細胞特異的な分子が釣れてくる。そしてさらなる驚きは、この方法で中心体と相互作用すると特定された蛋白質の多くが、RNAスプライシングや、mRNAのプロセッシングに関わる分子で、通常は核内で行われていることが中心体でも起こっていることを示唆している。
次の問題はこの変化する分子リストの中から、どのようにその機能的意味を見いだしてくるかだが、Götzが用いた方法は、深い知識に裏付けられたさすがと思える方法だ。これまで自閉症の科学の記事の中で、小児神経疾患に生殖細胞形成過程や発生初期に新たに発生するデノボの変異が大きく寄与していることを示してきたが、これまで神経疾患に関わるとされているデノボ変異のリストを、中心体と相互作用する分子のリストと比較して、中心体に集まる分子の機能を特定しようとした。
結果は期待以上で、多くの神経発生異常に関わるデノボ変異は、中心体と相互作用する分子に濃縮されている。すなわち、神経発生に中心体が重要な働きを示すことがわかる。ただ、例えば自閉症に関わるデノボ変異で中心体と相互作用する分子はそれでも400以上存在することから、それぞれの機能については他のアプローチが必要になる。
そこで、Götzは、お得意の神経幹細胞から神経細胞への分化過程で起こる細胞移動に注目し、この過程の以上として知られる「脳室周囲結節性異所性灰白質(PH)」として知られる、神経幹細胞の脳室周囲から皮質への移動が傷害される病気に注目し、この病気に関わるデノボ変異の一つでスプライシングに関わるPRPF6分子の機能と中心体について詳しく検討している。
詳細を省いて結果を述べると、
中心体は、核外オルガネラではあるが、RNAスプライシングに関わる分子を集めて、スプライシングに関わっている。PPRP6も中心体に局在している。 PRPF6のデノボ変異により、神経幹細胞は分化しても、皮質への移動が出来ない。 この移動異常は、様々な遺伝子のスプライシング異常に起因するが、特に微小管の胴体に深く関わるキナーゼBrsk2分子のスプライシング異常が、移動を阻害している。また、正常Brsk2を細胞に導入すると、発生異常を抑えることが出来る。 PPRP6蛋白質と同じで、Brsk2-RNAは中心体近くに局在し、そこでスプライシングされる。 以上が結果で、中心体がもう一つのRNAプロセッシングサイトとして働いていること、またそれにより効率よく細胞の基本機能を分化に合わせて調節しているという、全く新しい世界が見えてきた。今後、フラジャイルX症候群のようなスプライシング異常はもとより、多くのデノボ変異の機能を中心体から見ることで、病気の理解が大きく進むのではと期待できる。素晴らしい研究だと思う。
2022年6月22日
2回にわたって、ガンの生存戦略を突く治療法の開発論文を紹介してきたが、せっかくなので今日も、アンドロゲン阻害薬抵抗性の前立腺ガンの治療法について検討したワシントン大学からの研究を紹介することにする。タイトルは「Chronologically modified androgen receptor in recurrent castration-resistant prostate cancer and its therapeutic targeting(去勢抵抗性前立腺ガンの再発過程で順番に起こってくるアンドロゲン受容体の修飾は治療標的になる)」で、6月15日号の Science Translational Medicine に掲載された。
何度も紹介しているように、前立腺ガンでは治療がうまくいったと思っていたのに、急に転移が見つかってステージ4ですと告げられることがしばしばある。ただ、この段階でもガンはアンドロゲンを駆動力にして増殖しているので、去勢など徹底的にアンドロゲンが利用できなくする治療が行われる。ただ再発は必至で、これに対してアンドロゲン受容体(AR)自体を抑制する薬剤 enzalutamide が開発され、効果を上げている。ただ、前立腺ガンはしたたかで、ほとんどのケースで薬剤抵抗性が発生し、打つ手がなくなってしまう。
ガンの薬剤抵抗性というとすぐにゲノムの変化を考えるが、このグループはほぼ全例で抵抗性が生まれる背景には、ARの活性を変化させる修飾機能が新たに獲得された結果ではないかと考え、enzalutamide抵抗性を獲得した前立腺ガンから、enzalutamideに結合するARを精製し、質量分析によって、ARの609番目のリジンがアセチル化されていることを発見する。
この発見といい、その後の解析といい、このグループの生化学の力量を感じさせる膨大な実験が続くが、詳細は省いて箇条書きに紹介する。
enzalutamideはARの核内移行を阻害するが、アセチル化されたARはenzalutamideと結合しても、アセチル化されていないARと結合し、核内移行する。 アセチル化はzinc fingerドメインに起こるが、この結果AR本来のDNA結合部位とは全く異なる結合部位の転写を活性化する。しかも活性化される遺伝子には、AR自身や、ARリン酸化に関わるACK1が含まれる。 ARがアセチル化されるためには、ACK1によるリン酸化がまず必要で、その後p300によりアセチル化される。ACK1はアセチル化ARにより活性化されることから、ARのリン酸化とそれに続くアセチル化がいったん始まると、ARとACK1の転写が活性化し、アセチル化ARの量がどんどん上昇する、悪いサイクルが始まる。 以上のことから、ARのアセチル化を防げば、enzalutamide耐性を元に戻すことが出来るはずだ。生化学的にはアセチル化阻害剤でこの過程を抑制できるが、このような薬剤は機能が多様で利用しにくい。そこで、アセチル化の前に必要なARリン酸化を行うACK1に対する阻害剤を開発している。 おそらく、まだ実験的な阻害剤で、薬剤として使うためには、さらに至適化することが必要と思うが、この薬剤で、enzalutamide耐性の前立腺ガンの増殖をin vitro、 in vivoで抑えることが出来る。 開発した薬剤R-9bは、経口投与可能で、用量依存的にガンの増殖を抑制する。ただ、アセチル化と同じような立体構造を形成できる突然変異(609番目のリジンがアラニンに変換している)では、アセチル化非依存的に同じ効果を示すため、R-9bは効果がない。 実際の臨床例でも、ARのリン酸化及びアセチル化は悪性度に伴って上昇する。また、リン酸化とアセチル化は相関している。 以上が結果で、最も驚いたのはARがアセチル化されることにより、転写のレパートリーを拡大し、それまでとは全く異なる分子の発現を高めている点で、急速に悪性化が進む秘密の一端を見ることが出来た。
2022年6月21日
昨日に続いて、ガンの弱点を突く治療法の開発研究を紹介するが、昨日のBRAF/MEK阻害剤をアンドロゲン受容体阻害剤で抑えられることを示した現象論に徹した研究と比べると、細胞内のメカニズムを明らかにして研究を進めているので、読んだ満足感は高い。
今日紹介するオランダ・フロニンゲン大学からの論文は、正常細胞ならすぐに細胞死に陥る染色体不安定性をガン細胞は許容できるのかについて、染色体不安定性が引き金となるシグナル経路を徹底的に詰めて、メカニズムを明らかにし、新しいガン治療の可能性を示した研究で、5月15日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「cGAS–STING drives the IL-6-dependent survival of chromosomally instable cancers(cGAS-STINGはIL-6依存性に染色体不安定性を示すガン細胞の生存を助ける)」だ。
タイトルにあるGAS/STINGについては自然免疫の知識が必要なので、ザクッと説明しておこう。GAS-STINGは細胞質に存在するDNAセンサーで、DNAウイルスが侵入したときに、自然免疫系を活性化する分子だ。ただ検出する細胞質のDNAは、必ずしも侵入したウイルスDNAだけではなく、分裂時に染色体不安定性生じると、ちぎれたDNAもGAS-STINGに検知され、細胞死を誘導することで、異常な細胞を除去する仕組みにもなっている。
この研究では「ガンはしばしば染色体不安定性を示すのに、このシグナルによる細胞死から逃れているのか?」と言う不思議にチャレンジしている。
これに対する答えは、ガンでは全くGAS-STINGが機能していないと言うものだが、染色体不安定性を示す乳ガンを調べてみると、細胞分裂を阻害して染色体不安定性を高めると、このシグナル経路がはっきりと活性化されていることをまず確認している。すなわち、GAS-STING経路は働いているが、細胞はアポトーシスから守られていることになる。
そこで発想を逆転させ、GAS-STINGが染色体不安定性にによる細胞死を守る働きがあるかどうか、GAS-STINGをノックアウトしたガン細胞の染色体不安定性を誘導して調べると、驚くことにGAS-STINGシグナルが欠損すると、細胞死が誘導されることを発見する。
ここまで来ると、GAS-STINGシグナル経路は詳しく研究されているので、下流のシグナルを一つづつたどっていくことで、染色体不安定性から細胞を守るシグナル経路を特定できる。
GAS-STING経路は、主にIRF3およびNFkBの2つの回路を通して、自然炎症や細胞死を誘導しているが、この研究では、細胞レベルのノックアウトやシグナル阻害剤を用いて、染色体不安定性のストレスから細胞を守るシグナルを検索し、STAT3およびnon-canonical NFkB経路として知られるシグナル経路を介して、細胞が守られていることを明らかにする。
この経路は、IL-6の誘導路として知られているので、次にこの経路で分泌されるIL-6が細胞を守る鍵ではないかと着想し、染色体不安定性を誘導したガン細胞にIL-6 を加える実験を行い、予想通りIL-6だけで染色体不安定性を誘導した細胞を守れることを明らかにしている。
以上をまとめると、GAS-STINGは通常IRF、インターフェロン、STAT1経路を介して細胞死を誘導するが、これをもう一つのNFkB経路によって誘導されるIL-6が抑制していることになる。即ち、GAS-STINGはもともと相反する効果を誘導する、微妙なシグナルであることが想像される。
いずれにせよ、染色体不安定ストレスにさらされているガンでは、細胞を守るシグナルが強いので、下流のIL-6シグナルを抑えて、このバランスを崩すことで、ガン細胞を殺せないか、IL-6受容体の阻害剤を用いて調べると、染色体ストレスを誘導したガン細胞が殺されることを試験管内、およびガンの移植系で確認している。即ち、染色体の不安定性を強く示すガンや、染色体不安定性を誘導する薬剤を治療に用いる場合、IL-6シグナルを止めてやることで、ガンの治療効果を高められる可能性を示している。
最後に、人間のガンのデータベースから、IL-6Rを高発現しているガン患者さんでは生存が短いことも示し、この研究結果を実際の治療に利用できる可能性が大きいことも示している。
以上、徹底的にシグナル経路をたどることで、明日からでも可能な新しい治療法の可能性を示した研究で、読者としても様々なシグナル分子をたどりながら満腹した。
2022年6月20日
再生医療のハイウェイプロジェクトを引き受けたとき、選ばれた臨床の先生に、Nature やScienceなどに論文を出版するより、臨床的成果を上げたかどうかを評価したいとお願いしたのは、ほぼ15年前のことだが、最近、NatureやScienceも、臨床研究を採択するようになっている。ただ、臨床や前臨床研究の場合、他の分野の研究と比べると、採択基準は甘いなという印象を受ける。すなわち、あくまでも臨床応用ですぐに期待できるかどうかに基準が置かれ、詳しいメカニズムの解析が採択基準から外されると言うことだ。そんな例の典型を読んだのでこの点も考えながら紹介したい。
テキサス大学からの論文は、メラノーマをBRAF/MEKを標的にして治療を行う時、アンドロゲン受容体が誘導され、しかも標的治療の効果を落としてしまうと言う研究で、6月15日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Androgen receptor blockade promotes response to BRAF/MEK-targeted therapy (アンドロゲン受容体の阻害により、BRAF/MEK標的治療の反応が高まる)」だ。
タイトルだけ見ても、メッセージはすぐわかるし、多くの臨床雑誌で目にするタイトルと同じだ。事実、アンドロゲン受容体阻害剤をBRAF/MEK阻害剤と組みあわせればメラノーマ治療効果が高まるという結果が、この研究の主要メッセージと言っていい。
逆に言えば、何故こんなことが臨床現場でわかっていなかったのかが不思議になる。この研究ではまず、様々なステージのメラノーマに対して行われたBRAF/MEK阻害治療の効果を男女で比較して、ほぼ全ての場合、男性の方が女性より治療効果が低いことを明らかにする。
本当にこれまでこのような結果が示されなかったのか驚く結果だが、後の実験方向は見えている。
まずこの結果は男女でアンドロゲンの血中濃度が異なるという話ではなく、治療を始めるとガンのアンドロゲン受容体の発現が上がってくる結果であること確認している。そして動物実験から、このように誘導されたアンドロゲン受容体が、男性ホルモンの多い男性で刺激が続くため、BRAF/MEK阻害剤の効果が低下することを示している。
そして最後に、より臨床的な状態に似せるため、標的治療を始めると同時に、テストステロンを注射する実験、アンドロゲン受容体阻害剤enzalutamideを注射する実験、また両方を阻害する実験などを行い、確かに治療開始によりアンドロゲン受容体が上昇して、これがテストステロンで刺激されると、BRAF/MEK経路の阻害効果が低下すること、またenzalutamideでのアンドロゲン受容体阻害効果は、完全にテストステロンレベルを抑えた、すなわち去勢状態が必要であることを示している。
結果は以上で、ガン研究としては拍子抜けする。すなわち、何故RAF/MEK阻害でアンドロゲン受容体が上昇するのか、また何故アンドロゲン受容体刺激で、RAF/MEK阻害が抑えられるのか、メカニズムについては全く何も示されていない。しかし、臨床の立場では、こんな簡単なことで治療効果が高まるなら、明日からでも治験に取り組んで欲しいと思える結果だ。特に、BRAF/MEKに限るのか、他のMEK経路にも共通なのかも大事だと思う。
ただ、やはりNatureはもう少しメカニズムを追求した論文だけ掲載して欲しいと個人的には願っている。
2022年6月19日
1日途切れてしまったが、集中掲載最終回となる第5弾は、自閉症の科学でこれまで何度も紹介してきたゲノム研究を、総合的にまとめてくれたとさえ言える、カリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文を紹介する。タイトルは「A phenotypic spectrum of autism is attributable to the combined effects of rare variants, polygenic risk and sex(自閉症の形質のスペクトラムはレアバリアント、多遺伝子リスク、そして性差に帰せられる)」で、6月2日 Nature Genetics にオンライン掲載された。
これまで「自閉症の科学」でもっとも多く扱ってきた分野は、おそらくゲノム研究分野ではないかと思う。というのも自閉症スペクトラム(ASD)を構成するゲノムの多様性を目の当たりにすると、ASDを単純に正常/異常と分けるのではなく、人間の脳の膨大な多様性のなかの一群としてとらえるべきだという、neurodiversity (神経多様性)の考えをはっきりと実感できるからだ。
このコーナーを読んできていただいた皆さんの頭の中には、レアバリアント、コモンバリアントという言葉が、少なくとも単語としては刻み込まれているのではないだろうか。ここでもう一度簡単に解説しておこう。
私たちのゲノムは30億塩基対からできており、どの場所で変異が起こってもいいが、集団で見ると無秩序に配列変異がおこるわけではない。私たちが生きるためには、約2万個の遺伝子の機能を支えるための決まった配列が存在し、またそれ以外の部分でも、変異が入ると生命に関わる箇所は無数に存在しているため、集団の中でそんな変異が見つかることはほとんどない。このような生命機能に関わる変異をレアバリアントと呼んでいる。
一般的に遺伝子病と呼ばれている変異はほとんどがレアバリアントのことだ。そして、レアバリアントの中には、極めて低い頻度とはいえ集団の中で、ほそぼそと遺伝的に受け継がれている変異と、生殖細胞の発生から個体の発生初期に新しく発生した変異(デノボ変異と呼ばれる)に分かれる。ASDの場合、このようなレアバリアントは脳の発生過程に影響することで、ASD発症に大きな影響力があると考えられている。
一方、生命機能に強い影響はないが、変異により一定の形質変化が起こり、例えば病気のリスクになるような変異がある。レアバリアントと比べると、命に関わる程度が少ないので、集団の中に一定の頻度で遺伝的にい受け継がれ、コモンバリアントと呼ばれている。このようなコモンバリアントは、必ずしも病気のリスクに連結するのではなく、例えば顔貌の違いや、身長、そして性格や身体能力などの差につながっている。この意味で、コモンバリアントは、個人の特異性の源といっていい。
ASDのゲノム研究が始まった当初は、検出の容易なコモンバリアントの探索が行われ、予想を超える数のASDと連関するコモンバリアントが発見された。もちろんどの病気でも、その発症に関わるコモンバリアントは複数個存在する。例えば、コロナウイルス感染重症化についての報告を見ると、20近いコモンバリアントが特定されている。しかし、ASDと相関するコモンバリアントは、200近く存在することが明らかにり、数の上で別格であることがわかった。すなわち、コモンバリアントからASDを眺めると、ASDは極めて多様な、しかし小さな変化の組み合わせからなる、まさに neurodiversity の状態であることがわかる。
その後、解析されたASDの数が万の単位になり、さらにエクソームや全ゲノム配列解析が集まってくると、先に述べたレアバリアントも発見されはじめ、これまで紹介したように、現在ではASDと相関するレアバリアントがリストできている。また、期待通りコモンバリアントと比べると、レアバリアントとASDとの相関は強いことも明らかになってきた。
この研究は、これまで集まった3万人規模のASDとの相関が確認されたレアバリアント、コモンバリアントを集め、レアバリアントもデノボの変異と、それ以外に分けて分類し、それぞれのASD発症への寄与度を計算した研究だ。その意味で、これまでのゲノム研究の一つの集大成と考えられる論文だと言える。
結果は、これまでの研究から想定されていた結論と同じだ。
まず、個々のバリアントについてその寄与度を調べると、どのタイプでもデノボ変異の寄与度は大きい。そしてレアバリアントの中には集団の中で維持出来ているものもあるが、ASDで遺伝性のレアバリアントが関与する程度は低い。すなわちほとんどのレアバリアントが集団内で選択除去されているからだと言える。このことは、ASDの多くでは、遺伝と言うより、個人に特有の新しい変異が寄与していることを示している。例を挙げると、レット症候群やFOPなども、ほとんどがデノボの変異だが、これと同じと考えてもらっていい。
ただ、レット症候群と大きく異なるのは、一つのレアバリアントだけで発症しない点だ。個々のコモンバリアントの寄与度は低いが、集まってくることでASD発症に重要な役割を演じている。トータルで見ると、レアバリアントとコモンバリアントは同じ程度にASDに関与している。すなわち、ASDはコモンバリアントとレアバリアントが組み合わさっていることがわかる。すなわち、一つのコップに2種類の水を注いでいっぱいになった状態と同じだ。このため、レアバリアントの寄与が大きい場合、必要なコモンバリアントの寄与度は減る。
これを裏付けるもっと面白い例が男女差で見られる。女性では必要なレアバリアントも、コモンバリアントの組みあわせも、男性より遙かに多い。すなわち女性を、ASD発症まで満たすために多くの変異が必要なコップに例えることが出来る(変異を多い少ないと表現しているが、単純な数ではなく個々の変異の寄与度の和と考えて欲しい)。
このようにそれぞれの変異を分類しておくと、個々の症状に対するそれぞれの寄与度も計算できる。例えばASDに見られる運動の連携障害はデノボの変異と強く関わっているが、コモンバリアントの寄与はほとんどない。一方、社会性を測るSocial Communication Questionaireテストでは、コモンバリアントの寄与の方がデノボの変異より大きい。
さらに、コモンバリアントと異なり、デノボの変異の寄与度は、出産時の両親の年齢と強く相関していることも、これまで示されてきたとおりで、生殖細胞の形成過程の変異が、ASD発症に大きく関わることが確認された。
残念ながら、これまでの多くの研究をひとまとめにしたと言うだけで、新しい発見があったわけではない。しかし、前回紹介した構造の変異も含めて、ASDをコモンな違いと、レアな違いに分けて考えていく必要性がうまくまとめられており、大変参考になる論文だった。
これまで紹介した論文も含めて、この論文を再度まとめると、
自閉症は、性差も含めて様々な遺伝子の多型や変異が集まって形成される。 この点からASDの遺伝性を説明することは出来るが、それでもASD特異的変化を強く誘導する変異は、個体が生まれる過程で発生したデノボの変異によるところが大きい。 男女差と変異の関係から、変異が集まって発症するまでの過程で、それぞれ個人の器のキャパシティーが大きく影響していることがわかる。このことから、このキャパシティーを変化させる方法を開発することが、今後の重要な課題になる。 症状に関しても、コモンバリアントの寄与が大きいものと、レアバリアントの寄与が大きいものに分かれるので、この点を考慮した対策も今後の課題になる。 以上、5回にわたって、様々な論文を紹介したが、参考になれば幸いです。
2022年6月19日
今日紹介するハーバード大学、Dian Mathisラボからの論文は、免疫学長年の謎を解明したとても重要な論文なので、次々回のジャーナルクラブの題材にすることを約束して、ここでは概要だけを紹介する。幸い共同著者に挙げられている和歌山大学、改正さんを個人的にも知っているので、彼にも参加してもらってこの研究の重要性を伝えたいと思う。タイトルは「Thymic epithelial cells co-opt lineage-defining transcription factors to eliminate autoreactive T cells(胸腺上皮は体細胞の分化を決める転写因子を動員して自己反応性T細胞を除去する)」で、6月16日 Cell にオンライン掲載された。
私たちの免疫細胞は、自己の細胞や分子には反応しない免疫寛容が成立している。T細胞については胸腺内でT細胞が分化する時、自己抗原反応性のT細胞が除去されるからで、この概念は私の学生時代から既にMedawarらの研究により明らかにされていた。しかし、私たちの体細胞は極めて多様で、それぞれに対応する自己抗原をどうして胸腺で用意できるのかについては、古くからの謎だった。
ただ、Aireと呼ばれる、コファクターのような役割を持つ分子が、胸腺内で自己抗原を用意するのに重要な働きをすることがわかっていた。そして、Aireがランダムに末梢組織の分子の転写を誘導することで、胸腺上皮細胞が自己抗原を展覧会のように提示できるのではと考えられてきた。
この問題解決のため、Mathisらは胸腺上皮を分離し、single cellレベルでAtac-seqを用いてクロマチン状態を調べた。そして、オープンなクロマチン部分の特徴を調べると、Aireが存在することで、特にヒストンコードの差が生まれるのではなく、Aire結合サイトが特異的にオープンになっていることを明らかにした。一種パイオニア因子に似ている。いずれにせよこの結果は、Aireがクロマチンをオープンにして転写マシナリーを動かすというこれまでの考えと一致する。
ただ、2次元展開した胸腺上皮の各クラスターで発現している分子を詳しく見ると、ランダムに転写のスイッチが入っているのではなく、それぞれのクラスターが、末梢組織の分化に必要な別々の分子セットを発現していることに気付く。例えば、Aire欠損マウスで発生が見られないクラスターは、FoxAとその下流分子を発現する内胚葉系の臓器に遺伝子発現が似ていることを突き止める。ジャーナルクラブでは詳しくデータを見ていこうと思っているが、胸腺上皮のクラスターを、腸上皮、皮膚、神経、筋肉型と分けられるのを見ると、興奮する。
さらに、胸腺上皮分化に平行するAireの発現に伴って、胸腺上皮内で末梢組織プログラムが、未熟から成熟へと分化することまで、M細胞の分化を例に示している。すなわち、胸腺上皮は自分の分化の過程で、Aireによってスイッチが入った末梢組織の分化を実際に再現して見せて、この時に発現する抗原を、自己反応性T、細胞の除去に使うというわけだ。山中さんの4因子も真っ青の能力を、胸腺上皮とAireが実現していることになる。さらに、さすがこの分野を見続けていたMathisだけあって、1800年代の組織学では、胸腺上皮が様々な形態を示すこと、すなわち末梢組織のプログラムが発現している可能性が既に示唆されていていたことまで言及している。
最後に、末梢組織特異的に蛍光分子が発現するようにした遺伝子改変マウスで、同じ分子が胸腺上皮で発現して、免疫寛容が成立することも示している。この時、T細胞除去だけでなく、Tregの誘導も同じように起こる可能性も示している。
概要は以上で、要するに胸腺内に様々な組織の動物園が形成され、T細胞を教育しているというのだから驚く。さらに、これまで不思議だった多くの問題の解決の糸口が見つかるように思える。例えば坂口さんの胸腺除去実験で、何故内分泌組織の自己免疫が起こりやすいかなどだ。
まだまだ説明したい点が満載の論文だが、詳細はジャーナルクラブで説明するので、それまでしばしお待ちを。
2022年6月18日
久しぶりにCovid-19論文を取り上げる。スタンフォード大学とイェール大学からの論文で、最近問題になっているcovid-19感染後の厄介なbrain fogと呼ばれる現象について、マウスモデルで研究している。タイトルは「Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation(軽度の呼吸器Covid感染は様々な神経系細胞とミエリンの調節不全を起こす)で、6月7日Cellにオンライン掲載されている。
我が国でも感染が収まりつつあり、世界中でも「ワクチンも行き渡り感染しても軽い」と考えられるようになったので、現在ではlong covidや、軽度感染の後に思いがけなく続く様々な神経症状を取り上げて、注意が喚起されている。この意味では、なかなかタイムリーな研究だ。
研究では肺にβ株のcovid-19を感染させ、その後の脳の変化を見ている。この時、軽い肺炎だけが起こって、全身にウイルスが回らないよう、単純にACE2トランスジェニックマウスを使わないで、感染に必要なACE2をコードしたアデノウイルスをコロナウイルスと同時に投与するというトリックを用いて、軽症のcovid-19感染を再現している。
そして、感染は軽症で肺だけに限局されていても、脳では様々なサイトカインが、感染直後だけでなく、7週間後も高いレベルを維持している。特にとりわけこれまであまり注目されていないCCL11は、1週間目より7週間目の方がさらに高いレベルを示している。この結果、脳のミクログリアが活性化され、老化による白質障害で見られるミクログリアによく似た性状を示すようリプログラムされることを示している。
これと呼応して、白質維持に関わるオリゴデンドロサイトの喪失がやはり7週間持続し、さらに海馬の神経真性が抑えられる。以上の結果から、covid-19の場合、軽症でも持続するCCL11が、中心的役割を持つ炎症が脳で持続し、これがbrain fogの原因になると結論されている。
次の問題は、この炎症の分子的主役がCCL11なのか?、なぜcovid-19だけでこれが問題になるのか?、そして、このモデルは人間の症状を説明できるか?だ。
まず、CCL11をマウスに投与する実験を行い、驚くことに海馬白質特異的にミクログリアの活性化を誘導し、海馬の神経再生を抑制することを示している。ただ、これが持続的自立的炎症を誘導するのに十分かについては検討されていない。
次にインフルエンザ感染と比較して、同じようにCCL11を中心にした炎症が続くが、7週目でも上昇しているサイトカインの数や、ミクログリア活性化の程度などで、炎症の程度が低いことを示している。
ただ、なぜcovid-19のみこのような現象が起こるのかについては、答えは出ていないと思う。今後、他のコロナ株も含め、同じ実験系で調べることは重要だろう。特に、肺だけに炎症を限局させて脳を調べる実験の意味することは、ウイルスとは関係なく、脳で自律的な炎症の引き金が引かれることなので、より踏み込んだ実験が必要だと思う。
最後に、人間でもbrain fogを訴えた患者さんの脳ではCCL11が上昇していることを示している。
以上、まだ現象論的研究に終始しているが、局所の炎症が、サイトカインを介して細胞をリプログラムし、自立的持続的炎症を誘導するメカニズムを解明してほしいと思う。
2022年6月17日
2006年、英国University College Londonの研究者が、ロンドンのタクシードライバーの海馬灰白質が、同じ路線を繰り返し走るバスドライバーと比べて大きいと言う面白い論文を報告した。灰白質は神経細胞の数に相当するので、この結果は鍛えれば海馬の神経細胞は増やせられるのではと、大きく報道された。
ロンドンのタクシードライバーは資格基準が最も厳しいとされているが、この結果は解剖学的変化をある程度脳の機能と相関させられることを示している。
このことから、MRIを用いて微妙な脳構造の違いを特定し、ASDの早期診断が可能かを調べる研究が続けられており、論文ウォッチでも以下の2論文を紹介している。
ただ、これらの研究はASDを典型児から区別することだけを目的としていた。
しかし、ASDはスペクトラムと呼ばれるように極めて多様だ。またゲノム研究からも、典型児にも一定の頻度で見られる、一種の性格を反映すると考えられる頻度の高い多型(コモンバリアント)と、ASD発症の後押しになっているような、ASD特異的と言ってもいい稀な多型(レアバリアント)が混じっていることが示唆されている。すなわち、ASDの理解には、ASD特異的な変化と、ASD内の多様性に対応した変化を分けて調べることが望ましい。
今日紹介するボストンカレッジからの論文は、ASDのMRIデーータベースを用いて構造解析データを機械学習させるとき、contrastive learning(対照学習)を用いることで、ASDに関わる脳構造の特徴と、ASD内での多様性を区別して特定できることを示した研究で、6月3日Nature Neuroscienceに掲載された。
機械学習の話なので、ほとんどの議論が、ASD全体で共有される特徴と、ASDの間に見られる多様性を区別して捉えるためには、対照学習が遥かに優れていることの証明に費やされている(対照学習については是非自分で調べてほしいが、写真などの違いを自動的に比較し、似ている程度で分類していく機械学習法ぐらいに理解してもらえれば良い)。実際、対照学習法を用いて区別したASD特異的変化は、MRI撮影に使ったスキャナーの差にほとんど影響されないが、ASD間に見られる多様性の一部を説明できることを示している。すなわち、どこで検査したかはASDの診断には影響しないが、ASD間の多様性の原因になることは頭に入れておく必要がある。
一方、ASDの診断に使われる様々な指標は、全てASD特異的変化と強く相関するが、ASD内の多様性とは関係しないことも明らかになっている。すなわち、長年磨き上げられてきた信頼できる診断基準と、ASD特異的変化の関係を今後研究することの重要性がわかる。
ASD特異的差を除いた後の、ASD間で多様性が見られる脳領域は、かなり広い範囲に及んでおり、個々の領域の変化の意味と他の症状との関連については全く議論されていない。ただ、予想通り、ASD特異的な差と異なり、それぞれの領域の変化は、連続的で、どこまでが病的でどこまでが正常と線は引きにくいことが示されている。
以上が結果で、要するに対照学習により、ASD診断に関わる脳構造の変化と、個人間の変異を分けることができるということが結論で、ここで示された現象の意義については、全て今後の研究に投げているように思う。とはいえ、個人的には性格とオーバーラップする脳構造の多様性がなんとか抽出できるようになったことは、私たちのASD理解に新しい視点を与えてくれたと期待して、少し難しい論文だが、紹介する。
2022年6月17日
ジャレットダイアモンドのベストセラー「銃、病原菌、鉄(Guns, Germs, and Steel)」で取り上げられたように、世界史を形作ってきた最も大きな要因は、戦争と疫病だった。中でも中世の1346年から始まったペスト大流行は、10年でヨーロッパの人口が半減するほどの猛威を振るった。当然多くの記録が残され、それを手がかりに、この大流行がどのように始まったのか、研究が続けられている。
既に論文ウォッチでも2回紹介しているように、最近では疫病の起源と歴史を調べる手段として、ゲノム研究が加わり、大きな成果を挙げている。この結果、人類は5000年前よりペストと付き合っており(https://aasj.jp/news/watch/4277 )、また中世大流行のペスト菌だけでなく、他の系統も地域的流行に関わってきたことなどが示されている(https://aasj.jp/news/watch/4768 )。
今日紹介するライプニッツ マックスプランク人類進化研究所、チュービンゲン大学、そして英国スターリング大学からの論文は、中世のペスト大流行に関わるペスト菌の起源を、キルギスタンのKara-Djigach墓地に埋葬された遺骨から特定した研究で6月15日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia(14世紀ヨーロッパの黒死病は中央ユーラシア起源)」だ。
この研究では、中央ユーラシアで1338年に墓碑の数が急増しており、疫病についての記述が残されている墓地から、1338年に疫病で亡くなったと思われる人骨を掘り出し、ゲノムを調べている。まず、7体について民族的由来を確認した後、同じゲノムに混在しているペスト菌を再構成している。実際には3体の骨から、最終的には同じペスト菌ゲノムが再構成され、これまで知られている古代から現代まで、様々なペスト菌ゲノムと比較している。
この地区でエンデミックが起こった時期を1338年と特定できることから、これがヨーロッパパンデミックからほぼ8年前なので、その起源に近いため大きな期待が持てる。結果は期待通りで、ヨーロッパパンデミックに関わった系統、Branch1が、他のBranch 2、3、4から分岐する起点に存在することがわかった。
この分岐が起こった時期をゲノムから計算すると、大体ヨーロッパ流行の直前、1317年以降であると計算している。以上の結果から、天山地域を含む中央ユーラシアで発生したペスト菌が、この地域での短いエンデミックを起こした後、ヨーロッパに伝播したと考えられるが、これが戦争によるのか、交易によるのかについては今後の研究が必要になる。
いずれにせよ、それ以前、天山地域では、6世紀以降ヨーロッパ系統以外のいくつかの系統ペスト流行が確認されており、この地域でペスト菌のreservoirが形成され、ここから起源後のほとんどのペスト菌が供給されたと考えられる。とすると、reservoirを特定することが、パンデミック予測の鍵になるので、この分野への研究が進むと思う。細菌学もどうやら地震予知学に似てきた。