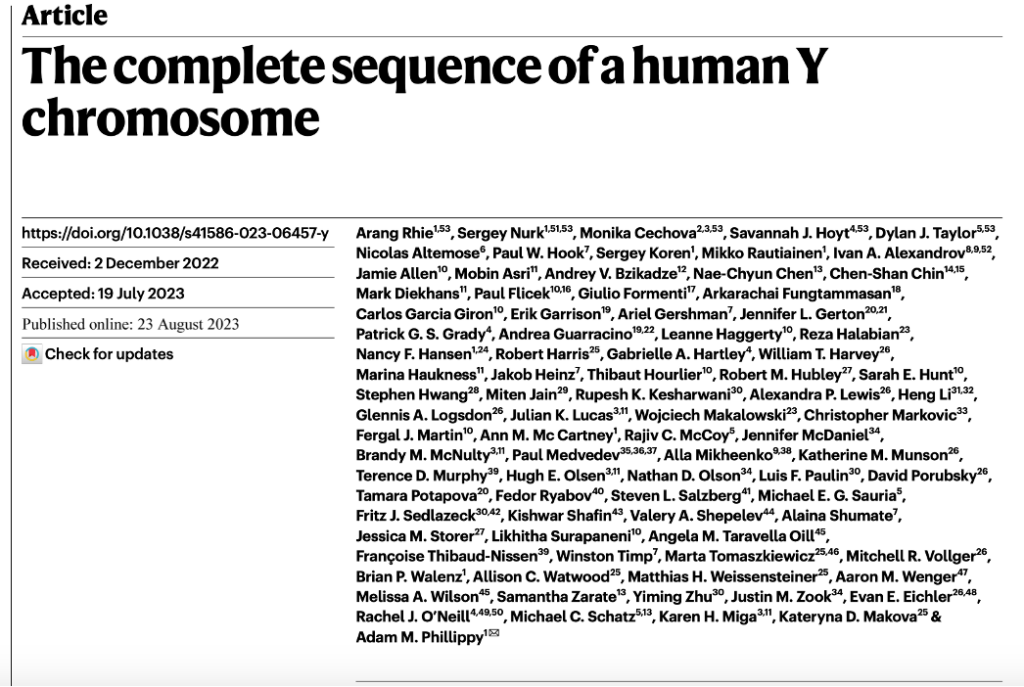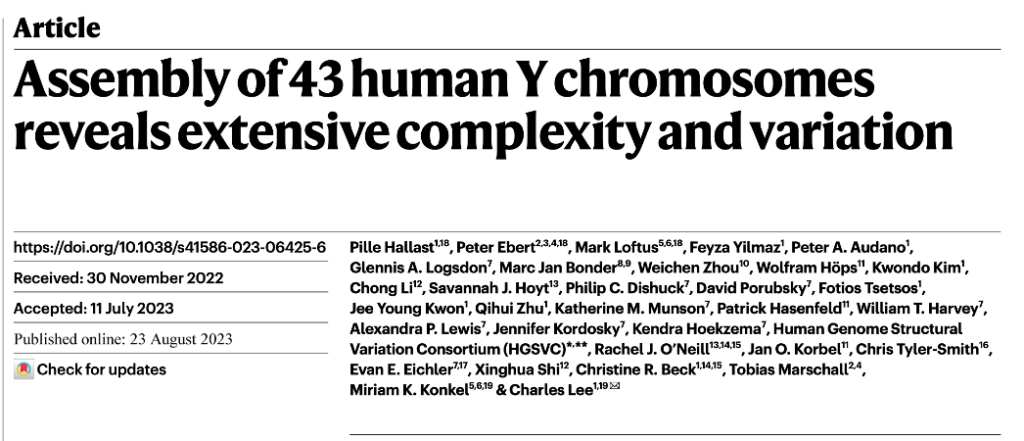2023年8月31日
この HP で何度も紹介しているように、膵臓ガンの特徴は極めて強い間質反応にあり、線維芽細胞が増加するとともに、コラーゲンを中心にマトリックスの過生産が起こり、組織は「硬い」とよく表現される。そして、この強い間質反応が、膵臓ガンの治療成績が30年間改善せず、極めて悪性のガンとされる理由の一つとなっている。
今日紹介するオーストラリアの創薬ベンチャー Pharmaxis と Garvan 医学研究所を中心とした国際チームからの論文は、間質を標的として細胞画のマトリックスを低下させる薬剤の開発についての論文で、8月28日 Nature Cancer にオンライン掲載された。タイトルは「A first-in-class pan-lysyl oxidase inhibitor impairs stromal remodeling and enhances gemcitabine response and survival in pancreatic cancer(新規の Panlysyl oxidase 阻害剤は膵臓ガンのストローマを再モデル化し、ゲニシタビンの効果を高め、生存期間を延長できる)」だ。
上に述べたように、膵臓ガンを抑制するために間質のマトリックス合成を抑えてみようと考えるのは当然の帰結で、コラーゲンやエラスチンの重合に関わる lysyl oxidase の機能阻害剤を用いる治療の開発が進められてきたが、明確な結論には至っていなかった。
この研究では、これまでの阻害剤が、4種類ある Lysyl oxicase(LOH) のうち一部しか阻害できないのが問題ではないかと考え、すべての LOH に効果がある薬剤 PXS-5505 を開発した。ラットを用いた薬剤動体や、副作用テストの結果は上々で、経口投与でガン組織に速やかに到達し、6ヶ月追跡で問題になる毒性は見られなかった。
LOH はガンが発現しているわけではなく、周りの間質組織が発現する。実際にこの分子がガン治療の標的になるのかを確認する意味で、ガン患者さんのデータベースから、ガン組織での LOH 発現量が高い人と低い人に分けて予後を調べると、高い人は明らかに生存率が低い。すなわち、ガンに直接効くわけではないが、ガン治療を補助する意味で、治療に使える可能性はある。
そこで、マウス膵臓ガンモデルを用いて、PXS-5505 の効果を調べている。このモデルでも、ガン組織の LOX は正常組織の10倍以上で、人間の膵臓ガンに近い。この組織でのコラーゲン沈着を試験管内で PXS-5505 が抑えられることを確認し、治療実験に進んでいる。
繰り返すが、PXS-5505 はガンに直接効くわけではないので、これを投与してもガン増殖に変化はないが、膵臓ガンでよく使われるゲムシタビン(gem)と組み合わせると、gem 単独より生存期間を伸ばすことができる。実際、PXS-5505 投与ではガン周囲の間質反応を抑えることに成功している。
最後に、ヒト膵臓ガンを脾臓に移植して、増殖や転移を調べる実験系を用いて、PXS-5505 は gem と併用することで、肝臓への転移を gem 単独より強く抑制できることを示している。
マウス膵臓ガンモデルで PXS-5505 を投与すると、それだけでガン組織への血流量が増加することも観察しており、これらの結果から、膵臓ガンの間質反応により薬剤のガンへの浸透が妨げられているので、gem の効果を高めていると考えられる。一方、免疫系細胞の浸潤については、残念ながら効果はあまりなく、免疫療法との併用が可能かは今後の課題になる。
結果は以上で、今後人間に使うことになるが、マウス実験から見ても根治につながるものではないが、間質を標的にした治療という意味で、期待したいと思っている。
2023年8月30日
抗原と結合する部位だけでなく、抗体の Fc 部分は様々な機能を持っている。補体を活性化して細胞を溶かすのもこの部分の機能だし、また何よりも抗体が他のタンパク質と比べて血中に存在できる期間が長いのも全て Fc 部分のおかげだ。ただ一方で、Fc 部分を認識する受容体の中にはリンパ球の機能を抑制する FcγRIIB 分子もあり、これがガン免疫を担う細胞で発現すると、抗体によるガン治療を抑制する可能性が指摘されてきた。ただ、ガンを攻撃するキラー細胞が FcγRIIB を発現するかどうかは議論が続いており、また PD-1 治療も問題なく行えているので、臨床的にはあまり問題ないと考えられてきた。
今日紹介する米国・エモリー大学からの論文は、人間の CD8キラー細胞の一部には FcγRIIB が発現しており、ガン免疫効果を低下させていることを示した研究で、8月23日号 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「FcγRIIB expressed on CD8 + T cells limits responsiveness to PD-1 checkpoint inhibition in cancer(CD8陽性T細胞が発現している FcγRIIB は PD-1 チェックポイント阻害ガン治療を抑制する)」だ。
この研究ではまず、FcγRIIBが割合は少ないが確かに末梢血の CD8 陽性細胞に発現していることを確認した後、ガン局所で様々な炎症性サイトカインを分泌する主要な細胞であることを明らかにしている。キラー活性で見ると、FcγRIIB 陽性も、陰性も同じような能力があるが、そこに強い炎症を誘導できるのは FcγRIIB 陽性細胞であること言う結論だ。もし炎症誘導がガン抑制に重要だとすると、治療抗体の Fc 部分により FcγRIIB が刺激され、ガン抑制効果が低下する可能性がある。
この可能性について、今度はマウスに移植したガンに対するチェックポイント治療実験を行い、FcγRIIB ノックアウトマウスではチェックポイント効果が高いこと、さらに PD-1 抗体を投与するときに、FcγRIIB の機能を阻害する抗体を投与すると、チェックポイント抗体の効果が高まることを明らかにしている。
実際には、ガンの種類を変えたり、FcγRIIB に対する抗体を変えたりして様々な実験を繰り返し、間違いなく FcγRIIB がチェックポイント治療効果にネガティブに働いていると結論している。
最終的には人間でも同じかは明確ではないが、チェックポイント治療を受けた人では FcγRIIB 細胞が減少することから、少なくとも使った抗体が FcγRIIB 陽性 CD8T 細胞の増殖を抑制していることは確かそうだ。
以上の結果から、チェックポイント治療に FcγRIIB 受容体に対する抗体を必ず組み合わせよと言うのは乱暴だろう。FcγRIIB と Fc との結合は交代のサブクラスによって違うので、これが正しいとすれば、今後は FcγRIIB 刺激性の低い Fc にして使用すればいいだろう。
臨床的には解決可能で重大な問題ではないが、いずれにせよ長年の問題には終止符が打たれた。
2023年8月29日
奄美のトゲネズミのようにY染色体がなくてもオス・メスの区別ができ、Y染色体なしで正常に性生殖が可能なので、Y染色体は将来滅亡する運命にあるというお話は、一般メディアによく取り上げられる話題だ。しかし、マウスY染色体の完全配列が決まり、Y染色体で独自に遺伝子増幅が進み、多様化していることがわかると(https://aasj.jp/news/watch/2485 )、消滅説のような単純な考えは完全に否定され、染色体の中でも最も多様性が高い染色体として様々な機能があるように思える。
考えてみると、人間の男らしさは多様で、しかも人種やY染色体のタイプとも相関が強い。要するに人間でもY染色体の完全ゲノムを解読し、その多様性の程度を調べることは、人間のY染色体の運命を知る意味で重要だ。しかし人ゲノムがほぼ完全に解読された今でも、Y染色体をテロメアからテロメアまで完全に解読することができていなかった。
これはY染色体には膨大な数の重複配列が存在するため、リピートを完全に読み切ることが難しいからだ。すなわち、現在一般に用いられる次世代シークエンサーでは読めるストレッチが短いため、リピート配列には歯が立たない。この問題を、single moleculeシークエンサーを組み合わせてようやく解決し、95%以上Y染色体ゲノムを解読した論文が8月23日 Nature にオンライン掲載された。
ただ、今日紹介したいのはこの論文ではなく、同じ時 Nature に Jakson研究所から発表された、43人のY染色体を single moleculeシークエンサーを合わせて、それぞれほぼ完全に解読、比較した以下の論文を紹介したい。この研究のポイントは、21種類のY染色体のタイプ(ハプログループ)を代表する43人を選んでいる点で、このハプログループの関係から、18万年前ホモサピエンスがまだアフリカで暮らしていた時以来の歴史を追いかけることができることだ。
このように、人類史とY染色体を重ね合わせた面白い研究なのだが、研究の真髄を味わおうとするとY染色体の場合、かなり専門的なゲノム知識が必要で、実はこの論文も紹介するのが極めて難しい。そこで、今日は論文に即して紹介するのをやめ、面白いと思ったポイントだけを紹介する。
まず、Y染色体はオープンな染色体構造(ユークロマチン)の中に、閉じたクロマチン(ヘテロクロマチン)が点在する前半部分と、完全にヘテロクロマチンだけの後半部分に分かれ、機能的遺伝子は前半にしか存在せず、後半は繰り返し配列からできている。
男性の多様性という目でこの染色体を見ると(勝手な見方をお許しあれ)、まず全体の長さがまちまちなのに驚くが、長さの違いは特に後半のヘテロクロマチン部分に集中している。
長さに大きな差はないが、前半のユークロマチン部分も多様性では負けていない。構造的変異、挿入欠失、そして単一塩基の違いを比べると、1Mbあたりそれぞれ、1.9個、165個、994個と驚くべき数だ。
この構造変化の中心は逆位で、その部分のゲノムの向きが逆さまになっている。こんなことが起こるのは、Y染色体には対立遺伝子が存在せず、組み替えでもとに戻ることがないためだ。ただ、人間の歴史の過程で固定してほとんどのハプログループに存在する逆位部分がある。詳しい説明は専門的になるので省くが、これは染色体の交換を抑制し、ゲノムを守る役割があると考えられる。
マウスの解析により、Y染色体上の遺伝子の中にはコピー数の大きな多様性がある遺伝子が示されているが、人間でもTSPY遺伝子は23個から39個までコピー数の多様性が見られる。
後半のヘテロクロマチン領域には機能的遺伝子はなく、ザクっと言うと171塩基配列を持つDYZ3と呼ばれる繰り返し配列に、170塩基からなる α繰り返し配列が組み合わさってできている。当然、長さも違うし、組み合わせも異なる大きな多様性が存在する。これは組み換えのないY染色体でも、繰り返し配列が存在すると遺伝子変換が起こりやすく、多様性の原因になる。
以上が私が勝手に選んだこの論文のポイントだが、読めば読むほどY染色体は多様化するようにできている。この多様化を見ると、遺伝子が存在しないから後半のヘテロクロマチン領域は消失する運命などと言えるはずがない。おそらく、この遺伝子のない多様化も、男性の多様性になんらかの役割をしていると言えないだろうか。
大谷選手や、世界陸上を見ていると、Y染色体がないと到達できない頂点があるように思える。おそらく人間が多様性を維持する限り、Y染色体による男性の多様性も維持されていくと思う。
2023年8月28日
昨日に続いて、ノンコーディングRNAが関わる論文を紹介する。フランクフルト大学からの論文で、なんと歳をとると心臓と神経系の連結が低下することを示し、それにマイクロRNAと呼ばれる翻訳制御に関わるRNAが関与することを示した研究だ。タイトルは「Aging impairs the neurovascular interface in the heart(老化は心臓の神経血管接点に大きく影響する)」で、8月27日号 Science に掲載された。
心臓には交感神経、副交感神経、そして感覚神経が投射しおり、痛みを感じたり、胸をときめかせたりしている。確かに歳を重ねると、胸のときめきはなくなっては来るが、心臓に分布する神経数が低下するとは思っても見なかった。しかし、副交感神経、交感神経ともに、活動が低下すると不整脈になることが知られていることから、神経支配の低下はときめかないでは済まない深刻な影響があるらしい。
この研究ではまず、老化マウスでは心臓に分布する神経数が左心室特異的に大きく低下していることを発見している。右心室では若者と比べて差はない。同じ心室でこれほどの差があるとは予想外の発見だ。しかも、三種類すべての神経で数が低下している。
この原因を遺伝子発現と組織学を組み合わせて追求し、老化マウスでは神経との接合を排除する semaphorin3(sema3) の血管内皮での発現が上昇していることを発見する。神経数の減少に sema3 が関わっていることを確認するため、内皮で sema3 を過剰発現させると、神経数は減少するし、逆にノックアウトすると心臓へ分布する神経数が上昇することも確認している。
ではなぜ老化により心室血管の sema3 が上昇するのか?このメカニズムを追求し、sema3 の遺伝子翻訳を低下させるマイクロRNA、miR143/145 の発現が老化により低下し、sema3 のタンパク質量が上昇してしまうこと、そして miR143/145 を低下させているのが、血管内皮の細胞老化であることを発見している。
残念ながらなぜ細胞老化により miR143/145 が低下するのか、また老化はあらゆる血管内皮で起こっていいのに、どうして心室血管特異的なのかといった問題については議論できていない。代わりに、以前紹介したことがある dasanitiv(広いスペクトラムのリン酸化阻害剤)と抗酸化のためのケルセチンを投与して老化した細胞を積極的に除去する処理を18ヶ月齢から始めると、miR143/145 の低下が抑えられ、結果神経分布の減少を抑えられること、そしてその結果、神経密度減少により誘発されると考えられる心臓の交感神経、副交感神経のバランスが正常化して不整脈の危険性が抑えられることを示している。
結果は以上で、なぜ左心室だけでこのメカニズムが働くのかについての説明がなくフラストレーションが残るが、しかし神経密度が半数になるというのは驚きの話だった。
2023年8月27日
無菌マウスは一般的に太らないことが知られており、細菌叢が我々のカロリー摂取を高めてくれていることがわかる。「なに!太らされるとは許せない」と考えられるかもしれないが、太るほど食べられる様になったのは最近のことで、人間が食うや食わずの時代には、細菌のおかげで栄養が摂取できていたと言える。実際、細菌叢は植物繊維を脂肪酸に変えてくれるし、腸上皮での脂肪摂取も高めてくれることが知られている。
今日紹介するテキサス・サウスウェスタン大学と中国・浙江大学からの共同論文は、細菌叢が脂肪代謝を高めるちょっと変わった毛色の存在を示唆する研究で、8月25日号 Science に掲載された。タイトルは「The gut microbiota reprograms intestinal lipid metabolism through long noncoding RNA Snhg9(腸内細菌叢は小腸の脂肪代謝を長鎖ノンコーディングRNAのSnhg9を介してプログラムし直す)」だ。
この研究は無菌マウスと通常のマウスの象徴上皮の遺伝子発現を比べるところから始まり、細菌叢が形成されることで発現が低下する遺伝子の中で Snhg9遺伝子がトップに来ることを発見する。
Snhg9 は、翻訳される遺伝子ではなく、長鎖ノンコーディングRNAと呼ばれる機能的RNAの一群に属している。ノンコーディングRNAはDNAからタンパク質まで様々な分子と反応して多様な機能を発揮することが知られているが、この研究ではタンパク質と結合するRNAではないかと仮説を立て、Snhg9 と結合するタンパク質を探索した結果、これまで細胞分裂や、細胞死に関わることが知られており、またヒストン脱アセチル酵素SIRT1の抑制因子として知られるCCAR2分子が見つかった。
生化学的研究、および Snhag9 を過剰発現する実験から、Snhg9 が CCAR2 と結合することで、CCAR2 と SIRT1 との結合が阻害され、結果 SIRT1 の活性が上昇することを明らかにした。SIRT1 は様々な分子のエピジェネティック制御因子だが、脂肪代謝のマスター分子と言える PPARγ を抑制することが知られており、Snhag9 の発現は、SIRT1 の活性をレスキューすることから、PPARγ の発現を抑えると予想される。結果は予想通りで、Snhag9発現により PPARγ発現が抑えられることを確認している。
さらに Snhag9発現により脂肪代謝の変化が起こるか、小腸の上皮で Snhag9 を過剰発現するトランスジェニックマウスを作成し、脂肪の吸収が抑えられるとともに、高脂肪食を摂取しても体重の増加や代謝異常が起こらないことを確認している。
以上、阻害分子の阻害の阻害といったわかりにくい話だが、無菌動物では Snhag9 の発現が上昇しているために、PPARγ の機能が抑えられ、脂肪代謝が低いレベルで維持されるという話になる。逆に、細菌叢が成立すると、Snhag9発現を抑えて、PPARγ の発現が上昇するため、脂肪代謝が上昇して、太ることになる。
最後に、細菌叢による上皮の Snhg9発現抑制メカニズムを探り、ホストと細菌叢の相互作用に関わる3型自然リンパ球が IL22 や IL23 を分泌して上皮を刺激することで、Snhg9 の発現が抑えられることを示している。
以上が結果で、面白い仕組みだが、実際に人間で存在するのかを、オルガノイド培養などを用いて確認する必要があるそして、なぜ無菌条件で Snhg9 がわざわざ発現して脂肪代謝を抑えている必要があるのか、この進化的理由がわからないと、この現象を完全に理解することはできない。
2023年8月26日
ミトコンドリアはそれ自身で独立して増殖し、遺伝形式は母親からのみ伝わる。しかし、ミトコンドリアゲノム自体には、ミトコンドリア特異的なリボゾームRNA やトランスファーRNA を含めて37個程度の遺伝子しか存在せず、その活動に必要な遺伝子の多くは、核に存在するゲノムに依存している。このホストとの複雑な関係が、ミトコンドリア異常の理解を難しくしている。
ミトコンドリアの数は細胞の様々な機能を左右するためその調節は重要だが、問題を複雑にしているのが、ミトコンドリアゲノム自体突然変異率が何十倍も高く、その結果ゲノムに変異が起こったミトコンドリアが正常ミトコンドリアと混ざって存在するヘテロプラスミーと呼ばれる状態が存在することだ。母親の生殖細胞形成時に強い選択は存在するが、それでもヘテロプラスミーは母親から遺伝子する。ところがその子供を調べると、ヘテロプラスミーの割合がまちまちで、ミトコンドリア異常による症状も、子供の間で大きく違ってしまうと言う複雑性の原因となっている。
今日紹介するマサチューセッツ工科大学からの論文は、UKバイオバンクなどに登録された30万近い人たちのゲノム解析から、血液細胞に存在するミトコンドリアの数に絞って、数の変化、ヘテロプラスミー、そしてそれを調節する核内ゲノム遺伝子について大規模な解析を行った研究で、8月16日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Nuclear genetic control of mtDNA copy number and heteroplasmy in humans(ミトコンドリアDNAのコピー数とヘテロプラスミーについての遺伝的調節)」だ。
短い断片を解読して集めるゲノム配列決定から、細胞あたりのミトコンドリアの数を調べることができる。この研究では、ゲノム配列データから、正常ミトコンドリアと、変異ミトコンドリアの数についてまず調べ、
血液では一つの細胞に60個程度のミトコンドリアが存在するが、この数は老化とともに低下する。
明らかにミトコンドリア異常と言える症状が見られるケースは、200人に一人ぐらいの割合で存在し、その多くでヘモグロビンA1c が高い糖尿病、難聴、視覚障害が見られる。したがって、この様な軽度障害を調べれば多くのミトコンドリア異常症が存在すると言える。
ヘテロプラスミーの存在しない人間はほぼいないといってよく、これらはミトコンドリアでの変異頻度の高さを反映している
ミトコンドリア変異も挿入や欠損を伴う大きな変化と、単一塩基の変化が存在するが、面白いことに挿入欠失型は母親から遺伝しているケースがほとんどである一方、単一塩基変異は遺伝しないものが多い。
血液のミトコンドリア数は変化が大きいが、これを忘れると間違ったミトコンドリア異常の診断が行われてしまう。これまでミトコンドリア数の減少との相関が指摘された心臓疾患の多くは、炎症が起こったため血液細胞の構成が変化したことによる2次的変化であることがこの研究で分かった。
この様にミトコンドリアの数の変化は、同じ集団のゲノムデータで、数を決めている遺伝子と相関を求めることができる。この研究ではまずミトコンドリアの数の決定に関わる遺伝子をリストし、それぞれの分子の機能をデータサイエンス的に調べている。詳細は省くが、それぞれの遺伝子は当然ミトコンドリア異常症につながる可能性があり、重要だ。いくつかの例が挙げられているが、例えば chM:302 と呼ばれる長さが多様なミトコンドリアが半数の人に維持されるメカニズムについて説明しているが、専門的なので興味ある人はぜひ論文を読んでほしい。ヘテロプラスミーが維持される様々なメカニズムについて考察されている。
結果は以上で、ミトコンドリアの数の調節機構の重要性がよくわかる研究で、今回リストされた遺伝子について、さらに研究が進むことで、少なくとも一部のミトコンドリア異常症の治療法の衣鉢につながるかもしれない。
2023年8月25日
この10年間でバーコード技術や、マイクロフルイディックス技術が大きく進歩した結果、Single cell レベルの遺伝子発現、ゲノム、さらにはエピゲノム解析などは特に珍しくなくなった。しかし、これらの技術は採取したフレッシュな組織か、あるいは急速凍結した組織からの細胞や核に限られていた。逆に言うと、大学や研究機関でこれまで集められ、保存されてきた膨大な数の固定標本は、この様な解析に使えないことを意味している。
今日紹介するテキサス・MDアンダーソンがん研究所からの論文は、少なくとも30年近く経った、フォルマリン固定後パラフィン包埋された組織から単一核を取り出し、ゲノム解析を可能にし、術後長い経過を経て再発した乳ガンの進化を追いかけた研究で、8月15日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Archival single-cell genomics reveals persistent subclones during DCIS progression(長く保存された標本の single cell ゲノミックスは限局した乳ガンの進展で見られる持続的サブクローンの存在を明らかにする)」だ。
この研究のハイライトはなんといっても、フォルマリン固定パラフィン包埋標本から核を分離し、一定のクオリティーに達した核に含まれるゲノム配列を解析する方法を確立したことだ。プロトコルについて紹介すると、パラフィン包埋ブロックを脱パラフィン処理した後、核を分離、DNA染色後セルソーターで品質をチェック、ほぼ完全な核のみ一個づつ50nlのマイクロウェルに入れる。このマイクロウェルの中で、まず核を溶解して得られたDNAにTn5トランスポゾンによるタグ付けを行い、同時に各ウェルに異なるバーコードを付加した後、PCR増幅を行った後、すべてのウェルのDNAをプールして配列決定を行なっている。
基本的にはバーコードを利用した他の single cell テクノロジーと変わるところはないが、フォルマリン処理された核から本当に十分なゲノム情報が得られるかがこの研究の最大のポイントになる。フレッシュな細胞と、固定した細胞を同じ方法で処理して比較するなど、様々な検証を行い、最終的に30年前に作成された固定包埋組織でも十分 single cell ゲノム解析が可能であることを確認している。
この Arc-Well と名付けられた方法の開発が研究のハイライトだが、Arc-Well の能力を示すのに最も相応しい対象として、ガンが管腔にとどまり浸潤がないと診断し、完全に切除されたDuctal carcinoma in situ (DCIS)が再発した乳ガンについて、原発組織と再発組織の single cell genomics を行なって、ガンの進化を調べている。
結果は最近の乳ガンゲノム研究が示してきた結果と合致しており、まずどんなに限局性で浸潤がなくても、ガン細胞は多様化しており、様々な遺伝子増幅が発生している。また、再発ガンと比べると、様々な進化の様式、例えば特定の経路を通ったクローンだけが再発巣を形成するボトルネックタイプや、手術により散布したと考えられる、数種類のクローンが同時に再発するケース、あるいは原発巣とは無関係のクローンから再発巣が形成されるケースが確認されている。要するに、乳ガンは外科より前にネオアジュバント、アジュバント治療が必要であることを改めて確認させてくれる。もちろん現在の医学でも、この事実に沿った治療が行われている。
他にも様々なクローン解析が行われているが、ときには20年経った後急に再発する様なケースを乳ガン以外にも経験することを考えると、パラフィン包埋標本を蔵から引っ張り出して調べられることは大きな進歩だと言える。
2023年8月24日
75歳を過ぎた今の食欲を考えてみると、体調に左右されるが特に季節性は感じない。勿論食べ物の季節性はある。例えばそーめんはめったに冬食べないし、鍋物は冬に多い。ただ、生理的には動物は寒くなると自然とたくさんの食物をとる。これは、寒さに対抗する熱を発生させるためにエネルギーが必要だからと説明されている。
今日紹介する米国スクリップス研究所からの論文は、寒さに対応して代謝がスイッチすることで起こる行動変化に関わる回路を明らかにした研究で、8月16日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Xiphoid nucleus of the midline thalamus controls cold-induced food seeking(視床正中核内の剣状核が寒さで誘導される食物探求行動を調節している)」だ。
最近の行動脳科学は、どの行動に注目するかが勝負で、後は様々な道具が揃っており、ずいぶん研究はやりやすくなっている。マウスは4度の部屋に移すと、まずジッとしてエネルギーを熱生産に回すのだが、3-5時間ぐらいすると今度は食欲が上昇し、食べ物を探すため動きが増える。すなわち、寒さだけでなく、寒さが持続して代謝が変化したことで、食べ物を求める行動が始まる。
この行動変化のスイッチを入れる脳領域を、脳全体の活動を低温に晒したマウスで記録することで調べると、ほとんどの脳領域では温度が下がると活動が低下するが、視床正中核の剣状核という極めて小さな領域で活動が高まることがわかった。
活動する脳領域が特定されると、後はこの領域を刺激する実験に移るが、剣状核はほとんど研究されておらず、よい分子マーカーもないことから、低温に長時間晒された時興奮した神経をラベルするキャプチャー法を用いて、特異的刺激を行い、この領域の刺激により食欲が上昇するとともに、食を求める行動にスイッチが入ることを明らかにしている。
この領域の刺激による行動をさらに詳しく調べると、常温でいくら刺激しても行動は変化しないことがわかる。すなわち、低温に晒されたときだけ行動変化を誘導していることがわかる。
様々な実験から、このスイッチは剣状核のグルタミン酸作動性ニューロンが担っていることが明らかになったので、次に神経投射実験を投射領域から逆行性に追跡する方法を用いて調べ、いわゆる報酬回路の核になっている側座核へ投射する神経回路によりこの行動が調節されていることを明らかにしている。
結果は以上で、要するに一種の本能行動も、寒さによる代謝変化というコンテクストに応じて合理的に調節されていることを示した面白い研究だ。ただ、温度を下げるだけではこの回路は刺激されないので、どのような代謝変化がこの回路を刺激しているのかは今後の課題と言える。
2023年8月23日
1型インターフェロンには全部で5種類存在する様だが、α、β以外の研究をほとんど読んだことがなかった。1型インターフェロンはガンを含む外来因子に対する第一線の防御機構なので、当然多様化していてもよい。
今日紹介するインターフェロンε (IFNε)についてのオーストラリア・ハドソン医学研究所からの論文は、1型インターフェロンが特殊任務に合わせて多様化していることを改めて認識させてくれた研究で、8月16日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Interferon-ε is a tumour suppressor and restricts ovarian cancer(インターフェロンεはガン抑制因子として卵巣ガンを抑制する)」だ。
この論文を読んで初めて知ったが、IFNε は他の1型 IFN と同じ受容体を使っているにもかかわらず、IFNα、βが悪化させる生殖器のクラミジア感染を抑制する作用があり、生殖器官特異的機能が注目されていた。
この研究ではまず IFNε の発現を調べ、卵巣と子宮をつなぐファロピアン管の上皮特異的に発現していること、そしてその上皮に由来する悪性の高異型度漿液性ガン(HGSC)では全く発現が見られないことを発見する。
この結果から IFNε が HGSC 抑制に関わるのではと着想して、ノックアウトマウスに HGSC を移植すると、ガンの腹膜転移が急速に拡がる。そこで、HGSC を移植したマウスに IFNε あるいは FGNβ を投与する実験を行い、IFNβ に比べて IFNε が遙かに強いガン抑制効果を持つことを発見する。
興味深いのは、IFNε 治療によって腹膜に散種した腫瘍増殖は強く抑制されるのに、卵管に移植した元のガンへの抑制効果が少ないことで、この結果は免疫が誘導されにくいとされてきた HGSC に対する免疫が腹腔では誘導できていることを示唆している。
このメカニズムを調べるため、ガンを移植する側のマウスから IFNε の受容体をノックアウトして移植実験を行うと、IFNε の効果が大きく低下するので、ホストの免疫機構を介する可能性が強く示唆される。
さらに、HGSC細胞株から IFNε受容体をノックアウトして移植すると、ノックアウトされていないガン細胞と同じように増殖が抑制できることから、IFNε の作用はガン細胞への直接効果よりも、ホストの腹腔内での免疫機構を活性化させる効果によることが示された。
結果は以上で、何よりも腹膜播種と呼ばれる HGSC をコントロールする方法が示されたことは大きい。メカニズムから考えると、おそらく他のガンでも腹膜播種が起こった場合はI FNε の効果が見られるのではと期待できる。
臨床的にも重要な研究だが、インターフェロンの進化を考える意味でも面白い分子で、勉強になった。
2023年8月22日
ドーパミンはパーキンソン病で合成が減少することでよく知られているが、実際には運動調節だけでなく、ムードやモチベーションと言った高次脳機能に関わっており、様々な精神疾患との関連も示されている。これらの機能は、パーキンソン病で問題になる黒質線条体経路、モチベーションや感情に関わる中脳辺縁回路、そしてやはり感情などの高次機能に関わる中脳皮質経路により 主に担われている。
今日紹介するハーバード大学梅森研究室からの論文は、黒質から尾状核被蓋 (CPu) に投射している黒質線条体回路と、中脳の復側被蓋野から側座核 (NAc) へと投射する中脳辺縁系回路という、機能が全く異なる2経路が形成されるメカニズムを明らかにした研究で、8月17日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「The projection-specific signals that establish functionally segregated dopaminergic synapses(機能的に分離したドーパミン作動性シナプスを確立するための投射特異的シグナルについての研究)」だ。
この研究ではまず CPu と NAc でのドーパミン作動性のシナプス形成をラットで調べ、ドーパミン作動性のプレシナプスの形成が生後4-10日に完成することを確認する。すなわち、この時期に投射先の細胞からシナプス形成を誘導する重要な因子が分泌されていることを示唆している。実際培養実験で、CPu 由来の因子は黒質由来のドーパミン神経、NAc 由来の因子は復側被蓋のドーパミン神経特異的にシナプス形成を誘導できることを明らかにし、それぞれの投射領域が特異的に黒質由来、及び復側被蓋由来の神経シナプス形成を誘導していることを発見している。
そこで、この経路特異的分子を遺伝子発現の比較から、CPu 由来因子を BMP2 & BMP6、NAc 由来因子を TGFβ2、またこれに反応する受容体も、それぞれの経路のドーパミン神経で特異的発現が見られることを明らかにしている。そして、CPuのBMP2/6をノックダウン、NAcのTGFβ2遺伝子を脳内でノックダウンする実験を行い、予想通りこれらのシグナルが特異的に、各経路のドーパミンシナプス形成を誘導していることを証明している。
次に、ラットからマウスに実験系を移して、BMP2/6 及び TGFβ2 シグナル下流で働くSmad1 か Smad2 をドーパミン神経でノックアウトしたマウスを作成、BMP2/6 及び TGFβ2 シグナルの機能を調べると、予想通り Smad1 KO では黒質線条体回路特異的にシナプス形成が低下、逆に Smad2 KOでは中脳辺縁系回路特異的にシナプス形成が低下することを確認している。そして、これらのマウスでは、神経投射ではなく、生後に進行する成熟シナプス形成が回路特異的に抑制されることを明らかにしている。
この結果、Smad1 をノックアウトしたマウスでは黒質線条体回路でのドーパミン遊離が低下し、行動実験で運動器が傷害されることがわかる。一方、Smad2 ノックアウトマウスでは、運動機能は正常だが、モチベーションが強く抑えられることを明らかにしている。
以上が結果で、発生学に関わってきた経験から言うと、発生因子の本家本元が、しかもそれぞれの経路特異的に発現して、生後の神経発生に関わっていることは驚きだ。さらに成体になってからノックアウト実験を行い、成体のドーパミンシナプス維持にもそれぞれのシグナルが関わっていることを示しており、今後統合失調症を始め様々な精神疾患のメカニズムを知るための新しい観点が提供されたと思う。