


 1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む
1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む 1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む
1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む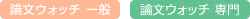 1月18日 肥満で自然炎症が亢進するメカニズム(1月15日 Science 掲載論文)
Covid-19パンデミックで広く知られるようになったが、肥満の人は重症化しやす...続きを読む
1月18日 肥満で自然炎症が亢進するメカニズム(1月15日 Science 掲載論文)
Covid-19パンデミックで広く知られるようになったが、肥満の人は重症化しやす...続きを読む 1月17日 多発性硬化症とEBウイルス研究3題(1月13日 Cell オンライン掲載論文)
このブログでも紹介してきたが、多発性硬化症はEBウイルスにより引き金を引かれるこ...続きを読む
1月17日 多発性硬化症とEBウイルス研究3題(1月13日 Cell オンライン掲載論文)
このブログでも紹介してきたが、多発性硬化症はEBウイルスにより引き金を引かれるこ...続きを読む 1月16日 腸内細菌によるガン免疫活性化の極めつけメカニズム(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
腸内細菌、特にセグメント細菌 (SFB) と呼ばれる分節した繊維状形態をとる細菌...続きを読む
1月16日 腸内細菌によるガン免疫活性化の極めつけメカニズム(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
腸内細菌、特にセグメント細菌 (SFB) と呼ばれる分節した繊維状形態をとる細菌...続きを読む 1月15日 eGENESIS社のブタ腎臓に対する免疫反応:1報告(1月8日 Nature Medicine オンライン掲載論文)
昨年注目された医学の進歩の一つは、69種類の遺伝子改変を加えたブタ腎臓を移植され...続きを読む
1月15日 eGENESIS社のブタ腎臓に対する免疫反応:1報告(1月8日 Nature Medicine オンライン掲載論文)
昨年注目された医学の進歩の一つは、69種類の遺伝子改変を加えたブタ腎臓を移植され...続きを読む 1月13日 炎症性腸疾患での線維化メカニズム(1月7日 Nature オンライン掲載論文)
炎症性腸疾患 (IBD) の研究で最近特に目立った研究者の一人がハーバード大学の...続きを読む
1月13日 炎症性腸疾患での線維化メカニズム(1月7日 Nature オンライン掲載論文)
炎症性腸疾患 (IBD) の研究で最近特に目立った研究者の一人がハーバード大学の...続きを読む 1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む
1月20日 脳内での強化学習過程を海馬の場所細胞から探る(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
私たちのNPOの理事の一人の呼びかけで「AI x 生命科学」と名付けた勉強会を行...続きを読む 1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む
1月19日 頭蓋骨髄中の白血球に脳へ薬剤を運ばせる(1月16日 Cell オンライン掲載論文)
この10年中国の研究力は急速に高まっており、毎日論文を読んでいるとそのことを強く...続きを読む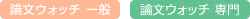 1月18日 肥満で自然炎症が亢進するメカニズム(1月15日 Science 掲載論文)
Covid-19パンデミックで広く知られるようになったが、肥満の人は重症化しやす...続きを読む
1月18日 肥満で自然炎症が亢進するメカニズム(1月15日 Science 掲載論文)
Covid-19パンデミックで広く知られるようになったが、肥満の人は重症化しやす...続きを読む 1月17日 多発性硬化症とEBウイルス研究3題(1月13日 Cell オンライン掲載論文)
このブログでも紹介してきたが、多発性硬化症はEBウイルスにより引き金を引かれるこ...続きを読む
1月17日 多発性硬化症とEBウイルス研究3題(1月13日 Cell オンライン掲載論文)
このブログでも紹介してきたが、多発性硬化症はEBウイルスにより引き金を引かれるこ...続きを読む 1月16日 腸内細菌によるガン免疫活性化の極めつけメカニズム(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
腸内細菌、特にセグメント細菌 (SFB) と呼ばれる分節した繊維状形態をとる細菌...続きを読む
1月16日 腸内細菌によるガン免疫活性化の極めつけメカニズム(1月14日 Nature オンライン掲載論文)
腸内細菌、特にセグメント細菌 (SFB) と呼ばれる分節した繊維状形態をとる細菌...続きを読む 1月15日 eGENESIS社のブタ腎臓に対する免疫反応:1報告(1月8日 Nature Medicine オンライン掲載論文)
昨年注目された医学の進歩の一つは、69種類の遺伝子改変を加えたブタ腎臓を移植され...続きを読む
1月15日 eGENESIS社のブタ腎臓に対する免疫反応:1報告(1月8日 Nature Medicine オンライン掲載論文)
昨年注目された医学の進歩の一つは、69種類の遺伝子改変を加えたブタ腎臓を移植され...続きを読む 1月13日 炎症性腸疾患での線維化メカニズム(1月7日 Nature オンライン掲載論文)
炎症性腸疾患 (IBD) の研究で最近特に目立った研究者の一人がハーバード大学の...続きを読む
1月13日 炎症性腸疾患での線維化メカニズム(1月7日 Nature オンライン掲載論文)
炎症性腸疾患 (IBD) の研究で最近特に目立った研究者の一人がハーバード大学の...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 23 カントの生物観―ジェニファー・メンシュ著「Kant’s Organicism」の紹介。
1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。とい...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 23 カントの生物観―ジェニファー・メンシュ著「Kant’s Organicism」の紹介。
1年間カントの著作を読んできたが、そろそろカントについて書く気になってきた。とい...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書22回:番外編 ChatGPTと実験哲学あるいは合成哲学の可能性
デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これま...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書22回:番外編 ChatGPTと実験哲学あるいは合成哲学の可能性
デヴィッド・ヒュームについて書いて以来、ずっとカントの著作と格闘している。これま...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 20回 バークリー:世界を仮想現実と言い切った反科学哲学
イギリス経験論の哲学者として、教科書的には、イングランドのジョン・ロック、アイル...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 20回 バークリー:世界を仮想現実と言い切った反科学哲学
イギリス経験論の哲学者として、教科書的には、イングランドのジョン・ロック、アイル...続きを読む 生命科学の目で読む哲学書 19回 ジョン・ロック:脳科学の始まりと言えるかもしれない
17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒ...続きを読む
生命科学の目で読む哲学書 19回 ジョン・ロック:脳科学の始まりと言えるかもしれない
17世紀を代表する大陸合理主義哲学を終え、今回から、ロック、バークリー、そしてヒ...続きを読む 17世紀近代哲学誕生はガリレオに負うところが大きい( 生命科学の目で読む哲学書 18回 )
17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む...続きを読む
17世紀近代哲学誕生はガリレオに負うところが大きい( 生命科学の目で読む哲学書 18回 )
17世紀を振り返る最後に、ガリレオ・ガリレイに登場いただこう。生命科学の目で読む...続きを読む なぜスピノザだけが「エチカ=倫理」を書けたか?(生命科学の目で読む哲学書第17回)
なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしに...続きを読む
なぜスピノザだけが「エチカ=倫理」を書けたか?(生命科学の目で読む哲学書第17回)
なかなか生命科学の目からスピノザを位置づけられたという気になれず、延ばし延ばしに...続きを読む 17世紀近代科学誕生に関わった人たち: ライプニッツのモナド論を現代的視点から読み直す (生命科学の目で読む哲学書 16回)
今回は、この歳まで何回かチャレンジして、結局理解できいないまま放置していたライプ...続きを読む
17世紀近代科学誕生に関わった人たち: ライプニッツのモナド論を現代的視点から読み直す (生命科学の目で読む哲学書 16回)
今回は、この歳まで何回かチャレンジして、結局理解できいないまま放置していたライプ...続きを読む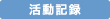 京都大学野生動物センター・熊本サンクチュアリーの寄付活動に応援メッセージを寄せました。まだ募集中なので、是非皆様もご寄付お願いします。
寄せた文章は以下のサイトでご覧になれます。 https://readyfor.j...続きを読む
京都大学野生動物センター・熊本サンクチュアリーの寄付活動に応援メッセージを寄せました。まだ募集中なので、是非皆様もご寄付お願いします。
寄せた文章は以下のサイトでご覧になれます。 https://readyfor.j...続きを読む