昨日、東大の河岡さんたちがThe New England Journal of Medicineに発表した、猫が新型コロナウイルスに感染しやすいことを示した論文がメディアの話題になっている。
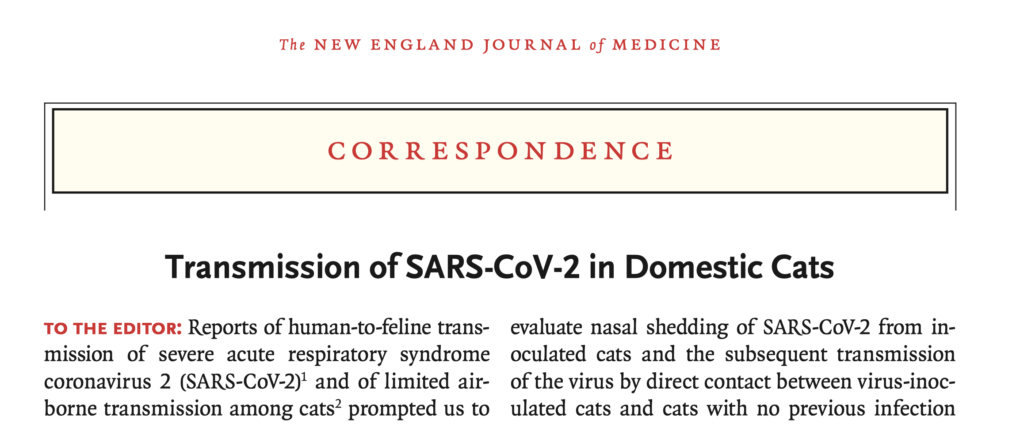
詳しくは記事を読んでもらえばいいと思うが、このウイルスが私たちの身近にいる動物にも感染できるとすると、今後のコロナ対策も全く違ったものになるだろう。
この問題は中国でも強く懸念されており、35種類の動物から1,300以上の血清を集めて、抗体検査を行った論文すら発表されている。
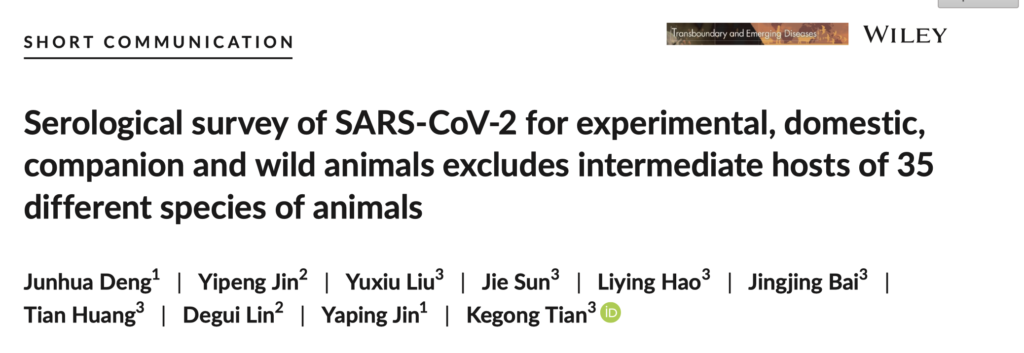
幸い結果は全て陰性で、動物がこのウイルスのキャリアーとなる心配はないと言う結論だ。事実、先の猫への感染実験でも、河岡さんたちは、猫が感染しやすいとはいえ、ウイルスを排出する期間は短く、発症もしないので普通の状態で猫がキャリアになることはないだろうとコメントしている。すなわち、現在のコンセンサスは、ペットから新型コロナウイルスがヒトへと伝搬する危険性はほとんどないと言うものだが、話はそれほど簡単ではないことを示唆する論文が、香港大学から5月13日Nature Medicineにオンライン掲載された。
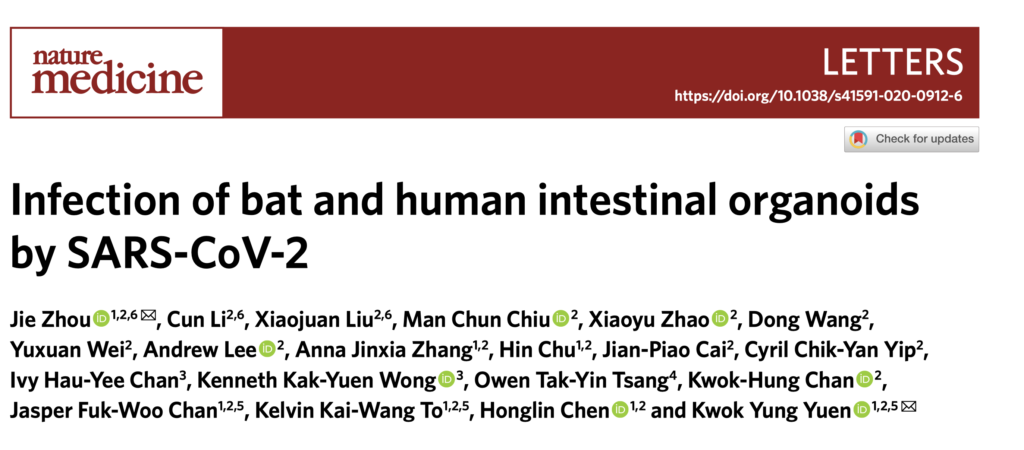
この研究では、ヒトとコウモリの腸上皮細胞をオルガノイド法と呼ばれる方法で培養し、ヒトの鼻粘膜から採取した新型コロナウイルスを感染させる実験を行なっている。
このオルガノイド培養は、現在慶応大学医学部の佐藤(俊朗)さんが開発した方法で、細胞から立体的な腸組織を再構成する方法で、フレッシュなヒト組織の代わりとして消化管の研究にはなくてはならない方法になっている。
この研究では、同じオルガノイド法で、コウモリの腸組織を試験管内で一定期間維持することができることをまず示し、試験管内で新型コロナウイルスを感染させた。驚くなかれ、ヒト鼻粘膜から調整したばかりの新型コロナウイルスはコウモリの腸組織に感染し、ヒトの腸オルガノイドを用いたのと同じぐらいの効率でウイルスを排出する事が示された。すなわち腸上皮細胞であれば、猫どころか、コウモリの細胞にすら新型コロナウイルスはそのまま感染する事になる。この結果は、コウモリのACE2とTMPRSS2も、新型コロナウイルスの感染の入り口として機能する事を示している。要するに、新型コロナウイルスは、そのままで広い範囲の哺乳動物に感染できる可能性が示された。
恐ろしい話だが、十分可能性がある事を示す論文が南京大学から5月13日にJournal of Virologyにオンライン出版された。

この研究では、ウイルスが細胞に感染するときに使うスパイクタンパク質と、その受容体ACE2との結合について構造解析を行い、ヒトACE2と比べた時、他の動物のACE2にもウイルスのスパイクが結合できるか、アミノ酸配列から理論的に考察している。
研究で行われたのは、構造解析からわかっているヒトACE2がスパイクタンパク質と直接コンタクトする20アミノ酸について、他の種のACE2と比較している。理論的可能性だけで、直接結合を調べた研究では無いので評価は難しいが、ヒト感染性の新型コロナウイルスを発生させた主として疑いをかけられているコウモリも、センザンコウも含めて、新型コロナウイルス感染は広い種に感染する可能性があると結論している。
以前、中国のグループがイヌ、ブタ、ニワトリ、ガチョウ、ネコ、フェレットに新型コロナウイルスを感染させる実験を行い、フェレットとネコ以外はほどんど感染できない事を示していた。
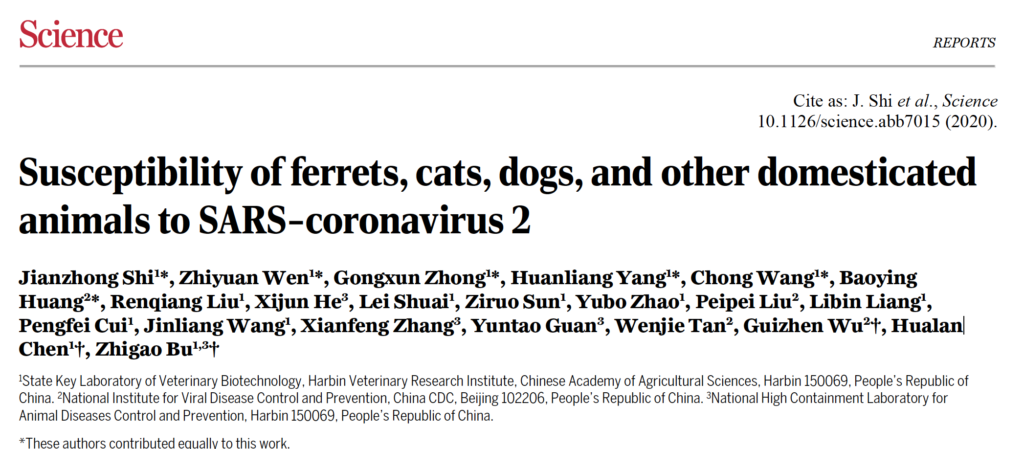
しかし、これは経鼻的に感染させた時の感染効率を調べた実験で、動物コロナウイルスのほとんどは消化管感染の方が多い事を考えると、消化管も含めて新型コロナウイルスの動物への感染がないのかは、しっかり調べた方がいいように思う。
新型コロナウイルスは、不顕性感染が多い事、発症から重症化までの時間が短い事、血管炎を伴う事など、インフルエンザなどとは全く質の異なる扱いにくさを持っているが、この上に様々な動物への感染のし易さが加わるとすると、ポストコロナに備えたこれまで以上の対応が必要になるだろう。
例えば鳥インフルエンザのように、新型コロナの場合も私たちの周りにいる動物の感染状態については、定期的なモニタリングが、次の流行に備えるために必要だと思う。その時、様々な動物の消化管や呼吸器のオルガノイド培養が重要な鍵を握るような気がする。わが国のもう一つのお家芸が役に立つ時がきたようだ。



