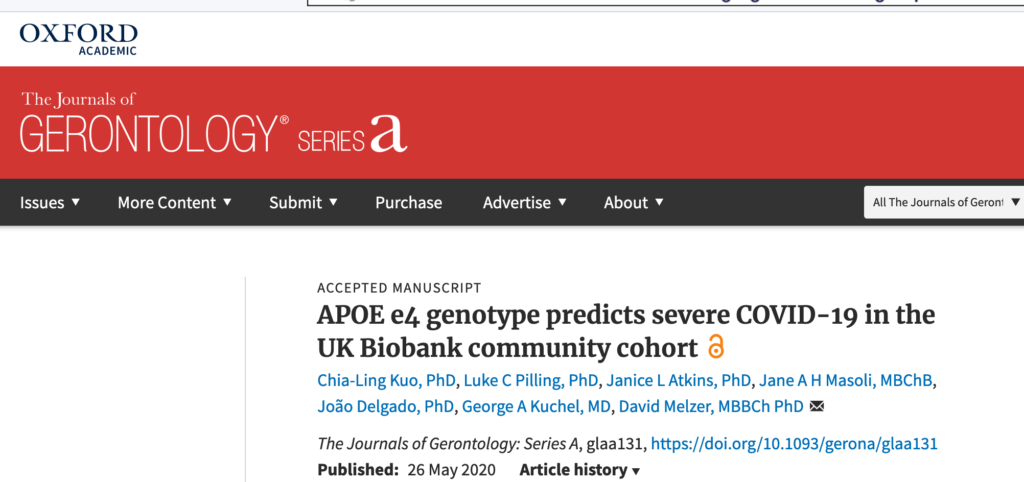2020年5月31日
18世紀、生命現象を物理的因果性と比較しながら考えるNatural Historyが発展し、この延長に19世紀のダーウィンが生まれるが、Natural Historyの生命についての結論は「自然目的により組織化されている点で、物理的因果性とは異なる有機体とするカントの有機体論」で止まったように思う。カントが終着点とは、哲学も科学も渾然としていた時代に見えるが、実際にはカントは科学者といってもいいほど科学への造詣が深かった。
ダーウィンは、この科学とは相容れないように思える自然目的を、彼の進化アルゴリズムで説明した、すなわち目的論を排除したわけだが、進化を考える時に目的や機能といった因果性を頭の中から排除することは難しい。というのも、現在の生物のHistoryを考える時、現在の姿が目的になるので、それを排除するのは簡単でない。その意味で、その過程を科学的に説明できるなら、目的や機能といった、厳密に言えば非科学的(?)概念を積極的に取り入れて研究することは問題ないと私は思う。
今日紹介するシカゴ大学からの論文は、ヘモグロビンが現在のα2β2の4量体をなぜ取るようになったのか、現在の形質を目的として過去の分子過程を再構成しようとした論文で5月28日号のNatureに掲載された。タイトルは「Origin of complexity in haemoglobin evolution (へモグロビン進化過程での複雑性の起源)」だ。
ヘモグロビン(Hb)は4量体を取ることで、酸素の結合と解離を効率よく行えるわけだが、遺伝子配列上の進化という点から見てしまうと、酸素結合性のサイトグロビン、グロビンE、そしてミオグロビンなどの酸素結合性分子と同じ先祖から進化した分子ファミリーとして納得して終わる。
この研究では、ミオグロビンは多量体を形成しないのに、なぜHbは4量体を形成できるのかという問題に置き換えて、遺伝子配列の条件を検討している。すなわち、現在の分子を目的として、その機能を達成するために必要なアミノ酸の変化を追跡しようとしている。通常この目的のためには、現存の多くの生物の中から中間形を探し出し、その遺伝子配列を決定するのがこれまでの方法だったが、この研究では現存のHbの祖先形をコンピュータで推察して、そのタンパク質を再構成し、機能を調べるという、かなり大掛かりな手法を用いている。
まず配列からミオグロビンとHbの先祖型、HbαとHbβ共通の先祖型、そしてHbα、Hbβそれぞれの先祖型のアミノ酸配列を推定して、その情報から先祖型分子を再構成している。このインフォーマティックスについてはちんぷんかんぷんだが、驚くことにミオグロビン先祖型はモノマーだけ、α、βそれぞれの先祖型は4量体を形成できることを示しており、このような手法がかなり進んでいることをうかがわせる。
さらに驚くのは、αβ共通の先祖型を再構成すると、2量体は作れるが、4量体は形成できない。すなわち、モノマー、ダイマー、テトラマーという機能的進化が再構成されている。
あとはこの先祖形の物理化学的性質や構造を詳しく解析、どのアミノ酸を変化させると新しい機能を獲得できるか調べ、まずミオグロビンとの共通先祖形のInterface1と呼んでいる部位に一個突然変異が入ると、酸素結合性はそのままで2量体形成が可能なHbの先祖形が生まれ、次にInterface2と呼ばれる場所にいくつかの変異が蓄積することで、4量体形成が可能になる。これに伴い、酸素結合能は低下するが、これによって酸素を結合したり遊離することが可能になるというシナリオだ。
分子進化というとどうしても配列レベルでの研究を読むことが多かったが、ここまで機能の再構成が可能な面白い実験進化学の領域が出来上がっていることに感心した。
2020年5月30日
APOEには3種類のアイソフォームが存在し、それぞれのアイソフォームは様々な形でアルツハイマー型認知症に関わっている。例えばAPOEのε4アイソフォームはアルツハイマー病のリスクを10倍以上高めることが知られている。一方、稀なアイソフォームだが、クライストチャーチ型変異を持つAPOEによって、アミロイドがどれほど蓄積しても認知症状が出ない老人がいることを示した論文を以前紹介した(https://aasj.jp/news/watch/11677 )が、場合によっては認知症リスクを下げる。
今、私が最も期待している新型コロナの研究分野は、感染や重症化の遺伝的リスクについての論文だ。当然のことながら組織適合抗原については論文が出始めたし、欧米でのゲノム解析が進んでいるので、多くのリスクファクターがわかるのも時間の問題だろう。これによって、個人の感染や重症リスクをあらかじめ知ることができることは大きい。ただ論文として現れるにはまだ少し時間がかかるようだ。
それでもゲノムデータの揃っているコホート研究から断片的な論文は発表されている。例えば50万人規模の英国バイオバンクに登録された人たちも当然コロナに感染し、600人近くの人がPCRで陽性と診断されている。この人たちのAPOEのアイソフォームを調べると、様々なリスクファクターを補正した後でもE4アイソフォームを持つ人がオッズ比で2.5倍ぐらい高いことが示された。これは、すでに認知を発病した人を除いても同じなので、APOE4が感染しやすさのリスクであることを示している。
残念ながらデータはこれだけで、今後診療データを集めた検討が行われることで、重症化などについても相関が見えてくるだろう。ただ、感染性が免疫反応と関わるとすると、E4が免疫を抑えることになるが、ちょっと違和感がある。
実際ほとんど同じ時にNature Medicineにオンライン出版されたロックフェラー大学からの論文では、悪性黒色腫への免疫反応はE4アイソフォームを持つ人の方が高いという結果が示されているので最後に紹介する。
このグループはAPOEのアイソフォームが異なるモデルマウスを用いて、E4の生理活性を調べていたようだ。一つの試みとして、マウスメラノーマを注射してE4と E2アイソフォームのマウスを比べると、E4マウスでは腫瘍の増殖が強く抑えられる。そして、この原因が腫瘍内での免疫系細胞の数に反映されていることを明らかにしている。すなわち、E4マウスでは腫瘍内のキラー細胞やNK細胞の数が高まっている。すなわち抗腫瘍免疫について言えば、明らかにE4アイソフォームの方が良い効果がある。
これが特殊なマウスモデルのせいでないことを示すため、今度はメラノーマ患者さんのデータベースから生存期間とAPOEアイソフォームとの相関を調べると、E4(E3も)アイソフォームは長期間生存するチャンスが大幅に高まっている。
これが免疫系の効果であることは、E4アイソフォームの人ではチェックポイント治療の効果高いことからも推察される。
このように、少なくともガン免疫で腫瘍内への細胞浸潤と腫瘍障害で見たときは、アルツハイマーリスクであるE4も捨てたものではない。おそらく、新型コロナに対してももう少し精密な研究が進めば、より免疫との関わりが見えるだろう。いずれにせよ、早く大規模ゲノム検索結果が発表されるのを心待ちにしている。
2020年5月29日
毎年京大皮膚科学講義で、「皮膚科で習えない皮膚」とタイトルで特別授業を行なっていますが、今年は録画になりました。幸い担当の椛島先生から公開しても良いという許可をいただきましたので、京大の学生さん以外にも公開します。
一般向けではありません。医学を学ぶ学生さんに聞いていただければ幸いです。
第一回:https://www.youtube.com/watch?v=gfxDNanGZv0
第二回:https://www.youtube.com/watch?v=eYjmSVuP0JA
2020年5月29日
ネアンデルタール人ゲノムを最初に解読し、私たちホモ・サピエンスにもネアンデルタール人のゲノムが遺産として伝わっていることを初めて明らかにしたのは、今年日本国際賞を受賞したSvante Pääbo さんだ。この発見のおかげで、私たちのゲノムに流入したネアンデルタール人ゲノム断片の機能を、私たち自身の形質の違いから推察することが可能になった。すなわち、ネアンデルタール人の形質を、私たち人類の多様性の中から拾いだして再構成できる。
今日紹介するSvante Pääboさんたちの論文はネアンデルタール人ゲノム解析と、英国のバイオバンクの情報を結びあわせてネアンデルタール人が安産だった可能性を示す研究でMolecular Biology and Evolutionに掲載された。タイトルは「The Neandertal Progesterone Receptor (ネアンデルタール人のプロゲステロン受容体)」だ。
ネアンデルタール人から受け継いだ多型の中にプロゲステロン受容体のアミノ酸変化を伴う多型が存在する。面白いことに、この多型はヨーロッパ人に多く、アジア人には少ない。この研究では、この多型の中にさらに繰り返し配列の挿入の多型が存在し、これがネアンデルタール人集団の多型を反映していることをまず明らかにしている。すなわち、ネアンデルタール人集団に存在していた多型が、異なる交雑機会を通して、私たちに流入している。
プロゲステロンは妊娠の維持に関わるホルモンなので、次にこの多型が妊娠に関わる形質と関係するか、50万人規模のゲノムと個人形質が集められているUKバイオバンクのデータと照らし合わせている。
まず、この多型があるとほとんどの組織で遺伝子の発現が上昇している。そして、妊娠初期の出血頻度や流産の頻度がコントロールと比べてオッズ非で0.85と低下する。さらに、この多型を持つ人は兄弟姉妹の数も多い。すなわち、母親も同じ多型を持つと考えられるので、兄弟が多いということは、子供が多いことになる。
以上が結果で、ネアンデルタール人から我々に流入したプロゲステロン受容体遺伝子の多型は我々に安産をもたらしたという結論になる。
ではなぜアジア人には安産の遺伝子多型が残っていないのか不思議に思うが、プロゲステロンの作用が強く出ることは、乳がんなどの危険性を上げる可能性があるので、他の遺伝子と組み合わさると当然ネガティブに働く可能性もある。いずれにせよ、一つ一つのネアンデルタール人多型を丹念に調べることの重要性がよく理解できた。
2020年5月28日
新型コロナでも明らかになったが、免疫系が絡む現象は、多様性が著しく、メカニズムが複雑になる。その辺をすっ飛ばして一般の人に説明すると「免疫力」で済ませたり、ワクチンの効果を抗体だけで判断することになる。しかし、脳ほどではないにしても、免疫反応では役者が多く、多くのフィードバック、フィードフォワードサーキットができて、これを理解するには特殊な能力が必要と思えるほどだ。
今日紹介するハーバード大学からの論文はまさに専門外ではストーリーを追うのが嫌になる免疫の複雑性を、しかし楽しく解析している研究で6月11日号のCellに掲載予定だ。タイトルは「An Immunologic Mode of Multigenerational Transmission Governs a Gut Treg Setpoint (免疫様式による世代を超えた伝達が腸内の制御性T(Treg)のセットポイントを決める)」だ。
この研究のコレスポンデンスになっているBenoistは個人的にも知っているが、この複雑な回路を頭の中で描ける特殊な能力を持つ免疫学者の代表だろう。
この研究は、Tregの中でもRORγ転写因子陽性のタイプ(RORγTreg)の腸内での数が、B6マウスとBalb/cマウスで完全に別れ、一見遺伝的に支配されているように見えるが、この数を支配する要因のうち最も大きいのが、母親の影響であるという発見から始まっている。すなわち、B6マウスに育てられると、遺伝的背景にかかわらずRORγTregは多く、Balb/cマウスに育てられるとRORγTregが少ないことがわかった。一種ミトコンドリアの遺伝に似ている。
現在ではRORγTregと腸内細菌叢の研究が進んでおり、RORγTregを誘導する細菌も特定されていることから、この現象は母親から移行する腸内細菌叢の違いで説明することが可能だが、様々な実験から細菌叢そのものの作用は否定している。
面白いことに、RORγTreg数は生まれてから1週間までに決まり、その後安定に続くことから、授乳との関係が示唆される。そこで、可能性をひとつひとつ検討するための実験を繰り返し、RORγTregを誘導する細菌に結合する母乳内に存在するIgAが、腸内でのRORγTregレベルを決めているという結論に到達する。
詳細を省いて、彼の提案するシナリオを紹介すると次のようになる。
腸内でRORγTregレベルは、特定のバクテリアの刺激により維持される。RORγTregが多いと、腸内での免疫反応が抑えられ、IgA分泌は低下するが、この結果バクテリアが増加すると、RORγTregが増加する。このように、IgAを介するフィードバック回路が腸内で成立して一定のRORγTregレベルが維持される。
しかし生まれたばかりの子供にはこの回路は全く存在しない。しかし、腸内でのIgAとRORγTregの回路が乳腺に移行することで、この回路を維持することができるIgAが子供にも伝えられ、このIgAが母親から移行する腸内細菌叢のRORγTreg刺激レベルを設定することで、子供にも大人と同じバクテリアRORγTreg、IgAというサイクルが出来上がり、特定のレベルのRORγTregが維持される。
私が留学した1980年代は、免疫学ではこのような議論が当たり前だったが、やはりわかりにくいかもしれない。しかし、これが本当で、人間でも確認できるなら、IgAを使って一生続く腸内の制御性T細胞のレベルを決めることができるかもしれない。
2020年5月27日
今回の新型コロナ流行でも薬剤の効果判定について、一般人まで巻き込んだ議論が行われた。このとき、ほとんどの専門家は医療統計学に基づく治験以外に薬効を判定できないというコメントを繰り返えした。しかし、一般の人から見ると、一度希望の星としてマスメディアが取り上げた薬剤が、専門家の冷ややかな言葉で否定されるのは納得いかなかったのではないかと思う。
この時、なぜアビガンやレムデシビルなどに期待が集まったのか考えてみると、これがウイルスのRNAポリメラーゼを阻害することがわかっているからだ。少なくとも私が読んだ論文の中でレムデシビルとポリメラーゼの詳細な構造解析が行われており、特異的な結合の基盤が示されている。おそらく専門家がみれば、これより優れた薬剤の開発は可能だろうと思っていると思う。
いずれにせよ、レムデシビル、アビガン、レピナビル、リトナビル、そして抗ウイルススパイク抗体など、ウイルス分子特異的な阻害剤は、新型コロナウイルス分子に合わせた、さらに効果が高い薬剤が開発でき、新型コロナもエイズのように治療が可能になること間違い無い。もちろん、エイズのように複数の薬剤の併用は重要で、そのとき私たちホスト側分子に対する治療も組み合わせられる。
個人的な意見だが、治療メカニズムが明確な薬剤の効果をしかもパンデミックという状況で確かめていくためには、冷ややかに医療統計を盾にした議論をするのではなく、原理に基づくデータを取ることで医師の匙加減を科学的に引き上げるような新しい治験方法が必要ではないかと思っている。
などと考えていたら、すい臓ガンに免疫治療を導入しようと症例を積み重ねて一つのプロトコルに到達したコーネル大学を中心に形成された国際チームからの論文が5月25日 Nature Medicineに掲載された。タイトルは「BL-8040, a CXCR4 antagonist, in combination with pembrolizumab and chemotherapy for pancreatic cancer: the COMBAT trial (CXCR4阻害剤BL-8040をペモブロリツマブと組み合わせたすい臓ガン治療:COMBAT治験)」だ。
この研究は、すい臓ガンにはあまり効果がないとされてきた本庶先生により開発されたPD-1抗体による治療を、効果のある治療に変えられないか調べることを目的としている。いかに医療統計学的な治験に基づいて効果がないと判定されても、原理ははっきりしている。なら、治験結果がどうであれ、諦めずに新しい方法を開発したいと思うのは当然だ。
このために、この研究ではPD-1抗体に、すい臓ガンの周りに起こる炎症を抑えることが知られているケモカイン受容体CXCR4の阻害剤を組み合わせることを着想した。すなわち、どちらも単剤の治験で思わしい結果が得られなかった薬剤を原理に基づいて組み合わせた。
詳細は省くが、まず打つ手がなくなった患者さんに両者の組み合わせ治療を行い、平均で3.5ヶ月延命が可能であることを確認し(といってもまったくコントロールはない)、次にジェムシタビンが効かなくなった転移すい臓ガン患者さんを選び、2番目の選択としてこの組み合わせを使ったところ、平均値で7.5ヶ月生存した。他のお薬をジェムシタビンの後に使う場合、生存期間が6.5ヶ月などで一定の効果がある可能性がある。
重要なことは、この研究ではリンパ球の動態や転移巣のバイオプシーによる組織検査が詳しく行われており、効果を細胞レベルで検証することができている。これにより、この治療が末梢に多くのリンパ球を動員し、さらに転移組織へのキラーT細胞などの動員を高めることを明らかにしている。
このように原理は確認されたが、結果としてはたかだか1ヶ月程度の延命だったが、ここで諦めずに医師のさじ加減として、それまでやはりジェムシタビンの次に使う化学療法として治験が行われ、やはり少しだけ延命が見られていたイリノテカン、ロイコボリン、5FUの併用治療を、なんとPD-1抗体とBL-8040に組み合わせている。
まだ最終結果は得られていないが、患者さんの3割以上で癌が縮小したまま経過しており、77%ではガンの進展が抑えられ、この状態が平均で8ヶ月近く続くことを示している。
最後の結果もコントロールはない。ただ、誰が見ても大きな進展ということで、Nature Medicineに掲載されたのだと思う。治験ではエンドポイント、例えば生存期間が重視されるが、原理に自信がある場合は、データを積み重ねで、それを元にさじ加減を繰り返すことで、新しい治療に行き着ける可能性もあることを示す重要な研究だと思う。
2020年5月26日
これまでなんどもケトンダイエットの不思議な効果を示す論文を紹介してきた。例えば小児の難治性てんかん発作が4割の子供で軽減できるという報告などを見ると(https://aasj.jp/news/lifescience-easily/11255 )、そのメカニズムを突き詰めてより簡便な治療法へと発展してほしいと思う。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文はケトン食の効果の一つ原因が、腸上皮細胞のケトン体分泌、ケトン体による細菌叢の変化、細菌叢による免疫系の変化という複雑な回路を介していることを示した研究で5月28日号Cellに掲載された。タイトルは「Ketogenic Diets Alter the Gut Microbiome Resulting in Decreased Intestinal Th17 Cells (ケトン食は腸内細菌叢を変化させ、腸管のTh17細胞を低下させる)」だ。
ケトン食が腸内細菌叢の変化を誘導する可能性は誰でも考えつくと思うが、あまり研究がされていなかったようで、腸内細菌叢の研究としてはあまり質が高いと思えないのだが、Cellに掲載されていることにまず驚いた。
比較的単純な研究で、炭水化物が5%というケトン食を1ヶ月続けて、便の細菌叢を調べると、ほとんど完全に消失する放線菌など、細菌叢に大きな変化が起こること、そして細菌種の詳しい検討から、様々なビフィズス菌がケトン食で増殖を抑えられるという観察をきっかけに、あとは動物に人の便を移植する実験系を使って、細菌叢の変化の意味を調べている。
結論は単純で、ケトン食はまずホストの代謝バランスを変化させ、ケトン体の生産を高める。おそらく同じことは腸管上皮でも起こっており、上皮から分泌されるケトン体が細菌叢に働いて、ビフィズス菌などの増殖を抑える。このビフィズス菌量の低下が、腸管や脂肪組織への炎症性Th17細胞をの蓄積を抑えることを、実験的に示している。
なるほどケトン食も細菌叢への効果があるのかと納得した以外は、Cellの論文としては雑で物足りないという印象が強かったが、それでもケトン体を投与することで細菌叢のバランスを変化させられるプレバイオの可能性、およびケトン体により善玉と思っているビフィズス菌や乳酸菌が減るいっぽう、発ガンにつながるEccoliやFusobacteriumなどが増殖することは気になった。
特に後者は、ケトン食を続けていると知らず知らずのうちに発ガンのリスクは高める可能性を示唆しており、ケトン食の効果が素晴らしいからこそ、この点はさらに詳しい検討をしてほしいと思った。
2020年5月25日
コロナ騒ぎの中でひっそりと報道されていたが、黄斑変性症治療の目的で移植したiPS由来色素上皮細胞は、5年経った今もガン化することなくホストの中で生存しているらしい。今後は機能面の評価など、論文として読めるようになると思うが、最も危惧された長期安全性はクリアできたように思う。
実際iPS由来細胞の移植治療の実用化が視野に入った頃、ガン化など安全性の問題を指摘する論文が数多く出された。雑誌のエディターも、安全性への懸念を強調した論文には甘いのはという印象すら持った。しかし、この学会の態度が、どうしてもアクセルを踏みがちになる研究者に、ブレーキを意識させる効果を生んだ結果、安全な治療が可能になってきたのだと思う。
今日紹介するイスラエルテルアビブ大学からの論文は、すでに臨床応用も始まっているCRISPR/Cas9による遺伝子操作の問題点を調べた論文で5月18日号のNature Geneticsにオンライン掲載された。タイトルは「Cas9 activates the p53 pathway and selects for p53-inactivating mutations (Cas9はp53経路を活性化し、p53機能欠損変異を選択する)」だ。
これまでCas9が標的以外のDNAを切断して細胞に突然変異を誘導する危険性については指摘が続いてきた。結果、Cas9のオフターゲット活性を下げる様々な改良が進んでいるが、現在のところはプラクティカルには問題ないとして、Cas9をそのまま用いているケースが多い。
この研究ではCas9による突然変異導入だけでなく、細胞そのものの増殖容態が変化して、これが異常細胞の選択的増加をきたすのではという懸念を確かめている。
細胞株にCas9だけを導入する実験系で導入による変化を調べると、DNA切断活性の結果と思われるp53経路の活性化が見られる。もしオフターゲット切断があるなら当然の話で、細胞の増殖を抑える方向にp53の出番になるのは正常だ。
ただ問題は、この状況が続くなかで細胞増殖を維持しようと思うと、p53分子の抑制が起こる可能性がある。実際、Cas9を導入された細胞株ではp53分子の機能喪失変異が高まることが観察される。また、細胞同士の増殖競合実験を行うと、p53欠損株の方がより高い増殖を示し、集団内で優勢になることを観察している。
以上の結果から、Cas9を導入することで、p53変異が選択的に増殖する危険性があり、これがガン化など問題を引き起こすことは注意が必要という結論になる。実際の体細胞遺伝子操作では、おそらくp53 のみでは大きな問題にはならないような気はするが、注意は必要だろう。
この研究では、遺伝子操作ではなく、CRISPR/Cas9を用いて網羅的な遺伝子昨日スクリーニングを行う際の問題を実際に検証しており、このような系で特定される遺伝子は、p53経路の異常を反映していることを考慮して解釈すべきだとしている。
特に驚くほどの論文ではなかったが、様々な観点からCRISPR/Cas技術の安全性を検証することは重要だ。
2020年5月24日
Stay Homeの最大の副作用は食べ過ぎ、運動不足による肥満だが、今回は生物学的・身体的要因だけでなく、法的にも世界中で自由が制限されたという精神的ストレスが加わっているため、深刻なデータが出てくるような気がする。
そんな中、別にダイエットをしているわけでないのに太らない人を必ず見かける。おそらく多くの人は、同窓会などにでてこのことを感じておられるだろう。おそらく太らない遺伝的素因があると考えられるが、メラノコルチンなど太る遺伝子多型は多く見つかっているのに、太らない遺伝子多型となると、病気を除くとほとんど見つかっていない。
今日紹介するオーストリア分子生物学研究所と食品メーカー ネッスルの研究所からの論文はなんと発ガン遺伝子として研究が盛んなALKが欠損すると、食べても太らないこという意外な結果を示した研究で6月11日号のCellに掲載予定だ。タイトルは「Identification of ALK in Thinness(ALKが痩せに関係することの発見)」だ。
著者らはこれまで太らないことと関係する遺伝子の発見が難しいのは、生活習慣や年齢の背景を補正して多型を探すことが難しかったことが原因であると反省し、これらの条件を満たしたゲノムコホート研究として、エストニアバイオバンクが使えることを発見する。
年齢や性別などの要因を補正した上で、痩せていることと相関する多型を探し、5つの領域を特定するが、この中に肺の非小細胞性腺ガン、白血病、そして神経芽腫などのガンのドライバーとして知られているALKのイントロンに存在する多型が存在することを発見する。
まずショウジョウバエを用いたRNAiによる昨日検索で、ALKノックダウンにより摂食行動は変化しないにも関わらず、太らないことを突き止め、マウスを用いた研究へ進んでいる。
ガン遺伝子としてのイメージが強いため、個人的にノックアウトマウスを用いるのは難しいだろうと思っていたが、意外なことにノックアウトマウスは正常に生まれ、生殖能も正常らしい。ただ、期待通り正常食でも、高脂肪食でも太ることがなく、常に正常より体重が低い。これは、エネルギー消費が高く、白色脂肪組織で脂肪の分解が高まっていることが原因であることがあきらかになった。
ただ、脂肪代謝に関わる肝臓や脂肪組織ではALKの発現はほとんど見られないためALKを発現が高く、脂肪代謝と関わる組織を探索し、最終的に視床の室傍核の興奮神経が脂肪代謝に関わっていること、そしてALKイントロンの多型によりこの神経細胞でのALK発現が低下することを確認する。
最後に、室傍核特異的にALKをノックアウトする実験で、この部位のALK発現が減少すると、太らないマウスができることを明らかにしている。
以上が結果で、もしこの多型を持っている人が全く正常な一生を送れることが明らかなら、ALKの発現を標的とした太らないためのお薬ができるかもしれない。
2020年5月23日
キラーT細胞が細胞を殺すメカニズムとして、当時、順天堂大学医学部の真貝さん(現、理研)がパーフォリン遺伝子を報告したのはずいぶん前だが、この仕事はよく覚えている。その後グランザイム、そして長田さんが明らかにしたFasを刺激するFasLも相手を殺す時のメカニズムとして特定された。パーフォリントグラン財務に関しては、パーフォリンでできた穴を通して、グランザイムが細胞内に侵入し、細胞を殺すと理解している。また、両方の分子は小胞の中に詰め込まれて分泌されることも知られている。
今日紹介するオックスフォード大学からの論文はこの過程を細胞生物学的に詳しく解析し、パーフォリン・グランザイムが一種カプシド型ウイルスの様な構造を形成し相手の細胞へ受け渡されることを示した面白いプロの仕事で、5月22日号のScienceに掲載された。タイトルは「Supramolecular attack particles are autonomous killing entities released from cytotoxic T cells (超分子的攻撃粒子がキラーT細胞から遊離するキラー分子の実体)」だ。
このグループは、キラー分子が集められたカプシド型ウイルスの様な超分子攻撃粒子(SMAP)が細胞を殺すと仮説を立て、パーフォリンやグランザイムを蛍光ラベルするとともに、分子コンプレックスをラベルする目的でレクチンであるWGA分子もラベルし、これらがコンプレックスを作って、殺したい相手の細胞に受け渡されるかまず調べている。
実験は細胞生物学の粋を集めたもので、SMAPに分子が集められ、それが相手の細胞に移行する様子を見せるだけでなく、人工的にスライドグラスの上に形成させた脂肪二重膜の上でT細胞を活性化し、分泌されたSMAPが膜に突き刺さる様子もリアルタイムで捉えている。まさに、ウイルスの侵入を見ているようだ。
このようにパーフォリンや、グランザイムが単純に分泌されるのが細胞障害性でないとすると、SMAPを構成している分子が重要になる。そこでこの構造を集めて分子解析を行うと、様々な分子が集まった構造を取っており、中でも血小板で多く見られるスロンボスポンディン1が最も多く含まれることが明らかになった。そこでスロンボポイエチンをノックアウトしたT細胞を作り、キラー活性を調べると期待通り活性は低下していた。
あとは、クライオ電顕など画像解析を通して、SMAPがグランザイムやパーフォリンを中央に、その周りをスロンボスポンディンがカプシドのように取り囲む構造を持ち、111nmほどの大きさの粒子であることを明らかにしている。
結果は以上で、中に核酸はないが、カプシド型ウイルスの構造と同じだ。さらに考えると、キラーT細胞はFasLを表面に持った小胞体を分泌して、Fasを持った相手を殺すことも知られている。この場合、コロナのような一種のエンベロープ型ウイルスに近い。
勝手な想像だが、このような擬似ウイルス武器をもって、ウイルス感染を防いでくれるのがキラーT細胞であることがよくわかった。うまくいけば、キラーT細胞ではなく、他の方法でこの武器を使える日が来るかもしれない。