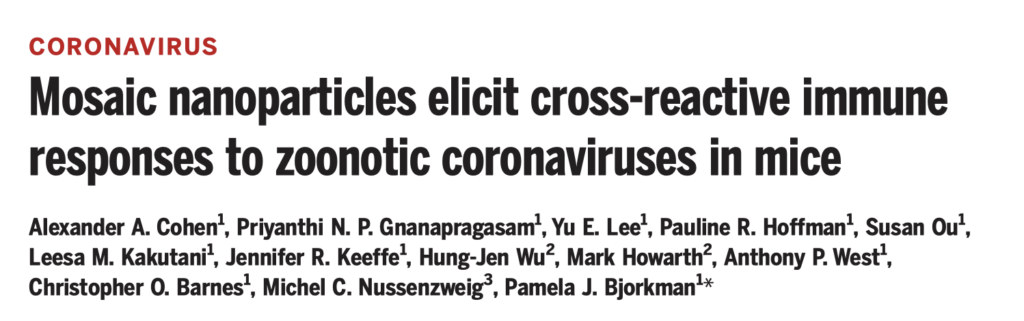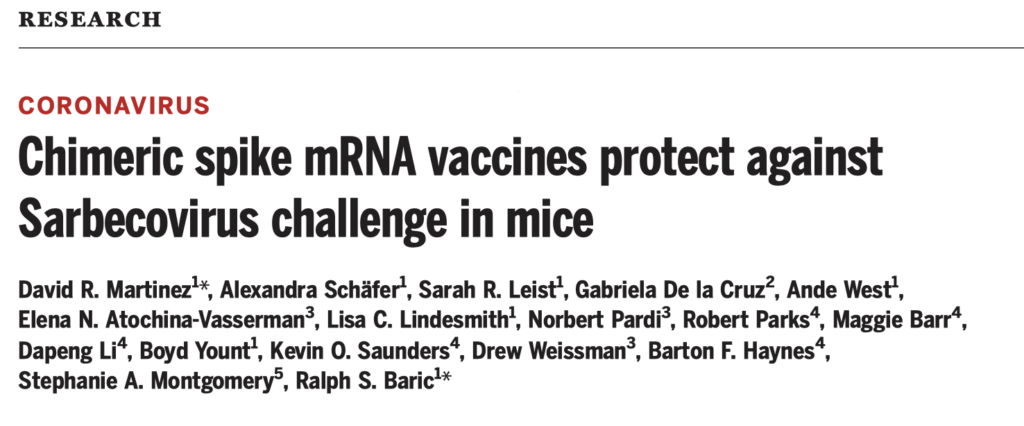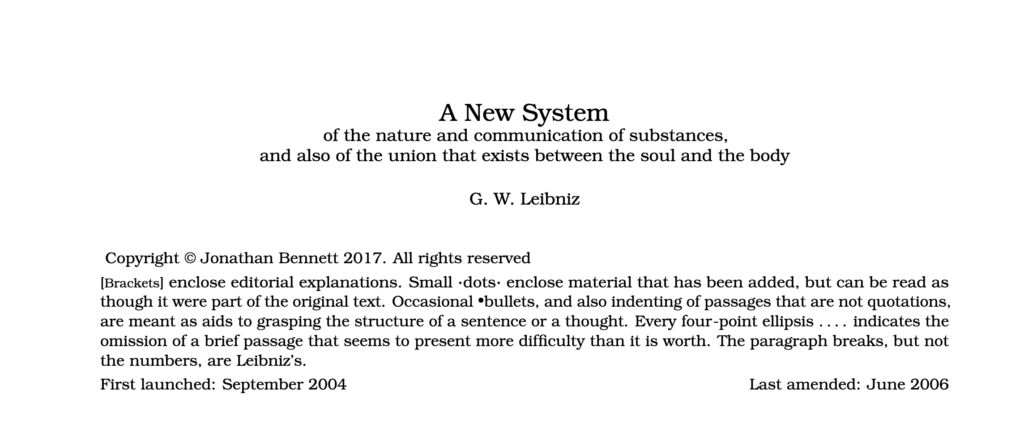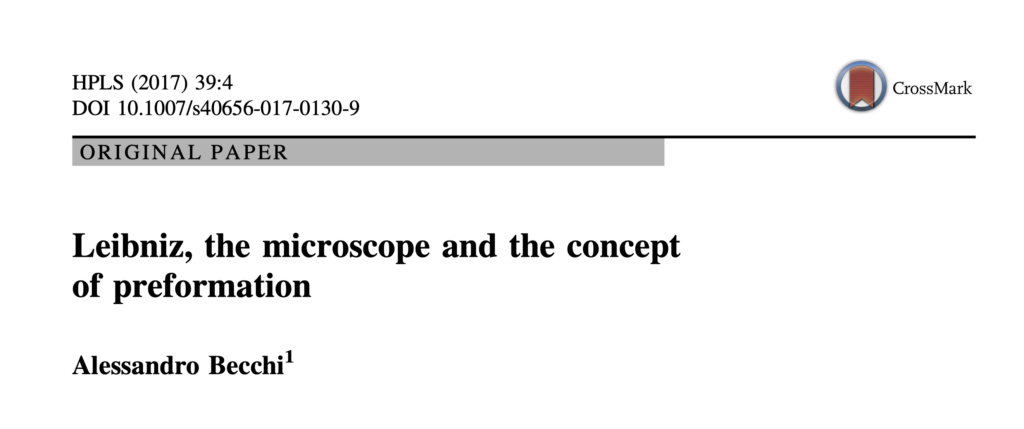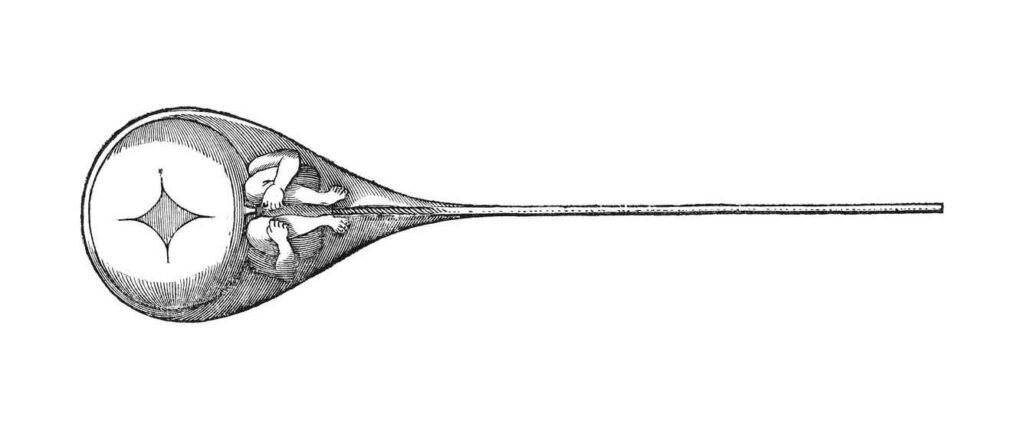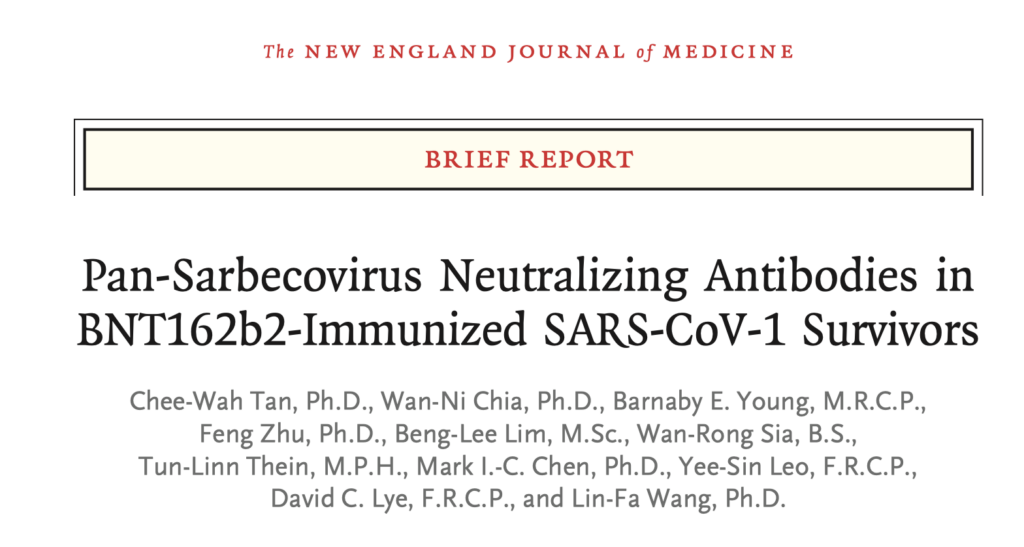2021年8月31日
現在腎不全に対する治療法は、人工透析と腹膜灌流があるが、腹膜灌流の方は様々なメリットがあるにもかかわらず、普及していない。我が国の腹膜灌流比率1%は例外としても、欧米でも10−20%の普及率にとどまっている。この理由の一つは、自宅での清潔作業が必要であるなど運用上の問題もあるが、現在使われているicodextrin入りの灌流液が、生物学的に全く不活性というわけではなく、どうしても腹膜を刺激して、血管新生、腹膜細胞障害、線維化などを誘導して、灌流効果が低下してしまうことも問題になっている。
今日紹介するウィーン大学からの論文は灌流液による腹膜の変化のメカニズムを探り、この作用を塩化リチウムで抑えることが可能であることを示した研究で、8月25日号のScience Translational Medicine に掲載された。タイトルは「Lithium preserves peritoneal membrane integrity by suppressing mesothelial cell αB-crystallin (リチウムは中皮細胞のαBクリスタリンを抑制して腹膜の機能を保全する)」だ。
まず、世界中で安全に使われている灌流液に満足せず、さらに完全なものにしようと努力しているこのグループに脱帽したい。このグループは、灌流液に加えることで、灌流液による影響を軽減させる分子を探索する中で、細胞保護作用と抗炎症効果が知られている塩化リチウムに着目し、この研究を始めている。
研究ではヒトの腹腔由来中皮細胞を培養し、灌流液に暴露したときに見られる変化を、細胞学的遺伝子発現解析や発現タンパク質解析で特定するとともに、この変化を塩化リチウムにより抑制できないか調べている。
結果は期待通りで、灌流液にさらすことで中皮細胞の細胞死や形態変化が誘導されるが、これを塩化リチウムが見事に抑制することができる。そして、遺伝子発現やタンパク質発現の網羅的研究から、この変化を誘導するマスター遺伝子として、αBクリスタリンを特定する。
事実、灌流液にさらされた中皮細胞ではαBクリスタリンの発現が上昇し、塩化リチウムはこの上昇を抑える。そして、αBクリスタリンを過剰発現した細胞では、灌流液による細胞死や形態変化の誘導を塩化リチウムが抑制できなくなる。
次に、このメカニズムを解析し、灌流液がαBクリスタリンのリン酸化を介して核内移行を誘導し、TGFβにより活性化されるSMAD4のユビキチン化を抑制することで、TGFβシグナルが増強し、中皮細胞から間質細胞への転換が誘導されること、そして塩化リチウムはこのαBクリスタリンリン酸化を抑え、中皮細胞/間質細胞転換を抑えることを明らかにしている。
最後に、マウスの腹膜灌流モデルで誘導される、腹膜肥厚、線維化、血管新生などを塩化リチウムが抑制できることを確認し、臨床へのトランスレーションが可能であることを示している。
以上が結果で、少なくとも現在の腹膜灌流液は刺激性があり改善の余地があること、またこの問題を灌流液に塩化リチウムを加えることでかなり改善できることを示している。ただ、臨床へのトランスレーションに当たって今後確認が必要な点は、塩化リチウムの副作用の問題だ。塩化リチウムは躁病に対する薬剤としてすでに利用されており、命に関わる有害事象が発生する可能性は少ないが、それでも腎毒性などが指摘されており、灌流液に加えて使う場合も副作用への注意が必要になる。ただ、著者らは灌流液に有効濃度の塩化リチウムを加えても、血中の塩化リチウム上昇が少ないことから、副作用もかなり局所で抑えられると議論しているが、今後の研究が必要だろう。
いずれにせよ、αBクリスタリンを、灌流液の腹膜障害性の鍵として特定できたことは、今後より安全な腹膜灌流液の開発に大きく寄与できると期待する。
2021年8月30日
先週、梅北2期、参加型ヘルスケアプロジェクトの活動として、WHO武漢調査にも参加された国立感染研究所・獣医科学部部長の前田健先生をお招きしzoom講演をしていただいた。熱い議論が続き、1時間を優に超してしまったが、その様子は近々このHPでも公開するので楽しみにしてほしい。今後多くの新しいコロナウイルスが、動物の中で人間に感染する機会を待っていることがよくわかる講演だった。
もしコロナウイルス、特にsarbecovirusにより、新しいパンデミックを覚悟する必要があるとすると、一つは広い範囲のsarbecovirusに効果がある治療薬とワクチンの開発が必要になる。
例えばすでに米国政府が170万回分を12億ドルで調達を決めたメルク社molnupiravirは、以前紹介した、経口投与可能、ウイルスRNA複製を中断しないで遺伝子変異を指数関数的に上昇させるという特徴で、レムデシビルを凌駕する可能性があり、しかも軽症者に投与可能な治療薬だが(https://aasj.jp/news/watch/17631 )おそらく他のSarbecovirusにも効果があるだろう。
他にも現在治験が進むCoV2ウイルスのメインプロテアーゼを標的にしたファイザーや塩野義の阻害剤も、SARS関連コロナウイルス(sarbecovirus)全体に効果を示すのではないだろうか。
またEUが緊急承認したGSK社ウイルス中和モノクローナル抗体sotrovimabは、元々SARS患者さんから分離された抗体で、多くのsarbecovirusに効果を示すことから、新しいsarbecovirusパンデミックの備えになる。
このような広いスペクトラムのsarbecovirusの感染を抑える抗体が存在する事実は、同じような抗体を誘導できるワクチンの開発が可能であることを示している。またこれとは別に、スパイクの一部がup formをとるときに初めて分子表面に現れる領域に対するモノクローナル抗体が、ほとんどのsarbecovirusに効果があることを示した研究は、この領域特異的に抗体を誘導するワクチンを設計できれば、多くのコロナ感染に備えることが可能であることを示している(https://aasj.jp/news/watch/17067 )。
よく効く薬と抗体薬があれば、ワクチンは必要ないのではという考えもあるが、パンデミック制御に必要なコストはワクチンの方が驚くほど少ない。これは国産が可能になっても同じで、広い範囲のsarvecovirusに対して抵抗力をつけるワクチンが設計できればそれに越したことはない。
ただ、お手本になる抗体とそれが認識しているスパイク領域の構造がわかっても、それだけを誘導するワクチンの設計は、簡単ではなく、現在は様々な可能性を試す試行錯誤の段階にある。そのための一つのアイデアは、様々なウイルスのreceptor binding domain(RBD)を同時に免役するワクチンの開発で、例えば今年の2月、ウイルス様粒子上に数種類のRBDを発現させるワクチンが開発され、様々なコロナウイルスに対する免疫が誘導できることを示す論文がカルテックから発表された。ただ、構造が複雑なことを考えると、コストなどの面で実用化は遠い気がした。
これに対し、今日紹介するノースカロライナ大学からの論文は、いくつかのウイルスのスパイク分子を混合して免役するという発想から始まってはいるが、mRNAとより単純なモダリティーを持ちいている点で実現性は高く、これにより多くのsarbecovirus感染を抑えることができることを示した研究で8月27日号Scienceに掲載されている。
この研究では、RBDだけを抗原にしないで、スパイク全体を抗原に用いるが、それぞれの領域を様々なウイルスから持ってきたキメラ遺伝子を合成し、これをmRNAワクチンとして免疫に用いている。大きな分子を用いることで、細胞性免疫ペプチド抗原も十分確保するという点では、スパイク全体を使う方がRBDだけに絞るより実践的だ。様々なキメラ遺伝子を用意する必要はあるが、mRNAワクチンをモダリティーとして利用する場合は、十分実現性はあると思う。
実際には、N末領域(NTD)/RBD/S2領域の組み合わせを、コウモリウイルス/SARS/CoV2、SARS/Cov2/SARS、SARS/Cov2/Cov2、そしてCoV2/カメウイルス/CoV2の4種類キメラ遺伝子を用意している。
目的はノースカロライナ大学と同じで、4種類全部を用いれば、多くのウイルスに対応できると考えた。実際、4種類全部、あるいは最初に2種類、後から他の2種類でブーストと言った方法で免役すると、たしかに様々なウイルスに対応できるワクチンとして利用できることがわかった。また、様々なCoV2変異株にも効果があり、マウスの肺炎を予防する効果も高い。以前紹介したシンガポール在住のSARS感染者にCoV2ワクチンを接種することで、多くのウイルスをカバーする抗体が誘導できた結果(https://aasj.jp/news/watch/17664 )を考えると、ワクチン戦略としても十分あり得るかと納得できる。
この論文の明確な結論としてはここまでで、4種類を同時注射でもワクチンとして十分実現性はある。これとは別に、個人的に最も面白いと思ったのは、数種類を同時注射しなくても、カメ/CoV2/CoV2型ワクチンを単独で用いても、CoV2に対しての抗体誘導能は劣るが、調べた4種類全てのsarbecovirusに抗体が誘導されていた点だ。
これは個人の想像に過ぎないが、ACE2結合のための最も肝心のRBDがカメに置き換わったことで、up/downフォームの頻度が変化したりして、以前紹介した領域(https://aasj.jp/news/watch/17067 )に対する抗体を誘導できた可能性がある。全てポリクローナル抗体であること、そして抗原の構造解析が全くできていない点で、まだまだ研究が必要だが、さらに研究を重ねれば、sarbecovirus全般に対応できる、一種類のワクチンも開発できそうな印象だ。
このように、ワクチン競争はもはや新しいパンデミックを予想して、一つのウイルスだけでなく、その種全体をカバーできるワクチン開発にシフトしていることは確かだ。これはsarbecovirusだけでない。論文を見ていると最近だけでも、インフルエンザ、αウイルス、HIVなどなど、全てで開発競争が熾烈になっている。その意味で、今回のコロナウイルスパンデミックは、ワクチン研究にとって、大きなブースター効果があったと思う。
2021年8月29日
子宮内膜症は、子宮と名前がついているが、実際には子宮以外の卵巣や卵管(他にも様々な場所)に内膜様の組織ができてしまい、それが月経周期に併せて増殖・消退を繰り返す病気で、内膜症の場所を特定するのが難しい場合、診断が遅れる。治療としては、内膜の増殖を止めるためのホルモン治療が中心だが、内膜自体を除去する手術も行われる。
今日紹介するオックスフォード大学からの論文は、症状の重い子宮内膜症患者さんの遺伝学的解析から neuropeptide S(NPS)とその受容体neuropeptide S receptor 1(NPSR1)が内膜症の誘導因子であることを突き止め、治療可能性を示唆した論文で8月25日号Science Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Neuropeptide S receptor 1 is a nonhormonal treatment target in endometriosis (Neuropeptide S receptor 1は子宮内膜症のホルモン以外の標的になる)」だ。
すでにゲノム解析から、頻度は少ないが子宮内膜症と相関する遺伝子座が特定されており、この研究では染色体7番にある遺伝子座の中から、最終的にNPSR1遺伝子のアミノ酸の変化を伴う突然変異が子宮内膜症に関わっていることを特定している。
ただ、これは頻度の低いレアバリアントなので、次にNPSR1遺伝子がより広い範囲の子宮内膜症に関わっている可能性を、SNPデータベース探索により調べ、この領域にあるいくつかのSNPが子宮内膜症に関係すること、またそのうちのいくつかがNPSR1発現に関わっていることを確認している。
これで十分な気もするが、驚くことにこの研究ではアカゲザルの集団の子宮内膜症と遺伝解析を組み合わせた研究も行い、NPSR1の変異が子宮内膜症に関わることを明らかにしている。おそらくオックスフォードでは人間のデータをバックアップするためのサルの集団が維持されていると思われるが、用意周到さに驚く。
後は、NPSR1が子宮内膜症にどう関わるか、メカニズム解析になるが、これは難航したようで、正常と内膜症組織でNPSR1の発現などはほとんど差がない。様々な探索の結果、CyTOFと呼ばれる細胞内分子まで単一細胞レベルで調べられる方法で、ようやく子宮内膜症患者さんの腹腔液の中のマクロファージでNPSR1の発現が上昇していることを発見する。
メカニズムの探索はここまでで、あとはNPSR1阻害分子が存在するので、マウス腹腔に炎症を誘導したとき、この阻害剤が腹腔内の炎症を押さえて、痛みを取るかどうか、マウスモデルで調べている。結果は上々で、マウス子宮内膜症モデルで、痛みを示す行動を強く押さえるとともに、炎症性マクロファージをある程度抑制することを示している。
結果は以上で、NPSR1が脳で機能していることを考えると、脳には到達しないお薬が必要になるが、治療の難しい子宮内膜症症状改善に使えるのではと期待できる。
しかしこの論文で一番驚いたのは、サルの集団でゲノム解析が行われている点で、さすがサル学の進む日本でも、ここまで踏み込んだ研究はないように思う。
2021年8月28日
中東を通ってホモサピエンスがユーラシアに進出したのは4−5万年前だが、アラビア、インド、インドネシア、オセアニアにかけての南ルートは、ネアンデルタール人のような抑止力がなかったせいか、ずっと早くにホモサピエンスが進出し、ユーラシアとオセアニアの境、ウォレス線を渡ったのは6−7万年前と遙かに早い。この人たちの痕跡はパプアニューギニア人などに残っており、また絵や石器などが残されていても、高温多湿な気候のせいで、ゲノムが得られる遺跡が見つかっていなかった。
今日紹介するドイツ、イエナ・マックスプランク研究所を中心とする国際チームの論文は、ウォレス線を越した側のスラワジ島、Leang Panningeの発掘現場から発見された7千年前の女性の人骨からDNA採取に成功し、おそらく南ルートを通ってきたホモサピエンスの子孫であることを証明した研究で、8月25日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Genome of a middle Holocene hunter-gatherer from Wallacea(ウォレシアから出土した中期完新世狩猟採取民のゲノム)」だ。
ウオレス線の東側は、謎のフローレンス人が出土したり、最近では1万年前ぐらいまでデニソーワ人が生存していた証拠が出るなど、人類史研究のホットスポットになっているが、ゲノム考古学をリードしてきたドイツチームがすでに活動して成果を上げ始めているのには感心した。
いずれにせよ、このような発掘は考古学とゲノム科学の密接な連携が必要で、おそらく限られた領域で発見される特徴のある石器から、ユニークな文化(Toalean文化)を代表しており、これまでとは異なる系統のホモサピエンスが発見できるのではと期待して、発掘を進めてきたのだと思う。
そしてついに、17歳前後の女性の頭部の骨を発見できた。骨の形状からは、メラネシア人に類似しており、南ルートの末裔ではないかと期待が膨らんだはずだ。
やはり高温多湿地帯のため、7千年前の骨でも傷みが早く、到底全ゲノムというわけにはいかないが、大体30万SNP部位を解読でき、これとミトコンドリアゲノムの配列を、これまで知られているゲノムと比較している。
その結果、
ウオレス線西側の民族と、ウオレス線東側の民族のちょうど中間に、今回のゲノムが位置しており、オンゲ族や天元人とパプア人が半々に混ざった構成をとっていることがわかった。 デニソーワ人ゲノムは、パプア人と比べると低いが、一般より高い割合(2.2%)で存在しており、パプア人とLeang Panninge人の共通祖先の段階で、交雑があったと考えられる。 以上の結果から系統関係を構築すると、Leang Panninge人はパプア人と同じ南ルートで広がったホモサピエンスと、天元人/斎河人のゲノムを半々に持つ民族が形成され、その後あまり交雑なく小さな領域でToalean分化を維持した。 以上の結果は、パプア人ルートと、天元人のような南アジアの民族との交流がかなり昔からあったことを示している。いずれにせよ、この地域の古代ゲノム研究は始まったばかりで、期待される。
2021年8月27日
昨日はコウモリの赤ちゃんの言葉の話だったが、今日は大きくジャンプして、人間の成人の言語処理に関する論文を紹介する。
言語に関わる脳領域というと、運動失語に関わるブロカ領域や感音性失語に関わるウェルニッケ領域をはじめとする、高次情報処理に関わるプロセスを思い浮かべるが、それより前に、音を感知して、言葉か単純な音かの判断を、一次聴覚領域である程度済まさないと、刻々入ってくる複雑な言語情報を処理することは困難だ。しかし、時間解像度の高い脳波計では正確に活動計測が難しい領域であることから、音を聞いた直後の言語処理ネットワークについては以外と研究は遅れている。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、脳の大きな溝、シルビウス溝下部の一次聴覚野全体に、てんかん診断のための留置クラスター電極を設置した患者さんを用いて、言葉を聞いたときの各領域の反応を計測し、それぞれの神経の特異性をマッピングした研究で、9月2日号Cellに掲載された。タイトルは「Parallel and distributed encoding of speech across human auditory cortex (人間の一次聴覚野の言語の平行分散型処理)」だ。
この研究は、9人のボランティアのシルビウス溝下部側頭葉の一次聴覚野(6領域に分けているが名称などは割愛する)にクラスター電極を設置して、ただの音や言葉を聞かせた時の活動を計測し、記録するだけの実験だ。電極が設置された領域に刺激を与えた時のネットワークへの影響も調べているが、基本的には多くの電極から得られたビッグデータを情報処理して、一次視覚野の言語処理過程を推察する研究になる。
9人のうち5人は、手術中に実験を行っている。9人全体で、総数636カ所からの活動記録が得られており、それぞれの神経の活動特性を全て総合して解析している。
課題は簡単で、単純な音を聞かせた時、および、短いセンテンスを聞かせた時の、それぞれの電極が拾った記録をベースに、音が感知されてから、どのように神経興奮が伝搬しているのかを、それぞれの神経の興奮時間を元に計算していく。すなわち、早く興奮したところが最初の知覚で、そこから他の神経に広がると、時間差が生まれるので、時間経過からどう伝搬しているかがわかる。
これまで、蝸牛の配置に対応するコア領域(HG)でまず音が感知され、他の領域へ伝搬する中で言語であることの判断など、様々な処理が行われると考えられていたが、今回の研究により、言葉を聞かせた時の興奮経過を調べると、HGだけでなく、PTやSTG(名前の説明は割愛する)にも、HGとほぼ同時に興奮する神経があり、シグナル処理がいわゆる並行処理型で行われることが明らかになった。
そして、単純な音、あるいは言語に対する神経活動を分析すると、言語だけに反応し処理に関わる神経が存在すること、そして言語でも、音節の始まりに反応する神経、絶対的ピッチに対応する神経、相対的ピッチに対応する神経、などが存在し、個々の神経が異なる情報処理を専門的に行うことがわかる。
重要なのは、これらが一次聴覚野の決まった領域に固まって存在しているのではなく、それぞれの領域に分散的に存在していることで、それぞれの音を迅速に処理することに役立っていると思われる(絶対ピッチに関わる神経だけはTPにクラスターしている)。
階層的ではない並行処理が本当に行われているのか調べる目的で、階層的な処理の場合、必ず通過する必要のある最初の入り口としてのHGに電気刺激を行う実験を行うと、刺激により幻聴は生じるものの、言葉の聞き取りに全く影響ないことがわかる。またてHGにあるてんかん巣を取り去った患者さんでも、幻聴は消失したのに、言葉の理解は全く傷害されなかった。一方で、2次処理に関わるSTG領域の刺激は、言葉の認識を傷害することも示している。
繰り返すと、この研究から、おそらく言葉や音楽のような複雑な音を処理するために、聴覚神経がHG意外にも投射しており、このようなインプットを、散在する特殊な機能に特化した神経が処理する、分散型並行処理が言語理解の脳ネットワーク構造であることが示唆されている。
実際には、ビッグデータの情報処理研究なので、ついて行くのは難しかったが、なるほどと納得できる論文だった。
2021年8月26日
今日から2回、言語についての論文を紹介する。
さて一昨日、ライプニッツを、現在、我々が理解している細胞理解にかなり近いイメージを持っていたとする「モナド論」解題をアップロードしたが(https://aasj.jp/news/philosophy/17672 )、ライプニッツの名前を、数学の研究所ではなく、自然史に近いNaturkunde博物館付属の研究所につけているのが、Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Scienceで、同じ意見の人がいると思うと心強いが、今日紹介するのはこの研究所からの論文で、コウモリの赤ちゃん語(Babbling)から、成人型への発語への転換を研究して、この過程が人間のそれと多くの類似性があることを示した研究で、8月20日号のScienceに掲載された。タイトルは「Babbling in a vocal learning bat resembles human infant babbling(コウモリの発語学習でのbabblingは人間の幼児のbabblingに似ている)」だ。
全く知らなかったが、コウモリの赤ちゃんも、大人の発語とは全く異なる、赤ちゃん特有のbabblingを行うことが知られていたらしい。この研究では、パナマとコスタリカで、20匹の幼児の発達を追跡するとともに、その間の行動と発語を記録し、最終的に216種類のbabbling発語の中から55056シラブル分離し、それを大人の発語と比べている。個々でシラブルとは、明確に分離した音の塊と考えれば良い。
結果は、
コウモリの幼児は大人の発語とは全く異なる、特有のbabblingを生まれてすぐから発声する。 ただ、決まったシラブルを持つbabblingを発声するのは2.5週目からで、それが7週間続く。 babblingのシラブルは、個体ごとに大きく異なるが、人間と同じで同じ音の繰り返しが多い(da-da, pa-paのような感じ) 人間とは異なり、親は子供のbabblingに反応しないことから、社会的コミュニケーションの意味はない。従って、大人型の発語のための本能的な練習と考えられる。 実際、大人型のシラブルの原型が徐々にbabblingシラブルの中に混じるようになる。 3ヶ月でコウモリは離乳を果たすが、このとき大人言葉はせいぜい25シラブルに過ぎない。また、どのシラブルを学習するかも全くランダムで、決まっていない。 大人型シラブルの学習は、始まると急速に増加し一定に達する。決して順番に学習するものではない。 などなどだ。これを人間と比べると、babbling発生に時間がかかること、大人言葉に似ていても異なる特有の構成を持っていること、様々なシラブルが発声すること、子供ごとにbabblingレパートリーが異なること、リズミックであること、babblingは特に社会的要求を反映しないことなど、確かに似ている。おそらくbabblingで私たちは発語の自然訓練を行うようできているようだ。
それはともかく、個人的には、大人型のシラブルが混合を始め、それが言葉として独立した途端に、急速にレパートリーが増えるという、人間の言語獲得過程との類似性に感銘を受けた。これが、人間の言語獲得と、チンパンジーやボノボの言語獲得の違いで、コウモリの脳科学は進みつつあるので、この辺の秘密も解けるかもしれない。
普遍文法を唱えたチョムスキーも最近では動物に普遍的な脳過程として言語を考える総説を書いている。ずいぶん先になると思うが、是非生命科学の目で見る哲学でも取り上げたいと思っている(頭がぼけていなければだが)。
2021年8月25日
遺伝子が重複して組織での遺伝子発現が正常より上昇してしまうと病気になる多くの病気が存在する。わかりやすいのはダウン症のように染色体数が増えることで起こる病気だが、MECP2重複症のように、局所的に遺伝子が重複する場合もある。このような状態の治療には、RNAase 依存性のアンチセンスオリゴ核酸(ASO)や、Dicer依存性の2本鎖RNAを用いるRNAiやshRNAを用いて、mRNA量を半分程度に低下させる方法が考えられ、開発が進んでいる。
今日紹介する東京医科歯科大学からの論文は、DNAとRNAが結合したheteroduplexに脂肪を結合させることで、遺伝子制御効率を高められるだけでなく、全身投与した核酸薬が脳血管関門を通って脳組織で働けることを示した研究で8月12日、Nature Biotechnologyにオンライン掲載された。タイトルは「Cholesterol-functionalized DNA/RNA heteroduplexes cross the blood–brain barrier and knock down genes in the rodent CNS(コレステロールとDNA/RNA ヘテロドゥプレックス結合体は脳血管関門を通ってマウス中枢神経で遺伝子をノックダウンできる)」だ。
ワクチンで注目されている核酸テクノロジーだが、我が国でも様々な研究開発が行われていることがわかる研究だ。このグループは、両端(Wingと呼んでいる)に修飾RNAを持った、DNAとRNAのheteroduplexをもちいる核酸薬を独自に開発し、ASOと同じようにRNaseH依存的に遺伝子ノックダウンできること、さらにこれにビタミンEやコレステロールを結合させると、細胞へのデリバリーが高まり、高いノックダウン効果があることを示してきた(HDO技術と名付けている)。
この研究では、同じように設計したHDOが、全身投与するだけで自然に脳組織に到達し、そこで遺伝子ノックダウンが起こることを示すための詳細な技術的検証が行われている。
例えばHDOを静脈投与するだけで、神経変性に関わることがわかっているノンコーディングRNA、Malat1の発現を脳内のほぼすべての領域、および全ての細胞種で、半減させられることを示している。また、一度に大量を注射するのは難しい場合、連続投与すればさらに効果が高まることが示されている。そして得られた結果は2週間がピークだが、効果は1ヶ月以上長続きできることも示している。一定レベルにRNA量を落とせばいいMECP2重複症のような場合はかなり期待できるデータだ。
個人的印象だが、コレステロール結合HDOだけが何もしなくても循環から脳へ移行するという今回の結果は驚くべき結果だと思う。我が国発の核酸技術として発展してほしい。ただ、投与量についてみると、直接脳内に注射する場合と比べると、ほぼ10倍のHDO を投与する必要がある。この場合、全身性の遺伝疾患の場合は、脳以外の組織でのノックダウン効率と、神経組織内での効率が変わることになり、例えば脳症状が最も強いが、全組織で発現が見られるMECP2重複症に使うのは難しいかもしれない。
しかし、脳に入るかどうかは別にしてHDOの効率は高そうなので、髄腔投与であっても、高い効果が見られる気がする。是非進展することを願うが、wing付きのheteroduplexに脂肪を結合させる設計から推察すると、さぞコストがかかるのではと少し心配だ。
2021年8月24日
今回は、この歳まで何回かチャレンジして、結局理解できいないまま放置していたライプニッツの「モナド論」を取り上げる。なんとか理解して皆さんに紹介しようと性根を入れ替えて取り組んだおかげで、面白い思想だと実感できた。今回は彼の著作「モナド論」を取り上げ、全く個人的な解釈を述べてみたいと思っている。
自分自身が携わっていた生命科学の根本課題を考える上で、ヨーロッパの17世紀思想は参考になると思っている。17世紀思想のもつ生命科学的意味を考えようと、彼らが自然や人間をどう捉えていたのか考えながら、この1年、デカルト、ライプニッツ、スピノザの三人の著作を読んできた。これまで読んだことのある哲学者達も、生命科学の歴史との関わりという観点で読むと、新しい見方ができるようになる。前回は、デカルトが解剖学や生理学に自らチャレンジした哲学者であることを強調して、彼の二元論について私の考えをまとめてみた。これに続いて、ライプニッツ、スピノザを、生命科学者の目という新しい視点から彼らの思想を考えてみたいと思っている。
今回は、ライプニッツを取り上げる番になるが、これまで「モナド論」や「形而上学序説」に何度もチャレンジしたが、難解というより理解しづらい哲学者だ。これは私だけの印象ではないと思う。実際、ライプニッツを、デカルトやスピノザと比較すると、かなり知名度で劣る(ライプニッツの研究家の皆さんごめんなさい)。これは講義を通した学生さんとの交流経験からも実感している。
講義では21世紀の生命科学の歴史的背景がテーマで、当然17世紀の3哲学者についても言及することになる。日本の学生さんと直接話すと、残念なことに最も有名なデカルトですら、読んだことがあるという学生に出会うことは珍しい(講義のあと、是非読んでみたいと感想を書いている学生さんもいるので期待はしているが)。一方、毎年日本にくる米国からのサマースチューデントにも同じ講義をするが、「デカルトやスピノザを読んだことがあるな」と感じられる学生がかなり存在するのを実感する。それでも、ライプニッツまで読んでいる学生にはまだ出会ったことはない。
なぜこれほど知名度が落ちるのかつらつら考えてみると、代表的著作として本屋に並んでいるのが、「モナド論」と、あとは「形而上学序説」で、デカルトの「方法序説」やスピノザの「エチカ」と比べると、内容があまりに現代離れして、読み通すのが困難なのだ。現代に生きる私たちにとって、最も理解し難い著作しか手に入らないことになる(おそらく欧米でもそうではないだろうか)。
今回再度ライプニッツにチャレンジしようと決めた時、「モナド論」は最後に回して、とりあえずこれまで読んだことのない著作から始めようと決めた。そして、工作舎から発行されているライプニッツ著作集2冊、みすず書房発行の人間知性新論を読んでから、アルノー書簡、形而上学、そして最後にモナド論と読み進んだ。また、1〜2英語に訳されている短文や彼についての論文も読んでみた。
それぞれの本について詳しく紹介はしないが、ライプニッツはモナド論から始めないことが付き合うコツであることがわかった。そして今回初めて、ライプニッツが何か宗教的ドグマに凝り固まった風変わりな哲学者ではなく、時には実務的、時には自由な発想でドグマにとらわれずに思考する、17世紀を代表する思想家であることがわかった。
少し値が張るが多くのライプニッツの著作は和訳で手に入る。 図に示した実務的な著作を集めたライプニッツ著作集II期、第2巻の中には、当時の最大の問題であったペストを予防するための政策についての著作が掲載されているが、内容は今の厚生官僚が書いているのと何ら違いはない。時代を考えると、おそらく極めて優秀な実務家であったこともわかる。要するに能力の高い、しかし普通の人なのだ。私は数学が苦手なのでもともとライプニッツを有名にしている数学についての著作を全く読まなかったが、おそらく優れた著作が多くあると思う。
彼がオーソドックスな思想家であることを一番実感したのが、ロックの「人間知性論」に啓発されて、対話形式で書かれた「人間知性新論」(図右)だ。この本を読むと、ライプニッツが当時世界中から得られる哲学的思想に熟知しており、多くの哲学•神学者との対話を通して、自分の思想を発展させようと努力していたのがよくわかる。ぜひロックを取り上げるときに、この本も取り上げてみようと思う。要するに、これらの著書には、モナド論を読んだときに感じた、突拍子もない発想の、宗教くさい人物という印象は全くなかった。
その上で、もう一度「モナド論」を読み直してみた。 彼の一生を少し勉強したおかげで、モナド論が思想の集大成として書かれたことも頭に入れて読んだ。そして「モナド論」より20年前、ライプニッツ自身がモナドに込めた思想をより具体的に説明するために書いた、「A New System of the nature and communication of substances, and also of the union that exists between the soul and the body」(https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/leibniz1695c.pdf から以下の短い記述をダウンロードできる)を、一種の解説書として参考にしながら読むことができた。
WebからダウンロードできるライプニッツのThe New System その結果、これまで全く理解できなかった、「モナド論」に込められた意図を理解できる気がした。そしてモナド論の思想が、生命科学に内在する基本問題を含んでいることに気付いた。そこで、ライプニッツについては、ほかの著作を無視して、「モナド論」に集中して見ていくことで、彼の思想の核心に迫ってみたい。
しかし、昔と比べて私の何が変わったのか?わからないまま読み進める忍耐力がついたわけではない。何が変わったのか伝えることは難しいが、一つ思い当たるのは、彼のモナドを考えるとき、そのまま書かれていることを理解しようとしないで、現代的な「細胞」の概念をモナドにオーバーラップさせながら読んだことだ。というのも、彼は英国の王立協会のOldenburgや有名なイタリアの病理学者Malpigiと親交があり、英国ではRobert Hook、オランダではレーベンフックを訪れ、顕微鏡下にうごめく微生物のイメージに魅せられ、ここからモナドの着想を得たと思われる(History of Phylosophy of the Life Sciences 39, 2017: 下図参照)。すなわち、ライプニッツもモナドを考えるとき、私たちが顕微鏡下で見る細胞と同じイメージを常に念頭に置いていたことになる。
ライプニッツが顕微鏡下の世界に魅せられていたことを述べた総説 前置きはこのぐらいにして、「モナド論」がどんな著作なのか、テキストを見ながら、私の理解を紹介していこう。「モナド論」を読み始めて最初に出会うのが次のセンテンスだ。
これからお話しするモナドとは、複合体をつくっている、単一な実体のことである。単一とは、部分がないという意味である。
複合体がある以上、単一な実体はかならずある。複合体は単一体の集まり、つまり集合にほかならないからである。
さて、部分のないところには、ひろがりも、形もあるはずがない。分割することもできない。モナドは、自然における真のアトムである。一言でいえば、森羅万象の要素である。
だからここには、分解の心配がない。まして、自然的に消滅してしまうなどということは、どう見てもありえない。
おなじ理由からいって、単一な実体は自然的に発生するわけがない。単一な実体は、部分の組合わせによってつくることができないからである。
そこでこう言える、モナドは、発生も終焉も、かならず一挙におこなわれる、つまり(神のおこなう)創造によってのみ生じ、絶滅によってのみ滅びる。ところが複合体では、どちらの場合にも、一部分ずつ、徐々におこなわれる
(以後引用はすべてライプニッツ. モナドロジー 形而上学叙説 (中公クラシックス) (Japanese Edition) Kindle 版.) この部分を読んで、内容に納得はできないにしても、あまり違和感はないと思う。アトムという言葉も使っているので、世界を構成している分割不可能な単位について考えていることがわかる。これらの最小単位の全ては宇宙誕生とともに現れ、永遠に、損なわれることなく持続するという話も、一種の質量不変則だと考えれば納得できる(現代風に解釈すべきだと言っているわけではない。ただある程度自分で納得できる部分がないと読み続けるのは難しい)。さらに「モナド」という言葉が、これまでの哲学で実在を表現する単位として使われてきたことを知っておくと、世界の「森羅万象」を説明するための実体論を展開しようとしている意図が理解できる。
出だしはまずまずなどと思っていると、均質で物理学的アトム概念を基本とした現代的な解釈はすぐに否定される。まず、モナド自体アトムのような基本単位ではなく、それぞれが独自に変化をする存在だとライプニッツは言い出す。
また、すべて創造された存在は、変化をまぬかれない。創造されたモナドも、同様である。しかもその変化は、どのモナドのなかにおいても、不断におこなわれている
そしてこの変化の内容について、
このような(変化の)具体的内容とは、「一」すなわち単一なもののなかにふくまれている、(無限な)多のことにほかならない。つまり、すべての自然的変化は徐々におこなわれるから、あるものは変化し、あるものは変化しない。したがって、単一な実体には部分はないが、(無限に)さまざまな動きや関係は、かならず存在しているわけである。
私たちはアトムと聞いて、物質の単位を思い浮かべるが、文章からわかるように、実体と言いながらも、モナドは決して単純な物質ではなく、内部に「変化できる無限の多を含んでいる」 実体で、この「多」こそが、個々の実体が変化する原動力になっていると言う。
さらに読み進むと、この「多」の正体が、エンテレケイアと名付けた「実体が変化するポテンシャルやエネルギーなどの原動力(19世紀の生気論の生気に近いと考えてもいい)、しかも低次から高次まで多様なエンテレケイアがあり、人間や動物では魂に相当する内的力として働くと述べている。すなわち、単一の実体には、それを動かし変化させる、目的やエネルギーまでを含んだ内因が統合されており、これが外見や行動の多様性を生み出していることになる。
唯物論、あるいは物理学的に考えると「多を内部に含む単一の実体」などといった概念はわかりにくい。私にとってもこのようななぞなぞのような言葉は躓きの石だった。しかし、先に述べたように、モナドに「細胞」という有機的な存在をオーバーラップさせた上で読み直してみると、ライプニッツがモナドという概念を通して、無生物から我々人間を含む生物まで、全て同じ基盤で考えようとしていることに気づき、多を内部に含む単一の実体(=細胞)という概念も荒唐無稽なイメージではないと思える様になる(この点については最後に議論したい)。
要するにモナドという概念を書いてある通りにそのまま受け取ろうとすると、現代に生きる我々にとって関係のない話になってしまう。その結果、ほとんどの思想と同様に、モナドも歴史の一コマとして片づけられてしまう。しかし、これほど不思議なモナド概念を、なぜライプニッツが構想するのか、その理由を考えてみると、この「なぜ」の現代的意味が少しわかってくる。
今回、この「なぜ」を頭に置いて読みなおしてみて、最後にわざわざ「モナド論」で自分の生涯を締め括ろうと思った動機が、デカルトの二元論拒否であることが実感できた。すなわち、デカルトのように心と身体を分離できるとする立場を拒否しようとすると、その代わりに、永遠の魂が身体(=物質)に宿ったのではない「私」とは具体的には何なのかという問題を説明する必要がある。これこそがライプニッツの生涯をかけたテーマで、これを最後にまとめようと「モナド論」を書いた。
考えてみると、現代人にとっても、いわゆる心と身体を統一した実体を構想することは簡単でない。現代でも何らかの宗教を信じる人は多い。おそらくそのほとんどは、魂は不滅で、肉体とは分離しており、肉体が滅びても魂は残るとデカルト流に考えているのではないだろうか。一方唯物論では、心という特別な存在を否定し、精神や魂を複雑な物理的実体から生まれる属性と考える(17世紀当時のラメトリの人間機械論はこれに近い)。従って、身体が消滅するとき精神も消滅する。これらに対し、ライプニッツはこのどちらでもない、第3の道、すなわち心と身体が統合された実体の可能性を追求した。しかし魂と身体が統合された実体とは何かについて、答えを構想することは現代でも難しい。
今回、彼のモナドが二元論でもない、唯物論でもない、第三の道だと気づいたとき、この心と身体の有機的統合の問題は、18世紀の自然史思想として始まった生命科学の「生命という目的を持った有機体」の概念に形を変えて受け継がれたことを確信した。
以前述べたように、生命科学にとってデカルト二元論の意義は、生命の属性でわからないことはすべて魂=神の世界に棚上げして、動物と共通の身体を研究すればよいとした点で、医学発展に大きく寄与した。すなわち、医学生物学の理解と、魂の不滅を信じるかどうかが全く切り離されたおかげで、皮肉にも科学としての生命科学は二元論から解放される。しかし、例えば「なぜ見るために目が存在するのか?」といった、生命本来の機能や目的について理解しようとすると、生命科学を単純な物質科学として片付けることはできない。
たとえば、生物には物理学的存在では説明できない生気が存在するとする生気論は20世紀後半まで繰り返し形を変えて顔を出してきた。このような生気論は、ダーウィンの進化アルゴリズムや、ゲノムを含む情報科学が生命科学の中に定着することで、もはや過去の話になったと私は確信しているが、突き詰めれば現代生命科学が扱おうとしている問題も、心と身体が統一された実体とは何かという問題だといえる。科学的データなど全く存在せず、自分の頭で考えるしか頼るものがない17世紀、結局顕微鏡下にうごめく生命物質を手がかりに、モナドという突拍子もない構想に思い至ったのも、十分理解できる気がしてくる。例えは悪いかもしれないが、現在でも、宇宙の状態を説明するために、物理学者たちはダークマターという概念を提案しているではないか。
こう考えると、第三の道を模索するというライプニッツの意思は理解できる。ライプニッツのモナド構想を導いた意思については、モナド論の二十年前に書かれた「The New System」に、彼がスコラ哲学から離れて、心と体が統合された実体を求めるに至った経緯を述べている文章にすでに明確に述べられている。
At first, when I had freed myself from the yoke of ·the schools, and thus of· Aristotle, I was in favour of ·an approach to physics based on· atoms and empty space, because this approach best satisfies the imagination—·i.e. it gives us a physics that we can always picture in our mind’s eye·. (最初スコラ哲学やアリストテレスから解放された後は、唯物論的な実体論を目指したことを述べている) I became aware that it is impossible to find the sources of real unity in matter alone,(唯物論では、心と身体の真の統一は難しい) Now a real collection or multiplicity must involve true unities·things each of which is one thing in a more basic way than a collection is one thing·—and these true unities must come from elsewhere, i.e.cannot themselves be members of the collection. • They can’t be material things, because what is material can’t at the same time be perfectly indivisible, which is what is needed for true unity(要するに見えない因果性が内在する実体が存在するかどうかを考えている).
ライプニッツ The New Systemより。 このように、若い時からライプニッツは二元論および唯物論的実体論を拒否して、心と体が統一された実体を求めるための第3の道を模索した。その結果が、モナドという今から考えるとわかりにくい概念に結実するのだが、チャレンジした課題自体が難しいため、私たち現代人にはモナドも概念も理解しづらいものになってしまった。
ただライプニッツは間違いなくこの課題を「モナド論」で解けたと確信し、デカルトの二元論を以下のように批判している。
「一」すなわち単一な実体において、(瞬間ごとに)多をはらみ、多を表現している状態、その流れがいわゆる表象である。だんだんわかってくることであるが、これとアペルセプションもしくは意識とは、区別しなくてはならない。デカルト哲学の末流が、この点で大きなあやまりをおかしたのも、意識にのぼらない表象は無とみなしたからである。彼らは、人間の精神だけがモナドであって、動物の魂とか、他のエンテレケイアとかは存存しないと思いこみ、また、俗衆とおなじように、長い失神状態を、厳密な意味での死と混同した。そしてそのあげく、魂と体とがまったく切りはなされているとする、スコラ学者の偏見に(さかさまに)落ちこんだばかりでなく、(そのメカニックな考えをさらにすすめて、)ものを正しく見ることのできない人たちに、魂はほろびるというあやまりをかたく信じさせるような結果にさえ、なってしまったのである。
ライプニッツは、デカルトやスコラ哲学に言及し、意識やアペルセプション(統覚)を起点として考える、すなわち考える自分を起点とする主観的実体論の問題を、「人間の精神だけがモナドであって、動物の魂とか、他のエンテレケイアとかは存存しないと思いこむ」 ことで、実体を否定することになると明確に批判している。そして、物質(物理的)因果性と、心(=神)の因果性を分離するのではなく、「私」も含む人間から、動物、そして無生物まで世界の全てを、物質とそれを動かす因果性が完全に統合された実体の集合として統一的に説明しようとした。
統一的と言ってももちろん人間から無生物まで、世界は複雑だ。このように様々な因果性が内部で統一された実体を求めるとすると、人間を構成するモナドと無生物のモナドを構成するモナドが全く同じと考えられるはずはない(事実顕微鏡下の細胞は同じに見えても実際には全て異なっている)。結局、どれ一つ同じ存在ではないモナド自身は、内なるエンテレケイアの違いにより様々な階層に分かれていると考えている。
モナドに属して、そのモナドを自分のエンテレケイアや魂にしている物体は、エンテレケイアといっしょになって、生物と呼ばれるものを構成する。また魂といっしょになると、いわゆる動物を構成する。ところで、この生物や動物の体は、常に有機的である。どのモナドも、それぞれ宇宙を自分流に映しだしている鏡であり、かつ宇宙は、完全な秩序にしたがってととのえられているから、それを表現するものの側にも、秩序はかならずあるのである。つまり魂の表象や、したがってまた、魂が宇宙を表現するさいその手段になっている体のなかにも、秩序はかならずあるのである。
だから、生物の有機的な体は、どれもいわば神の機械か、ある種の自然の自動体なのであって、人工のどんな自動体よりも無限にすぐれている。なぜかというと、人間の手になった機械は、その部分の一つ一つまでは機械ではない。たとえば、真鍮でつくった歯車の歯は、部分とかかけらとかになれば、もうわれわれの目には人工のものとはいえないし、歯車本来の用途から見ても、もはや機械らしいところはすこしもない。ところが自然の機械、つまり生物の体は、それを無限に分けていってどんなに小さな部分になっても、やはり機械なのである(細胞の概念に近くないだろうか?)。これが自然と人工、つまり神のわざとわれわれの仕事とのちがいである。
モナドの概念は生物に限るわけではないが、この引用から、彼が生物を統一的に考えているのがわかる。特に「生物の身体は、それを無限に分けていってどんなに小さな部分になっても、やはり機械なのである」という、部品概念を拒否した生物イメージは、ライプニッツの生物観をよく表していると思う。解剖学的、生理学的に生物の身体を考えるとき、往々にして器官や組織を部品として考えてしまうが、細胞生物学、発生生物学的に考えると、部品といった機械論的概念は全く馴染まない。間違いなくモナドの概念は我々が持つ細胞の概念と重なる。
以上「モナド論」からの引用に沿って思いつくままに述べてきた私のモナド理解をまとめ直すと、次のようになる。
まずこれまで見てきたように、すべてのモナドは、宇宙が創造されたとき神の力により創造され宇宙を隙間なく埋めている万物の構成単位だが、物理学的アトムで想像するような単一の単位ではなく、全てのモナドは創造時に目的とか形相と呼べる内部エンテレケイアを付与されている。このエンテレケイアはそれぞれのモナドで異なっており、この差により、無生物、生物、さらに高等動物から人間まで、異なる階層のモナドが形成される(宇宙の万物に、それ本来の場所が存在すると考えるアリストテレス の形相因に近い:私の勝手な解釈)。 生物も当然モナドの表現で、ただエンテレケイア(ライプニッツはエネルギーとか力動といった意味で用いて、無機物のモナドと有機体のモナドを区別している)、そしてそれがさらに高い段階になった魂と呼べるモナドからできており、無生物から区別される。すなわち、モナドにはそれぞれの最終目的に応じた内因的な力動やエネルギー、さらには生気と言っていいような力が統合されている。 この階層の頂点に全てのエンテレケイアの起源たる神が存在し、すべてのモナドに自立的力動を与えている。その意味で神を完全なモナドと呼ぶことすらできる。 個々のモナドには個性があり、それぞれが過去から未来まで、宇宙の秩序が詰まっている。詰まっているというのは、宇宙の秩序・法則に従うというのではなく、まさに創造の時点から未来の最終目的(アリストテレス の目的因)まで、それぞれのモナドに神によりプログラムされた因果性が実装されている。 この説明なら、大分わかってもらえたのではないだろうか(納得する必要はさらさらない)。
二元論でもない、唯物論でもない、心と身体が統一された実体を考えるために、結局神に頼らざるを得ないという点で、二元論もモナド論も、結局同じことだと断じることもできるが、生物学者としては見える因果性と見えない因果性が統合された実体を考えようとするライプニッツの方向性は評価したくなる。すなわち、宗教くささを差引いて考えると、モナド論を、生命科学の歴史を考えるときの重要な思想の一つとして捉えたい。
けれども一部の人たちのように、わたしの思想を誤解して、魂にはそれぞれ固着の、つまり永遠に自分のためにふりあてられている、物質の塊や部分があるなどと、考えては困る。魂は、いつでも自分に役だってくれる、他の下等な生物を所有しているのだなどと、考えては困る。物体はみな、川のなかにあるように、永遠に流れていて、ある部分がそこから出たかと思うと、ある部分がそこへはいったりする。そのようなことがたえずおこなわれているからである。
と述べているように、自分も他人も、全ての生物も世界を埋める全モナドの流れの中に(自然と言っていいのではないだろうか)存在しており、私ですら決して特別な実体ではないことを強調している点は、まさに現代の生物観に近い。しかも、生命の流れは均一ではない。個々のモナドは異なっており、階層的で多様だが、それでも特別の場所はなく、全て大きな自然の変化の一部という考えは現代的だ。
この点が特にはっきりするのは、彼自身が生物の生死をこの自然の流れの中で捉え、魂の生まれ変わりといった概念を明確に拒否している箇所だ。
というわけで魂は、自分の体をとりかえるのに、かならず徐々に、まただんだんにおこなうから、その全器官をいっぺんに失うことはけっしてない。動物の場合、変態はめずらしくないが、生まれかわり、つまり魂の転生は断じてない。また、体とまったく切りはなされた魂とか、体のない精霊などというものもない。ただ神だけが、肉体から完全に解きはなたれている。
神という言葉を気にせず読むと、新陳代謝、発生、さらには変態のような生命現象を例に生命とは何かについての彼の考えは共感できる。
ところで、精神つまり理性的魂についていえば、いまお話ししたことがらはじっさいどんな生物や動物にもあてはまると思うが〔つまり、動物も魂も世界とともにしか生ぜず、また、世界とともにしか滅びないという点〕、理性的動物の場合やはり特殊なところがあるのであって、それらのもつ微小な精子的動物が精子的動物にとどまっているかぎり、そこにはふつうの魂つまり感覚的な魂しかない。しかし、そのなかのいわば選ばれたものが、じっさいに受精をとおして、人間の本性をもつようになると、その感覚的魂も高められ、理性の段階、すなわち(次に述べるような)精神という特権的な状態にまで達するのである。
ライプニッツのモナドはレーベンフックの顕微鏡下で観察される微生物にヒントを得ていたが、上記の文章を読むと、レーベンフックの弟子のハートソーカーがスケッチしている、精子内に存在するホムンクルスの図を念頭に置いてこの文章を書いていたのではと思えてくる(図:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N._Hartsoeker,_Essay_de_dioptrique_Wellcome_M0016638.jpg より)。
実際、この文章と当時の生物学的な考え方から、ライプニッツも前成説を支持し、生殖細胞の中に個体のすべてが用意されており、受精によりその成長が誘導されたと考えているとされているが、実際には受精を契機として、精神や理性と言った高次のモナドが発生を通して新たに現れてくると述べており、また成長や死に関して新陳代謝の重要性が述べられているのを考えると、私には彼の思想が18世紀の後生説に近いように思える。
生物について、日本語やドイツ語では「生物」「Lebens Wesen」とそのまま表すが、英語やラテン語ではOrganismと表現される。ライプニッツの生物観は、発生により持続的に組織化されていく有機体論(Organicism)の概念に近く、その意味で18世紀の自然史を先取りした近代的な思想だと思う。
このように、デカルトが解剖学や生理学に思想の根拠を求めたように、ライプニッツは顕微鏡下の微生物の世界、すなわち外部の力がなくても、その内部に存在するエンテレケイアにより独立した動きを示す微生物に、すなわち現代的に考えれば「細胞」に思想の根拠を求め、細胞を起点に多様かつ複雑な生物を構想しようとした。
十分な説明になったかどうかはおぼつかないが、以上が私自身のモナド理解で、少しは「モナド論」を読んでみようかなと言う気になっていただいたのではないだろうか。
魂は不滅だと説く多くの現代宗教があることからわかるように、デカルトやスコラ哲学の滅びる身体と不滅の魂という二元論は、信じるかどうかは別にしても現代人にもわかりやすい。これに対して、魂と身体が統一された実体の生死を構想することは簡単ではない。結局この難しさが、モナド論を理解することの難しさの根底にある。しかし、まさに同じ問題を現在まで探求し続けているのが生命科学だ。そこで最後にモナド=細胞という仮説の下、私の考える近代的モナド論を考えてみたい。
ただ締めに入る前に、ライプニッツ理解のもう一つのハードル、宗教臭さについて少しだけ述べておく。スピノザもデカルトも、神がしょっちゅう顔を出すという意味で、19世紀以降の哲学と比べると宗教くさいのだが、なぜかライプニッツを読む時、宗教くささが際立って感じられる。この原因だが、デカルトの二元論は、魂を含む様々な非物理的因果性(目的、道徳、善悪などなど)のすべてを神の領域に棚上げした点で、もちろん宗教くさいのだが世俗に神が顔を出す機会は少ない。一方、ライプニッツのモナドの場合、世俗に存在する実体に心と身体が統一されており、しかもこの統一を神が保証していると考えているため、個々の実体を考えるときに常に神が顔を出さざるを得ない。このことを反映して、「モナド論」の終盤は神の役割についての話で終わっており、これが「モナド論」を理解することを難しくしている。
最終部分を引用してみよう。
つまり一般的に魂は、被造物から成りたっているこの宇宙の生きた鏡、似姿であるが、精神はさらにすすんで、神そのもの、自然の創造者そのものの似姿である。したがって宇宙の体系について知ることも、また、神が宇宙を建築したさいの図面をたよりに、そのいくぶんかをまねすることもできるから、精神はどれも自分の領分のなかにおける、小さな神のようなものである。
このようにして精神は、神と一種の共同関係にはいることができる。だから、精神にたいする神の関係は、たんに機械と発明者との関係ではなく〔神と精神以外の被造物との関係のように〕、君主と臣下、いやむしろ父と子の関係なのである。
とすると、すべての精神が集まれば、そこにかならず神の国(84)、つまりもっとも完全な君主が統治する、可能なかぎり完全な国家がつくられるという結論がすぐにでる。
この神の国、この真に普遍的な王国こそ、宇宙のなかにある道徳的世界である。神の作品のなかにおいても、これはもっとも高く、もっとも神に近い。神の栄光も、まさしくここに宿っている。もし神の偉大さと善意とが、精神によって認められ、讃美されるのでなかったら、神の栄光はないにひとしいからである。また、神の知恵や神の力は、どこにでもしめされているが、神がほんとうに善意をもってたいしているのは、この神の国をおいてない。
ライプニッツ. モナドロジー 形而上学叙説 (中公クラシックス) (Japanese Edition) (Kindle の位置No.1123-1136). Kindle 版. モナド論の最終部分でライプニッツは、モナドに内在する、目に見えない因果性の起源を明らかにして締めくくろうとした。ただ、現代の我々と違い、神以外の因果性の起源を思いつくことができなかった。そのため、ここではモナドの概念はほぼ神と一体化され、私が近代的だと議論してきたモナドも、結局宗教くさいドグマになってしまっている。しかしこれまでも、生命には超自然的な目的論が常にかぶせられてきた。これを神に任さず、科学的に考えようとしたのがダーウィン以降の生命科学で、モナド論の最終部分は気にせず読み飛ばしておけば十分だ。
ただ驚くのは、ここで示されている神や実体についての概念が、スコラ哲学で見てきた当時のキリスト教ドグマとは異なっている点だ。例えば、天地創造をモナド誕生と言い切ってしまって、当時のキリスト教とうまくやれたのだろうかと心配になる。このように、デカルトやスピノザと同じで、彼の神も、当時のキリスト教ドグマとは関係のない、人間ファーストの理神論的神といっていい。その意味でも、宗教臭いライプニッツも、17世紀の合理主義を代表していたと言える。
少し脱線したが、最後にモナド論を、モナド=細胞という新しい視点で私のモナド論を展開してみよう。
これを読んでいる読者の多くは生命科学に関わるか、興味を持っている方々だと思う。そこで生命科学の課題について考えてみよう。現在は専門化が進んで、生命科学と言っても、幹細胞生物学、脳科学、発生学などなど、それぞれの分野ごとの課題があるが、17世紀の哲学者と課題を共有するため、極めて抽象的な課題「私」とは何かを、現代生物学の視点から考えてみよう。
まず明らかなのは、私は「細胞」という実体が集まってできている。ここで細胞をモナドと読み替えると、私はモナドが集まってできていると言える。このモナド(細胞)は、単純な物理的粒子ではない。もちろん物理的物質からできてはいるが、その中にゲノムという情報が存在し、地球上最初のモナド形成時に獲得したアルゴリズムと共同して細胞のオペレーション、および細胞が集まった有機的発生、維持、そして死のオペレーションが働いている。言うまでもなく、地球上の生物は全て異なるゲノム情報を持っている。そして、単細胞から人間まで、種に応じてその情報は極めて階層的だ。しかし、情報は決して物理学的な量でも因果性でもない。すなわち、ライプニッツが構想したモナドに内在する見えない因果性と重なる。この情報は、神によって与えられたのではないが、38億年前、生命が誕生してから、ダーウィン進化アルゴリズム下で、刻々変わる地球上の変化に合わせて形成されてきた。そしてこの情報は、私たちの身体を形作る全てのモナド一つ一つの中に存在している。
私の始まりを考えてみよう。最初は意識はおろか一つのモナド以外は何も存在しない、他の動物と全く変わらない状態からスタートするが、内在するゲノム情報のおかげで、個々の細胞の振る舞いが調節され、私という複雑で有機的な個体を形成できる。このとき、人間など高等動物では、ゲノムやそれに随伴するエピゲノムなどの情報の他に、脳の神経ネットワーク、そしてそれを基盤とする言語という、全く新しい情報も形成される。しかし、これら全ては、私というモナドの表現を基盤として形成される。すなわち、ほかのレベルの情報の成立にはゲノム情報が必須だが、ゲノム情報からの独立した情報が、私に時間とともに積み重なる。実際、このような多様なレベルの情報が「私」に随伴しているおかげで、ライプニッツが言うところの、精神や理性を私は持つことができている。
この「私」についての生命科学をまだまだ発展させることは可能だが、これは現在の生命科学の課題になるのでこれでやめる。ここで強調したいのは、エンテレケイアやモナドと言った特殊な概念を全て現代生物学の用語に置き換えてみることが可能だという点だ。とするとまだまだ科学的には未熟な時代の産物だが、モナド論も生物学の著作とみることができる。確かに、目に見える因果性と目に見えない因果性の本当の統一について、ライプニッツは神の力に頼らざるを得なかった。しかし、現代の生命科学も、生物を構成する物質と、その実体に内在する様々な情報や、アルゴリズムが如何に統一されているのかについては、答えを見つけていないことも確かだ。その意味で、ライプニッツと同様未熟な段階にある。
結論:ライプニッツのモナド論は、現代生命科学の課題を先取りする注目すべき著作だ。
2021年8月24日
今回Covid-19に関する研究を眺めていて感じるのは、様々なワクチンや治療手段が前臨床研究から臨床治験に至るまで迅速に論文として発表されている点だ。とはいえ、全く論文を発表せずEUとFDAの承認を得たモノクローナル抗体薬がsotrovimab(VIR-7831)で、ベンチャー企業Vir Biotechnologyが開発、GSKが製造販売している(https://jp.gsk.com/jp/media/press-releases/2021/20210604_gsk-and-vir-biotechnology-announce-sotrovimab/ )。
この抗体について最初に知ったのは治験結果をレポートした3月のNature記事で、なんと2003年にSARSからの回復者から分離してきた抗体薬であること、そしてδ株を含むほとんどのCoV-2に高い効果を示すことが書かれていた。
残念ながらsotrovimabについてはその後も論文は発表されていないが、7月31日に紹介したワシントン大学からの論文(https://aasj.jp/news/watch/17067 )では、1)Covid-19から回復した36歳男性から、Sarbecovirusに属するほとんどのコロナウイルス(変異株も含めて)に反応するsotrovimabと良く似たモノクローナル抗体が分離できたこと、2)このような広いスペクトラムの反応性は、抗体が認識しているRBD領域がSarbecovirus共通に保存されているスパイク分子内に隠れている部位であること、3)抗体の結合はACE2との結合を直接阻害するのではなく、抗体結合によりスパイク自体の構造が変化し、スパイクS1領域が乖離してしまったpostfusion formができてしまうことで、正常な膜融合の確立を下げていることを示した。
おそらく上に書いたスパイクの変化はほとんどの方には理解不能だと思う。これは、スパイクを用いてウイルスが侵入する過程が極めて複雑で、一般に説明されているようなACEとスパイクが、鍵と鍵穴となってウイルスが侵入するといった話とは全く違うためで、これに興味ある学生さんはScience Museum Groupの提供している解説を読んでほしい(https://www.sciencemuseumgroup.org.uk/blog/coronavirus-the-spike/ )。
いずれにせよ、sarbecovirus全体に反応できる抗体が人間で誘導できることは明らかになったが、どの程度の確率でこのような抗体が誘導できるのかについてはわからなかった。
今日紹介するシンガポール国立大学医学校からの論文は、以前SARS-CoV1に感染既往のある人にファイザー/ビオンテックmRNAワクチンを注射すると、ほとんどのケースで同じようなsarbecovirus全体に反応する抗体が誘導できることを示した面白い論文で8月19日号のThe New England Journal of Medicineに掲載された。
この研究では、SARS既往のある人、Covid-19回復者、コロナウイルス既往歴のないワクチン接種を終えた人、Covid-19回復者でワクチン接種を終えた人、そしてSARS既往者でワクチン接種を終えた人、それぞれの血清を、δ株を含む様々なCoV2, センザンコウウイルス、コウモリウイルス、そしてSARS-CoV1ウイルスの感染実験(実際のウイルス感染ではなくpseudo-中和試験)系で調べている。
結果は驚くべきもので、ワクチンや感染はウイルス特異的な抗体だけを誘導するが、SARS-CoV1感染者がCoV2のスパイクに対するmRNAワクチン接種を受けると、ほぼ全員ですべてのウイルスに対する中和抗体が誘導される。さらに、この結果を確かめるために、真性のウイルス中和試験も行い、SARS既往者がワクチン接種を受けたときだけ、すべてのウイルスに対する中和活性があることを示している。
結果は以上で、誘導された抗体がワシントン大学の論文が明らかにしたスパイク部位を認識しているのかどうかはまだわからない。しかし、変異株も含めsarbecovirus全体に強く反応できる抗体がヒトで誘導できること、しかも抗原を工夫することで、ほぼ100%の確率で同じような抗体を誘導できる可能性が示されたことから、今後起こるsarbecovirus感染も含めてカバーできるワクチンの開発が可能になったことを示している。
すでに多くの人がワクチン接種した現状でも、同じようなクローンを引っ張ってこれるのか、まだまだハードルは高いが、パンコロナ抗体とパンコロナワクチンの可能性を示唆する驚くべき論文だと思う。
2021年8月23日
留学時代は別にして、在籍した研究室では、実験動物飼育は動物施設に中央化されていない場合も多く、助手から教授時代まで、週一回のケージ交換は教室全員が参加して行う恒例行事だった。善し悪しはともかく、この恒例行事のおかげで、実験マウスの生態をいろいろ観察することができた。特に、遺伝子改変した大事なマウスが生まれる場合、母親がしっかり育ててくれるよう、注意を払った。
今日紹介するニューヨーク医科大学からの論文は、新生児の声を聞いて子供を巣に運んだり、巣から出ないようにケアする母親の行動を、まだオスとの交配も経験したことのない処女メスが、他のメスから学ぶ行動の脳回路を解析した研究で、回路研究としては普通のレベルだが、行動としては個人的馴染みもあり、面白いと思った。タイトルは「Oxytocin neurons enable social transmission of maternal behaviour(オキシトシン神経は母親の行動の社会的伝達を可能にする)」で、8月11日のNatureにオンライン出版された。
研究では、処女メスと、子供をケア中のメス(子供も一緒に)を同居させたとき、メスが処女メスを子供のケアをするように導く行動を対象に、その脳回路を調べている。
数え切れないほどマウスの子育てを見てきたが、それでも他のメスが、処女メスに子育てを教えるという行動には気づかなかった。元々子育ては本能にプログラムされているが、教えてもらうことで1−2日でほとんどの処女メスは、この本能プログラムを発揮できるようになる。そして、この学ぶ期間にオキシトシン神経を抑制すると、学びが遅延することを明らかにしている。また子育てを学習中の処女メスのオキシトシン神経は、学習中に興奮する。
このオキシトシン神経は、学習とは無関係に、母親が子供のケアを行うときには必ず興奮する。従って上記の結果は、子供の声が聞こえる中で行われる、初経験の子供のケアを学ぶ過程にも、同じオキシトシン神経を興奮させて予行演習を行っているように見える。
次に、学習過程を単純にするために、処女メスに透明な敷居を隔てて、視覚インプットだけでメスの子育てを学ばせると、これだけでも子育て行動を学ぶことがわかる。また、オキシトシンがないとこの学習は起こらない。この状況でオキシトシン神経の興奮を見ると、期待通り興奮する。このとき学習なしで、光遺伝学的に視覚神経からオキシトシン神経の投射を刺激すると、同じように学習が起こる。
大事なのは、学習過程で興奮するオキシトシン神経が、子供の声を聞かせたときに興奮する聴覚領域に投射し、興奮すると子供の声に対する反応が高まる点だ。これは、オキシトシン神経から、聴覚領域への投射があることを示しているが、実際この投射経路にオキシトシン阻害剤を注入すると、学習効果はなくなる。
以上、少しごちゃごちゃした実験だが以下のようにまとめることができる。
子育て行動は元々本能としてプログラムされているが、オキシトシン神経の興奮が、子供の声に反応する聴覚領域に投射することで、学習により聴覚反応の閾値を下げる回路が成立しており、学習によりこの回路を刺激することで、本能プログラムが誘導される閾値を下げられる。すなわち、オキシトシン神経は、本能と学習をつなぐ重要なハブになっていることを示す。
オキシトシンは様々な社会行動に関わっているが、本来の本能行動を起こりやすくすると言うシナリオは面白かった。