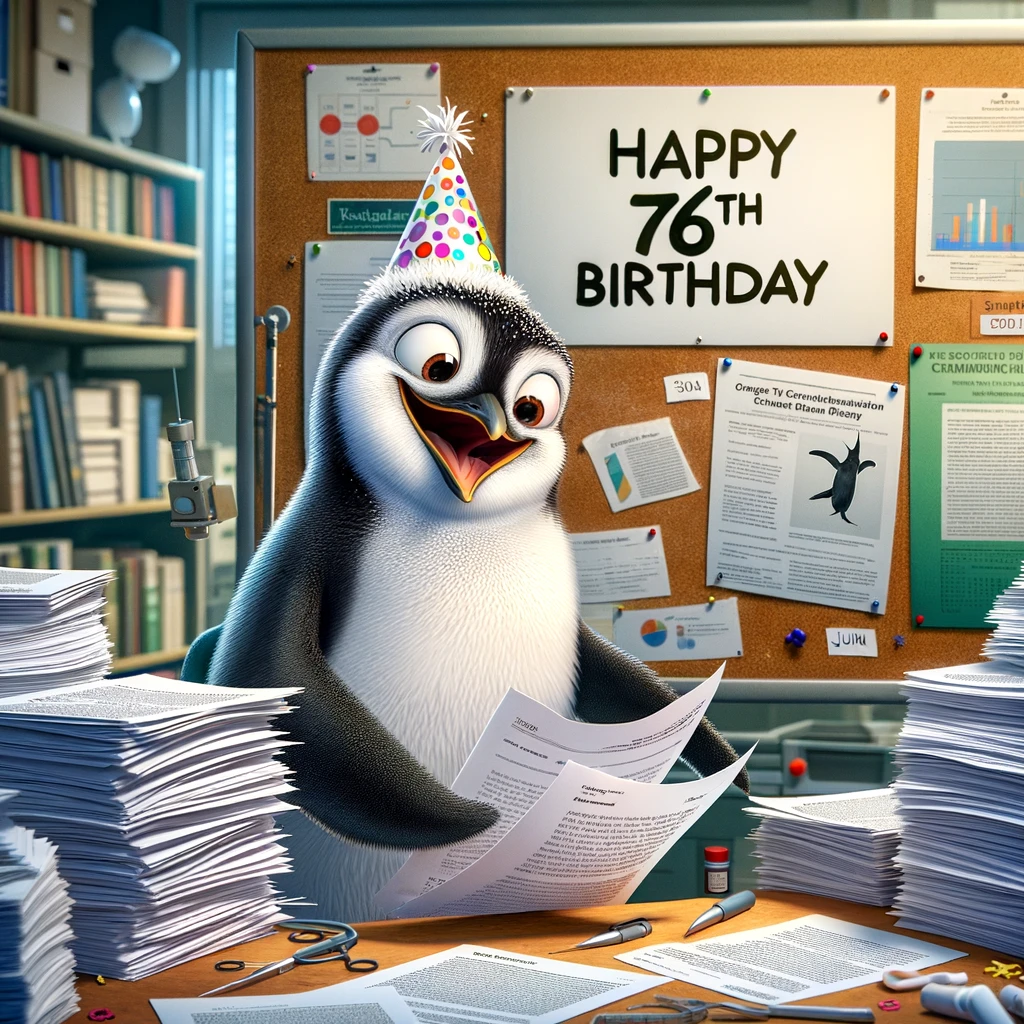2024年6月10日
Ras変異は半分以上のガンで見られ、ガン治療標的の一丁目一番地といえる。ただ、変異Ras に対する薬剤開発は一時ほとんど不可能ではないかとすら考えられるほど、多くのチャレンジをはねつけてきた(https://aasj.jp/news/watch/3288 )。しかし、G12C 型変異に対する薬剤開発の成功に続いて、昨年に入って新しい発想の Ras 阻害剤が開発され(https://aasj.jp/news/watch/23613 )個人的にも Ras がついに治療標的になりつつあると期待している。
今日紹介するノースカロライナ大学からの論文はその意味では極めてタイムリーな論文だが、これほど研究されてきた変異 Ras の作用がほとんどわかっていなかったことを実感させる研究で、6月7日 Science に掲載された。タイトルは「Defining the KRAS- and ERK-dependent transcriptome in KRAS-mutant cancers(変異 KRAS ガンの KRAS と ERK 依存性トランスクリプトームを定義する)」だ。
これまでも変異 KRAS が発現したとき細胞内に起こる変化についての研究は数え切れないぐらい存在する。思い起こすと、KRAS 経路の研究はショウジョウバエで進み、RAS-RAF-MEK-ERK というシンプルなキナーゼのカスケードの集約した様に思う。ただ、実際のガンでの経路になると、話はもっともっと複雑になっていた。
この研究では人間のガンを用いた KRAS のこれまでの研究が複雑になってしまった要因は、細胞が置かれた状況が複雑すぎた結果で、試験管内でできるだけ単純化して KRAS 阻害のしかも急性効果を調べることから始めるべきと考えて実験を計画している。
主に KRAS 変異を持つ膵臓ガンに、KRAS ノックダウンを行い24時間後の転写因子の変化を調べている。ノックダウンでも、あるいは阻害剤を用いても、例外なく細胞周期が抑制される。実際の臨床では、KRAS 阻害剤が効かない例が多く存在するが、少なくとも試験管内で維持された細胞株では変異 KRAS が必須だ。
そして、KRAS を阻害したとき変化する遺伝子発現は、ほとんどの細胞株でほぼ同じであることがわかった。しかも膨大な変化を誘導するシグナル経路もショウジョウバエの研究以来知られているRAF―MEK―ERK に集約され、これまで指摘されていた PI3K 経路などは、膵臓ガンでは特定することはできない。
そして、この転写の変化をもたらす下流の分子も E2F、MYC、SRF、FRA1 の限られた転写因子の活性化によることがわかる。これらの一部は RAS-ERK 経路で直接リン酸化され活性化されるが、サイクリン/CDK のリン酸化により維持される E2F のように、KRAS カスケードシグナルによる間接効果と考えられる分子が多い。例としては、細胞骨格リン酸化による SRF 転写因子の活性化だが、完全に ERK からの経路が特定できているわけではない。
このように、KRAS-ERK のリン酸化カスケードが重要であることは間違いなく、早い時期の細胞周期だけではなく、細胞周期後期を調節する APC/C 複合体のメンバーは直接 ERK によるリン酸化を通して調節されている。また、エピジェネティック調節因子もこの経路によるリン酸化で調節される。
このように、サイクリン/CDK 、エピジェネティックス、細胞骨格など細胞周期にとって必須の分子がこの経路により調節されており、その結果 RAS 阻害による細胞増殖の抑制が起こる。
この研究のハイライトは、ERK などの阻害実験を KRAS 阻害実験と比べることで、KRAS の効果はほぼ100%古典的経路を使って伝達されていることを明らかにした点で、KRAS 阻害の抵抗性出現も、この結果をまずベースにして考えていく必要がある。
極めて複雑で膨大な結果を単純化して紹介したが、この単純性から出発し直して KRAS シグナルを再検討し、これからの RAS 阻害剤を使った治療を丹念に観察することの重要性を示している。例えば薬剤が効かないのは本当に RAS-MEK 経路の急性抑制が消失したのか確かめた上で、抵抗性を考える必要がある。
いずれにせよ、KRAS 阻害が古典的経路に集約することを改めて確認した研究で、RAS 阻害薬時代の論理的治療計画にとっても重要な研究だと思う。
2024年6月9日
PD-L1 は PD-1 のリガンドとして、T 細胞の免疫抑制に関わることは一般にも広く知られ、PD-L1 に対する抗体も、PD-1 に対する抗体と同じようにチェックポイント治療に使われている。ただ最近になって、PD-L1は細胞膜だけではなく核に移行して転写に関わったり、小胞に移行して小胞と細胞骨格との相互作用に関わることが示されてきた。
今日紹介するロサンゼルスにある Cedars-Sinai 医学センターからの論文は、PD-L1 が微生物を取り込んだ時にできる小胞、ファゴゾームに発現して、マクロファージの酵母やカビ特異的反応の受容体として働いているという意外な機能を明らかにした研究で、6月5日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Profiling phagosome proteins identifies PD-L1 as a fungal-binding receptor(ファゴゾーム内のタンパク質をプロファイルする過程で PD-L1 がカビを認識する受容体であることが明らかになった)」だ。
このグループは、マクロファージが貪食した時にできる細胞内小胞、ファゴゾーム内での過程を研究するために、取り込んだ微生物の分子と直接相互作用する細胞側の分子を網羅的に調べるための PhagoPL という方法を開発して研究をしていた。微生物にパーオキシダーゼを発現させ、この酵素を用いてファゴゾーム内で微生物に直接相互作用するホスト側の分子をビオチンラベルする方法で、ファゴゾームで取り込んだ微生物を処理するための一般的分子とそれに加えて微生物の種類ごとに特異的に発現する分子を網羅的に調べることができる。
この実験を出芽酵母、黄色ブドウ球菌、そして大腸菌について行うと、PD-L1 が特に出芽酵母を食べさせたファゴゾーム内に移行して、しかも出芽酵母の分子と直接相互作用していることを発見する。この発見が研究のハイライトで、なぜ PD-L1 が出芽酵母のファゴゾームへ優先的に移行するか、不思議な現象だ。
ただ、この研究では PD-L1 と出芽酵母との相互作用に焦点を当てて研究を進めている。まず、出芽酵母のどの分子と相互作用するのかを調べ、なんと出芽酵母の膜上に発現したリボゾームタンパク質の一つ Rpl20b と直接結合することを発見する。リボゾームタンパク質が場合によっては細胞膜上に発現されることも初耳で、いろいろ不思議なことが起こっている。ただ、これは出芽酵母に限るわけではなく、カンジダでも Rpl20b が膜上に発現すると PD―L1 と結合するので、カビ類に広く見られる現象だと結論している。面白いことに、Rpl20b と相互作用する能力はもう一つのファミリー分子 PD-L2 にも認められる。
最後に、酵母の Rpl20b の分解を人為的に分解できるようにした方法を用いて貪食後に分解させたとき、ホスト側に起こる変化を調べ、Rpl20b と PD-L1 の相互作用の機能を調べている。この実験では、最初からサイトカインや自然炎症に関わる分子に焦点を当てて検索し、特にマクロファージの IL-10 や IL-6 分泌が少し低下することを発見する。最近の研究で PD-L1 は STAT3 と相互作用することがわかっているが、Rpl20b の過剰発現実験などから、PD-L1 と相互作用して生成する STAT3 のレベルが上がることから、おそらくこの経路が IL-10 転写抑制に関わると結論している。
残念ながらカビの感染時に何が起こるのかを示すことはできていないが、PD-L1 がカビのセンサーとして働いていることは、分子進化を知る上でも面白く、また意外な現象だと思う。
2024年6月8日
老化に伴って大本の血液幹細胞の数や機能が低下することが知られているが、にもかかわらず血小板産生だけが上昇していることが示されていた。今日紹介するカリフォルニア大学サンタクルズ校からの論文は、細胞分化で起こることが知られている Flk2 発現というイベントを記録できるマウスを用いることで、老化動物では血小板だけが正常幹細胞分化経路を外れて合成される経路ができることを示して、この謎を見事に解いた研究で、6月6日号の Cell に掲載された。タイトルは「An age-progressive platelet differentiation path from hematopoietic stem cells causes exacerbated thrombosis(年齢とともに増加する血小板分化経路が血栓症を悪化させる)」だ。
この研究では、Flk2 発現により誘導される Cre 組み替え酵素を用いて、それ以前の血液幹細胞と、Flk2 発現というイベントを経験した後の血液幹細胞を、赤い蛍光(Tom)と緑の蛍光(GFP)でそれぞれ区別できるマウスを使っている。
通常血液分化では Flk2 発現というイベントを経験するので、血小板も含めて末梢血は GFP を発現する。これは老化したマウスでも同じだが、驚くことに血小板だけ老化とともに GFP 陽性細胞が低下し、Tom 陽性細胞が5割を占めるようになる。これは巨核球の前駆細胞レベルですでに起こっており、血小板の分化経路の極めて早い段階で、Flk2 発現というイベントを通らない合成経路が老化とともに増えることがわかる。これは血液の老化に存在する新しい様式を示す驚くべき発見だ。
分化経路が違うということは、同じ血小板分化経路でも発現する遺伝子に違いが出るということで、Tom 陽性巨核球は single cell RNA sequencing で全くことなるクラスターを形成している。また血液幹細胞特異的遺伝子が Tom 陽性の巨核球前駆細胞へ分化した後も強く発現していることから、Flk2 発現をすっ飛ばした分化経路であることがわかる。
問題は、分化経路が変わったために、血小板としての機能が変化することで、まず増殖能が高く、血小板増加刺激に対して強く反応し、若いマウスと比べ144時間目の血小板数は3倍以上に達する。さらに、血小板機能自体も、活性から血栓形成に至るまでの過程が促進しており、結果血栓形成能が高くなっている。
実際老化したマウスの血管にレーザーで傷をつけて血栓形成を見ると、Tom 陽性の血小板の割合が多いことがわかる。すなわち、新しい老化型分化経路で合成されてきた血小板が血栓形成に優先的に関わっていることがわかる。
以上が結果で、おそらく老化に伴うエピジェネティックな変化で巨核球から血小板への分化経路だけが Flk2 を経由する経路から分化し、これが血栓形成能の高い血小板が老化動物だけで見られる原因であることがわかる。寿命の全くことなる人間でどうかについては、まだまだ研究が必要だが、この経路につながるエピジェネティックな変化がわかれば、明らかになってくると思う。そして、この変化は明らかに老化の指標として使えるので、今後面白い領域へ発展する予感がする。
2024年6月7日
冬眠は広く知られているが、Diapause(休眠)についてはあまり知られていないのではないだろうか。冬眠と異なり、休眠は外界の急な変化に対応しており、例えばマウスの胚盤胞は母親が外敵のような強いストレスに晒されると発生を長期間停止し、ストレスが解消してから発生することで、胎児が発達することで生じる危険を回避する。LIF は ES細胞を維持するための重要な因子だが、マウスでは発生の維持ではなく、なんと休眠の維持に関わっていることを Austi Smith らが発表したときは驚きだった。
この休眠が最もドラマチックな形で見られるのがアフリカの African turquoise killifish(以後 killfish )で、乾期で乾ききった池の中で何ヶ月も休眠を続け、短い雨期に生殖を行う種が存在し、休眠の仕組みを理解する重要な動物になっている。
今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、killfish が休眠性を進化させる過程をゲノムから調べた面白い研究で5月28日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Evolution of diapause in the African turquoise killifish by remodeling the ancient gene regulatory landscape( African turquoise killfish は古い遺伝子の転写を再構成することで休眠を進化させた)」だ。
この論文ではまず休眠で特異的に発現している遺伝子を探索し、その多くが薬5億年以上前、脊髄動物進化過程で起こったゲノム重複で生まれたパラローグ遺伝子であることを特定する。また、killfish以外の哺乳動物の休眠でも同じ種類の遺伝子が選択的に発現していることを明らかにする。一方、その後魚類の進化で起こったり、killfish 進化過程で起こった遺伝子重複による新しいパラローグ遺伝子はほとんど使われていない。すなわち killfish の休眠には脊椎動物進化という古い段階で発生したパラローグを使い回していることがわかった。
Killfish が休眠性を獲得するのは1千万年よりざらに新しい時代なので、様々な killfish のクロマチン構造を ATAC-seq で比較し、クロマチン構造の進化を調べると、休眠で発現する、極めて古い進化で発生したパラローグ遺伝子の転写調節領域のクロマチン構造が、極めて最近進化してきたことが確認される。すなわち、古い遺伝子に新しい転写システムを導入して休眠という特殊な状況で使っていることがわかる。
そこで、休眠遺伝子の発現に関わる転写因子を、転写調節領域の配列から特定すると、何種類かの転写調節因子の結合部位が、主に点突然変異によって新たに発生し、休眠で発現するようになることがわかる。そして、結合部位の変化が明らかな転写因子全てについて、CRSPR でノックアウトすると、REST、FOXO3、PAPR の3種類の転写因子ノックアウトで休眠遺伝子特異的な発現変化が起こることを明らかにする。
そして、それぞれの転写因子が脂肪代謝、オートファジー、シナプス、細胞周期などを調節して休眠という大きな変化を誘導することを示している。中でも脂肪細胞分化の核といえる PPAR が関与していることから脂肪代謝の変化について生化学的に詳しく調べ、長い脂肪酸のついたトリグリセライドの合成が休眠遺伝子により高まり、結果として細胞内の脂肪滴の量が増えることを示している。
以上、休眠という多くの遺伝子の発現をプログラムし直して、しかし正常とは違った条件で生きるための遺伝子発現システムの進化を、とてもわかりやすい物語として提示し、なるほど休眠とはこんなことだったのかと納得する面白い研究だった。
2024年6月6日
ガンは生まれついて持っている遺伝子に突然変異が重なって(somatic mutation)発生するが、一般にガン家系とか、ガンの遺伝とか言われてきたように、遺伝可能な多様性(germ line variation)が関わることも間違いない。もちろんガン遺伝子やガン抑制遺伝子そのものの多様性はガンの発生しやすさに直結するが、それに限らず実に多様な遺伝子がガンの遺伝リスクとして特定されており、例えば乳ガンだけでも200種類のゲノム多型がリストされている。
免疫反応を低下させる様々な多型もガン発生リスクになることはわかっているが、免疫を誘導するガン抗原そのものが遺伝性要因になる可能性はほとんど研究されていない。というのも、somatic mutation と比べると、germ line の変異は免疫発生時期から発現して、免疫系の自己と認識されるため、germ line変異はトレランスになると考えられてきた。
ところが今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、この先入観を疑い、トレランスになっている自己抗原でも免疫を誘導し、これがガン発生の免疫サーべーランスに関わる可能性を追求した面白い研究で、先入観を持たないことの重要性を示す論文だ。タイトルは「Germline-mediated immunoediting sculpts breast cancer subtypes and metastatic proclivity(生殖系列に媒介される免疫編集がガンのサブタイプと転移しやすさを決める)」だ。
自己抗原でも場合によっては自己免疫反応を誘導するように、全く変異のないガン遺伝子ERBB2 や H4ヒストンに対して T細胞反応が起こっていることが報告されている。すなわち、ホストの MHC との結合が弱いケースでは、トレランスが成立しない可能性がある。
この研究では、ガンで遺伝子増幅が起こる分子では、somatic 変異がなくても、それに対する免疫反応の起こりやすさがガンの発生頻度の差を生むのではないかと考え、様々なサブタイプ(例えば HER2 陽性、あるいはトリプルネガティブなど)が知られている乳ガンを例に、ゲノムデータベースを解析して、自己分子に対する免疫反応が乳ガンの発生に影響している可能性を調べている。
最初に調べたのは、乳ガンで増幅が見られる HER2 分子で、この分子由来のペプチドと高い親和性を持つMHCを持つ人と、親和性の低い MHC を持つ人を比べると、前者は HER2 陽性のガンになりにくいことを示している。すなわち、HER2 ペプチドを抗原として提示できる MHC を持つ人では、HER2 の増幅が始まると免疫サーべーランスが働くために、HER2 陽性のガンが発生しにくいことになる。
この現象をさらに裏付けるため、次に HER2 の germ line 変異が片方の染色体に存在して、複数のペプチドが提示できる場合と、変異が存在せず同じペプチドしか提示できない場合で HER2 陽性乳ガンの発生リスクを調べている。予想通り、MHC がペプチドを提示できる場合、変異の数が多い HER2 陽性腫瘍は起こりにくい。
他にも乳ガンで増幅がおこる遺伝子 MYC、SCKE などでも同じような現象が見られルことが示され、乳ガンに見られる増幅遺伝子の多くが、ガン抗原としても働いて、遺伝子増幅が始まった細胞の免疫サーべーランスに関与し、特定の乳ガンサブタイプの起こりやすさを決めていると結論している。
面白いことに、転移ガンについて同じように germ line 遺伝子の免疫原性とガンのサブタイプを調べると、初期ガンとは全く逆の現象が見られることを次に示している。HER2 を例に説明すると、転移ガンでは HER2 を提示して免疫を誘導できる MHC を持っている方が、HER2 陽性腫瘍の率が高くなる。他の増幅ガン遺伝子でも同じ傾向が見られることから、おそらく抗原に対する免疫反応が、ガンに対する選択圧となって、免疫をすり抜けた悪性のガンで見ると、逆境となる抗原を持っているガンの方が増えるという結果を招いたと考えられる。
結果は以上で、ガン発生時には、ガン発生に必要な増幅遺伝子は、免疫原性が高いほど免疫サーべーランスによりがんリスクを下げるが、このサーベーランスはより悪性で免疫をすり抜けるガンの選択圧としても働くため、悪性再発例では逆に germ line 変異が多いほど悪性になる傾向があるという結論だ。
実際の免疫反応は全く調べていないので専門外には少しわかりにくい論文になっているが、データベース解析だけからガンの免疫サーべーランスを見事に示した研究だと思う。
2024年6月5日
アルツハイマー病(AD)治療薬の開発はこれまで、βアミロイドやリン酸化 Tau タンパク質の合成阻害や除去を中心に行われてきた。ただ、これら分子の変化から神経細胞死までの間にはまだまだ多くのプロセスが複雑に絡んでいるので、他にも創薬ターゲットは間違いなく存在する。ずいぶん前のことになるが、2017年に HP で、患者さんの海馬に留置電極を設置して記録すると、脳波では解らないてんかん様の過剰な興奮が見られることを示したマサチューセッツ総合病院からの論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/6848)。これは AD 神経で細胞質への Ca 流入が高まっているからで、特に Store operated Ca チャンネル(SOC)がリン酸化 Tau により活性化されるチャンネルとして注目されてきた。当然 SOC などを AD 治療薬の直接標的にする可能性が考えられるが、Ca は細胞シグナルの要で、AD 特異的作用を得ることは簡単ではない。
今日紹介するベルギーの創薬ベンチャー reMYND からの論文は、Ca チャンネルにこだわることなく、まずリン酸化 Tau を発現する神経細胞特異的に起こる Ca 流入異常に基づく細胞死を防止する薬剤を探索し、これまで想定されなかったメカニズムの AD 細胞死メカニズムに対する薬剤の開発で、5月31日 Science に掲載された。タイトルは「Pharmacological modulation of septins restores calcium homeostasis and is neuroprotective in models of Alzheimer’s disease(セプチン機能を薬理学的に回復させることでアルツハイマー病モデルのカルシウムのホメオスターシスを回復し神経を保護する)」だ。
Ca 異常を抑える分子のスクリーニングについてはほとんど詳しく述べられていないが、いくつかのヒットから、リン酸化 Tau による神経死を抑える REM127 の開発に成功している。REM127 は神経死だけでなく、試験管内でアミロイドにより誘導されるシナプス結合喪失を防ぐことができ、AD 神経のカルシウム異常、そしてそれに続く細胞死の阻害薬として期待できる。
次に問題になるのが、この薬剤が AD 特異的な効果を示すメカニズムだが、かなり複雑なのでほとんど詳細を省いて紹介するが。AD 治療薬開発という目的に合致した作用機序が示されている。
まず REM127 が結合する分子を探索すると、細胞膜近くで微小管の調節を通して ER と SOC との相互作用を介して Ca 流入を調節している Sepsin6(SP6) が特定された。SP6 をノックダウンすると、細胞質への Ca の異常流入が高まり、細胞死が誘導されることから、SP6 は細胞膜直下で SP2、SP7 などと一緒に、SOC の活性化を抑えていることがわかった。
次にリン酸化 Tau を発現させる実験などから、通常神経細胞では SP6、SP2、SP7 により形成される細胞骨格の働きで、SOC が低い活性レベルで抑えられているのに、リン酸化 Tau が強く発現すると、この細胞骨格が破壊され、その結果 SOC が活性化され、細胞質内の Ca が上昇し、細胞死が誘導される。しかしこのとき REM127 が存在すると SP6 が安定化するとともに、ReS19-T 分子を新たにリクルートすることで、SOC 活性化を抑制する構造を再構築し、細胞死を抑えるというシナリオだ(それぞれの分子の名前については気にせず読み飛ばしてほしい。興味のある人は是非自分で調べてほしい)。
結論だけを述べたが、実際には構造解析、細胞への遺伝子導入やノックダウンを駆使して、SOC、SP6、そして ReS19-T 分子の関係や機能を細胞学的に詳しく調べている。ただ、このような詳細をすっ飛ばし誰もが知りたいのが、この薬剤の AD に対する効果だ。
これについては、Tau 及びアミロイドそれぞれのトランスジェニックマウスに経口投与する実験を行い、REM127 により、神経の異常興奮が押さえられること、アミロイドや Tau によるシナプス可塑性や長期記憶の低下を抑えられることを示している。
そして何より驚くのは、REM127 投与により、βアミロイドの蓄積やリン酸化 Tau 蓄積のような病理変化も抑制できる点だ。すなわち、Ca 異常がそれぞれの蓄積に深く関わっていることだ。これを見ると、アミロイドβ 蓄積から Tau リン酸化といった順番を再検討する必要が出てくるかもしれない。
いずれにせよ、カルシウムチャンネル自体ではなく、SOC と小胞体の相互作用を調節する SP6 を標的にし、しかも抑制ではなく、分子安定化を誘導して、Tau により破壊された SP6/2/7 骨格を再建するという複雑なメカニズムで、ついにAD 特異的な SOC 抑制に成功したといえる。
REM127 がそのまま人間に使えるかは全くわからないが、新しいメカニズムが明らかになったことは、AD 特異的 Ca 異常の治療薬が開発できることを示しており、期待している。
2024年6月4日
何でも調べてみるという気持ちが新しい発見を生む。今日紹介する中国北京、国立生物医学研究センターからの論文は、普通なら調べようと思わない脾臓内の自律神経支配を調べた結果、免疫による脾臓での胚中心形成にカプサイシン受容他 TRPV1 で刺激され、CGRPペプチドを分泌する神経が関わることを示した研究で、5月20日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Innervation of nociceptor neurons in the spleen promotes germinal center responses and humoral immunity(脾臓への侵害受容ニューロンの神経支配が胚中心形成と抗体反応を促進する)」だ。
侵害受容ニューロンとはカプサイシン受容体 TRPV1 を発現して痛みなど様々な刺激に反応する神経細胞だが、この研究では侵害受容細胞が発現するカルシトニン遺伝子様ペプチド(CGRP)をマーカーにして脾臓を染色し、侵害受容ニューロンが脾臓深く投射し、特に免疫の成熟に必須の胚中心に投射していることを発見する。
存在が確定すると、次は機能を調べることになるが、ジフテリアトキシンを使って TRPV1 発現細胞を除去する方法で内臓に投射する TRPV1 陽性細胞を除去し、免疫反応を調べると、抗体産生やクラススイッチはほぼ正常だが、抗原に反応する胚中心の形成が低下し、結果として抗原への親和性の上昇が抑えられることを発見している。
ただ、多くの臓器で侵害受容ニューロンを除去してしまうと、脾臓への投射以外の様々な要因が持ち込まれ解釈が難しくなるので、次に脾臓へ投射する神経回路をたどって胸椎レベル T8-T12 の後根神経細胞に由来することを特定し、より脾臓特異的な神経細胞除去を行う実験を行っている。結果は全身の侵害受容細胞を除去したときと同じで、抗原に反応して起こる胚中心の形成に侵害受容ニューロンが直接関わることがわかった。
後はメカニズムだが、ザクッとまとめてしまうと、抗原刺激による炎症刺激でプロスタグランジン E2 が脾臓で分泌され、これが TRPV1 を刺激する。この刺激は侵害受容神経の CGRPペプチドの分泌を誘導するが、これが B細胞上の Gタンパク質共役型受容体を刺激し、cAMP 上昇を誘導し、B細胞の抗原特異的反応を介して胚中心形成を促すというシナリオになる。
では抗原反応ではなく TRPV1 を刺激すれば免疫反応は高まるのか?おそらくこの最後の実験がこの研究のハイライトだと思うが、なんと免疫前にカプサイシンを含む食事をとらせ、免疫を行うと胚中心の形成が高まり、その結果抗体の抗原結合親和性が高まることを示している。この亢進は侵害受容を除去すると消えるので、まさに唐辛子を食べると免疫が上昇することを意味する。
実際その通りで、ウイルス感染実験で、まずカプサイシン入りの餌を28日間続けて食べさせ、7日目と21日目ににワクチンを接種、その後30日目にウイルスを感染させる実験を行い、カプサイシンを食べ続けた方が高い抗体反応を示し、感染防御を促進できることを示している。
結果は以上で、どのぐらいのカプサイシンを食べると免疫効果が高まるのかよく読んでみると、1Kgあたり100mgのカプサイシンを混ぜた食事をとらせている。このカプサイシン量がどのぐらい辛いのか調べてみると、農林水産省のサイトにタバスコソースが100-300mg/kgとなっていた。とすると免疫を上げるためにはタバスコソース並みの辛い食事を続ける必要があることになり、マウスがそんな食事を一ヶ月もよく続けたなと感心するとともに、唐辛子で免疫を上げるのは簡単でないことを悟った。しかし、超大辛でも問題ない人は、ワクチン接種前には是非挑戦してもいいかもしれない。
2024年6月3日
私は今日76歳を迎えた。友人の訃報や、病に倒れたという知らせを聞く機会がどんどん増えてきて、その先に確実に自分の番が待っていること毎日感じている。一方で、身体や頭の回りは間違いなく遅くなっているが、それでも毎日論文を読み紹介することで、科学の進歩に興奮し、新しい知識が目の前で広がっていくのを見て、本当に今日まで生きてきてよかったと感謝している。そして、身体の動くうちは、仕事であれ、遊びであれ、どこにでも出かけて日常とは違う時間を過ごすよう心がけており、今回の誕生日も外国で過ごしている。こんな気持ちをAASJのシンボル・フンボルトペンギンに置き換えてGPT-4にインプットすると、ちょっと若すぎるペンギンに描かれているとは思うが、なかなかいいイラストができたのでまず紹介する。
論文紹介もできるだけ自分と関わる論文と探した結果、メディアでも紹介されている順天堂大学南野さんの論文を紹介することにした。タイトルは「SGLT2 inhibition eliminates senescent cells and alleviates pathological aging( SGLT2 阻害は老化細胞を除いて病理的老化を軽減する)」だ。
これまで何回か紹介してきたが、死にかけの細胞を積極的に細胞死に導く Senolysis は、細胞の新陳代謝を促し身体の老化を抑えるとともに、老化がリスクになる肺線維症や腎硬化症などの治療の切り札として研究が進められている。76歳を迎えた私も自分事としてこの分野の研究に注目しているが、これまで Senolysis を誘導するとされた方法は、やってみる気には全くならなかった。ところが、南野さんたちが Senolysis を誘導すると発表した SGLT2 阻害剤は、循環器から腎臓まで、よくわからないが素晴らしい効果があることを知って、昨年から主治医にお願いして糖尿病治療薬として処方してもらっている。すなわち、今回南野さんたちが、基本的には様々な病的な状態で蓄積する老化細胞とはいえ、それを SGLIT2 が抑えることを示したことで、私も Senolysis 実験の当事者になったことになる。そんなわけで、誕生日この論文を取り上げた。
この論文以前にも、腎臓の尿細管では SGLT2 阻害によって、Senolysis が起こることが知られていたようだ。南野さんたちは、この効果が他の細胞でも見られないかと、高脂肪食により脂肪組織に蓄積する老化細胞について調べると、たった7日間 SGLT2 剤を服用させるだけで、老化した脂肪細胞を Senolysis 追い込むことを発見する。このとき、糖代謝は改善しているが、体重は変化しない。さらに、長く投与を続けると、かなり老化細胞を除去することができる。
これが Senolysis であることを確認するために、細胞周期が押さえられた細胞をジフテリアトキシンで積極的に殺す方法と比べると、ほぼ同じ効果があり、ジフテリアトキシンにより Senolysis を誘導すると SGLT2 阻害剤の効果がなくなる。
次にメカニズムを調べるために、まずインシュリンで同じ効果があるか調べると、血糖は低下させられても、Senolysisは起こらない。また、培養系で脂肪細胞にSGLT2を直接作用させても、Senolysisは誘導できないことから、全身レベルでの効果が脂肪細胞に影響していると結論している。
そして、メカニズムを理解できなかったが、SGLT2阻害剤を投与したマウスでは運動や低酸素で上昇して、AMPK 活性化する分子と知られるプリン代謝物 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl
最後に、高脂肪食以外の老化細胞蓄積が起こるケースとして知られている、APOEノックアウトマウスの動脈硬化巣で老化細胞を除去できること、さらにはラミンA変異による早老症など、異常な老化細胞蓄積を SGLT2 阻害剤が抑制できることを示している。
読んだ後まだまだ知りたいことが多いと感じた。最終エフェクターが AICAR としても、それが誘導されるプロセスをもっと知りたいし、AMPK が媒介しているならメトフォルミンでも同じ効果があるのか、そして何より正常食マウスでも他の臓器で Senolysis は起こるのかなどだ。
SGLT2 阻害の効果は糖尿病治療から始まって、今や心血管系、腎臓、そしてアルツハイマー病進行抑制まで多岐にわたっており、まだまだ研究の必要な分野だ。個人的には、腎臓でのグルコース再吸収阻害だけでは説明できないメカニズムがあるように感じている。そしてこの魔法の薬が、Senolysis 一般に効果があることを願いながら、誕生日を過ごしている。
2024年6月2日
歩くために必要な脊髄神経の刺激を AI モデルに記憶させ、それを硬膜外から刺激としてインプットすることで、慢性完全脊髄損傷患者さんを歩かせるローザンヌ工科大学の研究についてはこれまで何回も紹介してきた。ただ、このような AI を用いる方法は、脳との結合が実現できないと、複雑な刺激が必要な手や腕の機能回復にはつながらない。このため現在でもなおリハビリテーションが機能回復にとって最も重要だ。
さて、この論文を読むまで知らなかったのだが、腕と手のリハビリテーションを行っているときに、経皮的に損傷部位に電流を流すことで、おそらく新しい神経をリクルートし、リハビリテーションの効果が高められるという症例報告が発表されていたようだ。
今日紹介するローザンヌ工科大学からの論文は、ARCex-therapy と名付けた経皮的脊髄刺激法を、65名の患者さんで試した、より大規模な臨床観察治験で、5月号の Nature Medicine に掲載されている。タイトルは「Non-invasive spinal cord electrical stimulation for arm and hand function in chronic tetraplegia: a safety and efficacy trial(非侵襲的な脊髄電気刺激による四肢麻痺患者さんの手と腕の機能の回復:安全性と効果に関する治験)」だ。
この治験は、コントロール群を置く治験ではなく、全員が治療対象となる観察研究になる。ただ、最初の2ヶ月は通常のリハビリテーションだけを行い、その後リハビリテーション時に電気刺激を行う治療を2ヶ月行って、最初の2クールと、後の2クールを比較している。
対象は損傷後少なくとも12ヶ月が経過している慢性脊髄損傷患者さんで、様々な程度の障害を持っている。また介入は脊髄損傷部位に設置した2カ所の表面電極で、30Hz のシグナルを 10kHzキャリアーシグナルに乗せて刺激している。見た目で言うと、低周波マッサージ器に似ている。
最終的に60人が全4ヶ月の治験を終え、評価を受けている。まず安全性については中断を余儀なくされる副作用はないので、安全性は確認されたとしている。その上で、最初の2クールと、後の2クールを比較すると、1)腕を持ち上げる力のようなリハビリテーションで回復がしっかり見られ、電気刺激が特に影響がない評価項目、2)握る力などのようにリハビリテーションの効果は存在するが、電気刺激によりさらに回復速度が高まる評価項目、3)そしてリハビリテーションではほとんど回復できないが、電気刺激を始めたときからすぐに回復が始まる評価項目、の3種類の機能が存在することがわかった。
結果は以上で、これまでの症例報告を中規模の対象者を用いて確認した治験で、目新しいというわけではない。しかし詳細は省いたが、リハビリテーションで改善が見られない機能も電気刺激で回復の可能性が見られたこと、またリハビリテーションの効果を電気刺激がさらに高められるという結果は重要だと思う。副作用もなく、また治療方法も単純で安価(?)であることから、ダメ元でも腕と手のリハビリテーションにもっと積極的に採用したらいいような気がする。
この研究は、これまで何度も脊髄損傷の機能を AI で取り戻す方法を開発してきたローザンヌ工科大学から発表されたものだが、AI のようなハイテク技術だけでなく、もっとローテクの手法でも脊髄損傷患者さんの機能回復につながるなら積極的に臨床に提供しようとする意志が感じられる研究だと思う。まさに、ローザンヌが脊髄損傷治療の一大中心になろうとしているのがわかる。
2024年6月1日
ALK2分子の変異により筋肉が骨に変化する病気 FOP のメカニズムが明らかになったの今から10年近く前の2015年で、ALK2 に結合して BMP による刺激を抑える働きを持っていたアクチビンが、突然変異により抑制ではなく、刺激因子に変わってしまい、BMP が存在しないときでも筋肉の修復過程で誘導されるアクチビンが、ALK2 を刺激して骨に変えてしまうことがわかった(https://aasj.jp/news/watch/4043 )。従って、ALK2 特異的阻害か、アクチビンの阻害により骨化を抑えることができると予想され、昨年リジェネロン社によりアクチビンに対する抗体が実際の患者さんで骨化を抑えることが示された(https://aasj.jp/news/watch/4043 )。
この抗体薬はこれまで治験が行われた薬剤と比べ、特異性が高く、副作用が少ないと報告され、FOP 患者さんにとっては画期的研究結果として現在治験が続いている。ただ、抗体薬にはいくつか問題がある。一つは、最も重要な小児期から抗体薬を一生涯打ち続けることが可能かということと、アクチビン自体はそれ自身で ALK2 シグナル抑制以外の機能を持つこと、また FOP 変異型 ALK2 はアクチビン以外に BMP でも刺激を受けるため骨化を完全に押さえられる保証はないこと、などが問題になる。
このため、ALK2 機能を特異的に抑制する方法の開発も望まれている。今日紹介する創薬ベンチャーBlueprint Medicine Corporation からの論文は、ヒト ALK2 特異的小分子化合物を探索し、それがマウスモデルのFOPで筋肉損傷後の炎症から骨化までを抑えることを示した研究で、5月29日 Science Translational Medicine に掲載された。タイトルは「An ALK2 inhibitor, BLU-782, prevenerotopic ossification in a mouse model of fibrodysplasia ossificans progressiva(ALK2 阻害剤 Blu-782 はマウスモデルの FOP での異所性骨化を防止する)」だ。
この研究では ALK2 を含むキナーゼタンパク質と結合する小分子化合物の中から ALK2 に特異性の高い分子で、副作用の大きな原因になる ALK1 との結合が見られないリード化合物を特定し、このリード化合物と ALK2 との結合状態を構造解析し、これを元に至適な化合物への改良を加え、最終的に Blu-782 に到達している。同じことは、以前理研の後藤創薬チームでも試みたことがあったが、リードの選び方か、至適化に至るシステミックはアッセイ系が完全でなかったのか、残念ながら開発を断念している。その意味では、ALK1 をはじめとするキナーゼに反応せず、最終的に脳内への移行が抑制された Bu-782 に到達しているこの研究は、まさにプロの研究といえるだろう。
後はマウスモデルで、この薬剤の効果を調べている。実験では、筋肉を傷つけ、その修復過程で異所性の骨化が20日目ぐらいに観察されるモデルと用いて効果を調べている。驚くのは、傷つけた後に発生する浮腫及びその後の異所性骨化が Blu-782 で全て押さえられることで、この一連の過程全体に FOP 変異を持つALK2 が関わっていることがわかる。
最初は傷をつける前に腹腔投与を行って効果を確かめているが、その後傷をつけるより前から経口投与を続けていると、同じように浮腫と異所性骨化が押さえられることを示している。
実際の患者さんの状況を考えると、いつ筋肉に障害が起こるかわからない。従って、実験のように最初から予防的に投薬が必要になる。そのためには飲み薬が最も適している。ただ、もし筋肉損傷が起こったことが検出できるなら、検出後に服用して余計な副作用を防ぐ可能性もある。そこで、筋肉損傷後2日目、4日目から投薬を開始する実験を行っている。
結果は筋肉損傷後2日目だとほぼ完全に抑えることができるが、4日目では抑制できない。すなわち、浮腫が起こる段階ですでに骨化へのプロセスが走っていることがわかる。また、投薬を途中でやめる実験を行うと、12日目まで投与を続けると効果は見られるが、1週間で服用をやめたのでは完全に効果が失われる。以上のことから、FOP 型変異を持つ ALK2 が働く時期が、2日目から12日目までの、まだ骨化が起こっていない段階であることがわかる。
ワクチン接種のように、筋肉障害を誘導した時期が明確な場合はともかく、通常いつ筋肉障害が起こったのか明確でない FOP 患者さんの場合、当面この薬剤をほぼ一生涯飲み続けることになるが、今後自覚以前の筋肉障害の早期検出法が開発されれば服薬回数を減らすことは可能になるかもしれない。いずれにせよ、希少疾患の代表といえる FOP でも、創薬ターゲットが明らかになることで、抗体薬から ALK2 特異的な内服薬まで、治療法開発が加速するのを見ると、本当に心強い。