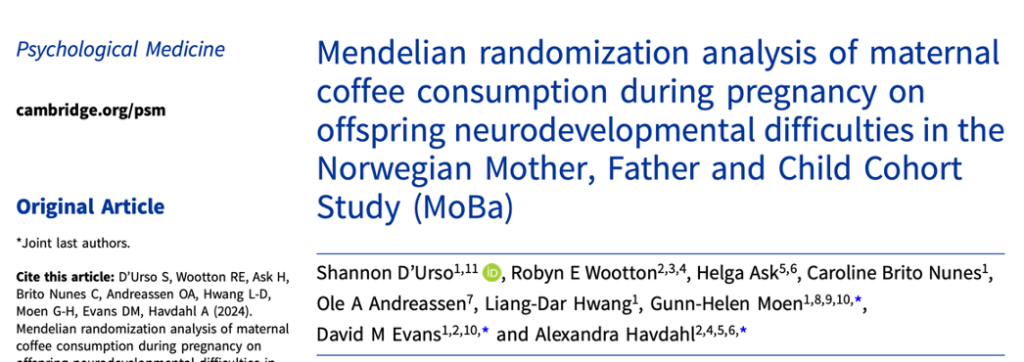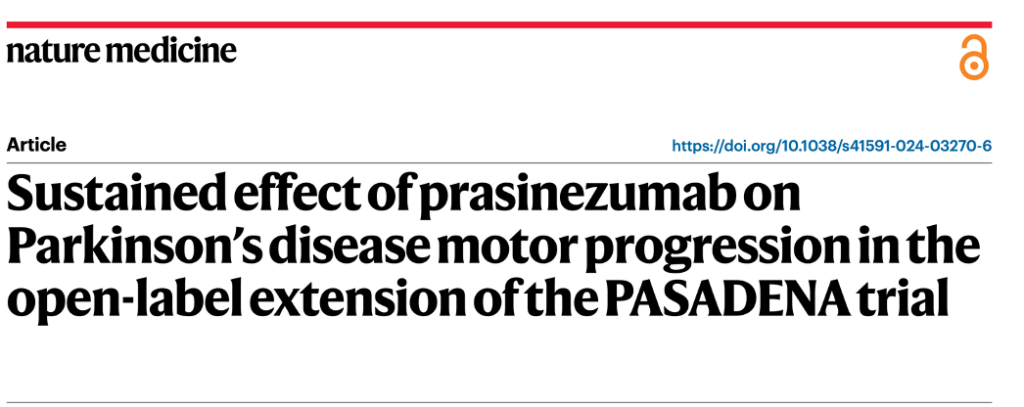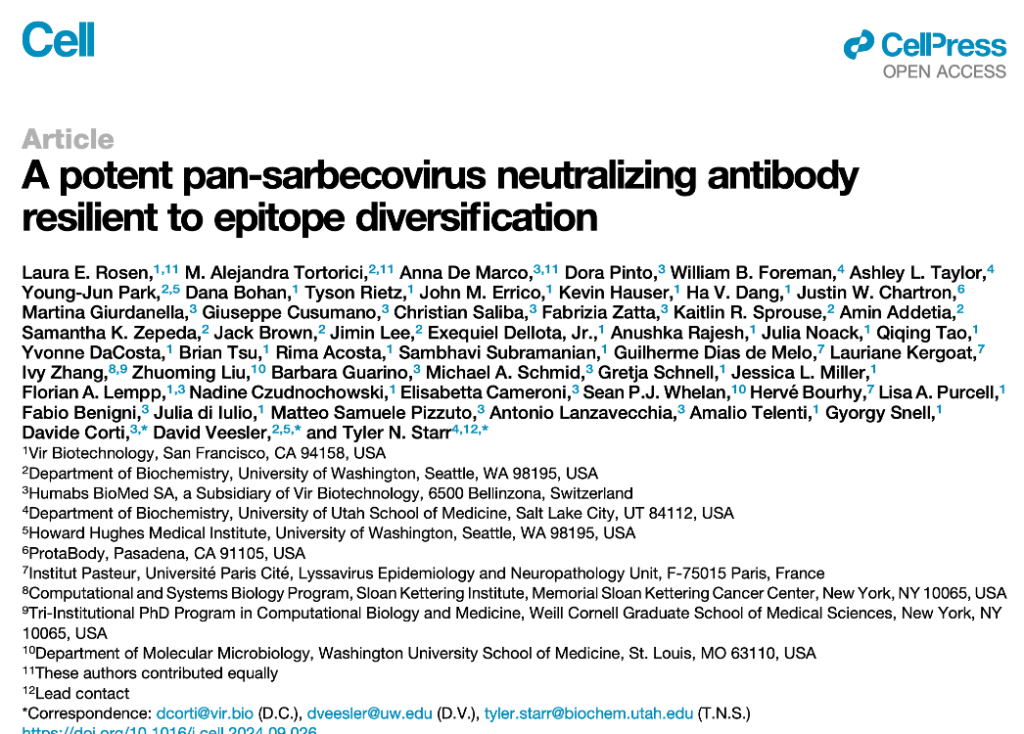2024年10月21日
ギリシャの民主主義を衆愚政治だと絶望したプラトンは、人知を超えた哲人王を夢見た。そして現代では哲人王ではなく、カリスマ性を持った鉄人王を求める結果、プーチンのような怪物が誕生することになる。これに対し、市民が熟議を繰り返し、一つの一般意志に到達することを夢見たのがルソーだが、東浩紀さんは2011年、「一般意志2」を書いて、新しい IT 技術を使えばルソーの夢見た一般意志を実現できるのではと大胆な提案をして、若い世代が本当に新しい可能性を示していると感心した。
そして今日紹介するグーグルからの論文は、大規模言語モデルを用いることで民主主義的熟議が可能であることを示し、東さんの夢が可能であることを実際に示した研究で、10月18日 Science に掲載された。タイトルは「AI can help humans find common ground in democratic deliberation( AI は民主主義的熟議の共通基盤を見つけることを助けることができる)」だ。
しかしノーベル賞の熱気そのままに、Google の進撃が止まらない。今回は LLM を用いて熟議が可能かを検証しているが、完成したモデルにドイツの社会哲学者で、熟議民主主義を唱えたユルゲン・ハーバーマスの名前をとってハーバーマスマシン (HM) と名付けている点でも知性を感じる。現代最もホットな研究現場の一つだろう。
この研究ではチンチラと名付けた、パラメーターのサイズは小さくても、学習するトークン数が1兆を超えるよう至適化した LLM を用いている。
具体的には6人からなる75グループに、英国が抱える様々な問題について、意見を書いてもらったあと、多数派意見を割り出し、そこからグループの結論をアウトプットして、それに対して批判した意見を再度集め、それを計算して新しいグループ意見をアウトプットすることを HM に行わせている。そして、様々な民主主義の問題について、HM が役立つかどうか検証している。
最初は、同じ意見、批判、それを聞いた意見を聞いたあとで、そのグループの議論の共通基盤を人間にも書いてもらって、HM から出てきた答えと、参加者に評価してもらう実験を行い、グループ全体の意見を反映したまとめを書くという点では HM の方が優れていることを示している。
その上で、意見の調整がある程度できる結果、HM によりグループ内で異なる意見は合っても、分断意識はかなり解消される。
というのも、それぞれの意見をエンコーダーで多次元(768次元)空間としてエンベッディングしたあと、多数意見と少数意見にまず分類し、そのあと批判を聞いたあとでの意見を加えてできた新しいエンベディングを調べると、少数意見が尊重され、専制主義に陥っていないことがわかる。
そして、HM を200人の参加者による議論の場で利用してもらうことで、議論の基盤をそれぞれが理解し、よりまとまった意見に集約できることを示している。
実際に示されたデータを正確に評価する能力は持ち合わせていないので、著者らの結論をそのまま紹介したが、東浩紀が「一般意志2」で期待していたことが、可能になっている実感がある。今回は小さなグループについて意見調整するという形の使用だったが、モデルの能力を考えると、スケールアップは問題ないように思える。
さらに感心したのは、科学のように単純に多数決ではない手続きでコンセンサスをとる方法と、HM は全くことなる点をわかっている点で、今後科学的判断も尊重する熟議モデルが形成されると期待できる。
いずれにせよ、またGoogleから今の社会に一石が投じられた。
2024年10月20日
パーキンソン病 (PD) やレビー小体認知症、さらに他系統萎縮症は通常シナプスで働いている αシヌクレインが異常構造をとることで凝集し、オリゴマーや繊維化を形成することで細胞障害性が発揮されるとされている。レビー小体のように繊維化したシヌクレインが集まるとかなり目立つが、細胞毒性で見るとオリゴマーが毒性を持つとされている。
元々変異を持つ αシヌクレインは別として、どうして正常の分子が異常構造をとるのかについては諸説あってまだよくわかっていない。ところが、今日紹介する熊本大学からの論文は、シヌクレインのオリゴマー形成を誘導するのが RNA G-quadruplex である可能性を示した論文で、少なくとも私にとっては全く新しい話なので驚いた。タイトルは「RNA G-quadruplexes form scaffolds that promote neuropathological a-synuclein aggregation(RNA G-quadroplexes は神経病原性の αシヌクレイン凝集のスキャフォールドを形成する)」で、10月18日 Cell にオンライン掲載された。
RNA G4 についてはほとんど知らなかったので調べてみると、グアニンを多く含むリピートを持つ mRNA や non coding RNA で、Gがカチオンを中心に4つ集まった環状構造をとり、それが重なってできる特殊な構造で、人間のゲノムにはテロメアを中心になんと376000箇所もこの構造をとる部位が特定されており、特に相分離を通して RNA 結合タンパク質を隔離したりする役割、そして様々な神経疾患での関与が知られるようになり、急速に研究が進んでいる分野だ。
この研究ではシーズと呼ばれるシヌクレインを加えた神経細胞で起こるシヌクレイン凝集形成過程を詳しく調べ、最初 RNA 結合タンパク質とともに相分離体を形成することに気づく。そして、それ自身では相分離が起こらない αシヌクレイン相分離させる分子機構を探索して、RNA G4 がシヌクレインのN末端と結合して凝集を誘導できることを発見する。これが研究のハイライトで、私の知る限りシヌクレインの凝集メカニズムについての全く新しい可能性が示されたことになる。
次に、細胞質の Ca濃度が高まったストレス神経細胞を用いて、シヌクレインシーズで処理された神経細胞でシヌクレインと RNA G4 が相分離体を形成していることを証明している。そして、パーキンソン病の患者さんの死後脳でもリン酸化されたシヌクレインが RNA G4 と結合していることを確認している。
次に RNA G4 の由来を、凝集が起こっている神経細胞内でシヌクレイン結合RNAの配列から、すでに G4構造をとることが知られている CAMK2a と Dlg4 遺伝子の mRNA と特定している。
次にこの凝集が神経細胞機能を傷害することを調べるため、光を当てると凝集が誘導される cryptochrome2 分子を利用した一種の光遺伝学を用いて、シヌクレインが RNA G4 により凝集すると、シナプス発火が抑えられることを示している。また、同じシステムがドーパミン神経に導入されたマウスの中脳に光を毎日照射し、シヌクレインの凝集を誘導し続けることで、ドーパミン産生細胞が低下すること、そしてその結果運動障害が現れることを示している。
これだけでも十分面白いのだが、さらにシヌクレインシーズを中脳に注射することで誘導されるドーパミン神経細胞の減少を、RNA G4 のシヌクレインとの結合を阻害分子PPIX に転換される 5-ALA を経口摂取することによって抑えられることを示している。
以上が結果で、全くオリジナルなアイデアに基づいて、利用可能な薬剤まで示した力作で、今後はシヌクレイン・シード注射という急性モデルから、患者さんの iPSモデルや、遺伝子改変マウスを用いた検証実験が必要だと思うが、期待したい。
また 5−ALA はサプリとして利用されているので、治験のハードルも低いように思う。
私自身は熊本大学と縁が深い。その意味で、このようなオリジナルな研究が発表されたことは単純にうれしい。
2024年10月19日
ガンワクチンというと、ペプチド、mRNA、ウイルスベクター、抗原パルス樹状細胞などを思い浮かべるが、バクテリアをガン免疫を含む様々な治療に使おうとする試みも盛んに行われてきた。このHPでガンとバクテリアで検索すると(https://aasj.jp/?s=%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%AF%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2&x=0&y=0 )実に様々な可能性が試みられていることがわかる。
今日紹介するコロンビア大学からの論文は、大腸菌にガンのネオ抗原を組み込んでワクチンとして使うためには、バクテリアの方の操作がいかに重要かを教えてくれる研究で、10月16日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Probiotic neoantigen delivery vectors for precision cancer immunotherapy(バクテリアによるガンネオ抗原デリバリーを用いたガンのプレシジョン医療)」だ。
すでに述べたように、バクテリアにガン抗原を発現させて使うアイデアは、バクテリア自体の自然免疫誘導性が高く、また遺伝子操作が簡単であることを考えると、当然のことだと思う。
この研究では、マウス大腸ガンやメラノーマをモデルに、エクソーム解析からガンのネオ抗原セットを特定し、それぞれ19種類、42種類の抗原遺伝子をプラスミドに組み込んで、腫瘍局所、あるいは静脈内に注射している。
まず結論から述べてしまうと、今回設計した大腸菌は、腫瘍局所でほとんど増殖せず、すぐに免疫系に取り込まれ、CD4及びCD8T細胞免疫を誘導するだけでなく、免疫抑制的な細胞を抑える働きがある。その結果、ガンの予防だけでなく、すでにガンが大きくなってからワクチン投与を行っても、ガンを抑制することができる。また、静脈注射を用いれば、転移ガンについても免疫を誘導できるという素晴らしい結果になる。
このような最終結果もそうだが、この研究のハイライトは大腸菌の操作が尽くされている点だ。もちろん、ネオ抗原遺伝子も大腸菌の転写翻訳系に合わせて設計するのは言うまでもないが、大腸菌ゲノムに隠れているプラスミドを除くことで、発現が抑えられないようにしている。
その上で、Lon、OmpT と呼ばれるプロテアーゼ遺伝子を除くことで、外来のタンパク質が大腸菌内で蓄積できるようにしている。大腸菌が取り込まれると、結果大量のネオ抗原がマクロファージや樹状細胞に取り込まれる。ただ、これだけならエンドゾーム内でクラスII MHC に提示されるので、大腸菌にリステリア菌の持つ listeriolysin を発現させることで、エンドゾーム内で pH が上昇すると、穴が空いて細胞質へタンパク質が流れるようにして、クラスI MHC と結合した抗原が、CD8キラー細胞を誘導しやすくしている。
その上で、大腸菌を静脈から全身投与しても体内で増殖ができないよう、マクロファージに取り込まれやすくするとともに、血液に触れると増殖ができないように操作している。
こうすることで、マウス実験では全く安全だが、ネオ抗原の生産が80倍を超え、期待通りTh1型ヘルパーT細胞とキラーT細胞の両方が誘導できるシステムを作り上げている。
以上が結果で、できれば多くのガンでシェアされている、例えば変異KRASなども抗原として用いられるかも調べられると、より多くの人に使えるワクチンになると期待できる。他にも、ガンを制御する分子のデリバリーにも使えるので、意外と主流になるかもしれない。
2024年10月18日
私とほぼ同い年の西田敏行さんを偲ぶ報道で一色のありさまだが、糖尿病を煩っておられたと報道されている。西田さんの死亡の直接原因についてはほとんど報道がないが、突然死と聞くと、私たちの頭に浮かぶのが、糖尿病で血糖コントロールを強化した結果起こる低血糖による心臓突然死の可能性だ。
2型糖尿病だけでなく、インシュリン治療法が進歩した今も、1型糖尿病の最大の問題はインシュリン過剰による低血糖だ。この問題を解決するには、血糖が高いときだけ効果を示すインシュリンがあればいいのだが、開発は簡単ではない
今日紹介するデンマーク、ノボノルディスク社研究所からの論文は、低血糖時には働かないインシュリンが開発できたという夢のような報告で、10月18日 Nature にオンライン掲載された。タイトルは「Glucose-sensitive insulin with attenuation of hypoglycaemia(低血糖を弱めるグルコース感受性インシュリン)」だ。
この論文を読むと、低血糖では働かなくなるインシュリン開発はすでに1970年代に始まっており、様々な可能性が試されてきた歴史がイントロダクションで述べられており、勉強になる。そこで紹介されている、血糖が高いとインシュリンが溶けでる仕組みはなじみ深いが、反応性の面から実現できていない。
この研究では、ブドウ糖及び配糖体と異なる親和性で結合するマクロサイクルと呼ばれる環状化合物をインシュリンの片方の端に結合させ、さらにもう一方の端にリンカーでつながった配糖体を結合させたインシュリンを設計している。通常配糖体が近くのマイクロサイクルと結合するので、インシュリンの活性部位がカバーされて、作用が抑えられる。そこに、一定以上の濃度のブドウ糖が来ると、アフィニティーに応じて配糖体を追い出し、マイクロサイクルに結合する。そうすると、インシュリンの作用部位が解放されて、インシュリンとしての効果が発生するというわけだ。
様々な調整を加えた結果完成した NNV2215 と名付けたインシュリンは、グルコースと配糖体がマイクロサイクルを競合する構造になっていることを、化学的、構造学的に確認し、また血清存在下条件でも期待通り働くことを確認したあと、ラットとブタを使った実験で、体内で使えるか調べている。
NNC2215 は L-グルコース、D-グルコースのどちらにも反応することを利用して、L-グルコースを投与して血中等濃度を高めると、D-グルコース値が低下する実験で、確かに生体内でもブドウ糖濃度に合わせて作用することを示している。他にも、インシュリンを一定にしてブドウ糖を上昇させる耐糖試験で、血糖に合わせて NNC2215 がインシュリン効果を発揮することを確認している。また、ブタでも NNC2215 連続投与とインシュリン連続投与で、NNC2215 で低血糖にならないことを確認している。
最後に、薬剤で β細胞を破壊した糖尿病ラットを用いて、インシュリン補助剤として十分利用可能であることを示している。
結果は以上で、例えば長期投与で免疫反応が誘導されないかなど、確かめる点は数多く残るが、低血糖に陥らないインスリンにかなり近づいたと思う。ただ、気になるのは値段で、おそらく通常のインシュリンの量を減らして、レベル維持に使うといった使い方がされると思うが、現実的な値段が示されるのを期待して待とう。
2024年10月17日
最近、妊娠中の女性の行動と生まれてきた子供の病気について調べた疫学論文を2編、目にしたので紹介する。
最初はフィンランド東フィンランド大学からの論文で、妊娠中のエクササイズが生まれてきた子供の喘息を防ぐという研究で、10月9日 Med 紙にオンライン掲載された。
基本的には妊娠中のエクササイズ状況を自己申告してもらい、生まれてきた子供が5-7歳時点で喘息症状を示すかを調べている。
全く交絡因子を考慮せずに、エクササイズと喘息発症の相関を調べると、エクササイズをしているグループは驚くなかれ、オッズ比で0.5まで喘息の発症率が低下している。ただ、妊娠中も運動を欠かさないという生活スタイルは、それ自体母親の健康(例えば BMI など)と相関するので、生後の子供の環境も含めてそれらの影響を考慮して計算し直しているが、食生活も含めてほとんど影響がない。
また、毎週3回以上、汗をかく程度のエクササイズをしておれば、それ以上の強度のエクササイズ、あるいはもっと頻回にエクササイズするグループと明確な差はない。
以上が結果で、汗をかくぐらいの運動を週3回以上続ければ、子供が喘息にかかるオッズ比が0.53まで低下するなら、推奨するに値する。
もう一編の論文はオーストラリア ブリスベーン大学からの論文だが、実際はノルウェーで行われた調査で、妊娠中の女性のコーヒー摂取と、生まれた子供の脳神経異常の関係を調べた研究で、10月9日 Psychological Medicine にオンライン掲載された。
コーヒーにはカフェインなど脳神経に働く化合物が含まれているので、胎児の脳発達への影響はこれまでも懸念され、また社会性や言語発達への影響が指摘されてきた。ノルウェーはコーヒー消費国らしく、この問題への関心は深く、この研究が行われた。対象は5万人規模の妊娠女性で、コーヒー摂取については妊娠前、15週、22週自己申告で調べている。
この研究でも、妊娠中もコーヒーを飲んだ人と、飲まなかった人で比べると、18ヶ月から8歳まで調べた、社会性、言語発達、注意障害など様々な子供の神経症状との相関が見られる。
ただ、コーヒーを続けるということは、他の生活スタイルなどの交絡因子が存在する可能性があるので、それらを考慮して計算すると、ほとんどの相関はなくなってしまう。すなわち、タバコやアルコールなどコーヒーと関わる生活習慣(間接喫煙も含めて)の影響が大きい。それでも、8歳時点での社会性など、明確にコーヒー摂取との相関が残っている。
そこで、コーヒー摂取に関わる遺伝子多型を加えて調べる Mendelian Randomization を、対象者のゲノム検査に基づいて行っている。コーヒーの嗜好性は、カフェイン代謝、脳の報償回路など、様々な過程に関わる多型が特定されている。
結果は、個人レベルの多型をベースに Mendelian Randomization を行うと、それまで相関が認められていた社会性の異常もほとんどコーヒーは無関係になるという結果だ。
何か Mendelian Randomization へと誘導されている気分になる研究で、コーヒー好きのノルウェー人にとっては朗報かもしれないが、ある程度の相関はあるので、妊娠中はやめる残したことはないような気がする。
2024年10月16日
ダーウィンがダーウィンフィンチの図を前に一般の人に講義をしているイラストを描いてほしいとGPT4にインプットするとできてきたイラストをまず掲載する。
大変よくできているのだが、ダーウィンフィンチの進化についてはかなりいい加減だと思う。すなわち、変化はほとんど毛色で表現されており、顔や嘴はほとんど同じだ。図作成のためにインプットしたプロンプトが悪いのだと思うが、実際のダーウィンフィンチの種分化の研究は嘴の形を中心に行われている。
今日紹介するマサチューセッツ大学からの論文は、ガラパゴス島のフィンチの嘴の形状が種分化に必須の交配率にどう関わるかを調べた面白い研究で、10月11日 Science に掲載された。タイトルは「Ecological speciation in Darwin’s finches: Ghosts of finches future(ダーウィンフィンチの生態学的種分化:未来のフィンチの幽霊を使う)」だ。
未来のフィンチの幽霊というタイトルが面白い。なぜこんなタイトルがついたのか。この研究が目指している生態学的種分化をわかりやすく説明すると、地理的に分離された同じ動物が、その環境に合わせて進化するとともに、他のタイプの個体との交雑がなくなるため、交雑の起こらない異なる種として分離することを示している。ダーウィンは、嘴の形が環境の食べ物により決まっていることを観察して、自然選択の説明に用いた。
ただ、フィンチは飛べるので、ガラパゴス諸島のような距離間では、完全に交雑を防ぐのは難しい。また、ニッチを探して同じ島でも種分化は起こる。これを説明するために、嘴の形や大きさが変わると、鳥の交配に必要な鳴き声が変わるのではと考えられ、研究が続けられてきた。
この研究では、嘴の変化によって起こる鳴き声の変化を人工的に作り出して、それに対する野生のフィンチの反応を調べる実験で、嘴の形状変化が食性だけでなく、メーティングの行動変化を誘導して種分化を促進することを調べており、これが「未来のフィンチの幽霊の声」になる。
この鳴き声作りで参考にしたのが、干ばつを1回経験すると、堅い実を食べるためにフィンチの嘴が大きくなることで、1回から6回まで干ばつを経験すると、嘴の深さが6mm大きくなる。このような嘴による鳴き声を採取して、人工的に干ばつ経験1、3、6回の鳴き声を作って、それを野外で聞かせ、フィンチの行動を調べている。
要するに人工的に作成した鳴き声を自分の仲間と認識するかだが、3回ぐらい干ばつを経験したあとででも、ちゃんと自分の種として認識するが、6回となるとかなり反応が鈍くなる。すなわち、嘴の大きさは、ある一定のレベルを超えると食性だけでなく、メーティング行動を変化させられる。
もちろん、他の個体との関係により、鳴き声の好みが変化することが知られており、その影響を調べると、この社会的な認識の効果は大きい。しかしそれでも嘴の大きさは十分影響力があり、種分化の力になり得る。
以上が結果で、未来のフィンチを想像して声を作成したというのがハイライトだが、実際の観察実験は大変だと想像する。
2024年10月15日
私のように高齢になっても、脳は変化し続けており、今日の脳は昨日の脳と違っている。例えばニューラルネットを基盤した AI は、ある時点でネットワークの結合様態をフリーズできるかもしれないが、私たちにはそれは不可能だ。この日々変化する脳を捉えることができるか、ともかくやってみようと計画されたのが、今日紹介するフィンランド Aslto 大学からの研究で、10月8日 Plos Biology にオンライン掲載された。タイトルは「Longitudinal single-subject neuroimaging study reveals effects of daily environmental, physiological, and lifestyle factors on functional brain connectivity(一人の人間の脳イメージを長期間とり続けることで、毎日の環境や生理状態、そして生活スタイルの脳の結合性に及ぼす影響が明らかになった)」だ。
この研究のハイライトは、一人の人を19週間、週2回 MRI をとり続けて、脳の変化を調べたことだ。もちろん脳全体の変化を調べるのは簡単でない。そこで前頭前野内の結合性 (PFC) 、前頭側頭ネットワーク (FPN) 、デフォルトモードネットワーク (DMN) 、Cingulo-opercularネットワーク(CON) 、体性感覚運動野 (SM) など重要な回路に絞って結合性を「調べている。
被験者は、様々なウェアラブルモニターを装着し、毎日の心拍数や呼吸数の変化、睡眠の質などを調べるとともに、毎週質問に答える形でそのときのムードなどを調べている。
こうして得られた様々なデータの間での相関を徹底的に調べたのがこの研究だが、結果自体は少しわかりにくく、また驚きはなく、なるほどと納得するものだった。いくつかの例を以下に示す。
睡眠の質、特に睡眠中に動きが止まらない場合、注意を維持する課題を行っているときのDMN、SM、CONなど多くのネットワークの結合性が低下する。
睡眠の質や日常の活動性が一定しない場合、記憶課題を行っているときのDMN、FPN、CONの結合性が低下する。
睡眠の質とともに、心拍数など自律神経系の状態が振れる人は、安静時のDMN、FPNの結合性が低下する。
以上の相関は全て、脳内ネットワーク結合性に長期的効果を及ぼす。
一方で、書くネットワークの結合性の状態は、生活での活動性に強く影響し、結合性が低い場合、活動性が低下する。
自律神経系の変化は、特に安静時の結合性の変化につながる。
個々でそれぞれのネットワークの機能について、誤解を恐れず簡単に紹介すると、DMN は脳を自己に統括する機能、PFC は記憶や計画実行、FPN は認知と感情の調節、CON は注意や行動調節、そして SM は感覚と運動調節に関わるが、単純に決めつけない方が良い。従って、それぞれの結合性が低下していること、また短期や長期の効果があることの意義については、まだまだわからない。
結局、ともかくやってみることで、毎日脳は変化することを実感したというのがこの研究だろう。しかし面白いことを着想するものだ。被験者は33歳の健康な女性ということだが、よく協力してくれるものだ。
一見馬鹿げた研究だが、実際には人間の研究が進むべき方向を示しているように思う。
2024年10月14日
ガンや炎症でエピジェネティック変化が起こり、それまで抑制されていたトランスポゾンなどの反復配列の一部が転写され、それが自然免疫を刺激し、ガンの増殖や免疫に大きな影響があることが知られている。例えば、新しいガン抗原ができて、自然炎症を起点にガンに対する免疫反応が起こると、ガンの進行抑制に働くが、最近ではガンの上皮間葉転換を促し、浸潤や転移を促進することも報告されている。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、内容としてはこれまで示されてきた反復配列転写によるガンとガンの環境変化を扱っているが、組織レベルでがんと周囲組織を調べたという点では全く新しい研究で、10月8日 Cell にオンライン掲載された。タイトルは「Disruption of cellular plasticity by repeat RNAs in human pancreatic cancer(ヒト膵臓ガンの反復配列由来RNAは細胞の可塑性を破壊する)」だ。
この研究のハイライトは、膵臓ガン組織を CoxMx と呼ばれる in situ hybridization を何度も繰り返して細胞レベルで転写を調べる方法で、LINE、ORF、HSAII など数種類の反復配列由来RNAとともに、他の転写RNAを調べ、反復配列がどこで発現しているかを克明に調べた実験で、膵臓ガンが反復配列転写レベルが最も高いこと、線維芽細胞や血液系の細胞では大体半分程度しか検出できないことを示している。
このような反復配列転写物はエクソゾームを介して回りに伝搬されることが知られているが、実際膵臓ガンを中心にその検出レベルが低下するパターンが観察される。そして、LINE を反復配列転写物の指標として、ガン周囲線維芽細胞の転写を調べると、反復配列の高い線維芽細胞は、筋繊維型から炎症型へシフトすることを示している。
あとは、これまでの研究と同じで、エクソゾームを介した膵臓ガンとガン組織の線維芽細胞との相互作用を、主に試験管内の実験で調べている。
まずほとんどの反復配列転写物は筋繊維型線維芽細胞を炎症型に変化させる。ただこれだけで止まらず、膵臓ガン周囲の線維芽細胞の培養上清を膵臓ガンに加えると、膵臓ガンの上皮間葉転換を誘導することができる。このように、ガン組織でガン細胞と周囲線維芽細胞が相互作用を行い、悪性化を進めている。
さらにエクソゾームの中に反復配列転写物が存在することで、一種のウイルスに対する反応が誘導され、これにより誘導されるインターフェロン反応が、線維芽細胞だけでなく、膵臓ガン細胞にも影響を及ぼす。
これまで、いくつかのグループにより膵臓ガンの上皮間葉転換を誘導できるのは、2重鎖をとりやすいセントロメア付近の反復配列であることが知られている。従って、反復配列転写物の中で2重鎖をとりやすい HSAII などは、膵臓ガンと線維芽細胞で異なる反応を誘導し、インターフェロン反応と協調してより複雑なガン組織を形成してしまう。
本来なら、この点こそ組織学的に調べてほしかったのだが、データはあるはずなのに詳しい組織学的解析はできておらず、上皮間葉転換が起こったガンで HSAII が高いという従来の結果を確認するのにとどまっている。他にも、同じ反復配列転写物に対して、膵臓ガンと線維芽細胞では使っているシグナル経路が異なっていることも示している。
いずれにせよ、反復配列転写物の出所が膵臓ガン自体だとすると、このシナリオはなかなか理解しがたい。このような研究を組織レベル、単一細胞レベルでできるようになったのは素晴らしいので、組織データに絞った解析をしてほしかったと思う。しかし技術は着実に進んでいる。
2024年10月13日
今日は将来有望と思われる抗体治療論文2編を紹介する。
最初は、ロッシュ社研究所から論文で、パーキンソン病でプリオンのように働いて神経細胞を傷害する凝集シヌクレインに対する抗体を用いた治験で10月8日Nature Medicine にオンライン掲載された。
アルツハイマー病で現在使われている抗体はアミロイドβのように細胞外に蓄積する分子なので、抗体さえ届けば進行を遅らせられることはわかるが、Tauやシヌクレインは細胞内で作用すると考えられ、抗体治療の可能性は少ないと考えられていた。しかし、Tauでも抗体が細胞内で分解を促進したりすることがわかってきており、当然シヌクレインに対する抗体も、神経細胞間の伝搬だけでなく、神経を保護する可能性も十分ある。
実際、凝集シヌクレインに対する抗体を用いた小規模治験が行われており、効果が見られている。この研究はその延長で、厳密にコントロールされた第二相治験での症状に関する効果を中間報告したもので、4年の経過を調べている。この研究の特徴は最初から抗体治療を受けた人と、最初は偽薬で、1年目から抗体治療にスイッチした患者さんでの効果を調べている。
結果は極めて有望で、運動機能障害の進行を抗体投与により強く抑制できると結論している。ただ、ドパミントランスポータSPECT検査では、脳画像上の改善は見られていない。従って、今後さらに長期の経過が調べられる予定だが、有望だと思う。
次は Vir Biotechnology とワシントン大学、ユタ大学からの論文で、Covid-19の原因ウイルスSARS-CoV-2(CoV2)は言うに及ばず、なんとほぼ全てのコロナウイルスの感染を抑制できるモノクローナル抗体の開発で、10月8日 Cell にオンライン掲載された。
これまでも、突然変異体も含めて多くのコロナウイルスをカバーできる抗体の開発が進められてきた。この研究では、最初の武漢株ワクチンを受けた後、オミクロンに感染した患者さんから分離したB細胞が分泌している抗体遺伝子を分離、それを Cov2、CoV1 を含む様々なコロナウイルスパネルと反応させ、広く反応する抗体を選び、これを酵母に発現させて変異を誘導し、その配列を機械学習で選択することで、最終的に調べたほとんどのコロナウイルスに反応できる VIR-7299 を選んでいる。
たしかにコウモリに存在するいくつかのウイルスの中には反応しないものもあるが、現実的にほぼ全てをカバーできると言っていい。
また、多くの変異体について調べても、これまで知られているCoV2変異体はほぼ全てカバーできている。さらに、VSVウイルスを用いた感染システムで、抵抗性の変異体の出現を見ても、これまでの抗体と異なり、ほとんど抵抗性の変異が現れない。
なぜこのような特徴を持つに至ったかを、構造的に解析している。詳細を省いて、わかりやすく言うと、まずウイルスの受容体結合部位に、抗体の3つの可変部分全てを使って結合し、しかも結合部位の構造を決める分子の骨格に直接結合して、抑制を行っている。この骨格は感染に必須であるため、変異が起こりにくい。さらに、多くのアミノ酸と水素結合を形成していることから、親和性も高い。
結果は以上で、明日からでも治験を行って、将来の新しいコロナパンデミックの備えとしてほしいものだ。
2024年10月12日
統合失調症の遺伝性は高く、一卵性双生児の場合5割の一致率がある。またゲノム研究から、100を超すコモンバリアントがリスク多型として特定されており、これに加えて病気の発症を強く後押しする希な遺伝子変異も特定されている。しかし、ガンと異なり体細胞で新たに生じる突然変異の研究はほとんど行われていない。これは、ガンと異なり変異が細胞の増殖につながらないため、検出が難しいので、脳組織で体細胞突然変異を特定できても、それは発生の早い段階で起こり、細胞のモザイク構成につながる変異に限られる。
今日紹介するハーバード大学からの論文は、61人の統合失調症の解剖で得られた脳から特定の神経細胞を集めて、そのゲノムを詳しく解析し、体細胞突然変異を特定し、統合失調症でみられる特徴を探った研究で、10月11日 Science に掲載された。タイトルは「Somatic mosaicism in schizophrenia brains reveals prenatal mutational processes(統合失調症で見られる脳細胞のモザイクは発生前の突然変異を明らかにする)」だ。
統合失調症の脳細胞から核を取り出し、50万個から100万個の核から得られるDNAを、平均239カバー率で全ゲノム解析し、一塩基変異や、コピー数の変異などを特定している。繰り返すが、突然変異はあらゆる細胞で起こっているが、ガンのようにその細胞が増殖しない限り、検出するのは難しく、200カバーレートから発見できるのは、変異が発生した後、細胞が一定期間増殖する発生時期に限られてしまう。そして、このような変異は、病気にかかわらず誰でも持っている。
実際、統合失調症と正常人の脳を比べても、検出できる一塩基変異の数はほとんど変わらない。しかし、変異の場所を遺伝子発現調節因子の結合サイトとの距離でプロットしてみると、統合失調症では結合部位に近い場所の変異頻度は正常の数倍にも上昇する。すなわち、転写調節サイトに近い体細胞突然変異が発生期に生じると、統合失調症になりやすいことを示している。
次に、そのときの変異の種類を調べると、メチル化DNAが脱メチル化された後、再度メチル化を受ける発生初期に生じた変異のタイプが目立っている。すなわち、受精後いったん失われたDNAメチル基が細胞分化とともに再構成される着床期に起こった変異が、統合失調症のリスクを形成していることがわかる。
さらに、体細胞で検出できる一塩基多型は、各個人にユニークで、発ガンに関わる場合以外は繰り返して観察されることはないが、調べた統合失調症61人で、3回繰り返した同じ場所の同じ一塩基多型を発見している。この変異のタイプから、除去修復機構の異常が関わることが推察できるが、それ以上の解析はできていない。しかし、この部位の変異が統合失調症リスクとして関わることが強く示唆される。また、除去修復の低下が背景として統合失調症のなりやすさに関わる可能性が示唆される。
最後に細胞株にマーカー遺伝子を発現させる系で、変異部位の遺伝子発現調節活性を調べて、実際にエンハンサー活性が多型で異なることを機能的に確認し、今回統合失調症特異的として特定してきた一塩基多型の中に、確かに病気発症と関わるリスク変異が含まれていることを示している。
結果は以上で、大変な研究とはいえ統合失調症の理解に大きな光が差したというわけではない。しかし、特定の変異が統合失調症で選択されていることを見ると、ガンと同じで体細胞突然変異の寄与も調べることが必要だと実感する。