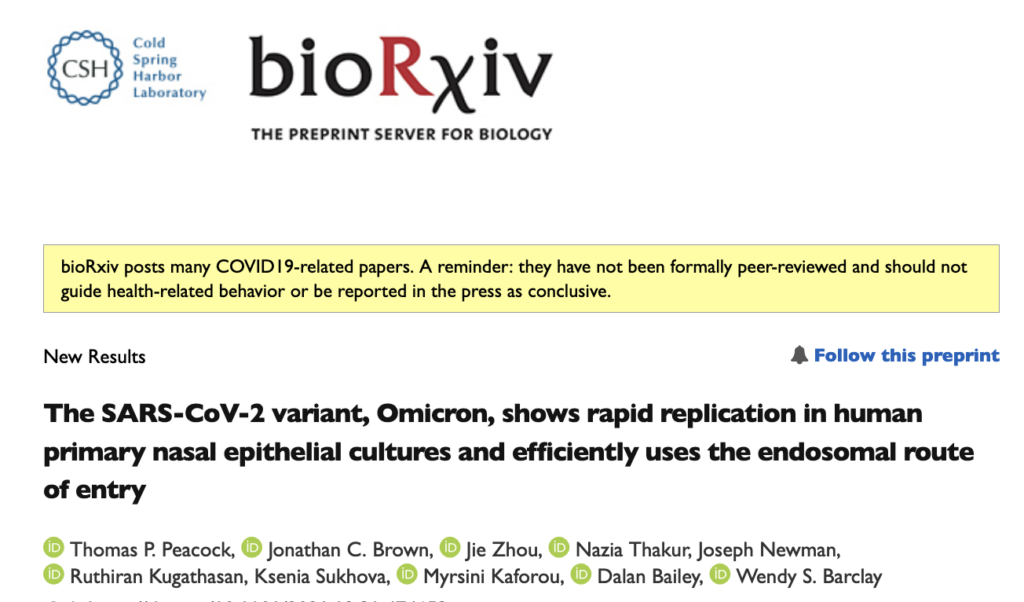2022年1月31日
最近紹介したように、自閉症スペクトラム(ASD)では、解剖学的には脳にほとんど異常が認められないものの、介在神経の機能異常が起こり、神経抑制のバランスが変化した結果、脳波検査でγ波が上昇することなどを紹介した(https://aasj.jp/news/autism-science/18807 )。 実際、興奮精神系と異なり、介在神経はいくつかの場所でまとまって作られた後、移動によって脳内に分布する。すなわち、発生を経て最終目的地に落ち着くためには複雑な過程を経る必要があり、異常が起こりやすいと考えられる。したがって、この過程を解明することは、そのままASDのみならず、てんかんや、統合失調症の理解にもつながる。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、発生過程の人間の脳標本を用いて、介在神経発生過程の解明に迫った研究で、1月28日号のScienceに掲載された。タイトルは「Nests of dividing neuroblasts sustain interneuron production for the developing human brain(増殖する神経芽細胞の集まりが発生途上の人間の脳の介在神経産生を受け持つ)」だ。
この研究の前半は、精細な組織学で、大脳基底核源基と呼ばれる脳室内に突き出した領域の中で、内側の隆起にDCX分子を発現した介在神経が増殖する特別な場所が存在し(他の基底核部位には存在しない)、そこで胎生14週から23週まで、神経芽細胞が一種のガンのような増殖集団を形成して、増殖が続くことを明らかにしている。大事なのは、興奮神経と異なり、等分裂から不等分裂の様な転換があまり見られないことで、著者らは神経の細胞同士が接着因子で凝集することが増殖に必要ではないか、またプロトカドヘリンの一つが欠損すると介在神経発生異常が起こるのも、この凝集塊の形成の問題ではないかと議論している。いずれにせよ介在神経の前駆細胞の増殖調節についてさらに研究が必要であることが分かる。
23週を過ぎると、細胞増殖の速度は低下するが、生まれるほぼ前まで増殖が続き、介在神経が脳へ供給されることが分かる。実際、増殖が止まった細胞は、集団から離れ、分化し移動が始まる。
この研究のハイライトは、この神経芽細胞凝集塊を取り出してマウスに移植しても同じような塊が形成され、マウスの中で発生が続くことの発見で、なんと移植後1年間にわたって、増殖、分化を観察できることが示されている。しかも、最終的に機能的介在神経が分化するのに、この条件で200日必要で、こうして分化した介在神経はマウスの脳ネットワークに統合されることが示されている。
結果は以上で、介在神経前駆細胞が細胞塊を形成することで増殖すること、これをマウス脳内でほぼ同じ時間スケールで再現できることなど、少なくとも発生過程のほとんどの部分を研究する方法を示した、今後人間の介在神経発生を研究する上で、重要な貢献ではないかと思う。今後、iPSなどを組みあわせることで、様々な疾患での介在神経発生異常も分かるように思う。自閉症の科学としても紹介したい論文だ。
2022年1月30日
アルツハイマー病(AD)を始め、様々な神経疾患の一群を、病状との相関が高く、さらに神経から神経へと伝搬可能なTauタンパク質の異常症と捉えTaunopathyとして眺め直す研究が進んでいる。ただTaunopathyといっても、ではTauの機能と病気との関連を説明せよと言われると、Tauについて微小管結合タンパク以外の何の知識も無いことを思い知る。
その意味で今日紹介する米国のグラッドストーン研究所をはじめとする3つの機関が共同で発表した論文は、私の頭の中のTau像をより明確にしてくれるとともに、ADをはじめとするTaunopathyの原因について新しい説明を与えてくれたという意味で大変重要な研究ではないかと考える。タイトルは「Tau interactome maps synaptic and mitochondrial processes associated with neurodegeneration(Tauと相互作用する分子マップはシナプスとミトコンドリア過程が神経変性に関わることを明らかにした)」だ。
これまでTauと相互作用する分子については数多くの研究が行われてきており、私もいくつかは目にしてきた。ただ、この研究では神経細胞中でTauと相互作用を行っている分子を網羅的に特定し、その中からTauの変異により相互作用が変化する分子を探そうとしている点がユニークだ。
この目的のために、Tauに標識をつけて結合分子を免疫沈降する方法とともに、Tau分子のN末、C末に近くのタンパク質をビオチン化する酵素を合体させたキメラ分子を用いて、Tauと相互作用している分子をビオチン化し、回収する方法を用いている。
まずビオチン化方法を用いてTauと相互作用する分子の中から、微小管の構成単位tublinと結合する分子を除くと、246種類という多くの分子が何らかの形でTauと結合している。そして、網羅的に調べることでしか見えないことがあることを実感する。なんといっても、核内タンパク質から、シナプトソーム形成まで、実に多様な分子と様々な場所で様々な分子と相互作用しており、微小管と相互作用する分子などと思っていたイメージが覆される。
またシナプトゾームに関わる機能についてみても、N末と相互作用する分子、C末と相互作用する分子は、異なる過程に関わっており(前者はシナプス接合部の形成、後者は細胞膜融合)、Tau機能の重要性を示唆している。
その中で、Taunopathyに関わる分子を探す目的でいくつかの実験が行われ、以下の重要な発見が行われている。
1)変性したTauは神経細胞間で伝搬する。すなわち、神経刺激に応じて細胞外に分泌され、また取り込まれることを意味するが、神経を活性化したときだけにTauと結合する分子を調べると、シナプトソーム形成時に細胞質側に飛び出ている分子と相互作用している。この結果から、Tauの分泌がactive zoneの細胞膜融合を介して起こることが示唆される。
2)様々な分子との相互作用は存在するが、前頭側頭認知症を誘導する変異型Tauとの結合が低下する分子を調べると、ほとんどがミトコンドリアの内側の膜に存在する分子。
3)前頭側頭痴呆症の変異があると、ミトコンドリア膜を通したプロトンの漏出が高くなり、ミトコンドリアの酸化的リン酸化とエネルギー生産とのカプリングが悪くなる。
4)前頭側頭痴呆症で低下が見られるTau結合分子のレベルは、ADをはじめとするTaunopathyの患者さんで低下している。
以上が主な結果で、本当はさらに様々な可能性を含んでいるとはおもうが、これだけでも私のTauに対する理解は大きく変化した。AD治療開発にも期待したい。
2022年1月29日
ついこの前、EBウイルス感染が多発性硬化症(MS)発症の引き金を引くという論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/18787 )、この論文は一種の自然感染実験で、MSを発症した人のEB感染時期を追いかけて、EB感染後に神経変性が始まり、最終的にMSが発症するという因果関係を明らかにした研究だ。
この結果は、かなり強くMSのEB原因説を示しているが、この可能性を今度はメカニズムの面から明らかにした、やはり画期的なスタンフォード大学からの論文が1月24日オンライン掲載された。タイトルは「Clonally Expanded B Cells in Multiple Sclerosis Bind EBV EBNA1 and GlialCAM(多発性硬化症でクローナルに増殖したB細胞はEBウイルスのEBNA1抗原とともにGlialCAMに結合する)」だ。
もしEBウイルスが自己免疫反応を誘導しているとしたら、EB特異的B細胞がクローン増殖するはずだと著者らは当たりをつけ、患者さんの末梢血と、脳脊髄液のB細胞を取り出し、個々の細胞が発現している免疫グロブリン(Ig)遺伝子をまず特定している。
するとMS患者さんだけで、特に脳脊髄液B細胞で同じIg遺伝子が使われている、すなわちクローナル増殖が起こっていることを発見する。さらに、脳脊髄液中の抗体のアミノ酸配列を決めると、クローナルに増殖しているB細胞のIg遺伝子に一致する。この結果は、活性化されたB細胞が脳に移行し、さらに抗原特異的なクローナル増殖を起こしていることを強く示唆している。
そこで、クローン増殖していた148種類のB細胞のIg遺伝子から抗体を再構成し、EBへの反応性を見ると、1/3がEB特異的に、2割が他のヘルペスウイルスに反応することが分かった。そして、患者さんレベルで見ると9例中6例でEBNA1に対する抗体が存在することがわかった。さらに、EBNA1抗体が出来るために、遺伝子の変異がほとんど必要ないことも構造解析から明らかにしている。
以上からEBウイルス感染が引き金になっている可能性が示唆されたが、これによって出来た抗体が自己の抗原に反応するかが問題になる。そこで、代表的抗体をヒトタンパク質アレーを用いて調べると、グリア特異的に発現しているGlical CAMと反応すること、さらにセリンリン酸化されたGlialCAMに対してはEBNA1と同じ強さで結合することを発見している。すなわち、EBウイルスに対する抗体反応が、自己抗原に対する免疫反応を誘導することが明らかになった。
実験的には、ミエリンペプチドで誘導する脳炎モデルマウスにEBNA1を免役すると病状が悪化することを確認するとともに、臨床例で血中のGlialCAMに対する抗体が上昇していることも確認している。
以上、この研究ではEBウイルス感染が最初の引き金なのか、あるいは病気を悪化させる要因なのかについては結論していないが、EBウイルス感染が自己免疫を誘導する可能性については明確にした重要な仕事だと思う。
この論文ではほとんど触れていないが、個人的にはEBウイルス感染でGlialCAMに対する抗体が出来ることにおどろいた。というのも、最近YouTubeで勉強会をした皮質下嚢胞を伴う大頭型白質脳症(MLC)の原因遺伝子の一つがGlialCAMの変異であることだ(https://www.youtube.com/watch?v=0oOJFM19Ohc )。MLCの子供達は白質障害、すなわち神経軸索が傷害される。MSも同じ白質障害と言えるので、この共通性が、白質障害の成り立ちにの理解について新たな糸口になるのではと期待している。
2022年1月28日
ドイツ留学以来一貫して、実験にはfluorescence activated cell sorter (FACS)のお世話になってきたし、自分たちでもFACSに使える様々なmAbを樹立してきた。この間、処理速度やパラメーターの数など様々な改良が行われてきたが、これまでとは質的に異なるイノベーションは起こってこなかったように思う。
今日紹介するドイツにあるEMBLとFACSを提供する老舗ベクトン・ディッキンソンからの論文は、FACSに、これまで顕微鏡でしか見ることの出来なかった細胞内の構造を検出するシステムを合体させた、画期的な機器Image enabled cell sorting (ICS)についての開発研究で、1月21日号Scienceに掲載された。タイトルは「High-speed fluorescence image–enabled cell sorting(蛍光イメージによる高速細胞ソーティング)」だ。
このICSは、2013年UCLAから発表されたFIREと名付けられた、細胞の形態を検出してソーティングを行うFIREという技術を基盤としている。フローシステムで細胞形態を分類できると、当然これまでのFACSとを組みあわせる可能性を探る。FIREから10年近く経過しているが、FIREを開発したDieboldさんがベクトン・ディッキンソンに移って、EMBLと共同でこれを実現したと言えるのがICSになる。
技術についての詳細は全く理解していないが、一般的なフォトマルに加えて、フォトダイオードを用いて、形態や細胞内の蛍光イメージを検出できるようにしている。フォトダイオードも2個用いて、光が細胞で遮られることによるスポットを用いた形態検出、また細胞そのもののイメージを合わせることで、より正確な形態が検出できるようになっている。
驚くのは、細胞内イメージという大きなデータを、他のデータと細胞形態上に、高速に合成する技術で、画像解析技術の進歩を実感する。
後は、細胞内の異なるオルガネラを染めた時、正確に画像が再建されていること、それを用いて細胞をソートできることを示した後、ICSによりこれまで難しかった課題が解決できることを示している。
細胞分裂は、顕微鏡イメージの染色体の分離やポジションに応じて、prometaphase, metaphase, anaphase, そしてtelophaseに分けられるが、これらが別々にソーティング可能になっている。
最後に、TNFなどのNFκBが活性化シグナルにより、RelAは核内に移行するが、この核内移行、およびその維持に関わる分子を、CRISPRを用いたスクリーニングで特定する実験系を設定し、RelAの核内移行が異常になった細胞をソートし、どの遺伝子がノックアウトされているのか検出する実験系が可能であることを示している。
結果は以上で、FACSを使ったことがある人なら、これがどれほど素晴らしいことか分かると思う。今後実際の組織のように、異なるサイズの細胞が混在する条件で、どのぐらいの精度が得られるのかなど、製品までの検討項目は多いと思うが、大きなイノベーションが起こったという気がする。
2022年1月27日
男女の脳に、解剖学的、機能的差が存在していることは間違いない。例えば、男性の方が脳が大きく細胞数も多いことが分かっているし、自閉症スペクトラムは圧倒的に男性に起こりやすい。ただ、これらの差が人間の発生過程でどのように生まれるのかについては分からないことが多い。
今日紹介するケンブリッジのMedical Research Council研究所からの論文は、ES細胞から脳のオルガノイドを形成させるときに、様々なホルモン環境にさらすことで誘導される変化を、分子生物学的、細胞学的に調べた研究で、男女の脳発生の差についての細胞学的違いを特定したという意味で、重要な研究だ。タイトルは「Androgens increase excitatory neurogenic potential in human brain organoids(アンドロゲンは人間の脳オルガノイドの興奮性ポテンシャルを高める)」だ。
実験自体はオス・メス由来のES由来オルガノイドを、dihydrotestosteron(DHT)、testosteron(T)および、estrogen(E)で刺激し、細胞学的、分子生物的に淡々と調べており、特に何かが目を引くことはない。しかし、笹井さんたちが始めたオルガノイドが、ここまで安定的に人為的操作が加えられるようになっているのかと、感心した。
DHTとTを別々に調べているのは、Tはエストロゲンに変換されエストロゲンとして働く一方、DHTはそのまま男性ホルモン受容体(AR)だけを介して働くため、AR特異的刺激として扱えるためだ。実際、マウス脳発生では、不思議なことにTが一度Eに変換されて男性化を誘導するという不思議なことが起こっているのが知られている。
幸い人間のオルガノイドでは、DHTもTも細胞学的には同じ効果を示し、自己複製能を持つradial gliaの数が上昇する。そして、男性ホルモン存在下でこの細胞は基底層にとどまっていることから、分化が抑えられていることが分かる。この結果、この倍養系では男性ホルモンが存在すると大体10%程度細胞数が上昇する。
次に、この変化を誘導する分子生物学的基盤を発現遺伝子の比較から検討し、分化に関わる遺伝子、および代謝のハブmTORに関わる遺伝子の発現が大きく変化していることを突き止める。この結果に基づき、ヒストン脱アセチル化酵素を阻害する実験、およびmTORを阻害する実験を行い、男性ホルモンの作用をそれぞれの阻害剤が抑えること、逆に言うと男性ホルモンによりHDACおよびmTORが活性化されることが、脳の男女差を発生させる原因になっていることを示している。
感心したのは、オルガノイドの性質を変化させる培養法が存在することで、皮質培養から、もう少し背側側の脳オルガノイドを誘導し、自閉症スペクトラムや統合失調症に機能的に強く関わる抑制性神経の発生に及ぼす男性ホルモンの効果を調べる実験が行われている。驚くことに、この条件下での抑制性ニューロンの発生は、ほとんど男性ホルモンに影響されない。
この結果は、基本的に興奮性ニューロンだけが男性ホルモンで上昇することを意味しており、これが男が興奮しやすい原点かもしれない。
以上、言ってみれば男性ホルモンを培養中に加えるだけの実験だが、これだけの変化が発生で生まれることに驚く。この原稿を書きながら、「男と女の間には・・・」と歌っている野坂昭彦を思い出していた。
2022年1月26日
ガン細胞で細胞膜分子の糖鎖調節が大きく変化していることはよく分かっているが、これをガン特異的な治療に利用することは簡単ではないようだ。一方、ガン特異的な糖鎖の変化が、ガンに対する免疫反応を落としてしまう可能性があり、この場合は糖鎖添加を抑えることで治療効果を高めることが出来る。
今日紹介するミラノにあるサンラファエロ研究所からの論文は膵臓ガンに対するCAR-T治療開発過程で、抗原に使っているCD44ver6のガン特異的な糖鎖修飾をブロックすることで治療効果が高まることを示唆した研究で、かなり特殊なセッティングではあるが、糖鎖修飾にも目を配ることの重要性を示した研究と言える。タイトルは「Disrupting N-glycan expression on tumor cells boosts chimeric antigen receptor T cell efficacy against solid malignancies(腫瘍細胞上のN-グリカン発現を止めることで、固形ガンへのCAR-T治療効果を高めることが出来る)」だ。
Nature Medicineが選んだ昨年の医学研究トップニュースの一つが骨髄腫に対するCAR-T治療の成功で、ようやくB細胞白血病以外にもCAR-Tが拡大し始めたという期待がこもっているが、それでもいわゆる固形ガンに対する開発の歩みは遅い。
このグループは膵臓ガンなどRAS発現腫瘍で特異的に発現するCD44のスプライス型CD44ver6に対するCAR-Tの効果を高めるために、この抗原の糖鎖修飾を標的に出来ないか調べる中で、Nグリカン合成に関わる酵素を欠損させると、ガン細胞とCAR-Tとの免疫シナプスと呼ばれる、アクチン依存性のプロセス田高まり、結果CAR-Tのキラー効果が高まることを発見している。
後は、この試験管内の結果を、生体内へ移行させられるか実験を重ね、Nグリカン合成阻害剤として、2DG(2-deoxy-D-glucose:glucose/mannoseのアナログ)を静脈注射と、CAR-Tを併用することで、単独ではほとんど効果の無いCAR-Tによる効果を得ることが出来ることを示している。さらに、PD-1/PD-L1チェックポイント分子の機能を抑えることも示し、2DG投与が、療法の効果で固形ガンのCAR-T治療を高める可能性を示した。
後は、この処理がCAR-Tの疲弊を防ぐ効果があること、他の抗原にも利用できることなどを示しているが、割愛する。
これまで大きな困難が伴う固形ガンのCAR-T治療のために、小さな穴でもなんとか見つけようとする研究の一つで、2DG自体はガンに特異的に取り込まれることが知られており、可能性はある。効果が高いとは言えないが、それでも一歩ゴールに近づけるという意味で、期待したい。
2022年1月25日
クジャクを見ると、ダーウィン進化アルゴリズムのパワーに驚くとともに、この形が生まれる過程を説明することがいかに難しいか思い知る。人間にとって美しい鳥という観点から見ると、もちろんクジャクは進化の極致を行っている。しかし一方で、動きは鈍くなるし、大きな危険を抱えることになる。これを説明するためには、時間を巻き戻してクジャクの進化が起こった過程と環境を再現する必要があるが、これはほとんど不可能に近い。結局、遺伝子変異を眺めて想像するしかない。
同じような状況がCovid-19禍ではオミクロンに見られた。スパイクだけで語ることが危険であるのは承知の上で言うと、これまで我々が経験してきたα型からδ型まで、遺伝子変異は限られており、段階的な進化が起こったなと感じることが出来る。ところが、昨年現れたオミクロン株はスパイクだけでも15種類の変異が重なっており、これまでの3倍の変位数だ。
メディアではこの変異の数を感染力と直結させているが、生物をかじったことがある人なら、感染という形質から見ると、変異が多いことは逆に感染力が低下する危険につながる方が多いと思ってしまう。まさに、オミクロンモンスターはクジャク進化と同じ問題を抱えている。
幸い様々な方法で、オミクロンモンスターの感染力を調べることが出来るのが今の科学だ。まず、最も気になるスパイクについて、構造解析が行われ、これほどの変異がACE2結合にどう影響しているのかが調べられた。一編は中国北京科学アカデミー研究所からで、現在はまだpre-proofの段階だ。もう一編は、カナダブリティッシュコロンビア大学からで1月22日Scienceにオンライン掲載された。
正直、中国の論文の方が包括的な研究だが、結論は同じだ。
1)ACE2と結合している立体構造を見ると、多くの突然変異を有するにもかかわらず、δとACE2との結合に類似しており、結合表面が他と比べて広い。
2)この結果、ACE2との結合だけで見ると、δ株とほぼ同等、実際にはδの方が少し結合が高い。
3)変異の多くはACE2との結合サイトに起こっている。しかし、そのうちの多くはACE2との結合を低下させる。この低下を補うようにして、いくつかの変異がこの結合低下を代償している。これには、変異により起こるsalt-bridgeの変化が大きく関わっている。
4)δと比較したとき、ACE2との結合力だけが選択圧とは考えられない。カナダのグループは、感染やワクチンにより出来た抗体をすり抜ける選択圧が、これほどの大きな変異を生み出した、すなわちまず抗体から逃れるという性質が形成され、そのあとでACE2との結合で選択が起こった可能性を示唆している。一方、中国のグループは、オミクロンの変異が、他の動物の中で選択された可能性を示唆している。
以上、おそらくスパイクタンパクは極めてダイナミックで、変異による結合力の低下は、他の部分の変異で代償できるように出来ているように思える。
ただ、構造解析だけからは、現在私たちが経験しているオミクロンの感染力を説明するには至らない。
これについては、まだ査読前だが、ロンドン王立大学からの論文が面白い可能性を示している。
この研究は、様々な細胞を使ったウイルスの感染実験を重ねたものだが、現在の感染状況を説明する様々なヒントが、試験管内実験から得られている。面白いところだけ箇条書きにしておく。
1)まず驚くのが、δと比べたとき、鼻粘膜細胞での増殖力が早いが、時間がたつとほとんど同じになる。これはウイルス分泌でも見られ、24時間目では高いウイルス量を排出するが、48時間になると逆転する。
2)この原因は、感染細胞が速やかに細胞死に陥ることと相関しており、δ株の場合、感染後の繊毛が遙かに長く動いているのが観察できる。これが、早い病気の収束に関わる可能性がある。
3)オミクロンはスパイクが分断しやすい変異を有しており、細胞膜同士の融合をしやすいと考えられるが、実際の融合率は低い。実際、融合に必要なTMPRSS2を発現しない細胞でも感染できる。
4)細胞膜融合の効率が落ちた代わりに、IFITMと呼ばれるウイルスがエンドゾームに取り込まれるのを防ぐ分子の影響を受けずに、エンドゾームに感染できる。
5)エンドゾームを感染の入り口にすることで、多くの動物にかかりやすくなる。
なぜエンドゾームに取り込まれて特異性が低下したのに、上気道感染で止まるのかなど、いくつか気になる点はあるが、査読前とはいえ、この論文から学ぶところは多い。
以上、頭の整理という意味で、オミクロンの機能面を整理してみたが、生物学的にも圧倒的な面白さがある、モンスター、当にクジャクが発生したことは間違いが無い。
2022年1月24日
カルシウムイオンは別にして、他の金属イオンが細胞外でタンパク質と相互作用して、生理学的機能を調節している可能性はあまり考えたことは無かった。しかし、今日紹介するバーゼル大学からの論文は、LFA-1と呼ばれる免疫に関わるインテグリンとしては最も有名な分子の構造変化がMgイオン依存性で、Mgイオンが無いと、キラーメモリー活性が低下し、様々な免疫治療が台無しになりかねない可能性を示唆する、臨床的に重要な研究で1月19日Cellにオンライン掲載された。タイトルは「Magnesium sensing via LFA-1 regulates CD8 + T cell effector function(LAF-1を介するマグネシウム感受性がCD8T細胞のキラー活性を調節する)」だ。
LFA-1はインテグリンとして細胞遊走にも関わるが、ICAM-1を認識して細胞内のシグナルを活性化し、キラーT細胞活性を誘導することも知られている。構造的にはCD11aとCD18の2種類の分子から構成されており、抗原刺激による細胞内シグナルにより活性化され(inside outと呼んでいる)、extension form(EF)およびhead-open form(HF)へと変化し、HFを摂ると高い親和性でICAMと結合して、T細胞を活性化する(outside inと呼ぶ)極めて複雑な分子であることが分かっている。実際1990年ぐらいから詳細な研究が進んだ分子の一つだ。
この研究は、まず細胞外液のMgイオンが、CD8T細胞のキラー活性に大きく影響するという発見から始まっている。すなわち、細胞外の分子がMgイオンにより機能調節されていることになる。そこで、キラー細胞上の分子を様々な条件でフィルターをかけ、ついにLFA1がMgイオンにより調節される分子であること、およびMgイオンがinside-outで活性化されたLFA-1のextensionとhead-openに関わることを発見する(LFA-1の構造変化は様々なモノクローナル抗体でモニターできる)。
あとは、MgイオンによるLAF-1変化が、ICAMトの結合や、T細胞内のシグナルや活性にも関わることを多くの実験で示し、CD8T細胞のキラー活性がMgイオンにより調節を受けるメカニズムを明らかにしている。ただ、詳細は割愛する。
この研究の面白さは、メカニズム研究の上に、臨床にトランスレーションするための様々な実験を行っていることだ。それをまとめておく。
マウスにMg欠乏食を与えると、リンパ節や筋肉のマグネシウム量が選択的に低下し、体内での抗原刺激に対するT細胞の活性化が低下する。また、同じマウスをガン抗原で免役しても、キラー活性が低下している。 Mg欠乏食で腫瘍免疫が低下しても、腫瘍局所にMgを注射すると、ガンの増殖を抑えられる。 CAR-T治療や、ガン抗原とCD3T細胞をブリッジするBilnatumomab治療は、Mg濃度に強く影響される。 チェックポイント治療のコホート研究では、血中Mg濃度が高いグループははっきりと予後が良い。 以上が結果で、キラーを高める免疫治療を行う場合、まずMg欠乏でないかどうか調べることの重要性を示唆しており、すぐにトランスレーションする必要があると思う。それ以外にも、ガンの局所療法やCAR-Tの改変など、様々なヒントが得られる面白い研究だと思う。
2022年1月23日
虫歯菌に感染するからと、最近では幼児期に口移しで食べたり、キスをしたりすることは避けるよう勧められているようだ。一方で幼児期のスキンシップの重要性はわかっており、この狭間で悩む人も多いのかもしれない。しかし、虫歯菌の感染が問題なら、口腔ケアを念入りにすればいい話で、口移しも含めてスキンシップを制限する必要は、一部の例外を除いて無いと思う。それでなくともスキンシップが禁じられてしまうパンデミック時代、スキンシップ欠如の子供への影響の方が深刻に思える。
といってみたところで全てエビデンスのない個人的意見だが、今日紹介するハーバード大学心理学科からの論文は、1歳半ぐらいの幼児は唾液の交換を伴う行動を見て、社会性を判断していることを示した研究で、1月21日号のScienceに掲載されている。タイトルは「Early concepts of intimacy: Young humans use saliva sharing to infer close relationships(幼児期での親密性の概念:幼児期には唾液共有を人間同士の親密さを判断するのに使っている)」だ。
このような研究は、仮説とそれを証明するための課題の設計が全てだ。この研究の仮説は、他人の唾液が混じるのをいとわない行為は、人間同士の親密な関係を示すことだ。
まず、同じストローでジュースをシェアしている子供と、お菓子を分けて食べている男女の子供を見て、「2人は兄妹」と効くと、唾液が混じっても同じストローでジュースを飲んでいる子供の方がより兄妹である可能性が高いと感じることを、小児で確かめている。
ただこのセッティングを見ただけで、親密度を判断するためには経験が必要で、もっと若い1歳半の幼児で同じことを調べたい場合、新しい課題を設定する必要がある。この研究のハイライトは、幼児でもテスト可能ないくつかの課題を設計したことにつきる。
まず第一の課題だが、女性Aが人形と一つの食べ物をシェアしているビデオと、女性Bがボールを人形に渡しているビデオを見せた後(人形は同じ)、人形を挟んで両方の女性がいる状況で、人形が助けを求めたとき、幼児はどちらの女性を見るかという課題だ。
すなわち、自分が人形の立場になったことを想像して、まず助けを求めるのは関係が緊密な人になるが、これを判断するとき唾が混じるのを気にする関係かどうかを基準に出来ないか調べている。
結果は期待通りで、1歳半の幼児のみならず、8ヶ月令の乳児でも、唾液を共有していることを感知し、それを親密なサインとして理解している。
同じ問題を、一人の女性が食物やボールを使わず、直接指を自分の口から人形の口に運ぶ、あるいは自分の額から人形の額に運ぶというタスクを設定し、今度はこの女性が助けを求めたとき、どちらの人形を見るかという課題で確かめると、やはり唾液交換を伴う行動を、親密度の判断に使っていることが分かった。
他にも様々な確認実験を行っているが、人間はかなり早い段階から社会的親密度を判断でき、その基準として唾液共有が行える仲かどうかで判断しているという研究だ。いずれにせよ、唾液共有をいとわない関係を積極的に作らないと、子供に親密とは思ってもらえないことを示した面白い論文で、虫歯菌が感染するという心配を払拭することの重要性を意味していると思う。
2022年1月22日
昨日紹介したように、人間の言語活動を支える脳活動を調べるためには、脳の広い範囲にわたって、高い時間空間解像度で、しかも異なる波長の活動を区別して測定することが必要だ。しかし、脳への障害を最小限に止めておく必要があるため、電極を刺し込むことは許されない。この目的には、手術中に機能的に運動野と感覚野を区別したり、あるいはてんかんの発生源を電気的に特定するために開発された皮質表面の電気活動を拾うことが出来る表面電極(ECoG)が使われる。
今日紹介するカリフォルニア大学・サンディエゴ校からの論文はこの技術を飛躍的に高め、さらに大きな領域を、さらに高い空間解像度で記録できるプラチナ・ナノロッドの開発で1月19日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Human brain mapping with multithousand-channel PtNRGrids resolves spatiotemporal dynamics(数千のチャンネルを持つプラチナナノグリッドによるヒトの脳のマッピングにより脳活動の空間時間ダイナミックスが明らかになる)」だ。
この研究のハイライトはあくまでもプラチナナノグリッド表面電極(PtNRG)の開発だが、材料工学については全くの素人なので、肝心なところの解説は省略せざるを得ない。ただ、頭蓋の外から脳波を測るために、心電図と同じように電極を頭の異なる場所に設置するのを想像してもらうと、1000−2000の電極を30µの間隔で設置することがいかに大変か理解できるだろう。
この研究では、これまで使われていたシリカの代わりに、ガラスを用いて薄く大きく、しかも高い解像度を持った表面電極を達成している。しかし、皮膚の表面に置く電極とは異なり、電極の間に体液を灌流できる穴が配置されており、一個一個のプラチナ電極には電線が接合されているなど、顕微鏡写真を見ると、いくらナノパターンの形成技術が進んだとはいえ、その精巧さに目を奪われる。
後はこれを用いて、神経活動を高い解像度で拾えるかが示されており、最初に行われたラットのヒゲに空気を吹きかける刺激実験では、ヒゲに対応するカラム構造が見事に浮き上がり、刺激後活動が伝播していることがキャッチできる。
もちろんこのようなデバイスは臨床応用を目的に開発される。この論文では、
1)脳外科手術時に、感覚野と運動野を正確に区別し、手術のプロトコル決定に使えるかどうか、
2)手の運動と感覚の神経活動をできるだけ正確に記録して、Brain-Machineインターフェースで、将来機能的義手に使えるか、
3)手術中にてんかん巣を正確に特定して、できるだけ小さな領域の切除でてんかんを抑えられるか、
などについて、これまでのECoGと比べて、飛躍的に高い機能が提供できることが示されている。
以上が結果で、新しいPtNRGを用いて高い空間解像度の記録が可能であることは分かったが、例えば昨日紹介したような研究に使えるようになるには時間がかかりそうだ。というのも、電極から測定器までのコネクターがこのままでは、手術中にしか使えない。今後、膨大な数の電線をまとめて頭蓋の外のコネクターに接合できないと、生活の中でのてんかん巣検出や、長期にわたる記録は難しい。ただ、おそらくこのような問題は解決されるだろう。その結果、例えば思い描いた文字を実際に書かせたり、発話したりと言ったbrain-machineてんかんに関しては、さらなる飛躍が期待できる。そしてこの方向での進歩が、人間の脳機能の理解の進展に直結する。