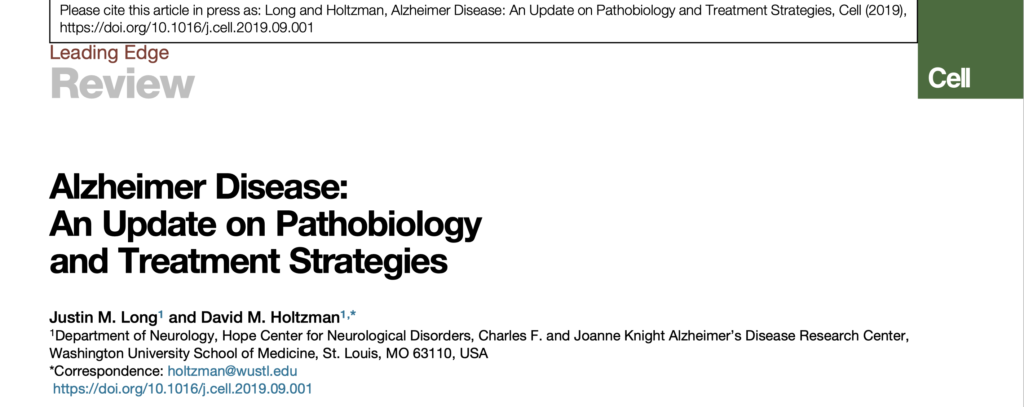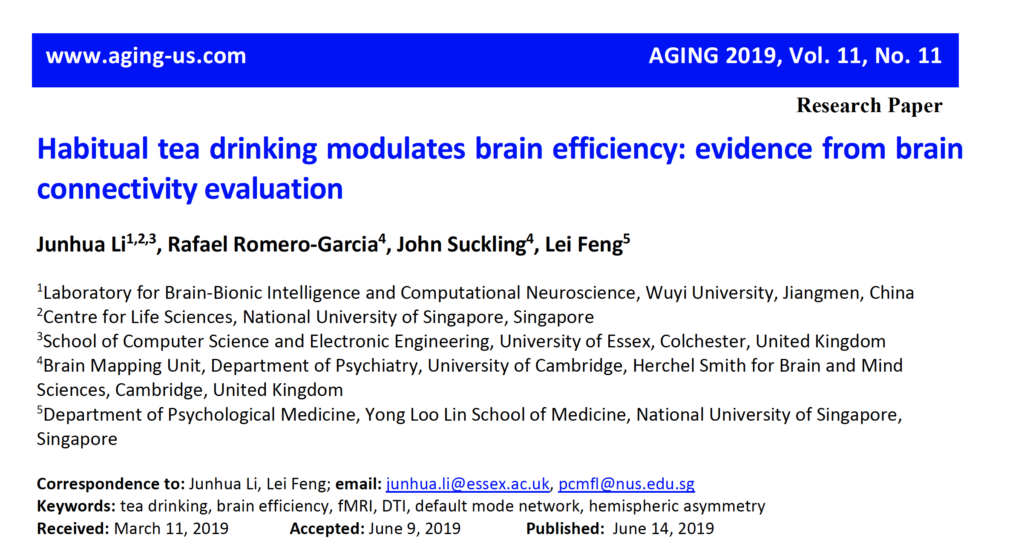2019年10月31日
単一あるいは少数の細胞のゲノムを詳しく解析することが可能になってわかったことは、前癌状態は言うに及ばず、正常組織でも、突然変異の蓄積と、変異を持った細胞同士の競合により、増殖力の高い細胞に組織が置き換わっているという発見だ。しかしこの段階から実際のガンが発生するまでにはかなり大きの変化が必要であることもわかってきた。このため、ガンに至るまでのできるだけ多くのステップを特定してそこでの変異を調べることが重要になる。
その意味で肝硬変は同じ組織にガンと硬変巣が同時に存在する確率も高く、また肝硬変での細胞障害とそれを埋める増殖の繰り返しがガン発生に必須の過程と考えられていることから、前癌状態からガンまでの過程を調べる目的にかなっている。
今日紹介する英国サンガー研究所からの論文は、アルコール性、非アルコール性の肝硬変組織切片から様々な場所を切り出し、それぞれのゲノムを調べ、肝臓ガンと比べた研究で10月24日号のNatureに掲載された。タイトルは「Somatic mutations and clonal dynamics in healthy and cirrhotic human liver (正常および肝硬変の組織の突然変異とクローン動態)」だ。
研究では5人の健常人、9人の肝硬変の患者さんの組織から100−500個ぐらいの塊を顕微鏡下で切り出し、突然変異解析を行い、同じ組織で見つかった肝臓ガンおよび、一般の肝臓ガンのゲノム解析と比べている。
基本的には解析した遺伝子配列の解析の問題なので詳細を省いて、重要な点だけを列挙すると次のようになる。
中年以上の肝臓では正常組織でも1000を超す様々な変異が存在するが、大きな変異は肝臓では起こらない。 これと比べると肝硬変組織では場所と組織によるが、点突然変異、欠失挿入、そして大きなコピー数の変化まで変異の数が倍近くになる。しかし、ガン細胞と比べると変異数はまだ半分以下にとどまっている。 30種類のガンのドライバーやガン抑制遺伝子を選んで、各部位内、部以外との関係を調べると、他の組織と様々なガン遺伝子の変異がすでに始まっているが、特定のクローンが増殖している様子は認められなかった。ただ、膵臓ガンで高頻度に見られるクロモスプリシス(http://aasj.jp/news/watch/5918 )が、肝硬変のプロセスでも起こることがわかった 突然変異の原因は、ガンと同じで細胞の増殖時のエラーや、転写時のストレスなどが存在するが、多くの症例で様々な外因性の因子により誘導された変異が見られる。例えば、ポーランドから来た患者さんではアリストロキア酸の汚染による変異が見られたり、あるいはアスペルギールスに対するアフラトキシンの毒性による変異も認められている。中には、B細胞が増殖して紛れ込んできたため、極めて多くの変異が存在するクローンが見つかることもある。 肝硬変巣にはTERTの変異は認められないが、肝ガンでは認められるので、重要なドライバーの一つはテロメアの調節と考えられる。 以上が結果のまとめだが、結果から見えるのは肝硬変から肝ガンまでの道のりは長いことだろう。正常でも年齢とともに変異が積み重なるが、肝硬変が始まると増殖依存性の変異をはじめ様々な変異の蓄積が始まる。ただ、肝ガンに発展するのはほんの一部で、肝硬変はまだまだ前癌状態と呼ぶには役者不足という結論だろう。
2019年10月30日
今年もインフルエンザシーズンが近づいてきたが、米国CDCのガイドラインは予防はワクチン、健康人が感染した場合は経過観察を推奨しており、わが国で普通に処方されるタミフルなどの抗インフルエンザ薬は、入院が必要な重症患者や、様々なリスクを抱えている患者さんに限るよう推奨している。これは耐性ウイルスの出現などを考えての措置だが、実際タミフル耐性ウイルスの出現は、利用度の極めて高いわが国に最も多い。
とはいえ、一旦流行が始まると、いくら健康だからといって発熱している患者さんに対して、医師もこのガイドラインを守って静観するのは通常難しい。すなわち、インフルエンザ感染後に利用できる抗ウイルス特効薬は今も求められている。昨年塩野義製薬からゾフルーザが新しい抗インフルエンザ剤として発売されたのもこの要求に応えたものだ。しかし、耐性ウイルスの出現など抗インフルエンザ薬は常に課題を抱えており、完璧な薬はまだ開発されていない。
今日紹介するアトランタ・ジョージア州立大学からの論文は、RNAのアナログを用いてウイルスRNAに多数の突然変異を誘導することで、耐性の出にくい抗インフルエンザ薬開発が可能と着想して研究を進め、経口摂取可能な化合物を同定した報告で、10月23日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Characterization of orally efficacious influenza drug with high resistance barrier in ferrets and human airway epithelia (経口投与可能なフェレットや人の気管上皮での耐性の出にくい抗インフルエンザ薬)」だ。
これまで発売されているタミフルやリレンザはノイラミニダーゼ阻害剤で、ウイルスの感染を阻害する。またゾフルーザはウイルスmRNA 複製阻害剤だが、それぞれウイルスタンパク質を標的にしているため、変異による体制の出現はどうしても避けられない。
このグループは核RNAに導入されて遺伝子配列を狂わせる核酸アナログを探索してすでにN-hydroxycytidine(HNC)がこの目的に利用できることを示していた。HNCは全てのインフルエンザウイルスに効果があるが、経口摂取の場合サルでは血中濃度が上昇しなかったので、さらに至適化を進め、サルでも高い血中濃度に達することができるEIDD-2801を合成した。
この化合物合成がこの研究のすべてで、あとは、この化合物が抗インフルエンザ薬として働けること、そして何よりも耐性ウイルスが出にくいことを調べる実験を行なっている。サルで血中濃度が十分上昇できることを確かめた後は、フェレットを用いたインフルエンザウイルス感染系、およびヒトの気管上皮を用いた培養系でこの化合物がウイルス特異的に作用し、期待通りウイルスRNAに変異を誘導して機能を失わせること、その効果はタミフルより高いこと、ホストの細胞には影響がないことを確認した後、ウイルス感染細胞を長期間低濃度のEIDD-2801と培養する実験系で、耐性ウイルスが全くでないことを確認している。
以上が結果で、一般の人にはわかりにくいと思うが、期待どおり化合物にたどり着いた気がする。実際には、わが国でも同じ原理に基づく肝炎ウイルス薬リバビリンなどが開発されているが、薬剤の使いにくさや、催奇形性から通常の使用には用いられないで非常時のストックとして維持されている。この薬剤も治験の結果同じ運命にならないとはいえないが、もし期待通りなら、なぜわが国でもインフルエンザにたいして普通に使える化合物の探索ができなかったのか残念な気持ちがある。いずれにせよ、抗インフルエンザ薬はうまくいけば大きな市場になること間違い無い。
2019年10月29日
アルツハイマー病に関する最近の最大のトピックスは、一度は有効性が認められなかったとして治験を中止したBiogenとエーザイのアルツハイマー薬Aducanumabが、その後のデータを補足して有効と判断し直し、FDAの認可を受ける見通しが出てきたという発表だろう。この結果、両社の株は乱高下した。このエピソードが語るように、この病気に対する治療法の開発は、これまで期待と失望の連続だった。
ちょうどタイムリーにCellにアルツハイマー病の治療開発についてまとめた創設が発表されたので、今日5時からジャーナルクラブで解説することにした。今日はいつもと違い5時始まりなので、最初から見たい人は気をつけてください。サイトは:https://www.youtube.com/watch?v=SGUDm0h184c
2019年10月29日
昨年の11月にパーキンソン病は盲腸で作られたシヌクレインが自律神経を通って脳に伝播する可能性を示した論文を紹介した(http://aasj.jp/news/watch/9180 )。最初は驚くが、よく考えてみると狂牛病のプリオンは腸管を通って脳に伝播することはわかっている。このように、最近脳神経の変性を誘導する変性タンパク質は神経ネットワークを通して伝播し、神経細胞を障害していくと言う考え方が広く信じられるようになっている。
今日紹介するカリフォルニア大学サンフランシスコ校からの論文は、もし神経ネットワークを伝って変性タンパク質が伝播するなら、神経変性疾患が最初に始まる場所と今後犯される場所を予測することができるはずだと言う着想に基づき患者さんの脳イメージを分析した研究で12月4日号のNeuronに掲載予定だ。タイトルは「Patient-Tailored, Connectivity-Based Forecasts of Spreading Brain Atrophy (脳萎縮の拡大を患者さんごとに神経結合に基づいて予測する)」だ。
この研究では症状から病気の拡大の様子が比較的明確にフォローできる前頭側頭型認知症と、原発性進行性失語症の患者さんを対象に、変性部位をMRIをもちいて特定、それを脳の各部位の連結性に基づいて作成されたネットワーク地図の上にマップして、変性の始まりと、拡大を脳領域の連結マップから説明できるか調べている。
まず変性の始まる場所(エピセンター)をネットワークから計算すると、変性が最も強い場所ではないが、それに隣接する場所を特定することができる。このエピセンターを起点にして、病気の拡大のモデルを作成し、実際に病気が1箇所から始まるのか、あるいは複数の箇所から始まるのか計算すると、1箇所から始まると考えるのが最も実態に合う。
とはいえ、このモデルが適用できない患者さんも2割程度存在する。面白いのはこれらの患者さんは、未だ変性が強くないことが多い。すなわち、一様に病気が進行しないため、統計的に予測がつきづらいステージがある。あるいは、遺伝的突然変異のケースもエピセンターを特定しにくい。すなわち、特定の1箇所から始まる場合が多いが、他のモードも確かに存在することを示している。
神経結合を通って伝搬する場合、伝搬先の神経領域から今度は2次的に新しい領域へ伝搬することになるが、エピセンターを含めて各領域での変性は一様ではない。このため、エピセンターが常に変性が最も強いと言うわけではなく、その近くに最も変性の強い場所が存在することが多い。また、変性の伝搬も一様に時間経過とともに進むのではなく、新しいノードの特性に合わせて進展が多様化する。他にも色々データは示されているが、以上の原則で変性が拡大するケースが多く、それに基づいて個々の症例での病気の進展を理解できることも示している。
以上、モデルに基づく解析から、これまで考えられていたように神経変性の多くは、どこか1箇所で始まり神経結合をベースに伝搬すると言う可能性を支持する研究だが、これによって患者さんのMRI画像を解釈できる面白い方法を提供していると思う。重要なのは、各患者さんの変性がこのモデルに従うかどうか?、従う場合今後どう進展するか?、を予測できる点で、今回は全く触れられていなかった症状の進行との対応がついてくると、言語などの高次機能について極めて面白いことがわかる予感がする。
2019年10月28日
免疫系の発生初期から腸内細菌叢が反応のバランスを調整することがわかってきたが、この中で不思議なMAITと名付けられたT細胞も浮き上がってきた。MAITはmucosal associated invariant T細胞の略で、腸内で細菌が作るビタミンB2前駆体を結合したMR1マイナー組織適合性抗原に反応して増殖することが知られている。重要なのは、MAITはこの抗原だけで誘導され、抗原非特異的に多発性硬化症、1型糖尿病をはじめとする様々な自己免疫反応を抑制してくれることで、増殖のための抗原特異性が決まっているので、うまく調節すれば臨床的な価値も高い。
ただMAITという名前から、腸内で分化するのかと思っていたが、今日紹介するフランス・キュリー研究所からの論文はこの細胞が胸腺内で発生するだけでなく成熟して末梢に出ていくことを示した研究で10月25日号のScienceに掲載された。タイトルは「Microbial metabolites control the thymic development of
mucosal-associated invariant T cells (細菌由来の代謝物がMAITの胸腺での発生を調節している)」だ。
MAITは腸内細菌叢のB2前駆体依存的に発生してくるので、腸内細菌の存在しない無菌マウスを腸内細菌叢の存在するマウスと一緒に飼育し始めてMAITの数を調べると、まず胸腺でMAITが増殖し、さらにIL17を産生する細胞への分化も胸腺内で起こることが明らかになった。
すなわち、バクテリアが作るB2前駆体が血中を通って胸腺に到達し、MAITの発生分化を促すことになる。実際、B2前駆体合成経路のないバクテリアを植えてもMAITは増殖しない。以上のことから、胸腺内にはB2前駆体を補足してMR1とともに提示してMAITを刺激する細胞の存在があることを示唆している。
そこで様々な組織の細胞を採取してMAITを刺激すると、胸腺細胞が最も刺激能力が高いこと、そしてこの理由は未熟T細胞であるdouble positive細胞が最もB2前駆体提示能力が高いことを明らかにしている。また、皮膚にB2前駆体を貼り付ける実験でも同じように胸腺細胞はMAITを刺激できることから、腸内細菌叢で作られたB2前駆体が循環を通って胸腺に入り、そこで発生分化を誘導することを証明している。
ただ、B2前駆体だけを無菌マウスに注射するとMAITは除去されるので、おそらく細菌が産生する他の因子と一緒に胸腺に到達した時、抗原としてMAITの発生分化を刺激すると考えられるが、この因子が何かを特定できていない。
以上の結果から、胸腺内のMAIT発生分化をコントロールする可能性は少し見えてきたように思える。もともと細菌とともに暮らす私たちなのでもう一つの因子は満ち足りていると思える。とすると、皮膚にB2前駆体パッチを貼り付ける方法でMAITを増やし、自己免疫病を抑えることも可能になるかもしれない。
2019年10月27日
金曜日、こちらの頼みごとがあって理研創薬・医療技術基盤プログラムのディレクターを務められている後藤先生と久しぶりにお会いして、食事をする機会があった。まだ現役の頃お願いしたFOPも、9年をかけて着実に治療薬に向かっていることをお聞きして本当にありがたく思った。ただ、FK506を開発された後藤さんとしては、日本の製薬やアカデミアが、細胞、抗体、核酸薬へとシフトし、化合物開発に関わる人が急速に減っているのを心配しているとおっしゃっていた。
確かに、CMLに対するグリベックの組み合わせを除くと、ガンに対する化合物を開発してもほとんどは再発を許してしまうことなど、化合物開発の研究者の意欲を低下させる報告が多いことも確かだが、最近のアムジェンのRAS阻害剤のように、化合物開発にはまだまだ多くの期待が寄せられていることも確かだ。
そこで最近読んだ中から化合物開発として面白いと思った論文2編を今日は紹介する。
最初はオーストラリアクィーンズランド大学からの論文で、何とオーストラリアで発見された青カビ族から麻薬作用物質を発見したという研究で米国アカデミー紀要に掲載された。タイトルは「A tetrapeptide class of biased analgesics from an Australian fungus targets the μ-opioid receptor (オーストラリアの真菌由来の作用の限られたテトラペプチド型鎮痛剤はμオピオイド受容体に作用する)」だ。
鎮痛剤の切り札モルフィネは植物アルカロイドだが、同じ受容体に作用するナイン性のオピオイドは全てペプチドだ。このグループは同じようなペプチドを動物以外から分離するプロジェクトに関わっていたと思われるが、幸運にも青カビ族から3種類のテトラペプチドを分離し、全てが低いながらもμオピオイド受容体を活性化できることを発見する。そして、一つのテトラペプチドをさらに至適化してbilorphinと名付けたテトラペプチドを合成する。こうしてできたbilorphinは他の麻薬と異なり、βアレスチンがオピオイド受容体に結合して、受容体の感受性を下げる働きが極めて低いことを発見する。すなわち、中毒症状が出にくい麻薬が開発できる可能性を示唆している。最後にbilorphinを経口投与可能なbilactorphinを合成するところまですすんでおり、まさに、バクテリアや真菌から新しい生物活性物質を分離すると言う古典的方法が、今も十分役立つことを示している。
しかし真菌から麻薬が分離できると言うのは驚きで、その筋の人たちにの手に渡ったら大変なことになるのではとちょっと心配もしている。
もう一編はシカゴにあるノースウェスタン大学からの論文で、正常の酵素の活性を高める化合物でパーキンソン病の症状を抑えることができることを示した研究で10月16日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「A modulator of wild-type glucocerebrosidase improves pathogenic phenotypes in dopaminergic neuronal models of Parkinson’s disease (野生型のglucocerebrosidaseの活性を高めることでパーキンソン病モデルのドーパミン神経の異常を改善できる)」だ。
Glucocerebrosidase(G BA)はリソゾーム病の原因遺伝子の一つだが、この変異はパーキンソン病の重要なリスク遺伝子で、しかも酵素活性自体、他の原因によるパーキンソン病でも活性が低下していることが知られている。この研究では、まずGBAに変異をもつパーキンソン病の患者さんからiPSを作成、そこからドーパミン神経を誘導して、ドーパミン神経細胞の様々な異常を特定、それを正常化できる化合物S-181を作成している。そして、この化合物が正常のGBAを安定化することで、細胞レベルの病理を改善すること、またGBAには突然変異を持たないパーキンソン病由来のドーパミン神経の異常を改善することを示している。
最後にマウスを用いて、この化合物が脳へ移行できること、人間と同じGBAの変異を導入したマウスのシヌクレインの蓄積を抑えることを示している。
以上が結果で、突然変異を正常化できなくとも、残っている正常遺伝子の機能を高める化合物により病気の進行を抑えられることを示しており、多くの分子について同じような研究が行われ、遺伝子治療ではない化合物による治療が開発されることを期待する。
2019年10月26日
インフルエンザのシーズンが近づいてきて、マスメディアでもワクチン接種を呼びかけている。ただどのワクチンを注射するのか、厚労省資料によると今年のワクチン供給量は3000万本に近く、ほぼ接種希望に対応できるとしている。問題はインフルエンザといっても多様で、どのウイルスが今年はやるかの予想を立てた上で、ワクチン製造を行う必要がある点で、予想が完全に外れたりするとすべて無駄になる。
今年のワクチンについては、3月終わりにWHOが推奨したウイルス系統について国内メーカーで製造効率を確かめ、その結果を4月に2回開かれた審議会で検討した後製造に入っている。
この予測に伴う不確実性を克服するためには、一本のワクチンですべてのインフルエンザウイルスに対して抗体を誘導できるワクチンを開発する必要があり、このための努力が重ねられてきているが、なかなか実現していない。
今日紹介するThe
LancetとScienceに掲載された2編の論文は、このような試みを代表するもので、ユニバーサルインフルエンザワクチンもいつかは実現する可能性を示す研究だ。
最初のシンシナティ大学を中心とする論文は変異の少ないhemagglutininのストーク部分に対する抗体を誘導するためのワクチンの第一相治験で、タイトルは「Immunogenicity of chimeric haemagglutinin-based, universal influenza virus vaccine candidates: interim results of a randomised, placebo-controlled, phase 1 clinical trial (ヘマグルチニンキメラ分子を基盤とするユニバーサルワクチン候補の免疫原性:無作為化盲検による第1相治験)」だ。
詳細は全て省いて簡単に紹介するが、B 型も含むほとんどのhemagglutinin(HA)に共通のストークスに対する抗体を、H8、H5のヘッドと組み合わせたキメラタンパク質を用いて効率に誘導しようとする方法で、普通のHAワクチンの場合どうしてもヘッドに対する抗体ができてしまうのを、ヘッドを変えて免疫することで、本来抗体ができにくいストーク部分のメモリー反応を誘導するという戦略だ。
治験のアウトカムは抗体ができたかどうか、そしてそれに対するメモリーB細胞が誘導されたかどうかだが、AS03ワクチンと組み合わせると、ヘッドを変えたワクチンを2回接種されたグループは、1ヶ月以内に高いストークスに対する抗体およびB細胞が誘導されることから、ユニバーサルワクチンとして使える可能性が高いという結論だ。次は実際に流行を予防できるかの治験が待っているが、期待したい。
もう一編のマウントサイナイ医大からの論文はインフルエンザの感染を防ぐことのできる抗体を分離したという論文で、タイトルは「Broadly protective human antibodies that target the active site of
influenza virus neuraminidase (インフルエンザのニューラミニダーゼに対するヒト抗体は広い範囲のインフルエンザウイルスを防御できる)」。
この研究ではやはり変異が少ないニューラミニダーゼ(NA)を標的にしており、感染した患者さんからヒトモノクローナル抗体を3種類分離し、その特異性を様々なNAと反応させると、1G01,!E01という抗体はほとんどのNAに対して反応することがわかった。
そこでマウスに感染させる実験でそれぞれの抗体が感染や病気の発症を止めるか調べると、1G01,1E01ともにほとんどのインフルエンザの発症を防ぐことができ、なかでも1G01は調べたすべてのウイルスによる病気を予防できた。
これは抗体の話だが、それぞれの抗体が認識しているNA部分が特定できたので、今後この部分を免疫原として用いるユニバーサルワクチンの開発も可能になると期待できる。
2019年10月25日
お茶が健康にいいという研究は疫学から栄養学まで数多くあるとおもうが、さすがにお茶を飲んでいる人と飲まない人の脳の構造を比べた研究は見たことがなかった。
、ところが、英国とシンガポールのグループがお茶をよく飲む生活を送ってきた人と、あまり飲まない生活を送って来た人(平均70歳、1日3回以上を6点、全く飲まないを1点、それに生活年数をかけて計算したスコアで分けている)をそれぞれ15人、21人集め、なんとMRIで脳の機能と構造を調べたた論文をAging 11月号に発表した。
詳細は専門的なので省くが、お茶を長年飲んで生活してきた高齢者は、
右脳と左脳の構造的神経結合のバランスが取れているが、機能的な左右の差に大きな変化はない。 お茶を飲む人は、安静時に調べる脳全体の機能的結合が強まっている。しかし、構造的には両者で大きな差はない。 以上が結果で、お茶を飲む習慣はMRIレベルでわかる脳の変化をもたらすことを初めて示した面白い論文だと思う。
2019年10月25日
塩分のとりすぎは認知症の原因の一つになるが、これはすべて高血圧などの血管疾患の結果起こる循環血液量の低下によると考えていた。ところが今日紹介するコーネル大学からの論文は、塩分が認知症を誘導するのは、循環血液量の低下を介してではなく、Tauタンパク質をリン酸化することで脳内に沈殿させ、アルツハイマー病に似た同じメカニズム(Tauopathy)で認知症を誘導することを示した研究で、10月23日号のNatureに掲載された。タイトルは「Dietary salt promotes cognitive impairment through tau phosphorylation (食塩の摂取はTauタンパク質のリン酸化を介して認知障害を促進する)」だ。
研究では最初から食塩を多く取るとTauタンパク質が沈殿するという仮説を出して、これを検証するところから始めている。マウスに普通より8−16倍の食塩を摂取させ(人間の摂取量に換算すると12−20g)、その後様々な時期に脳内のTauタンパク質のリン酸化の有無を生化学的、組織学的に調べている。結果は著者らの予想通りで、皮質や海馬で摂取を始めて4週間と早い段階からTauタンパク質のリン酸化が見られる。また、リン酸化により切断された短い沈殿型のTauタンパク質の蓄積も進むことも確認している。そしてこれに並行して12週ぐらいから認知機能の低下が認められた。ただ、アルツハイマー病と違い、アミロイドβの蓄積は認められていない。すなわち、純粋なTauopathyが塩分摂取により誘導されることが示された。
はっきり言って、この発見がこの論文のすべてで、全く予想外の結果だ。通説にとらわれずになんでも確かめることの重要性を示している。次に、塩分摂取によりなぜTauリン酸化が起こるのか、生化学的過程についても調べている。その結果、高い塩分の食事はNO産生を低下させ、これが神経細胞内のカルパインニトロシル化を抑制してカルパインを活性化、その結果CDK5が活性化され、Tauをリン酸化する経路を特定した。これに基づき、NO産生を高めるためアルギニンを同時に摂取させると、Tauリン酸化を抑制でき、またNOの生産が低いマウスでは、高い塩分とは無関係にTauリン酸化が亢進することも明らかにした。以上の結果は、脳でのTauリン酸化の引き金はこれまで考えられていたような食塩による血管障害で、ただ脳血液循環により認知症が起こるのではなく、血管障害がTauopathyを誘導し認知症が起こることを示している。
以上がシナリオだが、このシナリオを決定的にするため、Tauの欠損したマウスに高い塩分を摂取させる実験を行い、Tauが存在しないと全く認知症は起こらないことを示している。
もしこれが正しいとすると血管性とされてきた多くの認知症でもTauopathyが起こっている可能性を示す。これについては、PETを使って確かめられるので、ぜひ新しい目で認知症を調べなおしてほしいと思う。
2019年10月24日
9月9日、「寝ないで済む突然変異」というタイトルでカリフォルニア大学サンフランシスコ校が発表したアドレナリン受容体の活性が低下する突然変異の論文を紹介したばかりなのに、今度は同じグループから違う遺伝子の活性が高まった突然変異がやはり睡眠時間の短縮につながるという論文が10月16日号のScience
Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Mutant neuropeptide
S receptor reduces sleep duration with preserved memory consolidation (Neuropeptide S 受容体の突然変異は記憶の固定化機能を損なわずに短時間睡眠を可能にする)」だ。
要するにこのグループは睡眠時間が一般より短い人を代々輩出している家族を見つけ出し、その遺伝子を特定して睡眠の分子メカニズムを研究している。今回は、父親と息子睡眠時間が短い(父親平均5.5時間、息子4.3時間)家族を発見し、両方に共通な遺伝子変異をエクソーム解析でNeuropepitide Sに対する受容体NPSR1の206番目のアミノ酸がチロシンからヒスチジンに変化していることを特定する。206番目のチロシンはなんとカエルやトカゲから人間まで保存されている。
そこで例のごとく同じ変異をマウスに導入して、マウスの行動解析を行うと睡眠時間が1時間近く低下、また活動的に動いている時間も1時間ぐらい増加している。
次にこの突然変異による分子機能を調べるため、受容体下流のリン酸化CREB量を調べ、覚醒時、睡眠時ともに突然変異マウスで上昇していること、また脳のスライス培養を用いて睡眠に関わる脳領域の細胞のNeuropeptideSに対する反応を調べ、刺激に対して深く長く反応するタイプの神経が突然変異マウスで増加していることを明らかにする。すなわち、この変異は活性化型の突然変異であることを示している。
さて、普通睡眠時間が短いと、睡眠中に行われる記憶の固定化が障害されたり、様々な問題が発生するのだが、この家族は特に症状はなく、また突然変異マウスも特段の行動以上は示さない。それどころか、睡眠を障害することで低下するコンテクスト記憶の固定化も、突然変異マウスではあまり低下しない。すなわち、寝なくともしっかり記憶機能を維持できるということがわかった。
話は以上で、読めば読むほど望ましい突然変異で、どうしてこの変異が極めて稀な変異のままで止まっているのか不思議な気がする。残念ながら、この変異を持つshort sleeperが本当に何の問題もないのか、詳しい臨床的研究も必要だろう。何か睡眠の秘密が、このグループの発見した家族の解析から分かるような気がする。