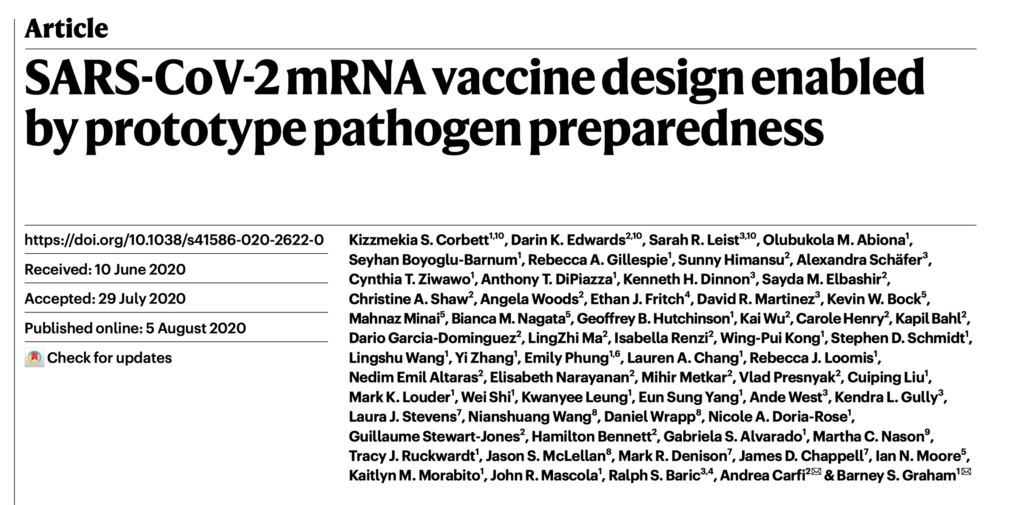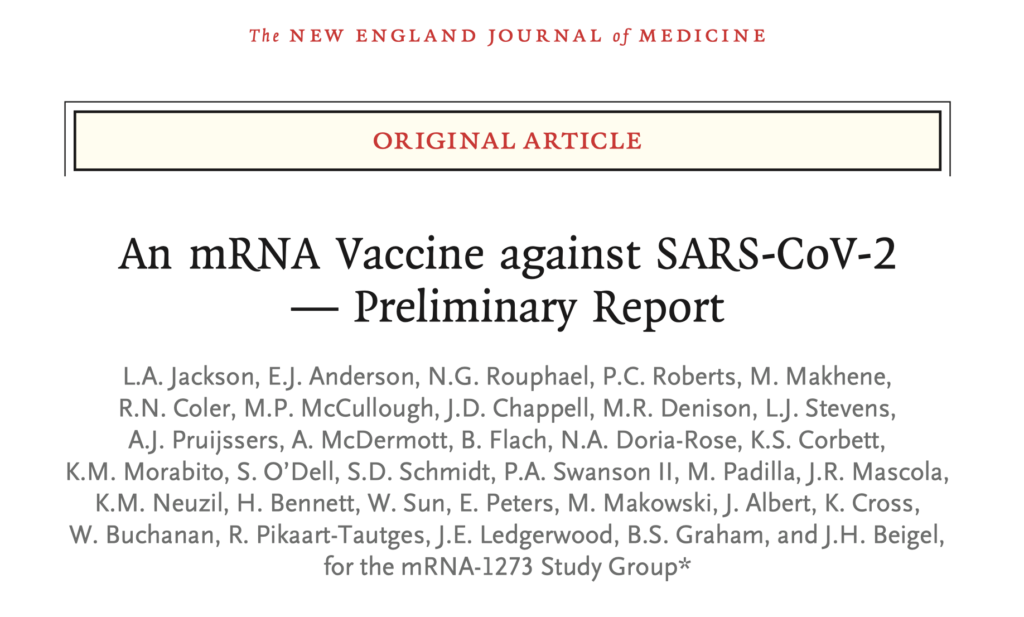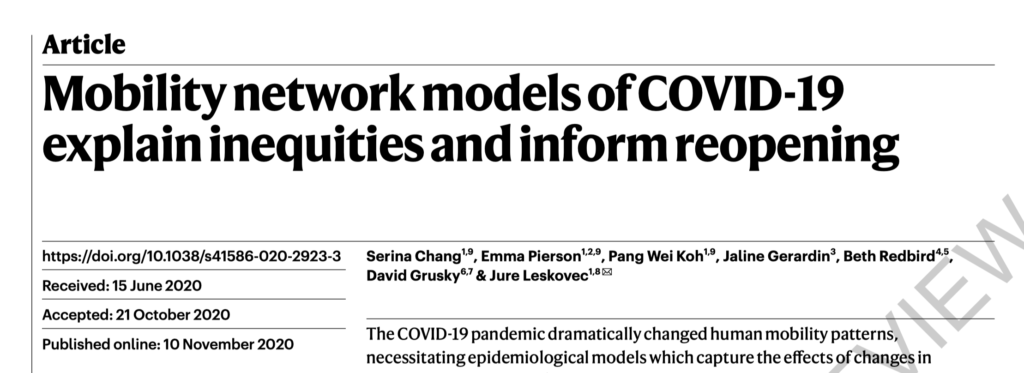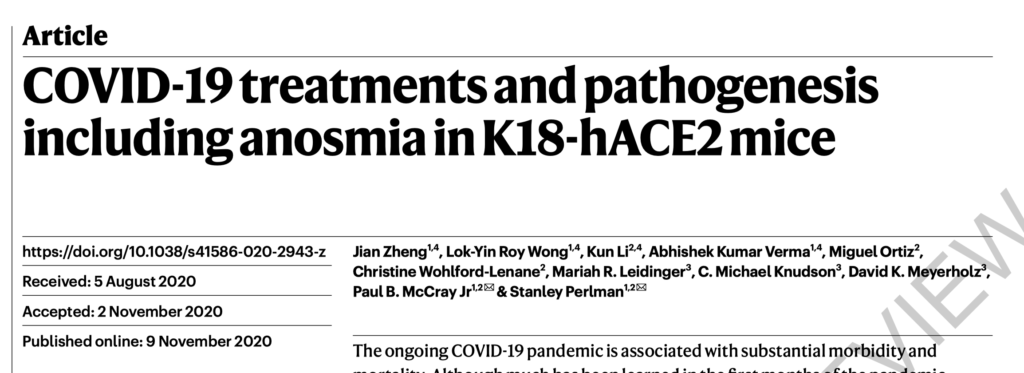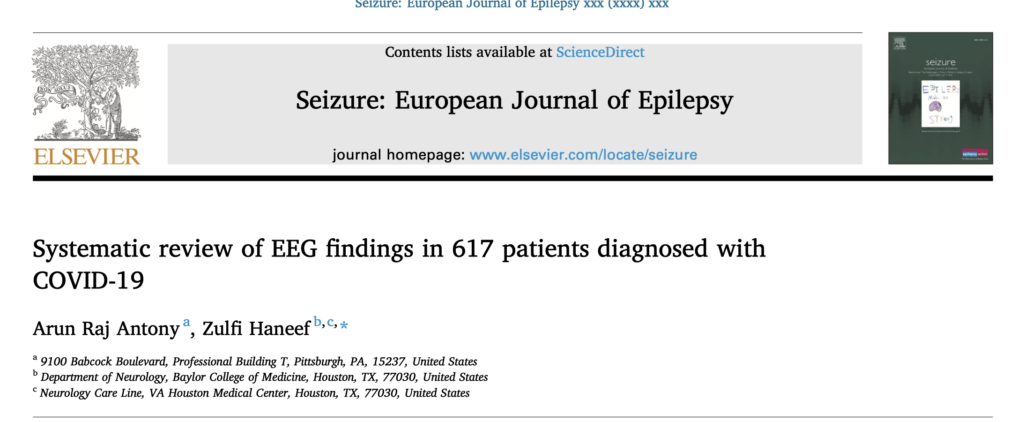2020年11月22日
私たち人間が進化的に近いのは当然サルの仲間だが、このサルの仲間に最も近いのが最も実験動物として用いられるネズミだ。これがよくわかるのが胎盤で、ネズミと人間はよく似ており、機能的にも母親のIgGを子供に移行させるメカニズムを備えている。従って、胎児期から抗体を通した抵抗力を持つことができる。一方、多くの哺乳類では母親の抗体は生後母乳を通して初めて与えられる。本来胎児は無菌的で、母親に守られているのに、わざわざ早くから抗体がなぜ必要なのかよくわからないが、このシステムの問題として母親のアレルギーが、抗原とは無関係に子供に伝えられる心配がある。
しかしこれまでIgGが胎児に伝わることの問題は考えたことがあったが、IgEが子供に移行してアレルギーを起こす可能性は考えたことはなかった。今日紹介するシンガポールA*STARからの論文は、「どうして今まで問われなかったのだろう」と思ってしまう、母親のアレルギーの胎児への移行の問題を取り上げた研究で、11月20日号のScienceに掲載された。タイトルは「Fetal mast cells mediate postnatal allergic responses dependent on maternal IgE(胎児のマスト細胞は母親由来IgE依存的に生後のアレルギー反応に寄与する)」だ。
この研究ではまず胎児期の皮膚のマスト細胞の表面形質を調べ、一部の細胞が中途半端とはいえ発生とともに分化を始めていることに気づく。そして、この分化が母親から移行してきたIgEがマスト細胞に結合することで起こるのではないかと考えた。
そこで抗原特異的IgEをかなりの量(100μg)投与し、胎児の皮膚マスト細胞に注射したIgEが結合しているか調べると、はっきりと結合が見られ、IgEが結合したマスト細胞は対応する抗原にさらされると、脱顆粒を起こしてアレルギー反応を起こすことを確認している。また、これは胎児期だけでなく、胎児期に母親から移行したIgEは生後もマウス皮下マスト細胞に保持され、最終的に皮膚の接触過敏症を引き起こすことを明らかにする。
この移行はIgGと同じ胎盤に発現しているTcRN受容体を介して起こることや、生後1ヶ月に渡って母親のIgEが保持され、アレルギー反応に関わる可能性があることが示されているが、詳細は必要ないだろう。
大量のIgE抗体を母親に注射しており、この結果を額面通り受け取っていいのか懸念はあるが、可能性としては母親のIgEが移行することは間違い無く、条件によっては子供にアレルギーが移ることもわかる。実際同じことが人間でもありうるのか、人間の胎児皮膚や肺のマスト細胞を分離して検討し、マウスと同じ様にマスト細胞の成熟が起こっており、表面にIgEが結合していることも確認しており、母親からアレルギーが移る可能性を今後考慮すべきだと結論している。
今後多くの新生児をこの可能性を頭に見直すことが重要になると思うが、何故こんな危険なシステムが淘汰されずに残っているかも面白い点だ。この論文では出産時の産道感染から皮膚を守ることが一つの要因だと議論しているが、この論文を読んで私の頭に浮かんだのは、阪大病理の教授をされていた北村幸彦先生の実験だ。
北村先生は、現在同じ阪大病理の仲野さんの先生で、マスト細胞発生や病理の世界のリーダーだった研究者だ。ただ破天荒な性格で、決してオーソドックスでは無く、工夫に満ちた多くの実験を発表されている(仲野さんのキャラクターの一部は、こんな北村先生由来かもしれない)。中でも私の印象に残っているのは、マスト細胞の欠損マウス皮下にマスト細胞を注射し、その上に小さなケージを置いてダニを数匹飼う実験で、マスト細胞が存在するとダニの吸血能が抑えられるという実験だ。
皮膚にケージを置くなどなんとキュートな実験かと感心するが、この結果を考慮すると、生まれた時から皮下に成熟マスト細胞が存在するのは、ダニやノミから子供を守るためだったという可能性が私には最も納得できる。ただ清潔な環境で生きる様になった人間の子供には、この防御機構がアレルギーとして見えてしまうだけのことだ。ぜひ北村先生の意見を伺ってみたい。
2020年11月21日
新型コロナウイルスのようなプラス鎖RNA ウイルスは、細胞に入ると特殊なキャップ構造ですぐに翻訳が始まるようにできており、次の複製ステージに必要なタンパク質を合成する。このとき、助けてくれる味方は存在せず、細胞の中に情報を担うウイルスRNAだけが単独で存在することになる。頭で考えると、感染できても前途多難に思えるが、この最初の過程はほとんど単一分子の問題で、基本的には想像の世界だった。
今日紹介するオランダ ユトレヒト大学からの論文はウイルスの単一RNAからの翻訳された分子を一分子レベルで可視化し、ウイルスの細胞内での増殖過程を単一分子レベルで観察できるようにし、感染初期の様々な問題を解決したワクワクする論文で12月23日号Cellに掲載予定だ。タイトルは「Translation and Replication Dynamics of Single RNA Viruses (一本鎖RNAウイルスの転写と複製のダイナミックス)」。
以前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/5290 )、このグループは蛍光標識したラマの一本鎖抗体を細胞内で発現させ、タグづけされたタンパク質が翻訳されてくるのを単一分子レベルで観察するSun-Tagと呼ばれる技術を開発し、細胞内での翻訳過程をリアルタイムで観察する研究を続けている。まさにこの技術は、感染後最初に翻訳がすすむプラス鎖RNAウイルスの感染過程の可視化には最適で、今回はコクサッキーBウイルスを試験管内で感染させた後、ウイルスゲノムの複製が終了するプロセスをビデオで観察している。すべてのデータは新鮮で学ぶところが多かったが、特に印象に残った結果をまとめておく。
まず、細胞質に侵入した一本のウイルスゲノムはかなりの効率(7割以上)でポリゾームを形成転写を始める能力がある。 ウイルスゲノムの転写と複製は同時進行というより、どちらか一方へとスイッチオン・オフして調節される。最初の翻訳が始まらないと、もちろん複製も起こらないが、翻訳は複製が始まると、停止する。残念ながらこのスイッチの本体は特定できていないが、ゲノムの複製や、ウイルスタンパク質とは別に存在する。そのため、ウイルスタンパク質が十分準備ができていないと、次の複製段階が完全に終了できず、細胞はウイルス粒子を排出することなく死ぬ。 翻訳と転写のサイクルは、2回続く。最初は侵入したRNAの翻訳(phase1)、それに続く複製(phase2)、新たにできたプラス鎖の翻訳(phase 3)、そして複製(phase4)、そして新たな翻訳(phase5)。この時、複製がすすむphase2,4では翻訳は止まる。 それぞれのサイクルは細胞によってまちまち。特にPhase1の期間は数分から数時間に及ぶ。この時、プロテアーゼで複製などに関わるタンパク質が用意されるので、常に治療のターゲットとなる。 タンパク質が足りずに複製が止まると、もう一度翻訳のphase1に戻る。すなわち、初期の複製過程が最もセンシティブな時期で、ここを狙って治療を行うと効果が高そうだ。 ウイルスの翻訳が始まると、すぐにホストのelF4Gが分解され、ホスト側の翻訳が抑えられる。ただ、ホストの翻訳の程度自体はウイルスの翻訳や複製には影響はなく、おそらくこの初期の翻訳抑制は、ホストの抗ウイルス反応を抑える目的がある。 ウイルスタンパク質はインターフェロンにより誘導されるRNA分解酵素をはじめいくつかの分子を抑制して、自然免疫から逃れている。したがって、外部から1型インターフェロンを加えても、ウイルスを制御することは難しい。 他にも面白い話が示されているが、コロナウイルスを考える上では上記の結果が重要だと思う。
残念ながらコロナウイルスについての言及は全くない。事実、コロナウイルスは、エンテロウイルスの4倍ぐらいの大きさを持っており、さらに小胞体膜の再構成を通して、ウイルスの細胞内での動きが極めて複雑だと思う。しかし、Sun-Tagにより感染の初期過程を追跡する可能性は開けた。おそらくコロナウイルスでも準備が進んでいる思うが、エンテロウイルスでも見るということがこれほど重要であることがわかると、早く見てみたいと期待する。
2020年11月20日
標的分子の機能を抑制する化合物の中には、分子に結合してE3ユビキチンリガーゼをリクルートして、標的分子を分解するタイプが存在し、抗癌剤として利用されている。最もポピュラーなのは、サリドマイド・アナログのレナリドマイドで、標的分子に結合したレナリノマイドにCUL4–RBX1–DDB1–CRBNと4種類の分子からなる複合体が結合し、例えば骨髄腫細胞の増殖に必要な転写因子IKZF1などを分解してくれる。通常阻害剤の開発が難しい転写因子に適用できることから、現在もこのメカニズムの探索が進んでいる。
今日紹介するマサチューセッツ工科大学からの論文は、レナリドマイドと同じように標的分子の分解を誘導する化合物だが、新しいメカニズムでBリンパ腫を誘導するBcl6を分解する化合物の開発研究で、11月18日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Small-molecule-induced polymerization triggers degradation of BCL6 (Bcl6を重合させて分解する低分子化合物)」だ。
詳しくは書いていないが、Bcl6依存性に増殖するリンパ腫細胞株などを用いて化合物の探索を行う過程で発見された化合物の一つBI-3802で細胞を処理すると、Bcl6が特異的に分解されることを発見したところからこの研究は始まる。
この分解に至るメカニズムを探ろうと、Bcl6に傾向分子を結合させBI-3802で処理すると、分解される前に、まず分子が凝集して大きなスポットを作り、それが分解されることを発見する。クライオ電顕などを使って、この凝集塊を調べると、螺旋状のフィラメントが形成されることがわかった。すなわち、レナリドマイドとは異なり、BI-3802はBcl6同士を結合させる作用があることがわかった。
では凝集した分子を分解するメカニズムは何か?これを調べるため、BI-3802によるBcl6不活化に関わる分子をクリスパー/Cas9を用いて探索し、E3ユビキチンリガーゼの一つSIAH1が特異的に分解に関わることを発見する。そして、凝集することでBI-3802結合部位の反対側に存在するBcl6のVxPモチーフが露出しそこにSIAH1が結合、分解に至ることを明らかにしている。
話は以上で、新しいメカニズムに基づくBcl6阻害剤が発見されたという結論だが、今後Bcl6のような対称型の分子について、同じメカニズムを用いた阻害剤を開発できる可能性がある。多くの転写因子が発癌に関わり、その一部しか阻害剤が開発できていないことを考えると、サリドマイド型のメカニズムに加えて、分子を凝集させて分解させる新しいメカニズムの発見は重要だと思う。
2020年11月19日
ファイザー/ビオンテック及びモデルナのRNAワクチンの第3相治験の中間レポートの話題で世の中は持ちきりだ。もちろん最終的臨床効果の判断は、あらかじめ決めた評価基準と評価時期でワクチン接種群と対照群を比べることで行われる。従って、ワクチン接種後早期の効果としては、この治験の判断が全てで、中間レポートとしては期待できる結果だ。ただ有効な医薬・ワクチンは、大規模治験に進む前に、まず信頼できる科学に裏付けられた実験結果に支えられている。この臨床応用前に示される科学的データは、臨床的効果を評価、予測するための理論的根拠となり、常に参照することが重要になる。現在メディアがRNAワクチンの背景にある科学をどの様に伝えているのかわからないが、科学の今を論文紹介を通して伝える科学報道AASJとしては、今回話題になっている2種類のRNAワクチンの中から、モデルナのmRNA-1273の科学について、モデルナから今年の8月5日、及び11月12日に以下の2篇の論文を紹介することにした。ぜひ参考にしていただきたい。
まず最初のNature論文は、マウスを用いたmRNA-1273の前臨床研究で、RNAワクチンが今後のパンデミックに対応するための切り札としていかに重要かを強調した論文だ。すなわち、今回のCovid-19にとどまらず、ゲノム配列が特定されたウイルスに対して、とりあえず予防手段を迅速に提供するという目的に沿って、研究が行われている。
事実このグループは、一般的にコロナウイルススパイク分子が細胞側の受容体に結合する前のperfusion conformationと呼ばれる構造を解析してきた研究実績があり、他のコロナウイルスでの経験から、スパイク分子にわざわざ変異を導入することで、安定にperfusion conformationを取らせることができること、そしてこの構造を抗原とする方が10倍高い抗体を誘導できることを示している。
こうして特定した安定なスパイク分子をコードするmRNAが効率よく翻訳される様に改変した、mRNA-1273を脂肪酸ナノ粒子と混合したワクチンの抗体誘導能力を、同じ変異型スパイク分子をアジュバントと混合した組み換えタンパク質ワクチンと比べ、中和抗体レベルではほぼ同等、T細胞免疫誘導ではより優れていることを示している。RNAワクチンの場合、RNA自体が細胞内アジュバントとして働き、アジュバントを加える必要はないようだ、。もちろん、感染実験で肺炎の発症を抑えることができる。
RNAワクチンがタンパク質と同等かそれ以上であることを示した上で、次になぜタンパク質+アジュバントではなく、RNAワクチンかについて、効能より、生産の迅速性にあると結論している。それを示すために、今回彼らが進めてきた工程表が示されており、1月13日にはmRNA-1273の設計図を決め、次の日には医療用グレードのRNAの生産を始め、2月には上に述べた動物実験を始めている。そして、スパイクの構造について2月19日にはScienceに報告し、驚くことに3月2日にはFDAに申請、16日にこれから紹介するThe New England Journal of Medicineに発表された論文の元となる第1相試験を始めるというスピードだ。
要するに、組み換え分子をワクチンとして用いる場合は、迅速性でRNAワクチンに勝るものはなく、もし一定の期間免疫が誘導されれば、長期効果の有無にかかわらず、パンデミックをおさえこむ効果があると考えている様だ。
これを知ると、2番目の第1相論文が第3相の中間レポートのタイミングで出てきたことがよく理解できる。すなわち、3月に始められた第1相の目的は、安全性と、人間で中和抗体が誘導できるか調べることだが、この治験に参加した45人の成人については、半年という本来このワクチンが目指した中期効果の予測のデータを示すことができるわけだ。
結果は2回の接種により、回復患者さんの抗体を上回る中和抗体活性が誘導でき、100μg接種ではばらつきも少ない。しかも、2ヶ月では抗体の力価はプラトーで維持されている。おそらく、タンパク質や、不活化ウイルスをチャレンジする実験も計画されているだろうが、perfusion conformationを狙って中期の免疫防御を実現するという意味では、合格点と言える。残念ながらマウスと異なり、強いキラーT細胞活性は誘導できていないので、感染してしまった後にはこのワクチンの効果は期待できない様に思う。
最後に重要な副反応だが、2回目の注射を受けたあとは、用量に応じて様々な副反応が出る。実際に使われる100μgで見ると、倦怠感、寒気、頭痛、局所の痛みなどが半分以上の人に現れるが、その後半年間の経過観察で、これら以外に問題は出ていない。すなわち、急性の副反応が中心になる。これについては、第3相の3万人の詳しいデータが示されることが待たれるが、すぐに発表されるだろう。副反応の主な原因は、自然免疫による炎症であると考えると、RNA自体が持つアジュバント効果の強さに驚く。
細かい点までよく考えられた、科学的成果としても目的のはっきりした優れた論文だし、感染が拡大し始めたときの防御の第一線として、RNAワクチンが優れていることがよくわかった。
最後にでは私は接種を受けるかと考えると、仕事で出張(実は今日も東京)があり、マスクはしていても対面の仕事もあり、学生さんに直に講義したいと望み、すでに再開されたコンサートも楽しんでおり、できる限り早く海外にも出かけたいと思っているので、今の様に感染が拡大している状況ならぜひリスクを取りたいと思うし、その気にさせる科学的説得力がある。
アフリカの誘惑に駆られて、治験中の黄熱病ワクチンを受けて1週間倦怠感に襲われたが、今回も同じで、normalな生活への欲望は抑えられないとたかをくくっている。
2020年11月18日
新型コロナ対策のおかげで、我が国の清潔度は急速に高まっている様に思う。もちろん優先順位はCovid-19感染防御なので、清潔になることの副作用などを心配し始めると、不謹慎と咎められると思うが、子供の成長に興味を持って論文を読んでいると、やはり気になる。一つは、両親以外マスクをした人間の顔しか見ないで育つことの精神的影響で、もう一つは腸内細菌叢の成長が清潔な環境で遅れることだ。
今日紹介するドイツミュンヘン大学からの論文は乳児期の腸内細菌叢の成長に関する指標を工夫し、腸内細菌叢の成長度が喘息予防に重要な要因になることを示すとともに、農家での成長が細菌叢の成長を高めることを示した研究で11月2日、Nature Medicineにオンライン掲載された。タイトルは「Maturation of the gut microbiome during the first year of life contributes to the protective farm effect on childhood asthma(腸内細菌叢の生後一年での成長は農家で育つことが喘息を予防する効果に貢献している)」だ。
帝王切開で生まれた子供は腸内細菌叢の成長が遅く、その結果様々な炎症性疾患にかかるリスクが高まるが、これを母親の便移植で改善することができる(https://aasj.jp/news/watch/14064 )。この結果は、乳児期の腸内細菌叢の成長の重要性を見事に示すが、同じことが農家で育つと喘息になるリスクが低下するという観察からも示唆され、農家での成長により変化する腸内細菌を特定する研究が進められている。
この研究ではオーストリア、スイス、ドイツ、フィンランドの子供(半分は農家で生まれ育った)930人の腸内細菌叢を生後2ヶ月と、12ヶ月で調べ、喘息の発症率との相関を調べている。すなわち、喘息と農家で育つこととの相関とともに、それに寄与する腸内細菌叢の変化を特定しようとするコホート研究だ。
最初は、特定の細菌が喘息リスクや農家育ちと関わるか調べたと思うが、強い相関を示す細菌は特定できなかった。代わりに、生後2ヶ月、12ヶ月での細菌叢の構成から5種類のクラスターを同定し、2ヶ月齢では1−3のクラスターに分けられ、12ヶ月になると3−5のクラスターへと変化することを示している。すなわち、クラスター(C)1、2は未熟クラスター、C3が中間、そしてC3.5が成熟型と分類している。
このことから、細菌叢は未熟型から成熟型へ成長することがわかるが、C3の中間型で止まるグループも出てくる。この中間型と喘息を調べると、2ヶ月でも12ヶ月でも喘息リスクが高まることから、2ヶ月で早く中間型になることも喘息リスクを高めるし、12ヶ月経って中間型で止まっていることも喘息リスクを高めることがわかった。すなわち、2ヶ月から12ヶ月までの成長速度が重要と思われ、モデリングから成長度EMAという指標を算出している。
あとは、最終的にどのクラスターへと変化したかという結果より、EMAが様々な喘息指標と逆相関していること、そして農家で育つということがEMAと正の相関を持つことを示している。農家の生活条件のいくつかと、EMAとの相関を調べると、家畜に晒されること、農家自家製の卵を食べることなどが強く相関すること、逆に12ヶ月になっても母親のミルクを飲んでいる子供は腸内細菌叢の成長が遅いことを示している。
あとはこのEMAの元となる主成分となる細菌種間のネットワークや、これら細菌が生産する単鎖脂肪酸の種類の分析などが行われているが、割愛する。要するに、乳児期に腸内細菌叢成長を高めることがアレルギー疾患の予防になるという話で、この成長とは何かという点について、わかりやすいイメージを与えてくれる論文だと思う。
農家が不潔とは言わないが、清潔を実現するため環境の多様性が失われてしまうと、とんでもないしっぺ返しを食う様な予感がする。
2020年11月17日
だれにでも、正常な認知機能が維持される限り一生涯続く記憶があると思う。実際、70を越した今でも、幼稚園や小学校時代の記憶がふっと頭に浮かぶことがある。知っている限りの乏しい知識をもとに考えると、この様な長期記憶が成立するためには、一部の神経細胞が持続的な変化、発生学上の分化を遂げる必要がある。これにより神経ネットワークの構造が持続的に変化することになるが、発生と同じでシナプス自体の形態変化を伴う分化が起こっている。
などとわかった様な気になっても、実際特定の記憶を長期に維持するために変化した細胞を捕捉することは簡単でない。今日紹介するスタンフォード大学からの論文は、長期記憶に関わる細胞分化を遂げた脳細胞を特定し、どの様な分化が起こっているのか調べた研究で、11月11日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Persistent transcriptional programmes are associated with remote memory (持続的な転写のプログラムが長期記憶に関わっている)」だ。
なんとも平凡なタイトルだが、こんなことも実際には明らかにされていないという気持ちがこもっている様な気がする。カンデル以来、皆がわかっていると思っている記憶は転写プログラムの変化だということを明らかにするためには、まず長期記憶過程を支えるために機能的に変化した細胞を探し出す必要がある。いくら強烈な記憶だからと言って、動物の脳全体から見るとほんの一部の細胞でしかなく、機能的長期記憶細胞を他の細胞から区別して取り出せるのか?
この課題を、特別な部屋に入った時電気ショックを与えて強い恐怖記憶を誘発し、16日後に再度同じ部屋に入れて恐怖を思い出した時活動した細胞を、活動時に発現する様操作したタモキシフェン依存性Cre組み換え酵素を用いて、蛍光標識する、複雑な実験システムを用いて実現している。
電気ショックを与えなかった群や、電気ショックだけの群など、様々な条件で標識を行い、最終的になんと1.5%もの細胞が標識されることを発見する。一回の記憶でこれほど脳細胞を使ってしまったら、足りなくなるのではと心配するが、様々な条件検討から、この中に長期記憶のために機能的に変化した細胞が存在することを確認している。
特定の経験についての長期記憶に関わる細胞を他の細胞から区別して取り出すことができたというのがこの研究のハイライトで、あとはこの細胞をFACSを用いてソートし、single cell RNA seqを用いて、細胞の種類、転写プログラムの特徴などを調べているただ、明らかになった転写プログラムと、長期記憶機能との関係が解明されたわけではないので、私が面白いと思った点だけまとめておく。
99種類の長期記憶に関わると考えられる分子の多くは、スパインと呼ばれるシナプス結合に関わる分子がリストされた。なかでも、フォスファチジルセリンレベルを調節して、小胞体の膜融合に関わる過程に関わる分子が目立つが、この過程はこれまでも記憶の固定に必須であることが知られている。 これらの遺伝子発現には、共通の転写因子が関わると考え、シスモチーフを探すと、なんと低酸素で誘導されるHIF1βであることがわかった。最近海馬の記憶にもこの分子の関与が示されているので、HIFがどう関わるのか興味深い。 神経細胞だけでなく、アストロサイトやグリア細胞でも、神経細胞以上の数の分子の発現がプログラムされ直している。すなわち、我々の頭の中では、神経だけでなく、神経を支える細胞も変化し、記憶を維持している。実際、アストロサイトと神経の間で、neurexin1とその受容体neuroligin-1の相補的セットが誘導されており、長期記憶過程で相互作用が高まることがわかる。面白いのは、ミクログリアでは自然免疫に関わる分子が高まっており、これが何を意味するのか興味が湧く。 以上が結果で、まず入り口に到達したという話だ。今後、特異的分子の組織内発言、ATACseqなどを用いたsingle cellレベルのエピジェネティック過程、遺伝子ノックアウトを用いる機能研究など、新しい分野が開かれたと思う。
2020年11月16日
今回の新型コロナウイルス感染で露呈したが、我が国のゲノム医療レベルは先進国の中でもかなりレベルの低い位置に甘んじている様に思う。研究の方ではまだ頑張っているとは思うが、その応用になると十年は遅れている。例えば、我が国でもようやくガンゲノム医療が始まったと騒がれているが、特定の遺伝子をキャプチャーして配列を調べる対象の遺伝子が固定されているなど、診療する側の自由を縛るという方向で検査システム全体が決められている。例えば次世代シークエンサーを用いたエクソーム検査を利用したくても、検査の自由とクオリティーを保証する米国のCLIA基準がないため、研究者以外が次世代シークエンサーデータを使うことは難しいし、オンコパネル法でも、疾患ごとに対象遺伝子を変えることは難しい。
今日紹介する米国白血病リンパ腫協会からの論文は米国で進められている高齢者のAMLをゲノム情報に基づいて行う重要性を問うた治験研究で、米国でのガンゲノム治験の自由度について学ぶところが多いので、紹介することにした。タイトルは「Precision medicine treatment in acute myeloid leukemia using prospective genomic profiling: feasibility and preliminary efficacy of the Beat AML Master Trial(前向きのゲノムプロファイルを用いた急性骨髄性白血病のプレシジョンメディシンに基づく治療:Beat AML 基幹治験の実行可能性と予備的な有効性評価)」だ。
この研究の目的は、60歳以上の急性骨髄性白血病(AML)と診断された患者さん(平均年齢72歳)を対象に、ゲノム検査に基づく白血病治療の有効性を調べることだ。骨髄移植や幹細胞移植が普及してから、白血病の治療は根治へと大きく転換したが、骨髄移植に耐えられない高齢者の白血病に関しては、薬剤を用いる治療が中心になる。幸いこのHPでも紹介したアザシチジンとBcl2阻害剤を組み合わせる治験が終わり、かなり有効な標準治療の認可が近いと思うが、ガンのゲノムに基づくプレシジョンメディシンへの期待が最も高い分野だと思う。
この治験研究は骨髄細胞を吸引で採取してから1週間以内に、がん関連ゲノム配列決定を含むゲノム検査とその分析を終え、その結果に基づいて標的治療薬を決め、治療を行うプロトコルが実際に可能かを調べている。
我が国のオンコパネル検査は、がんセンターの資料によると1−2ヶ月検査に必要となっている。一方、この治験では組織診断とともに、我が国のオンコパネルで調べる113種類の遺伝子のなんと4倍、406遺伝子と、大きな変異を検出するための31遺伝子、さらには265遺伝子についての遺伝子発現まで行って、これを1週間で医師に返すフローを確立している。
最終的に参加施設により差は見られるが、各施設の達成率は90−100%で、これほどの迅速診断が可能であること見事に示した。ただ、7日というスピード診断にもかかわらず、この間に2.3%の方が亡くなり、8%の人は検査結果を待たずに治療開始を余儀なくされ、さらに10%近くの人は治療を諦めている。すなわち、高齢者のAMLの場合、1−2ヶ月で診断できますなどと悠長なことは言っておられないのだ。
ここまでして、ようやく57%の人が、標的治療薬治療へとたどり着け、残りの人は通常の治療方法に回されている。すなわち、この治験の最初のアウトカムとしては、現時点で約60%の高齢者AMLがプレシジョンメディシンを受けられるという結論になる。
そして、まだプレリミナリーな段階だが、標的薬を中心に治療を行った場合の方が50%生存率は13ヶ月対4ヶ月と大幅に異なる。また、一部の人は、ゲノム検査に基づき開発段階の治療を受け、この場合さらに成績は良い。
以上が結果で、
プレシジョンメディシンは生存期間を伸ばす点で有効性が期待できるが、高齢者AMLの場合、診断の迅速性が重要。 AMLの場合、利用できる標的治療薬が多く、また今後も増えていくため、プレシジョンメディシンを受けるチャンスは高くなる。 が示された。
しかし、このスピード感と自由度がなぜ我が国では可能でないのか、「努力しても結果は同じ」と嘯くことなく、是非真剣に考え、本当のガンゲノム診療実現に取り組んでほしいと思う。
2020年11月15日
コレステロールが高いと発癌のリスクが高くなることは多くのガンで知られている。確かに臨床的にも、コレステロール代謝を正常化することで、ガン自体や周りの環境を変化させることで、ガンの増殖を制御することができることは報告されているが、実際のメカニズムについてはほとんど理解が進んでいない。
今日紹介するデューク大学からの論文はコレステロール代謝と思って行った介入が実際には組織適合性抗原の発現に関わっていたため、ガン免疫を高めることができたというわかりやすい話で11月11日Natureに掲載された。タイトルは「Inhibition of PCSK9 potentiates immune checkpoint therapy for cancer (PCSK9阻害はガンの免疫チェックポイント治療効果を高める)」だ。
おそらくこの研究は、コレステロール代謝とガンの関係を解明する目的で始められたと思う。タイトルにあるPCSK9はLDL受容体に結合してエンドゾームで分解することで、受容体のリサイクルを止める働きがある。したがって、細胞表面場のLDL受容体が低下してコレステロールが高まる。最近になって、PCSK9に対するモノクローナル抗体を用いて、LDLの分解を防ぎリサイクル率を高めるコレステロール血症の治療が始まった。もしPCSK9機能阻害でガンの増殖を抑制できれば、既にFDAに認可された治療法を組み合わせることができるというわけだ。
まず様々ながん細胞株からPCSK9遺伝子を欠損させて、マウスに移植すると、ガンの増殖が抑えられる。これはホスト側のコレステロール代謝とは無関係で、LDL受容体を欠損させたマウスでも同じ効果が見られる。一方、免疫システムが欠損しているマウスに移植した場合は、抑制効果が全く見られないことから、ガン免疫を介して増殖抑制が起こっていることが明らかになった。
次に、本来の目的であるPCSK1阻害と、チェックポイント阻害を組み合わせることで、ガンを抑制できるかを調べ、ヒトの高脂血症に用いられるevolocumabとPD-1抗体を組み合わせることで、ガンの増殖を抑えられることを示している。
最後はこのガン免疫が高まるメカニズムだが、LDL受容体の再利用との関わりを調べる実験は全て否定的結果で終わり、結局ガン抗原を提示するときに使われるクラス1MHCの発現をPCSK9阻害が直接高めるという結論に落ち着いている。事実、PCSK9はClassIMHCに直接結合し、またPCSK9阻害の効果は、MHC遺伝子を過剰発現させることでキャンセルされる。
以上の結果から、最初コレステロール代謝と癌との関わりで始められた研究が、PCSK9によるMHCの代謝変化によるガン免疫の活性化という結論で終わっている。面白いことに、チェックポイント治療に抵抗性を獲得した癌細胞でも、PCSK9抗体処理により再度免疫の標的になることも示されており、evolocumabやalirocumabなどをPD-1組み合わせる治療は期待できる様に思う。
結果よければ全てよし。
2020年11月14日
Interim reportとはいえ、ワクチンの有効性が報告された。我が国では結果の解釈をめぐって議論がある様だが、新しい感染症と特定されてから11カ月でinterim reportが出たことを個人的には評価している。すなわち、その背後に強い科学が存在しているということで、それを伝えていくことが必要だ。並行して、新型コロナウイルス(Cov2)に対する人免疫反応に関する論文がひしめいてきたので、11月26日岡崎さんと論文ウォッチでまとめて報告することにする。代わりに今日は予防薬の観点から面白いと思った論文を紹介する。
現在我が国でも、急速に感染者数が増加してきた。経済優先にして人と人が集まると当然のことだが、このことを示す興味深い解析がNatureにオンライン掲載された。
なんと9800万人のスマフォデータについて、例えばレストラン、教会、病院などのポイントに集中する機会と時間を計算し、実際の感染者数増加との相関を見た研究で、どう人が動けば感染が拡大するかうまく解析できている。この解析によれば、一番危険なのはフルサービスのレストランでの会食で、他のカフェやホテル、フィットネスセンターなどと比べて5倍以上感染機会があることを示している。もちろんレストラン自体が危険なわけではなく、長時間滞在し、飲んで食べ、歓談することにより感染が起こることを示している。すなわち、会話時の飛沫が最も危険であることの裏返しだが、歯科医の治療を受ける際に推薦されている様に、洗浄液で口腔内のウイルスを不活化したあとレストランで食べるなどの工夫が必要かもしれない。ただ洗浄で味が損なわれれば難しい。アルコール度70前後のアブサンを口に含むのが私向きだが、まず手に入るか調べてみよう。
以上の結果は、感染しないだけでなく、感染ささない工夫の重要性を意味するが、感染初期の動態を解析するには動物モデルが必須になる。しかし適したモデル動物は少なく、手軽なマウスは受容体になるACE2との相性の違いか利用されにくい。そのため、マウスの上皮にヒトACE2を発現させたマウス作成し、これを簡便な動物モデルとして使うことが行われている。このマウスを使って感染初期過程について調べた研究がやはり11月9日Natureにオンライン掲載された。
ヒトACE2を発現させたマウスを用いた感染実験など、新しくも珍しくもないが、鼻に感染させたあとの初期過程に絞っている点で学ぶことも多かった。
まず何よりもウイルス感染は、最初の量が重要であることを再確認した。ウイルス感染単位を千単位、一万単位、十万単位で鼻から感染させると、10万単位感染させたマウスは全例死亡するが、千単位では全く死亡しない。そして、1万単位ではちょうど半分が10日程度で死亡するが、あとは回復する。しかも感染2日目から、肺には多くのウイルスが侵入しており、上気道が一体化していることがわかる。ただ、この結果を人間にそのまま当てはめるのは難しいと思う。というのも、ACE2の発現量は人間の場合、鼻粘膜上皮と比べて肺の上皮は低いため、おそらく拡大の速度は異なる可能性がある。
この研究が面白いと思ったもう一つの理由は、鼻粘膜に感染した場合、ウイルスは速やかに脳へ移行する可能性を示した点だ。この実験系では、Cov2はもっぱら上皮細胞のみに感染し、嗅細胞には感染を認めない。それでも、感染後6日で他の臓器より先に脳でウイルスが認められることには驚く。重症例での検討が中心だが、Covid-19感染により脳は異常が見られることが知られている。脳への伝搬に神経細胞は関与しないのかも含めて、詳しい解析が必要だと思う。
神経細胞には感染しないことを利用して、感染による嗅覚障害のメカニズムについて調べ、神経支持上皮細胞が失われるだけで、十分嗅覚障害が出ることを確認している。人間では、嗅細胞への感染を示すデータもあるが、おそらく初期の症状として見られる嗅覚障害は、神経細胞への感染は伴わない様に感じた。
この研究からわかるのは、初期の気道へのウイルス感染量を一桁減らすことで大きな効果があることを示している。もちろん、話す時間を一桁減らすこと、あるいは口内洗浄を繰り返すことでこれは可能かもしれない。ただ、ラマやラクダのH単鎖抗体を用いると、安くて有効な感染防御が可能だと主張する論文が11月5日、Scienceにやはりオンライン掲載された。
このHPでもラマのH単鎖抗体については何度も紹介してきたが、この抗体の利点はバクテリアや酵母で活性の高い抗体を産生できるので、価格を安く抑えることができる点だ。以前、抗体を発現する酵母を家畜に食べさせて腸炎を抑えるという論文を紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/9968 )、この技術をウイルス感染に必要なSタンパク阻害抗体作成に利用する話だ。我が国も含め、Cov2を中和するH単鎖抗体の論文は多く報告されているが、この研究では、トライマーにすることで、極めて高い中和活性を達成するとともに、なんと生産コストが安いだけでなく、凍らせても、凍結乾燥しても、さらには熱を加えても安定で、エアロゾルスプレーとして使える抗体へと進化させている。是非、食事の前に鼻にスプレーする製品を早く完成させて欲しい。
以上、感染が拡大しているが、感染防御の手段の開発も加速していることを伝えたい。
2020年11月13日
メタマーとかメタメリズムという言葉は一般には馴染みがないかもしれないが、服飾、建築、さらにはカラーディスプレー設計まで、色彩を扱う人には広く知られている。すなわち混じり合っている色の成分は違っていても、感覚的には同じ様に見える組み合わせを意味している。三種類の錐体細胞からのシグナルと、稈体細胞からの光度の情報を統合して色を感じる我々の情報処理システムを考えると、当然の概念だと思うが、どの組み合わせが同じに見えるかを科学的に決定するための情報科学は現在極めて重要な分野となっている。
今日紹介するイスラエルワイズマン研究所からの論文は匂いの成分からメタマーを設計できるかチャレンジした面白い研究で11月11日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「A measure of smell enables the creation of olfactory metamers(匂いを測定することで嗅覚メタマーを創造できる)」だ。
三種類の錐体細胞と稈体細胞のシグナルから統合される色彩感覚と違い、嗅覚細胞は何百種類もあり、メタマーの研究が簡単でないことは想像がつくが、要するに匂いの成分を組み合わせて、匂いという感覚をデザインできるかという問題になる。このために、一つ一つ、あるいは組み合わせた匂いを実際に嗅いでもらってその結果を情報処理することになるが、匂いの場合表現があまりに主観的なので(ワインテースティングの表現を考えればわかる)、結局二種類の匂いがどの程度違っていると感じるかを数値化して、これをもとに各匂いを情報空間上に位置付けるという情報処理方法に頼るしかない。
実際には4種類から10種類の成分を組み合わせた14種類を2種類づつ嗅ぎ比べ違いを数値化してもらい、これをもとに各組み合わせの感覚の違いを予想するモデルを構築している。これができると、実際の匂いも、この合成の匂いと比較してもらうことで、数値化することができ、それぞれの匂いの近さを、このモデルから予想することができる。実際、専門家に調合してもらったバラ、すみれ、香辛料アサフェティダの違いを予測することができることを示している。
また、この方法を用いることで、各人の匂い感覚の鋭さについてもかなり正確に推定することが可能であるようで、例えばワインのテースターに向いているか予測するテストになるのではと興味が湧く。
最後に、ほとんどの人が同じと感じる匂いのメタマー(構成成分の異なる組み合わせ)が存在するかどうか、匂いの比較実験結果から選んだ二種類の組み合わせを比べさせる実験を行い、80%以上の人がほとんど同じと感じる、成分が全く異なる2種類の組み合わせが存在することを確認し、匂いのメタマーを作ることができたと結論している。
よく考えると、2種類を感覚的に比較してスコア化した数値をもとにモデル化することで、各成分の感覚を数値化できるという話で、確かに異なる匂い成分を組み合わせて同じ感覚を誘導できたとしても、メタメリズムを本当に理解できたのか疑問に感じる。実際、例えば異なる成分を組み合わせて同じ匂い感覚をデザインするという究極の課題には、まだまだ遠い。これは、色彩と違って、異なる刺激に対する神経細胞の数が多すぎるからだが、この研究はこの長い道のりの第一歩として評価できると期待している。