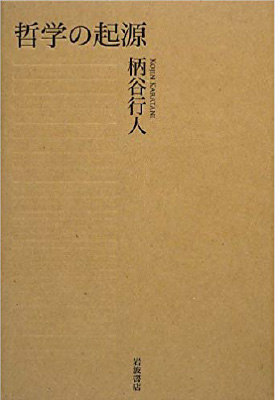
「生命科学の目で見る哲学書」では様々な著作を取り上げるつもりだが、あくまでも生命科学誕生の過程をたどることが主目的で、この観点から私が重要と思う著作を哲学書を中心に時代を追って自分なりにまとめ、現代の科学が成立するために必要だった条件を読み解きたいと思っている。
ただ、その当時を知るための著書がない場合も多い。例えば前回は、現代もなお科学や生命科学に大きな社会的影響力を及ぼしている一神教の誕生を取り上げたが、聖書や仏典は取り上げなかった。残念ながら仏典を読んではいないが、聖書は原典や注釈書は読んでいる。しかしこれを紹介したところで、科学の誕生を知るための作業にとっては、反面教師以外の価値を持たないと思った。キリスト教については、トマス・アクィナスに触れる時もう一度取り上げるつもりだが、今後も原典に当たることはしない。この判断から、前回もユダヤ教を例に一神教の誕生について書かれたフロイトの「モーセと一神教」を取り上げた。読者は、この一冊で一神教の本質を十分わかってもらえたと思う。
これに続く今回は、当然哲学の誕生と科学の萌芽について考えることになる。すなわち、人間が自然や人間について自分で考え、その結果を知識として蓄積し始める作業の始まりだ。
フロイトの「モーゼと一神教」で、ユダヤ教の起源として示されたイクナートン(アメントホーテプ4世)が生きていた時はだいたい紀元前14世紀で、各集団でユダヤ民族が独自に育んでいた民族的宗教を、モーゼを預言者とするユダヤ教として再統合したのが紀元前6世紀になる。ギリシャ(イオニア)での哲学誕生(最初の哲学者と言われるタレス)もほぼ同じ時期で、普遍宗教としての一神教と哲学はほぼ同じ時期に世界史に誕生することになる。
哲学はイオニア以外の他の場所でも存在していたはずだと反論されるかもしれない。実際同じ時期、中国でも孔子や老子の思想が生まれている。しかし、私にとって哲学の誕生がどこで最初に起こったのかは問題ではない。実際には、自然や人間について、自分で考え、独自の知識を生み出すようになった条件を知ることが重要だ。そしてそれがギリシャのイオニアで見られるならそれで十分だ。
更にイオニアの哲学から始めることは、他の地域の哲学から始めるのと違って、大きな利点がある。すなわち、イオニアでの哲学誕生は、そのまま2人のギリシャ人、プラトンとアリストテレスを経て(彼らにより哲学は、イオニアの哲学とは似ても似つかないほど変化するが)、17世紀の科学誕生まで、ヨーロッパの原点として受け継がれる。これは、ヨーロッパを科学誕生の場所と捉える私にとっては都合が良い。従って、多くの先人と同じように私も哲学の誕生を紀元6世紀のイオニアに求めたうえで、作業を進める。
と言ってしまったが、本当はイオニアの哲学が書いた原典を読むことはもうできない。というのも、プラトン以前のギリシャの哲学者の著書はほとんど失われており、またソクラテスを筆頭に、多くの哲学者は著作を残していない。このため、結局プラトンやアリストテレスが書き残した文章から当時の哲学者の思想を再構成してもらわないと、私たちの手には追えない。結果、今回も代表的な原典に当たるのではなく、この時代の哲学を紹介してくれる著書について紹介することにする。

幸い、様々な形でイオニア以降のギリシャ哲学を復活させる作業がヨーロッパで続けられた。すなわち、早い時期から失われてしまった初期の哲学者の言葉を復活させる大変な作業を、苦労を厭わず行う人がいた。これを成し遂げた最初の人が3世紀の歴史家ティオゲネス・ラエルティオスで、なんとギリシャ82人の哲学者の思想を「ギリシア哲学者列伝」と言う本にまとめている。岩波文庫から和訳も出ているので(図2)、各哲学者の大まかな考えを知ることができる。
私も全巻購入してはいるが、最初のタレス、ソロンと読んだあと、それ以上読み通すのは止めた。と言うのも、大変な作業を成し遂げた重要な本だと理解しつつも、記述が羅列的で退屈してしまう。結局辞書がわりに使うことになってしまった。
代わりに当時の哲学を知るためのお勧めが、イタリアIBMの支配人まで務めあげたあと、スパッとビジネスマンを辞め作家に転身したルチアーノ・クレシェンツォの「ギリシャ哲学史」谷口勇訳 而立書房(図3)だ。
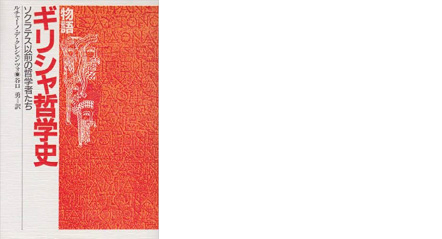
流石にイタリアのベストセラー作家により書かれただけあって、この本はともかく読み物としてよくできている。一人一人の哲学者が本当に身近に感じられ、また笑いを誘う場面も多い。例えば、ピュタゴラスの流派では、
「そら豆を食べざること、パンをちぎらざること」
などの教えが守られていた話を読んだときは、思わず笑った。
このようにユーモアを交えて読者を飽きさせないよう書かれているが、実際には本質的なことをわかりやすく的確に述べており、初期の哲学者が何をしようとしていたのかもよくわかる。
例えば最初の哲学者と言われるタレスについて、
「とどのつまり、タレスは哲学史上で極めて重要な位置を占めているのだが、それと言うのも、彼がいくつかの問題に答えを見出したからと言うよりも、これらの問題そのものを提起しようとしたからなのである。あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯塾考することこそ、宇宙の解釈へ向けて西洋の思考が歩み出すスタートだったのである」
と書いて、ギリシャ哲学の始まりを上手く一言で表現している。
ただ今回ギリシャ哲学の始まりを知る本として私が取り上げたのが柄谷行人の「哲学の起源」だ(図1)。若い頃から彼の著作には親しんできたので、柄谷さんと呼ばせてもらうことにする。
柄谷さんの文学論については読んだことはないが、哲学や社会に関しての著作は早い時期から読んでいた。個人的印象だが、ミレニアムが終わろうとする頃から(個人的な読書経験の話)、読んだ印象が大きく変わった。豊富な知識とオリジナルな考えに裏付けられている点ではどの著作も一貫しているが、最初の頃は、豊富な知識が、これでもかこれでもかと連発して打ち出されてくるのに対応が追いつかず、知識の圧力に圧倒されているうちに、読んだ後ほとんど頭の整理がついていないのが実情だった。そのため、一時柄谷さんの本から遠ざかっていた。
ところが私自身の専門が再生医学だった関係で、文科省や内閣府の生命倫理委員会に出席するようになって社会学や哲学の本を読む機会が増えた時、何かの参考になるのではとふっと手に取ったのが柄谷さんの「倫理21」だった。知識の豊富さはそのままで、本の目的が明確に理解でき、提示されているシナリオもわかりやすく、読んだ後自分の頭もしっかり整理されているという、新しい読書経験ができるようになった。それ以降、ほとんどの著作を愛読し、常に新しい視点に感銘を受けている。この中の一冊が「哲学の起源」だ。
しかし、私が生命科学の専門家を職業としていたこともあり、この経験の違いで同じ本についての見方もかなり違ってくることもよくわかった。これに関してはぜひ一度取り上げたいと思っており、カントを取り上げる時、柄谷さんのカント論「トランスクリティーク」を取り上げて、思想家と生命科学者の経験の差について考えてみたいと考えている。
さて「哲学の起源」は、「倫理21」「トランスクリティーク」「世界共和国へ」「世界史の構造」の後で書かれている。この間の一連の作業で、柄谷さんは、過去、現代の社会を、交換様式という独自の切り口から分析し、自由な支配されない(対等な交換関係に基づく)社会を保証できる世界共和国が可能であるかを考えようとしている。しかし、決して理想論を唱えて終わるのではない。歴史に学び、過去の思想に学び、その上で具体的な可能性を探るという強い意志が感じられる。そして、世界共和国の可能性の重要なヒントがあると目を向けたのが、ギリシャの政治、文化のルーツ、イオニアを中心とするギリシャの植民地で、この研究成果が「哲学の起源」だ。
このように「哲学の起源」では、柄谷さんが未来の理想的社会として構想している世界共和国という明確な目的が示され、イオニアを中心とするギリシャ植民地で生まれるギリシャ哲学を分析することが世界共和国を構想するのになぜ必要かが、物語として理解できるよう書かれている。この点で当時の各哲学者の考えを羅列した従来の本とは全く異なる。
イオニアは、音韻と文字が完全に一致した世界初の表音文字ギリシャ文字が発明され、貨幣経済が生まれ、ギリシャ民族の心ホメロスの叙事詩が文字として書き起こされ、人間が独自に自然についての説明を試み、医学が呪術から切り離され、人間の歴史が語り始められ、世界に先駆けてイソノミアと呼ばれる政治体制が生まれた地域だ(これらは全てこの本に書いてある)。
歴史になぜという問いはないが、それでも「なぜ」イオニアでこれほど多彩な新しい文化が生まれたのか説明しようとしたのがこの本だ。哲学に関していえば、クレシェンツォが「あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯塾考すること」(前述)が、イオニアを中心とするギリシャの植民地でなぜ可能になったを説明しようとしている。
この説明のために、柄谷さんは「世界史の構造」を中心とするそれ以前の著作で展開してきた、交換様式と言う視点で社会構造の変化を見る手法を用いている。柄谷さんの交換様式という概念の最大の特徴は、貨幣や資本といった物質の交換と同時に、人間の心の関わる目に見えない交流も統合して扱うことができ、哲学や宗教の誕生を、経済や生産の歴史と同時に捉えることができる点だ。
例えば前回扱った一神教・普遍宗教の誕生について柄谷さんは次のように説明している。
「普遍宗教もまた、交換様式の観点から見ることができる。一言で言えば、それは、交換様式Aが交換様式Β・Cによって解体された後に、それを高次元で回復しようとするものである。言い換えれば、互酬原理によって成り立つ社会が国家の支配や貨幣経済の浸透によって解体された時、そこにあった互酬的=相互扶助的な関係を高次元で回復するものである。私はそれを交換様式Dと呼ぶ。」
この引用だけではわかりにくいと思うので、ユダヤ教が普遍的一神教へと発展する過程について、私なりに彼のシナリオを脚色して説明しよう。
前回取り上げたように、ユダヤ教はそれまで分散して生きていたユダヤ民族がソロモン帝国に統一され、その後帝国が滅びてバビロン捕囚で奴隷として過ごす中で、普遍的一神教としての現在の形が生まれる。
この過程でユダヤ社会は、小さい部族の中での交換が中心の互酬的社会、すなわち交換様式Aが、ソロモン王朝による帝国支配という交換様式Bと貨幣経済と言う交換様式Cにより置き換わるが、帝国の崩壊とともに、全員が奴隷として交換様式BCから完全に阻害されるという変化が起こる。この間の変化を宗教の観点から見ると、最初部族の氏神様といった呪術的宗教が、帝国の誕生とともに、帝国支配と一体化して部族の呪術性を排した一神教的絶対宗教(必ずしも一神教である必要はない)へと変遷するが、バビロン捕囚により交換様式BCから完全に排除されことを機会に、個人と神の関係に基づく普遍的一神教が誕生する。
すなわち、普遍的一神教としてのユダヤ教は交換様式Dで、社会経済的な交換様式BCから完全に排除された穴を埋めるため、交換様式Aを高次元で回復させて誕生したと言うシナリオだ。
柄谷さんは、この同じメカニズムがイオニアでの哲学誕生にも働いている、すなわち、哲学も交換様式Dの発生として捕らえられると言う。しかも、イスラエルでユダヤ教が完成した時期に、イオニアの哲学にとどまらず、中国春秋時代の孔子、老子、そしてブッダまで現れていることから、当時世界中で帝国の崩壊が相次ぎ、これが世界レベルで交換様式Dの誕生を促したと言っている。
ただ他の地域と比べたとき、宗教や宗教的思想ではなく、自由な人間を基盤とする哲学がイオニアで誕生したのは、交換様式BもCも崩壊し、これに代わる高次な交換様式Aの回復が精神レベルに留どまらざるを得なかったユダヤ教の誕生とは違って、イオニアでは政治経済的にも交換様式Dの導入が一度成功しており、わざわざ架空の神と人間の関係を前提としなくとも、自由な人間と人間の関係の上に精神的な交換様式D、すなわち哲学を誕生させることができたと言う。この帝国や民主主義とは異なる社会経済体制はイソノミアと呼ばれる。
このイソノミア社会を生んだイオニアの歴史的条件について、この本から私なりに抜き書きしてみると次のようになる。
- イオニアには貿易を通じてエジプトからアジア全域の科学技術、宗教、思想が集まっていた。
- 社会的には、専制国家を目指さず官僚制、傭兵制をとらず、自由貨幣経済システムを取り入れた。
- 様々な地域から植民してきた(=すなわちそれまでの部族的伝統をきりはなした)人たちが、新たな盟約共同体を作り、伝統的支配関係から自由だった。
- 自由な貨幣経済を取っていても、大土地所有が起こらない構造になっており、貧富の格差が生じなかった。
このような特殊な条件が、その後の民主制では常に対立した関係にある自由と平等の関係を乗り越える、自由であることによって同時に平等であり得るイソノミア、すなわち誰も支配されない社会を可能にした。
柄谷さんの言葉を引用すると、
「イオニアの諸都市において回復されたのは、士族社会に先行するような遊動民のあり方である。無論イオニア人は狩猟採取民や遊牧民に戻ったのではない。彼らが遊動性を回復したのは、広範囲の交易や手工業生産に従事することを通してである。」
「イオニアに始まったのは、労働と交換によって生活することを価値とするような文化である。」
「交換様式という観点から見ると、イオニアでは交換様式Aおよび交換様式Bが交換様式Cによって超えられ、その上で交換様式Aの根本にある遊動性が高次元で回復されたのである。それが交換様式D、すなわち、自由であることが平等であるようなイソノミアである。」
これを読むと、柄谷さんが考える世界共和国のあり方がよく見えてくる。
要するに理想的交換様式Dでは、人間の自由と平等が実現されなければならない。ただ、この支配されない自由な人間関係という地上の交換様式Dがないと、人間を越えた神を前提として自由と平等を回復させる以外に交換様式Dは実現しない。一方、自由であることが平等である交換様式Dとしてのイソノミアが現実にこの世に実現すると、思想的には神・人間という不平等関係に依存するのではなく、自由な人間同士の精神的交換様式が生まれることになる。
しかし、自由と平等を享受できる社会だけでは、より精神・思想世界に自由を主張する哲学を誕生させる動機は弱かったようだ。すなわち、タレスが「あらゆる神秘の解決をもはや神に帰するようなことはしないで、自分の周囲を観察し、精一杯熟孝することで、宇宙の解釈へ向けて西洋の思考が歩み出すスタート」を切るためには、イオニア諸国が帝国の侵略を受けて、この世に実現した交換様式Dが失われるまで待つ必要があった。しかし一度世俗的交換様式Dを経験した後は、その喪失を埋めるための精神的な交換様式Dの回復も、宗教ではなく、より世俗的な精神の自由、すなわち哲学が誕生することになる。
このようなイオニアの思想を代表する例として、柄谷さんが、「病気の原因として神を持ってくることを拒否し、自然原因を求めた医学の父」、ヒポクラテスをまず持ってきたのには、さすがと感心した。素晴らしい例だ。そしてイオニアの哲学が、アテネ型の「フィロソフィア(知への愛)」ではなく、人間への愛を基盤とする思想だったことを以下のように述べている。
「イオニアにおける「人間の愛」は、人間をノモスではなくフィシスを通してみる態度、つまり人間をポリス、部族、氏族、身分のような区別を括弧に入れてみる態度と切り離せない」。
このようにあえてヒポクラテスから始めることで、イオニアの哲学誕生の条件を際立たせた後、柄谷さんは、ヘロドトス、ホメロス、ヘシオドス、ピタゴラス、ヘラクレイトス、パルメニデス(プラトンを議論する時に取り上げる)、エンペドクレスを取り上げて、イオニアの思想の、
- 宗教との関係、
- アテネのギリシャ哲学(プラトン、アリストテレス)との関係、
- 宇宙の起源と進化についての考え、
- 数学と音楽の扱い、
などについて、イオニア以外の思想と比較して議論することで、イオニア哲学の真髄を解説し、これがアテネで始まるプラトンやアリストテレスの哲学とはまったく相反する思想であることを説いているが、これ以上詳細を紹介する必要はないと思う。
なぜイオニアで哲学が始まるのか、柄谷さんの結論はクリアだ。紹介したように哲学は世俗から離れたところでは誕生できない。ヒポクラテスに見られるように、自由であることが平等であるような人間への愛が世俗に存在していて初めて、人間中心の哲学が生まれるということだ。本当の哲学は、決して単純な知への愛ではない。宇宙(科学)と生命(倫理)の両方について統合的に塾考することだ。この本を読んで初めて、私もイオニアで哲学が始まった理由を納得した。
ただ、それでもイオニアで始まったのは自然科学ではないと思う。すなわち、イオニアでは超越的力に頼らず自分で考えるという、科学にとって最も重要な一歩が踏み出された。しかし、自分の考えを他人と共有するために手段が、数学を除くと、対話や議論以外に存在しなかった。わかりやすくいうと、客観的に概念を検証するという態度はほとんど存在しなかった。その意味で、私にとってイオニアは哲学誕生の地であっても、科学誕生の場所ではない。実際、客観的に概念を検証できないという問題が、プラトンによる、神秘性を許容するより宗教的哲学の誕生を許すことになる。
次回はいよいよプラトンの著作の登場だ。



