2018年1月、テキサスのベーラー医大、オレゴン大学、オランダ・ライデン大学、そして英国のサンガー研究所が共同で、トレハロースを栄養源として増殖できる病原性の高いクロストリジウム(CD)が選択的に増えることが、2000年以降トレハロースの価格が低下し利用拡大と並行してこの感染症が増加した原因であるとするショッキングな可能性を示した。
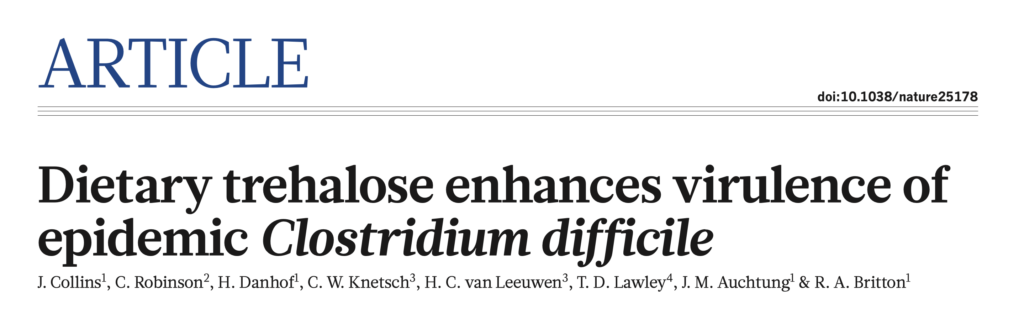
以前紹介したように(https://aasj.jp/news/watch/7897)、この研究は系統的に離れているCD系統RT027とRT078が共に毒性が高いことに注目し、それぞれが系統進化とは別に、腸内環境での高い増殖能力を獲得したのではと考え、増殖優位性を与える遺伝子を探索した結果、これがトレハロースを利用して増殖するための遺伝子セットであることを明らかにした。
この結果はNatureに掲載されたこともあり、外国では大きく報道された。勿論このHPでも紹介し、「大至急臨床の現場でも確かめる必要がある」と結論した。と言うのも、この研究の大半は動物を用いた研究で、臨床的検討は限られていた。
その後、この話題は私の頭の中から消えていたが、数日前株式会社林原の研究員の方から、臨床的な検討の結果トレハロースの濡れ衣を晴らしてくれた論文が昨年発表されているとの指摘を受けた。
早速読んでみて、ベイラー医科大学の論文を紹介した以上、今回の論文も紹介すべきだと考えたので、ここに紹介する。実際には別々のグループから2報の論文が発表されているが、EBioMedicineにオックスフォード大学から発表された論文が包括的なのでそちらを紹介する。

この研究は、まずこれまで全ゲノム配列が明らかにされている臨床例から分離された5232株のCDを比較し、臨床例から分離されCDの多くが、レファレンスCDのゲノムと異なり、トレハロース利用セットの遺伝子群を持っていることを示し、特にRT027が属している系統群ではほとんどが同じ遺伝子群を持っていることを明らかにした。すなわち、トレハロース利用能は病原性とは無関係に、クロストリジウム進化の早い段階で獲得された形質であることを示した。
さらに、CD感染症200例あまりから分離したCDの解析から、感染による死亡とトレハロース利用能に有意な相関がないことも示している。
以上の結果は、臨床例からの結果は、主に動物モデルを用いた先の論文と完全に相反することを示している。この結論の妥当性をさらに示すために、著者らは欧米でのトレハロースの輸入とCD感染症との相関性がないこと、また試験管内培養系ではトレハロースがCDの毒素産生を誘導するわけではないことも示している。
以上、抑制的ではあるが明確にベイラー医大の研究を否定した論文で、臨床例を直接扱っていることから、信頼していいように思う。
このように結論が真っ向から対立する研究は、科学では当たり前のことだ。ただ、内容が食の安全に関わる話だけに、両グループが討論できる場が設けられることが重要だと思う。



