自閉症スペクトラム(ASD)児が発熱すると一過性に、症状(特に社会性に関わる症状)が改善することが報告されていた。おそらく経験されている両親や医師の方には「そうそう!」と頷かれるかもしれないが、私も含めて多くの人は、本当にそんなことがあるのか疑問に思うのが普通だ。
ところが、コーネル大学、コロンビア大学、そしてカリフォルニア大学サンフランシスコ校が集まって、本当にこのような現象があるのかシモン財団データベースにに登録しているASD児について調べ、確かに発熱でASDの症状が一過性に改善する事を示した研究が昨年1月、Autism Researchに掲載された(Autism Res 2018, 11:175-184)。
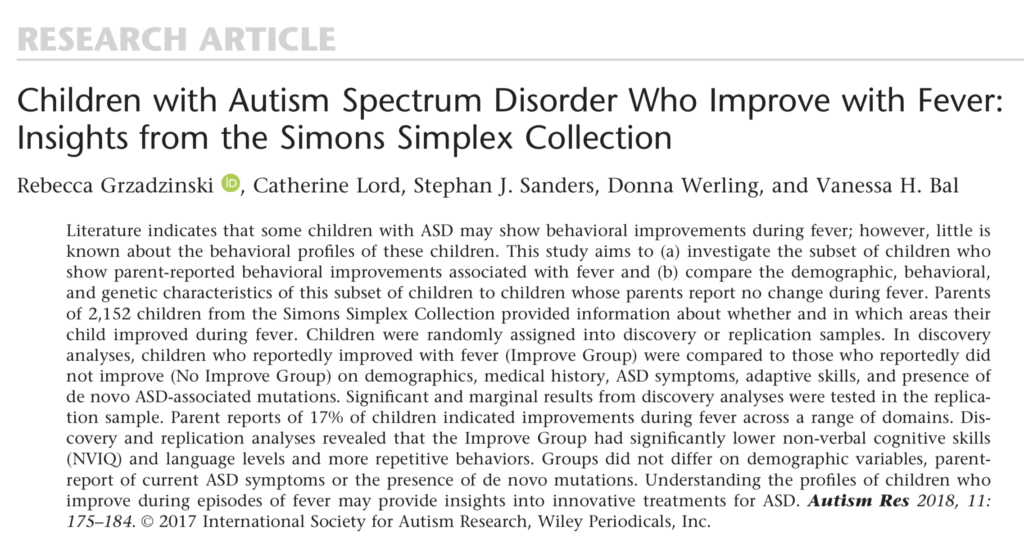
研究では4歳から18歳までのASD児を持つ2156家族に「ASDの症状が発熱で改善したと思ったことはあるか?」と質問したところ、驚くことに362家族(17%)が「確かに改善したことがある」と答えた。
どのような症状が改善したのかさらに聞いたところ、コミュニケーション能力と答えた人が166人、気分や行動と答えた両親が199人に上った。
次に、発熱の影響があったASD児と影響のなかったASD児を比べ、症状の違いを調べると、完全に有意差があるとは言えないものの、症状の重いASDほど改善が見られる傾向が見られた。例えば、適応性が悪く、行動異常が強い子供ほど発熱による症状の改善が見られる。一方、遺伝的な影響についても調べているが、特別の関連は認めていない。
以上の結果から、確かに発熱がASD児の症状の改善につながることがあること、そして症状の重い児童ほど発熱により症状改善が見られる確率が高いことが確認された。
一過性でも症状改善が見られるというこの結果は、治療法開発という観点からは勇気付けられる結果だ。ただ、この研究結果だけでは、なかなか糸口はつかめなかった。
ところが先週、マサチューセッツ工科大学の研究グループが、ASDの発熱と社会行動を研究できるモデル動物システムを開発し、減少の背景にあるメカニズムを探った論文を発表した(Reed et al, IL-17a promotes sociability in mouse models of neurodevelopmental disorders (神経発生異常モデルマウスの社会性をIL17aが促進する), Nature, 2019: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1843-6)。
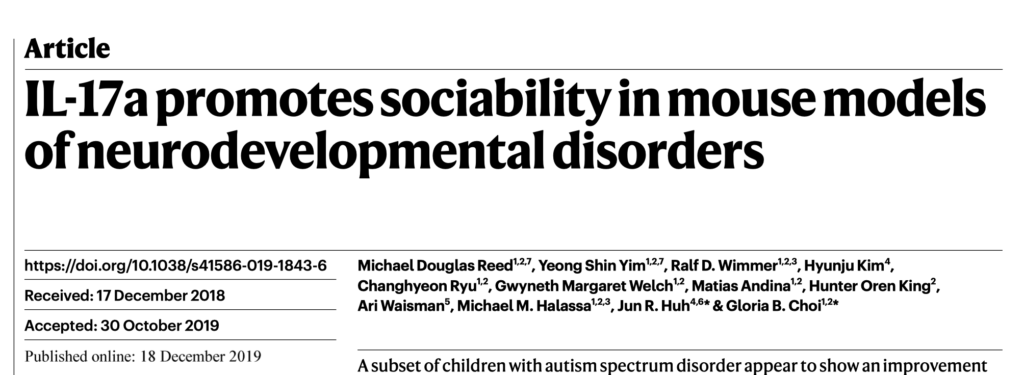
発熱を誘導するといった研究を人間で行うことはできない。そこで、モデル動物が必要になる。このグループは、何種類かの遺伝的ASDモデルマウス(一つの遺伝子の変異によりASD症状を示すマウス)を使っている。マウスで社会行動を調べる様々な方法が開発されているが(例えば他のマウスと一緒にいる時間を測る)、遺伝的な変異だけでは症状がはっきりしないことが多い。そこで、このグループは妊娠時に炎症が起こるとASDが発症しやすいという現象を動物モデルで再現する方法を組み合わせ、背景の遺伝的要因は問わず、ほとんどのASDモデルで社会行動の低下を誘導することに成功している。
こうしてできた社会行動低下モデルマウスを用いて、次は発熱の影響を調べることになる。発熱誘導には感染症と同じ状態を誘導する方法と、発熱中枢を刺激する方法があるが、この研究ではまず感染で発熱する状態を再現するため、バクテリアの発熱誘導物質をマウスに投与する実験を行なっている。結果は期待通りで、LPSと呼ばれるバクテリア膜のポリサッカライドを投与された自閉症モデルマウスで社会性の回復が見られる。ところが、神経刺激のみで発熱だけを誘導すると、全く回復は見られない。すなわち発熱というより、炎症が社会性の回復に関わることが示された。
ここまでわかると、炎症時に分泌され社会性を回復させる分子を特定するのは現在の技術があれば難しくない。様々な探索を行い、最もパワフルな炎症物質の一つIL17aを注射することで社会性が回復することを示している。
結果は以上だが、もう少しわかりやすいようにこの研究の意義をまとめてみると、
- 人間で見つかった現象(発熱すると社会性が改善する場合がある)を研究するための動物モデルが見つかった。
- IL-17は強い炎症性サイトカインなのでむやみに注射するわけにはいかないが、脳だけでこの回路を刺激する方法がわかれば、少なくとも社会性については改善できる可能性がわかる。
- IL-17a受容体陽性神経細胞という細胞レベルのヒントが見つかったことで、新しい介入手段の開発が期待できる。
研究というと、基礎から始めて、臨床に進むと思いがちだが、このように臨床的観察から始めて、動物に進むことも重要で、今後も基礎と臨床がうまく連携して、ASDの社会性を回復させる方法の開発を期待する。



