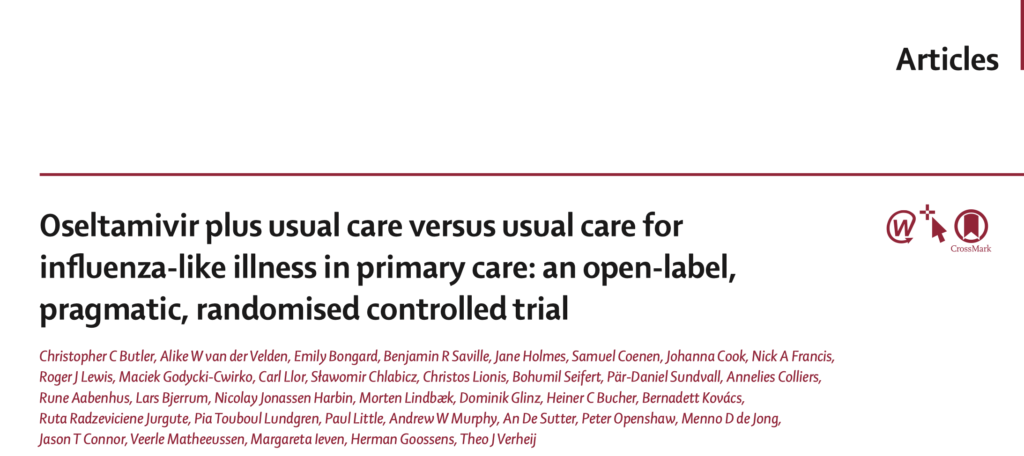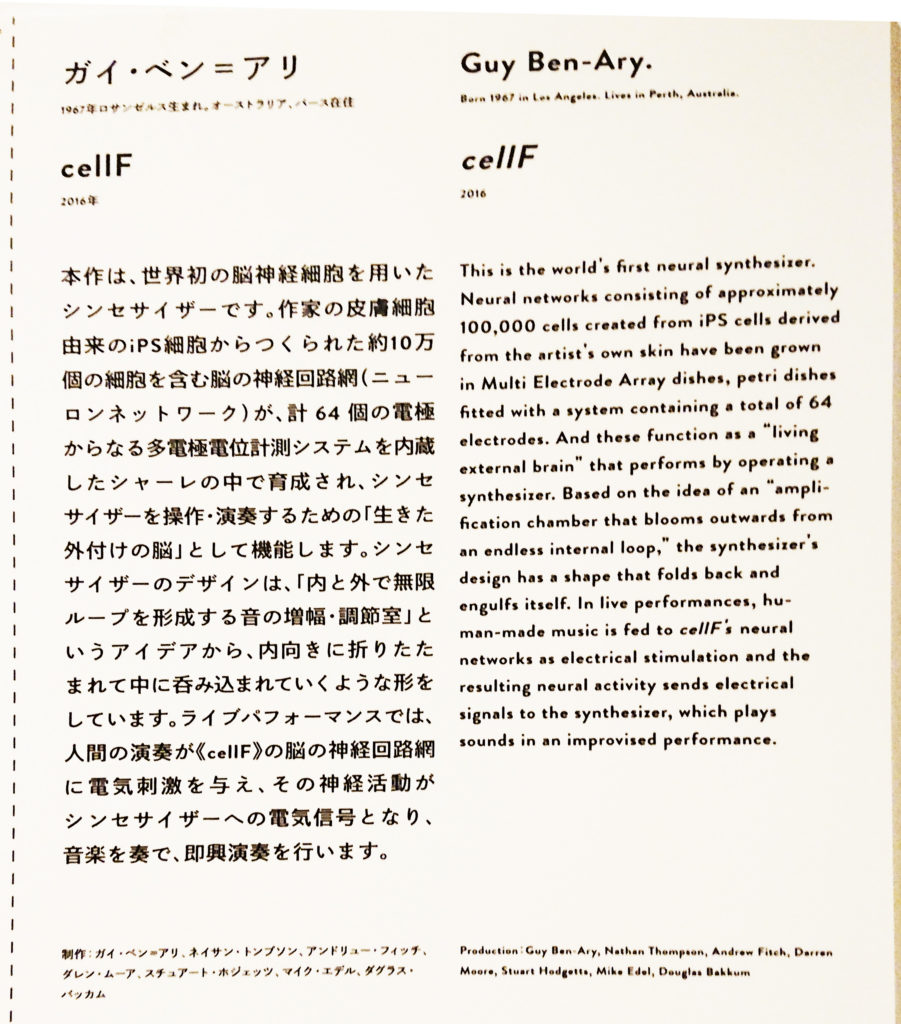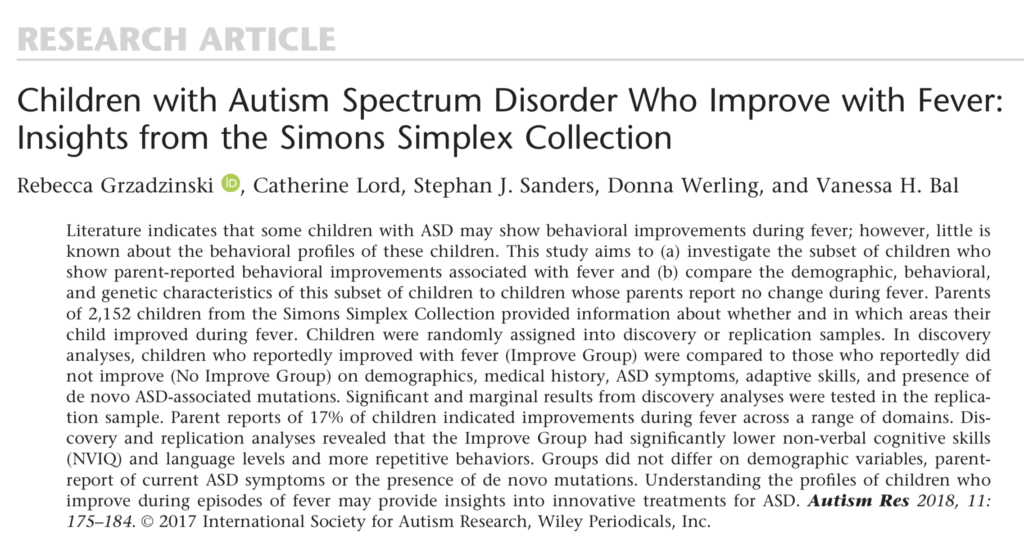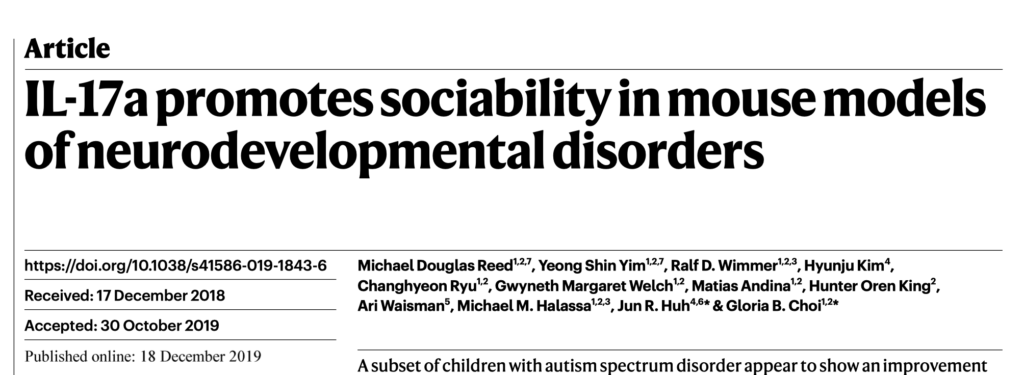2019年12月31日
細菌が増殖する際、到達した密度に応じて細胞の活性を変化させたり、バイオフィルムを形成したりするコミュニケーションメカニズムはクオラムセンシング(QS)と呼ばれ、例えば歯周病など局所で持続する細菌感染の治療標的として重要なメカニズムだ。
今日紹介するベルリンのマックスプランク感染生物学研究所からの論文はバクテリア同士のQSシステムがホスト側でも感知され、これを用いて細菌に対する防御反応を用意するという可能性を示した面白い研究で12月20日号のScienceに掲載された。タイトルは「Host monitoring of quorum sensing during Pseudomonas aeruginosa infection (緑膿菌感染時のホストによるクオラムセンシングのモニタリング)」だ。
研究ではQSの分子メカニズムについて研究が進んでいる緑膿菌を用いて、バクテリア間のコミュニケーションに使われるQS分子が、ホストの細胞でも検知できるか、またどのような作用を及ぼすかを調べている。さらに、これまでの研究から、QS分子を検知するホスト側の分子は、ダイオキシンの作用を媒介することでも有名な、本来は異物の代謝系を活性化させるマスター分子、Aryl Hydrocarbon Receptor(AhR)であると仮説を立てて研究している。
緑膿菌は細胞密度に応じて異なるQS分子を分泌し、自らの増殖を調節することが知られている。この増殖初期、中期、後期の上清をAhRレポーターを発現した培養細胞株に加えると、初期では抑制が、後期になるに従って活性化が起こることがわかる。また、AhR により活性化される代表的遺伝子であるCyp1の発現も後期の上清、およびそこから抽出される後期のQS分子(1HPで代表させる)で誘導される。一方初期上清中の分子(HSLで代表させる)は、AhR の機能を阻害することがわかった。また、1HP(後期)やHSL(初期)を細胞に加えて誘導される分子を調べると、1HPでは異物の代謝システムのみならず、炎症誘導性のサイトカインが上昇し、一方HSLではそれが抑制されることを示している。
以上の結果から、ホスト側の細胞も、バクテリア同士のコミュニケーションシステムを感知することでバクテリア数を感知することができ、細菌数が少ない時は防御システムを抑え共生を目指し、細胞が多くなると防御システムを動員して排除を目指すことがわかった。
最後に生きた生物でこの機能が働いているのか確かめるために、まずゼブラフィッシュを培養上清に晒す実験を行い、培養細胞と同じようにAhRが初期、後期のQS分子を分別できることを示している。そして最後に、マウスの肺に緑膿菌を感染させる実験を行い、後期増殖期の細菌ほど排除される効率が高まり、これにAhRが関わること、さらに増殖初期の細菌は除去されにくいことを示している。
他にも、除去に関わる炎症分子の発現なども調べているが、AhRが細菌の状態を検出して、適切に対応するためのセンサーとして、実際の生体内で働いていることが証明されたと思う。
AhRはほとんどの動物に存在し、様々な化合物と結合して異物を認識することがわかっており、おそらく他の細菌の検出にも重要な役割を演じている可能性がある。これがわかると、慢性感染症の新しい治療が可能になるかもしれない。
2019年12月30日
タイトルを見て「タミフルがインフルエンザに効くかどうかを今更調べることもないはずだ」と驚かれる人も多いだろう。
調べたわけではないが、おそらくインフルエンザウイルスが検出されると、我が国では患者さんの状態に関わらずタミフルなど、抗インフルエンザ薬が投与されのが普通で、実際テレビメディアでも処方が当たり前のこととして報道されている。
しかし、例えば米国の疾病コントロールセンターのガイドラインで投与を推奨している対象は、1)入院が必要な重症患者、2)2歳未満の幼児、3)65歳以上の高齢者、4)妊婦、5)様々な合併症のある患者、6)免疫抑制中の患者、などに抗インフルエンザ薬投与は限られ、それ以外は様子をみて重症化しそうなら投与とされている。しかし、様子を見ているうちに多くは軽快し、また悪化を予測するのは難しいため、欧米では結局抗インフルエンザ薬を投与しないことの方が多いらしい。
タミフル治験の論文を集めて効果を計算したら、健康人の場合インフルエンザからの回復が17.8時間早くなるという推定があるが、欧米ではこの程度の差なら吐き気などの副作用の方が問題で、わざわざ高い薬を飲む必要がないと判断されるが、我が国では「どの程度の差でも効果がある」ならともかく使おうということになっている。
今日紹介する治験論文は、現在はほとんど抗インフルエンザ薬が処方されない欧米で、タミフルの効果をもう一度確かめようとした研究といえる。個人的には、何を今更という気がするが、タミフルもすでにジェネリックの安価な薬剤も利用できるので、もっと気軽に使ったらどうかという考えが背景にあるのかもしれない。
治験だが、インフルエンザのシーズンに病院を訪問した患者さんを無作為にタミフル投与群と非投与群にわけ、その中でインフルエンザウイルスの感染が確認された患者さんについて、回復までの時間や、逆に症状の悪化による再診や入院などの経過を調べている。
様々な項目について調査が行われており、一般の人にはわかりにくいので要点だけを紹介すると次のようになる。
全患者さんで見たとき、インフルエンザで生活が制限される期間は平均6.5日だが、タミフルを処方した群では平均1.02日は回復が早まる。 高齢者や基礎疾患により悪化のリスクの高い患者さんでは、回復までの日数が2−3日早まる。 タミフルでは吐き気や嘔吐を訴える人の数が増える。 以上が結果で、はっきり言ってこれまでの研究とほぼ同じで、タミフルは間違いなく効果がある。特に健康に問題ある患者さんには投与が望ましいという結果だ。結局判断はこの効果の程度が見合うだけのコストパーフォーマンスがあるかどうかの評価の問題になる。
この治験グループは、「使うべきだと強く宣伝はできないが、1日でも早く治りたいのが患者さんなので、幼児や高齢者、さらには悪化するリスクが少しでもある患者さんは当然のこと、健康人が感染した場合も使ってもいいのではないか」と結論している。言い換えると「値段も安くなったことだし、もう少し使ってもいいよ」が結論だ。
インフルエンザと抗インフルエンザ薬の統計を見ると、病気に対する我が国と欧米の間の大きな差を感じるが、一般の皆さんはどう考えられるのか、ぜひ知りたいところだ。
2019年12月30日
IL-17というと炎症の親玉サイトカインだと長く思い込んでいたが、腸管ではバリアー機能を高めて、バクテリアの侵入を防ぐ良い働きをするTh17細胞があることが最近明らかにされてきた。すなわちIL-17を分泌するT細胞にも自己免疫病などの炎症に関わる悪いTh17と腸管を守るTh17の2種類が存在することになる。
今日紹介するニューヨーク大学Littman研からの論文は、炎症性腸炎や脳炎をおこす炎症型Th17が誘導される仕組みを探った研究で1月9日号のCellに掲載されている。タイトルは「Serum Amyloid A Proteins Induce Pathogenic Th17 Cells and Promote
Inflammatory Disease (血清アミロイドA タンパク質は病原性のTh17細胞を誘導し炎症性の疾患を進行させる)」だ。
これまで腸管で局所的に分泌される血清アミロイド(SAA)はTGFβ依存的な良いTh17誘導を高めることが知られていた。この研究では、SAAをTGFβ非存在下で培養すると、直接T細胞に働き、試験管内でがTh17を誘導できるという発見から始まっている。そして、誘導されてきたTh17は、驚くことにIL23受容体を発現した炎症型のTh17であることを確認する。
この発見がこの研究のハイライトで、あとはSAAが本当に自己免疫性の炎症に関わるかどうか、ヒトやマウスモデルで調べている。
まず炎症性腸疾患で調べると、ヒトでもマウスでもSAAは炎症局所で強く発現が誘導されている。そして、炎症性腸炎を誘導する実験系でしらべたとき、SAAノックアウトマウスでは炎症が誘導できないことを示している。
次に他の自己免疫疾患でもSAAが関わっているのか調べるため、マウスをミエリンタンパク質で免疫して炎症性脳炎を誘導する実験を行なっている。ミエリンタンパク質で免疫すると、肝臓からSAA1/SAA2が強く誘導され、また脳局所でもSAA3が誘導される。様々なノックアウトマウスで脳炎を誘導すると、肝臓由来の血中SAAも脳に発現している局所SAAも両方脳炎に関わることを示している。
そして最後に、試験管内で誘導したミエリン特異的Th17細胞をマウスに移植する実験を行い、肝臓で作られるSAAが炎症型のTh17細胞の誘導を行い、それがSAAが誘導された局所に到達すると、そこで炎症を誘導することを明らかにしている。
実験が複雑で読むのに苦労する論文だが、SAAのシグナルを明らかにすることで、今後新しい免疫性の炎症を制御する可能性を強く示唆する重要な結果で、是非今後の発展を期待したい。
2019年12月29日
このコーナーはあくまでも論文紹介で、私の考えをただ表明するのは控えている。従って、何か急に伝えたいことが出ると、無理にこれまで読んだ論文の中からその話題に近い論文を引き出して紹介することになる。今日紹介する上海交通大学からの論文は先月目にしたが、なんでも適当にやって論文にするというスタイルなので、取り上げなかった。タイトルは「Dysregulation
of neuron differentiation in an autistic savant with exceptional memory (類まれな記憶力を持つASD的サバンの子供に見られる神経分化異常)」だ。
複雑な精神や知能に関わる神経ネットワーク状態について、iPSから神経細胞が作れたとしても、試験管内で再構成することは当分できないと思う。しかし、必ず細胞レベルで何らかの異常があるはずだと、患者さんからiPS作成して調べることは、以前「自閉症の科学23」で紹介したように(chttps://aasj.jp/news/autism-science/11091 )、重要な研究分野だと思っている。
この上海交通大学からの研究は、その意味では別に問題はない。例えば見た景色を詳細に至るまで頭に焼き付けることができるサバンの子供は、ASDの中に分類されるが、特異な能力を持っている。したがって、ASDとサバンの遺伝的、細胞学的違いを調べることは重要だ。そこでこの研究では、一人のサバンの子供の尿から細胞を取り出し、iPSを作成している。尿からと聞いて驚く人もいると思うが、これ自体は新規性はない。
結果だが、サバンのiPSから誘導された神経細胞は、ASDでは一般的に発現が低下しているPax6,TBR1,Foxp2(これらは学習や知能に関わる遺伝子として知られている)が、逆に上昇していることを発見している。また神経細胞学的には、細胞体が大きく、スパインの数は低下、しかしスパイン自体はよく発達している。この結果生理学的には、自然興奮が高まっているという結果だ。
一見面白い結果なのだが、結局同じ条件で作成したASDやサバンのコントロールが全くなく、結局アドバルーンを上げただけで、紹介するには値しないと考えて、そのままにしていた。
この話をまたわざわざ持ち出したのは、先日、森美術館で開催されている展覧会、「未来と芸術展:AI、ロボット、都市、生命――人は明日どう生きるのか」の展示の中に、なんとiPSを用いたメディアアートを発見したからだ。(図)
中央にiPS由来神経細胞培養器を設置したメディアアート cellF: 説明は以下のパネル参照。 cellFについて説明したパネル この展覧会にはもちろんゲノムや再生といった、メディアアートの格好の題材が目白押しだ。科学者としての個人的印象を述べると、科学が積み重ねてきた結果を、科学者の論理的アプローチを無視して、芸術家の自由な思い込み(あるいは自由な解釈)に基づいて提示し直し、未来を予想するという作品だ。すなわち、生命という制限にとらわれずに、生命を考えている。
そしてその中にiPS由来の脳のミニ組織を、外界と電極でつないで、音楽と直接連結し、音楽に対応して興奮し、音楽を一緒に演奏するcellFという作品を発見した(図)。この作品の内容は作品説明のパネルを見て欲しいが、専門家から見れば、脳の表象について全くわかっていないの一言で終わるだろう。
しかし全くあり得ない非現実を、現実にするメディアアートに私は共感する。そしてiPSまで文化にしてしまうこの遊びが、昨今のiPSを巡る我が国の議論に欠けていることだと実感した。
2019年12月28日
自閉症スペクトラム(ASD)児が発熱すると一過性に、症状(特に社会性に関わる症状)が改善することが報告されていた。おそらく経験されている両親や医師の方には「そうそう!」と頷かれるかもしれないが、私も含めて多くの人は、本当にそんなことがあるのか疑問に思うのが普通だ。
ところが、コーネル大学、コロンビア大学、そしてカリフォルニア大学サンフランシスコ校が集まって、本当にこのような現象があるのかシモン財団データベースにに登録しているASD児について調べ、確かに発熱でASDの症状が一過性に改善する事を示した研究が昨年1月、Autism Researchに掲載された(Autism Res 2018, 11:175-184)。
研究では4歳から18歳までのASD児を持つ2156家族に「ASDの症状が発熱で改善したと思ったことはあるか?」と質問したところ、驚くことに362家族(17%)が「確かに改善したことがある」と答えた。
どのような症状が改善したのかさらに聞いたところ、コミュニケーション能力と答えた人が166人、気分や行動と答えた両親が199人に上った。
次に、発熱の影響があったASD児と影響のなかったASD児を比べ、症状の違いを調べると、完全に有意差があるとは言えないものの、症状の重いASDほど改善が見られる傾向が見られた。例えば、適応性が悪く、行動異常が強い子供ほど発熱による症状の改善が見られる。一方、遺伝的な影響についても調べているが、特別の関連は認めていない。
以上の結果から、確かに発熱がASD児の症状の改善につながることがあること、そして症状の重い児童ほど発熱により症状改善が見られる確率が高いことが確認された。
一過性でも症状改善が見られるというこの結果は、治療法開発という観点からは勇気付けられる結果だ。ただ、この研究結果だけでは、なかなか糸口はつかめなかった。
ところが先週、マサチューセッツ工科大学の研究グループが、ASDの発熱と社会行動を研究できるモデル動物システムを開発し、減少の背景にあるメカニズムを探った論文を発表した(Reed et al, IL-17a promotes sociability in mouse models of neurodevelopmental disorders (神経発生異常モデルマウスの社会性をIL17aが促進する), Nature, 2019: https://doi.org/10.1038/s41586-019-1843-6 )。
発熱を誘導するといった研究を人間で行うことはできない。そこで、モデル動物が必要になる。このグループは、何種類かの遺伝的ASDモデルマウス(一つの遺伝子の変異によりASD症状を示すマウス)を使っている。マウスで社会行動を調べる様々な方法が開発されているが(例えば他のマウスと一緒にいる時間を測る)、遺伝的な変異だけでは症状がはっきりしないことが多い。そこで、このグループは妊娠時に炎症が起こるとASDが発症しやすいという現象を動物モデルで再現する方法を組み合わせ、背景の遺伝的要因は問わず、ほとんどのASDモデルで社会行動の低下を誘導することに成功している。
こうしてできた社会行動低下モデルマウスを用いて、次は発熱の影響を調べることになる。発熱誘導には感染症と同じ状態を誘導する方法と、発熱中枢を刺激する方法があるが、この研究ではまず感染で発熱する状態を再現するため、バクテリアの発熱誘導物質をマウスに投与する実験を行なっている。結果は期待通りで、LPSと呼ばれるバクテリア膜のポリサッカライドを投与された自閉症モデルマウスで社会性の回復が見られる。ところが、神経刺激のみで発熱だけを誘導すると、全く回復は見られない。すなわち発熱というより、炎症が社会性の回復に関わることが示された。
ここまでわかると、炎症時に分泌され社会性を回復させる分子を特定するのは現在の技術があれば難しくない。様々な探索を行い、最もパワフルな炎症物質の一つIL17aを注射することで社会性が回復することを示している。
結果は以上だが、もう少しわかりやすいようにこの研究の意義をまとめてみると、
人間で見つかった現象(発熱すると社会性が改善する場合がある)を研究するための動物モデルが見つかった。 IL-17は強い炎症性サイトカインなのでむやみに注射するわけにはいかないが、脳だけでこの回路を刺激する方法がわかれば、少なくとも社会性については改善できる可能性がわかる。 IL-17a受容体陽性神経細胞という細胞レベルのヒントが見つかったことで、新しい介入手段の開発が期待できる。 研究というと、基礎から始めて、臨床に進むと思いがちだが、このように臨床的観察から始めて、動物に進むことも重要で、今後も基礎と臨床がうまく連携して、ASDの社会性を回復させる方法の開発を期待する。
2019年12月28日
2型糖尿病に対して、インシュリン以外に様々な薬剤が開発されているが、なかでもメトフォルミンは世界中で最も処方されている薬剤だとおもう。この理由として、1000mgで40円程度と、糖を抑えるというサプリメントやドリンクと比べても圧倒的に安いこともあるが、よくこんな薬があったと思えるほど、様々な経路を絶妙に調整できることがわかっている。そのため、糖尿病ではない人について、老化を始め様々な病気に対する予防効果を調べるコホート研究が数多く走っている。最近Nature Reviews Endocrinologyにいい総説が発表されていたので、是非ジャーナルクラブでとりあげてみたいと思う。
今日紹介する英国ケンブリッジの代謝科学研究所からの論文は、メトフォルミンがなんと食欲を抑える効果もあることを示した論文で12月19日 Nature にオンライン出版された。タイトルは「GDF15 mediates the effects of metformin on body weight and energy balance (GDF15はメトフォルミンの体重とエネルギーバランスに対する効果を媒介している)」だ。
さて最近の疫学研究によりメトフォルミン服用がGDF15の血中濃度を上昇されることが指摘された。GDF15はストレスに対して分泌されるペプチドホルモンで、後脳の神経細胞に発現しており、レベルが上がると食欲が落ちることがわかっている。
そこでこのグループは、糖尿病はないが心臓発作を起こした人に対するメトフォルミンの効果を確かめるコホート研究の人たちについてGDF15のレベルを調べ、全ての人で2−4倍GDF15が上昇していることを確認する。
この結果は、メトフォルミンがグルコース代謝全体を改善させるだけでなく、食欲も抑えて体重を減らす効果があることを示している。これについては、人間で実験することは難しいので、GDF15ノックアウトマウスを用いてメトフォルミンの体重抑制効果が見られるかどうか調べ、メトフォルミンがGDF15を介して食欲を抑え、体重抑制することを示している。
一方、インシュリン感受性などグルコース代謝についてはGDF15が存在しなくても同じようにメトフォルミンの効果が見られることから、食欲抑制作用は代謝とは独立していることを示している。
最後に、メトフォルミンによってGDF15が誘導される細胞を探索し、普通考えられている筋肉ではなく、腸管上皮がCHOPと呼ばれるエンハンサー結合タンパクを介してGDFを分泌しているのではないかと結論している。
2019年12月27日
ガンの変異を特定して、その機能を抑制する分子標的薬で治療することは、最も合理的なガン治療だと考えられている。事実、最も成功した慢性骨髄性白血病に対する分子標的薬グリベックは、この病気の制圧にほぼ成功したと言える。しかし、その後多くの分子標的薬治療が開発され、様々なガンに使われるようになって、薬剤耐性のがん細胞の出現を防ぐことが難しいことがわかってきた。
このような耐性が生まれるメカニズムだが、ガンが発生し大きくなる過程で、低い確率ではあっても様々な突然変異が蓄積されており、治療によってその中から耐性株が選ばれると考えられている。ところが今日紹介するイタリア・トリノ大学からの論文は分子標的薬に適応してガン細胞が変異が起こりやすい体勢にシフトする可能性を示唆する研究で12月20日号のScienceに掲載された。タイトルは「Adaptive mutability of colorectal cancers in response to targeted therapies (分子標的治療に対する大腸ガンの適応的変異)」だ。
この研究では分子標的薬で処理することで、ガン細胞が変異を蓄積しやすくなる性質を獲得するとする仮説に基づいて研究を進めている。まず大腸ガン細胞株にEGFに対する分子標的薬を加えることで、複製時のミスマッチ修復に関わる酵素(MMR)群の発現が軒並み低下していることを確認する。また、細胞内の修復機能を調べ、修復が低下していることを示している。
さらに念のいったことに、DNAの複製に関わるポリメラーゼも、信頼性の高いポリメラーゼから、突然変異の起こりやすいポリメラーゼにシフトすることも明らかにしている。すなわち、すべての面でDNAに様々な変異が起こりやすいように変化している。生物を目的論で考えることが間違っていることをわかっていても、ここまで見事に協調していると目的論的に考えてしまう。
残念ながら、分子標的薬処理によりなぜこれほど見事な変異しやすい細胞へのシフトが起こるのかは明らかになっていないが、この結果間違いなく変異が導入されやすくなることは様々な方法で示している。そして最後に、大腸ガンや膵臓癌細胞株を用いて、EGFに対する分子標的薬によって染色体不安定性が誘導されることを、マイクロサテライト領域の解析から確認している。
結果は以上で、実際の臨床サンプルでの確認が残されてはいるが、ガンが治療に対応して変異しやすい不安定な体質に変化し、これにより標的薬に対する耐性株を生まれやすくしている可能性が明らかになった。もしこの結果が正しければ、実際の治療にも様々なヒントが得られると思う。最も重要なのは、修復やDNA 複製の信頼度が落ちることだが、確かにこれにより耐性株が出やすくなるが、逆にガン細胞自体はDNAダメージを起こす薬剤や放射線に対する抵抗性を失うと考えられる。したがって、相同組み換えを抑える薬剤や、放射線療法の併用により、よりガンをコントロールできる可能性がある。うまくいけば、分子標的治療をより根治的な治療へと変えることすら可能になると思う。
2019年12月26日
昨日パイエル板の研究について続けて紹介すると予告したが、これは私の思い違いで、実際にはリンパ節を中心に記憶B細胞の出現を調べたロックフェラー大学からの論文で、タイトルは「Restricted Clonality and Limited Germinal Center Reentry Characterize Memory B Cell Reactivation by Boosting (ブーストによる再刺激により出現する記憶B細胞はクローン数が制限され、胚中心への再移動も制限されている)」だ。
はっきり言って極めてマニアックな論文だが、私のドイツ留学中から繰り返して議論が続いてきた、免疫記憶はどう形成されるかに関わる研究で、これが本当に理解できると、誰にでも効果があるワクチン設計をより論理的に進めることができる。
この分野の研究はあまりフォローしていないが、この論文を読むまで私の頭にあった記憶B細胞のイメージは、最初形成されたB細胞レパートリーから特異性の高いB細胞が選ばれ、この細胞はリンパ組織の胚中心で長期間生存し、次の抗原の侵入には、すでに抗原を記憶したB細胞で対応するというものだった。
この研究では同じ問題に、遺伝的ラベリングによる細胞の追跡や、single cellテクノロジーなどを駆使してチャレンジしている。
その結果まず明らかになったのは、最初の免疫で活性化されたB細胞のレパートリーは、次の抗原注射(ブーストと呼ぶ)で活性化されたいわゆる記憶B細胞とはほとんど重なっていないことだ。もちろん、一部のクローンが長期間働き記憶を形成している場合も見られるが、極めて稀だ。また、ブーストにより発生したクローンも数は限定されており、記憶B細胞として反応するクローンは少ないというこれまでの通説に合致はしているが、これが最初の免疫で作られたからではなく、ブーストのたびに新たにクローンの選択をしていることになる。
以外な結果なので、本当かどうか、最初反応したB細胞をラベルする実験や、1回目の免疫をしたマウスと、免疫をしていないマウスの血管を結合させ、リンパ球が両方のマウスに移動できるようにして調べると、ブーストによって現れるB細胞のほとんどは、最初の免疫で刺激された細胞ではないことが明らかになった。また、最初の免疫に反応したからと言って、胚中心で増殖する活性が高いわけではないこともはっきりし、一部の長期記憶を除いて、抗原ブーストでも新たなB細胞が刺激されることがわかった。
これを確認するため、最初の抗原に反応したB細胞をラベルし、2次反応で活性化されるクローンと系統解析を綿密に行なっているが、詳細はいいだろう。1次免疫とは異なるレパートリーからリクルートされるとはいえ、突然変異はちゃんと蓄積し、抗原に対する親和性も上がっている。
以上の結果は、免疫を繰り返すことでクローン数が限定され、親和性が上昇していくという単純な概念を覆し、「こんな場当たり的な対応で免疫大丈夫か?」と思ってしまう。しかしよく考えると、T細胞の方はしっかりと記憶ができているし、あまり選択してしまうと、抗原のちょっとした変化に対応できなくなる危険があり、それを回避できるという点も重要だ。さらに、インフルエンザワクチンなど、様々なウイルスにさらされているのに、記憶がうまくできないのかも説明できる。
もちろんこのまま鵜呑みにするのはだめで、例えば一生うまく続くワクチンと、そうでないワクチンについて人でのレパートリー解析などを通じて確認が必要だろう。いずれにせよ、このような例があることを念頭に、新しい発想でワクチン開発が大事だと思う。
2019年12月25日
現役時代、多くの教室メンバーの人たちと取り組んだリンパ組織パイエル板についての論文が2報も1月9日発行予定のCellに掲載されていたので、今日から連続して紹介することにした。
まず最初はハーバード大学からの論文で、脊髄後根節神経の一部がパイエル板に侵害受容器の軸索を伸ばし、腸内での細菌感染に重要な役割を示した論文で。タイトルは「Gut-Innervating Nociceptor Neurons Regulate Peyer’s Patch Microfold Cells and SFB Levels to Mediate Salmonella Host Defense (腸管に侵害受容体神経はパイエル板のM細胞とセグメント細菌のレベルを調節することでサルモネラに対するホストの防御を媒介している)」だ。
これまで光遺伝学を用いた研究で、腸管に投射している迷走神経などを刺激することで免疫機能を変化させられることが知られていた。この研究はその中の痛みや機械刺激に反応する侵害受容器を持つ神経細胞だけ遺伝的に欠損させたマウスを作成し、サルモネラ菌の腸内での増殖への影響を調べ、侵害受容体神経が欠損するとサルモネラ菌の腸や脾臓、肝臓での増殖が高まることを発見する。
さらに腸内の侵害受容体神経は迷走神経と後根節神経があるが、後根節細胞を除去した時のみサルモネラ菌の増殖が見られることを確認し、後根節神経細胞が何らかのメカニズムで細菌感染防御に関わっていると結論する。
次にこのメカニズムの探索を2方向から行なっている。一つは、後根節神経除去により起こる腸内細菌叢の変化を調べ、セグメント細菌と呼ばれる細菌が欠損していることを発見する。セグメント細菌は通常パイエル板を覆う上皮に強い局在を示しており、またパイエル板はサルモネラ菌の体内への入り口として考えられているので、セグメント細菌はパイエル板からの細菌侵入を防御していると考えられる。これを確認するため、セグメント細菌を強制的に後根節神経細胞除去マウスに注入してサルモネラ感染を調べると、完全ではないが防御が回復することから、セグメント細菌はパイエル板からのサルモネラ菌侵入を抑えていることが明らかになった。
もう一つの方向は、神経除去によるパイエル板組織構造への直接的影響の探索だが、サルモネラ菌はパイエル板にある特殊上皮M細胞から侵入することがわかっているので、M細胞に焦点を当てて調べると、神経除去によりM細胞の数が上昇している、すなわちサルモネラ菌の入り口が増えていることが明らかになった。
これを確認するため、M細胞の発生に必要なRANKL分子を抑制して、神経除去マウスのM細胞の密度を下げてやると、サルモネラ菌の侵入が抑えられることを確認している。
最後に後根節神経細胞が分泌し、パイエル板M細胞発生に関わる分子を探索し、CGRPと呼ばれるニューロペプチドが、M細胞発生とセグメント細菌維持に重要な役割を持つことを明らかにしている。
結果は以上で、CGRP、M細胞分化、セグメント細菌維持、の3つの柱の間の関係についてはまだはっきりしない点も多いが、役者が出揃ったことから、解明は時間の問題だと思う。特に、リンパ球ができないマウス(それでもパイエル板原器はできる)や、無菌マウスを用いた研究が期待される。ひょっとしたら、パイエル板の場所決めも神経が関わるかもしれない。
2019年12月24日
食べ過ぎ、飲み過ぎになりがちのクリスマスイヴにふさわしい話題と思って、カロリーや肥満の論文を物色していたところ、カリフォルニア大学サンディエゴ校とソーク研究所から、カロリー制限の代わりに、食事時間の調節で肥満と戦うと言う論文が発表されていたので紹介することにした。タイトルは「Ten-Hour Time-Restricted Eating Reduces Weight, Blood Pressure, and Atherogenic Lipids in Patients with Metabolic Syndrome (食事をとるのを10時間に制限すると、メタボリックシンドロームの患者さんの体重、血圧、動脈硬化性脂質が低下する)」だ。
以前も紹介したが(https://aasj.jp/news/watch/8469 )空腹時間を伸ばすと、同じカロリーを取っていてもメタボリックシンドロームを改善できることが知られている。ただこの時紹介したような厳重な食事管理を家庭ですることは難しい。
今日紹介する研究は、食事を10時間以内に全て済ませると言うプログラムを、個人に合わせた自由な方法で実現できるように、スマフォのアプリを設計し、このスマフォに腕時計を通して活動記録や脈拍などの連続記録、食事時間と食べた食物の写真を含むレコードなどが集められるようにして、最初2週間はこれまでどおり、その後12週間はできるだけ食事を10時間以内にとる努力をしてもらって、プログラムの開始時、終了時のメタボリックシンドローム指標を調べている。
特に対照群は設定せず、プログラム前後を比べるだけの観察研究。しかし、意識しないと10時間以内というのは簡単でなく、実際50%の人が15時間以上の時間帯で食事をとっており、12時間以内となるとたった10%の人しかいないことが知られている。
まずこのアプリをベースにした方法でどのぐらい目標を達成できるか調べると、参加したほとんどの人が時間制限に成功し、開始前の15.13時間から10.78時間に制限することに成功している。このことは、12週間とはいえアプリをうまく利用すると、10時間以内に食事をとることは可能であることを示している。
このために実際に行われたのは、朝食時間を遅らせること、夕食を早めることで、基本的に朝を抜いて時間を制限するという方法は取られなかった。
さて結果だが、まずこの方法でカロリー摂取量も低下することがわかる。おそらく間食なども減るからだろう。そして体重、BMI、体脂肪率、ウエストサイズなど、大きくはないが優位に低下した。
また、血圧だけでなく、LDL-Cを含むコレステロールはおおきく低下している。
空腹時血糖やインシュリンなどは低下の傾向が見られるが、優位差はみられていない。ただ、血糖の上下変化が大きく低下しており、インシュリン抵抗性が改善されていることがよくわかる。
結果は以上で、特にそれまでのメタボリックシンドロームがすっかり改善した人の話も出てくるが、紹介はいいだろう。食事の時間をなんとか10時間以内に収めることで、食べながら健康になるという話で、少し工夫してやってみてもいいかなと思う