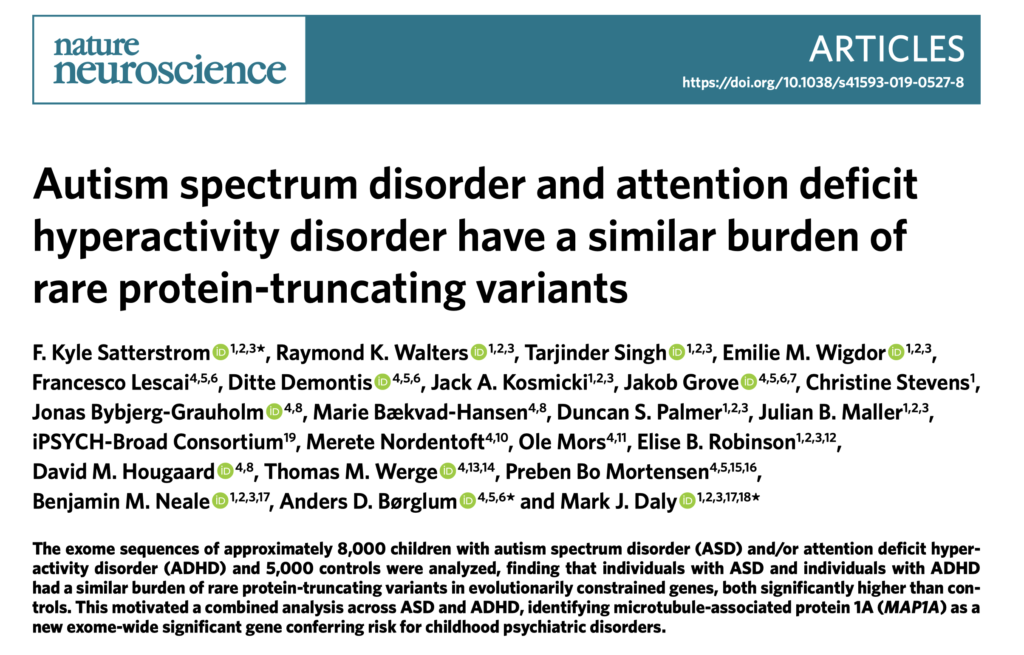2019年12月15日
全ゲノムレベルで病気と相関する遺伝子多型を調べるGWAS研究は、最近新たなブームを迎えている。もちろんこの分野の歴史は長く、2000年を境に多くの論文が発表され、疾患ゲノム研究として第一次ブームを作った。このブームが再燃した最大の理由は、ゲノム検査を受けた人の数が飛躍的に増大し、疾患ゲノムもこれまでより1桁も2桁も違う数の対象を使って行うことができるようになったからだ。このおかげで、多くの遺伝子が複雑に絡まる病気のゲノムもより高い精度でわかるようになってきた。この典型が統合失調症やうつ病などの精神障害だ。
今日紹介するハーバード大学を中心とするコンソーシアムからの論文は、全部で23万人を超す8種類の精神障害のゲノム検査データから、各障害の共通性を調べた論文で12月12日号のCellに掲載された。タイトルは「Genomic Relationships, Novel Loci, and Pleiotropic Mechanisms across Eight Psychiatric Disorders (8種類の精神障害をまたぐゲノムの関連性、新しい相関領域、そして多面的メカニズム)」だ。これまでも精神障害のゲノム研究は行われていたが、最も大きな調査は3万人規模だった。今回は、統合失調症、双極性障害、うつ病、自閉症スペクトラム(ADS)、注意力欠損/多動(AHD)、強迫神経症、神経性無食欲症、そしてトゥレット症候群の8種類のゲノムデータを集め、それぞれの疾患と相関が認められ多型について、疾患同士で共通性がないかを確かめている。結果は膨大なので、私が面白いと思った点を箇条書きにまとめることにした。
それぞれの疾患と強く相関を示す多型が136種類特定できるが、このうち101種類の遺伝子は複数の精神障害共通に相関が見られた。 ゲノムの関連性から各障害の関連性を見ると、統合失調症と双極性障害の間、強迫神経症と神経性無食欲症のあいだ、そしてうつ病とADS、ADHDの間で強い関連が認められた。 相関するゲノムから、それぞれの障害は脅迫的行動障害、ムード障害、そして発生障害に分けられる。 このモデルで見ると、うつ病はムード障害型と、発生障害型の異なる2種類の型に分けることができる。 全ての障害と相関する多型としてネトリン受容体DCCが特定された。この分子は神経伸長に関わる最も重要な分子。 疾患により逆の働きを示す遺伝子多型が特定され、双極性障害とうつ病が違うモーメントを持つ病気であることがわかった。 神経発生に関わる遺伝子の多型が障害発症に多く関わっている。 多くの障害と相関する多型が存在する遺伝子のほぼ全ては神経細胞、特に前頭皮質、前頭前野皮質に発現がみられる。 一つの障害に強く相関する遺伝子の多くは、遺伝子発現の時期が強く制限されているが、多くの障害と相関する多面的遺伝子の発現は生涯にわたって発現するものが多い。 などなどだ。それぞれの障害同士の関連など、なるほどと思うことも多く、遺伝子の種類も100種類程度なので、興味のある人は一つ一つの遺伝子を眺めながら、それぞれの障害を考えることで、いろんなヒントが得られるのではないだろうか。しかし、ゲノム検査の数だけでなく、多くの情報処理技術が開発されたことも、現在のブームを生み出していることがよくわかった。
2019年12月14日
現在大腸癌を始めいくつかの上皮性ガンの分子標的薬として広く利用されているのがEGFに対する抗体だろう。根治は難しくとも、生存期間の延長が可能であることは確認されており、BRAFなどの下流の遺伝子変異が存在する場合の効果は高いことが知られている。
ただこの治療の最大の問題点は、抗体治療を受けている患者さんの多くに皮膚のアトピー様の炎症がおこることで、その結果治療を中止せざるを得ないことも多い。EGFはもちろんケラチノサイトを刺激するので、おそらく炎症性サイトカインの分泌を誘導するのだろうと考えられているが、これがEGF の直接作用か間接作用かなど、その原因ははっきり特定されていない。
今日紹介するウイーン医科大学からの論文はマウスを用いてこのメカニズムに迫った研究で12月11日号のScience
Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Hair eruption
initiates and commensal skin microbiota aggravate adverse events of anti-EGFR
therapy (抗EGF受容体抗体治療の皮膚副作用は、毛の生え出しによりトリガーされ、常在細菌により増悪される)」だ。
この研究では皮膚でのEGF機能阻害が最も強く現れるのが新生児期、毛根から最初の毛が現れる(hair eruption)時期であることに着目し、この時期にEGF抑制により起こる組織過程を丹念に調べ、毛根の幹細胞の増殖がEGF 阻害により抑制されることで、毛根から起こる皮膚のバリアー機能の修復不全が起こり、これが最初の炎症の原因となることを突き止める。これは新生児マウスに限らず、大人でも毛を剥がして毛根の再生を促したときに、抗EGF受容体抗体が皮膚の炎症を誘導することを示している。
このようにバリアー機能が壊れることで、緑膿菌のような常在菌が侵入しやすくなり、感染による炎症の増悪が起こるが、決して感染が最初の引き金ではない。あくまでもEGFの機能が抑えられ、バリアー機能が壊れること自体が、ケモカインや炎症物質の局所での発現を誘導し、TH2タイプの炎症がはじまることを確認している。その後感染が始まると、今度はTH17タイプの炎症が加わってくる。
この最初のシグナルがEGFシグナルカスケード抑制であることは、EGF下流のシグナルを遺伝子導入で活性化してやると、この炎症は抑制できることでしめしている。また、EGFの代わりにFGF7 を用いても、炎症を止める効果があることも示している。
最後に、皮膚癌で抗EGF受容体抗体治療している患者さんの皮膚サンプルを調べ、バリアーが壊れているのと同時に、ほぼアトピーと同じようなTH2タイプの炎症が起こっていることを確認している。
以上が結果だが、この研究から、
皮膚副作用に対して抗菌剤は2次的感染を抑制する意味で効果がある。 皮膚炎症が始まったらFGF7などの局所塗布により炎症を止めることが可能かもしれない。 一方、病像がアトピーに酷似しているので、アトピーをEGF塗布により治療することができるかも知れない。 という2つの重要なメッセージが得られているような気がする。驚くほどの研究とは思えないが、地道にしかも臨床に役立つ情報が得られたと言える。
2019年12月13日
抗体は細胞の中では働かず、また全身に投与した場合中枢神経への浸透は脳血管関門により阻害されているというのが常識だと思う。もちろん、それでも
抗Aβ抗体のように脳内の病理を変化させるために使われる抗体もあるが、それでもほんの一部しか脳へ到達しないとされているし、ましてや細胞内へ到達するなどとは誰も考えなかった。
今日紹介するフロリダ大学からの論文はこの常識の全てをひっくり返す驚くべき研究で2月19日号のNeuronに発行予定だ。タイトルは「Antibody Therapy Targeting RAN Proteins Rescues C9 ALS/FTD
Phenotypes in C9orf72 Mouse Model(C9orf72マウスの側索硬化症/前頭側頭型認知症をRANを標的にする抗体で治療する)」だ。
タイトルにあるC9orf72とは、遺伝的即作成硬化症(ALS)の中では最も多い遺伝的変異で、イントロンにあるGGGGCC という配列の数が増大して、センス、アンチセンス側からランダムに6種類のアミノ酸繰り返し配列(RAN ペプチド)が作られ、これにより神経変性が誘導される病気だ。
この研究ではまず、高齢者の末梢血から採取したB細胞の中から、センス側の2種類のペプチド(GAとGP)に対する抗体を作成し、これをマウスIgG2a/λクラスに変化して使っている。なぜ一般的なκにしないで、λにしたのか、よくわからないがここに秘密があるのかもしれない。
ます第一の驚きは、試験管内でRANが発現する細胞にこの抗体を加えると、何もしないで細胞内に入り、できたペプチドと結合し、さらにRANタンパク質の細胞内での処理を早める。もちろん普通抗体は細胞内に浸透しないが、これにはIgG2aに結合するFc受容体が絡んでいる。また、抗体が結合したペプチドは、抗体Fc部分を介してTRIM21ユビキチンリガーゼと結合し、プロテオソームやオートファジー経路で処理することを示している。これにより直接凝集したペプチドがプロテアソームに停留するのを防ぐことが可能になり、細胞死を防ぐことがわかった。
次に、この抗体をC9orf72からRANタンパク質を作るALSモデルマウスの腹腔に投与すると、驚くことに脳血管関門を通り、さらに抗原と結合していないフリーの抗体が神経細胞内に取り込まれて、RANタンパク質の除去を早め、神経症状を緩和することを示している。
特に毎週30mg/kgの抗体を打ち続けた実験でマウスの死亡率を強く抑制することを示しており、実際神経ないのRANペプチドの量が減っていることまで示して、臨床的にも応用可能であることを示している。
結果は以上で、現在根本治療のない患者さんにとったら素晴らしい結果だと言える。本来ならもっと騒がれてもいい研究結果ではないかと思う。ただ、私たちの常識に逆らうところがあるため、まだ疑う人も多いのかもしれない。ただ、これが正しいとすると、アルツハイマー病でのTauやあるいはレビー小体ができるシヌクレインに対しても同じ戦略が取れることになる。
とはいえ30mg/kgという濃度が必要な点、また完全に治るわけではない点も、抗体を細胞内で使うという離れ業の限界なのかもしれない。
2019年12月12日
1型糖尿病の発症時期を調べると、寒い時期に多いという統計があり、また多くのウイルス感染防御に関わる遺伝子多型と1型糖尿病の関連が報告されていることから、1型糖尿病がウイルス感染により引き金がひかれる自己免疫病ではないかと疑われてきた。
実際マウスモデルとはいえエンテロウイルスの一つコクサッキーウイルスBで誘導する1型糖尿病をワクチンで防げるという論文がDiabetological(61:476, 2017)に発表され、注目を集めた。というのも、コクサッキーウイルスは膵臓ベータ細胞に感染することが知られており、自己免疫病の引き金になると考えられるからだ。
では人間でも同じことが言えるのだろうか?これを確かめるためには、実際にウイルス感染と膵臓ベータ細胞に対する自己免疫病との相関を丹念に調べる必要がある。
今日紹介する論文は、ウイルスをはじめ、1型糖尿病(T1D)に関わる外的要因を調べるために組織された国際コホート研究チームによる研究で、膵島に対する自己免疫反応や、さらに進んだ1型糖尿病の発症と、便に排出されるウイルスの相関を調べた調査研究で12月号のNature Medicineに掲載された。タイトルは「Prospective virome analyses in young children at increased genetic
risk for type 1 diabetes (1型糖尿病の遺伝的リスクの高い児童の前向き網羅的ウイルス解析)」だ。
この研究は膵島に対する自己免疫反応、そしてそれが進展した1型糖尿病の発症を前向きに追跡するコホート研究だが、3ヶ月齢より毎月便のサンプルが採取され保存されている。こうして集めた膨大な数の便に存在する全DNAを解析し、その中に存在するウイルスDNAの種類をしらべることができる。このデータを、追跡期間自己免疫を発症した383人、T1Dを発症した112人、そして発症しなかったグループと比較している。
便に存在するウイルスの72%はバクテリアに感染するファージウイルスで、20%がヒトに感染するウイルスになる。一番多いのはアデノウイルス、ついでParechovirus、bocavirus、そして問題のエンテロウイルスB、エンテロウイルスAが続く。この中にコクサッキーウイルスが含まれる。
ではこれらのウイルス感染と膵島への自己免疫反応やT1Dとは相関するのか。膨大なデータなので、詳細を全て飛ばして結果だけをまとめると次のようになる。
ウイルス感染と自己免疫の相関を調べると、やはりエンテロウイルス感染が最も高い相関を示すが、アデノウイルスなどでも相関が見られる。 エンテロウイルスも長期間慢性的便に排出された場合に自己免疫発症リスクが高まる。 自己免疫反応で相関が見られたエンテロウイルス感染も、T1D発症時に限ると相関がはっきりしなくなる。 以上の結果は、エンテロウイルス(コクサッキーウイルスを含む)が原因となる自己免疫反応はまちがいなく存在するが、オッズ比で高くても3倍で、またT1Dとの相関は強くないことから、ウイルス感染だけで説明できるT1Dの比率は高くないことを示している。
エンテロウイルスだけでなく、同じ受容体を使って細胞に侵入するアデノウイルスと自己免疫反応の相関が認められたことは、ベータ細胞に慢性の感染が起こることが自己免疫の引き金になることを示している。従って、頻度は高くなくとも、コクサッキーBウイルスなどに対するワクチン開発は、医学にとって重要な課題だと言える。
これほど大規模なコホート研究が行われたことに敬意を評したい。
2019年12月11日
これまで人間で抗原に対する抗体反応を調べようと思うと、抗原に結合している抗体を分離して、アミノ酸配列を調べるか、最近では抗原に結合するB細胞を分離してそれが発現する抗体遺伝子を調べる方法がとられる。ただ、抗体にしても、B細胞にしても、精製したときにはどの程度強い抗原特異性があったのかは、一旦アミノ酸配列が決定されて、抗体を再構成してからでないとわからない。
今日紹介するバンダービルド大学からの論文は、この問題をバーコードをつけた抗原を用いることで一挙に解決した面白い方法で12月12日号のCellに掲載された。タイトルは「High-Throughput Mapping of B Cell Receptor Sequences to Antigen Specificity(B細胞の抗原受容体のハイスループット解析)」だ。
基本的には方法論の問題なので、その点のみ詳しく紹介する。
この方法では現在急速に普及している単一細胞の遺伝子解析技術を用いている。まず抗原に蛍光とDNAバーコードを結合させる。この抗原をB細胞集団と混合して、抗原に結合した細胞だけをまずセルソーターで精製する。こうして、抗原特異的B細胞に抗原特異性を示すバーコードをつけることができる。重要なのは、一つのB細胞に結合したバーコードの数が、抗原結合性を反映することで、後で反応が強いB細胞のデータだけを取り出すことができる。
ただこれだけでは、一個一個の細胞を識別することはできない。そこで、精製したB細胞を一個づつ油滴の中に包み込むとき、バーコードのついたビーズを一緒に入れることで、各細胞がバーコードラベルされる。
あとは、細胞を処理し、それぞれのバーコードと、免疫グロブリンA遺伝子の配列を決定すると、抗原特異性、抗原の結合程度に対応する免疫グロブリンA遺伝子の配列を決めることができる。
この方法がうまくいくか、エイズウイルスに長年感染して強い免疫反応を獲得している患者さんの血液を分析し、これまで他の方法で得られた結果に対応する、抗原特異的免疫グロブリン遺伝子配列を特定できること、さらにはこれまで発見されていない免疫グロブリン配列も多く発見できることを示している。
また、何種類もの抗原に対して同時に反応を調べることもできる。以上、要するに、うまく働くということで、今後様々なウイルスに対する免疫グロブリン遺伝子ライブラリーが作成できることがよくわかる。
今後、人間から直接モノクローナル抗体を作るという技術の基盤として使われると期待できる。ただ、個人的感触だが、免疫反応の解析という意味では、モノクローナル抗体作り以上の用途がひらけているように思う。抗原さえわかっておれば、人間の免疫反応を詳しく調べることができ、抗体遺伝子だけでなく、他の遺伝子発現も個々のB細胞で同時に調べることができる。新しい人間の免疫学がまた一歩進んだことを実感した。
2019年12月10日
網膜は、桿細胞と錐体細胞で光を感受、そのシグナルをまず網膜内で統合した後、そのシグナルを総局細胞を経て神経節細胞に伝達するよう配置された、美しい構造を持っている。このスキームでは、光はあくまで桿細胞と錐体細胞で感受することになるが、実際には神経節細胞も光を感じる能力がある。
以前光感受性色素を静脈に注射するだけで、桿細胞と錐体細胞の失われた網膜に光感受性を取り戻せることを示した論文を紹介したが、(https://aasj.jp/news/watch/5866 )、これは神経節細胞の中に光感受性色素が浸透して、P2Xと呼ばれる受容体を介して光シグナルを興奮に変えることができる。
ただ、わざわざこのような色素を導入しなくとも、神経節細胞の中にはメラノプシンを使って光を感じる細胞があることがわかっている。今日紹介するソーク研究所からの論文はこの機能がヒトの網膜神経節細胞にも残っていることを示した論文で12月6日号Scienceに掲載された。タイトルは「Functional diversity of human intrinsically photosensitive retinal
ganglion cells (固有の光感受性能力を持つ網膜神経節細胞は機能的に多様化している)」だ。
研究は極めてオーソドックスで、手術で切除されたヒト眼球から得られた網膜片を多数の電極の上で培養し、個々の神経節細胞の光に対する反応を一個一個電気生理学的に調べている。
この条件ではもちろん桿細胞と錐体細胞からのシグナルも神経節細胞に入るので、シナプスによるシグナル伝達は全てブロックするという条件で調べると、光を当て始めて少しして反応が始まり、明かりを消してもしばらく興奮が続く活動をひろうことができ、これが神経節細胞によることを明らかにする。
ただ全ての神経節細胞が反応しているわけではなく、1ミリ平方あたり2.5個の細胞が反応に関わる。ここの細胞の反応を解析すると、
感受性が高く、興奮が長く続く1型細胞 感受性が低く、興奮が短い2型細胞、 そして今回初めて発見された、強い光にしか反応できないが、興奮は強いが短い、3型細胞。 に分かれることを確認している。
また、反応波長についても調べ、反応パターンはそれぞれのタイプで違うが、ピークは470nmに来ることを示している。これは同じメラノプシンを光受容に使っていることから当然の話だろう。
最後に、これらの神経節細胞の反応を、シナプス阻害剤の有無で調べ、桿細胞と錐体細胞からの刺激が、固有の刺激とどう関わるかも調べ、神経節細胞固有の反応が、外部のシグナルで変化させられることを示している。
このように、第三の視覚が人間にもあることがはっきりしたのは面白い。しかし残念ながら、全て細胞レベルの反応測定で、この第三の視覚が何をしているのかはやはりわからない。これまでの研究で、おそらく概日周期を光で調整するときに利用しているのだろうと考えられているが、それぞれの型の神経節細胞の高次の役割はまだまだ解析が必要だ。しかし、動物実験でも統合されたシグナルがどう処理されているのか知るのは簡単ではない。その意味で、以前紹介した神経節細胞を光受容体として利用する治療実験は今後多くのことを教えてくれるような気がする。
2019年12月9日
今日は久しぶりにゲノム解析の話を取り上げる。少し難しいかなとは思うが、ASDやADHDを病気ではなく、脳の多様性として捉える時のカギになる分野で、まだまだ研究は始まったばかりだ。その意味で、多くの読者が無理してもフォローして欲しいなと願っていいる。
今日紹介したい論文(Autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder have a similar burden of rare protein-truncating variants, Nature Neuroscience, 2019: https://doi.org/10.1038/s41593-019-0527-8 ) 自分の小学校時代を思い返すと、「じっとするのが苦手、思ったことを口にする、整理整頓が苦手で、忘れ物が多い」という、注意欠如/多動症(ADHD)ともいえる性格を持っていた。担任の先生も心配したのか、一度だけだが学校の指示で児童相談所で診察を受けた覚えがある。今ならADHDと診断がついていたと思うが、幸い学業や学校での生活には全く問題を感じておらず、その後いくつかの症状は治ることなく続いて今に至っている。
実際、現在ADHDの発症頻度は5%を超えていると言われており、普通にみられる性格のタイプと言ってもいい。あまりに普通で境がはっきりしないためか、ASDについては多くのゲノム研究が発表され、100を超す遺伝子多型が発見されている一方、ADHDに関連する遺伝子多型の解析は遅れていた。しかし、一卵性双生児を用いた研究からADHDの一致率は高く、精密な多型解析の必要性は高い。また、片方がASDと診断されたケースで、もう片方がADHDと診断されることも多く、両者の状態の遺伝的背景に何らかの共通性があるのではと考えられてきた。
これらの問題を解決しようと、デンマーク・オーフス大学と、ハーバード大学を中心とする国際グループは、各国の多型解析データベースを統合してASD、ADHDの遺伝子多型解析を行い、今年相次いでNature Geneticsに発表した。詳細は省くが、ADHDも多くの遺伝領域の多型が重なり合った結果生まれる神経多様性の一つの状態であることが確認され、またADHDと診断される高いリスクに関わる多型も12種類特定された。しかし期待に反して、こうしてリストされた高いリスク遺伝子多型の中にはASDの多型とオーバーラップするものはほとんど存在しなかった。
ただ、これまで疾患のリスクに関連するとして特定されてきたほとんどの遺伝子多型は、タンパク質に翻訳されない部分(イントロン)に見られる多型で、特定の一つの多型を取り出してその意味を調べても、その意味はほとんどわからずじまいで終わることが多い。そのため、2種類の病気の遺伝背景を知ろうと思うと、多くの小さな変異を積み重ねた結果を計算して関係を推測する必要があり、まだまだ時間がかかると思われる。
そこで著者らは、小さな遺伝的変化を基礎にした遺伝子多型の研究から少し離れて、タンパク質の大きさが変化するような稀な変異に絞って、ASDとAHDHで調べたのが3番目の論文だ。一部の明確な遺伝子変異が原因のASDと異なり、ほとんどのASDでは、まずタンパク質の大きな構造変化を伴うような変異は存在しないと考えられてきた。このグループは、よく調べればそんな変異も見つかるのではと、何千人もの血液サンプルから、タンパク質に翻訳される部分を全て解読して、大きな変異を探索した。
詳細は省いて結論だけをまとめると、
典型児と比べると、ASDもADHDもこのような稀な変異が見られる頻度は高い。 ASDとADHDでリストされる変異遺伝子にはほとんど差がなく、稀で大きなタンパク質の構造変異に限ればASDもADHDもほぼ同じ。 もっとも多くのケースに見られたのが、神経発生時の細胞骨格の形成に必要なMAP1A遺伝子の変異で、ASDやADHDに神経発生時の変化が関わる可能性が示された。 となる。「視点を変えれば、ADSとADHDは高い遺伝的共通性を持っている。おそらく、タンパク質の構造変化を伴う様々な遺伝子の変異の上に、小さな遺伝的変化が積み重なって特徴的な症状が形成される」が結論だろう。
これまでタンパク質に翻訳される遺伝変化が原因で起こるASDのケースは、稀とはいえ知られている(例えばレット症候群)。これらの遺伝子変異ほど高い決定性はないとはいえ、今回トップ15にリストされたASD,ADHD両方に見られる変異も、神経細胞機能に何らかの影響を及している可能性がある。とすると、それぞれの分子の機能を丹念に調べることで、ASDやADHDの新しい理解へと進展するような予感がする。
「だからなんなの?」と言われそうだが、タンパク質の構造が変化する変異は研究が易しい。その意味で、私はこの研究の重要性は大きいと感じている。おそらく、理系の学生さんにとっても難しい内容かもしれないが、今後もできるだけASDのゲノム研究の進展は紹介していくつもりだ。
2019年12月9日
いつも学生さんに講義するとき、21世紀の生命科学がダーウィンの進化論と20世紀シャノンやチューリングの情報科学という、非物理的因果性を追求してきた流れがゲノム研究として交わった所に生まれた大きな渦だと、私の歴史観を述べたうえで、21世紀の重要な課題は、ゲノム、エピゲノム、脳回路、言語・文字など媒体としては独立した情報の集まりを統合することだと強調している。
20世紀の後半からゲノム研究が進み、病気の多型解析などが進んだが、21世紀の最初の統合の動きは、リストされた多型の意味を探る目的で行われてきた遺伝子発現と多型解析の統合に典型的に見られていると思う。
今日紹介するカリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文は、遺伝子発現を染色体構造情報に置き換えて多型と統合できないか模索した研究で、11月29日号のScienceに掲載された。タイトルは「Brain cell type–specific enhancer–promoter interactome maps and
disease-risk association(脳の細胞特異的エンハンサーとプロモーターの相互作用地図と病気のリスク)」だ。
もともとこの大学はエピゲノムの素晴らしいデータベースで有名で、現役時代門外漢の私も論文を読みながら興味が湧いた遺伝子のエピゲノムをこのデータベースで調べていた。この研究では、人間の脳からミクログリア、ニューロン、オリゴデンドロサイト、そしてアストロサイトを分離し、その核のクロマチン構造を、ATAC-seq(クロマチンがオープンかクローズかを調べる)、とゲノム状のヒストン修飾、H3K27ac(活動しているエンハンサー)、そしてH3K4me3(活動しているプロモーター)を特定し、さらにプロモーターやエンハンサーとは2次元的には離れていても、立体的には接して存在しているゲノム領域を調べるPLACと呼ばれる方法を用いて解析している。
膨大なデータで、データベースができたという点がハイライトなので、詳細は省く。もちろん予想通り、遺伝子発現、H3K27ac、H3K4me3はほぼ一致している。さらに染色体構造を調べる方法が合わさるおかげで、それぞれのエンハンサーやプロモーターの相互作用も同時に調べることができ、例えばSALL1遺伝子領域ではミクログリアだけでスーパーエンハンサーが形成されているのが特定できる。
次に、こうして解析した染色体構造を、これまで発表されている遺伝子多型解析結果と統合させている。基本的にはどの病気の多型解析にでも使えるが、この研究ではアルツハイマー病の多型解析と比べている。
もちろんそれぞれの細胞ごとにアルツハイマー病と関連する多型を特定できるが、中でも多いのがミクログリアで、結果か原因かはともかく、アルツハイマー病にミクログリアが深く関わっていることがわかる。
さらに重要なのは、ヒストン修飾や遺伝子発現からだけではわからなかった、多型が見られる領域同士の相互作用がはっきりと見られることで、いくつかの遺伝子を例として詳しく解析しているが、詳細は割愛する。
これらのデータも、この大学のデータベースで公開されると思うので、ぜひ多くの若手研究者が利用して、宝の山を当てて欲しいと思う。これはほんの始まりだが、もっと面白い新しい発想の生命情報の統合が進んでいくことが期待される。
2019年12月8日
遺伝的原因、すなわち疾患に関わる遺伝子が特定されていても、実際の病気の発症機構を明らかにするのは難しいことが多い。今日紹介するペンシルバニア大学からの論文はまさにそんな典型といえる研究ではないだろうか。脳海綿状血管奇形(CCM)と呼ばれる病気の発症機序についての研究で11月27日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Distinct cellular roles for PDCD10 define a gut-brain axis in
cerebral cavernous malformation (脳海綿状血管奇形発症においてPDCD10は腸管―脳軸に特殊な役割を果たしている)」だ。
CCMの8割は特に遺伝的要因がないが、残りの2割は家族性があることが知られ、これに関わる遺伝子が現在3種類明らかにされた。それぞれは様々なシグナルに関わるアダプタータンパク質で、血管形成時のシグナルが異常になり奇形が発生すると考えられているが、わかってないことの方が多い。そんな中、今日紹介する論文のグループは、生後新たに発生してくる脳静脈瘤などの異常がCCMタンパク質の欠損で抑制が効かなくなったMEKKシグナルによること、そして血管内皮のMEKK分子が腸管からのグラム陰性菌由来のLPSが脳に到達することで発生することを証明した(Tang et al, Nature 2017: doi:10.1038/nature22075 )。
今日紹介する論文ではCCM1−3までの別々の変異のうち、CCM3(PDCD10)変異の患者さんだけ、発症が早く病状が重いのかを追求している。
まず血管内皮にだけ変異を導入して、血管内皮内でMEKKを抑えているという点では3種類のCCM分子は全く変化がないことを確認した上で、脳の血管障害を促進する要因を探索し、腸管上皮のバリアーが敗れると、脳血管増殖が高まることを明らかにする。
この結果から、PDCD10が血管内皮だけでなく、腸上皮のバリアー機能に関わっている可能性を着想しこれを追求している。すなわち、血管内皮だけでなく、腸上皮にPDCD10を欠損させると、血管内皮だけで欠損した時と比べると異常の発症が促進される。しかし、他のCCM分子が欠損してもい血管内皮での欠損異常の変化は起こらない。
次にPDCD10欠損により腸内で起こる変化を調べると、腸管内での粘液層の形成が阻害される。 以上の結果から、PDCD10は腸管の粘液分泌と血管内でのMEKK阻害の両方に関わるため、欠損によりグラム陰性菌からのLPSが全身に循環してしまい、異常が早く起こると結論している。実際、これを確かめるため、腸内の粘液層が壊れる処理を行うと、同じように異常が促進されることを示している。
結果は以上で、様々な場所で働く一つの分子の機能が、CCMという病気で一点に集まってしまい、不幸な結果を招くということが明らかになった。ただ、この結果から、遺伝子異常がなくても、腸のバリアーが壊れると、脳や網膜での血管内皮の異常が誘導される可能性も示唆しており、今後の広がりもあるような予感がする。
2019年12月7日
一般メディアではクリスパー/Casシステムを使えば全て遺伝子編集という話になるが、編集というからには切ったり、貼ったり、あるいは必要な配列を挿入したり、自由自在に遺伝子を変化させる必要がある。それに対して、ちょっとハサミを入れるだけで遺伝子編集と思われてしまうので、正確な知識がない人たちは簡単に遺伝子編集という言葉に騙されてしまう。その結果、将来性のないクリスパーを使った技術に投資させられているケースも目にすることがあり、困ったものだと思う。
結局はどんな変異でも治すことができるかが問題になる。1ベースを変化させる(例えばCからTに変える)などは様々なテクノロジーが開発されているが、対象となる変異は半分に満たない。そのため一定の長さを置き換えてしまうのがいいのだが、その技術として現在利用できるhomology directed repairはどうしてもDNAの両端を切ってしまうので、他の場所での変異を引き起こしやすい。
これに対して今日紹介するハーバード大学からの論文はCas9が標的DNA領域の片方に切れ目を入れたあと、それに相補的なRNAをプライマーとしてデザインしたRNAを鋳型に逆転写させることで、望む遺伝子配列を導入する方法の開発で12月5日号のNatureに掲載された。タイトルは「Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or
donor DNA(探して置き換える2重鎖切断を必要としないゲノム編集)」だ。
要するに遺伝子クローニングを行うとき私たちが試験管内で行う実験を全て細胞の中でやらせようという発想の研究だ。必要なのはCas9に逆転写酵素を結合させたキメラ分子で、これにより標的の場所に切れ目をいれ、そこからRNA鋳型で逆転写させることを狙っている。これに合わせて、ガイドに用いるRNAも、標的DNAと結合する相補的配列、Cas9と結合する配列とともに、切れ目を入れた3‘端のDNAと相補的に結合して逆転写酵素のプライマーとして働くサイトと、編集後の配列を持つRNA鋳型が結合した少し長いRNAが必要になる。
その後ホストのシステムをうまく使って、編集した側のDNA鎖のみが残るように修復が起これば、ある程度の長さを自由自在に編集し直せることになる。
ただ構想はできても、実際のシステムを組み上げるには様々な改良が必要で、レトロウイルス由来逆転写酵素をCas9のC末につけたほうが良いとか、さらには温度耐性、鋳型への親和性、あるいはRNA分解酵素不活化活性などを変化させた19種類の逆転写酵素を作成し、最初編集効率が5%以下だった方法を10%以上に高めている。
次に、ガイド、Cas9結合、プライマー、鋳型の4役をもつRNAも細かく調整している。さらに、最後の修復時に編集した側のDNA鎖が残るように、編集しない方のDNA鎖に切れ目を入れてしまうようなCas9を使って、バージョン3では、ほぼ望む全てのタイプの書き換えを50%近い確率で可能にしている。
本当にDNA編集が近づいてくると言う実感が持てる結果だが、まだまだ様々な問題を抱えており、正常細胞の編集への道のりは簡単ではないだろう。しかし、方法は決定されたので、後は改良あるのみだと思う。当面はES細胞や動物卵での遺伝子編集を目標に開発が進む。
このようにこの分野の進展は早い。一方ほとんどの人はこのスピードについていけない。その結果クリスパーという言葉だけに惑わされて、技術を売り込まれてしまう。この技術は大丈夫かと気になって目利きが必要なら、いつでも相談は受け付ける。