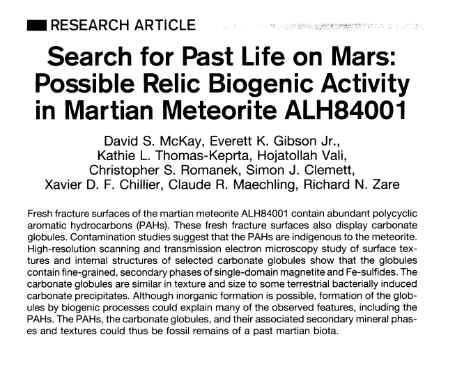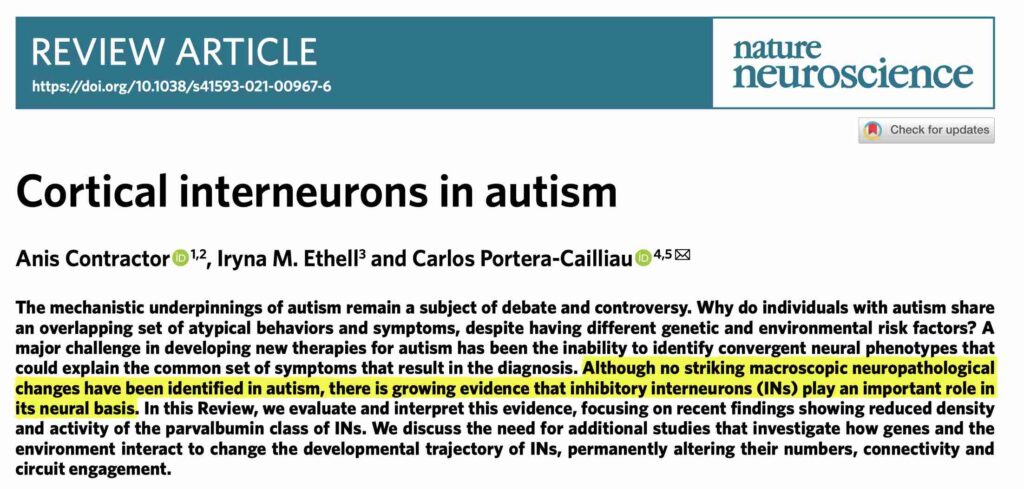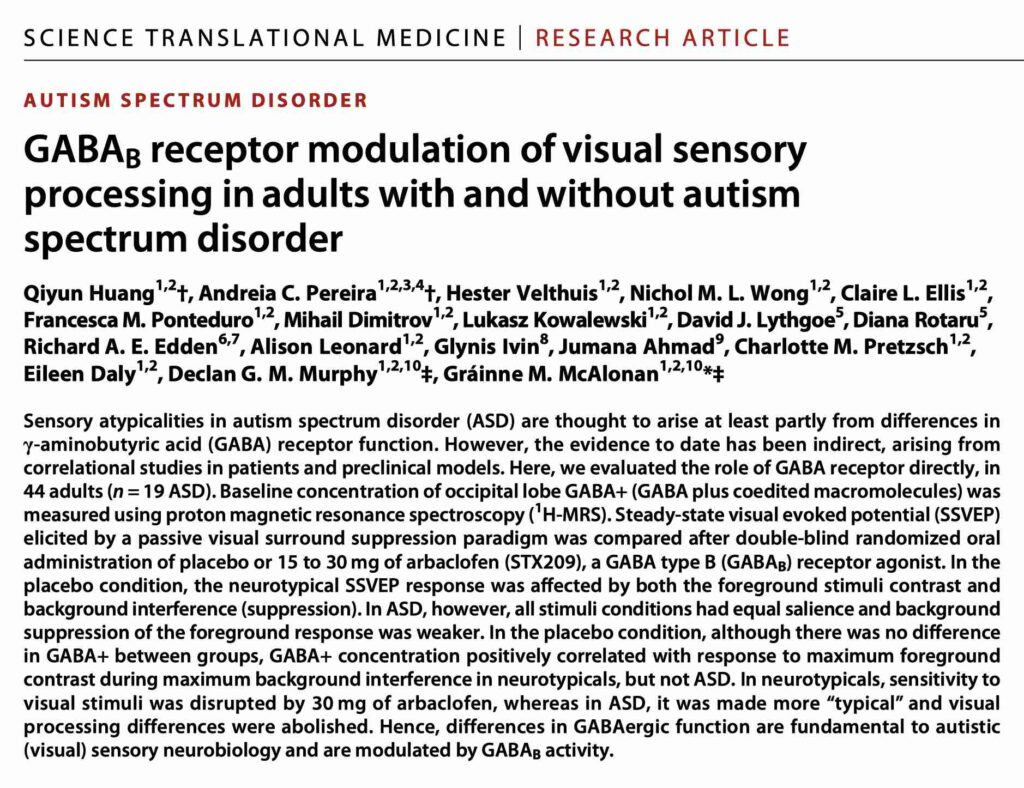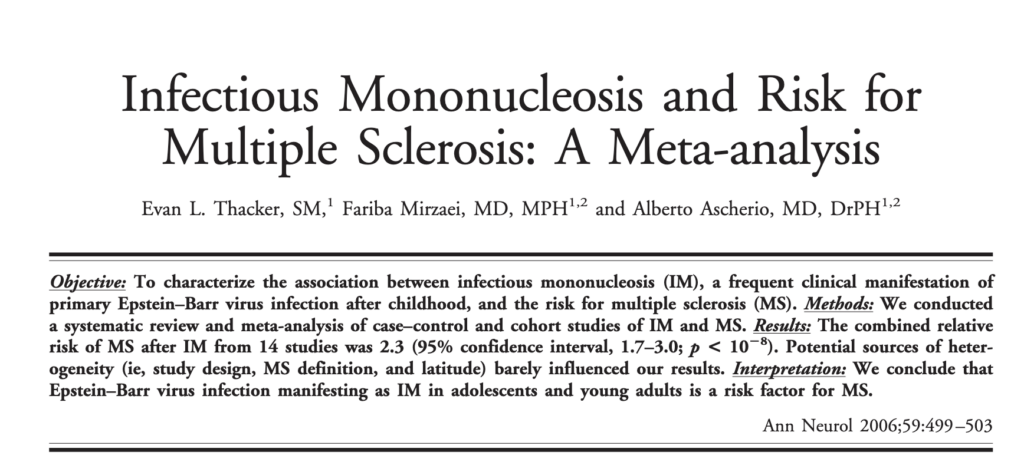2022年1月22日
昨日紹介したように、人間の言語活動を支える脳活動を調べるためには、脳の広い範囲にわたって、高い時間空間解像度で、しかも異なる波長の活動を区別して測定することが必要だ。しかし、脳への障害を最小限に止めておく必要があるため、電極を刺し込むことは許されない。この目的には、手術中に機能的に運動野と感覚野を区別したり、あるいはてんかんの発生源を電気的に特定するために開発された皮質表面の電気活動を拾うことが出来る表面電極(ECoG)が使われる。
今日紹介するカリフォルニア大学・サンディエゴ校からの論文はこの技術を飛躍的に高め、さらに大きな領域を、さらに高い空間解像度で記録できるプラチナ・ナノロッドの開発で1月19日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「Human brain mapping with multithousand-channel PtNRGrids resolves spatiotemporal dynamics(数千のチャンネルを持つプラチナナノグリッドによるヒトの脳のマッピングにより脳活動の空間時間ダイナミックスが明らかになる)」だ。
この研究のハイライトはあくまでもプラチナナノグリッド表面電極(PtNRG)の開発だが、材料工学については全くの素人なので、肝心なところの解説は省略せざるを得ない。ただ、頭蓋の外から脳波を測るために、心電図と同じように電極を頭の異なる場所に設置するのを想像してもらうと、1000−2000の電極を30µの間隔で設置することがいかに大変か理解できるだろう。
この研究では、これまで使われていたシリカの代わりに、ガラスを用いて薄く大きく、しかも高い解像度を持った表面電極を達成している。しかし、皮膚の表面に置く電極とは異なり、電極の間に体液を灌流できる穴が配置されており、一個一個のプラチナ電極には電線が接合されているなど、顕微鏡写真を見ると、いくらナノパターンの形成技術が進んだとはいえ、その精巧さに目を奪われる。
後はこれを用いて、神経活動を高い解像度で拾えるかが示されており、最初に行われたラットのヒゲに空気を吹きかける刺激実験では、ヒゲに対応するカラム構造が見事に浮き上がり、刺激後活動が伝播していることがキャッチできる。
もちろんこのようなデバイスは臨床応用を目的に開発される。この論文では、
1)脳外科手術時に、感覚野と運動野を正確に区別し、手術のプロトコル決定に使えるかどうか、
2)手の運動と感覚の神経活動をできるだけ正確に記録して、Brain-Machineインターフェースで、将来機能的義手に使えるか、
3)手術中にてんかん巣を正確に特定して、できるだけ小さな領域の切除でてんかんを抑えられるか、
などについて、これまでのECoGと比べて、飛躍的に高い機能が提供できることが示されている。
以上が結果で、新しいPtNRGを用いて高い空間解像度の記録が可能であることは分かったが、例えば昨日紹介したような研究に使えるようになるには時間がかかりそうだ。というのも、電極から測定器までのコネクターがこのままでは、手術中にしか使えない。今後、膨大な数の電線をまとめて頭蓋の外のコネクターに接合できないと、生活の中でのてんかん巣検出や、長期にわたる記録は難しい。ただ、おそらくこのような問題は解決されるだろう。その結果、例えば思い描いた文字を実際に書かせたり、発話したりと言ったbrain-machineてんかんに関しては、さらなる飛躍が期待できる。そしてこの方向での進歩が、人間の脳機能の理解の進展に直結する。
2022年1月21日
言語を議論するとき最初に話す統計がある。地球上の哺乳類の総量は11億トンに達しているが、このうち、人間、家畜、ペットが占める重さは10.7億トンで、野生の哺乳類はたったの3300万トン(3%)にすぎない。しかし、1000年前にはこの関係は逆転していたという。これほど人類が繁栄した原因は、なんと言っても、おそらく5万年頃前にホモサピエンスが獲得した言葉を話し、会話する能力によっている。すなわち、現実かどうかに関わりなく、特定の内容を理解し合う、シンボル化された仮想現実を表象し伝える能力の獲得にある。
しかし、これほど重要な会話能力を支える脳の研究は難しい。というのも、会話を研究するためには、時間解像度の高い方法を用いて脳を解析し、まずどの領域が会話を支えるか特定する必要がある。このため、会話する脳の研究は、解析の時間解像度にとらわれない脳傷害の結果生じる失語症の研究から始まり、その後脳波や脳磁図を用いて会話中の脳の変化を記録し、会話に関わる脳ネットワークを特定する方向へ変わっていく。ただ、これらの方法は頭蓋の外から記録を行うため、どうしても空間解像度を犠牲にする。このギャップを埋めるため、脳外科手術中に電極で脳を直接記録することも行われてきたが、成果は限定的だった。
これを大きく変革したのが、かなり広い範囲をカバーできるクラスター電極(頭蓋内皮質脳波計)を脳内に設置した(てんかん巣診断のため)患者さんの了承を得て、時間および空間解像度の高い脳の活動情報を記録する方法の開発だ。(この進歩については明日テクノロジーの論文を紹介する)
今日紹介するニューヨーク大学からの論文は、この頭蓋内皮質脳波計(ECoG)を設置したてんかん患者さんについて、会話の重要なプロセスに関わる脳領域を、高い空間時間解像度で解析した研究で、1月5日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「A speech planning network for interactive language use(相互的言語使用時の発語を計画する脳ネットワーク)」だ。
会話は、まず相手の話を聞いて理解し、その中のキーになる単語をキャッチし、それに合わせて答えを計画、最後にそれを言葉として発語する過程からなっている。このとき、話の理解については、例えばN400反応のような概念などかなり詳しく解析されてきた(https://aasj.jp/news/watch/8178 )。この研究では、理解しながら次の答えを計画する過程で働く脳領域を特定しようとしており、面白い課題を設計している。
The opposite of SOFT is what familiar word? とWhat familiar word is the opposite of SOFT ? (答えはROUGH)の、質問の核(CIと呼んでいる)SOFTが前半、あるいは後半に来る文章を設計し、ROUGHという答えが出てくるまでの脳記録を行うと、CIを感知したあとから答えのプランニングが始まるので、このときの時間差を使って、CIに反応する脳領域を特定している。
実際CIが前半に来ると、答えのプランニングはすぐに始まり、答えるまで続く。一方、 後半にCIが来ると、答えを計画する領域は急速に立ち上がり、答えを発語するときにはすでに活動が低下する。いずれにせよ、この答えの計画に関わる領域はCIの1とは無関係に共通で有ることが分かる。また、発語に関わる領域は、計画中には全く反応しない。
この様に、3つのプロセスに特異的に活動する領域を特定することで、
1)答えを計画するプロセスは複雑なので、多くの領域が動員されると考えられているが、前頭側頭葉の特定の場所に限局したクラスターが明確に存在することが分かった。
2)特定のCIに対する答えを計画するときに活動する領域は、同じCIに対してジェスチャーや、表情で答える用にと言う命令に対しても活動するが、同じ言葉を繰り返したり、それを複数形に直したりせよという、言葉に関わる命令に対してはほぼ9割の一致率で活動する。すなわち、答えの計画は、様々な答え方のモダリティーに共通の領域と、言葉というモダリティーに特異的な領域が存在する。
3)このように課題型の会話と、自由な会話を比較することで、答えを計画する領域の活動が、相手の話を聞いているときから活動していること、そして活動する領域は明確なクラスターを形成することが分かった。
結果は以上で、本当に新しいという意味では、この論文は、相手の言葉に反応し得て答えを計画する過程を浮き上がらせる課題を設計し、認知、計画、発語に関わる領域を決定し、発語過程が古典的なBROCA領域だけではなく、答えの計画に関わる領域も含むことも明らかににした点にあるのだろう。実際、この領域の脳外科手術の結果、計画と、発語が完全に切り離されたapraxiaの患者さんが発見されており、この結果を支持している。
失語研究として習った過程が、本当に解明されていくのが分かるが、ネットワークのアルゴリズムとなると、次世代の課題になるのだろう。
2022年1月20日
昨日、火星から一度飛び散った破片が宇宙を旅して、約1万年前に南極に飛来したアランヒルズ隕石に、水の作用によるserpentinizationの結果合成された有機物が残っていることを示した研究を紹介した。これは、アランヒルズが火星を離れた1300万年前には、火星には水が存在し、生物はいないにしても、有機物を合成できる環境にあったことを示唆している。
なんと、これを書いた同じ日、ペンシルバニア州立大学を中心とする火星の生物の可能性を検証した論文が米国アカデミー紀要に発表されているのを見つけたので、ちょうど良い機会と、専門外の鉱物学とはいえ簡単に紹介することにした。タイトルは「Depleted carbon isotope compositions observed at Gale crater, Mars(火星のゲールクレーターで発見された炭素同位元素の欠如)」だ。
有機物が見つかっても生物の存在を示す証拠でないとすると、では生物の存在可能性をどう調べたらいいのか?
少なくとも地球上では、この目的に13 Cと12 Cの比率が使われる。生物は、様々な酵素反応を起こしやすい12 Cを好む性質があり、その結果生物が合成した有機物の炭素は12 Cが増加する。これを用いて、生物による有機物と、それ以外の有機物を区別することが行われる。
この研究は、有名な火星に送られた探査ロボット、キュリオシティー(https://mars.nasa.gov/msl/home/) 2012年8月から2021年7月にかけて、ゲールクレーターを動き回り(といっても計画に沿ってと思うが)、30カ所で岩石の掘削を行い、その岩石を、evolved gas analysisと呼ばれる熱をかけて発生するガスをレーザー分光光度計で分析している。結果だが少なくとも4カ所から採取したサンプルで、重い炭素同位元素13が除去されており、同時に34 S低下していた。
以上が結果で、後はこれが本当に生物が存在した痕跡かどうかを詳しく考察している。というのも、例えば地球の熱水噴出口のメタンが、生物由来かどうかを調べるのとは異なり、長い年月の最終結果を見ていることから、この結果をそのまま生命の痕跡と大騒ぎは出来ない。
しかし、発見された場所が全て水の作用を受けた場所であったり、硫黄同位元素の結果と一致していることから、他にも炭酸ガスの紫外線による還元、さらには宇宙塵の蓄積など、地球とは異なる環境による生命の関与しない反応の可能性も考慮した上で、生命の可能性を排除するまでには至らないと結論している。
極めて控えめな結論だが、火星に生物がいたより明確な痕跡を見つけるために、キュリオシティーにはまだまだ頑張ってもらう必要がある。しかし、この火星探査の用意周到さに本当に驚く。
2022年1月19日
生物が誕生するには有機物が必要だが、有機物が出来たとしても、生物が誕生するまでには確率の低い過程が積み重なる必要がある。従って、有機物の存在を、そのまま生物の証拠を示すと早とちりしてはならない。
今日紹介する米国カーネギー研究所からの論文は、1984年南極で発見された火星から飛来した隕石の中の有機物を詳しく解析し、その形成過程を調べた研究で、1月14日号のScienceに掲載されている。タイトルは「Organic synthesis associated with serpentinization and carbonation on early Mars(初期の火星で起こったserpentinizationと炭化に伴う有機物生成)」だ。
この研究が対象にしたのは、アランヒルズ84001と呼ばれている南極で発見された隕石で、解析の結果から40億年前に形成された岩石で、1300ー1600万年前の小惑星の衝突で隕石となり、約13000年前に南極に飛来した。すでに多くの論文が発表されており、1996年には、火星の生物の痕跡があるという論文までScienceに発表されている。
1996年当時と比べると分析方法は大きく進歩しているようで、私の知らない分析方法のオンパレードだ。まずこの隕石の断片から、イオンビームを用いて切片を作り、これを電子顕微鏡や、切り出した結晶の割れ方の解析、走査型X線顕微鏡解析、そして二次元二次イオン質量分析装置などを組みあわせて、微少な切片の中の有機物の組成を調べている。実際には、3カ所から調整した切片を分析し、総合的に考察している。
鉱物学には全く素人で、論文を読むのも苦労しているので結論だけを紹介する。有機物の生物由来説についてはあまり考慮に入れていないようで、イントロダクションで触れてはいても、後は全く考慮していない。基本的には、炭素化合物が岩石と相互作用して、有機物が形成されるための水が存在し、岩石と水との相互作用が起こったかが問題になる。
この岩石と水との作用が起こり有機物が形成される過程をserpentinizationと呼んでおり、現在の地球でも例えば熱水噴出口などで起こっている。この過程で起こる様々な現象が今回の分析片にも存在することから、基本的にこの隕石の有機物はserpentinizationが関わっていることを示唆している。これとともに、2つの切片では鉱物が水に溶けた二酸化炭素と反応する炭酸飽和有機物が形成されていることも示している。いずれにせよ、「水と鉱物相互作用でこの隕石の有機物が生成された」がこの研究の結論になる。
以上のことから、長期にわたって火星に水が存在し、有機物の合成が続いたことが想像できる。昨年火星上で観測された地震から明らかになったように、火星内部は液体状、すなわち高温であることを考えると、地球上と同じ熱水噴出口も出来ていたのではと考えられる。その意味で、火星に生物が存在した可能性は十分あると思う。ただ、生物由来かどうかを火星の条件で解析できる方法論の確立は、火星探検が急速に進みつつある今最も重要な課題かもしれない。
2022年1月18日
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は常在菌だが、免疫が低下した方に感染してしまうと、抗生物質が効かないため治療が難しい感染症を引き起こす。抗生物質耐性であることから、抗生物質を投与された家畜で発生した例外的なケースを除いては、病院内で抗生物質が使われることで発生すると考えられていた。もちろん私もそう考えていた。
ところが、今日紹介するデンマーク国立血清研究所を中心とする多施設共同論文は、ハリネズミと人間のMRSAを比較することで、MRSAは抗生物質が誕生するずっと前からおそらくハリネズミの中で発生していたことを示した、まさに「(科学的)事実は小説より奇なり」を地で行く研究で、1月5日Natureにオンライン掲載された。タイトルは「Emergence of methicillin resistance predates the clinical use of antibiotics(メチシリン耐性は抗生物質が臨床で使用されるより前に誕生していた)」だ。
ヨーロッパのハリネズミは200年ほど前にニュージーランドから持ち込まれた外来種で、おそらく定期的な調査対象になっていたのだろう。デンマークとスウェーデンで行われたハリネズム調査は、MRSAが北欧のハリネズミに広く分布しているとする驚きの結果を示した。
MRSAを病院感染由来と思うと、この結果は人間から持ち込まれたMRSAがハリネズムに拡がったと言うことになるが、そこに逆転の発想が持ち込まれ、ひょっとしたらMRSAの発生はハリネズミが先ではないかと考えたのが今回の研究だ。
英国、デンマークを中心に、ヨーロッパの広い地域でハリネズミに耐性遺伝子の一つmecCが存在しているかを調べた結果、様々な国に広く分布しており、英国では7割、デンマークやチェコでは5割近くのハリネズミが耐性遺伝子を保持していることを発見する。
当然次の課題は、これら耐性遺伝子の進化経路をゲノムからたどって、この遺伝子が人間から来たのか、あるいはハリネズミ由来かを調べることになる。詳細を省いてまとめてしまうと、ハリネズミmecCは独立に進化した3種類の系統に分けられ、このうちCC1943系統の3ラインはなんと1800年代に発生していることが分かった。
CC130は最も広く分布しており、多くのラインへと分かれているが、この発生も元をたどると、20世紀初めで、ほとんどのラインは人類が抗生物質を手にする前に発生していることが分かった。また、それぞれの系統で、進化のほとんどはそれぞれの地域で、ハリネズミの内部で起こっていることが示されている。従って、英国と大陸間については、人間や家畜による持ち込み、あるいは鳥を媒介とした感染などが重なる必要はあるが、進化自体は地域のハリネズミ内で進んだことが確認される。
ではなぜハリネズミ内で薬剤耐性遺伝子が発生するのか?これについては、ハリネズミに広く見られる皮膚糸状菌にペニシリン、すなわちβラクタムを合成する能力があり、糸状菌培養上清がブドウ球菌の殺菌効果を有することを示し、ハリネズミ内で、抗生物質合成糸状菌がMRSAを発生させたことを示唆している。
結果は以上で、ウイルスだけでなく多くの感染症が人間と動物の関係に深く根ざしていることを示しており、繰り返すが「科学的事実は小説より奇なり」としか言い様がない。15日から、多発性硬化症の原因としてのEBウイルス、嗅覚受容体発現マクロファージと動脈硬化、甘みを感じる十二指腸のneuropod細胞、そして今日のハリネズミ内でのMRSA発生と、面白い研究を続けて紹介したが、今年も何が出てくるかわくわくする。
2022年1月17日
昨日はマクロファージに発現した嗅覚受容体の話を紹介したが、今日は十二指腸で発現している味覚受容体の話を選んだ。この論文を読むまで、味の感覚は全て舌にある味覚受容体を介して伝達され、好みといった行動は、意識下の味覚認識に依存していると考えていた。しかし、甘みに対する受容体を欠損させたマウスが、なんと砂糖の入った食べ物を好むことが発見され、意識下の味感覚以外にも甘さが感知されていることが明らかになっていた。
今日紹介するデューク大学からの論文は、最近発見されたneuropod細胞が、異なるメカニズムで、蔗糖と人工甘味料を区別し、シナプス結合している迷走神経を刺激することで、蔗糖への好みが形成されることを示した大変な力作で、1月13日Nature Neuroscienceにオンライン掲載された。タイトルは「The preference for sugar over sweetener depends on a gut sensor cell(人工甘味料より砂糖を好む行動は腸の感覚細胞に依存している)」だ。
コレストキニン(CCK)を発現するNeuropod細胞(NC)が、腸管内分泌細胞だけで無く、迷走神経とシナプスを形成することで、感覚神経として働いていることが確立したのはつい最近(2015-2018年)のことだ。この研究では、このNCが、味覚が無くても、砂糖を好む行動を支配しているのではと考え、この可能性を膨大な実験を積み重ねて明らかにしているが、特に脳向けに開発された光遺伝学を腸内へ適応するために開発し直すなど、大変な力作だ。詳細は省いて、結果だけを箇条書きに紹介する。
1)蔗糖や人工甘味料のスクラロースは、十二指腸に注入すると、迷走神経興奮を引き起こす。この興奮は光遺伝学的にNC細胞を過興奮させることで抑制されることから、NCがセンサーになっている。
2)NC細胞にはシナプス形成分子のみならず、甘み受容体を形成できるT1R3やグルコーストランスポーターSGLT1が発現している。
3)蔗糖はグルコースに分解された後、SGLT1を通って細胞内に流入することで、興奮を誘導する。一方、スクラロースはT1R3に直接作用してNCを興奮させる。それぞれの刺激反応の仕組みは、細胞ごとに違っており、これが砂糖とスクラロースを区別する基盤になっている。
4)GLUT1を介する砂糖の刺激はグルタミン酸、T1R3を介する刺激はATPを神経伝達因子として使う。
5)砂糖への好みはグルタミン酸による興奮伝達による条件付けにより成立しており、グルタミンによるシナプス刺激を十二指腸で抑えると、砂糖への好みは消失する。
以上が結果で、まとめてしまうのが申し訳ないぐらいの面白い研究だ。この無意識の感覚がなぜ発生したのか、省略したがなぜ果糖は感じられず、蔗糖なのか、など進化的に面白い話が満載の気がする。
2022年1月16日
(この記事は、1月9日論文ウォッチで紹介したものに加筆してよりわかりやすくし、自閉症の科学50として再掲したものです。)
典型人と比べたとき、自閉症スペクトラム(ASD)では脳ネットワークに何か共通のの違いがあることは疑う人はいない(共通の違いという点が重要!個別に見れば脳ネットワークは一人一人違っている)。
ASDはスペクトラムと称されているように、多様性が高く、神経多様性概念が拡がるきっかけになった。また、遺伝要因や個人の変異を調べるゲノム研究でも多様性が明らかで、多くの頻度の高い遺伝子多型とともに、希な変異も発症に関わる、多様な状態であることもわかっている。
このような多様性にもかかわらず、ASDには、社会性、言語能力、行動などで共通の症状が存在している。すなわち、このような症状の元になる脳回路の変化が存在する。にもかかわらず、現在まで「これが典型児との違いです」と病理学的に明確な変化が示されたことは全くない。
ただ最近になって、典型児と比べたときASDではGABA作動性の抑制性介在神経の数や活性に違いがあるのではと言う証拠が示されるようになってきた。
注1) GABA作動性抑制性介在神経は、短い範囲をカバー(神経軸索の長さが短い)するニューロンで、GABAを神経伝達因子として用いて、シナプス興奮を抑える役割を持つ。これにより、神経興奮と抑制のバランスが維持される。発現している分子(パルブアルブミンとソマトスタチン)の差で2種類に分けられる。
幸い最近、ASDと介在神経についてまとめた総説がシカゴのノースウェスタン大学から発表されたの図1)。まずこれにもとづいて、ASDの介在神経異常についてまとめ、その後で新しい論文を紹介してみよう。
ASD死後解剖例の解析から、解剖学的にはほとんど異常は認められないが、パルボアルブミン(PV)陽性介在神経の低下が見られる。 ASD様の症状を発症する遺伝子欠損マウスモデルでも、介在神経数の低下が見られる。 遺伝子多型解析でASDとの相関が認められる多くの遺伝子が、介在神経とその発生途上で発現が見られる。 MECP2遺伝子欠損によって起こるRett症候群などでは、介在神経機能低下による、脳領域の過興奮(時にてんかん)や、同期的興奮が見られる。 介在神経が強く関与する振幅の短いγ波がASDでは上昇し、感覚異常やコミュニケーション異常に関わっている。 以上がまとめで、ASDに見られる感覚異常とGABA作動性介在ニューロンがつながってきたことは、薬理学的治療の可能性まで視野に入る重要な進歩だと期待されている。
このHPでも、脳内には到達しないGABAシナプス刺激剤を投与すると、モデルASDマウスの感覚異常が改善され、ASD様症状が抑えられることを明らかにした論文(https://aasj.jp/news/autism-science/11245 )や、細菌叢がASDの症状に関わるのもGABA作動性の抑制神経の活動が低下しているためである可能性を示す論文を紹介してきた(https://aasj.jp/news/watch/10310 )。
今日紹介する英国キングズカレッジからの論文は(図2)、ASDのGABA 作動性抑制神経と、感覚異常に注目し、治療可能性まで示した重要な研究で、1月5日号のScience Translational Medicineに掲載された。タイトルは「GABA B receptor modulation of viual sensory processing in adults with and without autism spectrum disorder(ASDおよび正常成人の視覚処理はGABA B受容体により変化させられる)」で、「自閉症の科学50」として紹介する。
この研究を紹介する前に、Spatial Suppressionと、プロトンMRSと呼ばれる脳内分子測定法について少し解説する必要がある。
注2)Spatial suppression:図3に示すように、 コントラストの差や、背景と対象物のパターンの類似性などにより、対象物の見え方が異なる。このように、背景や対象物を変化させて、同じ対象物でも見づらくなることを、spatial suppressionと呼んでいる。不思議なことに、ASD児ではspatial suppressionにあまり影響されないことが知られている。
注3)プロトンMRS:正直、原理については私も理解できていないが、特定の場所に含まれる分子を、組織を傷害すること無く核磁気共鳴を用いて測定する方法で、代謝や神経伝達物質の測定に用いられる。この研究では視覚野でのGABAの量を測定している 。
例えば対象物のコントラストを下げたり、逆に背景のコントラストを落としたりしてspatial suppressionにより視覚認識を邪魔すると、典型人の認識力はsuppressionが高いほど当然低下する。ところが、ASDの人では、このような低下があまり認められないことが知られていた。
この研究の目的は、ASDでspatial suppressionが低下することを確認することと、GABA作動性ニューロンの活動低下が相関しているか調べることだ。このため、実験では典型人、ASDを3群に分け、1群は何もしない、2群は少ない量のGABAシナプス刺激剤、そして3群に高量の刺激剤を服用してもらい、spatial suppressionテストを行ったときの脳波を記録、視覚認識が低下するかどうかを調べている。
この実験により、
1)典型人でspatial suppressionによる視覚認識低下がGABA刺激で改善するのか、
2) ASDで予想されるspatial suppressionの感受性低下がGABA刺激で改善するのか、
について答えることができると期待される。
結果だが期待通りで、GABA刺激剤を投与していない場合、典型人ではspatial suppression が高めると、視覚野での脳波の変化をキャッチできるが、ASDではこの変化が見られない。すなわち、ASDの視覚認識は、spatial suppressionに影響されない。
ところが、高い濃度のGABAを刺激する薬剤を投与したグループでは、この反応パターンが逆転し、ASDではspatial suppressionに強く影響を受けるようになるのに、典型人ではspatial suppressionの影響が消える。
解釈は難しいが、この結果はGABA刺激の量が、spatial suppression の程度を調節していることをはっきりと示している。すなわち、ASDでも典型人と同じレベルにGABA刺激を高めてやると、視覚の認識異常が正常化することがわかる。
典型人で同じ量のGABA刺激剤を服用すると、spatial suppressionが見られなくなるのは、おそらく刺激が過剰になると回路がうまく働かないことを示しているのだろう。すなわち、介在ニューロンの一定レベルの活動が、spatial suppressionには重要で、GABA量が低くても、高くてもうまく働かないが、ASDではこのレベルが低いと結論できる。
このようにGABAの量によりspatial suppressionが調節されていることを確認した後、プロトンMRS技術を用いて、spatial suppression課題を行っているときの、視覚野でのGABA濃度を測定している。結果は完全に期待通りで、spatial suppressionによる脳波の変化と、GABA濃度の間には強い相関が見られる。そして、ASDでは、GABA濃度の上昇が見られない。
以上の結果から、ASDの視覚感覚異常には、GABA抑制性神経の活動の低下が深く関わることが証明されたと思う。以前紹介したように、マウスモデルでは体性感覚野異常にGABA作動精神系が関割ることが示されており((https://aasj.jp/news/autism-science/11245 )、おそらくほとんどの感覚で抑制性介在神経異常がASDで見られると考えて言いように思える。
脳内のGABAレベルを上げることが可能かどうか私には判断できないが、 細菌叢への介入を通して、GABA作動性の抑制神経の活動を正常化する可能性を示す論文も存在している(https://aasj.jp/news/watch/10310 )。その意味で、GABAを標的にした様々な治療法開発も視野に入ってきたのではと期待している。
正月早々、面白い論文を2編も紹介でき、満足している。
2022年1月16日
つい3日前、嗅覚受容体の一つが乳ガンに発現して、悪性化を誘導するという論文を紹介した(https://aasj.jp/news/watch/18764 )。驚いたことに、ガンだけでなく嗅覚受容体が臭い感知以外にも役割があるのではと考えて研究が行われているようで、今日紹介するLa Jolla免疫研究所からの論文は、マクロファージの一部がマウスではOlfr2、ヒトではOR6A2嗅覚受容体を発現し、動物脂肪酸から合成されるオクターナルを感知して、インフラマゾームを活性化し、動脈硬化を悪化させるという驚くべき結果を示している。タイトルは「Olfactory receptor 2 in vascular macrophages drives atherosclerosis by NLRP3-dependent IL-1 production(嗅覚受容体Olf2はマクロファージに発現し、NLRP3依存性のIL-1合成を誘導して動脈硬化を促進する)」だ。
ガンの悪性化を促すことを報告した論文にも驚いたが、この論文の驚きは機能的メカニズムが明らかにされている点で、さらに大きく、当然研究のレベルが高い。
まず、マウスマクロファージがOlf2を発現しており、しかもその発現がApo2欠損動脈硬化モデルマウスに脂肪の多い西洋型食事を与えることで上昇すること、また人間の動脈硬化巣のデータベースを再検討し、Olf2に対応するOR6A2の発現が上昇していることを確認し、マウスやヒトの動脈硬化巣浸潤マクロファージが嗅覚受容体を介して、動脈硬化に関わる可能性を明らかにしている。
次に、Olf2の発現に動脈硬化の上流シグナルTLR4が関わっており、例えばLPS刺激でOlf2発現が上昇すること、またOlf2ノックアウトマウスでは動脈浸潤マクロファージの数が低下すること、すなわちOlf2が確かに動脈硬化に関わることを示している。
重要なのは、Olf2やOR6A2を刺激するリガンドの一つとしてオクターナルが特定されていることで、オクターナル刺激により誘導された活性酸素がインフラマゾームを介してインターフェロンを誘導し、動脈硬化巣の炎症を誘導することがわかった。実際、オクターナル刺激をシトラール(芳香剤として使われる油)で抑制すると、IL-1βの発現も抑えられる。
しかも、オクターナルの合成経路を調べると、動物脂肪に含まれるオレイン酸由来であること、そして西洋型食事を食べると、動脈でのオクターナルんレベルが上昇する。さらに、Apoe欠損マウスでは、この値がさらに上がっており、また動脈内でのオレイン酸からオクターナルへの転換も上昇しており、リガンド、受容体とも動脈硬化とリンクしているという、ちょっと出来すぎた話だ。
後は骨髄移植の系などを用いて、マクロファージのOlf2を働かなくすると、動脈硬化が抑えられること、またシトラールを長期間投与してOlf2を阻害しても、動脈硬化を抑えられることなどを示し、将来ヒトのOR6A2阻害剤が動脈降下薬として使える可能性まで示している。
読みながら、出来すぎた話だと思い続けていたが、裏返せば驚きの連続の論文で、全く新しい動脈硬化治療に発展して欲しい気がする。
しかし、800種類以上嗅覚遺伝子が存在し、多くは脂溶性のリガンドを認識しているなら、当然進化過程で他の目的に使われても不思議はない。マウスとヒトは進化的に近いので、是非他の哺乳動物で調べてみて、この遺伝子がマクロファージで炎症刺激に使われる過程を明らかにすることで、なぜ動脈硬化プロセスが我々に現れたのかのルーツも理解できるかもしれない。
2022年1月15日
多発性硬化症(MS)は、ミエリンに対する自己免疫反応が基盤になっているが、この自己免疫反応の引き金を引くのがウイルス、特にEBウイルスではないかという可能性は長く示唆されてきた(例えば、Ana. Neurology 59, 2006:図)
ただ、EBウイルスの感染は全世界の95%が経験しており、いくらEBウイルス感染後にMSリスクが上昇したからと言っても、確かに因果性があると簡単に結論することは出来ない。
この問題を、米軍兵士1千万人のコホートサンプルを用いて解決し、EBウイルス感染が引き金になっている疑いが極めて濃いことを示したハーバード大学からの論文が1月13日Scienceにオンライン掲載された。タイトルは「Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis(長期追跡研究により多発性硬化症がEBウイルス感染とリンクしていることが明らかになった)」だ。
これまで、EB感染者とそれ以外を分けてMS発症を調べる研究は行われていたが、因果性まで示すとなると、感染と発症との関係をより詳細に追跡する必要がある。この研究では、米軍兵士1千万人の中から955人がMSを発症した集団を対象にした追跡研究を元に、残っている血清からEBウイルスの感染時期やEBに対する免疫反応や神経変性を検査し、因果性を確かめようとしている。
結果は驚くべきものだ。必要な全ての材料が残っていたMS例が801例だが、発症に一番近い時点で採取された血清でEB感染を調べると、陰性だったのは1例だけで、EB感染率を考えても極めて高い。
さらに驚くのは、さらに前の血清を調べ、最初はEBに感染しておらず、その後いつEBウイルスに感染したのか追跡できるケース35例を抜き出してみると、1例を除く全てが、MS発症以前のどこかでEBウイルスに感染し、その後MSを発症していることが明らかになった。すなわち、EBウイルス感染と、MS発症に強い時間的因果性があることが分かった。
同じように、最初は陰性だが、どこかで感染するウイルスとしてサイトメガロウイルスを調べてみると、感染とMS発症とに全く因果性は認められない。
さらに、自己免疫反応による神経変性をある程度反映できる検査マーカーを用いてEB感染、MS発症と、神経変性の始まりをモニターすると、EB感染以後、MS発症前から変性が始まっていることが明らかになった。また、VirScanと呼ばれる網羅的抗ウイルス抗体検出法を用いて、全体的な免疫変化が起こっているのでは無く、EB感染による変化が特異的に起こっていることも確認している。
結果は以上で、極めて大きな集団を対象にすることで、感染実験と同じことが可能になり、結果EB感染によるMS発症リスクは32倍と、驚くべき数値がはじき出されている。
この数値だけで驚くが、もう一度EB感染という視点からこの病気を見直してみると、全く新しい治療が可能になるのではと期待している。
2022年1月14日
(この文章は、1月8日論文ウォッチで紹介したものを、解説を加えて自閉症の科学として再掲載した文章です。)
久しぶりに自閉症の科学として紹介したいと思った二編の論文を、新年早々見つけることができた。すでに論文ウォッチとして1月8、9日連続して紹介したが、おそらく理解しづらい点も多いと思うので、自閉症の科学として、できるだけわかりやすく書き直すことにした。
最初の論文は、Mothereseと呼ばれる、お母さんが幼児に話しかける時に使う心のこもった呼びかけに対する、自閉症スペクトラム(ASD)幼児の反応を脳科学的、行動学的に調べた、カリフォルニア大学サンディエゴ校からの論文だ。1月3日Nature Human Behaviourにオンライン掲載され、タイトルは「Neural responses to affective speechi, including motherese, map onto clinical and social eye tracking profiles in toddlers with ASD(Mothereseを含む気持ちのこもった言葉に対する神経反応は、自閉症幼児のアイトラッキングによる臨床的、社会的反応と対応している)」だ。
最近のASDに関する論文では、神経多様性の観点から、ASDと正常グループと分けることはせず、典型グループとASDグループと分けるようになっている。ここでもこの表現を踏襲する。 注)まずタイトルにあるmothereseから説明しよう。Mothereseはあらゆる文化で見ることができる、幼児に話しかける時、自然に使ってしまう、ゆっくりしたテンポで、抑揚のついた、うわずった声の独特の話し方のことを指す。そう聞けば誰でもどんな話し方か思い当たるのではないだろうか。これは幼児への話しかけに使われるのだが、大人が聞いても、ほっとするし、実際脳の反応も異なることが報告されている。
もし感情と言葉が合体したMothereseの脳への影響が普通の言葉と違うとすると、他人とのコミュニケーションが苦手な自閉症スペクトラム(ASD)の子供では、Mothereseに対する反応も、典型児とは異なっている可能性がある。この可能性を、脳の機能的MRI(fMRI)と、視線を追いかけるアイトラッカーを用いた行動記録から調べたのがこの研究だ。
注)fMRIは、活動している脳領域の血流が上昇することを利用して、脳の活動を調べる方法。言葉の場合、読んだり聞いたりしているとき、あるいは言葉を使って書いたり話したりしているとき、いずれも、脳のどこが活動しているかがわかる。測定時に頭を固定する必要があるため、じっとできる大人では起きているときに測定することができるが、それが難しい幼児では通常睡眠時に測定する。睡眠中でも、音を聞くと脳は反応し、fMRIで記録することができる。
この研究ではまず、
比較的淡々とした文章、 少し心を込めた文章、 Motherese文、 を女性に読んでもらったテープを作成し、これらを聞かせたときの印象や脳の反応を調べている。
それぞれの語り方を成人に聞かせると、成人もMothereseを聞いたときに最も気持ちがこもった印象を持つことを確かめている。すなわち、それぞれの語り方にこもった感情の違いを感じることが出来る。
ところが、3種類の語り方を聞かせたときの典型成人と幼児の脳(言語に関わる領域)の反応をfMRIで調べると、それぞれの語りかけに対する言語領域の反応はほとんど変わらない。ちょっと不思議な気がするが、感情と言語とを別々に処理していると解釈できる。
ところが、2歳前後の典型児およびASD児の睡眠中に同じテープを聴かせ、典型児とASD児の言語領域の反応の違いを調べてみると、ASDの幼児では全ての語り方に対する言語野の反応が低下している。
以上の結果は、感情がこもったMonthereseですら、言葉に対してASDの子供の言語領域がうまく反応してくれないことを示しており、ASDの幼児には感情を込めて話しかければいいという単純な話が通らないことを示している。睡眠中の実験であることを考えると、生まれついて語りかけられる言葉に対する反応に問題がある可能性が高い。
とは言え、典型児ですら言語領域の反応はばらついている。そこで、個々の児童の言語領域の反応と、Vinelandと呼ばれるコミュニケーションや、社会性を評価する指標の相関を調べてみると、典型児でも、個々人のレベルでは特に左側の言語領域の反応が、個人の社会性や言語能力と相関していることがわかった。
そこで、ASD児でも、それぞれの話しかけに対する行動学的な差がないかを調べるため、テープが聞こえる方向に視線を向け、固定するかどうかについてアイトラッカー(視線の変化を記録できる装置)を使って調べると、典型児ではMothereseの方により強い関心を示すのに、驚くことにASD児では、他の語り方に比べてMonthereseに対する反応がさらに低下していることがわかった。すなわち感情がこもっている言葉と他の言葉を区別できているのに、感情がこもっている方を嫌っている印象がある。
このように、個々人の行動を調べていくと、期待したように典型児ではMothereseに対する関心が高いことがわかったので、Mothereseに関心を示す程度を指標化して、fMRIの反応の違いと相関させてみると、これまでのテストでは感情と相関しないように見えた言語領域、特に左側の反応が、典型児でも相関を示すことが分かった。ところが、このような相関はASD児では全く認められない。
以上の結果から、平均値で比べると感情と言語に対する反応が相関しないように見える典型児でも、個々人を比較すると、ある程度の相関が見られることがわかる。しかし、ASDではMothereseを嫌っているように見えるが、それが脳の言語に対する反応とはっきり相関しない。
そこで最後に、fMRIでの脳の反応、言語能力や社会性について調べた指標、アイトラッカーによるMothereseへの関心、など様々な要因を統合できるSNF-Louvainアルゴリズムを用いて個々人を分類すると、典型児からASD児までを4群に分けることが出来、それぞれの群は、この研究で調べた様々な指標をうまく反映できていることを明らかにしている。
結果は以上で、正直私にとっても理解しづらい論文だという印象が強かった。ましてや、一般の方がそれぞれの結果をすっと飲み込むのはさらに難しいはずだ。しかし、読み終わってからじっと考えてみるといくつか重要なポイントが浮かんでくる。
まず、問題はあるにせよ2歳時点で、典型児とASDをかなり正確に分離する方法が見つかったこと。将来医学的な介入を考えるとすると、早ければ早いほど介入が成功する可能性は高い。 典型児では、Mothereseのように感情がこもった言葉でも、言語領域の反応は、感情が抑えられた言葉に対する反応と変わりが無い。すなわち、言語野の反応は感情とは無関係に反応する。 アイトラッカーを用いた関心の高さを指標にすると、典型児は言葉にこめられた感情を感知することが出来る。これがあらゆる文化でMothereseが存在する基盤になっている。 しかし、この感情が言語にかぶさって来ることを、ASD児は嫌っている。従って、単純に愛情を持って話せばASD児とコミュニケーションを図れると考える根拠はない。 眠っているときに言葉に対する反応がASD児で低下していることは、ASD児の脳が生まれたときから持っている、典型児との違いであることを示している。 かなりわかりにくい論文だが、ASD児、特に幼児の理解という点では様々なヒントが得られるような気がする。
次回は、ASDと抑制性神経細胞について考える。