スコラ哲学紹介の最後となったオッカムを読んだ後(https://aasj.jp/news/philosophy/12487 )、すぐに17世紀近代(デカルト)に移っても良かったが、せっかく順番に読んできたので時代を飛ばさず橋渡しに16世紀を代表する、しかも「生命科学者の目」からみて推薦できる一人を選んでみたいと考えた。スコラ哲学と比べると、トマス・モア、エラスムス、モンテーニュ、フランシス・ベーコンなど16世紀には名前が知られた哲学者(?)が多い。そこで今回、4人の代表的な著作をまず読んでみた。
前回マルクス・ガブリエルを紹介した時(https://aasj.jp/news/philosophy/12813)、20世以降、哲学から排除されてしまったように見える「宇宙の中の精神」といった形而上学的課題を、今も哲学の課題であるととらえ、新たな目でチャレンジしている点が、彼の新鮮さだと述べた。逆にいうと、形而上学的課題を哲学から排除しようとする雰囲気が20世紀にはあったように思う。ただこのような根本問題への哲学的チャレンジを諦める傾向はギリシャからローマ時代に移行した後にも見られ、哲学(少なくとも読める形で残っている)が処世術といってもいいほど極端に世俗化したことについてはすでに述べた(https://aasj.jp/news/philosophy/11539)。
今回4人の著作を読んで、16世紀も哲学不毛の時代で、逆に形而上学的な課題はスコラ哲学議論と軽蔑されていたのがわかった。こうしてスコラ哲学からルネッサンスへと思想をたどってみると、世俗の勢いが増す時に、神学も含めて哲学は形而上学的課題を無視したり、軽蔑したりする傾向を示すようだ。ただ20世紀の場合、この世俗を代表したのが科学ではなかったかと思える。だからこそ、哲学にもう一度形而上学的課題を取り戻すために、マルクス・ガブリエルがその批判の矛先を向けたのは科学だった。何れにせよ、科学と哲学の関係については、17世紀を考える時扱ってみたい。
さて今回4人の著作を読んでみて、16世紀哲学を「ルネッサンス、宗教改革によりキリスト教会の相対的地位が低下し、世俗の王の権力が強まることで、教会に属さない世俗の賢人が現れ、人間のあり方(=ヒューマニズム)を論じた時代」と総括することにした。
世俗の賢人の最初はトマス・モアだ。教会内の神学者が担ったスコラ哲学時代と違い、16世紀を代表する思想家の多くは何らかの形で宮廷につかえる人たちで、トマスモアも大法官にまで上り詰めた国王の重臣だ。忙しい実務の合間に書いたのが有名な「ユートピア」で、この造語は今も理想郷を表す単語として定着している。

ユートピアはモアが考えた理想の国の話だが、おとぎ話というより16世紀の現実に即して構想されている。間違いなくプラトンの共和国を念頭に書かれたと思うが、ユートピアとはいうものの、プラトンの共和国と同じく国王が存在する。彼の描いた王はプラトンが述べた哲人王と同じで、哲学に基づく徳の精神で国を導く賢人に他ならない。面白いのは、この国で大事な哲学とは「宇宙の中の精神」を問うようなスコラ哲学でないとはっきり述べている点だ。モアにとって、形而上学などは世俗を中世に引き戻す邪魔な存在以外の何物でもなかったようだ。
ユートピアは読み物として面白く、構想が詳細にまでわたっていることに感心する。例えば奴隷の問題についてみてみよう。まず驚くのは、敵の捕虜といえども自由を奪うことは断じて禁止で、自由を奪えるのは唯一犯罪を犯した者だけだ。この時、罰として強制作業を要求できるとしており、現代の懲役刑と同じだ。さらに現代的なのは、市民権はないが外国から来て、自分で奴隷のような仕事を望む輩のことまで述べている。これも現在の外人労働者に相当する。このように内容は哲学というより、道徳的な賢人が世の中に向かって語る「お言葉」といっていいだろう。当然、いわゆる哲学からの引用は少ない。キンドルなので検索機能を利用して調べてみると短い本のなかにプラトンについての引用は15箇所もあるのに、例えばアリストテレスは1回だけで、しかも哲学の内容についての引用ではない。生命科学者の目から見ると、得るところは少ない。それでも、ユートピアに書かれた政治思想は革新的で、結果反逆罪で処刑されることになる。
世俗の賢人の二人目はエラスムス。他の三人と比べると、宮仕えはほとんどせず、自由な学者として過ごした賢人と言える。彼が友人のトマスモアの家に滞在しているときに書き上げたのが「痴愚神礼讃」で、モアのユートピアはこの本に刺激を得て描かれたと言われている。
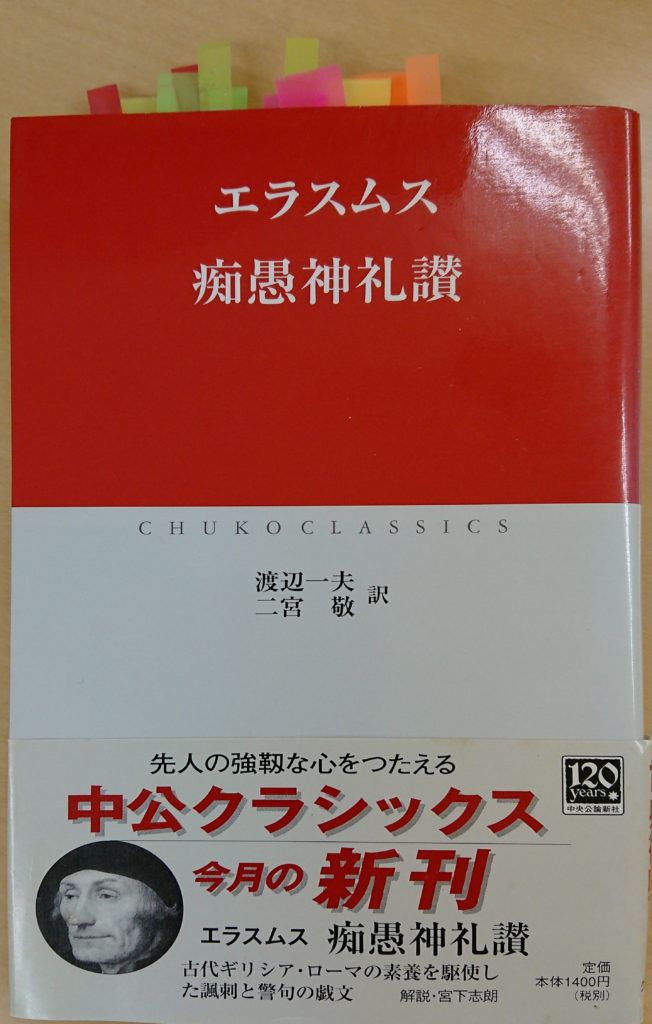
この本も一種のおとぎ話だが、モアのユートピアとは真逆で、架空の異教の女神の目を通して現状を痛烈に批判しすることで、理想的社会を探るという構成になっている。この本ではモアのユートピア以上に、当時の庶民が生き生きと描かれており、同時代のピーター・ブリューゲルの描いた庶民の姿と完全に重なり合う。もちろん、この世相の中にはキリスト教も含まれており、キリスト教信者であったエラスムスがよくまあここまで言った思える文章も多い。たとえば人間が真実より嘘が好きなことを示す例として述べたくだりを引用してみよう。
「(教会の説教では・・)、真面目なことが話されていると、聴衆は眠ったりあくびをしたり退屈したりしています。ところが、説教師が小母さんがなさるようなおとぎ話を始めますと、会衆は全部目を覚まして、口をポカンと開けて聴き惚れます。・・・聖ゲオルギウスだとか、聖クリスフォルスだとか、聖女バルバラだとかいう、ちょっとおとぎ話風な、聖職離れした聖人がいることになりますと、相手が聖ペテロだとか聖パウロだとか、また主キリストご自信だとかいう場合よりも、はるかに崇拝されるようになれるのですよ」
ここに書かれた「痴愚性」はいつの時代も変わらないことがよくわかる。これがエラスムスが現代にも通ずるヒューマニストとして評価される理由だろう。
重要なのは、モアのユートピアと同じで、「哲学=スコラ哲学」については、手厳しく軽蔑している点だ。例えば、
「さてこの面倒な上にも面倒な彼らの道具立ては、数限りもないスコラ学派の流派のおかげで、もっと霊妙でしち面倒臭いことになっていますから、実在論者や唯名論者やトマス派やアルベルトゥス派やスコトゥス派など、私は主なものの名前しかもうしませんが、こういう多くの学派の羊の腸のようにクネクネ曲がった道よりも、寧ろ迷路から抜け出す方が皆さんにとっては易しいことでしょう」
という文章から、当時の大学では、「実在論だ、唯名論だ、あるいはオッカムだ」と、過去の思想を担いで口角泡を飛ばす議論のための哲学論議行われていたことが推察される。これは20世紀にも通ずるが、世俗化が進むとアカデミックな議論はどうしても浮世離れしてしまい、「哲学議論」は一般人も世俗の賢人も軽蔑する悪いイメージが定着していたことがわかる。
世俗の賢人の3人目は、我が国で最も知られた16世紀のヒューマニスト、モンテーニュだ。彼もボルドー市長に選ばれるとともに、宮廷でも仕えた貴族で、彼の「エセー」はわが国でも広く知られている。私自身もずいぶん昔、抜粋本では読んだ覚えはあるが、全く印象は残っていなかった。今回もう一度読んでみようと全6巻新たに取り寄せて読み始めた。しかし、モアやエラスムスとは異なり、断片的文章の集まりで、すぐ退屈してしまった。賢人の思想というより、賢人の独白といった感じで、1巻読むのが精一杯で、これ以上続ける気にならなかった。

いきなりネガティブな結論になったが、エセーは彼の生きた時間に沿って書かれている独白なので、最後まで読み通せば16世紀の個人主義的ヒューマニズムのあり方もよくわかったのかもしれない。読み通していないのにそう思うのは、堀田善衛さんの「ミシェル城館の人」を読んだからで、エセーを読んだことのなかった私も、随分昔この本を読んで、カソリックとプロテスタントの抗争と世俗の権力をめぐるヨーロッパ全体の抗争が複雑に絡み合った時代と、その時代を世俗の賢人として生きたモンテーニュについて理解することができていた。
今回もう一度読み返したが、史実とフィクションがうまくブレンドされた16世紀を知るための素晴らしいガイド本になっている。しかし率直な印象を述べると、堀田さんはモンテーニュをあくまでもこの時代を案内するためのガイド役として登場させ、彼を思想家というより、家族や世間の間で苦労しながら自分を守ろうと努力している思索家として描いている。実際、モンテーニュ自身も、体系的思想など全く重視していなかったようだ。

堀田さんはこの本の中で、
モンテーニュの『エセー』(試み)は、実に進行形の思想の歩みを示すものであった。さればストア派の思想の枠を出て、精神と肉体の様々な存在の仕方の認識を経て、精神と肉体の解放と自由の歩みを示すものであり、その試みはつねに運動を伴っているのであった。それは固定した、一定の思想の平べったい陳述ではなかった。たとえば思想の陳述に、明確な、枠組みのはっきりした起承転結を求める人や、何につけても結論だけを求めるような人には、『エセー』は怪物的なまでに雑駁な、ある種の集積物と見えるかもしれないであろう。
(ミシェル城館の人 第三部 精神の祝祭 )
と述べて、エセーは思索の集積で、私のように「平べったい思想」を求めてはならないと戒めている。そして「私はその日その日を生きている。そして失礼は承知の上で、ただ私のためだけに生きている。私の目的はそこに尽きる。」という彼の晩年の言葉を引用して、同じ世俗の賢人でも、モアやエラスムスとは対極的な、極めて個人主義的傾向の強い賢人として描いている。
このように科学や哲学の観点から見ると、この3人の人文主義者の貢献は大きくないように思うが、しかし権威を疑い自分で考える、個人主義や主観主義の先駆けとして17世紀近代を準備したことは間違いない。この点では、世俗の賢人4人目、フランシス・ベーコンも同じだが、他の3人と比べるとベーコンの科学、哲学への貢献は大きい。世俗の人としては英国で大法官にまで上りつめた貴族だが、経歴を読むと失脚と復活を繰り返し、おそらく4人の中では最も政治的野心の強い賢人だったと思う。実際、著作からもヒューマニストと言う印象はほとんど感じられない。今回読んだ河出書房の世界の大思想には3つの著作が収載されている。この中のニュー・アトランティスは、ベーコンがモアのユートピアに対抗して理想郷を描こうとした作品で、他の3人と同じ側面を見せる作品だが、モアの構想と比べると理想からはほど遠く、退屈な本だった。政治的野心満々の賢人にはユートピアは構想できないことがよくわかる。

しかしこのようなギラギラした政治家に、賢人としての能力と知識が備わっていたことが重要で、他の3人と比べて彼が科学や哲学に大きく貢献できたのは、彼が政治家として現実的に世界と向き合っていたからではないだろうか。このことが最もよくわかるのが、「学問の進歩」で、この本を元にベーコンの思想を見てみよう。
この本は、国王に対して学問の重要性を進言すると言う形式で書かれており、まず主張しているのが、知識を信頼し、できるだけ蓄積し、それに基づいて判断することの重要性だ。現代風に言えば、エビデンスに基づいて判断することの重要性で、政治家としては当然の話だ。しかし、我が国の政治状況からもわかるように、エビデンスに基づいて判断することほど難しいことはなく、個人の思いつきや独断が判断を支配する。実際、今も昔も政治家の多くは学問など学者の遊びで役に立たないとバカにするようで、ベーコンも「学問は人間の気質をゆがめ、そこねて、支配や政治に関することがらに向かなくさせる。」とか、様々な理由をあげつらって学問蔑視の風潮が存在することを嘆き、アレキサンダー大王や、シーザーを例に、学問を通して知識を蓄積することの重要性を説いている。
学問が無意味であるとする様々な批判について一つ一つベーコンが丁寧に答えているのを読むと、今も昔も全く変わらないと思う。例えば、学問する時間などないと言う批判については、
「学問はあまりにも多くの時とひまをくうという異議の申し立てについては、わたくしはこう答える。ずばぬけて思いきり活動的な忙しいひとにも、(きっと)仕事がそのうちにたてこんでくるのを待っているあいだの、手すきの時間はたくさんある。」
どんなに忙しい人でも、学問の時間がないと言うのは理由にならないと一括している。
この「学問ノススメ」の確信は、そのまま学問の方法論へと向かう。ベーコンにとって学問とは、現実の世界に向き合い、世界と自分との相互作用の中で知識を蓄積する事で、自分の好き勝手に集めるものでも、一方的に外から与えられるものでもない。従って、信頼できる知識と、信頼できない知識をまず判断する事が必要になる。ここでも紹介したプリニウスの博物誌(https://aasj.jp/news/philosophy/11539)やアルベルトゥス・マグヌス(https://aasj.jp/news/philosophy/12074)についても、
「同じように自然誌においても、しかるべき選択と判定がなされていないことがわかるのであって、たとえば、プリニウス〔ローマの博物学者、「自然誌」の著者、後二三─七九年〕やカルダヌス〔ルネサンス期イタリアの自然哲学者、医学者、数学者、一五〇一─一五七六年〕やアルベルトゥス〔ドイツ出身のスコラ学者、その博識のゆえに大アルベルトゥスとよばれた。トマス・アクィナスの師、一一九三年頃─一二八〇年〕やアラビアの多くの学者の著作にあきらかであるように、それらは、寓話の類にみちみちており、それがまた大部分、真偽のほどもたしかめられていないばかりか、評判のうそごとであって、じみで、まじめな学者たちには、自然哲学の信用を大いにおとしている」
と断じて、知識の信頼性を判断する方法論の重要性を述べている。
ベーコンにとって、世界についての知識は分野を問わずできる限り集める事が学問だが、間違った知識を区別するためにも、分野を整理し、それを体系化する作業を繰り返す必要があると考えている。この点で、他の3賢人と異なり、自然哲学から倫理学まで知識を体系的に整理しようとしたアリストテレスへのベーコンの評価は高い。その結果、ベーコンが考える知識体系の中に形而上学も含まれており、形而上学、自然神学、自然哲学など異なる次元から多元的に世界に向き合う事の重要性を説く。少し長くなるが、彼が形而上学の重要性を述べている箇所を引用しよう。
「それゆえ、わたくしがいま解するような、形而上学という名称の用法と意味とに話をもどすことにしよう。すでに述べたところによって、わたくしが、これまで混同して同一のものとされていた、「第一哲学」すなわち最高の哲学と形而上学とを、二つの区別されたものと考えようとすることはあきらかである。というのは、前者をわたくしは、あらゆる知識に対する親または共通の祖先とし、後者をいま、自然に関する学問の一部門または子孫としてもちこんだのであるから。なお、わたくしが最高の哲学に、個々の学問に対して無差別で不偏である共通の原理や一般的命題の探求をわりあてたこともあきらかである。わたくしは、それにまた、量、類似、差異、可能性などという、実体の相対的で付加的な性質の作用に関する研究をもふりあて、そしてこの哲学に、それらの性質は論理的にとり扱うべきではなく、自然において作用するものとしてとり扱うべきであるという差別と規定をもうけたのである。なおわたくしが、これまで形而上学と混同されてとり扱われていた自然神学に、それの範囲と限界を規定したこともあきらかである。それゆえ、いまここに問題となるのは、何がなお形而上学のために残されているかということであるが、この問題に関して、自然学は、質料に包みこまれ、したがって変化するものを考察し、形而上学は、質料からひき離されて変化しないものを考慮するという点まで、古人の考えを保存しても、真理をそこなうことはないであろう。また、自然学は、自然界にただ存在と運動だけを想定するものをとり扱い、形而上学は、自然界になおそのうえに理性と知性とイデア〔原型〕をも想定するものをとり扱うといってもよかろう。しかし、その相違は、つぎのようにはっきり表現すると、もっともなじみぶかく、わかりやすい。すなわち、われわれは、さきに自然に関する哲学一般を原因の研究と結果の生産とに区分したように、原因の研究に関する部分をも、原因の一般に認められている堅実な区分〔アリストテレスの「四つの原因」の説、「形而上学」一の三等〕に従って、細分する。すなわち、〔原因の研究に関する自然哲学のうち〕自然学という部門は、質料因と作用因をとり扱って研究し、形而上学という他の部門は、形相因と目的因をとり扱うのである。フィジック〔自然学〕は(それをわれわれの医術を意味する慣用法に従ってではなく、その語源に従って解すれば)、自然誌と形而上学との中間に位する。というのは、自然誌は事物の種々相を記述し、自然学は原因を、ただし変易的なまたは相対的な原因を記述し、そして形而上学は固定的で恒常的な原因を記述するからである。」(ベーコン. ワイド版世界の大思想 第2期〈4〉ベーコン)
このように、世界を理解するためには、自然神学と形而上学を混同することなく、アリストテレスが考えた4つの因果性を理解するためには、眼に見える因果性(質料因と作用因)を研究する自然誌とともに、形相因や目的因のような眼に見えない因果性を扱う形而上学が必須であると述べている。さらには自然誌と形而上学の中間に、目的因も含めて考える医学生物学といってもいい中間的学問が必要なことまで指摘している。生命科学に関わってきた人間としては、読むだけでゾクゾクする文章だ。科学も、哲学も、宗教も、世界を理解するためには全て必要だとする多元的な見方は、現代に形而上学を復活させようとしたマルクス・ガブリエルに重なる。
このような多元的な知識の重要性の認識は、次にこの多元的知識をもとに何が真実かを判断するときの方法論へと移る。そして「ノヴム・オルガヌム」(大革新)というタイトルから彼の自信のほどがうかがわれる著作で、新しい方法論として示されるのが「帰納法」だ。
「さて、わたくしの方法は、実行することは困難であるけれども、説明することは容易である。すなわち、それは確実性の階段をつくる方法であって、感覚の権能を、それにある種の制限を加えて認めるが、しかし感覚につづいておこる精神のはたらきは大部分しりぞけて、感官の知覚から出立する新しくて確実な道を精神のために開く方法である。」
と述べ、3段論法などこれまでの方法論は個人的な予断の入る余地があまりに多すぎて信頼できず、「確実性の階段を作る方法」で、「感官の近くから出立する新しくて確実な道」、すなわち帰納法こそ信頼できる方法論であると述べている。
ベーコンの偉大さは、帰納法の重要性を論じた上で、帰納法がまだまだ完成していないことをはっきりと告白している点だ。
「ところで、一般的命題をうちたてるさいには、これまで用いられてきたのとは別の形式の帰納法を考え出さなければならない。しかもその帰納法は、ただ第一原理(といわれるもの)についてだけではなく、低次の一般的命題や中間の命題についても、いな、すべての一般的命題についても、それを証明し発見するために用いられなければならない。というのは、単純枚挙による帰納法は子どもじみたものであって、その下す結論はあぶなっかしく、矛盾的事例によってくつがえされることを免れず、そしてたいていの場合、あまりにも少数の、それも手近にある事例だけによって断定を下すからである。しかしながら、諸学と技術との発見と証明に役だつ帰納法は、適当な排除と除外によって自然を分解し、そうしてから否定的事例を必要なだけ集めたのち、肯定的事例について結論を下さねばならぬのであるが、このようなことは、定義とイデアを論究するためにある程度この形式の帰納法を用いたプラトン〔たとえば、「国家」第一巻において「正義」について〕によってのほかは、まったくまだなされたことはなく、また試みられたことさえもないのである。しかしながら、このような帰納法または証明をうまくうちたてるためには、これまでどんな人間も考えたものがないほどじつに多くのことがなされねばならず、したがってこれまで三段論法に費やされたよりももっと多くの労力がそれに費やされねばならぬのである。」
事実、現在も帰納法は「確実性の階段」を完成させるまでには至っていない。しかし、生命科学を始め、力学的因果性では理解できない多くの領域で最も重要な方法論になっていると言える。20世紀に入って、情報科学が進んだおかげで、帰納法も大きく進展した。全ての過程が見えるわけではないが、AIのパワーを見ると、新しい帰納法が生まれたという実感がある。その意味で、ベーコンは現在の情報科学の原点と言っていいのかも知れない。
ノヴム・オルガヌムは短い著作で、翻訳もわかりやすいので、生命科学を志す人にはぜひ読んで欲しいと思うが、ここに現れる思想は極めて近代的で、ヨーロッパの科学・哲学のルーツを見る思いがする。
長くなったのでまとめに入ろう。
16世紀はダビンチやミケランジェロが活躍した後期ルネッサンス期と重なるが、ヨーロッパ全土で戦争が絶えず、また宗教改革を通して、カソリックの力が低下、代わりに世俗の力が勃興した時期だ。これを反映して、当然哲学も大きな変化を遂げ、それまでキリスト教と一体だったスコラ哲学者に変わって、教会やアカデミアから独立した世俗の賢人が生まれる。しかし、世俗化は哲学の退潮とも同義で、モア、エラスムス、モンテーニュなどの有名な人文主義者は生まれたが、その後の哲学に対する貢献はほとんどなかったと言える。
ベーコンを読むまでは、これが私の16世紀の総括だったが、ベーコンを読んで一変した。引退後は自分で様々な実験を行なったと伝えられているので、コペルニクスに代表される科学の進展にも理解があり、政治的野心も隠さない、一種の超人だった。事実に基づき、宗教、政治、哲学、科学まで排除することなく多元的視点を貫ぬくことを説いたことが彼の哲学への貢献だ。マルクス・ガブリエルを読んでからベーコンを読んだが、読みながらずっとガブリエルを思い出していた。16世紀のマルクス・ガブリエルなどというと本末転倒だが、自由奔放な思想で新たに哲学を復興させようとした点も重なって見える。
多元主義と帰納法を基礎におくベーコンの思想は、近代に足を踏み入れているどころか、二元論を超えているようにさえ思う。少し褒めすぎた気もするが、ベーコンの思想を知ってから17世紀哲学を読んでみると、全く違った印象が得られるのではと今から楽しみだ。次回はデカルトから始めよう。



